30 / 150
第二部 序章 闘妃
第二部 黒白(グラデーション)の願い 序章
しおりを挟む
序章 闘妃
背筋を滑り落ちていく汗を、僕は感じていた。
約三メートル離れた位置に立っているのは、平泉夫人。
明るい照明の下、腰まで高さのある円形リングを挟んで、僕と夫人はお互いにスマートギアを被ったまま見つめ合う。
ディスプレイは下ろしているから、もちろん夫人の目が見えてるわけじゃない。
でもドレスのような黒いワンピースを着、金の装飾が施されたワインレッドのスマートギアを被り、口元に笑みを浮かべている彼女からは、圧力すら感じるほどの迫力を覚えている。
僕はいまいるのは平泉夫人の自宅。
一階の、パーティや社交ダンスができるほどの広間で、ピクシードール用のリングを挟んで僕は夫人と対峙する。
リングの中には、リーリエが操る身長約二十センチのアリシアが立っていた。
ヒルデ戦、ガーベラ戦を教訓に、白いソフトアーマーを覆っている水色のハードアーマーは、手甲だけじゃなく脚甲や胸甲も金属製の交換している。
ヘルメットを被らず、腕にかかるように伸びている水色のツインテールを含めて、デザイン的にはあまり大きな変化はない。でもPCWの親父と相談して、重量増を最低限にし、いままで以上に動きを邪魔しないよう、細かいところの形状に手を加えていた。
微かに笑みを湛えてるアリシアが対峙しているのは、夫人のドール。
黒を基調に紫や赤や黄色に彩られたその姿は、ハードとソフトが混在した特殊な形状のアーマーをしている。着物のように肘下に伸びる布地や、開いた襟元にも見える形状をし、顔はほっそりとしたヒューマニティフェイス。高い位置に結わえられたスフィアの冷却を兼ねた髪などから、どこか花魁とかそんな雰囲気を醸し出しているように思える。
名は、闘妃。
ピクシードールには意味がないと思うんだけど、ハイヒールな脚甲を履いてる闘妃は、何体か持ってる夫人のバトルピクシーの中で、バランスタイプの一体だった。
「全力全開で来て頂戴、克樹君。これは公式戦ではないんだから、すべての力を使って、ね。それくらいでないと面白くないから」
「……わかってます」
夫人の余裕を感じる言葉に威圧されつつ、僕はそう応える。
今日ここに来たのは、僕から夫人にお願いしたからだった。
目的はリーリエの訓練。
百合乃の脳情報から構築されたリーリエだけど、百合乃の記憶を持たないために、戦闘経験は圧倒的に不足してる。
今後、おそらくもっと厳しい戦いがあるだろうエリキシルバトルを勝ち抜いて行くには、まだまだ未熟なリーリエの強化は必須な状況だと言えた。
『いくよ、リーリエ』
『うんっ』
スマートギア越しにイメージスピークで声をかけると、リーリエの元気のいい返事が返ってきた。
でもその声音に若干の硬さを感じる。
それも仕方ない。
ただ立っているだけなのに、平泉夫人も、彼女が操る闘妃からも、僕は息を呑むほどの圧力を感じているのだから。脳を擬似的に再現して、アリシアの目を通して見ているリーリエも、同じものを感じてるんだろう。
「始めましょう」
言って夫人は、鞭らしきものや槍や剣など、闘妃の腰や背中に携えた武器の中から、左右の腰に佩いた細く反りのない日本刀のような片刃の剣を引き抜いた。
リーリエがアリシアにナックルガードで覆った両手を構えさせ、ひと呼吸置いた後、脇に静かに控えていたメイドさんが手にしたゴングを鳴らした。
『先手ひっしょ――、わぁっ!』
ゴングと同時に飛び出したリーリエだったけど、すぐさま横に転がるようにして回避の動きをすることになった。
足首近くまでを覆う布地が揺れたと思った瞬間には、闘妃が滑るように動いて接近し、横薙ぎの斬撃を加えてきたからだった。
アリシアを追って闘妃が歩を進めてくる。
リーリエがアリシアを立ち上がらせた瞬間、頭上から振り下ろされた剣。
左の手甲で受け流して踏み出そうと右脚を上げたときには、斜め下からの閃きが襲いかかる。
バランスを崩しながらも上げていた右脚の脚甲で受け止め、その衝撃を利用してアリシアを下がらせたリーリエ。
間を置かず、リーリエはアリシアにキャンバスを蹴らせる。
Cカップバッテリを覆う胸甲が擦るんじゃないかと思うほどの前傾姿勢の突進を、正確無比な斬撃が阻んだ。
両腕で剣をガードして横に転がったアリシアは、そのまま闘妃から距離を取った。
『びっくりしたぁ』
『もっとよく見て動くんだ、リーリエ。さっきのじゃ夫人には通用しないぞ』
『わ、わかった』
立ち上がったアリシアを見て、僕はリーリエにそう声をかけていた。
リーリエと共有してるアリシアの視界を左隅に映しつつ、細かに人工筋の調整をする僕はスマートギア越しに平泉夫人のことを見る。
余裕の笑みを浮かべながらも、彼女が放つ空気からは隙なんてひと欠片も感じられない。
リングの中で夫人と同じ笑みを浮かべてる闘妃もまた、同様だった。
――いまのリーリエじゃ、百合乃の半分の力もないな。
二年前のスフィアカップの際には、辛勝ならが百合乃は平泉夫人を破ることができた。
たぶんそのときの戦いよりも正確さもドールの性能も上がっているだろう平泉夫人は、いまのリーリエで敵うような相手じゃない。
それでも僕は、そしてリーリエは、少しでも夫人に近づけるよう強くならなくちゃいけなかった。
『必殺技を使うよ、リーリエ』
『わかった。……でも、通じるかな?』
『やってみないとわからないが、僕たちは僕たちの全力で戦うだけだ』
『うん……。そうだねっ』
リーリエの闘志の籠もった返事を聞いて、僕は必殺技を使う準備をする。
ガーベラ戦のときよりも精密に使えるようになったアリシアの必殺技。リーリエも必殺技のときの動きにあのとき以上に慣れてる。
普通の人間の反応速度を超える動きができる必殺技が通じなかったら、僕たちには夫人に勝つ手段なんてない。
「今度はこちらからいくわね」
言って夫人は闘妃をアリシアに向けて前進させる。
動きそのものは普通に歩いてるようにしか見えないのに、間合いに入った瞬間、無造作に下ろしていた右腕から剣が繰り出された。
『ふっ』
本当に息をしているように声を出しつつ、リーリエはわずかに身体を反らして下から上に斬り上げられた剣を躱す。
剣の動きを捕捉するリーリエが、アリシアの腰を落としつつ前傾姿勢にさせたのを見て、僕はポインタを操作しつつ叫んだ。
『疾風迅雷!』
『うんっ』
リーリエの返事が聞こえたときには、アリシアは闘妃の前にはいない。
僕のスマートギアに搭載されたカメラでは捉えきれない速度で動いて、闘妃の正面にいたアリシアは背後まで駆け抜けている。
『え?』
『わわっ!』
闘妃の無防備な背中に拳を叩き込もうと腕を振り被ったとき、アリシアの視界は真っ黒に染まっていた。
――袖?!
実視界側で見てみると、アリシアの眼前を覆っていたのは着物のように腕から垂れている袖だった。
『防御!』
叫んだときにはもう遅い。
振り向きざまの闘妃の膝蹴りが、アリシアの顔面に叩き込まれていた。
『まだまだ!』
『あぁっ。電光石火!!』
吹き飛ばされたアリシアの体勢を瞬時に整えたリーリエに、再度必殺技を発動させる。
飛ばされた距離を超速度で詰めて反撃、と思ったのに――。
「勝負あり」
ゴングが鳴り、決着を告げた。
リングの中では、すっ転んでうつぶせに倒れてるアリシアと、その首に剣を突きつけてる闘妃の姿があった。
何が起こったのか、僕にはわからなかった。
電光石火を使ったと思った瞬間、アリシアは障害なんてないはずのリングの中で何かに足を取られたように転んでいた。
スマートギアの視界で拡大して見てみると、アリシアの両足首にまとわりついている黒い紐があった。
紐が繋がっている先は、闘妃の左手。
いつ手にしたのかわからない鞭が、その手に握られていた。
「いったいそれはなんですか?」
闘妃が鞭を振るう動きなんてなかった。
手にしたのはたぶんアリシアの視界を袖で覆ったときだと思うけど、振るいもしてない鞭が絡みつくなんてことはあり得ない。
「コントロールウィップっていう、この前発売された武器よ。第五世代でスフィアやフレームのデータラインが増えたのと、手に外部機器の接続ポイントをつくれるようになったでしょう? 人工筋でできてるから、鞭のように振るわなくても動かすことができるのよ、これ。面白いでしょう?」
「そうですか……」
スマートギアのディスプレイを上げ、いたずらな瞳をして楽しそうに笑う夫人に、僕はため息を吐くように返事をしていた。
相変わらずというか何と言うか、夫人はこういう新しいオモチャが大好きだ。
僕じゃ絶対買いそうにないコントロールウィップ。
何より怖いのは、太さと長さから考えたらたいした力は出せず、攻撃になんて使えそうにない武器を、上手いこと使い道を探し出す彼女の発想力だ。
『負ーけーたーっ。うぅ……』
「お疲れ、リーリエ」
戦闘中はオフにしてあった外部スピーカーをオンにした途端、リーリエの悔しそうな声が響いた。
そんな彼女にねぎらいの言葉をかけつつ、まったく勝てる気がしないにせよ、二戦目の戦法を頭の中で組み立てていた。
*
薫り高い紅茶をひと口すすり、僕は小さくため息を吐いた。
結局全部で五戦して、一度も勝つことができないどころか、クリーンヒットの一発すら食らわせることができなかった。
絨毯から家具から調度品から、僕なんかじゃ隔絶した世界だと感じる平泉夫人の執務室で、応接セットのソファに座った僕は、頭の中で今回の戦いの反省点を思い浮かべていた。
『うー、うー、うー』
スマートギアのスピーカーからうなり声が聞こえているリーリエも、仮想の脳を駆使していろいろ考えてるらしい。
テーブルの上で器用にあぐらをかいてるアリシアは、腕を組んで頬を膨らませ、少し顔を俯かせている。
机を挟んだ僕たちの目の前で優雅にティーカップを口元に寄せている平泉夫人は、そんな僕たちの様子を楽しそうな色を浮かべた瞳で眺めてきていた。
正直、スフィアカップで百合乃と拮抗した平泉夫人が、これほど強いとは思っていなかった。以前にも夫人とはリーリエと戦ってもらったことはあったが、そのときは軽くいなされるだけで終わっていた。今回は少しはまともに戦ってもらえたけど、結果があんまり変わったようには思えない。
目標とする山が高いのは悪くないことだと思うけど、最初の目標が断崖絶壁の世界最高峰ともなると、昇り始める前に挫折してしまいそうだった。
「さて、反省会でもしましょうか」
しばらくして、夫人がそう言ってカップをソーサーに置いた。
「本当のところ、リーリエはどうでした?」
「そうね。以前戦ったときとは見違えるほどに強くなってるわ。けれど性格が素直すぎるからかしらね? フェイントへの対応ができていないし、目が良い分、細かな挙動まで見えていて、一々それに反応してしまってる。ドールの扱いについては私以上と言っても過言ではないし、スピードもパワーも性能を熟知した上で細かいところまで扱えていて、フルコントロールソーサラーとしてはすでに上級者と言えるわ」
『でも、あたしは一発も当てられなかったよ?』
「そうね。そこは人生経験の差による駆け引き、というのもあるけれど、リーリエちゃんの場合はとくに戦闘経験の不足が原因。ボディの動かし方は戦闘補助ソフトで補正できるけれど、駆け引きは経験から学んでいくしかないところだからね」
「確かに、そうですね……」
痛いところを突かれて、僕は口元に寄せたカップから紅茶を飲んで、その渋みに顔を歪ませる。
リーリエの戦闘経験は、皆無というほどではないけど、ほとんどないと言っていい。
百合乃が死んだ後、僕がピクシーバトルへの興味を失ったのもあるけど、人工個性のリーリエをあまり大っぴらにするわけにはいかなかったという事情もあって、バトル経験を積ませてない。
リーリエにアリシアを与えて以降で戦ったのは、システム購入の際に世話になって、成果を見せるように言われてた平泉夫人と、技術的には凄いけどバトルソーサラーではないショージさんくらい。リーリエ自身は戦いを想定してアリシアの動かし方を訓練したり、ネットで公開されてるピクシーバトルの動画を見たりと色々してたみたいだけど。
本気でリーリエが戦ったのは、夏姫のブリュンヒルデ戦が初めてだった。
『でも必殺技も効かなかったよね? あたしは見えるけど、おにぃちゃんでも見えないくらいの速さなのに』
「それも同じ理由よ、リーリエちゃん。何かを仕掛けてくるというのは、わずかだけど準備の動作が見えれば気づけるし、どんなに早くても意外性のない動きは先が読めるのよ」
『そっかー。うぅーん』
「いや、まぁ、確かにそうかも知れないけど……」
アリシアに腕を組ませてうんうんと納得したように頷かせてるリーリエだけど、僕の方は全然納得ができるものじゃない。
主に距離を詰めるのに使ってる疾風迅雷は一度見ていれば対応できるかも知れないが、電光石火は目の前にいた敵が消えるような動きで背後や側面に回るのに使ってる必殺技だ。
空間転移による瞬間移動ではないからコンマ数秒の時間はかかるけど、使うのがわかってても対応できるのは僕の常識を逸脱してる。
ちなみに、ボディへの負担が大きく、畳み込むのに使う疾風怒濤は、結局一回も使う機会が得られなかった。
「リーリエちゃんはとにかく、もっと戦闘経験を積むこと。それから他の人の戦いをもっと見る必要があるわね」
『うん、わかったー』
「役に立ちそうな映像資料をリストにしておいたから、参考にして頂戴。芳野」
「はい」
近くに立って控えてるのに、存在を忘れそうになる芳野と呼ばれたメイドさん。
黒髪を結い上げ、黒い瞳をした、たぶん二十代前半だろう、白のエプロンに地味な黒いワンピースを身につけた彼女は、携帯端末をエプロンのポケットから取り出して操作する。
ヘッドホンから聞こえてきた着信音に、ディスプレイを下ろしてメールを開いてみると、様々な動画がリストになって送られてきていた。
リーリエにも共有設定を入れて見たリストには、ピクシーバトルの動画に留まらず、いろんな格闘技の記録動画なんかもラインナップされている。無料で見られるもの、有料のものも含め、相当な数に上っていた。
「もし手に入らないものがあったら言って頂戴。貸せるものもあるでしょうし、来てもらえばここで見せられるものもあるから。ちゃんと手に入れておいた方がいいものばかりなのだけどね」
「こんなに……。リーリエのためにありがとうございます」
「あら、何を言ってるの?」
座ったままだけど深々と礼をした僕の頭に降り注いだ夫人の声。
顔を上げると、彼女は冗談を一切含まない澄ました顔で言った。
「リーリエちゃんだけじゃなくて、これは貴方も見るものなのよ、克樹君」
「え? でも僕は……」
確かに僕が見ても戦いの参考になるとは思うけど、戦闘のときの主役はやっぱりリーリエだ。僕は本当に参考程度に見ておけばいいと思う。
でも、真剣な顔つきをし、目を細めた平泉夫人は、威圧するような雰囲気を漂わせながら言う。
「貴方はフルコントロールソーサラーになりなさい」
「……僕が?」
「そうよ。貴方の参加しているエリキシルバトルがどんな戦いで、これからどんな敵に出会っていくのかは、参加していない私にはわからないし、詮索する気もない。でもね、克樹君。私は予感がしてるの。リーリエちゃんには弱点があるのは貴方も知ってる通りでしょう? これから先、リーリエちゃんに頼らずに戦わないといけない局面も出てくると思うのよ。そして、リーリエちゃんの代わりという意味ではなく、貴方自身にもピクシーバトルを戦う力が、今後必ず必要になる。そう感じてるの」
憂い、なのだろうか。
複雑な色を浮かべている平泉夫人の言葉に、僕は反論できない。
何しろ近藤との戦いでは早速その弱点を突かれて、窮地に陥ったのだから。
――でもなんでなんだ?
「あの、なんでフルコントロールソーサラーなんです? 僕は一応セミコントロールでは全国レベルではないにしても、そこそこドールを動かせるんですが」
「はっきり言うと、ただの勘よ」
それまでの緊張を吹き払うように笑った夫人は言葉を続ける。
「貴方のソーサラーとしての才能は、百合乃ちゃんにはもちろん及ばないし、どんなに鍛えても私に並ぶことも難しいと思うわ。でも、フルコントロールソーサラーなら四つから六つのポインタを操作できるものだけど、貴方は最大で一〇個のポインタを同時に、それも精密に操作することができる。ポインタの複数操作はフルコントロールソーサラーには必須の能力で、貴方の数と精密さは戦いではそれほど役には立たないけれど、今後克樹君が進む道の先で、必要になりそうだと思えるの」
「……わかりました」
ため息を吐きつつ。僕は了解の返事をした。
平泉夫人の勘は、僕もそれに助けられたことがあるから知ってるけど、恐ろしいほどに鋭い。
実際には勘と言うより閃きなんだと思う。様々な情報を蓄積してる夫人は、無意識のうちに問題の根っこを関知する能力に長けてるんだろう。
魔物が跋扈してるような財界とかで生きながら、女ひとりで規模は小さいとは言えやっていけるてるのは、そうした夫人の感知能力に負うところが大きいのかも知れない。
「それからこの辺りも全部とは言わないけれど、訓練の進み具合に応じて用意した方がいいわね」
夫人の目配せの指示を受けて芳野さんが送ってくれたのは、ピクシードールのアプリやアドオンソフトのリスト。
定番のフルコントロールアプリの最新版や、たぶん第五世代で新しく出てきただろうアドオンソフトなど、映像資料と同じくらいの項目が並んでいた。
スフィアドールに関わるいくつもの会社に出資や協力をしていて、自分の趣味でもあって詳しいのは知ってるけど、僕が家で調べるよりも多くのことを平泉夫人が知ってるのを感じる。決定的に嗅覚が違う。
「それとこれを買いなさい、克樹君」
言って夫人が芳野さんから受け取って僕に差し出してきたのは、薄い冊子の商品カタログ。
紙に印刷されていたものはほとんどが電子データに置き換わっているけど、宣伝を勝手に個人の端末に送ることはできないので、カタログや宣伝資料なんかはいまでも紙で配られてることが多い。
渡されたのはそんな商品カタログで、メカニカルウェア(MW)社という、スマートギアメーカーとして有名な会社のもの。一般向けから軍事産業向けまで様々に、とくに高性能高機能なモデルを中心に売ってる中でも、一般向けの最高グレード、プロゲーマーでも買うのをためらう高級シリーズの、つい最近発売された最新モデルのカタログだった。
ディスプレイを跳ね上げてまじまじとカタログを眺める僕は、開いて一覧に書かれた参考価格に息を詰まらせる。
「やっぱ高いですね、ここのは」
「えぇ、そうね。でも克樹君に必要なのはこのモデルよ」
手を伸ばしてきた夫人が開いたページに写真や表入りで掲載されているのは、カタログの中でも一番高いモデル。プレミアムグレードに位置するものだった。
その価格は、趣味の品としてはけっこう高いと言われるバトル用ピクシードールを新規で二体買っても充分お釣がくるくらいだ。
『すごいねぇ、おにぃちゃん。こんなの使うんだぁ』
「いや……、さすがにここまでのは必要ないと思うんだけど……」
「いいえ、必要よ」
高級グレードながら飾りが凄かったりゴツかったりしないスマートな形状のそのモデルの写真から顔を上げ、夫人はにっこりと笑う。
「展示会で少し使ってみたのだけど、一般向けとしては性能も機能も最高なのは当然として、外部カメラや集音マイクにも気を遣っているのよ。これからもリーリエちゃんとあの戦いを勝ち抜いていくつもりなら、これくらいのものは絶対に必要になるわ」
「わかりました。検討しま――ぐ、うっ」
返事をしようとした僕は、途中で喉を詰まらせた。
目の前では平泉夫人が微笑んでる。
黒真珠とあだ名される彼女の黒く艶やかな髪と、髪と服の黒さの対比で輝いているようにも見える白い肌。
いつもと変わらぬ柔らかい笑みを口元に浮かべながら、あだ名の通り黒真珠のような瞳に浮かんでいるもの。
それを見た僕は、背筋を凍るような感覚を覚えていた。
「これは提案じゃないの、克樹君。命令。わかる?」
「でもさすがに、これは……。いまのでもそんなに不都合ないですし、高いですし……」
「先月発売されたHPT社のヒューマニティフェイス、売れ行きは好調だそうじゃない? 価格を下げた前世代には及ばないけれど、生産が追いつかないと聞いてるわよ。いまの克樹君なら、買えるでしょう?」
本当に夫人の業界情報を仕入れる速さはどれくらいのものなのか。
頬を膨らませたり口をすぼめたりできる新型フェイスの売れ行きは、第五世代のパーツが出揃って買い換え需要が高まってきてるのもあって、かなり好調だった。売れ行きに応じて支払額が変わる僕への報酬も、過去最高になってる。
それだけじゃなく機能面をエルフやフェアリーサイズのドールへの応用も始まっていて、最近僕にHPT社から支払われた金額は、サラリーマンのボーナス並みになっていた。
「貴方にはこれが絶対必要になるから、必ず買いなさい。生産数が少なくて品薄だけれど、手配は私の方でして上げるから、連絡が届いたらすぐに支払いの手続きをして頂戴。できるだけ安くなるよう、交渉しておくわ」
「――わかりました」
間接的とは言え、懐事情すら把握してて、これまでいろんな貸しのある夫人の命令に僕が従わないわけにはいかない。
「克樹君。貴方には必ずあの戦いを勝ち抜いてほしいのよ。貴方の願いには賛同しかねるし、最後にどんなことが待ち受けているのかもわからない。でも、なんとなく、これは本当になんとなくの予感なのだけど、貴方は最後まで見届けなければならないように思えるの」
「……えぇ」
憂いを含んだ夫人の瞳が、僕の何を、そしてエリキシルバトルの何を見ているのかはわからない。
でもたぶん、純粋に僕のことを想って言ってくれてることなのはわかる。だから僕は、彼女の心配そうに揺れている瞳に、頷きを返していた。
背筋を滑り落ちていく汗を、僕は感じていた。
約三メートル離れた位置に立っているのは、平泉夫人。
明るい照明の下、腰まで高さのある円形リングを挟んで、僕と夫人はお互いにスマートギアを被ったまま見つめ合う。
ディスプレイは下ろしているから、もちろん夫人の目が見えてるわけじゃない。
でもドレスのような黒いワンピースを着、金の装飾が施されたワインレッドのスマートギアを被り、口元に笑みを浮かべている彼女からは、圧力すら感じるほどの迫力を覚えている。
僕はいまいるのは平泉夫人の自宅。
一階の、パーティや社交ダンスができるほどの広間で、ピクシードール用のリングを挟んで僕は夫人と対峙する。
リングの中には、リーリエが操る身長約二十センチのアリシアが立っていた。
ヒルデ戦、ガーベラ戦を教訓に、白いソフトアーマーを覆っている水色のハードアーマーは、手甲だけじゃなく脚甲や胸甲も金属製の交換している。
ヘルメットを被らず、腕にかかるように伸びている水色のツインテールを含めて、デザイン的にはあまり大きな変化はない。でもPCWの親父と相談して、重量増を最低限にし、いままで以上に動きを邪魔しないよう、細かいところの形状に手を加えていた。
微かに笑みを湛えてるアリシアが対峙しているのは、夫人のドール。
黒を基調に紫や赤や黄色に彩られたその姿は、ハードとソフトが混在した特殊な形状のアーマーをしている。着物のように肘下に伸びる布地や、開いた襟元にも見える形状をし、顔はほっそりとしたヒューマニティフェイス。高い位置に結わえられたスフィアの冷却を兼ねた髪などから、どこか花魁とかそんな雰囲気を醸し出しているように思える。
名は、闘妃。
ピクシードールには意味がないと思うんだけど、ハイヒールな脚甲を履いてる闘妃は、何体か持ってる夫人のバトルピクシーの中で、バランスタイプの一体だった。
「全力全開で来て頂戴、克樹君。これは公式戦ではないんだから、すべての力を使って、ね。それくらいでないと面白くないから」
「……わかってます」
夫人の余裕を感じる言葉に威圧されつつ、僕はそう応える。
今日ここに来たのは、僕から夫人にお願いしたからだった。
目的はリーリエの訓練。
百合乃の脳情報から構築されたリーリエだけど、百合乃の記憶を持たないために、戦闘経験は圧倒的に不足してる。
今後、おそらくもっと厳しい戦いがあるだろうエリキシルバトルを勝ち抜いて行くには、まだまだ未熟なリーリエの強化は必須な状況だと言えた。
『いくよ、リーリエ』
『うんっ』
スマートギア越しにイメージスピークで声をかけると、リーリエの元気のいい返事が返ってきた。
でもその声音に若干の硬さを感じる。
それも仕方ない。
ただ立っているだけなのに、平泉夫人も、彼女が操る闘妃からも、僕は息を呑むほどの圧力を感じているのだから。脳を擬似的に再現して、アリシアの目を通して見ているリーリエも、同じものを感じてるんだろう。
「始めましょう」
言って夫人は、鞭らしきものや槍や剣など、闘妃の腰や背中に携えた武器の中から、左右の腰に佩いた細く反りのない日本刀のような片刃の剣を引き抜いた。
リーリエがアリシアにナックルガードで覆った両手を構えさせ、ひと呼吸置いた後、脇に静かに控えていたメイドさんが手にしたゴングを鳴らした。
『先手ひっしょ――、わぁっ!』
ゴングと同時に飛び出したリーリエだったけど、すぐさま横に転がるようにして回避の動きをすることになった。
足首近くまでを覆う布地が揺れたと思った瞬間には、闘妃が滑るように動いて接近し、横薙ぎの斬撃を加えてきたからだった。
アリシアを追って闘妃が歩を進めてくる。
リーリエがアリシアを立ち上がらせた瞬間、頭上から振り下ろされた剣。
左の手甲で受け流して踏み出そうと右脚を上げたときには、斜め下からの閃きが襲いかかる。
バランスを崩しながらも上げていた右脚の脚甲で受け止め、その衝撃を利用してアリシアを下がらせたリーリエ。
間を置かず、リーリエはアリシアにキャンバスを蹴らせる。
Cカップバッテリを覆う胸甲が擦るんじゃないかと思うほどの前傾姿勢の突進を、正確無比な斬撃が阻んだ。
両腕で剣をガードして横に転がったアリシアは、そのまま闘妃から距離を取った。
『びっくりしたぁ』
『もっとよく見て動くんだ、リーリエ。さっきのじゃ夫人には通用しないぞ』
『わ、わかった』
立ち上がったアリシアを見て、僕はリーリエにそう声をかけていた。
リーリエと共有してるアリシアの視界を左隅に映しつつ、細かに人工筋の調整をする僕はスマートギア越しに平泉夫人のことを見る。
余裕の笑みを浮かべながらも、彼女が放つ空気からは隙なんてひと欠片も感じられない。
リングの中で夫人と同じ笑みを浮かべてる闘妃もまた、同様だった。
――いまのリーリエじゃ、百合乃の半分の力もないな。
二年前のスフィアカップの際には、辛勝ならが百合乃は平泉夫人を破ることができた。
たぶんそのときの戦いよりも正確さもドールの性能も上がっているだろう平泉夫人は、いまのリーリエで敵うような相手じゃない。
それでも僕は、そしてリーリエは、少しでも夫人に近づけるよう強くならなくちゃいけなかった。
『必殺技を使うよ、リーリエ』
『わかった。……でも、通じるかな?』
『やってみないとわからないが、僕たちは僕たちの全力で戦うだけだ』
『うん……。そうだねっ』
リーリエの闘志の籠もった返事を聞いて、僕は必殺技を使う準備をする。
ガーベラ戦のときよりも精密に使えるようになったアリシアの必殺技。リーリエも必殺技のときの動きにあのとき以上に慣れてる。
普通の人間の反応速度を超える動きができる必殺技が通じなかったら、僕たちには夫人に勝つ手段なんてない。
「今度はこちらからいくわね」
言って夫人は闘妃をアリシアに向けて前進させる。
動きそのものは普通に歩いてるようにしか見えないのに、間合いに入った瞬間、無造作に下ろしていた右腕から剣が繰り出された。
『ふっ』
本当に息をしているように声を出しつつ、リーリエはわずかに身体を反らして下から上に斬り上げられた剣を躱す。
剣の動きを捕捉するリーリエが、アリシアの腰を落としつつ前傾姿勢にさせたのを見て、僕はポインタを操作しつつ叫んだ。
『疾風迅雷!』
『うんっ』
リーリエの返事が聞こえたときには、アリシアは闘妃の前にはいない。
僕のスマートギアに搭載されたカメラでは捉えきれない速度で動いて、闘妃の正面にいたアリシアは背後まで駆け抜けている。
『え?』
『わわっ!』
闘妃の無防備な背中に拳を叩き込もうと腕を振り被ったとき、アリシアの視界は真っ黒に染まっていた。
――袖?!
実視界側で見てみると、アリシアの眼前を覆っていたのは着物のように腕から垂れている袖だった。
『防御!』
叫んだときにはもう遅い。
振り向きざまの闘妃の膝蹴りが、アリシアの顔面に叩き込まれていた。
『まだまだ!』
『あぁっ。電光石火!!』
吹き飛ばされたアリシアの体勢を瞬時に整えたリーリエに、再度必殺技を発動させる。
飛ばされた距離を超速度で詰めて反撃、と思ったのに――。
「勝負あり」
ゴングが鳴り、決着を告げた。
リングの中では、すっ転んでうつぶせに倒れてるアリシアと、その首に剣を突きつけてる闘妃の姿があった。
何が起こったのか、僕にはわからなかった。
電光石火を使ったと思った瞬間、アリシアは障害なんてないはずのリングの中で何かに足を取られたように転んでいた。
スマートギアの視界で拡大して見てみると、アリシアの両足首にまとわりついている黒い紐があった。
紐が繋がっている先は、闘妃の左手。
いつ手にしたのかわからない鞭が、その手に握られていた。
「いったいそれはなんですか?」
闘妃が鞭を振るう動きなんてなかった。
手にしたのはたぶんアリシアの視界を袖で覆ったときだと思うけど、振るいもしてない鞭が絡みつくなんてことはあり得ない。
「コントロールウィップっていう、この前発売された武器よ。第五世代でスフィアやフレームのデータラインが増えたのと、手に外部機器の接続ポイントをつくれるようになったでしょう? 人工筋でできてるから、鞭のように振るわなくても動かすことができるのよ、これ。面白いでしょう?」
「そうですか……」
スマートギアのディスプレイを上げ、いたずらな瞳をして楽しそうに笑う夫人に、僕はため息を吐くように返事をしていた。
相変わらずというか何と言うか、夫人はこういう新しいオモチャが大好きだ。
僕じゃ絶対買いそうにないコントロールウィップ。
何より怖いのは、太さと長さから考えたらたいした力は出せず、攻撃になんて使えそうにない武器を、上手いこと使い道を探し出す彼女の発想力だ。
『負ーけーたーっ。うぅ……』
「お疲れ、リーリエ」
戦闘中はオフにしてあった外部スピーカーをオンにした途端、リーリエの悔しそうな声が響いた。
そんな彼女にねぎらいの言葉をかけつつ、まったく勝てる気がしないにせよ、二戦目の戦法を頭の中で組み立てていた。
*
薫り高い紅茶をひと口すすり、僕は小さくため息を吐いた。
結局全部で五戦して、一度も勝つことができないどころか、クリーンヒットの一発すら食らわせることができなかった。
絨毯から家具から調度品から、僕なんかじゃ隔絶した世界だと感じる平泉夫人の執務室で、応接セットのソファに座った僕は、頭の中で今回の戦いの反省点を思い浮かべていた。
『うー、うー、うー』
スマートギアのスピーカーからうなり声が聞こえているリーリエも、仮想の脳を駆使していろいろ考えてるらしい。
テーブルの上で器用にあぐらをかいてるアリシアは、腕を組んで頬を膨らませ、少し顔を俯かせている。
机を挟んだ僕たちの目の前で優雅にティーカップを口元に寄せている平泉夫人は、そんな僕たちの様子を楽しそうな色を浮かべた瞳で眺めてきていた。
正直、スフィアカップで百合乃と拮抗した平泉夫人が、これほど強いとは思っていなかった。以前にも夫人とはリーリエと戦ってもらったことはあったが、そのときは軽くいなされるだけで終わっていた。今回は少しはまともに戦ってもらえたけど、結果があんまり変わったようには思えない。
目標とする山が高いのは悪くないことだと思うけど、最初の目標が断崖絶壁の世界最高峰ともなると、昇り始める前に挫折してしまいそうだった。
「さて、反省会でもしましょうか」
しばらくして、夫人がそう言ってカップをソーサーに置いた。
「本当のところ、リーリエはどうでした?」
「そうね。以前戦ったときとは見違えるほどに強くなってるわ。けれど性格が素直すぎるからかしらね? フェイントへの対応ができていないし、目が良い分、細かな挙動まで見えていて、一々それに反応してしまってる。ドールの扱いについては私以上と言っても過言ではないし、スピードもパワーも性能を熟知した上で細かいところまで扱えていて、フルコントロールソーサラーとしてはすでに上級者と言えるわ」
『でも、あたしは一発も当てられなかったよ?』
「そうね。そこは人生経験の差による駆け引き、というのもあるけれど、リーリエちゃんの場合はとくに戦闘経験の不足が原因。ボディの動かし方は戦闘補助ソフトで補正できるけれど、駆け引きは経験から学んでいくしかないところだからね」
「確かに、そうですね……」
痛いところを突かれて、僕は口元に寄せたカップから紅茶を飲んで、その渋みに顔を歪ませる。
リーリエの戦闘経験は、皆無というほどではないけど、ほとんどないと言っていい。
百合乃が死んだ後、僕がピクシーバトルへの興味を失ったのもあるけど、人工個性のリーリエをあまり大っぴらにするわけにはいかなかったという事情もあって、バトル経験を積ませてない。
リーリエにアリシアを与えて以降で戦ったのは、システム購入の際に世話になって、成果を見せるように言われてた平泉夫人と、技術的には凄いけどバトルソーサラーではないショージさんくらい。リーリエ自身は戦いを想定してアリシアの動かし方を訓練したり、ネットで公開されてるピクシーバトルの動画を見たりと色々してたみたいだけど。
本気でリーリエが戦ったのは、夏姫のブリュンヒルデ戦が初めてだった。
『でも必殺技も効かなかったよね? あたしは見えるけど、おにぃちゃんでも見えないくらいの速さなのに』
「それも同じ理由よ、リーリエちゃん。何かを仕掛けてくるというのは、わずかだけど準備の動作が見えれば気づけるし、どんなに早くても意外性のない動きは先が読めるのよ」
『そっかー。うぅーん』
「いや、まぁ、確かにそうかも知れないけど……」
アリシアに腕を組ませてうんうんと納得したように頷かせてるリーリエだけど、僕の方は全然納得ができるものじゃない。
主に距離を詰めるのに使ってる疾風迅雷は一度見ていれば対応できるかも知れないが、電光石火は目の前にいた敵が消えるような動きで背後や側面に回るのに使ってる必殺技だ。
空間転移による瞬間移動ではないからコンマ数秒の時間はかかるけど、使うのがわかってても対応できるのは僕の常識を逸脱してる。
ちなみに、ボディへの負担が大きく、畳み込むのに使う疾風怒濤は、結局一回も使う機会が得られなかった。
「リーリエちゃんはとにかく、もっと戦闘経験を積むこと。それから他の人の戦いをもっと見る必要があるわね」
『うん、わかったー』
「役に立ちそうな映像資料をリストにしておいたから、参考にして頂戴。芳野」
「はい」
近くに立って控えてるのに、存在を忘れそうになる芳野と呼ばれたメイドさん。
黒髪を結い上げ、黒い瞳をした、たぶん二十代前半だろう、白のエプロンに地味な黒いワンピースを身につけた彼女は、携帯端末をエプロンのポケットから取り出して操作する。
ヘッドホンから聞こえてきた着信音に、ディスプレイを下ろしてメールを開いてみると、様々な動画がリストになって送られてきていた。
リーリエにも共有設定を入れて見たリストには、ピクシーバトルの動画に留まらず、いろんな格闘技の記録動画なんかもラインナップされている。無料で見られるもの、有料のものも含め、相当な数に上っていた。
「もし手に入らないものがあったら言って頂戴。貸せるものもあるでしょうし、来てもらえばここで見せられるものもあるから。ちゃんと手に入れておいた方がいいものばかりなのだけどね」
「こんなに……。リーリエのためにありがとうございます」
「あら、何を言ってるの?」
座ったままだけど深々と礼をした僕の頭に降り注いだ夫人の声。
顔を上げると、彼女は冗談を一切含まない澄ました顔で言った。
「リーリエちゃんだけじゃなくて、これは貴方も見るものなのよ、克樹君」
「え? でも僕は……」
確かに僕が見ても戦いの参考になるとは思うけど、戦闘のときの主役はやっぱりリーリエだ。僕は本当に参考程度に見ておけばいいと思う。
でも、真剣な顔つきをし、目を細めた平泉夫人は、威圧するような雰囲気を漂わせながら言う。
「貴方はフルコントロールソーサラーになりなさい」
「……僕が?」
「そうよ。貴方の参加しているエリキシルバトルがどんな戦いで、これからどんな敵に出会っていくのかは、参加していない私にはわからないし、詮索する気もない。でもね、克樹君。私は予感がしてるの。リーリエちゃんには弱点があるのは貴方も知ってる通りでしょう? これから先、リーリエちゃんに頼らずに戦わないといけない局面も出てくると思うのよ。そして、リーリエちゃんの代わりという意味ではなく、貴方自身にもピクシーバトルを戦う力が、今後必ず必要になる。そう感じてるの」
憂い、なのだろうか。
複雑な色を浮かべている平泉夫人の言葉に、僕は反論できない。
何しろ近藤との戦いでは早速その弱点を突かれて、窮地に陥ったのだから。
――でもなんでなんだ?
「あの、なんでフルコントロールソーサラーなんです? 僕は一応セミコントロールでは全国レベルではないにしても、そこそこドールを動かせるんですが」
「はっきり言うと、ただの勘よ」
それまでの緊張を吹き払うように笑った夫人は言葉を続ける。
「貴方のソーサラーとしての才能は、百合乃ちゃんにはもちろん及ばないし、どんなに鍛えても私に並ぶことも難しいと思うわ。でも、フルコントロールソーサラーなら四つから六つのポインタを操作できるものだけど、貴方は最大で一〇個のポインタを同時に、それも精密に操作することができる。ポインタの複数操作はフルコントロールソーサラーには必須の能力で、貴方の数と精密さは戦いではそれほど役には立たないけれど、今後克樹君が進む道の先で、必要になりそうだと思えるの」
「……わかりました」
ため息を吐きつつ。僕は了解の返事をした。
平泉夫人の勘は、僕もそれに助けられたことがあるから知ってるけど、恐ろしいほどに鋭い。
実際には勘と言うより閃きなんだと思う。様々な情報を蓄積してる夫人は、無意識のうちに問題の根っこを関知する能力に長けてるんだろう。
魔物が跋扈してるような財界とかで生きながら、女ひとりで規模は小さいとは言えやっていけるてるのは、そうした夫人の感知能力に負うところが大きいのかも知れない。
「それからこの辺りも全部とは言わないけれど、訓練の進み具合に応じて用意した方がいいわね」
夫人の目配せの指示を受けて芳野さんが送ってくれたのは、ピクシードールのアプリやアドオンソフトのリスト。
定番のフルコントロールアプリの最新版や、たぶん第五世代で新しく出てきただろうアドオンソフトなど、映像資料と同じくらいの項目が並んでいた。
スフィアドールに関わるいくつもの会社に出資や協力をしていて、自分の趣味でもあって詳しいのは知ってるけど、僕が家で調べるよりも多くのことを平泉夫人が知ってるのを感じる。決定的に嗅覚が違う。
「それとこれを買いなさい、克樹君」
言って夫人が芳野さんから受け取って僕に差し出してきたのは、薄い冊子の商品カタログ。
紙に印刷されていたものはほとんどが電子データに置き換わっているけど、宣伝を勝手に個人の端末に送ることはできないので、カタログや宣伝資料なんかはいまでも紙で配られてることが多い。
渡されたのはそんな商品カタログで、メカニカルウェア(MW)社という、スマートギアメーカーとして有名な会社のもの。一般向けから軍事産業向けまで様々に、とくに高性能高機能なモデルを中心に売ってる中でも、一般向けの最高グレード、プロゲーマーでも買うのをためらう高級シリーズの、つい最近発売された最新モデルのカタログだった。
ディスプレイを跳ね上げてまじまじとカタログを眺める僕は、開いて一覧に書かれた参考価格に息を詰まらせる。
「やっぱ高いですね、ここのは」
「えぇ、そうね。でも克樹君に必要なのはこのモデルよ」
手を伸ばしてきた夫人が開いたページに写真や表入りで掲載されているのは、カタログの中でも一番高いモデル。プレミアムグレードに位置するものだった。
その価格は、趣味の品としてはけっこう高いと言われるバトル用ピクシードールを新規で二体買っても充分お釣がくるくらいだ。
『すごいねぇ、おにぃちゃん。こんなの使うんだぁ』
「いや……、さすがにここまでのは必要ないと思うんだけど……」
「いいえ、必要よ」
高級グレードながら飾りが凄かったりゴツかったりしないスマートな形状のそのモデルの写真から顔を上げ、夫人はにっこりと笑う。
「展示会で少し使ってみたのだけど、一般向けとしては性能も機能も最高なのは当然として、外部カメラや集音マイクにも気を遣っているのよ。これからもリーリエちゃんとあの戦いを勝ち抜いていくつもりなら、これくらいのものは絶対に必要になるわ」
「わかりました。検討しま――ぐ、うっ」
返事をしようとした僕は、途中で喉を詰まらせた。
目の前では平泉夫人が微笑んでる。
黒真珠とあだ名される彼女の黒く艶やかな髪と、髪と服の黒さの対比で輝いているようにも見える白い肌。
いつもと変わらぬ柔らかい笑みを口元に浮かべながら、あだ名の通り黒真珠のような瞳に浮かんでいるもの。
それを見た僕は、背筋を凍るような感覚を覚えていた。
「これは提案じゃないの、克樹君。命令。わかる?」
「でもさすがに、これは……。いまのでもそんなに不都合ないですし、高いですし……」
「先月発売されたHPT社のヒューマニティフェイス、売れ行きは好調だそうじゃない? 価格を下げた前世代には及ばないけれど、生産が追いつかないと聞いてるわよ。いまの克樹君なら、買えるでしょう?」
本当に夫人の業界情報を仕入れる速さはどれくらいのものなのか。
頬を膨らませたり口をすぼめたりできる新型フェイスの売れ行きは、第五世代のパーツが出揃って買い換え需要が高まってきてるのもあって、かなり好調だった。売れ行きに応じて支払額が変わる僕への報酬も、過去最高になってる。
それだけじゃなく機能面をエルフやフェアリーサイズのドールへの応用も始まっていて、最近僕にHPT社から支払われた金額は、サラリーマンのボーナス並みになっていた。
「貴方にはこれが絶対必要になるから、必ず買いなさい。生産数が少なくて品薄だけれど、手配は私の方でして上げるから、連絡が届いたらすぐに支払いの手続きをして頂戴。できるだけ安くなるよう、交渉しておくわ」
「――わかりました」
間接的とは言え、懐事情すら把握してて、これまでいろんな貸しのある夫人の命令に僕が従わないわけにはいかない。
「克樹君。貴方には必ずあの戦いを勝ち抜いてほしいのよ。貴方の願いには賛同しかねるし、最後にどんなことが待ち受けているのかもわからない。でも、なんとなく、これは本当になんとなくの予感なのだけど、貴方は最後まで見届けなければならないように思えるの」
「……えぇ」
憂いを含んだ夫人の瞳が、僕の何を、そしてエリキシルバトルの何を見ているのかはわからない。
でもたぶん、純粋に僕のことを想って言ってくれてることなのはわかる。だから僕は、彼女の心配そうに揺れている瞳に、頷きを返していた。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

鋼殻牙龍ドラグリヲ
南蛮蜥蜴
ファンタジー
歪なる怪物「害獣」の侵攻によって緩やかに滅びゆく世界にて、「アーマメントビースト」と呼ばれる兵器を操り、相棒のアンドロイド「カルマ」と共に戦いに明け暮れる主人公「真継雪兎」
ある日、彼はとある任務中に害獣に寄生され、身体を根本から造り替えられてしまう。 乗っ取られる危険を意識しつつも生きることを選んだ雪兎だったが、それが苦難の道のりの始まりだった。
次々と出現する凶悪な害獣達相手に、無双の機械龍「ドラグリヲ」が咆哮と共に牙を剥く。
延々と繰り返される殺戮と喪失の果てに、勇敢で臆病な青年を待ち受けるのは絶対的な破滅か、それともささやかな希望か。
※小説になろう、カクヨム、ノベプラでも掲載中です。
※挿絵は雨川真優(アメカワマユ)様@zgmf_x11dより頂きました。利用許可済です。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

関西訛りな人工生命体の少女がお母さんを探して旅するお話。
虎柄トラ
SF
あるところに誰もがうらやむ才能を持った科学者がいた。
科学者は天賦の才を得た代償なのか、天涯孤独の身で愛する家族も頼れる友人もいなかった。
愛情に飢えた科学者は存在しないのであれば、創造すればいいじゃないかという発想に至る。
そして試行錯誤の末、科学者はありとあらゆる癖を詰め込んだ最高傑作を完成させた。
科学者は人工生命体にリアムと名付け、それはもうドン引きするぐらい溺愛した。
そして月日は経ち、可憐な少女に成長したリアムは二度目の誕生日を迎えようとしていた。
誕生日プレゼントを手に入れるため科学者は、リアムに留守番をお願いすると家を出て行った。
それからいくつも季節が通り過ぎたが、科学者が家に帰ってくることはなかった。
科学者が帰宅しないのは迷子になっているからだと、推察をしたリアムはある行動を起こした。
「お母さん待っててな、リアムがいま迎えに行くから!」
一度も外に出たことがない関西訛りな箱入り娘による壮大な母親探しの旅がいまはじまる。
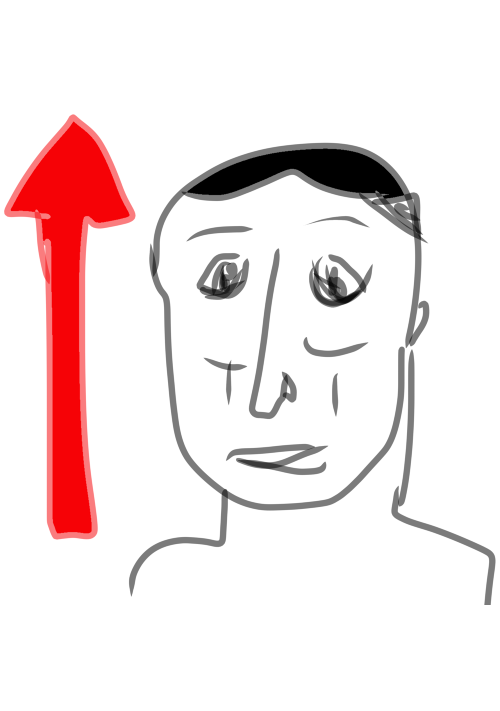
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)


決戦の夜が明ける ~第3堡塁の側壁~
独立国家の作り方
SF
ドグミス国連軍陣地に立て籠もり、全滅の危機にある島民と共に戦おうと、再上陸を果たした陸上自衛隊警備中隊は、条約軍との激戦を戦い抜き、遂には玉砕してしまいます。
今より少し先の未来、第3次世界大戦が終戦しても、世界は統一政府を樹立出来ていません。
南太平洋の小国をめぐり、新世界秩序は、新国連軍とS条約同盟軍との拮抗状態により、4度目の世界大戦を待逃れています。
そんな最中、ドグミス島で警備中隊を率いて戦った、旧陸上自衛隊1等陸尉 三枝啓一の弟、三枝龍二は、兄の志を継ぐべく「国防大学校」と名称が変更されたばかりの旧防衛大学校へと進みます。
しかし、その弟で三枝家三男、陸軍工科学校1学年の三枝昭三は、駆け落ち騒動の中で、共に協力してくれた同期生たちと、駐屯地の一部を占拠し、反乱を起こして徹底抗戦を宣言してしまいます。
龍二達防大学生たちは、そんな状況を打破すべく、駆け落ちの相手の父親、東京第1師団長 上条中将との交渉に挑みますが、関係者全員の軍籍剥奪を賭けた、訓練による決戦を申し出られるのです。
力を持たない学生や生徒達が、大人に対し、一歩に引くことなく戦いを挑んで行きますが、彼らの選択は、正しかったと世論が認めるでしょうか?
是非、ご一読ください。

惑星保護区
ラムダムランプ
SF
この物語について
旧人類と別宇宙から来た種族との出来事にまつわる話です。
概要
かつて地球に住んでいた旧人類と別宇宙から来た種族がトラブルを引き起こし、その事が発端となり、地球が宇宙の中で【保護区】(地球で言う自然保護区)に制定され
制定後は、他の星の種族は勿論、あらゆる別宇宙の種族は地球や現人類に対し、安易に接触、交流、知能や技術供与する事を固く禁じられた。
現人類に対して、未だ地球以外の種族が接触して来ないのは、この為である。
初めて書きますので読みにくいと思いますが、何卒宜しくお願い致します。

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~
おとら@ 書籍発売中
ファンタジー
アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。
どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。
そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。
その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。
その結果、様々な女性に迫られることになる。
元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。
「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」
今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















