お気に入りに追加
25
あなたにおすすめの小説

【完結】別れ……ますよね?
325号室の住人
BL
☆全3話、完結済
僕の恋人は、テレビドラマに数多く出演する俳優を生業としている。
ある朝、テレビから流れてきたニュースに、僕は恋人との別れを決意した。
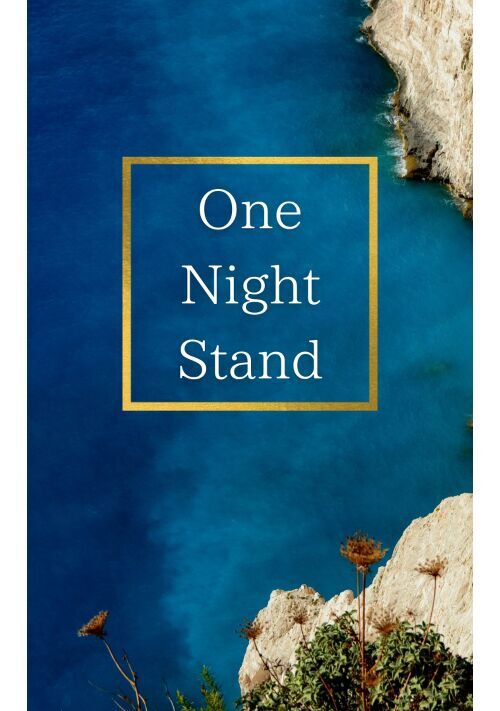
One Night Stand
楓
BL
「今日、デートしよ。中嶋瑛斗くん」
「……は?」
中嶋瑛斗(なかじまえいと)は都内の大学に通う4年生。就職も決まり、大学最後の思い出作りにと、貯めたお金で友人山本とハワイへ旅行に来ていた。ハワイでの滞在も残すところあと2日となった日。ひとり高級住宅街に迷い込んだ瑛斗は、長身の美男子、相良葵(さがらあおい)と出会う。我が儘で横暴な相良と強制的に1日デートすることになり、最初は嫌々付き合っていた瑛斗だが、相良を知る内に段々と惹かれていく自分を自覚して――。
スパダリ年上男子と可愛い系大学生の異国で繰り広げられる甘くて切ない一夜の恋の話。
★ハッピーエンドです。
★短い続きものです。
★後半に絡みがあります。苦手な方はご注意ください。
★別ジャンルで書いた物をオリジナルBLにリメイクした作品です。

十七歳の心模様
須藤慎弥
BL
好きだからこそ、恋人の邪魔はしたくない…
ほんわか読者モデル×影の薄い平凡くん
柊一とは不釣り合いだと自覚しながらも、
葵は初めての恋に溺れていた。
付き合って一年が経ったある日、柊一が告白されている現場を目撃してしまう。
告白を断られてしまった女の子は泣き崩れ、
その瞬間…葵の胸に卑屈な思いが広がった。
※fujossy様にて行われた「梅雨のBLコンテスト」出品作です。

愛玩人形
誠奈
BL
そろそろ季節も春を迎えようとしていたある夜、僕の前に突然天使が現れた。
父様はその子を僕の妹だと言った。
僕は妹を……智子をとても可愛がり、智子も僕に懐いてくれた。
僕は智子に「兄ちゃま」と呼ばれることが、むず痒くもあり、また嬉しくもあった。
智子は僕の宝物だった。
でも思春期を迎える頃、智子に対する僕の感情は変化を始め……
やがて智子の身体と、そして両親の秘密を知ることになる。
※この作品は、過去に他サイトにて公開したものを、加筆修正及び、作者名を変更して公開しております。

お客様と商品
あかまロケ
BL
馬鹿で、不細工で、性格最悪…なオレが、衣食住提供と引き換えに体を売る相手は高校時代一度も面識の無かったエリートモテモテイケメン御曹司で。オレは商品で、相手はお客様。そう思って毎日せっせとお客様に尽くす涙ぐましい努力のオレの物語。(*ムーンライトノベルズ・pixivにも投稿してます。)

フローブルー
とぎクロム
BL
——好きだなんて、一生、言えないままだと思ってたから…。
高二の夏。ある出来事をきっかけに、フェロモン発達障害と診断された雨笠 紺(あまがさ こん)は、自分には一生、パートナーも、子供も望めないのだと絶望するも、その後も前向きであろうと、日々を重ね、無事大学を出て、就職を果たす。ところが、そんな新社会人になった紺の前に、高校の同級生、日浦 竜慈(ひうら りゅうじ)が現れ、紺に自分の息子、青磁(せいじ)を預け(押し付け)ていく。——これは、始まり。ひとりと、ひとりの人間が、ゆっくりと、激しく、家族になっていくための…。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















