お気に入りに追加
4
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

【完結】亡き冷遇妃がのこしたもの〜王の後悔〜
なか
恋愛
「セレリナ妃が、自死されました」
静寂をかき消す、衛兵の報告。
瞬間、周囲の視線がたった一人に注がれる。
コリウス王国の国王––レオン・コリウス。
彼は正妃セレリナの死を告げる報告に、ただ一言呟く。
「構わん」……と。
周囲から突き刺さるような睨みを受けても、彼は気にしない。
これは……彼が望んだ結末であるからだ。
しかし彼は知らない。
この日を境にセレリナが残したものを知り、後悔に苛まれていくことを。
王妃セレリナ。
彼女に消えて欲しかったのは……
いったい誰か?
◇◇◇
序盤はシリアスです。
楽しんでいただけるとうれしいです。
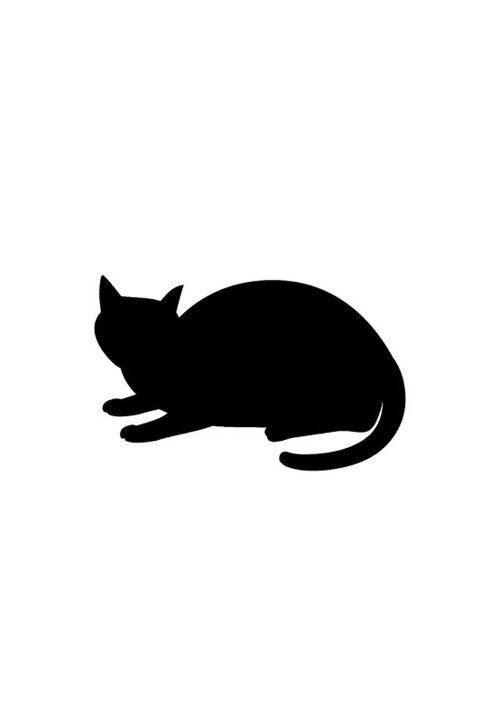
名探偵あやのん(仮)
オヂサン
ミステリー
これはSAISONというアイドルグループのメンバーである「林あやの」さんと、その愛猫「タワシ」をモデルにした創作ナゾトキです。なお登場人物の「小島ルナ」も前述のSAISONのメンバー(正確には小島瑠那さん)です。
元々稚拙な文章の上、そもそもがこのSAISONというグループ、2人の人となりや関係性を知ってる方に向けての作品なので、そこを知らない方は余計に???な描写があったり、様々な説明が不足に感じるとは思いますがご容赦下さい。
なお、作中に出てくるマルシェというコンカフェもキャストも完全なフィクションです(実際には小島瑠那さんは『じぇるめ』というキチンとしたコンカフェを経営してらっしゃいます)。

異世界子ども食堂:通り魔に襲われた幼稚園児を助けようとして殺されたと思ったら異世界に居た。
克全
児童書・童話
両親を失い子ども食堂のお世話になっていた田中翔平は、通り魔に襲われていた幼稚園児を助けようとして殺された。気がついたら異世界の教会の地下室に居て、そのまま奴隷にされて競売にかけられた。幼稚園児たちを助けた事で、幼稚園の経営母体となっている稲荷神社の神様たちに気に入られて、隠しスキルと神運を手に入れていた田中翔平は、奴隷移送用馬車から逃げ出し、異世界に子ども食堂を作ろうと奮闘するのであった。

病院の僧侶(プリースト) と家賃という悪夢にしばられた医者
加藤かんぬき
ミステリー
僧侶サーキスは生き別れた師匠を探す旅の途中、足の裏に謎の奇病が出現。歩行も困難になり、旅を中断する。
そして、とある病院で不思議な医者、パディ・ライスという男と出会う。
中世時代のヨーロッパという時代背景でもありながら、その医者は数百年は先の医療知識と技術を持っていた。
医療に感銘を受けた僧侶サーキスはその病院で働いていくことを決心する。
訪れる患者もさまざま。
まぶたが伸びきって目が開かない魔女。
痔で何ものにもまたがることもできなくなったドラゴン乗りの戦士。
声帯ポリープで声が出せなくなった賢者。
脳腫瘍で記憶をなくした勇者。
果たしてそのような患者達を救うことができるのか。
間接的に世界の命運は僧侶のサーキスと医者パディの腕にかかっていた。
天才的な技術を持ちながら、今日も病院はガラガラ。閑古鳥が鳴くライス総合外科病院。
果たしてパディ・ライスは毎月の家賃を支払うことができるのか。
僧侶のサーキスが求める幸せとは。
小説家になろう、カクヨムにも掲載しています。

縁仁【ENZIN】 捜査一課 対凶悪異常犯罪交渉係
鬼霧宗作
ミステリー
【続編の連載を始めました。そちらのほうもよろしくお願いいたします】
近代において日本の犯罪事情は大きな変化を遂げた。理由なき殺人、身勝手な殺人、顔の見えぬ殺人――。常軌を逸脱した事件が日常の隣で息をひそめるような狂った世界へと、世の中は姿を変えようとしていた。
常人には理解できぬ思考回路で繰り返される猟奇事件。事態を重く見た政府は、秘密裏に警察組織へと不文律を組み込んだ。表沙汰になれば世の中が許さぬ不文律こそが、しかし世の中の凶悪事件に対抗する唯一の手段だったのだから。
その男の名は坂田仁(さかたじん)――。かつて99人を殺害した凶悪猟奇殺人犯。通称九十九人(つくも)殺しと呼ばれる彼は、数年前に死刑が執行されているはずの死刑囚である。
これは死刑囚であるはずの凶悪猟奇殺人鬼と、数奇なる運命によって対凶悪異常犯罪交渉係へと着任した刑事達が、猟奇事件に立ち向かう物語。
スナック【サンテラス】の事件奇譚に続く、安楽椅子探偵新シリーズ。
――今度は独房の中で推理する。
【事例1 九十九殺しと孤高の殺人蜂】《完結》
【事例2 美食家の悪食】《完結》
【事例3 正面突破の解放軍】《完結》
【事例4 人殺しの人殺し】《完結》
イラスト 本崎塔也


有栖と奉日本『ミライになれなかったあの夜に』
ぴえ
ミステリー
有栖と奉日本シリーズ第八話。
『過去』は消せない
だから、忘れるのか
だから、見て見ぬ振りをするのか
いや、だからこそ――
受け止めて『現在』へ
そして、進め『未来』へ
表紙・キャラクター制作:studio‐lid様(twitter:@studio_lid)

真実【完結】
真凛 桃
恋愛
自分のせいで事件に巻き込まれた彼女を守るため、命懸けの決断をするイケメン俳優。だが、それがきっかけで2人は別れることに…
それから3年後。イケメン俳優は新たな真実を知ることになる。2人の行方は……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















