2 / 5
2話
しおりを挟む
ソバッカスは、悪魔と契約し美しさを手に入れた罪。母は美しさで男達を誘惑し、生気を吸い取った罪。
その時、もしも僕の顔が母の暴力で腫れ上がっていなければ、親子共々殺されていただろう。役人は酒で暴れる母を引きずりながら、ソバッカスを始めとする三人の女達を、大きな鳥籠のような檻にぶち込み吊るし上げた。
翌日だったか。訳のわからない魔女裁判とやらが行われ、檻籠は炎の中に入れられた。
脳を切り裂く様な断末魔の悲鳴の中、母だけが哂っていた。
いつの日だったか、英雄と謳われた若い娘の公開処刑を見に行った事があった。母は『所詮、神の声が聞けても人間は人間だ。歳も取ればいつか死ぬ』と冷たく僕に呟いた。
あの時に良く似ていた。娘も、悲鳴ではなく言葉を唱えていたから。
「所詮、美しくとも人間は人間。歳も取るし、いつかは死ぬ」
僕も、あの時の母の様に冷たく言い放った。そして、腫れ上がった顔を隠すストールの下で、必死に嗚咽を殺して泣いた。
僕は家で独り、今度は声に出して泣いた。泣いていたら、ソバッカスの母親が僕を尋ねてきた。赤く腫れた眼と青く膨れた顔を再びストールで覆って出迎えると、ソバッカスの母親も同じ様に泣いていた。
「あの子はねぇ、良い子だったんだよ。アンタの事が好きでね、いつもアンタと並んで歩いても恥ずかしくない様に綺麗になるんだと言っていたんだよ」
ソバッカスの母親は、僕に銀のロザリオを渡した。
「あの子の形見だからね、アンタに」
それから三日後ぐらいだったと記憶する。突然、劇場の団長が僕を連れに来た。聞けば生前、母が僕を借金のカタにしていたらしい。
「お前には多額の金がかかってるんだ。必要以上に働いてもらうぞ!! 恨むんなら“ロスピアーニャ・バシュロ・ナルカン”を恨むんだな」
僕は反抗する間もなく医者に連れて行かれ、そのまま団員にされてしまった。
団長には、毎日のように虐められる、僕。これは、後から団員同士の噂話で耳にしたのだが、団長は母にゾッコンだったそうだ。母は脂ののった団長には興味が無く、それでも騙すようにして金や貢ぎ物を巻き上げていたらしい。近いうちに、母を自分のモノにする。そんな団長の野心も魔女狩りと共に消えて失くなった。
母にそっくりな僕は、心も身体も男だ。母への腹いせに、団長は僕を奴隷として死ぬまで離さない気だ。
飲み残しのワインと少しばかりのパンくず、夕食の残り物を与えられ、団員達の世話に加え舞台の上で血が滲むまで踊らされる、毎日。それが、舞台を見上げる観客達の想像とは遥かに劣るトップスター、シャルル・アンリ・バシュロ・ナルカンの私生活だ。
いつか、この顔を焼いてしまおうかと考えた事もあった。顔を焼いてしまえば、母の呪縛から開放される。そんな気がしたから。
……実際には出来る筈もなく、僕にはそんな勇気もなかった。
「愛しき王子様。今宵も貴方の為に、あのギラギラと輝く月の世界から……」
僕だって、人間だ。台詞に詰まることもある。その瞬間、団長が持っていた木のコップを投げ付けた。それは、舞台上にワインをぶちまけながら僕の背中に直撃すると、鈍い音を立てながら床に転がった。
王子こと相手役であるダミアン・バルテレモンが、慌てて僕の元へと駆け寄ってきた。
「この木偶の坊が!!」
団長の怒鳴り声が、辺りに響き渡る。
「すいません」
屈辱に震えながらも逆らう事すら許されず、ダミアンに支えられながらゆっくりと身体を起こした。、
「あのギラギラとかがやく月の世界から、やって参りました」
「あぁ、月の影法師よ。あの月がヴェールに隠れてしまう度、私は君も隠れてしまうのではないかと心配なんだ」
「王子様、今日の夜は晴れています。貴方に会えた私の心の様に」
団長が手を叩きながら、満足そうに言う。
「ダミアン、なかなか良い芝居になりそうじゃないか」
こんな時、ダミアンが嫌味を込めて団長に言う台詞がある。
「シャルルが、美人なんでね」
団長は、いつも通り鼻で哂った。
「そろそろ、飯にしようじゃないか。シャルル、直ぐに支度するんだ」
僕も嫌味を込めて、団長へ婦人の一礼をした。
全員が舞台を離れようとするタイムングで、脚本書きのサガスピエールが走り寄って来た。
「月の影法師は、傑作だ! ご婦人方だけでなく、全ての観客が涙すること間違いないぞ」
実はこの“月の影法師”まだ完成していなかったのだ。
正直、劇の中身なんて僕にとってはどうでもいい。僕は、命じられたまま演じるだけだ。それより、団長にまた怒られる前にさっさと食事の支度をしようとサガスピエールの横を擦り抜けようとしたら、まあ待てと彼に腕を掴まれた。
「シャルル。是非、君にも意見を聞きたいんだ」
「僕に?」
「そぅ。いつもハッピーエンドだからね、今回は、バッドエンドにしてみたんだ」
月の影法師。ストーリーはこうだ。
ある国に、一人の王子がいた。王子は月に語りかけながら薔薇の咲き乱れる自慢の庭を、毎晩散歩するのが大好きであった。
やがて、王子にも婚期が訪れる。ハンサムな王子を狙う女性は後を絶たなかったが、何度お見合いをしても、王子は気に入った女性に巡り合う事が出来なかった。毎日、王子はうんざりと過ごしていた。
ある晩、いつもの様に窓から身を乗り出し月を眺めていると、庭の白薔薇道を歩く一人の美しい娘を見つけた。その娘を運命の妻だと見初めた王子は、なんの疑いもなくその娘に声を掛けた。
娘は言う。いつか自分も王子と共に白薔薇道を歩いてみたいと思っていた、と。王子は娘に、いつでも待っていますよ、と告げた。
翌日も娘は現れた。王子は娘の名前を聞いてみることにした。娘は“月の影法師”とだけ答えた。
月の影法師は、月の綺麗な夜にだけ現れた。
時が流れても、彼は幸せであった。
変わらない月の影法師。愛を語り共に夢を見て……だが、王子の時間だけは無情にも流れていった。
ある日、水面に映る自分の老いた姿を見つめて王子は絶望する。絶望は怒りとなり、変わらない月の影法師を魔女だと罵り始めた。
月の影法師は自分が月の精霊である事を明かし、王子の前に現れる以前から王子の事を愛していたと告げた。しかし、年をとり、絶望した王子には理解されなかった。
王子は、月の影法師を塔から突き落とそうとし、逆に王子が足を滑らせて死んでしまうのだ。
嘆き悲しむ影法師を背景に、舞台はそこで幕を閉じる。
「どうだい? シャルルは悲しい役の方が、より一層引き立つと思うんだ」
サガスピエールの問いに、僕はどう答えたらいいか戸惑いながらも、月並みな感想を述べた。
「いい話だね。きっとまた満員になるよ」
サガスピエールは、満足そうに頷いた。
せめて、コメディとまではいなかいにしろ、ハッピーエンドであれば良かったと思う。そうすれば、舞台の上だけでも悲しくはなくなるから。
少し紹介が遅れたが、ダミアン・バルテレモンは、僕の相手方や二枚目の主役を演じる事が多かった。彼は僕とは対照的な男らしい色気を持っていたから、この劇団では僕と並ぶ程の人気っぷりだ。
なにより、ダミアンは僕の一番の親友でもあった。
ダミアンとは、よく二人で語り合ったものだ。中でも特に印象深いのが、月の影法師の公演前夜だ。
僕は部屋を訪れて来てくれたダミアンの為、転がる蝋燭を手探りで拾いあげると火を点けた。
「シャルル、見てくれよ」
ダミアンは、持っていた箱の中から銀のカップを一つ取り出し、僕の前に差し出した。カップを手に取ると、繊細な彫刻が施されていて、実に綺麗な品だった。
「綺麗だね。これがどうしたの?」
僕の問いに、ダミアンは興奮気味に答えた。
「父の形見だよ。聖女から貰った物らしいんだ」
「へぇ、凄いじゃないか」
驚いた顔を向ける僕の手からダミアンはカップを受け取ると、彼はそれを蝋燭の揺らめく炎の明かりに照らしながら、愛しそうに彫刻を撫でた。
「僕はね、オルレアンから来たんだよ。自分を偽って役者になった。これは、戦士だった父が戦場で肺を患い已むなく帰還する時、聖女が回復と幸せを祈って父にくれたものなんだよ。優しさ、気品、強さに幼い僕は憧れた。だけど、父には敵わないと思った。だから、舞台の上ではどんな勇者にでもなれる役者を目指したんだ」
暫く愛しそうに銀のカップを眺めていたダミアン。その横顔は、蝋燭の炎に揺らめきながら、うっとりする程魅惑的に見えた。
「シャルル、このカップを今だけ君に貸してあげようと思うんだ」
「え?」
彼の意外な申し出に、僕は思わず疑問符を上げた。
「これは父が、“幸運”と“回復”を願って贈られたものだから。明日の公演で、君に幸福が舞い降りますように。僕は君と最高の芝居がしたいんだよ」
ダミアンの大切な大切な銀のカップを再び受け取ると、僕も彼と同様に銀のカップを優しく愛でた。
「ありがとう」
その時、もしも僕の顔が母の暴力で腫れ上がっていなければ、親子共々殺されていただろう。役人は酒で暴れる母を引きずりながら、ソバッカスを始めとする三人の女達を、大きな鳥籠のような檻にぶち込み吊るし上げた。
翌日だったか。訳のわからない魔女裁判とやらが行われ、檻籠は炎の中に入れられた。
脳を切り裂く様な断末魔の悲鳴の中、母だけが哂っていた。
いつの日だったか、英雄と謳われた若い娘の公開処刑を見に行った事があった。母は『所詮、神の声が聞けても人間は人間だ。歳も取ればいつか死ぬ』と冷たく僕に呟いた。
あの時に良く似ていた。娘も、悲鳴ではなく言葉を唱えていたから。
「所詮、美しくとも人間は人間。歳も取るし、いつかは死ぬ」
僕も、あの時の母の様に冷たく言い放った。そして、腫れ上がった顔を隠すストールの下で、必死に嗚咽を殺して泣いた。
僕は家で独り、今度は声に出して泣いた。泣いていたら、ソバッカスの母親が僕を尋ねてきた。赤く腫れた眼と青く膨れた顔を再びストールで覆って出迎えると、ソバッカスの母親も同じ様に泣いていた。
「あの子はねぇ、良い子だったんだよ。アンタの事が好きでね、いつもアンタと並んで歩いても恥ずかしくない様に綺麗になるんだと言っていたんだよ」
ソバッカスの母親は、僕に銀のロザリオを渡した。
「あの子の形見だからね、アンタに」
それから三日後ぐらいだったと記憶する。突然、劇場の団長が僕を連れに来た。聞けば生前、母が僕を借金のカタにしていたらしい。
「お前には多額の金がかかってるんだ。必要以上に働いてもらうぞ!! 恨むんなら“ロスピアーニャ・バシュロ・ナルカン”を恨むんだな」
僕は反抗する間もなく医者に連れて行かれ、そのまま団員にされてしまった。
団長には、毎日のように虐められる、僕。これは、後から団員同士の噂話で耳にしたのだが、団長は母にゾッコンだったそうだ。母は脂ののった団長には興味が無く、それでも騙すようにして金や貢ぎ物を巻き上げていたらしい。近いうちに、母を自分のモノにする。そんな団長の野心も魔女狩りと共に消えて失くなった。
母にそっくりな僕は、心も身体も男だ。母への腹いせに、団長は僕を奴隷として死ぬまで離さない気だ。
飲み残しのワインと少しばかりのパンくず、夕食の残り物を与えられ、団員達の世話に加え舞台の上で血が滲むまで踊らされる、毎日。それが、舞台を見上げる観客達の想像とは遥かに劣るトップスター、シャルル・アンリ・バシュロ・ナルカンの私生活だ。
いつか、この顔を焼いてしまおうかと考えた事もあった。顔を焼いてしまえば、母の呪縛から開放される。そんな気がしたから。
……実際には出来る筈もなく、僕にはそんな勇気もなかった。
「愛しき王子様。今宵も貴方の為に、あのギラギラと輝く月の世界から……」
僕だって、人間だ。台詞に詰まることもある。その瞬間、団長が持っていた木のコップを投げ付けた。それは、舞台上にワインをぶちまけながら僕の背中に直撃すると、鈍い音を立てながら床に転がった。
王子こと相手役であるダミアン・バルテレモンが、慌てて僕の元へと駆け寄ってきた。
「この木偶の坊が!!」
団長の怒鳴り声が、辺りに響き渡る。
「すいません」
屈辱に震えながらも逆らう事すら許されず、ダミアンに支えられながらゆっくりと身体を起こした。、
「あのギラギラとかがやく月の世界から、やって参りました」
「あぁ、月の影法師よ。あの月がヴェールに隠れてしまう度、私は君も隠れてしまうのではないかと心配なんだ」
「王子様、今日の夜は晴れています。貴方に会えた私の心の様に」
団長が手を叩きながら、満足そうに言う。
「ダミアン、なかなか良い芝居になりそうじゃないか」
こんな時、ダミアンが嫌味を込めて団長に言う台詞がある。
「シャルルが、美人なんでね」
団長は、いつも通り鼻で哂った。
「そろそろ、飯にしようじゃないか。シャルル、直ぐに支度するんだ」
僕も嫌味を込めて、団長へ婦人の一礼をした。
全員が舞台を離れようとするタイムングで、脚本書きのサガスピエールが走り寄って来た。
「月の影法師は、傑作だ! ご婦人方だけでなく、全ての観客が涙すること間違いないぞ」
実はこの“月の影法師”まだ完成していなかったのだ。
正直、劇の中身なんて僕にとってはどうでもいい。僕は、命じられたまま演じるだけだ。それより、団長にまた怒られる前にさっさと食事の支度をしようとサガスピエールの横を擦り抜けようとしたら、まあ待てと彼に腕を掴まれた。
「シャルル。是非、君にも意見を聞きたいんだ」
「僕に?」
「そぅ。いつもハッピーエンドだからね、今回は、バッドエンドにしてみたんだ」
月の影法師。ストーリーはこうだ。
ある国に、一人の王子がいた。王子は月に語りかけながら薔薇の咲き乱れる自慢の庭を、毎晩散歩するのが大好きであった。
やがて、王子にも婚期が訪れる。ハンサムな王子を狙う女性は後を絶たなかったが、何度お見合いをしても、王子は気に入った女性に巡り合う事が出来なかった。毎日、王子はうんざりと過ごしていた。
ある晩、いつもの様に窓から身を乗り出し月を眺めていると、庭の白薔薇道を歩く一人の美しい娘を見つけた。その娘を運命の妻だと見初めた王子は、なんの疑いもなくその娘に声を掛けた。
娘は言う。いつか自分も王子と共に白薔薇道を歩いてみたいと思っていた、と。王子は娘に、いつでも待っていますよ、と告げた。
翌日も娘は現れた。王子は娘の名前を聞いてみることにした。娘は“月の影法師”とだけ答えた。
月の影法師は、月の綺麗な夜にだけ現れた。
時が流れても、彼は幸せであった。
変わらない月の影法師。愛を語り共に夢を見て……だが、王子の時間だけは無情にも流れていった。
ある日、水面に映る自分の老いた姿を見つめて王子は絶望する。絶望は怒りとなり、変わらない月の影法師を魔女だと罵り始めた。
月の影法師は自分が月の精霊である事を明かし、王子の前に現れる以前から王子の事を愛していたと告げた。しかし、年をとり、絶望した王子には理解されなかった。
王子は、月の影法師を塔から突き落とそうとし、逆に王子が足を滑らせて死んでしまうのだ。
嘆き悲しむ影法師を背景に、舞台はそこで幕を閉じる。
「どうだい? シャルルは悲しい役の方が、より一層引き立つと思うんだ」
サガスピエールの問いに、僕はどう答えたらいいか戸惑いながらも、月並みな感想を述べた。
「いい話だね。きっとまた満員になるよ」
サガスピエールは、満足そうに頷いた。
せめて、コメディとまではいなかいにしろ、ハッピーエンドであれば良かったと思う。そうすれば、舞台の上だけでも悲しくはなくなるから。
少し紹介が遅れたが、ダミアン・バルテレモンは、僕の相手方や二枚目の主役を演じる事が多かった。彼は僕とは対照的な男らしい色気を持っていたから、この劇団では僕と並ぶ程の人気っぷりだ。
なにより、ダミアンは僕の一番の親友でもあった。
ダミアンとは、よく二人で語り合ったものだ。中でも特に印象深いのが、月の影法師の公演前夜だ。
僕は部屋を訪れて来てくれたダミアンの為、転がる蝋燭を手探りで拾いあげると火を点けた。
「シャルル、見てくれよ」
ダミアンは、持っていた箱の中から銀のカップを一つ取り出し、僕の前に差し出した。カップを手に取ると、繊細な彫刻が施されていて、実に綺麗な品だった。
「綺麗だね。これがどうしたの?」
僕の問いに、ダミアンは興奮気味に答えた。
「父の形見だよ。聖女から貰った物らしいんだ」
「へぇ、凄いじゃないか」
驚いた顔を向ける僕の手からダミアンはカップを受け取ると、彼はそれを蝋燭の揺らめく炎の明かりに照らしながら、愛しそうに彫刻を撫でた。
「僕はね、オルレアンから来たんだよ。自分を偽って役者になった。これは、戦士だった父が戦場で肺を患い已むなく帰還する時、聖女が回復と幸せを祈って父にくれたものなんだよ。優しさ、気品、強さに幼い僕は憧れた。だけど、父には敵わないと思った。だから、舞台の上ではどんな勇者にでもなれる役者を目指したんだ」
暫く愛しそうに銀のカップを眺めていたダミアン。その横顔は、蝋燭の炎に揺らめきながら、うっとりする程魅惑的に見えた。
「シャルル、このカップを今だけ君に貸してあげようと思うんだ」
「え?」
彼の意外な申し出に、僕は思わず疑問符を上げた。
「これは父が、“幸運”と“回復”を願って贈られたものだから。明日の公演で、君に幸福が舞い降りますように。僕は君と最高の芝居がしたいんだよ」
ダミアンの大切な大切な銀のカップを再び受け取ると、僕も彼と同様に銀のカップを優しく愛でた。
「ありがとう」
10
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

淡き河、流るるままに
糸冬
歴史・時代
天正八年(一五八〇年)、播磨国三木城において、二年近くに及んだ羽柴秀吉率いる織田勢の厳重な包囲の末、別所家は当主・別所長治の自刃により滅んだ。
その家臣と家族の多くが居場所を失い、他国へと流浪した。
時は流れて慶長五年(一六〇〇年)。
徳川家康が会津の上杉征伐に乗り出す不穏な情勢の中、淡河次郎は、讃岐国坂出にて、小さな寺の食客として逼塞していた。
彼の父は、淡河定範。かつて別所の重臣として、淡河城にて織田の軍勢を雌馬をけしかける奇策で退けて一矢報いた武勇の士である。
肩身の狭い暮らしを余儀なくされている次郎のもとに、「別所長治の遺児」を称する僧形の若者・別所源兵衛が姿を見せる。
福島正則の元に馳せ参じるという源兵衛に説かれ、次郎は武士として世に出る覚悟を固める。
別所家、そして淡河家の再興を賭けた、世に知られざる男たちの物語が動き出す。

すさまじきものは宮仕え~王都妖異聞
斑鳩陽菜
歴史・時代
ときは平安時代――、内裏内を護る、近衛府は左近衛府中将・藤原征之は、顔も血筋もいいのに和歌が苦手で、面倒なことが大嫌い。
子どもの頃から鬼や物の怪が視えるせいで、天から追放されたという鬼神・紅蓮に取り憑かれ、千匹鬼狩りをしないと還れないという。
そんな矢先、内裏で怪異が相次ぐ。なんとこの原因と解決を、帝が依頼してきた。
本来の職務も重なって、否応なく厄介事に振りまわさる征之。
更に内裏では、人々の思惑が複雑に絡み合い……。

思い出乞ひわずらい
水城真以
歴史・時代
――これは、天下人の名を継ぐはずだった者の物語――
ある日、信長の嫡男、奇妙丸と知り合った勝蔵。奇妙丸の努力家な一面に惹かれる。
一方奇妙丸も、媚びへつらわない勝蔵に特別な感情を覚える。
同じく奇妙丸のもとを出入りする勝九朗や於泉と交流し、友情をはぐくんでいくが、ある日を境にその絆が破綻してしまって――。
織田信長の嫡男・信忠と仲間たちの幼少期のお話です。以前公開していた作品が長くなってしまったので、章ごとに区切って加筆修正しながら更新していきたいと思います。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。


九州のイチモツ 立花宗茂
三井 寿
歴史・時代
豊臣秀吉が愛し、徳川家康が怖れた猛将“立花宗茂”。
義父“立花道雪”、父“高橋紹運”の凄まじい合戦と最期を目の当たりにし、男としての仁義を貫いた”立花宗茂“と“誾千代姫”との哀しい別れの物語です。
下剋上の戦国時代、九州では“大友・龍造寺・島津”三つ巴の戦いが続いている。
大友家を支えるのが、足が不自由にもかかわらず、輿に乗って戦い、37戦常勝無敗を誇った“九州一の勇将”立花道雪と高橋紹運である。立花道雪は1人娘の誾千代姫に家督を譲るが、勢力争いで凋落する大友宗麟を支える為に高橋紹運の跡継ぎ統虎(立花宗茂)を婿に迎えた。
女城主として育てられた誾千代姫と統虎は激しく反目しあうが、父立花道雪の死で2人は強く結ばれた。
だが、立花道雪の死を好機と捉えた島津家は、九州制覇を目指して出陣する。大友宗麟は豊臣秀吉に出陣を願ったが、島津軍は5万の大軍で筑前へ向かった。
その島津軍5万に挑んだのが、高橋紹運率いる岩屋城736名である。岩屋城に籠る高橋軍は14日間も島津軍を翻弄し、最期は全員が壮絶な討ち死にを遂げた。命を賭けた時間稼ぎにより、秀吉軍は筑前に到着し、立花宗茂と立花城を救った。
島津軍は撤退したが、立花宗茂は5万の島津軍を追撃し、筑前国領主としての意地を果たした。豊臣秀吉は立花宗茂の武勇を讃え、“九州之一物”と呼び、多くの大名の前で激賞した。その後、豊臣秀吉は九州征伐・天下統一へと突き進んでいく。
その後の朝鮮征伐、関ヶ原の合戦で“立花宗茂”は己の仁義と意地の為に戦うこととなる。

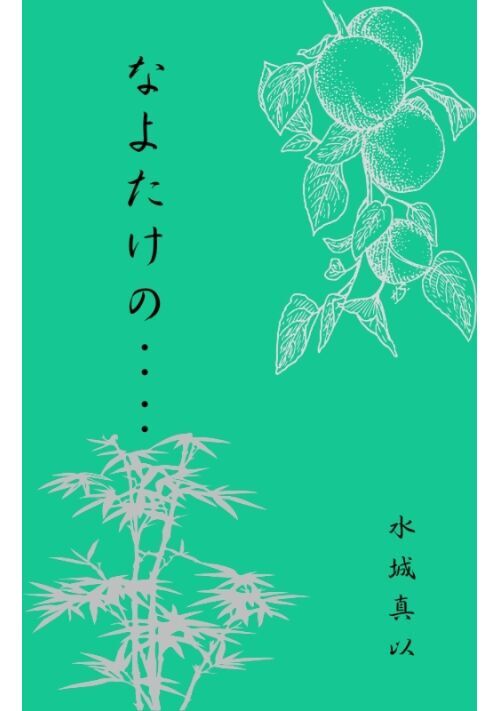
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















