1 / 1
台風ヤンマ
しおりを挟む
なん十年にいちどとかいう大型台風がやってきて、そこらじゅう水びたしになったんだ。
ぼくの家も床のすぐ下にまで水がきてさ。夜なかに「わあっ、わあっ」とおかしげな声がするから、げんかんのほうへいってみたら、母さんが三和土をあがったところにぺたんとしりもちをついていて、そのとなりで父さんが「うーむむ」とうでをくんだまま、目の下をぷかぷかただよう靴やサンダルをながめているんだもの。おどろいちゃうよ。
どうやら町の中心を流れる黒目川の水が、ていぼうをきってあふれだしたらしいのさ。もちろん、そのときはどうなるかとみんなでヒヤヒヤしたよ。でも水はそれより上にはあがってこなかったから、ぼくのうちはながされずにすんだんだ。
あくる日は、まぶしいくらいの青空でさ。二階のベランダからながめてみると、
町ぜんたいがぽっかりと水にうかんでるんだ。
「ヒロシーッ!」と声がするからみおろすと、いとちんが、プール用のゴムボートの上でぼくをみあげて笑ってた。
「おりてこいよお。みせたいものがあるんだ」
みせたいものって、なんだろう?
いとちんは、おなじ五年三組の友だちで、ぼくと家も近いから、こうしてときどき遊びにやってくる。いつもおかしなことをいってはクラス中を笑わせているおもしろいやつで、飛行機のことにかけちゃ、だれよりもくわしいんだ。旅客機のパイロットになるのが夢だって、いつかきいたことがあったな。
「ほら、これ」
ちんが後ろにまわしていたうでを、ぼくの鼻の先につきだした。
「わっ!」
ぼくはびっくりした。
いとちんがみせてくれたのは。三十センチもある銀色のヤンマなんだ。いとちんのうでにとまって、大きな目玉をきょときょとうごかしている。すきとおった羽にひびわれたようなもようがあって、すらっとした体がジェット戦闘機みたいだ。
「すげえなあ! こんなでかいのみたことないよ!」
ぎらっぎらっとすばらしく光るヤンマは、いとちんのうでに赤い糸でつないであったけれど、ぼくがつかむと、ぶぶぶぶっとあばれてにげようとする。まったくすごい力だ。
「台風にのってやってきたんだぜ」いとちんはほこらしげにいった。「学校の校庭にいっぱい飛んできてるんだ。これからみにいこう」
そんなわけで、ぼくらはゴムボートにのって、でかけることになったんだ。
水があふれて川のようになった道には、どこかのうちのおなべだとか、スイカだとか、流れていておもしろい。二階の窓からつり糸をたらしている人までいる。
「つれますかーっ!」と大声でたずねると、おじさんは「おう」と手をふって、
「黒目川の魚がなあ。こんなところにまで流れてきてるんだよ。コイとかフナとか、いっぱいつれるぞお」
さぼっさばっとぬき手をきって、すばらしいスピードでまえを泳いでいく人がいるので、「だれだろう?」と良くみたら、かどのたばこ屋のおじさんだった。三十年前に水泳の自由形で、オリンピックのこうほにもあげられたとかいう人だ。
空気がすんでいるせいか、なにもかもきらきらしている。なんだかうれしくなる。
商店街に入ると、おじさんやおばさんが「おっ、ヒロシじゃねえか」とか、「どこまで行くんだい?」とか、さかんに声をかけてきた。
いとちんが、ゴムボートのオールをはなして、手をふった。そのとき、ヤンマを
むすんでいた糸がぴーんとはったかと思うと、ぶつっときれた。赤い糸をひらひら
させて、ヤンマが青空へにげていく。ぼくは手をのばしたんだけれど、まにあわなかったんだ。
「あ。あーあ。にげちゃったよ」
ヤンマは、ゴムポートの上を、ふわりふわりと二回まわって、とこかへ飛んでいっちゃった。きっと、糸がオールにからまってたんだ。
だけどいとちんは、へいきだった。
「またつかまるよ。すげー、いっぱい飛んできてるんだから」
くねくねとまがりくねった運河のような道を、ゴムボートでどこまでもくだっていくと、学校につく。
校庭をひとめみて、ぼくはすごくびっくりした。
ひとばんのうちに、校庭が湖のようにかわっていたんだ。まわりよりすこし低くなっているから、あちこちから水がながれこんで、こぼこぽといい音をたてている。
校庭がガラスのようになって、空と雲とそれからさかさまになった校舎をうつしてた。
「ほら、すげーぞ。みてみろよ!」
いとちんが、目をかがやかした。
水のなかから顔をだした、すべりだいやジャングルジム。そのまわりを、たくさんのヤンマたちが飛びまわってるんだ!
ヤンマたちは、ぼくらのゴムボートのすぐそばまてやってきては、くるっと旋回したり、きりもみで落下しては水面すれすれをかすめてまた空高くまいあがったり、だれもいない夏休みの校庭占領して、曲芸飛行をくりひろげていた。
なんだか目がまわりそうだ。
「こいつら、どこからきたんだろうなあ」とぼくはいった、
「だからさ、白風にのってどこか遠い国からやってきたんじゃねえ?」いとちんが、ヤンマたちをみあげてこたえる。「いいよなあ、こいつらきっと、風にのっていろんな国を旅してるんだ、おれもいってみたいよなあ」
そのことばでぼくは、いとちんのうちへ遊びにいったときのことを思い出したんだ。
いとちんの部屋のかべには、飛行機のポスターがべたべたはってあって、たなには飛行機のプラモがすらりとならべてあって、本だなには飛行機の本や雑誌もいっぱいで、いともんはそれらをひとつひとつゆびさしては、真けんな願でぼくに解説してくれたっけ。
「これがエアコD・H・4。一九一七年につくられたイギリスの飛行機で、リンドーグこれを操縦したことがあるんだぜ。こっちは、アメリカのカーチスJN―4ジュニア。バイロット養成のためにつくられた練習機なんだ。それから、これがフランスのニューポール117で、となりのやつがドイツのフォッカーDⅦ
「わかるだろ? いとちんは古い時代の飛行機が好きなんだ。いとちんによれば、昔の人は先をあらそうように大空をめざしたんだって。ある者は空にかぎりないロマンをもとめて、ある者は賞金をめあてに、ある者は男の名誉とプライドをかけて。
それで命を落とした人もたくさんいたんだって。
ジョージ・ケーリー、オットー・リリエンタール、それにライト兄弟が、いとちんのあこがれだった。だけどなんといっても一九二七年に大西洋無着陸横断飛行に
成功したリンドバーグが、いとちんにとっては、いちばんのヒーローだった。
「こい霧をさけるために、あるときは空高く、あるときは海面すれすれを飛んで、リンドバーグのスピリット・オブ・セントルイス号はパリの灯をめざしたんだ。胴体の中にまで、めいっぱいガソリンをつんだから、ぎゅうづめでさ。眠気と必死に戦いなから、なにもない海の上を飛びつづけて、とうとうルブールジュ空港の照明灯の灯がみえたとき、リンドバーグはいったいどんなことを考えただろうって、よく思うんだ」
いつもふざけてばかりいとちんだったけれど、飛行機の話をするときはこわいくらいまじめだった、 いとちんがもつと昔に生まれていたら、きっミリンドバーグよりも先に大西洋をわたっていたんじゃないかって思うくらいだ、
ぼくも、そのときのリンドバーグのことを、思いうかべてみる。
いとちんもそうらしいけど、ぼくはなにかきっかけがあると、こんなふうに空想をはじめちゃうくせがあるんだ。それでね。考えはじめるととまらなくなる。つかれるまでやめないんだ。いきつくところまでいっちゃうって感じかな。
いとちんにはまけるけど、ぼくだって飛行機は好きだ。
すごいよなあ。
三十三時間三十分かけて、二ューヨークとパリの間を飛んだリンドバーグ。どこにも着陸しないでだよ。せまい操縦席に体をちぢめて大海原を飛びつづけるんだ。陸のかげはもうみえない。羅針盤だけがたよりだ……。
あれっ、なんかヘンだ。
たしかにぼくはリンドバーグのスピリット・オブ・セントルイス号を思いうかべたんだよ。だけどいまぼくの目の前を飛んでいるのは、たくさんのヤンマたちなんだ。わっ、すごい。あんなに太いおびになって、海面すれすれを泳ぐように飛んでいる。なんだか銀色の竜が飛んでいるみたいだ。竜が頭をもたげはじめた。雲の上にでる気だな。
雲の上にでたヤンマたちのむこうから、なにかやってきた。ジェット旅客機だ!
目を丸くした乗客が、窓からヤンマたちをながめている。あわててカメラをむける人もいる。雲が太陽に照らされて、あかね色にそまっている。そのなかを泳ぐように、ヤンマたちは飛んでいく。
ぼくは横にすわっているいとちんをみた。
どうして、こんなおかしな空想をしちゃったのかな?
いとちんは、とろん、とした目でヤンマたちをみつめている。
そういえば、ヤンマたちのようすがなんだかおかしいんだ。うれしそうに羽をぶつけあって、メリーゴーランドの木馬たちのように、ぼくらのまわりをまわっている。
「どうしたんだろ。おれ」と、いとちんがつぶやいた。「ヒロシ。なんだか眠くねえ?」
いわれてみれば、そうなんだ。ヤンマたちをみたときから、ぼくも眠くてしかたなかった。
「うん」とうなずいて、ぼくはヤンマたちの輪をゆびさした。
「目がまわって、あそこへすいこまれていくみたいだ」
「おっかしいなあ。こいつらのせいなのかなあ。ヘンだなあ」
どんどん遠ざかっていくいとちんの声をききながら、ぼくはまたリンドバーグのことを考えていた。こい霧におおわれた海の上を飛んだリンドバーグ。そういえば、リンドバーグも眠いのをがまんして、飛びつづけたんだっけ。ふしぎなミルクいろの海。きこえるのは、風をきる音と、単調なエンジン音だけ。まるで静かなべつの世界を飛んでいるみたいだ。天国って、こんな感じなのかな。ああ。霧が晴れてきた。高度をさげなちゃ。操縦桿をしっかりにぎるんだ。よし。それでいい。
けれども、霧が晴れたときそこにあらわれたのは、大海原ではなくて砂漠だった。
なんだろう? 四頭のらくだにまたがった男たちがみえる。大きなにもつをつんだらくだをつれている。ああ。そうか。きっと砂漠の旅をつづけるキャラバンだ。
風がふいた。砂がさらさらとうごく。男たちが頭にかぶった白い布もはためく。
男たちが、らくだをとめて、空をみあげた。
あっ。ヤンマだ! またヤンマが空を飛んでいる。ぎらつく太陽の下を、編隊をくんで、ぞくぞくと飛んでいく。
ぼくはもうすっかり夢をみているらしい。リンドバーグのことを考えているうちに、それがいつのまにかヤンマの夢になっちゃったみたいなんだ。それとも、リンドバーグのことを考えはじめたときから、ぼくはもう夢をみていたのかな? それ
それともそれとも、まさかとは思うけど、いとちんがゴムボートでやってきたのもみんな夢だったりとか、目をさましたら部屋のふとんの中で、台風なんかきていなくて、あんなでっかいヤンマもきていなくて⋯⋯とか。ほんと、まさかとは思うけど。
ああ。こんどは白い雪をかぶったアルプスの山々がみえてきた。まったく、いろんなものがみえてくるなあ。青い空。空ってあんなに青かったっけ。山のふもとにひろがるのは、目にしみるような緑の草原だ。あっ、だれかいる。女の子だ。色とりどりの刺繍をした外国の服をきた女の子が三人。手をつないで、わになっておどっている。ヤンマたちに気がついて、大きく手をふりだした。ヤンマたちは大空をながれる大河のように、どんどん高みにのぼって、アルプスの山々をこえていく。
そうか! わかったぞ。これって、ヤンマたちがいろいろな国を旅して、これまでにみてきた風景なんだ。じぶんたちの旅の記録を、夢の中でみせてくれているんだ!
あれっ、こんどは自動車だ。これもヤンマたちがみた風景なのかな。カーナンバーをつけた車が、草がまばらにはえた草原を、つぎつぎに走りぬけていく。あっ、わかった。サファリラリーだよ、これ。いつかテレビでみたもの。
土けむりをあげて走ってきた車が、いきなり目の前でとまった。サングラスをかけた男の人が、車からおりてきて、ボンネットをあけてエンジンのぐあいをしらべている。男の人はしばらくそうしていたけれど、やがて車のドアにもたれて、たばこをすいはじめた。その横をべつの車が、猛スピードでとおりすぎていく。この人、きっとリタイヤしちゃうんだ。なんだかかわいそうだな。せっかくここまでがんばってきたのに。
地上の車とデッドヒートをくりひろげるヤンマたちを、男の人はぼんやりとみあげている。
いとちんのことがすこし気になった。ヤンマたちは、いとちんにもこの夢をみせてくれているのかなあって。だとしたら、いとちんはすごくよろこんでるはずなんだ。だって、いとちんは飛行機にのっていろんな国へ行きたがっていたんだから。
あっ。また景色がかわった。
青いカーテンが、夜空でゆれている。わっ、白く光った。わっ、こんどは黄色くうずをまいた。すごいすごい! どんどん形がかわっていく。オーロラだ! オーロラって、北極や南極にしかできないんだろ。こんなところにまでヤンマたちは行ったんだ!
あっ、またかわった。こんどは赤い滝がながれおちているみたいだ。
すごいなあ。
だれもいないこおりついた大地をみおろして、静かに飛びつつけるヤンマたち。その上にはためくオーロラ。
目をあけると、いとちんがほんやりとぼくをみていた。たったいま起きたばかりのように、目をシパシパさせている。
「みたか!」とぼくにきいてきた。
「みた!」と、ぼく。
どうやら、いとちんもおなじ夢をみていたらしいんだ。
「すげーよ。ヒロシッ/」いとちんは、息をはずませていった。「ヤンマたちはやっぱりいろんな国を旅しているんだよ。それをおれたちにみせてくれたんだよ。おれの思ったとおりだ。すげえなあ」
いとちんはほんとうに空を飛ぶのが好きなんだなあって、ぼくは思った。いとちんにとって、自由に空を飛べるヤンマたちは、きっと飛行機乗りとおなじなんだ。
いとちんのこうふんが、ぼくにぴんびんつたわってきた。
いとちんが、とつぜんだまった。
2
「おおーい」「おおーい」
ふりかえると、男の子がひとり、シャングルジムの上にぽつんとすわって、ぼくらに手をふっていた。まっ黒に日にやけた男の子だ。ぼくらの知らない子だった。
ぼくらがそばにゴムボートをよせると、
「のぼっておいでよお」
男の子は白い歯をみせて笑った。まるでわけがわからなかったけれど、ほくといとちんは、ジャングルジムによじのぼって、男の子のとなりにすわったんだ。
男の子は、ぼくといとちんをかわりばんこにみて、にこにこ笑っている。
「なんだかおかしいぜ。こいつ」
いとちんが、ぼくの耳にささやいた。
男の子の左手の小指に、赤い糸がむすんであるのがみえた。ほくがじっと見つめていると、男の子は左手をあわててボケットにかくして、はずかしそうに笑った。どこかでみたな、と思ったら、いとちんがつかまえたヤンマにむすんであったあの糸なんだ。
ぼくは気味が悪くなった。
こいつ、さっきにげていったあのヤンマかもしれない。
「すごいだろう」男の子が、まだ空をまわっているヤンマたちを、みあげていった。
「台風をよびよせてるんだ。またべつの場所にいくんだよ」
まわりの雲がひきよせられて、どんどんヤンマたちのほうへ飛んでいくのがわかった。
赤い糸をみてなかったら、きっと男の子に「どうしてそんなこと知ってるんだよ?」って、たずねたと思う。でもこの子がヤンマだとしたら、知ってて当然なんだ。
「いいなあ」と、いとちんがいった。
「いっしょにくる?」
男の子がたずねた。
ぼくはどきどきしてきた。やっぱり、そうだ。こいつ、さっきのヤンマだ!
「でもなー。おまえらヤンマだろ。おれは人間だしなー」
いとちんはそういって、くすくす笑った。いとちんも気づいてるんだ。
男の子はなにもいわずに、いきなりジャングルジムの上に立ちあがった。なにをするんだろう、とみていたら、そのまま、ざぶんと水の中へとびこんじゃうんだもの。びっくりだ。
「お、おい。だいじょうぶかあ?」
いとちんが、あわてて声をかける。
「へーきへーき」男の子は笑いながら手をふった。水はそんなに深くない。男の子のこしのあたりくらい。「気持ちいいから、きみたちもおいでよ」
「よおし」
いとちんが、準備体操をはじめた。
「ほら、早く。ジャンプ、ジャンプ!」
男の子がいとちんに声をかける。
「やめろよ。いとちん」
ぼくがとめると、いとちんはにやっと笑った。
「だいじょうぶだよ。ヒロシ。おれは飛ぶぜ。リンドバーグみたいに飛ぶぜ。ヤンマなんかに負けねえもん」
そして、いとちんは飛んだ。
そのときぼくはみたんだ。
水に落ちるすんぜん、いとちんの体が紙をまるめたみたいにくしゃくしゃにちぢんでしまうのを。いとちんのびんと広げたりょううでが、みるみるすきとおってヤンマの羽にかわってしまうのを。
ヤンマになったいとちんは、ついっと水の上を滑空した。
「きみはどうするう?」
男の子が大声でぼくにきいてきた。
ぼくは⋯⋯動けなかった。
ぼくも、世界じゅうを旅してみたい気もした。いとちんといっしょにどこまでもいってみたい気もした。でも、ぼくはこわかったんだ。あんなふうにヤンマになってしまうのがこわかったんだ。
男の子は、くすっと笑うと、ヤンマにすがたをかえて空にまいあがった。そして、なかまたちの輪のなかへ、すいこまれるようにもどっていった。
あくる日。ヤンマたちは台風にのって、またどこかへ飛んでいってしまった。
だから、それからこの町でいとちんをみたものはいない。
いとちんがいなくなって、やっとわかったんだ。ヤンマが子どもに化けたんじゃなくて、子どもがヤンマになったんだってことに。ヤンマになった子どもたちが、こうしてときどき地上におりては仲間をふやしていくんだってことに。
やがて夏休みが終わり、二学期が始まっても、いとちんはもどってこなかった。でもぼくは思うんだ。あの日、ぼくがうちにもどったとき、机の上で、ひっそりとぼくを待っていたあのヤンマがいとちんなんじゃないかって。
ぼくが手をのばすと、そのヤンマは開いていた窓からするりとでていってしまったのだけれど。
世界中を旅したあとで、いとちんはきっとまたこの町へもどってくる。ぼくはそう信じている。ぼくの目には、あの日のリンドバーグのように大海原を飛びつづけるいとちんのすがたがみえるのだ。
ぼくは窓のそばにすわり、そしてきょうも空をみあげる。
そこにみえるのは、まるで空を焼きつくすようなあざやかな夕焼け。
・「飛行機ハンドブック」(西田清一著日本工業新聞社)を参考にさせていただきました。
ぼくの家も床のすぐ下にまで水がきてさ。夜なかに「わあっ、わあっ」とおかしげな声がするから、げんかんのほうへいってみたら、母さんが三和土をあがったところにぺたんとしりもちをついていて、そのとなりで父さんが「うーむむ」とうでをくんだまま、目の下をぷかぷかただよう靴やサンダルをながめているんだもの。おどろいちゃうよ。
どうやら町の中心を流れる黒目川の水が、ていぼうをきってあふれだしたらしいのさ。もちろん、そのときはどうなるかとみんなでヒヤヒヤしたよ。でも水はそれより上にはあがってこなかったから、ぼくのうちはながされずにすんだんだ。
あくる日は、まぶしいくらいの青空でさ。二階のベランダからながめてみると、
町ぜんたいがぽっかりと水にうかんでるんだ。
「ヒロシーッ!」と声がするからみおろすと、いとちんが、プール用のゴムボートの上でぼくをみあげて笑ってた。
「おりてこいよお。みせたいものがあるんだ」
みせたいものって、なんだろう?
いとちんは、おなじ五年三組の友だちで、ぼくと家も近いから、こうしてときどき遊びにやってくる。いつもおかしなことをいってはクラス中を笑わせているおもしろいやつで、飛行機のことにかけちゃ、だれよりもくわしいんだ。旅客機のパイロットになるのが夢だって、いつかきいたことがあったな。
「ほら、これ」
ちんが後ろにまわしていたうでを、ぼくの鼻の先につきだした。
「わっ!」
ぼくはびっくりした。
いとちんがみせてくれたのは。三十センチもある銀色のヤンマなんだ。いとちんのうでにとまって、大きな目玉をきょときょとうごかしている。すきとおった羽にひびわれたようなもようがあって、すらっとした体がジェット戦闘機みたいだ。
「すげえなあ! こんなでかいのみたことないよ!」
ぎらっぎらっとすばらしく光るヤンマは、いとちんのうでに赤い糸でつないであったけれど、ぼくがつかむと、ぶぶぶぶっとあばれてにげようとする。まったくすごい力だ。
「台風にのってやってきたんだぜ」いとちんはほこらしげにいった。「学校の校庭にいっぱい飛んできてるんだ。これからみにいこう」
そんなわけで、ぼくらはゴムボートにのって、でかけることになったんだ。
水があふれて川のようになった道には、どこかのうちのおなべだとか、スイカだとか、流れていておもしろい。二階の窓からつり糸をたらしている人までいる。
「つれますかーっ!」と大声でたずねると、おじさんは「おう」と手をふって、
「黒目川の魚がなあ。こんなところにまで流れてきてるんだよ。コイとかフナとか、いっぱいつれるぞお」
さぼっさばっとぬき手をきって、すばらしいスピードでまえを泳いでいく人がいるので、「だれだろう?」と良くみたら、かどのたばこ屋のおじさんだった。三十年前に水泳の自由形で、オリンピックのこうほにもあげられたとかいう人だ。
空気がすんでいるせいか、なにもかもきらきらしている。なんだかうれしくなる。
商店街に入ると、おじさんやおばさんが「おっ、ヒロシじゃねえか」とか、「どこまで行くんだい?」とか、さかんに声をかけてきた。
いとちんが、ゴムボートのオールをはなして、手をふった。そのとき、ヤンマを
むすんでいた糸がぴーんとはったかと思うと、ぶつっときれた。赤い糸をひらひら
させて、ヤンマが青空へにげていく。ぼくは手をのばしたんだけれど、まにあわなかったんだ。
「あ。あーあ。にげちゃったよ」
ヤンマは、ゴムポートの上を、ふわりふわりと二回まわって、とこかへ飛んでいっちゃった。きっと、糸がオールにからまってたんだ。
だけどいとちんは、へいきだった。
「またつかまるよ。すげー、いっぱい飛んできてるんだから」
くねくねとまがりくねった運河のような道を、ゴムボートでどこまでもくだっていくと、学校につく。
校庭をひとめみて、ぼくはすごくびっくりした。
ひとばんのうちに、校庭が湖のようにかわっていたんだ。まわりよりすこし低くなっているから、あちこちから水がながれこんで、こぼこぽといい音をたてている。
校庭がガラスのようになって、空と雲とそれからさかさまになった校舎をうつしてた。
「ほら、すげーぞ。みてみろよ!」
いとちんが、目をかがやかした。
水のなかから顔をだした、すべりだいやジャングルジム。そのまわりを、たくさんのヤンマたちが飛びまわってるんだ!
ヤンマたちは、ぼくらのゴムボートのすぐそばまてやってきては、くるっと旋回したり、きりもみで落下しては水面すれすれをかすめてまた空高くまいあがったり、だれもいない夏休みの校庭占領して、曲芸飛行をくりひろげていた。
なんだか目がまわりそうだ。
「こいつら、どこからきたんだろうなあ」とぼくはいった、
「だからさ、白風にのってどこか遠い国からやってきたんじゃねえ?」いとちんが、ヤンマたちをみあげてこたえる。「いいよなあ、こいつらきっと、風にのっていろんな国を旅してるんだ、おれもいってみたいよなあ」
そのことばでぼくは、いとちんのうちへ遊びにいったときのことを思い出したんだ。
いとちんの部屋のかべには、飛行機のポスターがべたべたはってあって、たなには飛行機のプラモがすらりとならべてあって、本だなには飛行機の本や雑誌もいっぱいで、いともんはそれらをひとつひとつゆびさしては、真けんな願でぼくに解説してくれたっけ。
「これがエアコD・H・4。一九一七年につくられたイギリスの飛行機で、リンドーグこれを操縦したことがあるんだぜ。こっちは、アメリカのカーチスJN―4ジュニア。バイロット養成のためにつくられた練習機なんだ。それから、これがフランスのニューポール117で、となりのやつがドイツのフォッカーDⅦ
「わかるだろ? いとちんは古い時代の飛行機が好きなんだ。いとちんによれば、昔の人は先をあらそうように大空をめざしたんだって。ある者は空にかぎりないロマンをもとめて、ある者は賞金をめあてに、ある者は男の名誉とプライドをかけて。
それで命を落とした人もたくさんいたんだって。
ジョージ・ケーリー、オットー・リリエンタール、それにライト兄弟が、いとちんのあこがれだった。だけどなんといっても一九二七年に大西洋無着陸横断飛行に
成功したリンドバーグが、いとちんにとっては、いちばんのヒーローだった。
「こい霧をさけるために、あるときは空高く、あるときは海面すれすれを飛んで、リンドバーグのスピリット・オブ・セントルイス号はパリの灯をめざしたんだ。胴体の中にまで、めいっぱいガソリンをつんだから、ぎゅうづめでさ。眠気と必死に戦いなから、なにもない海の上を飛びつづけて、とうとうルブールジュ空港の照明灯の灯がみえたとき、リンドバーグはいったいどんなことを考えただろうって、よく思うんだ」
いつもふざけてばかりいとちんだったけれど、飛行機の話をするときはこわいくらいまじめだった、 いとちんがもつと昔に生まれていたら、きっミリンドバーグよりも先に大西洋をわたっていたんじゃないかって思うくらいだ、
ぼくも、そのときのリンドバーグのことを、思いうかべてみる。
いとちんもそうらしいけど、ぼくはなにかきっかけがあると、こんなふうに空想をはじめちゃうくせがあるんだ。それでね。考えはじめるととまらなくなる。つかれるまでやめないんだ。いきつくところまでいっちゃうって感じかな。
いとちんにはまけるけど、ぼくだって飛行機は好きだ。
すごいよなあ。
三十三時間三十分かけて、二ューヨークとパリの間を飛んだリンドバーグ。どこにも着陸しないでだよ。せまい操縦席に体をちぢめて大海原を飛びつづけるんだ。陸のかげはもうみえない。羅針盤だけがたよりだ……。
あれっ、なんかヘンだ。
たしかにぼくはリンドバーグのスピリット・オブ・セントルイス号を思いうかべたんだよ。だけどいまぼくの目の前を飛んでいるのは、たくさんのヤンマたちなんだ。わっ、すごい。あんなに太いおびになって、海面すれすれを泳ぐように飛んでいる。なんだか銀色の竜が飛んでいるみたいだ。竜が頭をもたげはじめた。雲の上にでる気だな。
雲の上にでたヤンマたちのむこうから、なにかやってきた。ジェット旅客機だ!
目を丸くした乗客が、窓からヤンマたちをながめている。あわててカメラをむける人もいる。雲が太陽に照らされて、あかね色にそまっている。そのなかを泳ぐように、ヤンマたちは飛んでいく。
ぼくは横にすわっているいとちんをみた。
どうして、こんなおかしな空想をしちゃったのかな?
いとちんは、とろん、とした目でヤンマたちをみつめている。
そういえば、ヤンマたちのようすがなんだかおかしいんだ。うれしそうに羽をぶつけあって、メリーゴーランドの木馬たちのように、ぼくらのまわりをまわっている。
「どうしたんだろ。おれ」と、いとちんがつぶやいた。「ヒロシ。なんだか眠くねえ?」
いわれてみれば、そうなんだ。ヤンマたちをみたときから、ぼくも眠くてしかたなかった。
「うん」とうなずいて、ぼくはヤンマたちの輪をゆびさした。
「目がまわって、あそこへすいこまれていくみたいだ」
「おっかしいなあ。こいつらのせいなのかなあ。ヘンだなあ」
どんどん遠ざかっていくいとちんの声をききながら、ぼくはまたリンドバーグのことを考えていた。こい霧におおわれた海の上を飛んだリンドバーグ。そういえば、リンドバーグも眠いのをがまんして、飛びつづけたんだっけ。ふしぎなミルクいろの海。きこえるのは、風をきる音と、単調なエンジン音だけ。まるで静かなべつの世界を飛んでいるみたいだ。天国って、こんな感じなのかな。ああ。霧が晴れてきた。高度をさげなちゃ。操縦桿をしっかりにぎるんだ。よし。それでいい。
けれども、霧が晴れたときそこにあらわれたのは、大海原ではなくて砂漠だった。
なんだろう? 四頭のらくだにまたがった男たちがみえる。大きなにもつをつんだらくだをつれている。ああ。そうか。きっと砂漠の旅をつづけるキャラバンだ。
風がふいた。砂がさらさらとうごく。男たちが頭にかぶった白い布もはためく。
男たちが、らくだをとめて、空をみあげた。
あっ。ヤンマだ! またヤンマが空を飛んでいる。ぎらつく太陽の下を、編隊をくんで、ぞくぞくと飛んでいく。
ぼくはもうすっかり夢をみているらしい。リンドバーグのことを考えているうちに、それがいつのまにかヤンマの夢になっちゃったみたいなんだ。それとも、リンドバーグのことを考えはじめたときから、ぼくはもう夢をみていたのかな? それ
それともそれとも、まさかとは思うけど、いとちんがゴムボートでやってきたのもみんな夢だったりとか、目をさましたら部屋のふとんの中で、台風なんかきていなくて、あんなでっかいヤンマもきていなくて⋯⋯とか。ほんと、まさかとは思うけど。
ああ。こんどは白い雪をかぶったアルプスの山々がみえてきた。まったく、いろんなものがみえてくるなあ。青い空。空ってあんなに青かったっけ。山のふもとにひろがるのは、目にしみるような緑の草原だ。あっ、だれかいる。女の子だ。色とりどりの刺繍をした外国の服をきた女の子が三人。手をつないで、わになっておどっている。ヤンマたちに気がついて、大きく手をふりだした。ヤンマたちは大空をながれる大河のように、どんどん高みにのぼって、アルプスの山々をこえていく。
そうか! わかったぞ。これって、ヤンマたちがいろいろな国を旅して、これまでにみてきた風景なんだ。じぶんたちの旅の記録を、夢の中でみせてくれているんだ!
あれっ、こんどは自動車だ。これもヤンマたちがみた風景なのかな。カーナンバーをつけた車が、草がまばらにはえた草原を、つぎつぎに走りぬけていく。あっ、わかった。サファリラリーだよ、これ。いつかテレビでみたもの。
土けむりをあげて走ってきた車が、いきなり目の前でとまった。サングラスをかけた男の人が、車からおりてきて、ボンネットをあけてエンジンのぐあいをしらべている。男の人はしばらくそうしていたけれど、やがて車のドアにもたれて、たばこをすいはじめた。その横をべつの車が、猛スピードでとおりすぎていく。この人、きっとリタイヤしちゃうんだ。なんだかかわいそうだな。せっかくここまでがんばってきたのに。
地上の車とデッドヒートをくりひろげるヤンマたちを、男の人はぼんやりとみあげている。
いとちんのことがすこし気になった。ヤンマたちは、いとちんにもこの夢をみせてくれているのかなあって。だとしたら、いとちんはすごくよろこんでるはずなんだ。だって、いとちんは飛行機にのっていろんな国へ行きたがっていたんだから。
あっ。また景色がかわった。
青いカーテンが、夜空でゆれている。わっ、白く光った。わっ、こんどは黄色くうずをまいた。すごいすごい! どんどん形がかわっていく。オーロラだ! オーロラって、北極や南極にしかできないんだろ。こんなところにまでヤンマたちは行ったんだ!
あっ、またかわった。こんどは赤い滝がながれおちているみたいだ。
すごいなあ。
だれもいないこおりついた大地をみおろして、静かに飛びつつけるヤンマたち。その上にはためくオーロラ。
目をあけると、いとちんがほんやりとぼくをみていた。たったいま起きたばかりのように、目をシパシパさせている。
「みたか!」とぼくにきいてきた。
「みた!」と、ぼく。
どうやら、いとちんもおなじ夢をみていたらしいんだ。
「すげーよ。ヒロシッ/」いとちんは、息をはずませていった。「ヤンマたちはやっぱりいろんな国を旅しているんだよ。それをおれたちにみせてくれたんだよ。おれの思ったとおりだ。すげえなあ」
いとちんはほんとうに空を飛ぶのが好きなんだなあって、ぼくは思った。いとちんにとって、自由に空を飛べるヤンマたちは、きっと飛行機乗りとおなじなんだ。
いとちんのこうふんが、ぼくにぴんびんつたわってきた。
いとちんが、とつぜんだまった。
2
「おおーい」「おおーい」
ふりかえると、男の子がひとり、シャングルジムの上にぽつんとすわって、ぼくらに手をふっていた。まっ黒に日にやけた男の子だ。ぼくらの知らない子だった。
ぼくらがそばにゴムボートをよせると、
「のぼっておいでよお」
男の子は白い歯をみせて笑った。まるでわけがわからなかったけれど、ほくといとちんは、ジャングルジムによじのぼって、男の子のとなりにすわったんだ。
男の子は、ぼくといとちんをかわりばんこにみて、にこにこ笑っている。
「なんだかおかしいぜ。こいつ」
いとちんが、ぼくの耳にささやいた。
男の子の左手の小指に、赤い糸がむすんであるのがみえた。ほくがじっと見つめていると、男の子は左手をあわててボケットにかくして、はずかしそうに笑った。どこかでみたな、と思ったら、いとちんがつかまえたヤンマにむすんであったあの糸なんだ。
ぼくは気味が悪くなった。
こいつ、さっきにげていったあのヤンマかもしれない。
「すごいだろう」男の子が、まだ空をまわっているヤンマたちを、みあげていった。
「台風をよびよせてるんだ。またべつの場所にいくんだよ」
まわりの雲がひきよせられて、どんどんヤンマたちのほうへ飛んでいくのがわかった。
赤い糸をみてなかったら、きっと男の子に「どうしてそんなこと知ってるんだよ?」って、たずねたと思う。でもこの子がヤンマだとしたら、知ってて当然なんだ。
「いいなあ」と、いとちんがいった。
「いっしょにくる?」
男の子がたずねた。
ぼくはどきどきしてきた。やっぱり、そうだ。こいつ、さっきのヤンマだ!
「でもなー。おまえらヤンマだろ。おれは人間だしなー」
いとちんはそういって、くすくす笑った。いとちんも気づいてるんだ。
男の子はなにもいわずに、いきなりジャングルジムの上に立ちあがった。なにをするんだろう、とみていたら、そのまま、ざぶんと水の中へとびこんじゃうんだもの。びっくりだ。
「お、おい。だいじょうぶかあ?」
いとちんが、あわてて声をかける。
「へーきへーき」男の子は笑いながら手をふった。水はそんなに深くない。男の子のこしのあたりくらい。「気持ちいいから、きみたちもおいでよ」
「よおし」
いとちんが、準備体操をはじめた。
「ほら、早く。ジャンプ、ジャンプ!」
男の子がいとちんに声をかける。
「やめろよ。いとちん」
ぼくがとめると、いとちんはにやっと笑った。
「だいじょうぶだよ。ヒロシ。おれは飛ぶぜ。リンドバーグみたいに飛ぶぜ。ヤンマなんかに負けねえもん」
そして、いとちんは飛んだ。
そのときぼくはみたんだ。
水に落ちるすんぜん、いとちんの体が紙をまるめたみたいにくしゃくしゃにちぢんでしまうのを。いとちんのびんと広げたりょううでが、みるみるすきとおってヤンマの羽にかわってしまうのを。
ヤンマになったいとちんは、ついっと水の上を滑空した。
「きみはどうするう?」
男の子が大声でぼくにきいてきた。
ぼくは⋯⋯動けなかった。
ぼくも、世界じゅうを旅してみたい気もした。いとちんといっしょにどこまでもいってみたい気もした。でも、ぼくはこわかったんだ。あんなふうにヤンマになってしまうのがこわかったんだ。
男の子は、くすっと笑うと、ヤンマにすがたをかえて空にまいあがった。そして、なかまたちの輪のなかへ、すいこまれるようにもどっていった。
あくる日。ヤンマたちは台風にのって、またどこかへ飛んでいってしまった。
だから、それからこの町でいとちんをみたものはいない。
いとちんがいなくなって、やっとわかったんだ。ヤンマが子どもに化けたんじゃなくて、子どもがヤンマになったんだってことに。ヤンマになった子どもたちが、こうしてときどき地上におりては仲間をふやしていくんだってことに。
やがて夏休みが終わり、二学期が始まっても、いとちんはもどってこなかった。でもぼくは思うんだ。あの日、ぼくがうちにもどったとき、机の上で、ひっそりとぼくを待っていたあのヤンマがいとちんなんじゃないかって。
ぼくが手をのばすと、そのヤンマは開いていた窓からするりとでていってしまったのだけれど。
世界中を旅したあとで、いとちんはきっとまたこの町へもどってくる。ぼくはそう信じている。ぼくの目には、あの日のリンドバーグのように大海原を飛びつづけるいとちんのすがたがみえるのだ。
ぼくは窓のそばにすわり、そしてきょうも空をみあげる。
そこにみえるのは、まるで空を焼きつくすようなあざやかな夕焼け。
・「飛行機ハンドブック」(西田清一著日本工業新聞社)を参考にさせていただきました。
0
お気に入りに追加
1
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

シャルル・ド・ラングとピエールのおはなし
ねこうさぎしゃ
児童書・童話
ノルウェジアン・フォレスト・キャットのシャルル・ド・ラングはちょっと変わった猫です。人間のように二本足で歩き、タキシードを着てシルクハットを被り、猫目石のついたステッキまで持っています。
以前シャルル・ド・ラングが住んでいた世界では、動物たちはみな、二本足で立ち歩くのが普通なのでしたが……。
不思議な力で出会った者を助ける謎の猫、シャルル・ド・ラングのお話です。

閉じられた図書館
関谷俊博
児童書・童話
ぼくの心には閉じられた図書館がある…。「あんたの母親は、適当な男と街を出ていったんだよ」祖母にそう聴かされたとき、ぼくは心の図書館の扉を閉めた…。(1/4完結。有難うございました)。



月からの招待状
樹(いつき)@作品使用時は作者名明記必須
児童書・童話
小学生の宙(そら)とルナのほっこりとしたお話。
🔴YouTubeや音声アプリなどに投稿する際には、次の点を守ってください。
●ルナの正体が分かるような画像や説明はNG
●オチが分かってしまうような画像や説明はNG
●リスナーにも上記2点がNGだということを載せてください。
声劇用台本も別にございます。
⚠動画・音声投稿サイトにご使用になる場合⚠
・使用許可は不要ですが、自作発言や転載はもちろん禁止です。著作権は放棄しておりません。必ず作者名の樹(いつき)を記載して下さい。(何度注意しても作者名の記載が無い場合には台本使用を禁止します)
・語尾変更や方言などの多少のアレンジはokですが、大幅なアレンジや台本の世界観をぶち壊すようなアレンジやエフェクトなどはご遠慮願います。
その他の詳細は【作品を使用する際の注意点】をご覧下さい。

プラネタリウムのめざす空
詩海猫
児童書・童話
タイトル通り、プラネタリウムが空を目指して歩く物語です。
普段はタイトル最後なのですが唐突にタイトルと漠然とした内容だけ浮かんで書いてみました。
短い童話なので最初から最後までフワッとしています。が、細かい突っ込みはナシでお願いします。
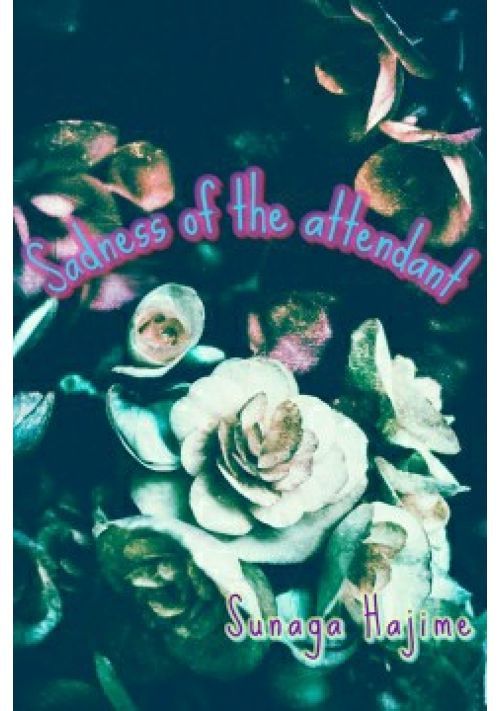
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

「羊のシープお医者さんの寝ない子どこかな?」
時空 まほろ
児童書・童話
羊のシープお医者さんは、寝ない子専門のお医者さん。
今日も、寝ない子を探して夜の世界をあっちへこっちへと大忙し。
さあ、今日の寝ない子のんちゃんは、シープお医者んの治療でもなかなか寝れません。
そんなシープお医者さん、のんちゃんを緊急助手として、夜の世界を一緒にあっちへこっちへと行きます。
のんちゃんは寝れるのかな?
シープお医者さんの魔法の呪文とは?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















