47 / 120
第47話 昔取ったラグタイム 1
しおりを挟む
仕事が休みということで安堂伊知郎は昼前まで眠ってしまっていた。
土日も含めたシフト制の派遣アルバイトなので平日に休みがくる。
会社勤めをしていた頃には有給でも取らない限り無かった感覚だったので、馴れるまで少し時間がかかった。
昼前まで誰も起こしに来ないというのも、家族が出ていってからの変化だった。
アラームを鳴らしたわけでもなく、自然と起きたわけでもなく、伊知郎は玄関チャイムの音で目を覚ました。
古びた一軒家の途切れ途切れに鳴る玄関チャイムの音に、ああ修理頼むの忘れていたな、と寝起きのぼんやりした頭で思い浮かべる。
何度か玄関チャイムが鳴り、少し間を置いて玄関のガラス戸を叩く音がした。
少しばかり控えめなノック。
ゆっくりと目が覚めて、伊知郎は起き上がった。
午前休したことを取り戻そうと昨日は仕事をはりきってしまい、五十を前にした身体は疲れ果てて二階にある自室に戻ることもできず一階のリビングで倒れるように眠ってしまっていた。
「風呂、入らないと汗臭いな。家族が居なくて良かったよ」
つんとくる汗の臭いに独り言を呟く。
笑えない冗談を口にして自嘲してしまう。
来客が女性じゃなければいいな、と思いながら疲労の回復しない身体でふらふらと玄関へと向かう。
玄関のガラス戸のノックが続く。
トントンとかドンドンというより、古い戸の動きからガタガタと五月蝿い音がたつ。
いい加減割れそうで怖いからどうにかしてよ、と娘に言われたのを思い出す。
「すみません、真盛署の者ですが。安堂さん、いらっしゃいますか?」
のろのろとした足取りになってしまいなかなか辿り着かない玄関先から若い男性の声が聞こえる。
「はい、ちょっと待ってください」
伊知郎は慌てて返事をした。
玄関チャイムが鳴った後、玄関まで行かなきゃならないのは不便で不用心だからインターホンを付けようと妻に相談されたことを思い出す。
設置について考えてると娘が意外にも反対してきて驚きだった。
反対理由は古びた一軒家に最新のカメラ付きインターホンは不恰好だというもので、これには妻も驚いていたが、だったら最新の物じゃなくても良くないか、とか話は何故か難航することになってしまい、そうこうしてるうちに妻も娘も家を出ていって、業者に頼みそびれてしまっていた。
やっとのことで辿り着き、伊知郎は玄関の戸を開けた。
「あ、すみません、突然お伺いして」
「我々はこういうものです」
男性が二人。
一人は深い茶色のよれよれの背広を着た男性で、白髪混じりの短髪と顔に刻まれる皺の数で伊知郎よりも歳を重ねているように見える。
正面から見てもわかるほどの猫背で背が低めなのも、相まってそれほど身長の高くない伊知郎を下から見上げる形になっていた。
浮かべる表情は人懐っこい温和なものであったが、目の奥は笑っているようには見えなかった。
胸ポケットから取り出した警察手帳から若菜歩という名前がわかる。
その若菜の横に立つのは、暗めの青い背広を着た若者で見た目だけで言えば若菜の息子のようにも見えるほど年が離れてそうだった。
若菜に比べれば頭二つ、伊知郎からしても頭一つ背の高い若者も警察手帳を提示している。
井上梅吉。
井上は何故だか気まずそうに苦笑いを浮かべていた。
「警察を騙る詐欺とかありますが、我々は違いますのでご安心を」
若菜はそう言って、よく確認しろと言わんばかりに手帳を伊知郎に向けて見せる。
そんなにしっかり見せられても何処を確認して本物か偽物か判断できるのか伊知郎は知らなかった。
「警察が、私に何を?」
頭に過ったのは昨日文哉と会話した内容だった。
羽音町は意外と荒れていて、娘ぐらいの若い世代はそれを当たり前のことのように周知しているという事実。
もしかして、娘が事件に巻き込まれたのか?
「いえね、安堂さん、貴方昨日怪我した若者を二人、救急車を呼んで病院へ運んでくれたらしいじゃないですか?」
「え? いや、私がしたのは救急車を呼んだまでのことですよ」
想像してたことが外れたようで伊知郎は安堵した。
昨日のことについて隠し立てるようなこともないので、素直に訂正する。
救急車を呼んだはいいが名前も知らない若者二人の処置を、救急隊員に任せるぐらいしか出来なかった。
「若者二人は顔面など大怪我を負っていましたが、安堂さんは事件性を感じましたか?」
「事件性、ですか?」
「ええ、あの二人の姿を見て、警察に通報しようとは思わなかったのか、と思いましてね?」
温厚な表情を保ち見上げてくる若菜。
何を問い詰められているのかわからないが、伊知郎は妙な緊張を感じて息を飲んだ。
「ああ、そういう風に頭が回りませんでしたよ。怪我人がいるから救急車を呼ぼう。安直かもしれませんが、そういう風にしか思いつきませんでした」
「そうですか・・・・・・」
救急車を呼んだ後に警察へと連絡しようとも伊知郎は思っていたのだが、何となくあの若者の邪魔をするような気がしてそれを止めることにした。
ふむ、と納得しかねないという態度をあからさまに取る若菜。
井上は何も言わずにただ最初から変わらずの苦笑いを浮かべたままだった。
「ところで──何故、安堂さんはあのような場所に?」
若菜の問い。
伊知郎は迂闊にもその答えを用意していなかった。
そして、伊知郎はようやく感づいた。
若菜が探りを入れているのは、伊知郎の昨日の動向ではないのだ。
あの赤いベロアジャケットの若者。
名前を聞きそびれたあの若者のことを、どうやら警察は探り当てようとしている。
土日も含めたシフト制の派遣アルバイトなので平日に休みがくる。
会社勤めをしていた頃には有給でも取らない限り無かった感覚だったので、馴れるまで少し時間がかかった。
昼前まで誰も起こしに来ないというのも、家族が出ていってからの変化だった。
アラームを鳴らしたわけでもなく、自然と起きたわけでもなく、伊知郎は玄関チャイムの音で目を覚ました。
古びた一軒家の途切れ途切れに鳴る玄関チャイムの音に、ああ修理頼むの忘れていたな、と寝起きのぼんやりした頭で思い浮かべる。
何度か玄関チャイムが鳴り、少し間を置いて玄関のガラス戸を叩く音がした。
少しばかり控えめなノック。
ゆっくりと目が覚めて、伊知郎は起き上がった。
午前休したことを取り戻そうと昨日は仕事をはりきってしまい、五十を前にした身体は疲れ果てて二階にある自室に戻ることもできず一階のリビングで倒れるように眠ってしまっていた。
「風呂、入らないと汗臭いな。家族が居なくて良かったよ」
つんとくる汗の臭いに独り言を呟く。
笑えない冗談を口にして自嘲してしまう。
来客が女性じゃなければいいな、と思いながら疲労の回復しない身体でふらふらと玄関へと向かう。
玄関のガラス戸のノックが続く。
トントンとかドンドンというより、古い戸の動きからガタガタと五月蝿い音がたつ。
いい加減割れそうで怖いからどうにかしてよ、と娘に言われたのを思い出す。
「すみません、真盛署の者ですが。安堂さん、いらっしゃいますか?」
のろのろとした足取りになってしまいなかなか辿り着かない玄関先から若い男性の声が聞こえる。
「はい、ちょっと待ってください」
伊知郎は慌てて返事をした。
玄関チャイムが鳴った後、玄関まで行かなきゃならないのは不便で不用心だからインターホンを付けようと妻に相談されたことを思い出す。
設置について考えてると娘が意外にも反対してきて驚きだった。
反対理由は古びた一軒家に最新のカメラ付きインターホンは不恰好だというもので、これには妻も驚いていたが、だったら最新の物じゃなくても良くないか、とか話は何故か難航することになってしまい、そうこうしてるうちに妻も娘も家を出ていって、業者に頼みそびれてしまっていた。
やっとのことで辿り着き、伊知郎は玄関の戸を開けた。
「あ、すみません、突然お伺いして」
「我々はこういうものです」
男性が二人。
一人は深い茶色のよれよれの背広を着た男性で、白髪混じりの短髪と顔に刻まれる皺の数で伊知郎よりも歳を重ねているように見える。
正面から見てもわかるほどの猫背で背が低めなのも、相まってそれほど身長の高くない伊知郎を下から見上げる形になっていた。
浮かべる表情は人懐っこい温和なものであったが、目の奥は笑っているようには見えなかった。
胸ポケットから取り出した警察手帳から若菜歩という名前がわかる。
その若菜の横に立つのは、暗めの青い背広を着た若者で見た目だけで言えば若菜の息子のようにも見えるほど年が離れてそうだった。
若菜に比べれば頭二つ、伊知郎からしても頭一つ背の高い若者も警察手帳を提示している。
井上梅吉。
井上は何故だか気まずそうに苦笑いを浮かべていた。
「警察を騙る詐欺とかありますが、我々は違いますのでご安心を」
若菜はそう言って、よく確認しろと言わんばかりに手帳を伊知郎に向けて見せる。
そんなにしっかり見せられても何処を確認して本物か偽物か判断できるのか伊知郎は知らなかった。
「警察が、私に何を?」
頭に過ったのは昨日文哉と会話した内容だった。
羽音町は意外と荒れていて、娘ぐらいの若い世代はそれを当たり前のことのように周知しているという事実。
もしかして、娘が事件に巻き込まれたのか?
「いえね、安堂さん、貴方昨日怪我した若者を二人、救急車を呼んで病院へ運んでくれたらしいじゃないですか?」
「え? いや、私がしたのは救急車を呼んだまでのことですよ」
想像してたことが外れたようで伊知郎は安堵した。
昨日のことについて隠し立てるようなこともないので、素直に訂正する。
救急車を呼んだはいいが名前も知らない若者二人の処置を、救急隊員に任せるぐらいしか出来なかった。
「若者二人は顔面など大怪我を負っていましたが、安堂さんは事件性を感じましたか?」
「事件性、ですか?」
「ええ、あの二人の姿を見て、警察に通報しようとは思わなかったのか、と思いましてね?」
温厚な表情を保ち見上げてくる若菜。
何を問い詰められているのかわからないが、伊知郎は妙な緊張を感じて息を飲んだ。
「ああ、そういう風に頭が回りませんでしたよ。怪我人がいるから救急車を呼ぼう。安直かもしれませんが、そういう風にしか思いつきませんでした」
「そうですか・・・・・・」
救急車を呼んだ後に警察へと連絡しようとも伊知郎は思っていたのだが、何となくあの若者の邪魔をするような気がしてそれを止めることにした。
ふむ、と納得しかねないという態度をあからさまに取る若菜。
井上は何も言わずにただ最初から変わらずの苦笑いを浮かべたままだった。
「ところで──何故、安堂さんはあのような場所に?」
若菜の問い。
伊知郎は迂闊にもその答えを用意していなかった。
そして、伊知郎はようやく感づいた。
若菜が探りを入れているのは、伊知郎の昨日の動向ではないのだ。
あの赤いベロアジャケットの若者。
名前を聞きそびれたあの若者のことを、どうやら警察は探り当てようとしている。
5
お気に入りに追加
17
あなたにおすすめの小説


優等生の裏の顔クラスの優等生がヤンデレオタク女子だった件
石原唯人
ライト文芸
「秘密にしてくれるならいい思い、させてあげるよ?」
隣の席の優等生・出宮紗英が“オタク女子”だと偶然知ってしまった岡田康平は、彼女に口封じをされる形で推し活に付き合うことになる。
紗英と過ごす秘密の放課後。初めは推し活に付き合うだけだったのに、気づけば二人は一緒に帰るようになり、休日も一緒に出掛けるようになっていた。
「ねえ、もっと凄いことしようよ」
そうして積み重ねた時間が徐々に紗英の裏側を知るきっかけとなり、不純な秘密を守るための関係が、いつしか淡く甘い恋へと発展する。
表と裏。二つのカオを持つ彼女との刺激的な秘密のラブコメディ。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
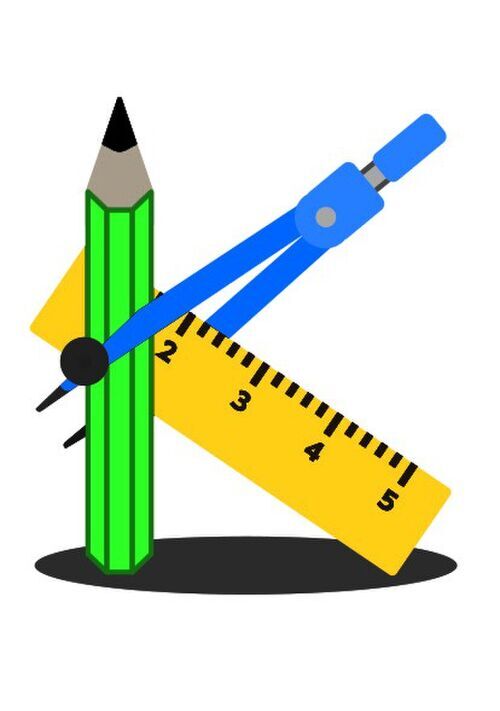
The Color of The Fruit Is Red of Blood
羽上帆樽
ライト文芸
仕事の依頼を受けて、山の頂きに建つ美術館にやって来た二人。美術品の説明を翻訳する作業をする内に、彼らはある一枚の絵画を見つける。そこに描かれていた奇妙な果物と、少女が見つけたもう一つのそれ。絵画の作者は何を伝えたかったのか、彼らはそれぞれ考察を述べることになるが……。

行くゼ! 音弧野高校声優部
涼紀龍太朗
ライト文芸
流介と太一の通う私立音弧野高校は勝利と男気を志向するという、時代を三周程遅れたマッチョな男子校。
そんな音弧野高で声優部を作ろうとする流介だったが、基本的にはスポーツ以外の部活は認められていない。しかし流介は、校長に声優部発足を直談判した!
同じ一年生にしてフィギュアスケートの国民的スター・氷堂を巻き込みつつ、果たして太一と流介は声優部を作ることができるのか否か?!

スライム10,000体討伐から始まるハーレム生活
昼寝部
ファンタジー
この世界は12歳になったら神からスキルを授かることができ、俺も12歳になった時にスキルを授かった。
しかし、俺のスキルは【@&¥#%】と正しく表記されず、役に立たないスキルということが判明した。
そんな中、両親を亡くした俺は妹に不自由のない生活を送ってもらうため、冒険者として活動を始める。
しかし、【@&¥#%】というスキルでは強いモンスターを討伐することができず、3年間冒険者をしてもスライムしか倒せなかった。
そんなある日、俺がスライムを10,000体討伐した瞬間、スキル【@&¥#%】がチートスキルへと変化して……。
これは、ある日突然、最強の冒険者となった主人公が、今まで『スライムしか倒せないゴミ』とバカにしてきた奴らに“ざまぁ”し、美少女たちと幸せな日々を過ごす物語。

182年の人生
山碕田鶴
ホラー
1913年。軍の諜報活動を支援する貿易商シキは暗殺されたはずだった。他人の肉体を乗っ取り魂を存続させる能力に目覚めたシキは、死神に追われながら永遠を生き始める。
人間としてこの世に生まれ来る死神カイと、アンドロイド・イオンを「魂の器」とすべく開発するシキ。
二人の幾度もの人生が交差する、シキ182年の記録。
(表紙絵/山碕田鶴)
※2024年11月〜 加筆修正の改稿工事中です。本日「60」まで済。

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















