100 / 114
1章【地獄のスパルタ訓練編】
第99話・底知れぬ力
しおりを挟む
時は、少々遡(さかのぼ)る。
魔王城にて、猛紅竜がテュラングルとの再会を果たす直前。
幼女が、地下の資料部屋へと向かっていた時の事だった。
「──隠した?」
片眉を吊り上げ、幼女は振り返る。
足を止め、ぱちくりと瞬きをする幼女は、後ろにいる相手へと近寄る。
“妙な説明”を受けた幼女は、真実の追求をするべく口を開いた。
「⋯⋯テュラングル、隠し事は良くないよねぇ?
タンコブ、もう1コいっとく?」
「は、話を最後まで聞いてください。
いいですか? 私が彼にやった事というのは─⋯」
⋯─端的に言うなら、“力の制限”です。
先程説明した通り、彼の口から貴女らしき存在の事を私は聞きました。
そこで私は、彼に力を付けさせる為に自身の角を折り、喰わせたのです。
まぁ、私の勘違いという可能性もありましたので、極僅かですが⋯⋯。
それでも、当時の彼にとって莫大な魔力量だった事には変わりありません。
そこで、私は与えた力の一部を“隠した”のです。
具体的に説明しますと、【魔力式】の切断ですね。
私が与えた力を、彼なら「放出」の様なブレス系統ではなく、「凝縮」⋯⋯つまり、“身に纏う使い方”をする筈です。
そうなった場合、“力”の出力を見誤れば、彼の肉体は必ず負荷に耐えかねます。
ですから私は、彼に角を喰わせた直後、魔力中毒で気を失っている隙に─⋯
「⋯─紅志(あかし)の中で生まれたばかりの、“炎系”の【魔力式】の一部を切断。
一定以上の出力が出せない様にしたワケだ」
「その通りです、アリア様。
弊害として、少しの間だけ炎の調整に手こずる時期はあったでしょうが⋯⋯」
「ふむ、よく理解した。
──ナイス判断だったね、テュラングル♪」
テュラングルの頭を撫で、幼女は微笑む。
実の所、彼女はテュラングルがそこまで考えているとは思っていなかった。
だからこそ、既に一発のゲンコツを食らわせてしまった訳だが。
しっかりと計算された上での行動だったと知り、早急に誤魔化そうとしてる状態なのである。
「いや~ホント! 私が見込んだだけのコだよ、君は♪」
「お褒めの言葉、有難く頂戴致します。
⋯⋯ところでですが、“紅志”というのが彼の名前。
“炎装”というのが彼の力の名前⋯⋯という事でよろしいですか?」
「ん? あぁ、そうそう。
えーっと。それじゃあ、私は色々忙しいから行くね!
久し振りだし、紅志にもあって行けば?」
スタコラセッセと早足で幼女は立ち去る。
広間の奥へと向かう彼女の背を見て、テュラングルは静かに言った。
「──えぇ、そのつもりです」
NOW LOADING⋯
「⋯⋯⋯⋯。」
テュラングルは、猛紅竜に施した策を思い返していた。
──魔力式の切断──
それは、“魔力の操作を根底から不可能にする”という技術である。
そもそも、“魔法”と“魔力の操作”という2つの間には、明確な違いが存在する。
魔法とは、「人間が創り出した」、「魔法陣によって」、尚且つ「体外で発動する魔力」の事。
魔力の操作とは、「魔族や魔物が行う」、「体内の器官で行われる」、「魔力への干渉」の事である。
この2つを端的に分けるのならば、「魔法陣の有無」だ。
本来、魔法陣とは、魔族や魔物の“魔力変換器官”を模倣して作られている。
そして裏を返すならば、形状に違いはあれど“仕組み”自体は全く同じ、という事である。
「魔力が流れる回路」=「魔力式」があり、そこを 「魔力が流れる」事で、初めて“効果が発動する”のだ。
だが、「発動ごとに生成できる魔法陣」と違い、「臓器の一部」である魔力変換器官は、一度破損をすると回復するまで使用は不可能になる。
──そして。
意図的に切断したとなれば、回復をさせない様に工夫しているのは当然。
現状の猛紅竜の炎装は、40%程の出力しか発揮出来ない様になっていた。
「──ハァ"ッ!! ハァ"ッ⋯⋯!!」
⋯⋯だが、しかし。
それ程までに力を制限されて尚、
「どうだッ、ティガァッ!」
「へッ、やるじゃねえか紅志! それでこそ漢だぜ!」
猛紅竜はティガから逃げ切った。
時間にして約1時間。危うい場面こそあったものの、間合い3m以内には決してティガを入れなかったのである。
圧倒的に格上に、様々なルールの上だった事はあるが、勝利したという事実。
テュラングルは、思わず口角を上げていた。
(“隠した力”を解放してやる日も、そう遠くは無いか⋯⋯)
彼が龍(ドラゴン)として、初めて猛紅竜を認めた瞬間であった。
「──よォし! 今日のトコは、もう終いだ。
しっかり休めよ? 明日はもっと上げてくからなッ!」
「ハァッ、ハァッ⋯⋯。上等じゃねえか⋯⋯」
地面に大の字で仰向けになり、猛紅竜は拳を掲げる。
大量の汗を全身から流す彼に、テュラングルは歩み寄る。
(──出会った瞬間は眼中にすら無かった幼竜が、今やここまで力を付けているとはな)
湧き上がる高揚を堪え、テュラングルは猛紅竜の隣に腰を下ろした。
「へへッ。見てたかよ、テュラングル?」
「あぁ、然(しか)とな。逞しくなったものだ」
「⋯⋯! アンタ、また変わったか?」
「ふん、我も火龍の王だ。
己が認めた者であれは、順当な評価とそれに見合った態度で応じるさ」
ドラゴン、2匹。
腹を割って話す両者は、静かに笑った。
「──紅志よ。お前、今回の件を終えたら、我らの住処(すみか)に来る気はないか?」
「ハッ、またまた。何を企んでんだ?」
「⋯⋯いや。お前ほどの男なら、“次代”を任せてもいいかも知れぬと思ってな」
空を見上げ、テュラングルは語る。
“新たな可能性”に目を輝かせる彼は、猛紅竜へと首を動かす。
不思議そうな表情を浮かべる猛紅竜に対して、テュラングルは言葉を続けた。
「我らドラゴンは、主に下位種と上位種に分けれる。
“竜種”と“龍種”だ。無論だが、文字だけの違いでは無いぞ?
れっきとした、“進化による違い”が存在してるのだ」
「進化による違い」
「そうだ。分かりやすく言うなら、“より原初に近いドラゴン”が龍、“そうでない者達”が竜だ。
まぁ、難しい話は省略しよう。
──ドラゴン族には、“王”という者が存在する。
それというのは、先代の王が次代の王を“指名”する事で受け継がれてきた訳なのだが⋯⋯」
テュラングルは、少々気まずそうな顔をする。
大きな尻尾を左右に揺らし、数秒間を開けた彼が、再び口を開く──よりも早く、猛紅竜が彼へ問い掛けた。
「今の“王”は、アンタって事か?」
「ウム、その通りだ。そこで──」
「あぁ、待った。話が見えたぞ。
先に言っておくが、俺は“王”になる気は無いぜ?」
「⋯⋯そうか、残念だ」
先手を打たれたテュラングルは、静かに俯く。
だが、要求を拒まれたにも関わらず、彼の表情に曇りは生まれていない。
そんな様子が気になった猛紅竜は、テュラングルの顔を覗き込んだ。
「──俺はてっきり、粘られるモンだと⋯⋯」
「ハッハッ。“自分だけが特別”だとでも?
我らの住処にも、お前に劣らぬ“次代”はいるさ」
「へぇ⋯⋯」
「それに、先の回答は予想通りさ。
お前は、“王”には向いていない。──良い意味で、な」
「⋯⋯はは、分かるか?」
テュラングルの言う、『良い意味』。
それは猛紅竜という魔物の性格を踏まえた表現であった。
“群れるのは好きではない”だが、“孤独は嫌い”といった、一見すると矛盾した様なその性格。
しかし、目の前の猛紅竜は、その性格が最もよく現れた事を好んでいた。
「──俺はさ、旅をするのが好きなんだ。
色んな景色を観て、色んな奴と出会って、色んな経験をする⋯⋯。そんな旅が」
「知っている、好きにするがよい」
テュラングルは立ち上がる。
大きな翼をはためかせ、その場を去ろうとする彼の表情は、とても満足気なものであった。
「──テュラングル! 聞いておきたい事がある!」
「なんだ?」
「さっきの俺にも劣らない“次代”ってのは、どんなヤツなんだ?」
巨躯が浮き始めるテュラングルは、小さく微笑む。
故郷の地を思い出す彼の脳裏には、美しい翼を持つ幼い竜(ドラゴン)の姿があった。
「彼奴は、まだ小さく、弱く、若い。
だが、その器量は間違いなく、次なるドラゴン族を託すに相応しいものだ」
「⋯⋯そいつの名前は?」
猛紅竜の質問に、テュラングルは。
巨翼を空気に打ち付けてから答えた。
「──バハムート」
魔王城にて、猛紅竜がテュラングルとの再会を果たす直前。
幼女が、地下の資料部屋へと向かっていた時の事だった。
「──隠した?」
片眉を吊り上げ、幼女は振り返る。
足を止め、ぱちくりと瞬きをする幼女は、後ろにいる相手へと近寄る。
“妙な説明”を受けた幼女は、真実の追求をするべく口を開いた。
「⋯⋯テュラングル、隠し事は良くないよねぇ?
タンコブ、もう1コいっとく?」
「は、話を最後まで聞いてください。
いいですか? 私が彼にやった事というのは─⋯」
⋯─端的に言うなら、“力の制限”です。
先程説明した通り、彼の口から貴女らしき存在の事を私は聞きました。
そこで私は、彼に力を付けさせる為に自身の角を折り、喰わせたのです。
まぁ、私の勘違いという可能性もありましたので、極僅かですが⋯⋯。
それでも、当時の彼にとって莫大な魔力量だった事には変わりありません。
そこで、私は与えた力の一部を“隠した”のです。
具体的に説明しますと、【魔力式】の切断ですね。
私が与えた力を、彼なら「放出」の様なブレス系統ではなく、「凝縮」⋯⋯つまり、“身に纏う使い方”をする筈です。
そうなった場合、“力”の出力を見誤れば、彼の肉体は必ず負荷に耐えかねます。
ですから私は、彼に角を喰わせた直後、魔力中毒で気を失っている隙に─⋯
「⋯─紅志(あかし)の中で生まれたばかりの、“炎系”の【魔力式】の一部を切断。
一定以上の出力が出せない様にしたワケだ」
「その通りです、アリア様。
弊害として、少しの間だけ炎の調整に手こずる時期はあったでしょうが⋯⋯」
「ふむ、よく理解した。
──ナイス判断だったね、テュラングル♪」
テュラングルの頭を撫で、幼女は微笑む。
実の所、彼女はテュラングルがそこまで考えているとは思っていなかった。
だからこそ、既に一発のゲンコツを食らわせてしまった訳だが。
しっかりと計算された上での行動だったと知り、早急に誤魔化そうとしてる状態なのである。
「いや~ホント! 私が見込んだだけのコだよ、君は♪」
「お褒めの言葉、有難く頂戴致します。
⋯⋯ところでですが、“紅志”というのが彼の名前。
“炎装”というのが彼の力の名前⋯⋯という事でよろしいですか?」
「ん? あぁ、そうそう。
えーっと。それじゃあ、私は色々忙しいから行くね!
久し振りだし、紅志にもあって行けば?」
スタコラセッセと早足で幼女は立ち去る。
広間の奥へと向かう彼女の背を見て、テュラングルは静かに言った。
「──えぇ、そのつもりです」
NOW LOADING⋯
「⋯⋯⋯⋯。」
テュラングルは、猛紅竜に施した策を思い返していた。
──魔力式の切断──
それは、“魔力の操作を根底から不可能にする”という技術である。
そもそも、“魔法”と“魔力の操作”という2つの間には、明確な違いが存在する。
魔法とは、「人間が創り出した」、「魔法陣によって」、尚且つ「体外で発動する魔力」の事。
魔力の操作とは、「魔族や魔物が行う」、「体内の器官で行われる」、「魔力への干渉」の事である。
この2つを端的に分けるのならば、「魔法陣の有無」だ。
本来、魔法陣とは、魔族や魔物の“魔力変換器官”を模倣して作られている。
そして裏を返すならば、形状に違いはあれど“仕組み”自体は全く同じ、という事である。
「魔力が流れる回路」=「魔力式」があり、そこを 「魔力が流れる」事で、初めて“効果が発動する”のだ。
だが、「発動ごとに生成できる魔法陣」と違い、「臓器の一部」である魔力変換器官は、一度破損をすると回復するまで使用は不可能になる。
──そして。
意図的に切断したとなれば、回復をさせない様に工夫しているのは当然。
現状の猛紅竜の炎装は、40%程の出力しか発揮出来ない様になっていた。
「──ハァ"ッ!! ハァ"ッ⋯⋯!!」
⋯⋯だが、しかし。
それ程までに力を制限されて尚、
「どうだッ、ティガァッ!」
「へッ、やるじゃねえか紅志! それでこそ漢だぜ!」
猛紅竜はティガから逃げ切った。
時間にして約1時間。危うい場面こそあったものの、間合い3m以内には決してティガを入れなかったのである。
圧倒的に格上に、様々なルールの上だった事はあるが、勝利したという事実。
テュラングルは、思わず口角を上げていた。
(“隠した力”を解放してやる日も、そう遠くは無いか⋯⋯)
彼が龍(ドラゴン)として、初めて猛紅竜を認めた瞬間であった。
「──よォし! 今日のトコは、もう終いだ。
しっかり休めよ? 明日はもっと上げてくからなッ!」
「ハァッ、ハァッ⋯⋯。上等じゃねえか⋯⋯」
地面に大の字で仰向けになり、猛紅竜は拳を掲げる。
大量の汗を全身から流す彼に、テュラングルは歩み寄る。
(──出会った瞬間は眼中にすら無かった幼竜が、今やここまで力を付けているとはな)
湧き上がる高揚を堪え、テュラングルは猛紅竜の隣に腰を下ろした。
「へへッ。見てたかよ、テュラングル?」
「あぁ、然(しか)とな。逞しくなったものだ」
「⋯⋯! アンタ、また変わったか?」
「ふん、我も火龍の王だ。
己が認めた者であれは、順当な評価とそれに見合った態度で応じるさ」
ドラゴン、2匹。
腹を割って話す両者は、静かに笑った。
「──紅志よ。お前、今回の件を終えたら、我らの住処(すみか)に来る気はないか?」
「ハッ、またまた。何を企んでんだ?」
「⋯⋯いや。お前ほどの男なら、“次代”を任せてもいいかも知れぬと思ってな」
空を見上げ、テュラングルは語る。
“新たな可能性”に目を輝かせる彼は、猛紅竜へと首を動かす。
不思議そうな表情を浮かべる猛紅竜に対して、テュラングルは言葉を続けた。
「我らドラゴンは、主に下位種と上位種に分けれる。
“竜種”と“龍種”だ。無論だが、文字だけの違いでは無いぞ?
れっきとした、“進化による違い”が存在してるのだ」
「進化による違い」
「そうだ。分かりやすく言うなら、“より原初に近いドラゴン”が龍、“そうでない者達”が竜だ。
まぁ、難しい話は省略しよう。
──ドラゴン族には、“王”という者が存在する。
それというのは、先代の王が次代の王を“指名”する事で受け継がれてきた訳なのだが⋯⋯」
テュラングルは、少々気まずそうな顔をする。
大きな尻尾を左右に揺らし、数秒間を開けた彼が、再び口を開く──よりも早く、猛紅竜が彼へ問い掛けた。
「今の“王”は、アンタって事か?」
「ウム、その通りだ。そこで──」
「あぁ、待った。話が見えたぞ。
先に言っておくが、俺は“王”になる気は無いぜ?」
「⋯⋯そうか、残念だ」
先手を打たれたテュラングルは、静かに俯く。
だが、要求を拒まれたにも関わらず、彼の表情に曇りは生まれていない。
そんな様子が気になった猛紅竜は、テュラングルの顔を覗き込んだ。
「──俺はてっきり、粘られるモンだと⋯⋯」
「ハッハッ。“自分だけが特別”だとでも?
我らの住処にも、お前に劣らぬ“次代”はいるさ」
「へぇ⋯⋯」
「それに、先の回答は予想通りさ。
お前は、“王”には向いていない。──良い意味で、な」
「⋯⋯はは、分かるか?」
テュラングルの言う、『良い意味』。
それは猛紅竜という魔物の性格を踏まえた表現であった。
“群れるのは好きではない”だが、“孤独は嫌い”といった、一見すると矛盾した様なその性格。
しかし、目の前の猛紅竜は、その性格が最もよく現れた事を好んでいた。
「──俺はさ、旅をするのが好きなんだ。
色んな景色を観て、色んな奴と出会って、色んな経験をする⋯⋯。そんな旅が」
「知っている、好きにするがよい」
テュラングルは立ち上がる。
大きな翼をはためかせ、その場を去ろうとする彼の表情は、とても満足気なものであった。
「──テュラングル! 聞いておきたい事がある!」
「なんだ?」
「さっきの俺にも劣らない“次代”ってのは、どんなヤツなんだ?」
巨躯が浮き始めるテュラングルは、小さく微笑む。
故郷の地を思い出す彼の脳裏には、美しい翼を持つ幼い竜(ドラゴン)の姿があった。
「彼奴は、まだ小さく、弱く、若い。
だが、その器量は間違いなく、次なるドラゴン族を託すに相応しいものだ」
「⋯⋯そいつの名前は?」
猛紅竜の質問に、テュラングルは。
巨翼を空気に打ち付けてから答えた。
「──バハムート」
0
お気に入りに追加
14
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る
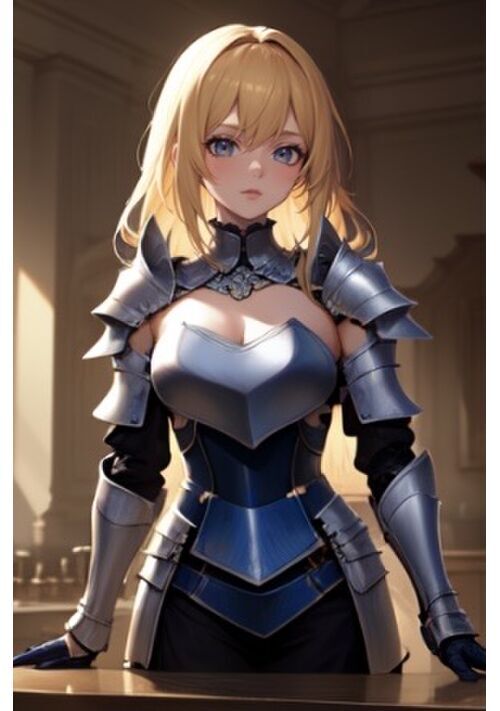
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!

大工スキルを授かった貧乏貴族の養子の四男だけど、どうやら大工スキルは伝説の全能スキルだったようです
飼猫タマ
ファンタジー
田舎貴族の四男のヨナン・グラスホッパーは、貧乏貴族の養子。義理の兄弟達は、全員戦闘系のレアスキル持ちなのに、ヨナンだけ貴族では有り得ない生産スキルの大工スキル。まあ、養子だから仕方が無いんだけど。
だがしかし、タダの生産スキルだと思ってた大工スキルは、じつは超絶物凄いスキルだったのだ。その物凄スキルで、生産しまくって超絶金持ちに。そして、婚約者も出来て幸せ絶頂の時に嵌められて、人生ドン底に。だが、ヨナンは、有り得ない逆転の一手を持っていたのだ。しかも、その有り得ない一手を、本人が全く覚えてなかったのはお約束。
勿論、ヨナンを嵌めた奴らは、全員、ザマー百裂拳で100倍返し!
そんなお話です。

特殊部隊の俺が転生すると、目の前で絶世の美人母娘が犯されそうで助けたら、とんでもないヤンデレ貴族だった
なるとし
ファンタジー
鷹取晴翔(たかとりはると)は陸上自衛隊のとある特殊部隊に所属している。だが、ある日、訓練の途中、不慮の事故に遭い、異世界に転生することとなる。
特殊部隊で使っていた武器や防具などを召喚できる特殊能力を謎の存在から授かり、目を開けたら、絶世の美女とも呼ばれる母娘が男たちによって犯されそうになっていた。
武装状態の鷹取晴翔は、持ち前の優秀な身体能力と武器を使い、その母娘と敷地にいる使用人たちを救う。
だけど、その母と娘二人は、
とおおおおんでもないヤンデレだった……
第3回次世代ファンタジーカップに出すために一部を修正して投稿したものです。

貴族に生まれたのに誘拐され1歳で死にかけた
佐藤醤油
ファンタジー
貴族に生まれ、のんびりと赤ちゃん生活を満喫していたのに、気がついたら世界が変わっていた。
僕は、盗賊に誘拐され魔力を吸われながら生きる日々を過ごす。
魔力枯渇に陥ると死ぬ確率が高いにも関わらず年に1回は魔力枯渇になり死にかけている。
言葉が通じる様になって気がついたが、僕は他の人が持っていないステータスを見る力を持ち、さらに異世界と思われる世界の知識を覗ける力を持っている。
この力を使って、いつか脱出し母親の元へと戻ることを夢見て過ごす。
小さい体でチートな力は使えない中、どうにか生きる知恵を出し生活する。
------------------------------------------------------------------
お知らせ
「転生者はめぐりあう」 始めました。
------------------------------------------------------------------
注意
作者の暇つぶし、気分転換中の自己満足で公開する作品です。
感想は受け付けていません。
誤字脱字、文面等気になる方はお気に入りを削除で対応してください。

ごめんみんな先に異世界行ってるよ1年後また会おう
味噌汁食べれる
ファンタジー
主人公佐藤 翔太はクラスみんなより1年も早く異世界に、行ってしまう。みんなよりも1年早く異世界に行ってしまうそして転移場所は、世界樹で最強スキルを実でゲット?スキルを奪いながら最強へ、そして勇者召喚、それは、クラスのみんなだった。クラスのみんなが頑張っているときに、主人公は、自由気ままに生きていく

幼なじみ三人が勇者に魅了されちゃって寝盗られるんだけど数年後勇者が死んで正気に戻った幼なじみ達がめちゃくちゃ後悔する話
妄想屋さん
ファンタジー
『元彼?冗談でしょ?僕はもうあんなのもうどうでもいいよ!』
『ええ、アタシはあなたに愛して欲しい。あんなゴミもう知らないわ!』
『ええ!そうですとも!だから早く私にも――』
大切な三人の仲間を勇者に〈魅了〉で奪い取られて絶望した主人公と、〈魅了〉から解放されて今までの自分たちの行いに絶望するヒロイン達の話。

蘇生魔法を授かった僕は戦闘不能の前衛(♀)を何度も復活させる
フルーツパフェ
大衆娯楽
転移した異世界で唯一、蘇生魔法を授かった僕。
一緒にパーティーを組めば絶対に死ぬ(死んだままになる)ことがない。
そんな口コミがいつの間にか広まって、同じく異世界転移した同業者(多くは女子)から引っ張りだこに!
寛容な僕は彼女達の申し出に快諾するが条件が一つだけ。
――実は僕、他の戦闘スキルは皆無なんです
そういうわけでパーティーメンバーが前衛に立って死ぬ気で僕を守ることになる。
大丈夫、一度死んでも蘇生魔法で復活させてあげるから。
相互利益はあるはずなのに、どこか鬼畜な匂いがするファンタジー、ここに開幕。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















