お気に入りに追加
1
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

アカペラバンドガールズ!! 〜島の女神様とわたし(見習い)のひみつの関係!?〜
Shooter
ライト文芸
「……一緒に、歌お?」
──これは、日常と非日常が絡まり合った、あるガールズアカペラバンドの結成と成長の物語。
南西諸島の島、音美(ねび)大島。
高校一年の遠矢桜良(とおやさくら)は、幼馴染の横峯早百合(よこみねさゆり)と偶然再会したことで、合唱に興味を持ち始める。しかし、早百合には何か秘密があるようで、体育祭の時終始浮かない顔をしていた彼女のことが、何となく気にかかっていた。
そんな折、桜良は夢の中である綺麗な女性と出会う。不思議なその人からの助言を元に、後日早百合を黒いもやから助け出すことに成功した桜良は、後日一緒に音楽活動をしようと提案する。
そしてその日の夜、再び目の前に現れた女性が口にしたのは、
「自分は神様で、あなたは『ユラ』という天命を持って生まれた子」だという、あまりにも非現実的なことだった……。
神秘的なオーラが漂う南の島を舞台に、時に笑い、時に泣き、常に全力で青春を駆け抜けた女子高生6人。そんな彼女たちとお茶目な島の女神様が紡ぐ、ちょっとだけ不思議な一年半の軌跡を紹介します。
現実世界が舞台の青春偶像劇ですが、一部ファンタジー要素があります。
【お知らせ!】
・7月連休をもって、無事完結致しました!
(現在続編、及びその他表現方法や媒体を模索中)
・劇中ガールズアカペラバンド『Bleθ』(ブレス)は、小説外でも活動中です!
公式YouTubeチャンネル → https://youtube.com/@bleth-felicita
⭐︎OPテーマ「Sky-Line!!」、EDテーマ「fragile」、歌ってみた(カバー)楽曲「Lemon」を公開中!
☆ 素晴らしいイラスト制作者様 → RAVES様
(ありがとうございます!)

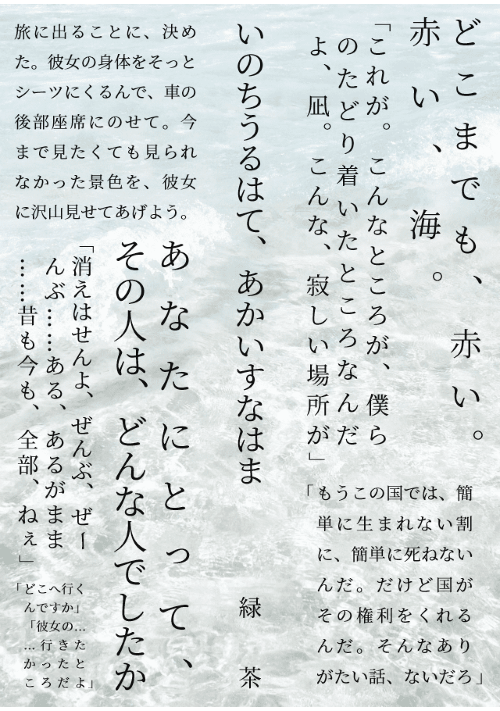
いのちうるはて、あかいすなはま。
緑茶
ライト文芸
近い未来、「いのち」は、売りに出されるようになっていた。それも、正式な政府のシステムとして。
市役所に勤務する「僕」は、日々その手続きに追われている。
病に伏している恋人。繰り返される「命の値段」についての問い。ふたつに板挟みになった「僕」は
苦悩し、精神をすり減らしていく。
彷徨の果て、「僕」が辿り着いたこたえとは――。


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

小説探偵
夕凪ヨウ
ミステリー
20XX年。日本に名を響かせている、1人の小説家がいた。
男の名は江本海里。素晴らしい作品を生み出す彼には、一部の人間しか知らない、“裏の顔”が存在した。
そして、彼の“裏の顔”を知っている者たちは、尊敬と畏怖を込めて、彼をこう呼んだ。
小説探偵、と。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















