お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

おっさんの神器はハズレではない
兎屋亀吉
ファンタジー
今日も元気に満員電車で通勤途中のおっさんは、突然異世界から召喚されてしまう。一緒に召喚された大勢の人々と共に、女神様から一人3つの神器をいただけることになったおっさん。はたしておっさんは何を選ぶのか。おっさんの選んだ神器の能力とは。

君が笑うから僕も笑う
神谷レイン
ライト文芸
神様に選ばれた善人だけが、死んだ命日から四年後、四日だけこの世に帰ってくる。
それは友人や家族、恋人、大切な人に会いに様々な想いを抱えて。
これはそんなお話が詰まった五作の短編集。
亡くなった人たちが残された人達に語りかける言葉とは?

俺だけ毎日チュートリアルで報酬無双だけどもしかしたら世界の敵になったかもしれない
亮亮
ファンタジー
朝起きたら『チュートリアル 起床』という謎の画面が出現。怪訝に思いながらもチュートリアルをクリアしていき、報酬を貰う。そして近い未来、世界が一新する出来事が起こり、主人公・花房 萌(はなぶさ はじめ)の人生の歯車が狂いだす。
不意に開かれるダンジョンへのゲート。その奥には常人では決して踏破できない存在が待ち受け、萌の体は凶刃によって裂かれた。
そしてチュートリアルが発動し、復活。殺される。復活。殺される。気が狂いそうになる輪廻の果て、萌は光明を見出し、存在を継承する事になった。
帰還した後、急速に馴染んでいく新世界。新しい学園への編入。試験。新たなダンジョン。
そして邂逅する謎の組織。
萌の物語が始まる。

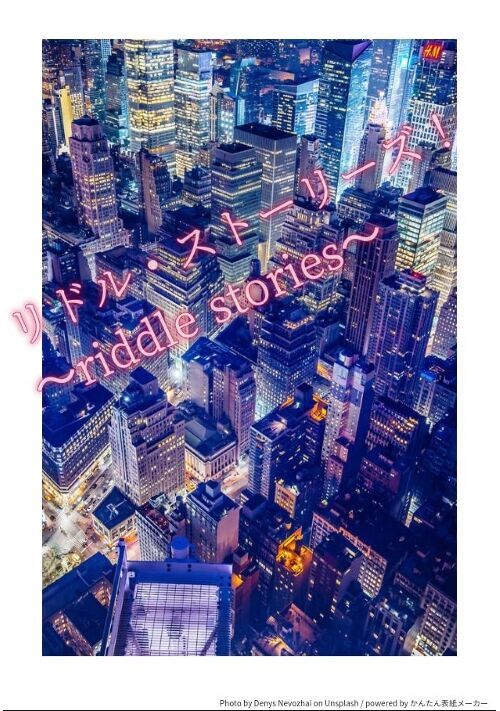
リドル・ストーリーズ!~riddle stories~
魔法組
ライト文芸
リドル・ストーリー。それはあえて結末を明かすことなく閉じられた物語のこと。物語に謎を残し、その後どうなったのかという結論と解釈を読者に丸投げ……もとい、委ねることによって成立する作品手法です。そんな話をいくつか思いついたので、つらつら書いていこうと考えています。
どれも短編の上、物語に連続性は全くないので一話から順番に読んでいただく必要はありません。お好きなものからどうぞ。
表紙画像は「かんたん表紙メーカー」様(https://sscard.monokakitools.net)にて作成したものを使っています。

ヤクザに医官はおりません
ユーリ(佐伯瑠璃)
ライト文芸
彼は私の知らない組織の人間でした
会社の飲み会の隣の席のグループが怪しい。
シャバだの、残弾なしだの、会話が物騒すぎる。刈り上げ、角刈り、丸刈り、眉毛シャキーン。
無駄にムキムキした体に、堅い言葉遣い。
反社会組織の集まりか!
ヤ◯ザに見初められたら逃げられない?
勘違いから始まる異文化交流のお話です。
※もちろんフィクションです。
小説家になろう、カクヨムに投稿しています。

心のかけら 〜6月 君の心笑-こえ-を聞かせて〜
桜月心愛
ライト文芸
ーー君の心笑-こえ-を聞かせて
幼馴染のあいつが死んだ。
会いに行くと約束したのに、その日が来ることなく、世界は彼女を連れ去った。
離れていた間、彼女は何を想っていたのか。
彼女は最期に何を想って死んでいったのか。
知りたいという思いと後悔。それらは入り交じって、有りもしない場所へと俺を誘う。
最期に見ていたであろう景色。
その視界にふわりと、彼女の白い帽子が見えた。
彼女を思わす白。落ちていく帽子。
それは彼女そのもののような気がして、、
俺は不意に手を、伸ばしていた。
これは遺された少年と頑張った少女のお話。
※初心者の作品です。誹謗中傷コメントは作者に猛毒となりますのでお控えください。
イラストもデジタル初心者で汚いですが気になさらずお読みください。(イラスト背景はIbis paint様からお借りしました)
最後に、ズラズラとすみません(´・ω・`)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















