50 / 72
革命戦争編(親世代)
四十八話 拠点放棄、ディーなりの心配り
しおりを挟む
雨が降る中でディーたちが拠点に戻ると、武器輸送の荷車とラクダが止まっているのが見えた。
ラクダの背にかかる布にはスハイル領の刺繍がしてある。
そして……荷車のまわりには誰もいなかった。
テントを貼っている様子もない。
一足遅かった。もうここに残ったメンバーは、見つかっている。
ゾワ、と鳥肌が立った。
拠点に走り、兵が入り込んでいる姿に気づいて加速した。
「離しなさい、もうすぐ反乱軍の仲間たちがここに来る! 貴方たちは一網打尽にされてしまうんだから!」
イーリスの声が、兵たちの集う先から聞こえた。
「ど、どうせ出任せだ。そんなのがいるならとっくに」
守る。絶対、ガーニムなんかのところに連れて行かせない。
ディーは疾走する勢いのまま、腰にさげたナイフを抜いて兵の背に飛び込んだ。
「ぐ、ぁ……」
王国兵といえど、不意打ちで刺されてはひとたまりもない。なすすべもなく前のめりに倒れた。
「じゃーん。ディー君、呼ばれて参上~! おじさんたち、イーリスに手を出したらただじゃおかないからね!」
「ディー! 来てくれたのね」
イーリスたちの不安を和らげようと、軽くおどけてみせる。
張り詰めていたイーリスの顔に、喜色が浮かんだ。
「そんな、まさか、本当に反乱軍が来た!?」
混合部隊のようだ。半分は王国兵、残る半分は傭兵に見える。
「その人たちに近寄らないでもらおうか。ここで引けば良し、引かないなら容赦しない」
ファジュルが短剣を構えて敵兵に言う。エウフェミアも両手に短剣を持ち応戦の体勢に入っている。
「なぜ我々が反乱軍の要求に応じなければならない。みんな、姫様を守るぞ」
三十代前半くらいだろうか。十人の兵を統率しているのは彼のようだ。無愛想な男が指揮をとる。
姫《・》に被害がいかないようにするためだろう。都合のいいことに、兵たちは外まで出てきてくれた。
「わざわざ出てきてくれて助かった。おかげでこっちを使えるよ」
エウフェミアが背にしていた武器《ジャーハ》に持ち替えた。矢をはめ、引き金に指をかけた。
黒い矢が王国兵の太ももに突き刺さる。
「くそ、女が、戦場にいる、だと?」
王国兵に女性兵はいないと聞いた。だからこその言葉だろう。エウフェミアが軽蔑の目で王国兵を見やる。
「男だから強い、女だから弱いと思っているなら赤子からやり直しな」
「チッ、舐めやがって」
「どっちが」
王国兵が体勢を立て直す前に次の矢が肩に刺さった。
ディーとファジュルも応戦する。
まわりを見ると何故かサーディクがいない。スラムでの戦いを経験しているのだから、今更逃げるなんてことしない、はず。
ディーと剣を交えていた傭兵が、ディーの後方で戦っているエウフェミアを睨む。
「おいエウフェミア。なんでお前、そっち側にいるんだ!」
「王子に雇われたからだよ」
エウフェミアが事前に言っていたとおり、相手の傭兵は顔見知りらしい。メインの活動地が異なるだけ。同業と親交があるのは、ディーの旅一座でもよくある。
「スハイル領の奴らはそっちにつくのかい?」
「金をもらったからな。金で動くのが傭兵ってもんだろ、エウフェミア。王国側につけば、反乱軍の倍額出してもらえると思うぜ」
「あいにく、あたしの報酬は金じゃない。この人が国王になったら、流民にも国籍を与えてくれると約束してくれたから」
帰る場所を持たない流民にとって、籍はこの国に帰ってきていいという標《しるべ》。
「ふん、傭兵すべてが国籍を望むと思ったら大間違いだ。俺は金さえ貰えれば何でもいい」
傭兵でも、全員が帰る場所を望むわけではないと、男は笑う。
「ならアンタはボクたちの敵だね。バイバイおじさん」
説得して味方になり得るならと手加減していたけれど、味方にならないなら障害物でしかない。
エウフェミアと会話する方に意識が集中している男は隙だらけだった。
ディーは剣の柄を振り上げ、傭兵の顎を打ち付ける。
傭兵がのけぞったところに追撃、胸にナイフを突き立てる。
これまで旅暮らしをしてきて、狩りで獣を殺して食べることはいくらでもあった。
けれどやはり、獣を殺すのと人を殺めるのではわけが違う。
ためらい、すきができれば自分の命が危ない。
自分に言い聞かせて、ディーはナイフを押し込めた。
「残り六人。油断するな、ディー」
顔を上げると、ファジュルとエウフェミアが連携して傭兵一人を沈めたところだった。
あの司令塔の男と王国兵二人、傭兵三人。
「不意打ちだったとはいえ、たった三人でよくもここまで……」
敵の司令塔が賞賛してくれる。
「サーディクはどこに行ったの」
「さあな。臆病風に吹かれたわけではないと思う」
訝しむエウフェミアと、肩をすくめるファジュル。思い返ば洞穴に突入するときからいなかったような。
用を足しにいったとかそんなところじゃないかと推測する。
「へへん。あんたら、のんきに戦っている場合じゃないと思うぜ」
サーディクが、ジャーハを手にして現れた。来るときはそんなもの持っていなかったのに。
矢をつがえてあるジャーハの照準を、司令塔の男に合わせる。
「貴様も反乱軍か? 戦っている場合じゃない、とはどういう意味だ」
「そのままの意味だって~」
顎だけ動かして、とある方向を指し示す。
ディーもつられてそちらを見た。
黒煙が上がっている。岩場だらけのこの場所に、燃えるのなんて…………。
「た、大変だ!! 積荷が!!」
王国兵と傭兵は、一気に青ざめた。
全員武器を収め、燃え盛る荷車に戻っていく。
「さ、今のうちに逃げよーぜ、みんな」
「お前、積荷を燃やしたのか」
「それだけじゃねーぜ。ラクダを始末して、ジャーハと、こいつをちょろまかしてきたんだ」
サーディクが腰に結んでいた革袋から複数の小瓶を取り出してみせる。瓶のラベルには毒の名前が書かれている。
「瓶のたぐいはこれで全部だ。毒は瓶に入ってるって先生が言ってたからよ。これを盗って、ついでに積んであった着火剤でボンと。ファジュル、もう盗むなって言ってたけど……これは窃盗の数に入らないよな?」
「そうだな。先に毒を奪うなんて、俺じゃ考え付きもしなかった。助かったよ、サーディク」
ファジュルが眉尻を下げて笑う。サーディクはなんだか得意げだ。
王国軍は荷車を引くラクダがいなくなり、積荷は燃え、しばらくは動けまい。消火に使う道具もろくにないのだから。
ディーたちは急いで洞穴にいる仲間のところに戻った。
「ディー、よかった、きてくれて、よかったぁうぁあぁん!」
「ちょ、イーリス! 濡れるよ」
洞穴に入った途端、イーリスが泣きながらディーにしがみついてきた。
ディーよりも二つ年上なのに、迷子になった幼児のように泣きじゃくる。
ディーは全身ずぶ濡れだから、抱きつくイーリスの服にも雨水が浸透している。それに、イーリスの胸は年頃の少女の中でもかなり豊かだ。抱きつかれれば否応なく当たる。
そのことが妙に気恥ずかしくて、ディーは慌てた。
「無事でよかった、ルゥ」
「うん。イーリスさんが守ってくれたから。ファジュルも、無事でよかった」
ファジュルが、十年ぶりの再会かってくらいの勢いでルゥルアを抱きしめている。そのことにツッコミをいれるとディーのほうが恥ずかしい思いをすると学習しているため、口に出さない。
存分にルゥルアを抱きしめたあと、ファジュルは地に膝をついてユーニスと目線を合わせる。
「ユーニスも、怖い目に遭ったな。来るのが遅くなってすまなかった」
「大丈夫だよ兄ちゃん。おれ、怖くなかったもん!」
「そうか。ユーニスは強いな」
「へへへっ」
大丈夫なんて言ってるけれど、ユーニスの足はガクガク震えている。ファジュルはユーニスの肩に手を乗せ、つとめて落ち着いた口調で話す。
「ユーニス、みんなも聞いてくれ。あいつらがまた来たら厄介だ。この隙に拠点を放棄して逃げよう」
敵に見つかった以上、もう隠れ家としての価値はない。
全員、身一つで荒野に飛び出した。
ファジュルがルゥルアの手を引いて歩き、ラシードとナジャーがユーニスの手を取る。
イーリスは黙リこくってディーの服の裾を摘んでいる。
ずっと摘まれていると変なシワになりそう、なんて頭の片隅で思うけれど、イーリスの好きにさせておくことにした。たぶん襲撃を受けて不安でいっぱいだったから、藁《わら》にもすがる、ってやつだ。
イーリスの気が済むまで藁でいよう。
エウフェミアとサーディクは、追っ手警戒のため最後尾にいる。
黙々と歩き続け、岩場を抜け荒野に出た。
視界にスラム居住地区が入り、誰からともなく安堵の息がもれる。
「ふへー、安心したらボクお腹空いちゃったよ」
「オレもー。ナジャー、ついたらなんか作ってくれよ」
「わかりました。腕によりをかけますね」
「じゃあおれ、ばあちゃんの手伝いするー!」
ユーニスがスラムの拠点目指して走り出す。
「ユーニス。足場が悪いから、走ると危ないよ」
「心配しすぎだよねーちゃん。だいじょーー、あわわっ!」
ルゥルアが声をかけたが間に合わず、ユーニスは全身泥だらけになった。
ラクダの背にかかる布にはスハイル領の刺繍がしてある。
そして……荷車のまわりには誰もいなかった。
テントを貼っている様子もない。
一足遅かった。もうここに残ったメンバーは、見つかっている。
ゾワ、と鳥肌が立った。
拠点に走り、兵が入り込んでいる姿に気づいて加速した。
「離しなさい、もうすぐ反乱軍の仲間たちがここに来る! 貴方たちは一網打尽にされてしまうんだから!」
イーリスの声が、兵たちの集う先から聞こえた。
「ど、どうせ出任せだ。そんなのがいるならとっくに」
守る。絶対、ガーニムなんかのところに連れて行かせない。
ディーは疾走する勢いのまま、腰にさげたナイフを抜いて兵の背に飛び込んだ。
「ぐ、ぁ……」
王国兵といえど、不意打ちで刺されてはひとたまりもない。なすすべもなく前のめりに倒れた。
「じゃーん。ディー君、呼ばれて参上~! おじさんたち、イーリスに手を出したらただじゃおかないからね!」
「ディー! 来てくれたのね」
イーリスたちの不安を和らげようと、軽くおどけてみせる。
張り詰めていたイーリスの顔に、喜色が浮かんだ。
「そんな、まさか、本当に反乱軍が来た!?」
混合部隊のようだ。半分は王国兵、残る半分は傭兵に見える。
「その人たちに近寄らないでもらおうか。ここで引けば良し、引かないなら容赦しない」
ファジュルが短剣を構えて敵兵に言う。エウフェミアも両手に短剣を持ち応戦の体勢に入っている。
「なぜ我々が反乱軍の要求に応じなければならない。みんな、姫様を守るぞ」
三十代前半くらいだろうか。十人の兵を統率しているのは彼のようだ。無愛想な男が指揮をとる。
姫《・》に被害がいかないようにするためだろう。都合のいいことに、兵たちは外まで出てきてくれた。
「わざわざ出てきてくれて助かった。おかげでこっちを使えるよ」
エウフェミアが背にしていた武器《ジャーハ》に持ち替えた。矢をはめ、引き金に指をかけた。
黒い矢が王国兵の太ももに突き刺さる。
「くそ、女が、戦場にいる、だと?」
王国兵に女性兵はいないと聞いた。だからこその言葉だろう。エウフェミアが軽蔑の目で王国兵を見やる。
「男だから強い、女だから弱いと思っているなら赤子からやり直しな」
「チッ、舐めやがって」
「どっちが」
王国兵が体勢を立て直す前に次の矢が肩に刺さった。
ディーとファジュルも応戦する。
まわりを見ると何故かサーディクがいない。スラムでの戦いを経験しているのだから、今更逃げるなんてことしない、はず。
ディーと剣を交えていた傭兵が、ディーの後方で戦っているエウフェミアを睨む。
「おいエウフェミア。なんでお前、そっち側にいるんだ!」
「王子に雇われたからだよ」
エウフェミアが事前に言っていたとおり、相手の傭兵は顔見知りらしい。メインの活動地が異なるだけ。同業と親交があるのは、ディーの旅一座でもよくある。
「スハイル領の奴らはそっちにつくのかい?」
「金をもらったからな。金で動くのが傭兵ってもんだろ、エウフェミア。王国側につけば、反乱軍の倍額出してもらえると思うぜ」
「あいにく、あたしの報酬は金じゃない。この人が国王になったら、流民にも国籍を与えてくれると約束してくれたから」
帰る場所を持たない流民にとって、籍はこの国に帰ってきていいという標《しるべ》。
「ふん、傭兵すべてが国籍を望むと思ったら大間違いだ。俺は金さえ貰えれば何でもいい」
傭兵でも、全員が帰る場所を望むわけではないと、男は笑う。
「ならアンタはボクたちの敵だね。バイバイおじさん」
説得して味方になり得るならと手加減していたけれど、味方にならないなら障害物でしかない。
エウフェミアと会話する方に意識が集中している男は隙だらけだった。
ディーは剣の柄を振り上げ、傭兵の顎を打ち付ける。
傭兵がのけぞったところに追撃、胸にナイフを突き立てる。
これまで旅暮らしをしてきて、狩りで獣を殺して食べることはいくらでもあった。
けれどやはり、獣を殺すのと人を殺めるのではわけが違う。
ためらい、すきができれば自分の命が危ない。
自分に言い聞かせて、ディーはナイフを押し込めた。
「残り六人。油断するな、ディー」
顔を上げると、ファジュルとエウフェミアが連携して傭兵一人を沈めたところだった。
あの司令塔の男と王国兵二人、傭兵三人。
「不意打ちだったとはいえ、たった三人でよくもここまで……」
敵の司令塔が賞賛してくれる。
「サーディクはどこに行ったの」
「さあな。臆病風に吹かれたわけではないと思う」
訝しむエウフェミアと、肩をすくめるファジュル。思い返ば洞穴に突入するときからいなかったような。
用を足しにいったとかそんなところじゃないかと推測する。
「へへん。あんたら、のんきに戦っている場合じゃないと思うぜ」
サーディクが、ジャーハを手にして現れた。来るときはそんなもの持っていなかったのに。
矢をつがえてあるジャーハの照準を、司令塔の男に合わせる。
「貴様も反乱軍か? 戦っている場合じゃない、とはどういう意味だ」
「そのままの意味だって~」
顎だけ動かして、とある方向を指し示す。
ディーもつられてそちらを見た。
黒煙が上がっている。岩場だらけのこの場所に、燃えるのなんて…………。
「た、大変だ!! 積荷が!!」
王国兵と傭兵は、一気に青ざめた。
全員武器を収め、燃え盛る荷車に戻っていく。
「さ、今のうちに逃げよーぜ、みんな」
「お前、積荷を燃やしたのか」
「それだけじゃねーぜ。ラクダを始末して、ジャーハと、こいつをちょろまかしてきたんだ」
サーディクが腰に結んでいた革袋から複数の小瓶を取り出してみせる。瓶のラベルには毒の名前が書かれている。
「瓶のたぐいはこれで全部だ。毒は瓶に入ってるって先生が言ってたからよ。これを盗って、ついでに積んであった着火剤でボンと。ファジュル、もう盗むなって言ってたけど……これは窃盗の数に入らないよな?」
「そうだな。先に毒を奪うなんて、俺じゃ考え付きもしなかった。助かったよ、サーディク」
ファジュルが眉尻を下げて笑う。サーディクはなんだか得意げだ。
王国軍は荷車を引くラクダがいなくなり、積荷は燃え、しばらくは動けまい。消火に使う道具もろくにないのだから。
ディーたちは急いで洞穴にいる仲間のところに戻った。
「ディー、よかった、きてくれて、よかったぁうぁあぁん!」
「ちょ、イーリス! 濡れるよ」
洞穴に入った途端、イーリスが泣きながらディーにしがみついてきた。
ディーよりも二つ年上なのに、迷子になった幼児のように泣きじゃくる。
ディーは全身ずぶ濡れだから、抱きつくイーリスの服にも雨水が浸透している。それに、イーリスの胸は年頃の少女の中でもかなり豊かだ。抱きつかれれば否応なく当たる。
そのことが妙に気恥ずかしくて、ディーは慌てた。
「無事でよかった、ルゥ」
「うん。イーリスさんが守ってくれたから。ファジュルも、無事でよかった」
ファジュルが、十年ぶりの再会かってくらいの勢いでルゥルアを抱きしめている。そのことにツッコミをいれるとディーのほうが恥ずかしい思いをすると学習しているため、口に出さない。
存分にルゥルアを抱きしめたあと、ファジュルは地に膝をついてユーニスと目線を合わせる。
「ユーニスも、怖い目に遭ったな。来るのが遅くなってすまなかった」
「大丈夫だよ兄ちゃん。おれ、怖くなかったもん!」
「そうか。ユーニスは強いな」
「へへへっ」
大丈夫なんて言ってるけれど、ユーニスの足はガクガク震えている。ファジュルはユーニスの肩に手を乗せ、つとめて落ち着いた口調で話す。
「ユーニス、みんなも聞いてくれ。あいつらがまた来たら厄介だ。この隙に拠点を放棄して逃げよう」
敵に見つかった以上、もう隠れ家としての価値はない。
全員、身一つで荒野に飛び出した。
ファジュルがルゥルアの手を引いて歩き、ラシードとナジャーがユーニスの手を取る。
イーリスは黙リこくってディーの服の裾を摘んでいる。
ずっと摘まれていると変なシワになりそう、なんて頭の片隅で思うけれど、イーリスの好きにさせておくことにした。たぶん襲撃を受けて不安でいっぱいだったから、藁《わら》にもすがる、ってやつだ。
イーリスの気が済むまで藁でいよう。
エウフェミアとサーディクは、追っ手警戒のため最後尾にいる。
黙々と歩き続け、岩場を抜け荒野に出た。
視界にスラム居住地区が入り、誰からともなく安堵の息がもれる。
「ふへー、安心したらボクお腹空いちゃったよ」
「オレもー。ナジャー、ついたらなんか作ってくれよ」
「わかりました。腕によりをかけますね」
「じゃあおれ、ばあちゃんの手伝いするー!」
ユーニスがスラムの拠点目指して走り出す。
「ユーニス。足場が悪いから、走ると危ないよ」
「心配しすぎだよねーちゃん。だいじょーー、あわわっ!」
ルゥルアが声をかけたが間に合わず、ユーニスは全身泥だらけになった。
0
お気に入りに追加
49
あなたにおすすめの小説

レヴァイアタン国興亡記 ゲーム・オブ・セイクリッドソーズ 奴隷の勇者か、勇者の奴隷か
Ann Noraaile
ファンタジー
レヴァイアタン国に散らばった7本の聖剣は誰の手に渡り、いかなる奇蹟を起こすのか?
そして善と悪の竜の思惑は聖剣の行方にどうかかわって行くのか?
この物語は、脅威の先住知的生命体が住む惑星上で孤立するレヴァイアタン国に、ヒューマンスードとして生まれた一人の奴隷少年のある決断と冒険から始まった。剣と魔法と勇者の逆進化世界に繰り広げられる、一大サーガの幕開けである。
【世界設定】 遠い過去、経済・自然・政治・戦争危機と、あらゆる点で飽和点に達した人類は、Ωシャッフルと呼ばれる最大級のバイオハザードと大地殻変動を同時に向かえ破滅寸前だった。 この時、グレーテルと呼ばれる新知性が、偶然にも地球に破損漂着した宇宙特異点ゲートを修理することに成功し、数%の人間達を深宇宙のある惑星に転移させた。
しかしグレーテルは転移先惑星のテラホーミングに失敗し、辛うじて人間が生息できるスポットへ彼らを分散させる事になった。レヴァイアタンはそんな分散先に作られた国の一つだった。

御機嫌ようそしてさようなら ~王太子妃の選んだ最悪の結末
Hinaki
恋愛
令嬢の名はエリザベス。
生まれた瞬間より両親達が創る公爵邸と言う名の箱庭の中で生きていた。
全てがその箱庭の中でなされ、そして彼女は箱庭より外へは出される事はなかった。
ただ一つ月に一度彼女を訪ねる5歳年上の少年を除いては……。
時は流れエリザベスが15歳の乙女へと成長し未来の王太子妃として半年後の結婚を控えたある日に彼女を包み込んでいた世界は崩壊していく。
ゆるふわ設定の短編です。
完結済みなので予約投稿しています。

カオスの遺子
浜口耕平
ファンタジー
魔神カオスが生みだした魔物と人間が長い間争っている世界で白髪の少年ロードは義兄のリードと共に人里離れた廃村で仲良く幸せに暮らしていた。
だが、ロードが森で出会った友人と游んでいると、魔物に友人が殺されてしまった。
ロードは襲いかかる魔物との死闘でなんとか魔物を倒すことができた。
しかし、友人の死体を前に、友人を守れなかったことに後悔していると、そこにリードが現れ、魔物から人々を守る組織・魔法軍について聞かされたロードは、人々を魔物の脅威から守るため、入隊試験を受けるためリードと共に王都へと向かう。
兵士となったロードは人々を魔物の脅威から守れるのか?
これは、ロードが仲間と共に世界を守る物語である!
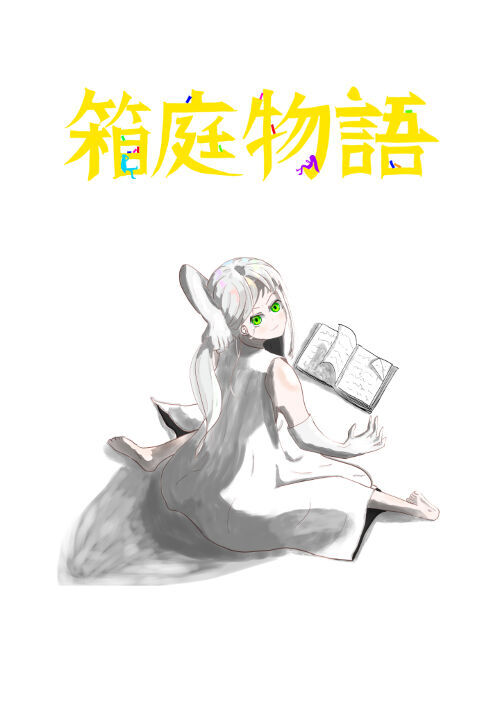
箱庭物語
晴羽照尊
ファンタジー
※本作は他の小説投稿サイト様でも公開しております。
※エンディングまでだいたいのストーリーは出来上がっておりますので、問題なく更新していけるはずです。予定では400話弱、150万文字程度で完結となります。(参考までに)
※この物語には実在の地名や人名、建造物などが登場しますが、一部現実にそぐわない場合がございます。それらは作者の創作であり、実在のそれらとは関わりありません。
※2020年3月21日、カクヨム様にて連載開始。
あらすじ
2020年。世界には776冊の『異本』と呼ばれる特別な本があった。それは、読む者に作用し、在る場所に異変をもたらし、世界を揺るがすほどのものさえ存在した。
その『異本』を全て集めることを目的とする男がいた。男はその蒐集の途中、一人の少女と出会う。少女が『異本』の一冊を持っていたからだ。
だが、突然の襲撃で少女の持つ『異本』は焼失してしまう。
男は集めるべき『異本』の消失に落胆するが、失われた『異本』は少女の中に遺っていると知る。
こうして男と少女は出会い、ともに旅をすることになった。
これは、世界中を旅して、『異本』を集め、誰かへ捧げる物語だ。

☆レグルス戦記☆
naturalsoft
ファンタジー
僕は気付くと記憶を失っていた。
名前以外思い出せない僕の目の前に、美しい女神様が現れた。
「私は神の一柱、【ミネルヴァ】と言います。現在、邪神により世界が混沌しています。勇者レグルスよ。邪神の力となっている大陸の戦争を止めて邪神の野望を打ち砕いて下さい」
こうして僕は【神剣ダインスレイヴ】を渡され戦禍へと身を投じて行くことになる。
「私もお前の横に並んで戦うわ。一緒に夢を叶えましょう!絶対に死なせないから」
そして、戦友となるジャンヌ・ダルクと出逢い、肩を並べて戦うのだった。
テーマは【王道】戦記
※地図は専用ソフトを使い自作です。
※一部の挿絵は有料版のイラストを使わせて頂いております。
(レグルスとジャンヌは作者が作ったオリジナルです)
素材提供
『背景素材屋さんみにくる』
『ふわふわにゃんこ』
『森の奥の隠れ里』

【R18】もう一度セックスに溺れて
ちゅー
恋愛
--------------------------------------
「んっ…くっ…♡前よりずっと…ふか、い…」
過分な潤滑液にヌラヌラと光る間口に亀頭が抵抗なく吸い込まれていく。久しぶりに男を受け入れる肉道は最初こそ僅かな狭さを示したものの、愛液にコーティングされ膨張した陰茎を容易く受け入れ、すぐに柔らかな圧力で応えた。
--------------------------------------
結婚して五年目。互いにまだ若い夫婦は、愛情も、情熱も、熱欲も多分に持ち合わせているはずだった。仕事と家事に忙殺され、いつの間にかお互いが生活要員に成り果ててしまった二人の元へ”夫婦性活を豹変させる”と銘打たれた宝石が届く。

蘇生魔法を授かった僕は戦闘不能の前衛(♀)を何度も復活させる
フルーツパフェ
大衆娯楽
転移した異世界で唯一、蘇生魔法を授かった僕。
一緒にパーティーを組めば絶対に死ぬ(死んだままになる)ことがない。
そんな口コミがいつの間にか広まって、同じく異世界転移した同業者(多くは女子)から引っ張りだこに!
寛容な僕は彼女達の申し出に快諾するが条件が一つだけ。
――実は僕、他の戦闘スキルは皆無なんです
そういうわけでパーティーメンバーが前衛に立って死ぬ気で僕を守ることになる。
大丈夫、一度死んでも蘇生魔法で復活させてあげるから。
相互利益はあるはずなのに、どこか鬼畜な匂いがするファンタジー、ここに開幕。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















