1 / 4
ネズミ駆除課
しおりを挟む
王都ミッテシュタットの路地裏を一ぴきのネズミと黒猫が走る。二ひきが通り過ぎると、石だたみのすき間から生えた雑草が揺れた。黒猫の緑色の瞳は、茶色く必死に逃げているネズミをしっかりととらえていた。この先にはネズミの巣穴がある。黒猫はスピードを上げた。ネズミとの距離をつめて、右の前足を思い切り横にふる。黒猫のパンチは見事にネズミに当たり、真横にあった壁までふっ飛んだ。ネズミはよろけながら体勢を立て直そうとしたが、そのすきに黒猫はネズミの体を押さえつけた。ネズミはジタバタしたが、黒猫は口にくわえると道の端に寄って、ネズミを食べ始めた。
黒猫はネズミを一匹食べ終わると、次のネズミをねらうために別の場所に移動した。
ネズミを見つけ、狩り、食べる。たとえ人間が黒猫の好物である、生の牛肉をくれても、それは変わらなかった。いつ食べられなくなるかわからない。その危機感だけは常にあった。
またネズミを見つける。黒猫は足音を立てずに近づいた。黒猫に気がついたネズミは、あわててにげ出した。しかし黒猫のほうが少し速く、あっという間にネズミをつかまえた。
「いやあ、すごいっ。立派な狩人だ」
背後から人間の声がして、黒猫はネズミをくわえたままふり返った。そこには黒猫から見てもわかるくらい清潔感があって、パリッとした服を着ている。
「ねえ、黒猫さん。ちょっとお時間いいですか? お話したいんですけれども」
黒猫はくわえていたネズミを一度地面に置き、人間に言った。
「悪いけれど、これから食事でいそがしいんだ。じゃあね」
しかしそんな風に言っても、人間には言葉は通じないことを黒猫は思い出した。ネズミをくわえ直し、人間に背をむけた。すると人間は黒猫にさらに話しかけてきた。
「ああ、どう、どうか話だけでも聞いてっ。きみのその狩りのうでを見こんでのことなんだ。そのネズミを食べながらでいいから」
黒猫は少し考えた。この辺りに住んでいる人間の多くは、猫にやさしい。おそらくネズミを食べるからだ、と野良猫仲間と話したことがある。
(まあおれたちのほうが足速いし、きょりをとってならいいか。ほめてくれたし)
黒猫はその場でネズミを食べながら、人間の話を聞くことにした。黒猫がその場で食事をはじめると、人間は話しはじめた。
「まずはぼくのことから簡単に。ぼくは王城のネズミ駆除課のパル。実はきみに王城のネズミを駆除する仕事に就いてほしいんだ」
「は? 王城って聖樹ミッテの手前にやつ?」
黒猫は食事をとめて、人間に思わず尋ねた。
母なる木、聖樹ミッテ。聖樹ミッテから精霊が生まれたおかげで、人間は魔法を使えるようになったという言い伝えがある。あまりにも大きいため聖樹ミッテの頂上を見たものはいないと言われており、根は世界の底まであるといううわさだ。その聖樹ミッテの前にあるのが、王族が暮らしている城。これらはどんな猫でも知っていることだ。言葉は通じていないが、黒猫の驚きは伝わったらしく、人間は「聖樹ミッテの手前にあるやつだよ」と言った。
「ぼくら人間にとってネズミってとっても困る存在なんだ。食べ物だけじゃなくって、なんでもかじっちまう。魔法のつえなんてかじられた日には、魔法が使えなくなってしまう」
(ふーん、人間が木の棒を持っているのはそのためだったのか)
ネズミを食べ終えた黒猫は、手や顔をなめながら納得した。
「王城のあちこちやつえをかじられないために、王城ではネズミ駆除課っていう部署があるんだ。きみにそこで働いてほしい。仕事は簡単、ネズミを狩ってもらいたい。温かい寝床はもちろん、きちんと食事もつく。どうだい? 君の好物も用意するよ」
「温かい寝床と牛肉……」
黒猫は想像した。柔らかい床とふかふかの毛布で横になり、生の牛肉を満足するまで食べる。
(毎日がそうならなんて幸せなんだろう!)
黒猫は想像するだけでわくわくした。すると急に目の前の人間、パルの言うネズミ駆除課の仕事というものが、みりょく的に思えてきた。
「と、いうわけできみの返事を聞きたいんだけれど、これをつけさせてくれないかな?」
そう言ってパルがふところからとり出したのは、きれいなガラス玉がついた緑色のリボンだった。
「これはきみたちの言葉がわかる魔法がかかっているんだ。もしよかったら、これをつけさせてくれないかい?」
「うん、いいよ」
黒猫はパルに近づいて、彼の前で座った。パルは手慣れた様子で黒猫の首にガラス玉のついたリボンをつけた。
(まるで飼い猫になったみたいだ)
黒猫はそんな風に思った。
「なにか気になることとか、聞きたいこととかあるかい?」
パルは言った。黒猫は思いきって尋ねることにした。
「好きなものって牛肉でもいいの?」
「お、ちゃんと動いてるな。もちろん、牛肉でもいいよ。まあ、高級な脂がたくさんのったものって言われたらちょっと困るけど……」
黒猫の心は決まった。
「いいよ。牛肉毎日食べられるなら、ネズミ捕る」
「本当っ? よかったー、断られたらどうしようかと思ってたんだ。いやあ、実はきみで五ひき目で……。きみさえよかったら、このまま王城に向かおうかと思うけれど、大丈夫かい?」
「いや、肉屋の主人にだけあいさつがしたいんだ。これつけたままでも大丈夫?」
肉屋の主人とおかみさんは、黒猫によく牛肉の切れ端をくれた。「ほら、好きだろう?」と笑顔を浮かべて、牛肉を食べる黒猫をよくなでてくれた。
「いいよ。一緒についていっていいかい?」
「うん。いいよ」
黒猫はパルを連れて、いつものように肉屋の裏手に回り、大きく声を出した。
「おかみさーん」
しばらくして出てきたのは、エプロンをつけたふくよかな女性だった。
「はーい、どちらさま?」
おかみさんはパルを見て「あなたが?」と尋ねた。パルは首を横にふって、黒猫を指した。
「おかみさん、おれだよ。いつも牛肉ありがとう」
「まあ、あんたしゃべれるようになったの?」
「なんかこの首につけてるやつが、話できるようにしてるんだって。おかみさん、おれ、王城に行くんだ。ネズミ駆除課に入ることにした」
「まあ、あんた王城で働くのかい? じゃあお別れなんだねえ。さみしくなるよ」
「うん、おかみさん。今までありがとう。主人さんにもよろしく言っておいて」
黒猫はおかみさんの足元に頭をこすりつけた。おかみさんは黒猫の頭をなでた。
「元気でやるんだよ」
「うん。じゃあね」
黒猫はパルのほうを見た。パルはおかみさんに頭を下げていた。
「お待たせ。もういいよ」
「それじゃあ行こうか、王城へ」
黒猫はパルと並んで王城へ向かった。
王城は路地裏の道よりも広かった。床はふかふかしていて、かたい地面しか知らない黒猫にとっては違和感のほうが大きかった。パルは入ってすぐ右に曲がった。右側には部屋が二つあり、左側には細いろうかが一本、その先には広そうな部屋があった。パルは曲がり角の手前にある、右側のドアを開けた。するとそこには複数の猫のにおいがしていた。かぎわけてみると、その数は四匹だった。
入って右側には一匹ずつ乗れるような場所があるタワーがあり、正面には皿が並んでいる。そこから食べ物のにおいがするので、ここで食事をとっているのがわかった。曲がった先にまだ部屋が続いているようだった。黒猫はおずおずと奥をのぞいた。高く登れるタワーが二つ、五つの箱がかべ側に横一列に並んでいる。そして一番奥には名前もよく知らない、木製の四つ足の台があり……のちにそれは机という名前だと知った……、四角いたて長の箱が三つほど置かれていた。そして人間が二人座っている。
「お、パル。新人かい? いや猫だから新猫か」
「はい、せんぱい。黒猫くん、この人はぼくの仕事のせんぱいで、ハイトさん。で、一番奥にいるのが、このネズミ駆除課で一番えらい人、ライデンさんだよ」
「やあ、黒猫くん。ようこそネズミ駆除課へ。この部屋がきみの家になる。ほかにも猫がいるから、いろいろ教えてもらってね」
パルは丸くて二本のはりがあるもの……これが時計であることもあとで知った……を見た。
「もうすぐほかの猫たちがもどってくるから、ちょっと待っててくれる?」
「わかった」
黒猫はきょろきょろ辺りを見回して、部屋のすみで丸まっておくことにした。
しばらくすると聞き慣れないメロディーが流れた。そのメロディーが流れると、ぞろぞろと猫がやってきた。最初に入ってきたのは黄トラの猫だった。
「お、なんだお前。新猫か?」
「そうだよ。さっききたところなんだ」
黒猫の代わりにパルが答えた。黄トラの猫があいさつとして鼻を近づけてきた。
「おれはフォイア。困ったことがあればなんでも言えよ。おまえ、名前は?」
「ないよ」
「お、そうなのか。なあパル。ほかのやつらがくる前に決めといてやればいいんじゃないか」
フォイアはパルに言った。
「名前、別になくったっていいよ」
「そういうわけにはいかないよ。きみはここの職員になるんだ。きちんと名前が必要だよ」
そう言ってパルはうでを組んで考え始めた。
(別に気にしないのになあ)
そんな風に思っていると、パルが「うん」と一人うなずき黒猫のほうを見て言った。
「きみの名前、ヴィントはどうかな? 風っていう意味だよ。ねずみを追いかけている姿が風のようだったから」
「うん。いいよ、それで」
「じゃあ改めて。よろしくな、ヴィント」
「よろしく、フォイア」
そのときさび猫が入ってきた。少しぽっちゃりしている。あくびをするとその場で伸びをした。さび猫はようやく黒猫いや、ヴィントに気がついたようだった。
「あれえ、見ない顔だあ」
「新猫だとよ」
「わー、そうなんだあ。ぼくエアデっていうんだあ。よろしくねえ」
「ヴィントっていうんだ。よろしく」
ヴィントとエアデはあいさつをした。すると続けてハチワレの猫と灰色の猫が入ってきた。
「ウニ、今日のネズミの捕獲数はいかがでしたか?」
「まあまあよ。ヴァッサ、あなたは?」
「ぼくもです。……おや? もしやそこの黒猫さんは新猫で?」
「たった今名前が決まってよ、ヴィントってんだ」
フォイアが代わりに言った。するとヴァッサと呼ばれた灰色の猫は「そうなのですね」とあいづちを打つと、ヴィントにあいさつをしにきた。
「ヴァッサです。どうぞよろしく」
「わたしはウニよ。よろしくね」
ハチワレの猫、ウニもあいさつをしにきた。ヴィントは二ひきと鼻を近づける。
「んでパル、ヴィントはいつから仕事するんだ?」
フォイアが尋ねた。するとパルはうでを組んで考えながら答えた。
「まあここに慣れるのが先かなあ。仕事はそれから」
「なるほど。ヴィント、いつでもおれをたよれよ」
フォイアがそう言うと、ヴァッサがあいだに入ってきた。
「別に彼だけじゃなくっていいんですよ、ぼくでもかまいませんからね」
フォイアとヴァッサはにらみ合った。ヴィントの横からウニがしっぽでせなかをつついてきた。
「あの二ひき、よくけんがするのよ。気にしないで」
「なるほど」
「ちなみにそこで丸くなってるさび猫のエアデと、わたしは姉弟よ」
「えっ」
ヴィントは思わずウニとエアデを見比べた。細い目にぽっちゃりした体のエアデに、すらりとしてくりっとした目のウニ。言われなければ姉弟だとはわからないだろう。
「あの子、すごく食いしんぼうなの」
「へえ」
フォイアとヴァッサはまだにらみ合っていた。するともう一人の人間、ハイトがなにか持ってきた。
「みんなー、ごはんだよー」
ハイトのその言葉を聞くと、フォイアとヴァッサはにらみ合いをやめて自分の皿の前にむかった。ハイトは持っていた皿をエアデの皿のとなりに置くと、抱えていた袋の中身を皿に移していた。
「ヴィント、きみもこっちにきてごはん食べな。きみ専用のお皿は明日には用意しておくから、今日はこの皿でがまんしておくれ」
「うん。ありがとう」
ヴィントは皿の中を見た。それは町の人がくれるカリカリのごはんだった。
「牛肉も明日から追加するね」
そう言ったのはパルだった。ヴィントはうなずいた。見てみると、カリカリはほかの四ひきと同じだが、その上にそれぞれの好物らしきものがのっていた。
食事を終えるころになると、三人の人間はがさごそとなにやら動きはじめた。そして「お先です」とパルとハイトが言った。そして一ぴきずつ頭をなでていく。パルがヴィントの頭をなでた。大きな手にヴィントの頭がすっぽり収まった。
「じゃあね、ヴィント。また明日ね」
「どこに行くの?」
「ぼくらは自分の家に帰るんだよ」
「また明日くるよ」
そう言いながらハイトもヴィントの頭をなでた。そして最後にネズミ駆除課で一番えらいという、ライデンも「それじゃあね」と言って帰って行った。
猫たちはそれぞれ自由に過ごし始めた。ヴィントは改めて部屋を見て回ることにした。路上暮らしでは見たことがないものがたくさんあった。三人の人間がいたところには背の高い箱……たなというらしい……がいくつもある。試しに中を見てみようと思ったが開け方がわからないのでやめた。かべ際には五つの箱が横一列にならんでいる。そこからはネズミのにおいがした。
「そこにとったネズミを置くんだ。するとどういう魔法かは知らないが、いつの間にか消えておれたちが捕まえたネズミの数が、ライデンにわかるらしい。捕まえたネズミはどこに行っているのかはわからないけどな」
近づいてきたフォイアが説明してくれた。
「そういえばネズミをたくさんとったら、なにかあるの?」
ふと疑問に思ったことをヴィントは尋ねた。するとフォイアはねる場所を見ながら教えてくれた。
「一週間でネズミをたくさんとったやつから順番に、ねる場所を決められるんだ。ちなみに一番気持ちいいのは上から二番目。一番上はちと高いんだよな。それから、めしの上にのってる好物がちょっと増える。一日だけだけど」
「ねるところ、ちょっと感触確かめてもいい?」
一番いい、という場所のことが少し気になったヴィントがそう尋ねると、フォイアは少し考えてから答えた。
「ま、おれのねどこだったらいいぜ」
「ちなみにどこ?」
「上から二番目」
「気持ちいいって話してたところじゃないか」
「へへん」
フォイアは「まあ上がれよ」と言って登らせてくれた。たしかに落ち着く高さで、ねどこもふかふかだ。ここでねられたら、たしかに心地いいだろう。
「これはいいね」
「だろ。なんかこう、いいだろ?」
「うん」
そんな風に二ひきが話していると、ヴァッサがフォイアに言った。
「今週は負けましたが、来週はぼくがそこにねますからね」
「ヴァッサ、おまえは考えすぎなんだよ。もっと足使っていろんなところ探せばいいのに」
「ぼくはこれまでのことを分析して、ネズミが出やすいところを見張ってるんです。あちこち動き回るなんて体力のむだです」
「なんだとっ。おれのやりかたにケチつけるのかっ」
「そっちが先にケチつけたんでしょうっ」
フォイアとヴァッサはとっくみ合いをはじめてしまった。
「ああなると長いから、ほっといてだいじょうぶだよお」
いつの間にか一番下に腰かけていたエアデが言った。大きくあくびをしている。
「あの二ひきがよくそこをとり合ってるよお」
「エアデは?」
「ぼくは一番下が楽でいいかなあ。いちいち上がるのめんどうくさいし」
そう言うエアデの体は横に広がっていた。
「あんたはもうちょっと動きなさい」
ウニがエアデのひたいをぺちんと軽くたたいた。
「まあわたしは一番上のほうが好きなんだけれどね。好みよ、好み」
「ぼくは今日どこでねればいいかな?」
ヴィントはウニとエアデに尋ねた。するとウニが答えた。
「下から二番目が空いてるから、そこでねたら? もうねるの?」
「いや、もうちょっと起きとく。ここの出入りっていつまでしていいの?」
「とくに決まってないよお。だから真夜中にネズミとりに行ってもいいんだよお。ぼくはゆっくりするけどねえ」
「わたしはネズミを捕りにじゃなくって、散歩に出かけるわよ」
「へえ、思ったより自由なんだね。よかった」
ヴィントはこれから自由な時間などなくなるのだと思っていたので、ほっとした。するととっくみ合いをしていたフォイアが、いつの間にか毛づくろいをしながら提案した。
「じゃあこの城の中、見て回ってみるか? どうせ明日案内されるだろうけれど」
「フォイア、ヴィントだって今日は疲れているでしょう。明日でいいんじゃないんですか」
ヴァッサが口をはさんできた。
「ぼく、疲れてないよ」
ヴィントがそう言うとヴァッサは首を横にふった。
「これまでずっと外で暮らしていたんでしょう。きっと意識していないだけで、疲れていますよ。ぼくだってそうでしたから。今日はゆっくりしたほうがいいですよ」
ヴィントはそう言われてもいまいちピンとこなかった。ヴィントの表情を見たヴァッサは、
「まあ、元気があるならあのタワーで遊んだらいいんじゃないですか?」
「タワーって、あのいろいろついているやつ?」
そのタワーはちょうどヴィントたちが通れるような穴が開いていたり、小さなかごがいくつもついていたりしていて、確かにそこで遊ぶのは楽しそうに思えた。
「ええ。あそこはぼくらが遊んでいい場所なので、好きにしたらいいですよ」
「そうなんだ。ありがとう。遊んでみる」
ヴィントは早速部屋のすみにあるタワーで遊び始めた。高いところにいき、穴をくぐり、降りる。まるで大きな木の中を探検しているような気持ちになった。
ヴィントはへとへとになるまで遊ぶと、ウニが言っていたねどこで眠ることにした。ヴィントは夢を見ることなく眠った。
黒猫はネズミを一匹食べ終わると、次のネズミをねらうために別の場所に移動した。
ネズミを見つけ、狩り、食べる。たとえ人間が黒猫の好物である、生の牛肉をくれても、それは変わらなかった。いつ食べられなくなるかわからない。その危機感だけは常にあった。
またネズミを見つける。黒猫は足音を立てずに近づいた。黒猫に気がついたネズミは、あわててにげ出した。しかし黒猫のほうが少し速く、あっという間にネズミをつかまえた。
「いやあ、すごいっ。立派な狩人だ」
背後から人間の声がして、黒猫はネズミをくわえたままふり返った。そこには黒猫から見てもわかるくらい清潔感があって、パリッとした服を着ている。
「ねえ、黒猫さん。ちょっとお時間いいですか? お話したいんですけれども」
黒猫はくわえていたネズミを一度地面に置き、人間に言った。
「悪いけれど、これから食事でいそがしいんだ。じゃあね」
しかしそんな風に言っても、人間には言葉は通じないことを黒猫は思い出した。ネズミをくわえ直し、人間に背をむけた。すると人間は黒猫にさらに話しかけてきた。
「ああ、どう、どうか話だけでも聞いてっ。きみのその狩りのうでを見こんでのことなんだ。そのネズミを食べながらでいいから」
黒猫は少し考えた。この辺りに住んでいる人間の多くは、猫にやさしい。おそらくネズミを食べるからだ、と野良猫仲間と話したことがある。
(まあおれたちのほうが足速いし、きょりをとってならいいか。ほめてくれたし)
黒猫はその場でネズミを食べながら、人間の話を聞くことにした。黒猫がその場で食事をはじめると、人間は話しはじめた。
「まずはぼくのことから簡単に。ぼくは王城のネズミ駆除課のパル。実はきみに王城のネズミを駆除する仕事に就いてほしいんだ」
「は? 王城って聖樹ミッテの手前にやつ?」
黒猫は食事をとめて、人間に思わず尋ねた。
母なる木、聖樹ミッテ。聖樹ミッテから精霊が生まれたおかげで、人間は魔法を使えるようになったという言い伝えがある。あまりにも大きいため聖樹ミッテの頂上を見たものはいないと言われており、根は世界の底まであるといううわさだ。その聖樹ミッテの前にあるのが、王族が暮らしている城。これらはどんな猫でも知っていることだ。言葉は通じていないが、黒猫の驚きは伝わったらしく、人間は「聖樹ミッテの手前にあるやつだよ」と言った。
「ぼくら人間にとってネズミってとっても困る存在なんだ。食べ物だけじゃなくって、なんでもかじっちまう。魔法のつえなんてかじられた日には、魔法が使えなくなってしまう」
(ふーん、人間が木の棒を持っているのはそのためだったのか)
ネズミを食べ終えた黒猫は、手や顔をなめながら納得した。
「王城のあちこちやつえをかじられないために、王城ではネズミ駆除課っていう部署があるんだ。きみにそこで働いてほしい。仕事は簡単、ネズミを狩ってもらいたい。温かい寝床はもちろん、きちんと食事もつく。どうだい? 君の好物も用意するよ」
「温かい寝床と牛肉……」
黒猫は想像した。柔らかい床とふかふかの毛布で横になり、生の牛肉を満足するまで食べる。
(毎日がそうならなんて幸せなんだろう!)
黒猫は想像するだけでわくわくした。すると急に目の前の人間、パルの言うネズミ駆除課の仕事というものが、みりょく的に思えてきた。
「と、いうわけできみの返事を聞きたいんだけれど、これをつけさせてくれないかな?」
そう言ってパルがふところからとり出したのは、きれいなガラス玉がついた緑色のリボンだった。
「これはきみたちの言葉がわかる魔法がかかっているんだ。もしよかったら、これをつけさせてくれないかい?」
「うん、いいよ」
黒猫はパルに近づいて、彼の前で座った。パルは手慣れた様子で黒猫の首にガラス玉のついたリボンをつけた。
(まるで飼い猫になったみたいだ)
黒猫はそんな風に思った。
「なにか気になることとか、聞きたいこととかあるかい?」
パルは言った。黒猫は思いきって尋ねることにした。
「好きなものって牛肉でもいいの?」
「お、ちゃんと動いてるな。もちろん、牛肉でもいいよ。まあ、高級な脂がたくさんのったものって言われたらちょっと困るけど……」
黒猫の心は決まった。
「いいよ。牛肉毎日食べられるなら、ネズミ捕る」
「本当っ? よかったー、断られたらどうしようかと思ってたんだ。いやあ、実はきみで五ひき目で……。きみさえよかったら、このまま王城に向かおうかと思うけれど、大丈夫かい?」
「いや、肉屋の主人にだけあいさつがしたいんだ。これつけたままでも大丈夫?」
肉屋の主人とおかみさんは、黒猫によく牛肉の切れ端をくれた。「ほら、好きだろう?」と笑顔を浮かべて、牛肉を食べる黒猫をよくなでてくれた。
「いいよ。一緒についていっていいかい?」
「うん。いいよ」
黒猫はパルを連れて、いつものように肉屋の裏手に回り、大きく声を出した。
「おかみさーん」
しばらくして出てきたのは、エプロンをつけたふくよかな女性だった。
「はーい、どちらさま?」
おかみさんはパルを見て「あなたが?」と尋ねた。パルは首を横にふって、黒猫を指した。
「おかみさん、おれだよ。いつも牛肉ありがとう」
「まあ、あんたしゃべれるようになったの?」
「なんかこの首につけてるやつが、話できるようにしてるんだって。おかみさん、おれ、王城に行くんだ。ネズミ駆除課に入ることにした」
「まあ、あんた王城で働くのかい? じゃあお別れなんだねえ。さみしくなるよ」
「うん、おかみさん。今までありがとう。主人さんにもよろしく言っておいて」
黒猫はおかみさんの足元に頭をこすりつけた。おかみさんは黒猫の頭をなでた。
「元気でやるんだよ」
「うん。じゃあね」
黒猫はパルのほうを見た。パルはおかみさんに頭を下げていた。
「お待たせ。もういいよ」
「それじゃあ行こうか、王城へ」
黒猫はパルと並んで王城へ向かった。
王城は路地裏の道よりも広かった。床はふかふかしていて、かたい地面しか知らない黒猫にとっては違和感のほうが大きかった。パルは入ってすぐ右に曲がった。右側には部屋が二つあり、左側には細いろうかが一本、その先には広そうな部屋があった。パルは曲がり角の手前にある、右側のドアを開けた。するとそこには複数の猫のにおいがしていた。かぎわけてみると、その数は四匹だった。
入って右側には一匹ずつ乗れるような場所があるタワーがあり、正面には皿が並んでいる。そこから食べ物のにおいがするので、ここで食事をとっているのがわかった。曲がった先にまだ部屋が続いているようだった。黒猫はおずおずと奥をのぞいた。高く登れるタワーが二つ、五つの箱がかべ側に横一列に並んでいる。そして一番奥には名前もよく知らない、木製の四つ足の台があり……のちにそれは机という名前だと知った……、四角いたて長の箱が三つほど置かれていた。そして人間が二人座っている。
「お、パル。新人かい? いや猫だから新猫か」
「はい、せんぱい。黒猫くん、この人はぼくの仕事のせんぱいで、ハイトさん。で、一番奥にいるのが、このネズミ駆除課で一番えらい人、ライデンさんだよ」
「やあ、黒猫くん。ようこそネズミ駆除課へ。この部屋がきみの家になる。ほかにも猫がいるから、いろいろ教えてもらってね」
パルは丸くて二本のはりがあるもの……これが時計であることもあとで知った……を見た。
「もうすぐほかの猫たちがもどってくるから、ちょっと待っててくれる?」
「わかった」
黒猫はきょろきょろ辺りを見回して、部屋のすみで丸まっておくことにした。
しばらくすると聞き慣れないメロディーが流れた。そのメロディーが流れると、ぞろぞろと猫がやってきた。最初に入ってきたのは黄トラの猫だった。
「お、なんだお前。新猫か?」
「そうだよ。さっききたところなんだ」
黒猫の代わりにパルが答えた。黄トラの猫があいさつとして鼻を近づけてきた。
「おれはフォイア。困ったことがあればなんでも言えよ。おまえ、名前は?」
「ないよ」
「お、そうなのか。なあパル。ほかのやつらがくる前に決めといてやればいいんじゃないか」
フォイアはパルに言った。
「名前、別になくったっていいよ」
「そういうわけにはいかないよ。きみはここの職員になるんだ。きちんと名前が必要だよ」
そう言ってパルはうでを組んで考え始めた。
(別に気にしないのになあ)
そんな風に思っていると、パルが「うん」と一人うなずき黒猫のほうを見て言った。
「きみの名前、ヴィントはどうかな? 風っていう意味だよ。ねずみを追いかけている姿が風のようだったから」
「うん。いいよ、それで」
「じゃあ改めて。よろしくな、ヴィント」
「よろしく、フォイア」
そのときさび猫が入ってきた。少しぽっちゃりしている。あくびをするとその場で伸びをした。さび猫はようやく黒猫いや、ヴィントに気がついたようだった。
「あれえ、見ない顔だあ」
「新猫だとよ」
「わー、そうなんだあ。ぼくエアデっていうんだあ。よろしくねえ」
「ヴィントっていうんだ。よろしく」
ヴィントとエアデはあいさつをした。すると続けてハチワレの猫と灰色の猫が入ってきた。
「ウニ、今日のネズミの捕獲数はいかがでしたか?」
「まあまあよ。ヴァッサ、あなたは?」
「ぼくもです。……おや? もしやそこの黒猫さんは新猫で?」
「たった今名前が決まってよ、ヴィントってんだ」
フォイアが代わりに言った。するとヴァッサと呼ばれた灰色の猫は「そうなのですね」とあいづちを打つと、ヴィントにあいさつをしにきた。
「ヴァッサです。どうぞよろしく」
「わたしはウニよ。よろしくね」
ハチワレの猫、ウニもあいさつをしにきた。ヴィントは二ひきと鼻を近づける。
「んでパル、ヴィントはいつから仕事するんだ?」
フォイアが尋ねた。するとパルはうでを組んで考えながら答えた。
「まあここに慣れるのが先かなあ。仕事はそれから」
「なるほど。ヴィント、いつでもおれをたよれよ」
フォイアがそう言うと、ヴァッサがあいだに入ってきた。
「別に彼だけじゃなくっていいんですよ、ぼくでもかまいませんからね」
フォイアとヴァッサはにらみ合った。ヴィントの横からウニがしっぽでせなかをつついてきた。
「あの二ひき、よくけんがするのよ。気にしないで」
「なるほど」
「ちなみにそこで丸くなってるさび猫のエアデと、わたしは姉弟よ」
「えっ」
ヴィントは思わずウニとエアデを見比べた。細い目にぽっちゃりした体のエアデに、すらりとしてくりっとした目のウニ。言われなければ姉弟だとはわからないだろう。
「あの子、すごく食いしんぼうなの」
「へえ」
フォイアとヴァッサはまだにらみ合っていた。するともう一人の人間、ハイトがなにか持ってきた。
「みんなー、ごはんだよー」
ハイトのその言葉を聞くと、フォイアとヴァッサはにらみ合いをやめて自分の皿の前にむかった。ハイトは持っていた皿をエアデの皿のとなりに置くと、抱えていた袋の中身を皿に移していた。
「ヴィント、きみもこっちにきてごはん食べな。きみ専用のお皿は明日には用意しておくから、今日はこの皿でがまんしておくれ」
「うん。ありがとう」
ヴィントは皿の中を見た。それは町の人がくれるカリカリのごはんだった。
「牛肉も明日から追加するね」
そう言ったのはパルだった。ヴィントはうなずいた。見てみると、カリカリはほかの四ひきと同じだが、その上にそれぞれの好物らしきものがのっていた。
食事を終えるころになると、三人の人間はがさごそとなにやら動きはじめた。そして「お先です」とパルとハイトが言った。そして一ぴきずつ頭をなでていく。パルがヴィントの頭をなでた。大きな手にヴィントの頭がすっぽり収まった。
「じゃあね、ヴィント。また明日ね」
「どこに行くの?」
「ぼくらは自分の家に帰るんだよ」
「また明日くるよ」
そう言いながらハイトもヴィントの頭をなでた。そして最後にネズミ駆除課で一番えらいという、ライデンも「それじゃあね」と言って帰って行った。
猫たちはそれぞれ自由に過ごし始めた。ヴィントは改めて部屋を見て回ることにした。路上暮らしでは見たことがないものがたくさんあった。三人の人間がいたところには背の高い箱……たなというらしい……がいくつもある。試しに中を見てみようと思ったが開け方がわからないのでやめた。かべ際には五つの箱が横一列にならんでいる。そこからはネズミのにおいがした。
「そこにとったネズミを置くんだ。するとどういう魔法かは知らないが、いつの間にか消えておれたちが捕まえたネズミの数が、ライデンにわかるらしい。捕まえたネズミはどこに行っているのかはわからないけどな」
近づいてきたフォイアが説明してくれた。
「そういえばネズミをたくさんとったら、なにかあるの?」
ふと疑問に思ったことをヴィントは尋ねた。するとフォイアはねる場所を見ながら教えてくれた。
「一週間でネズミをたくさんとったやつから順番に、ねる場所を決められるんだ。ちなみに一番気持ちいいのは上から二番目。一番上はちと高いんだよな。それから、めしの上にのってる好物がちょっと増える。一日だけだけど」
「ねるところ、ちょっと感触確かめてもいい?」
一番いい、という場所のことが少し気になったヴィントがそう尋ねると、フォイアは少し考えてから答えた。
「ま、おれのねどこだったらいいぜ」
「ちなみにどこ?」
「上から二番目」
「気持ちいいって話してたところじゃないか」
「へへん」
フォイアは「まあ上がれよ」と言って登らせてくれた。たしかに落ち着く高さで、ねどこもふかふかだ。ここでねられたら、たしかに心地いいだろう。
「これはいいね」
「だろ。なんかこう、いいだろ?」
「うん」
そんな風に二ひきが話していると、ヴァッサがフォイアに言った。
「今週は負けましたが、来週はぼくがそこにねますからね」
「ヴァッサ、おまえは考えすぎなんだよ。もっと足使っていろんなところ探せばいいのに」
「ぼくはこれまでのことを分析して、ネズミが出やすいところを見張ってるんです。あちこち動き回るなんて体力のむだです」
「なんだとっ。おれのやりかたにケチつけるのかっ」
「そっちが先にケチつけたんでしょうっ」
フォイアとヴァッサはとっくみ合いをはじめてしまった。
「ああなると長いから、ほっといてだいじょうぶだよお」
いつの間にか一番下に腰かけていたエアデが言った。大きくあくびをしている。
「あの二ひきがよくそこをとり合ってるよお」
「エアデは?」
「ぼくは一番下が楽でいいかなあ。いちいち上がるのめんどうくさいし」
そう言うエアデの体は横に広がっていた。
「あんたはもうちょっと動きなさい」
ウニがエアデのひたいをぺちんと軽くたたいた。
「まあわたしは一番上のほうが好きなんだけれどね。好みよ、好み」
「ぼくは今日どこでねればいいかな?」
ヴィントはウニとエアデに尋ねた。するとウニが答えた。
「下から二番目が空いてるから、そこでねたら? もうねるの?」
「いや、もうちょっと起きとく。ここの出入りっていつまでしていいの?」
「とくに決まってないよお。だから真夜中にネズミとりに行ってもいいんだよお。ぼくはゆっくりするけどねえ」
「わたしはネズミを捕りにじゃなくって、散歩に出かけるわよ」
「へえ、思ったより自由なんだね。よかった」
ヴィントはこれから自由な時間などなくなるのだと思っていたので、ほっとした。するととっくみ合いをしていたフォイアが、いつの間にか毛づくろいをしながら提案した。
「じゃあこの城の中、見て回ってみるか? どうせ明日案内されるだろうけれど」
「フォイア、ヴィントだって今日は疲れているでしょう。明日でいいんじゃないんですか」
ヴァッサが口をはさんできた。
「ぼく、疲れてないよ」
ヴィントがそう言うとヴァッサは首を横にふった。
「これまでずっと外で暮らしていたんでしょう。きっと意識していないだけで、疲れていますよ。ぼくだってそうでしたから。今日はゆっくりしたほうがいいですよ」
ヴィントはそう言われてもいまいちピンとこなかった。ヴィントの表情を見たヴァッサは、
「まあ、元気があるならあのタワーで遊んだらいいんじゃないですか?」
「タワーって、あのいろいろついているやつ?」
そのタワーはちょうどヴィントたちが通れるような穴が開いていたり、小さなかごがいくつもついていたりしていて、確かにそこで遊ぶのは楽しそうに思えた。
「ええ。あそこはぼくらが遊んでいい場所なので、好きにしたらいいですよ」
「そうなんだ。ありがとう。遊んでみる」
ヴィントは早速部屋のすみにあるタワーで遊び始めた。高いところにいき、穴をくぐり、降りる。まるで大きな木の中を探検しているような気持ちになった。
ヴィントはへとへとになるまで遊ぶと、ウニが言っていたねどこで眠ることにした。ヴィントは夢を見ることなく眠った。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

ペーシェとバラばあさんと
翼 翔太
児童書・童話
テディーベアのペーシェは、旅するぬいぐるみ。
ある町でペーシェはバラばあさんというおばあさんと知り合う。ペーシェはバラばあさんのところでお世話になりつつ、新たな出会いをして、交流を深める。

あさはんのゆげ
深水千世
児童書・童話
【映画化】私を笑顔にするのも泣かせるのも『あさはん』と彼でした。
7月2日公開オムニバス映画『全員、片想い』の中の一遍『あさはんのゆげ』原案作品。
千葉雄大さん・清水富美加さんW主演、監督・脚本は山岸聖太さん。
彼は夏時雨の日にやって来た。
猫と画材と糠床を抱え、かつて暮らした群馬県の祖母の家に。
食べることがないとわかっていても朝食を用意する彼。
彼が救いたかったものは。この家に戻ってきた理由は。少女の心の行方は。
彼と過ごしたひと夏の日々が輝きだす。
FMヨコハマ『アナタの恋、映画化します。』受賞作品。
エブリスタにて公開していた作品です。

ずっと、ずっと、いつまでも
JEDI_tkms1984
児童書・童話
レン
ゴールデンレトリバーの男の子
ママとパパといっしょにくらしている
ある日、ママが言った
「もうすぐレンに妹ができるのよ」
レンはとてもよろこんだ
だけど……

フツーさがしの旅
雨ノ川からもも
児童書・童話
フツーじゃない白猫と、頼れるアニキ猫の成長物語
「お前、フツーじゃないんだよ」
兄弟たちにそうからかわれ、家族のもとを飛び出した子猫は、森の中で、先輩ノラ猫「ドライト」と出会う。
ドライトに名前をもらい、一緒に生活するようになったふたり。
狩りの練習に、町へのお出かけ、そして、新しい出会い。
二匹のノラ猫を中心に描かれる、成長物語。
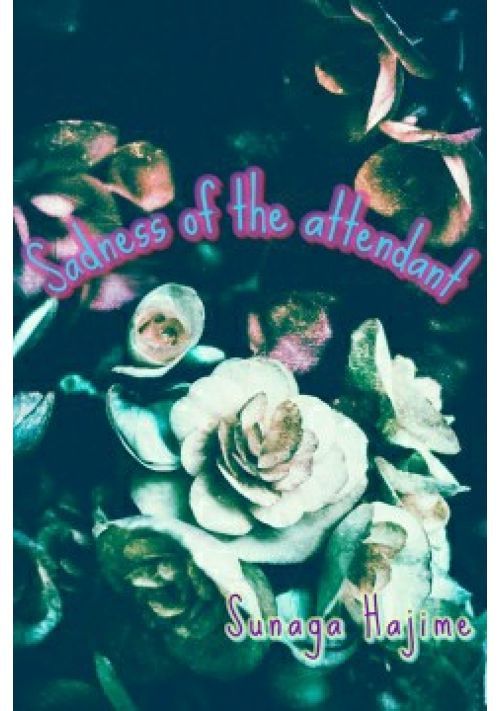
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

オハギとオモチ ~夏編~
水無月あん
児童書・童話
(きずな児童書大賞エントリー)子どもっぽい見た目を気にしている、小さな魔女オハギ。そんなオハギが、大嫌いな夏の気配を感じて、暑さ対策にのりだします!
魔女らしくあろうと、変な方向につきすすんでいたオハギが、どう変わっていくのか……。ゆるゆるとしたお話なので、気楽に読んでいただけたら幸いです。

ある羊と流れ星の物語
ねこうさぎしゃ
児童書・童話
たくさんの仲間と共に、優しい羊飼いのおじいさんと暮らしていたヒツジは、おじいさんの突然の死で境遇が一変してしまいます。
後から来た羊飼いの家族は、おじいさんのような優しい人間ではありませんでした。
そんな中、その家族に飼われていた一匹の美しいネコだけが、羊の心を癒してくれるのでした……。

銀河ラボのレイ
あまくに みか
児童書・童話
月うさぎがぴょんと跳ねる月面に、銀河ラボはある。
そこに住むレイ博士は、いるはずのない人間の子どもを見つけてしまう。
子どもは、いったい何者なのか?
子どもは、博士になにをもたらす者なのか。
博士が子どもと銀河ラボで過ごした、わずかな時間、「生きること、死ぬこと、生まれること」を二人は知る。
素敵な表紙絵は惑星ハーブティ様です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















