お気に入りに追加
1
この作品の感想を投稿する
みんなの感想(1件)
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る


就職面接の感ドコロ!?
フルーツパフェ
大衆娯楽
今や十年前とは真逆の、売り手市場の就職活動。
学生達は賃金と休暇を貪欲に追い求め、いつ送られてくるかわからない採用辞退メールに怯えながら、それでも優秀な人材を発掘しようとしていた。
その業務ストレスのせいだろうか。
ある面接官は、女子学生達のリクルートスーツに興奮する性癖を備え、仕事のストレスから面接の現場を愉しむことに決めたのだった。


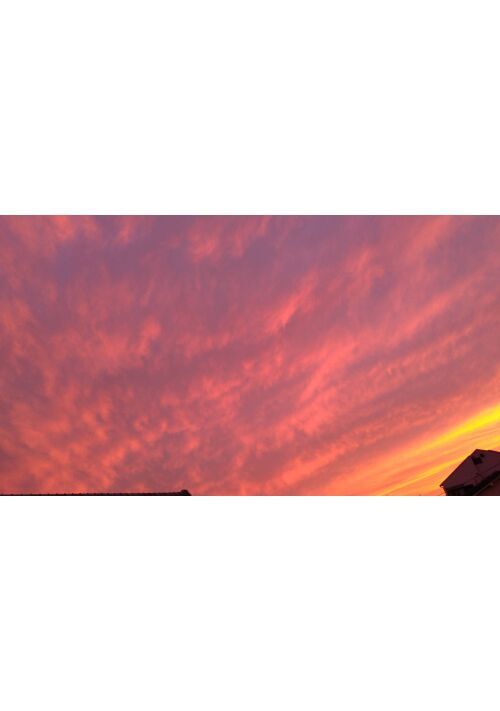
笑い上戸な死鳥
夢ノ瀬 日和
現代文学
学生の頃って、すごくストレスが溜まるよね。
家族、友人、先生、環境、進路、遠く感じる近い未来。
全部が全部、私の敵。
そう思ってしまう時期だってあるけど、
乗り越えられたのは、どうして?
この物語は、乗り越えられなかった私の話。
ホーホケキョ。

割れないしゃぼん玉
泣村健汰
現代文学
大学生の伸五は、6月のたまの晴れ間に、久々に家族水入らずで旅行に出かける事になった。
年の離れた兄と姉、そして父親と4人で、一路鬼怒川を目指す。
年を重ねすっかり丸くなった父親を中心に、過去を思い出しながら旅は続いていく。
この旅の本当の目的とは?
旅の果てに見つかる、家族のあり方とは?
愛しさと暖かさを詰め込んだ、心がじんわりと温かくなる、ホームロードストーリー。

君と探すこの上ない幸せ
夜梟
現代文学
明日が怖い──。
そう思い始めたのはいつからだっただろう。
仕事もない、お金もない、家族にも見放された男は、死んだように生きていた。そんな日々の中、彼の前に小さな幸せが姿を現す。
幸せは何処にあるのか。一匹の猫とともに探していきながら、男の過去が明らかになっていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。





















長く艶やかな黒の毛並み、蒼く光る宝石の如き瞳。
天から舞い降りた、美しく可愛らしい天使な存在。
そう――猫です。
この作品に登場するのは、
青空の下、野原に咲いた刹那の時に留めたくなる美しい花。
そんな儚き表現すら感じる、可愛らしい猫なのです。
偶然にも黒猫を保護した"彼"の、猫にまつわる物語。
とても楽しく読ませていただきました。
この感想を見た方も、気になりましたら是非とも読んでみてください!