お気に入りに追加
6
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説
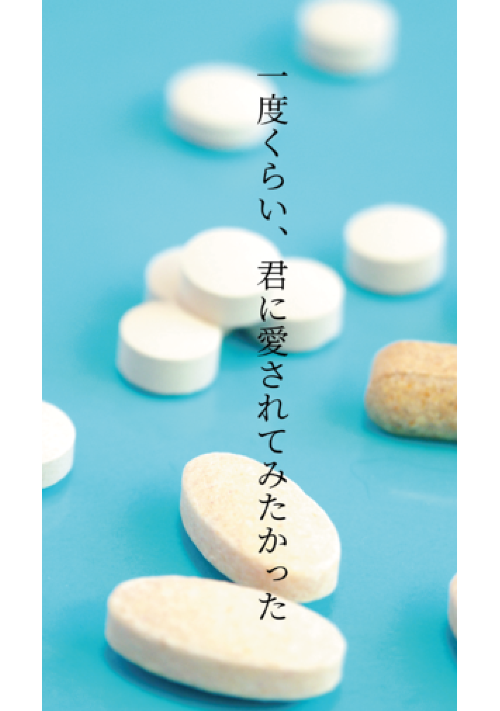



十七歳の心模様
須藤慎弥
BL
好きだからこそ、恋人の邪魔はしたくない…
ほんわか読者モデル×影の薄い平凡くん
柊一とは不釣り合いだと自覚しながらも、
葵は初めての恋に溺れていた。
付き合って一年が経ったある日、柊一が告白されている現場を目撃してしまう。
告白を断られてしまった女の子は泣き崩れ、
その瞬間…葵の胸に卑屈な思いが広がった。
※fujossy様にて行われた「梅雨のBLコンテスト」出品作です。


思い込み激しめな友人の恋愛相談を、仕方なく聞いていただけのはずだった
たけむら
BL
「思い込み激しめな友人の恋愛相談を、仕方なく聞いていただけのはずだった」
大学の同期・仁島くんのことが好きになってしまった、と友人・佐倉から世紀の大暴露を押し付けられた名和 正人(なわ まさと)は、その後も幾度となく呼び出されては、恋愛相談をされている。あまりのしつこさに、八つ当たりだと分かっていながらも、友人が好きになってしまったというお相手への怒りが次第に募っていく正人だったが…?


美人に告白されたがまたいつもの嫌がらせかと思ったので適当にOKした
亜桜黄身
BL
俺の学校では俺に付き合ってほしいと言う罰ゲームが流行ってる。
カースト底辺の卑屈くんがカースト頂点の強気ド美人敬語攻めと付き合う話。
(悪役モブ♀が出てきます)
(他サイトに2021年〜掲載済)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















