お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

西涼女侠伝
水城洋臣
歴史・時代
無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超
舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。
役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。
家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。
ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。
荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。
主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。
三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)
涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

浮雲の譜
神尾 宥人
歴史・時代
時は天正。織田の侵攻によって落城した高遠城にて、武田家家臣・飯島善十郎は蔦と名乗る透波の手によって九死に一生を得る。主家を失って流浪の身となったふたりは、流れ着くように訪れた富山の城下で、ひょんなことから長瀬小太郎という若侍、そして尾上備前守氏綱という男と出会う。そして善十郎は氏綱の誘いにより、かの者の主家である飛州帰雲城主・内ヶ島兵庫頭氏理のもとに仕官することとする。
峻厳な山々に守られ、四代百二十年の歴史を築いてきた内ヶ島家。その元で善十郎は、若武者たちに槍を指南しながら、穏やかな日々を過ごす。しかしそんな辺境の小国にも、乱世の荒波はひたひたと忍び寄ってきていた……
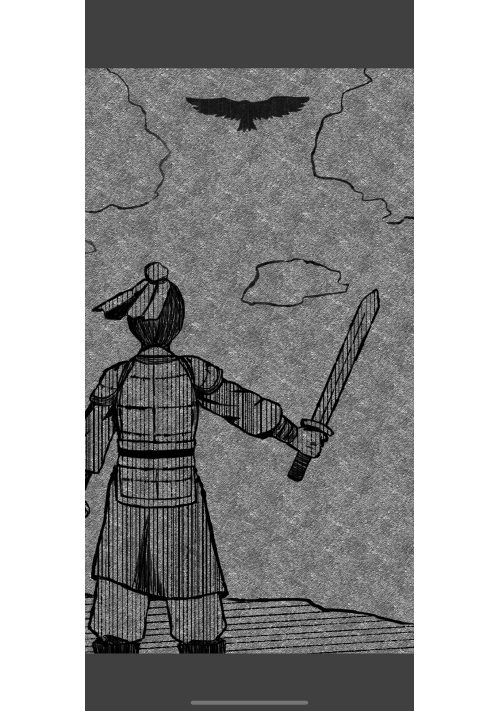
楽毅 大鵬伝
松井暁彦
歴史・時代
舞台は中国戦国時代の最中。
誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。
名は楽毅《がくき》。
祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、
在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。
山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、
六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。
そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。
複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!
イラスト提供 祥子様

要塞少女
水城洋臣
歴史・時代
蛮族に包囲され孤立した城を守り抜いた指揮官は、十四歳の少女であった。
三国時代を統一によって終わらせた西晋王朝の末期。
かつて南中と呼ばれた寧州で、蛮族の反乱によって孤立した州城。今は国中が内紛の只中にあり援軍も望めない。絶体絶命と思われた城を救ったのは、名将である父から兵法・武芸を学んだ弱冠十四歳の少女・李秀であった……。
かの『三國志』で、劉備たちが治めた蜀の地。そんな蜀漢が滅びた後、蜀がどんな歴史を辿ったのか。
東晋時代に編纂された史書『華陽國志』(巴蜀の地方史)に記された史実を元にした伝奇フィクションです。

荒川にそばだつ
和田さとみ
歴史・時代
戦国時代、北武蔵を治める藤田氏の娘大福(おふく)は8歳で、新興勢力北条氏康の息子、乙千代丸を婿に貰います。
平和のために、幼いながらも仲睦まじくあろうとする二人ですが、次第に…。
二人三脚で北武蔵を治める二人とはお構いなく、時代の波は大きくうねり始めます。
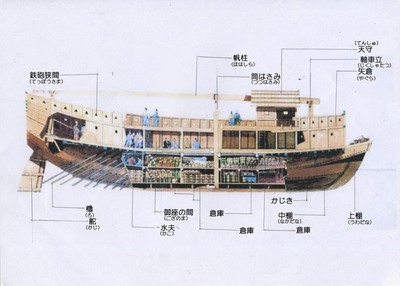


【完結】月よりきれい
悠井すみれ
歴史・時代
職人の若者・清吾は、吉原に売られた幼馴染を探している。登楼もせずに見世の内情を探ったことで袋叩きにあった彼は、美貌に加えて慈悲深いと評判の花魁・唐織に助けられる。
清吾の事情を聞いた唐織は、彼女の情人の振りをして吉原に入り込めば良い、と提案する。客の嫉妬を煽って通わせるため、形ばかりの恋人を置くのは唐織にとっても好都合なのだという。
純心な清吾にとっては、唐織の計算高さは遠い世界のもの──その、はずだった。
嘘を重ねる花魁と、幼馴染を探す一途な若者の交流と愛憎。愛よりも真実よりも美しいものとは。
第9回歴史・時代小説大賞参加作品です。楽しんでいただけましたら投票お願いいたします。
表紙画像はぱくたそ(www.pakutaso.com)より。かんたん表紙メーカー(https://sscard.monokakitools.net/covermaker.html)で作成しました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















