78 / 106
防衛西支部編
旋風
しおりを挟む
情けない、その一言が心の奥底を掻き乱す。
北支部監督官の一人とあろうものが、今生の別れとなったはずの昔馴染みと再会し、取り乱してしまうなどあってはならないことだ。
お陰で一番舐められたくない新人に醜態を晒してしまった。今後、下に見られるのは避けられない。それ以前の問題として、西支部の監督官に迷惑をかけてしまった自分が許せなかった。
むーちゃんは無言で、金切音一つあげずに包み込んでくれる。黒曜石を思わせる硬くて艶やかなその肌に、縋るように身を預けた。
ツムジ―――請負人なるずっとずっと昔、一緒に生活していた姉貴分にあたる人物。周囲からもたくさんの奴らから信頼されていて、基本的にむーちゃん以外は信じなかった自分でさえも、心を開いていた数少ない存在だった。
自分が知っている限りじゃ、ツムジは死人だ。憎むべき存在である暴閥の一角―――擬巖家に単身で攻め込み、それ以降帰ってこなかったからだ。
弱い奴が死ぬ。そんなことはよくあることだ。風に煽られ、枯れた葉が枝から千切れ落ち、なすすべなく誰かに踏み潰されるように、弱肉強食は自然の摂理。
ツムジは自分から見ても決して弱くはなかった。当時の自分では、どう足掻いても勝てないくらいの腕っ節はあったのだ。彼女だって自分の実力を過信していたわけじゃない。だが、敵対した相手が悪すぎた。
擬巖家。武市を支配する``大陸八暴閥``の一柱。流川や花筏に次ぐ、武市最大の暴閥。いくらツムジの腕っ節が強いといっても、所詮はスラムの中での話だ。``大陸八暴閥``からしたら、ただ井戸の中で虚しく鳴き叫ぶ蛙にすぎない。
あの頃の自分は半ば心を閉ざしていたからよく覚えていない。確かなのは、ツムジは帰ってこなかったってことだけだ。
「むーちゃん……」
額を擦りつけ、むーちゃんの甲殻に身を委ねる。その甲殻は並の防壁と比べるべくもなく硬いのだが、額から伝わるひんやりとした冷たさが、とても優しくて心地いい。
目の前に立つツムジが本物じゃないことには気づいていた。人の気配をしていなかったし、そもそも生き物ですらない。アレは魔法で形作られただけのハリボテだ。
理屈では分かっている。本物じゃない、ツムジの姿に限りなく似ているだけの、ただの別物であることなど。でも偽物であっても、ツムジはツムジだった。偽物なのだから、本物じゃないから。そんな理屈など吹き飛ばしてしまうほどに、彼女はツムジだったのだ。
「わかってる、ただかくごがたりねーだけだ。ツムジは、あーしがしってるツムジは、もうしんだんだ……」
何度思い起こそうとも変わらない。北支部監督官として、いや同じ釜の飯を食い繋いできたスラムの同胞として。あの偽物をなんとしても始末しなければならない。
そのとき、自分の中で何かが弾けた。己を縛りつけていた鎖の一部が、内側からの圧力で砕け散ったかのように、勢いのままに立ち上がる。
「おいてめーら」
ツムジの紛い物を倒すべく奮闘していたであろうバカ新人と西支部監督官の間に割って入る。が、バカ新人に肩を強く押し返される。
「何の用だ。邪魔だから下がってろ」
バカ新人はクソを見るような目で自分を見下げてくる。醜態をさらしてしまった手前かなり分が悪い状況だが、それでも引くわけにはいかない。ツムジの偽物に引導を渡さなきゃならないのは、紛れもなく自分なのだ。
いつもならバカ新人の態度は気に食わないが、今回限りはコイツが正しい。なすべべきときになすべきをなせなかったのだから、舐められて当然だろう。
でも、だったら実力を示せばいい。自分自身も忘れがちだが、自分だって北支部監督官なのだ。
「あーしにやらせろ」
「算段は?」
「かいじゅしておわらせる」
「できんのかよ?」
「だまってみてろ」
それ以上は言わせない。その圧力を霊圧として放つ。西支部監督官はその霊圧を察したのか、肩をすくめてそれ以上は何も言ってこなかった。
「ざけ……!!」
尚も自分に絡もうとしたバカ新人だったが、暗黒の帳がバカ新人と西支部監督官を覆い尽くし、その進路を阻む。
二人の前に現れた巨大な暗黒。それは紛れもなく、むーちゃんだった。
むーちゃんはいつだって自分の味方だ。一心同体。その言葉が自分たちの関係を一言で表すのに相応しい。
むーちゃんから放たれる霊圧は自分ら人間のそれとは格が違う。その巨大な体躯も相まって、強者の域に達している二人ですら容易にむーちゃんの間合に踏み込めなくなるほどに。
バカ新人に絡まれるのもクソ面倒なので、むーちゃんが牽制してくれている間にさっさとツムジの所まで向かう。
ツムジの所ではギガレックスの野郎と邪魔くせぇぬいぐるみどもがツムジをサンドバッグにしていた。六メトの巨体から放たれる殴打は筆舌に尽くし難く、既に床や壁がボロボロになっている。西支部のビルなのでどうなろうと興味ないが、このまま続けていても時間の無駄だ。
「じゃまだ、どけ」
「ああん!? んだぁオメーさっき取り乱してた奴じゃねーか!! オメーこそ邪魔だ!! すっこんでろチビ!!」
やはりというべきかどく気はないらしい。でけぇ声で喋りながらでも殴る手を止めやがる気配はない。
どかないのは予想通り。だったら、やることは一つだ。
「むーちゃん、アイツをどかせろ。おれのじゃまをさせるな」
むーちゃんは長い胴体を器用に使い、バカ新人どもに霊圧で牽制しながらもギガレックスを簀巻きにするとかいう器用な真似をやってのける。
突然ぐるぐる巻きにされ、血眼で俺らを睨みかかるが、むーちゃんに迷いなどなかった。ギガレックスが怒号を張り叫ぶよりも速く、壁にブチ投げたのである。
続いてぬいぐるみどもをエーテルレーザーで牽制。床が焼け焦げ炎上するが、ぬいぐるみどもは難なく避けて無傷だ。
「おい、何の真似だ? あんま舐めた真似してっと肥やしにすんぞ」
「突然エーテルレーザー撃ってくんのは穏やかじゃねぇっすねぇ、流石のオレもカチキレちまうぜ?」
「ハハッ!! ボクのち〇こから溢れ出る性欲で、その真っ黒な肌を白く染め上げちゃうよ!!」
「彼女がパンツを履いているかどうかを確かめるという崇高にして至高たる使命を邪魔するとは……唯一神パン=ツーへの背信だぞ」
突然攻撃されてぬいぐるみどもは不満げな視線をむーちゃんに集中させ、ぬいぐるみとは思えないほどのかわいらしさの欠片もない濃厚で刺々しい霊圧を全身から解き放つ。
相変わらずやかましいチビどもだが、霊圧から放たれる威圧感は本物だった。
「うるせぇだまってろカスども。あーしがぜんぶやるからしゅじんのところへかえんな」
ぬいぐるみどもがいても役に立たない。解呪魔法が使えるなら話は違ったかもしれないが、どちらにせよこの場を譲る気は毛頭ないのである。
空飛ぶ子熊が般若みたいな顔をして、ケツに手を突っ込んで出した黒い塊を投げようと短い腕を振りかぶるが、それを見逃すむーちゃんじゃない。再びエーテルレーザーで牽制し、ぬいぐるみどもと自分との間を爆煙と砂埃で埋め立てる。
ギガレックスが離れたことで、アイツの固有能力が解除された。ギガレックスとぬいぐるみども、そしてバカ新人の相手はむーちゃんに任せるとして、自分はツムジの対処だ。
目の前にいるツムジは外見こそツムジだがツムジそのものじゃない。その正体はツムジを素体として闇魔法で再現した疑似生物だ。
粗方の解析はむーちゃんと協力して既に終わらせてある。使用されている魔法も、見当がついていた。
むーちゃん曰く、ツムジを形作っている魔法は闇属性系魔法の一種である``捧贄蘇生``。素体の遺伝子情報を元にして、素体を再現する闇魔法である。
魔法で構築されているにすぎないから物理攻撃は一切効かず、生きているわけでもないから魔法攻撃だって効かない。素体を形作る魔法陣が破壊されない限り、如何なるダメージを負わない無敵の疑似生物だが、要は元が魔法なのだから結局のところ解呪してしまえばいいだけの話なのだ。
コイツらが苦戦していたのは単純に誰も解呪魔法を使える奴がいなかったからで、解呪魔法が使えるむーちゃんがいれば、ツムジの紛い物など問題にならないのである。
解呪魔法の魔法陣はむーちゃんから教えてもらった。後は隙を伺いながら魔法陣を記述するだけだ。
「ツムジ……」
ギガレックスやぬいぐるみどもにサンドバッグにされ、身体がゲル状になっているツムジ。普通なら致命傷のはずだし、粉微塵になっているはずだが、闇属性霊力そのものでしかないツムジは急速に身体を再構築し始めている。
「ひさ……しぶり……だ……な……げ……んき……にし……て……たか……」
鼓膜が揺れ、目頭が熱くなる。首を左右に振り、思わず揺らいでしまいそうになる自分を叱咤した。
闇魔法``捧贄蘇生``は、素体の遺伝情報を元に闇属性霊力で素体を再現する。いわば擬似的な蘇生魔法であり、素体と瓜二つの存在を作り出せる。
喋り方、声音、そして表情。紛い物だと分かっていても、その全ては生前のツムジそのもの。まだ請負人になる前、下威区スラムで燻っていた頃の、あのツムジなのだ。
魔法そのものでしかないのに、紛い物が何故自分のことを知っているのか。むーちゃん曰く、素体の肉体情報にはその者の魂の残滓が宿っているからだそうだ。
その残滓とは、いわば魂に刻まれた根源的な記憶の一部。たとえ精神という思考装置を失っても、肉体が器としての機能を失っても、その器に宿っていた魂の記憶は、なんらかの外的営力で上書きされない限り、決して失われない。
それが、この世界の摂理の一種。``世界情報全書``に記された、この世界の仕組みなのだ。
「げんきだよ。ナユタとはたもとをわかっちまって、いまどーしてるかわかんねーけど」
「そう……か……あんし……んした……ぞ」
「ああ。あーしもそーおもう」
目からこぼれ落ちそうになるそれを堪えるために、今の自分ができる全力の笑顔を貼り付ける。
ナユタ。自分が出会う以前からツムジとともに行動していた同胞の一人。ツムジが帰ってこなくなった後も、しばらくは一緒に暮らしていた。
あのときの自分は、とにかく下威区から出たかった。ツムジを含め、沢山の同胞の死を見送ってきて、スラムの生活に絶望しか感じなかったからだ。
ナユタには生きていけない、お前は弱すぎると言われた。下威区のスラム地域を行脚し、骨を埋めるのが相応しい生き方だとも。だが当時の自分は水魔法が使える自負があり、彼の全てを跳ね除けてしまった。
それが、ナユタと交わした最後の会話。下威区から出るつもりのなかったアイツとは、その会話を境に一度も言葉を交わすことなく道を違えてしまった。
今思えば、少しくらいは耳を傾けるべきだったと思う。実際、下威区を出るときはむーちゃんの封印が解けなければ死んでいたし、そうでなくてもレクと出会えなければそのまま討伐されていた。自分が今こうして請負人として生き、そして北支部監督官として生きていられているのは、単純に悪運に恵まれていただけにすぎない。
ナユタは自惚れていることを察してくれていた。決別してしまった今、アイツとは一度も会っていない。ナユタは優しいし、救える同胞には平等に手を差し伸べるお人好しだが、その反面リアリストでもある。自分のことはすでにどこかで野垂れ死んでいると勝手に考えているだろう。
自分の請負人としての目標は``武ノ壁``の破壊。すなわち下威区の解放だ。
下威区を封じる忌々しい結界を破壊すれば、今もスラム生活を強いられる同胞や、下威区に縛られたナユタを解放してあげられる。スラムの同胞全てが夢見る永遠の夢―――``自由``が手に入る。
そうなったとき、ナユタと再会して謝って、レクを加えた三人とむーちゃんとで、今度こそ笑って過ごすんだ。ナユタには請負人になってもらって、一緒に任務をこなして欲しい。アイツもかなり強いから、きっと請負人として抜擢されるはずだ。レクだってきっと嫌わない。
何にも縛られず、笑ってその日を過ごす。それはツムジやナユタと夢見た、自分たちの理想の生活だから。
「そう……だ……そ……のなゆ……たの……ことで……伝……えた……いこ……とが」
「なに? ナユタがどうした!? しってるのか!?」
「たの……む……なユ……タを……と……め……なゆたったたたたなゆユユッタタタタ」
「くっ……かんじんなときに……!!」
感慨に耽っていたが、魔法陣の記述は並行して行なっていた。ツムジが急に頭を抱えて苦しみ始め、同じ言葉を譫言のように復唱し始める。おそらく魂の残滓が闇魔法に刻まれた命令に抗っているせいで、人格に綻びが生じ始めているのだ。
本来、魔法陣に記述された命令は絶対だ。それに逆らうなんて真似は基本的にできない。その不可能を可能にしているのは、ツムジの意志がそれだけ強いからに他ならない。
生前の意志が強いほど、素体に焼きつく魂の残滓は鮮烈になる。だからこそ残滓でありながら、魔法の絶対命令にある程度抗うことができているのである。
しかしツムジを形作っているのが魔法である以上、魔法の支配からは逃れられない。いずれ魂の残滓は摩耗し、消失してしまうだろう。そうなる前に、引導を渡してあげたい。
「……いまらくにしてやる」
解呪魔法を起動する。身体全体が白く光ったと思うと、ツムジの真下から光の柱が現れ、彼女を優しく包み込んだ。
解呪魔法``解除``。なんの変哲もない、ただの解呪魔法だ。本来``捧贄蘇生``には、簡単に解呪されないように対解呪魔法対策を施すらしいが、どうやらこの魔法を仕込んだ奴は魔導師として半人前だったようだ。
それは自分にとって幸運と言えた。満面の笑みを浮かべるツムジを、その笑顔のまま送り届けることができるのだから。
「那由多を……とめ……」
解呪魔法によって魔法陣が破壊され、形を保てなくなった闇属性の霊力が霧散する。魔法の光に包まれていくツムジの顔は、笑っていた。生前よりもずっと、朗らかに、幸せそうに。
遂に瞼が決壊し、頬に熱いものが滴り落ちる。形を保てなくなり、もはや声すらも出せなくなったツムジが最後に残した言葉だけが、頭の髄にまで強く焼きついた。
必ず、会いにいく。そう自分の胸に、焼き印を強く押して―――。
瞼から湧き出る熱いそれを、ポンチョの袖で強く拭い去った。
光の柱が完全に消滅したのを確認すると、バカ新人と西支部監督官のもとへ戻る。
ツムジを楽にするのに夢中で感覚が麻痺していたが、今頃になって罪悪感が込み上げてきた。
北支部監督官でありながら戦場を混乱させた罪は重い。相手がツムジで、なおかつまだ意識が残っていたから事なきを得られたものの、もしもむーちゃん並の化け物だとかツムジとしての意識がまるでない人形の怪物だったなら、戦場はもっと混沌としていただろう。
監督官として、あるまじき失態だ。バカ新人にも面目が立たないし、はっきり言って今回の戦い、どうにかできなければ責任追及は絶対に免れなかった。
「大丈夫……みたいだな。安心したぜ」
どう繕おうかと悩んでいた矢先、西支部監督官が頭を掻きながら近づいてきた。その声音は出会ったときと変わりなく、抑揚がなくて気怠そうな感じのそれだ。
「まあ死んだ仲間が現れりゃあ、混乱の一つや二つしちまうさ。きちんとケツも拭けてんだし、とっととレクたちの援護に回ろうぜ」
親指で未だ交戦中であろう地下二階へのへ続く階段を指し示す。
人付き合いを積極的にしない自分でも分かる。気を遣われている、なんとも言えない居た堪れなさが身を削る。
「わりぃ。このかりはかならずかえす」
監督官としてあるまじき失態を犯してしまったが、くよくよしてはいられない。まだ戦いは終わっていないのだ。
レクが心配だし、なにより御玲が―――。
「新人も、それでいいだろ?」
西支部監督官がバカ新人の顔も伺う。
バカ新人は尚も不満タラタラな表情で俺を睨んでいたが、わざとらしい舌打ちをするのみで、それ以上は何も言ってはこなかった。
バカ新人からの熱い視線を背後から感じながらも、レクたちが戦っている地下シェルターへ歩を進める。
北支部監督官の一人とあろうものが、今生の別れとなったはずの昔馴染みと再会し、取り乱してしまうなどあってはならないことだ。
お陰で一番舐められたくない新人に醜態を晒してしまった。今後、下に見られるのは避けられない。それ以前の問題として、西支部の監督官に迷惑をかけてしまった自分が許せなかった。
むーちゃんは無言で、金切音一つあげずに包み込んでくれる。黒曜石を思わせる硬くて艶やかなその肌に、縋るように身を預けた。
ツムジ―――請負人なるずっとずっと昔、一緒に生活していた姉貴分にあたる人物。周囲からもたくさんの奴らから信頼されていて、基本的にむーちゃん以外は信じなかった自分でさえも、心を開いていた数少ない存在だった。
自分が知っている限りじゃ、ツムジは死人だ。憎むべき存在である暴閥の一角―――擬巖家に単身で攻め込み、それ以降帰ってこなかったからだ。
弱い奴が死ぬ。そんなことはよくあることだ。風に煽られ、枯れた葉が枝から千切れ落ち、なすすべなく誰かに踏み潰されるように、弱肉強食は自然の摂理。
ツムジは自分から見ても決して弱くはなかった。当時の自分では、どう足掻いても勝てないくらいの腕っ節はあったのだ。彼女だって自分の実力を過信していたわけじゃない。だが、敵対した相手が悪すぎた。
擬巖家。武市を支配する``大陸八暴閥``の一柱。流川や花筏に次ぐ、武市最大の暴閥。いくらツムジの腕っ節が強いといっても、所詮はスラムの中での話だ。``大陸八暴閥``からしたら、ただ井戸の中で虚しく鳴き叫ぶ蛙にすぎない。
あの頃の自分は半ば心を閉ざしていたからよく覚えていない。確かなのは、ツムジは帰ってこなかったってことだけだ。
「むーちゃん……」
額を擦りつけ、むーちゃんの甲殻に身を委ねる。その甲殻は並の防壁と比べるべくもなく硬いのだが、額から伝わるひんやりとした冷たさが、とても優しくて心地いい。
目の前に立つツムジが本物じゃないことには気づいていた。人の気配をしていなかったし、そもそも生き物ですらない。アレは魔法で形作られただけのハリボテだ。
理屈では分かっている。本物じゃない、ツムジの姿に限りなく似ているだけの、ただの別物であることなど。でも偽物であっても、ツムジはツムジだった。偽物なのだから、本物じゃないから。そんな理屈など吹き飛ばしてしまうほどに、彼女はツムジだったのだ。
「わかってる、ただかくごがたりねーだけだ。ツムジは、あーしがしってるツムジは、もうしんだんだ……」
何度思い起こそうとも変わらない。北支部監督官として、いや同じ釜の飯を食い繋いできたスラムの同胞として。あの偽物をなんとしても始末しなければならない。
そのとき、自分の中で何かが弾けた。己を縛りつけていた鎖の一部が、内側からの圧力で砕け散ったかのように、勢いのままに立ち上がる。
「おいてめーら」
ツムジの紛い物を倒すべく奮闘していたであろうバカ新人と西支部監督官の間に割って入る。が、バカ新人に肩を強く押し返される。
「何の用だ。邪魔だから下がってろ」
バカ新人はクソを見るような目で自分を見下げてくる。醜態をさらしてしまった手前かなり分が悪い状況だが、それでも引くわけにはいかない。ツムジの偽物に引導を渡さなきゃならないのは、紛れもなく自分なのだ。
いつもならバカ新人の態度は気に食わないが、今回限りはコイツが正しい。なすべべきときになすべきをなせなかったのだから、舐められて当然だろう。
でも、だったら実力を示せばいい。自分自身も忘れがちだが、自分だって北支部監督官なのだ。
「あーしにやらせろ」
「算段は?」
「かいじゅしておわらせる」
「できんのかよ?」
「だまってみてろ」
それ以上は言わせない。その圧力を霊圧として放つ。西支部監督官はその霊圧を察したのか、肩をすくめてそれ以上は何も言ってこなかった。
「ざけ……!!」
尚も自分に絡もうとしたバカ新人だったが、暗黒の帳がバカ新人と西支部監督官を覆い尽くし、その進路を阻む。
二人の前に現れた巨大な暗黒。それは紛れもなく、むーちゃんだった。
むーちゃんはいつだって自分の味方だ。一心同体。その言葉が自分たちの関係を一言で表すのに相応しい。
むーちゃんから放たれる霊圧は自分ら人間のそれとは格が違う。その巨大な体躯も相まって、強者の域に達している二人ですら容易にむーちゃんの間合に踏み込めなくなるほどに。
バカ新人に絡まれるのもクソ面倒なので、むーちゃんが牽制してくれている間にさっさとツムジの所まで向かう。
ツムジの所ではギガレックスの野郎と邪魔くせぇぬいぐるみどもがツムジをサンドバッグにしていた。六メトの巨体から放たれる殴打は筆舌に尽くし難く、既に床や壁がボロボロになっている。西支部のビルなのでどうなろうと興味ないが、このまま続けていても時間の無駄だ。
「じゃまだ、どけ」
「ああん!? んだぁオメーさっき取り乱してた奴じゃねーか!! オメーこそ邪魔だ!! すっこんでろチビ!!」
やはりというべきかどく気はないらしい。でけぇ声で喋りながらでも殴る手を止めやがる気配はない。
どかないのは予想通り。だったら、やることは一つだ。
「むーちゃん、アイツをどかせろ。おれのじゃまをさせるな」
むーちゃんは長い胴体を器用に使い、バカ新人どもに霊圧で牽制しながらもギガレックスを簀巻きにするとかいう器用な真似をやってのける。
突然ぐるぐる巻きにされ、血眼で俺らを睨みかかるが、むーちゃんに迷いなどなかった。ギガレックスが怒号を張り叫ぶよりも速く、壁にブチ投げたのである。
続いてぬいぐるみどもをエーテルレーザーで牽制。床が焼け焦げ炎上するが、ぬいぐるみどもは難なく避けて無傷だ。
「おい、何の真似だ? あんま舐めた真似してっと肥やしにすんぞ」
「突然エーテルレーザー撃ってくんのは穏やかじゃねぇっすねぇ、流石のオレもカチキレちまうぜ?」
「ハハッ!! ボクのち〇こから溢れ出る性欲で、その真っ黒な肌を白く染め上げちゃうよ!!」
「彼女がパンツを履いているかどうかを確かめるという崇高にして至高たる使命を邪魔するとは……唯一神パン=ツーへの背信だぞ」
突然攻撃されてぬいぐるみどもは不満げな視線をむーちゃんに集中させ、ぬいぐるみとは思えないほどのかわいらしさの欠片もない濃厚で刺々しい霊圧を全身から解き放つ。
相変わらずやかましいチビどもだが、霊圧から放たれる威圧感は本物だった。
「うるせぇだまってろカスども。あーしがぜんぶやるからしゅじんのところへかえんな」
ぬいぐるみどもがいても役に立たない。解呪魔法が使えるなら話は違ったかもしれないが、どちらにせよこの場を譲る気は毛頭ないのである。
空飛ぶ子熊が般若みたいな顔をして、ケツに手を突っ込んで出した黒い塊を投げようと短い腕を振りかぶるが、それを見逃すむーちゃんじゃない。再びエーテルレーザーで牽制し、ぬいぐるみどもと自分との間を爆煙と砂埃で埋め立てる。
ギガレックスが離れたことで、アイツの固有能力が解除された。ギガレックスとぬいぐるみども、そしてバカ新人の相手はむーちゃんに任せるとして、自分はツムジの対処だ。
目の前にいるツムジは外見こそツムジだがツムジそのものじゃない。その正体はツムジを素体として闇魔法で再現した疑似生物だ。
粗方の解析はむーちゃんと協力して既に終わらせてある。使用されている魔法も、見当がついていた。
むーちゃん曰く、ツムジを形作っている魔法は闇属性系魔法の一種である``捧贄蘇生``。素体の遺伝子情報を元にして、素体を再現する闇魔法である。
魔法で構築されているにすぎないから物理攻撃は一切効かず、生きているわけでもないから魔法攻撃だって効かない。素体を形作る魔法陣が破壊されない限り、如何なるダメージを負わない無敵の疑似生物だが、要は元が魔法なのだから結局のところ解呪してしまえばいいだけの話なのだ。
コイツらが苦戦していたのは単純に誰も解呪魔法を使える奴がいなかったからで、解呪魔法が使えるむーちゃんがいれば、ツムジの紛い物など問題にならないのである。
解呪魔法の魔法陣はむーちゃんから教えてもらった。後は隙を伺いながら魔法陣を記述するだけだ。
「ツムジ……」
ギガレックスやぬいぐるみどもにサンドバッグにされ、身体がゲル状になっているツムジ。普通なら致命傷のはずだし、粉微塵になっているはずだが、闇属性霊力そのものでしかないツムジは急速に身体を再構築し始めている。
「ひさ……しぶり……だ……な……げ……んき……にし……て……たか……」
鼓膜が揺れ、目頭が熱くなる。首を左右に振り、思わず揺らいでしまいそうになる自分を叱咤した。
闇魔法``捧贄蘇生``は、素体の遺伝情報を元に闇属性霊力で素体を再現する。いわば擬似的な蘇生魔法であり、素体と瓜二つの存在を作り出せる。
喋り方、声音、そして表情。紛い物だと分かっていても、その全ては生前のツムジそのもの。まだ請負人になる前、下威区スラムで燻っていた頃の、あのツムジなのだ。
魔法そのものでしかないのに、紛い物が何故自分のことを知っているのか。むーちゃん曰く、素体の肉体情報にはその者の魂の残滓が宿っているからだそうだ。
その残滓とは、いわば魂に刻まれた根源的な記憶の一部。たとえ精神という思考装置を失っても、肉体が器としての機能を失っても、その器に宿っていた魂の記憶は、なんらかの外的営力で上書きされない限り、決して失われない。
それが、この世界の摂理の一種。``世界情報全書``に記された、この世界の仕組みなのだ。
「げんきだよ。ナユタとはたもとをわかっちまって、いまどーしてるかわかんねーけど」
「そう……か……あんし……んした……ぞ」
「ああ。あーしもそーおもう」
目からこぼれ落ちそうになるそれを堪えるために、今の自分ができる全力の笑顔を貼り付ける。
ナユタ。自分が出会う以前からツムジとともに行動していた同胞の一人。ツムジが帰ってこなくなった後も、しばらくは一緒に暮らしていた。
あのときの自分は、とにかく下威区から出たかった。ツムジを含め、沢山の同胞の死を見送ってきて、スラムの生活に絶望しか感じなかったからだ。
ナユタには生きていけない、お前は弱すぎると言われた。下威区のスラム地域を行脚し、骨を埋めるのが相応しい生き方だとも。だが当時の自分は水魔法が使える自負があり、彼の全てを跳ね除けてしまった。
それが、ナユタと交わした最後の会話。下威区から出るつもりのなかったアイツとは、その会話を境に一度も言葉を交わすことなく道を違えてしまった。
今思えば、少しくらいは耳を傾けるべきだったと思う。実際、下威区を出るときはむーちゃんの封印が解けなければ死んでいたし、そうでなくてもレクと出会えなければそのまま討伐されていた。自分が今こうして請負人として生き、そして北支部監督官として生きていられているのは、単純に悪運に恵まれていただけにすぎない。
ナユタは自惚れていることを察してくれていた。決別してしまった今、アイツとは一度も会っていない。ナユタは優しいし、救える同胞には平等に手を差し伸べるお人好しだが、その反面リアリストでもある。自分のことはすでにどこかで野垂れ死んでいると勝手に考えているだろう。
自分の請負人としての目標は``武ノ壁``の破壊。すなわち下威区の解放だ。
下威区を封じる忌々しい結界を破壊すれば、今もスラム生活を強いられる同胞や、下威区に縛られたナユタを解放してあげられる。スラムの同胞全てが夢見る永遠の夢―――``自由``が手に入る。
そうなったとき、ナユタと再会して謝って、レクを加えた三人とむーちゃんとで、今度こそ笑って過ごすんだ。ナユタには請負人になってもらって、一緒に任務をこなして欲しい。アイツもかなり強いから、きっと請負人として抜擢されるはずだ。レクだってきっと嫌わない。
何にも縛られず、笑ってその日を過ごす。それはツムジやナユタと夢見た、自分たちの理想の生活だから。
「そう……だ……そ……のなゆ……たの……ことで……伝……えた……いこ……とが」
「なに? ナユタがどうした!? しってるのか!?」
「たの……む……なユ……タを……と……め……なゆたったたたたなゆユユッタタタタ」
「くっ……かんじんなときに……!!」
感慨に耽っていたが、魔法陣の記述は並行して行なっていた。ツムジが急に頭を抱えて苦しみ始め、同じ言葉を譫言のように復唱し始める。おそらく魂の残滓が闇魔法に刻まれた命令に抗っているせいで、人格に綻びが生じ始めているのだ。
本来、魔法陣に記述された命令は絶対だ。それに逆らうなんて真似は基本的にできない。その不可能を可能にしているのは、ツムジの意志がそれだけ強いからに他ならない。
生前の意志が強いほど、素体に焼きつく魂の残滓は鮮烈になる。だからこそ残滓でありながら、魔法の絶対命令にある程度抗うことができているのである。
しかしツムジを形作っているのが魔法である以上、魔法の支配からは逃れられない。いずれ魂の残滓は摩耗し、消失してしまうだろう。そうなる前に、引導を渡してあげたい。
「……いまらくにしてやる」
解呪魔法を起動する。身体全体が白く光ったと思うと、ツムジの真下から光の柱が現れ、彼女を優しく包み込んだ。
解呪魔法``解除``。なんの変哲もない、ただの解呪魔法だ。本来``捧贄蘇生``には、簡単に解呪されないように対解呪魔法対策を施すらしいが、どうやらこの魔法を仕込んだ奴は魔導師として半人前だったようだ。
それは自分にとって幸運と言えた。満面の笑みを浮かべるツムジを、その笑顔のまま送り届けることができるのだから。
「那由多を……とめ……」
解呪魔法によって魔法陣が破壊され、形を保てなくなった闇属性の霊力が霧散する。魔法の光に包まれていくツムジの顔は、笑っていた。生前よりもずっと、朗らかに、幸せそうに。
遂に瞼が決壊し、頬に熱いものが滴り落ちる。形を保てなくなり、もはや声すらも出せなくなったツムジが最後に残した言葉だけが、頭の髄にまで強く焼きついた。
必ず、会いにいく。そう自分の胸に、焼き印を強く押して―――。
瞼から湧き出る熱いそれを、ポンチョの袖で強く拭い去った。
光の柱が完全に消滅したのを確認すると、バカ新人と西支部監督官のもとへ戻る。
ツムジを楽にするのに夢中で感覚が麻痺していたが、今頃になって罪悪感が込み上げてきた。
北支部監督官でありながら戦場を混乱させた罪は重い。相手がツムジで、なおかつまだ意識が残っていたから事なきを得られたものの、もしもむーちゃん並の化け物だとかツムジとしての意識がまるでない人形の怪物だったなら、戦場はもっと混沌としていただろう。
監督官として、あるまじき失態だ。バカ新人にも面目が立たないし、はっきり言って今回の戦い、どうにかできなければ責任追及は絶対に免れなかった。
「大丈夫……みたいだな。安心したぜ」
どう繕おうかと悩んでいた矢先、西支部監督官が頭を掻きながら近づいてきた。その声音は出会ったときと変わりなく、抑揚がなくて気怠そうな感じのそれだ。
「まあ死んだ仲間が現れりゃあ、混乱の一つや二つしちまうさ。きちんとケツも拭けてんだし、とっととレクたちの援護に回ろうぜ」
親指で未だ交戦中であろう地下二階へのへ続く階段を指し示す。
人付き合いを積極的にしない自分でも分かる。気を遣われている、なんとも言えない居た堪れなさが身を削る。
「わりぃ。このかりはかならずかえす」
監督官としてあるまじき失態を犯してしまったが、くよくよしてはいられない。まだ戦いは終わっていないのだ。
レクが心配だし、なにより御玲が―――。
「新人も、それでいいだろ?」
西支部監督官がバカ新人の顔も伺う。
バカ新人は尚も不満タラタラな表情で俺を睨んでいたが、わざとらしい舌打ちをするのみで、それ以上は何も言ってはこなかった。
バカ新人からの熱い視線を背後から感じながらも、レクたちが戦っている地下シェルターへ歩を進める。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

法術装甲隊ダグフェロン 永遠に続く世紀末の国で 『修羅の国』での死闘
橋本 直
SF
その文明は出会うべきではなかった
その人との出会いは歓迎すべきものではなかった
これは悲しい『出会い』の物語
『特殊な部隊』と出会うことで青年にはある『宿命』がせおわされることになる
法術装甲隊ダグフェロン 第三部
遼州人の青年『神前誠(しんぜんまこと)』は法術の新たな可能性を追求する司法局の要請により『05式広域制圧砲』と言う新兵器の実験に駆り出される。その兵器は法術の特性を生かして敵を殺傷せずにその意識を奪うと言う兵器で、対ゲリラ戦等の『特殊な部隊』と呼ばれる司法局実働部隊に適した兵器だった。
一方、遼州系第二惑星の大国『甲武』では、国家の意思決定最高機関『殿上会』が開かれようとしていた。それに出席するために殿上貴族である『特殊な部隊』の部隊長、嵯峨惟基は甲武へと向かった。
その間隙を縫ったかのように『修羅の国』と呼ばれる紛争の巣窟、ベルルカン大陸のバルキスタン共和国で行われる予定だった選挙合意を反政府勢力が破棄し機動兵器を使った大規模攻勢に打って出て停戦合意が破綻したとの報が『特殊な部隊』に届く。
この停戦合意の破棄を理由に甲武とアメリカは合同で介入を企てようとしていた。その阻止のため、神前誠以下『特殊な部隊』の面々は輸送機でバルキスタン共和国へ向かった。切り札は『05式広域鎮圧砲』とそれを操る誠。『特殊な部隊』の制式シュツルム・パンツァー05式の機動性の無さが作戦を難しいものに変える。
そんな時間との戦いの中、『特殊な部隊』を見守る影があった。
『廃帝ハド』、『ビッグブラザー』、そしてネオナチ。
誠は反政府勢力の攻勢を『05式広域鎮圧砲』を使用して止めることが出来るのか?それとも……。
SFお仕事ギャグロマン小説。
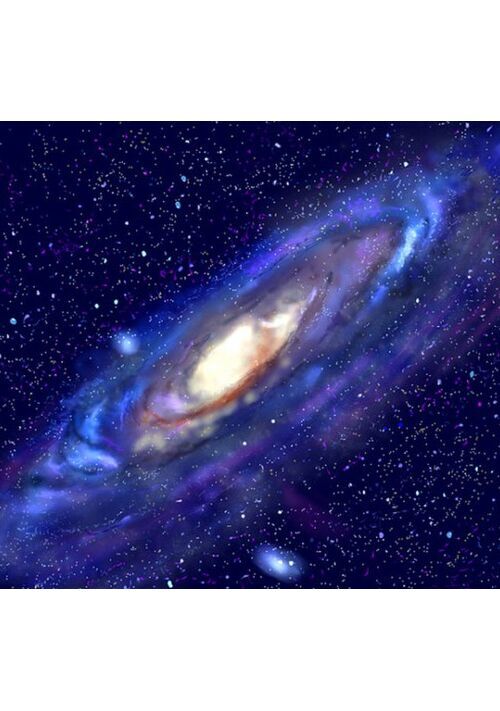
銀河文芸部伝説~UFOに攫われてアンドロメダに連れて行かれたら寝ている間に銀河最強になっていました~
まきノ助
SF
高校の文芸部が夏キャンプ中にUFOに攫われてアンドロメダ星雲の大宇宙帝国に連れて行かれてしまうが、そこは魔物が支配する星と成っていた。

セルリアン
吉谷新次
SF
銀河連邦軍の上官と拗れたことをキッカケに銀河連邦から離れて、
賞金稼ぎをすることとなったセルリアン・リップルは、
希少な資源を手に入れることに成功する。
しかし、突如として現れたカッツィ団という
魔界から独立を試みる団体によって襲撃を受け、資源の強奪をされたうえ、
賞金稼ぎの相棒を暗殺されてしまう。
人界の銀河連邦と魔界が一触即発となっている時代。
各星団から独立を試みる団体が増える傾向にあり、
無所属の団体や個人が無法地帯で衝突する事件も多発し始めていた。
リップルは強靭な身体と念力を持ち合わせていたため、
生きたままカッツィ団のゴミと一緒に魔界の惑星に捨てられてしまう。
その惑星で出会ったランスという見習い魔術師の少女に助けられ、
次第に会話が弾み、意気投合する。
だが、またしても、
カッツィ団の襲撃とランスの誘拐を目の当たりにしてしまう。
リップルにとってカッツィ団に対する敵対心が強まり、
賞金稼ぎとしてではなく、一個人として、
カッツィ団の頭首ジャンに会いに行くことを決意する。
カッツィ団のいる惑星に侵入するためには、
ブーチという女性操縦士がいる輸送船が必要となり、
彼女を説得することから始まる。
また、その輸送船は、
魔術師から見つからないように隠す迷彩妖術が必要となるため、
妖精の住む惑星で同行ができる妖精を募集する。
加えて、魔界が人界科学の真似事をしている、ということで、
警備システムを弱体化できるハッキング技術の習得者を探すことになる。
リップルは強引な手段を使ってでも、
ランスの救出とカッツィ団の頭首に会うことを目的に行動を起こす。

特殊部隊の俺が転生すると、目の前で絶世の美人母娘が犯されそうで助けたら、とんでもないヤンデレ貴族だった
なるとし
ファンタジー
鷹取晴翔(たかとりはると)は陸上自衛隊のとある特殊部隊に所属している。だが、ある日、訓練の途中、不慮の事故に遭い、異世界に転生することとなる。
特殊部隊で使っていた武器や防具などを召喚できる特殊能力を謎の存在から授かり、目を開けたら、絶世の美女とも呼ばれる母娘が男たちによって犯されそうになっていた。
武装状態の鷹取晴翔は、持ち前の優秀な身体能力と武器を使い、その母娘と敷地にいる使用人たちを救う。
だけど、その母と娘二人は、
とおおおおんでもないヤンデレだった……
第3回次世代ファンタジーカップに出すために一部を修正して投稿したものです。

世紀末ゾンビ世界でスローライフ【解説付】
しおじろう
SF
時は世紀末、地球は宇宙人襲来を受け
壊滅状態となった。
地球外からもたされたのは破壊のみならず、
ゾンビウイルスが蔓延した。
1人のおとぼけハク青年は、それでも
のんびり性格は変わらない、疲れようが
疲れまいがのほほん生活
いつか貴方の生きるバイブルになるかも
知れない貴重なサバイバル術!

忘却の艦隊
KeyBow
SF
新設された超弩級砲艦を旗艦とし新造艦と老朽艦の入れ替え任務に就いていたが、駐留基地に入るには数が多く、月の1つにて物資と人員の入れ替えを行っていた。
大型輸送艦は工作艦を兼ねた。
総勢250艦の航宙艦は退役艦が110艦、入れ替え用が同数。
残り30艦は増強に伴い新規配備される艦だった。
輸送任務の最先任士官は大佐。
新造砲艦の設計にも関わり、旗艦の引き渡しのついでに他の艦の指揮も執り行っていた。
本来艦隊の指揮は少将以上だが、輸送任務の為、設計に関わった大佐が任命された。
他に星系防衛の指揮官として少将と、退役間近の大将とその副官や副長が視察の為便乗していた。
公安に近い監査だった。
しかし、この2名とその側近はこの艦隊及び駐留艦隊の指揮系統から外れている。
そんな人員の載せ替えが半分ほど行われた時に中緊急警報が鳴り、ライナン星系第3惑星より緊急の救援要請が入る。
機転を利かせ砲艦で敵の大半を仕留めるも、苦し紛れに敵は主系列星を人口ブラックホールにしてしまった。
完全にブラックホールに成長し、その重力から逃れられないようになるまで数分しか猶予が無かった。
意図しない戦闘の影響から士気はだだ下がり。そのブラックホールから逃れる為、禁止されている重力ジャンプを敢行する。
恒星から近い距離では禁止されているし、システム的にも不可だった。
なんとか制限内に解除し、重力ジャンプを敢行した。
しかし、禁止されているその理由通りの状況に陥った。
艦隊ごとセットした座標からズレ、恒星から数光年離れた所にジャンプし【ワープのような架空の移動方法】、再び重力ジャンプ可能な所まで移動するのに33年程掛かる。
そんな中忘れ去られた艦隊が33年の月日の後、本星へと帰還を目指す。
果たして彼らは帰還できるのか?
帰還出来たとして彼らに待ち受ける運命は?

大工スキルを授かった貧乏貴族の養子の四男だけど、どうやら大工スキルは伝説の全能スキルだったようです
飼猫タマ
ファンタジー
田舎貴族の四男のヨナン・グラスホッパーは、貧乏貴族の養子。義理の兄弟達は、全員戦闘系のレアスキル持ちなのに、ヨナンだけ貴族では有り得ない生産スキルの大工スキル。まあ、養子だから仕方が無いんだけど。
だがしかし、タダの生産スキルだと思ってた大工スキルは、じつは超絶物凄いスキルだったのだ。その物凄スキルで、生産しまくって超絶金持ちに。そして、婚約者も出来て幸せ絶頂の時に嵌められて、人生ドン底に。だが、ヨナンは、有り得ない逆転の一手を持っていたのだ。しかも、その有り得ない一手を、本人が全く覚えてなかったのはお約束。
勿論、ヨナンを嵌めた奴らは、全員、ザマー百裂拳で100倍返し!
そんなお話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















