41 / 94
参上! 花筏ノ巫女編
騒々しい戦後処理
しおりを挟む
「……みお……さ……」
誰かの声が聞こえる。心地いい。女の子の声だろうか。
「……みお……!」
聞き覚えがあるような、ないような。そういえば俺、どうなったんだっけ。すっげぇ深く眠っていたような感覚だ。眠い。
「すみお……!」
この声、もしかして澪華。澪華なのか。すまん、寝てた。今行くぜ。
「れいがッ!?」
「あだっ!!」
「何やってんだお前ら……」
御玲が額に手を当てながらプルプルと震える。どうやら俺が勢い余って起き上がり、御玲のおでこに頭突きしちまったらしい。結構勢いつけたから、相当痛かったかもしれない。
「えっと……す、すまん。勢い余って……」
「んもうっ!」
「あだッ、ご、ごめんて!」
おでこに手を当てながら、片手で肩を引っ叩かれた。やっぱ結構痛かったらしい。割と本気で叩かれてしまった。
「まったく、おめでたい野郎だぜ。俺らがどんな目にあったかもしらねぇでよ」
金髪野郎の皮肉めいた言葉で、俺は初めて周囲の状況に気づいた。みんなの顔色が何故かあんまり良くない。というかどんよりしている。
見るからに南支部の執務室のようだが、戻ってきているということは、戦いは終わったってことだろう。なのにまるで戦いに負けたかのような雰囲気。戦死者が出たとでも言うのだろうか。
「あっ、そういや御玲!! お前怪我!!」
眠気が覚めてきた影響で、思考もはっきりしてくる。
そういえば俺が覚えている最後の情景は、御玲の腹に真っ黒の矢がぶっ刺さって、まるで死んだかのように倒れこんだ場面だった。
なにがなんでも仲間は守ると誓ったはずなのにそれができなくて自分を責めて、色々後悔して、精神がドス黒い何かに埋め尽くされて、視界が赤黒く染まって―――。
また俺は、溢れ出てくる破壊衝動に身を任せたんだった。
「それなら大丈夫ですよ、カエルが治してくれましたので。というか、見て分かりません?」
俺の表情から抱いている感情を悟ったのか、まだ額をごしごしと撫でながら、小さくため息を吐いてジト目で見つめてきた。言われてみればそうだった。
スケルトン系魔生物の攻撃は魔法毒とかいう劇物に塗れている以上、治療できてなかったら、呑気に膝枕できているわけがない。
むしろ俺よりも大怪我をしたはずの御玲が、無事でいてくれたことに例えようのない嬉しさを感じると同時、自分の凄まじい不甲斐なさでメンタルが死にそうになる。
今回もまた仲間に助けられた。明日にでも澄連に礼を言っておく必要がある。いつもはふざけていて何を考えているのか分からない連中だが、やっぱりここぞというときの頼もしさは凄まじいものである。
「ようやく起きたか。まちくたびれたぞ」
メン死寸前の心を保つため、澄連が先に家に帰ったことを御玲から聞くことで話題を逸らしていると、猫耳パーカーの隣で軽い定食を食っている身に覚えのない巫女が目に入った。
猫耳パーカーより背が高いだろうか。下手したら俺と同じくらいありそうな体躯だが、ソイツはお通夜みたいな雰囲気などなんのその、特に周りなんぞ気にせず、むしゃくしゃと飯を食うのみである。
こんな奴、メンバーにいなかったはず。何故だろう。全く身に覚えもないし、顔を見たところで名前も全く思い浮かばないのだが、どこか謎に親近感を感じるのは―――。
「ああ! 今朝、北支部の駐車場にいた奴じゃねぇか!」
頭がぼんやりしていて思い出すのに時間がかかったが間違いない。南支部に行く直前、暑がりの御玲のために清涼飲料水を買いに行くべく北支部の駐車場に行ったとき、チンピラをボコボコにしていたあの巫女である。服装や顔、髪型からして確実だ。
「そなたには西に行った後、南に向かうと言うたはずじゃがの」
澄まし顔で答える巫女。記憶の戸棚を漁るが記憶にない。ぼんやりとそんなこと言っていたような、そんな気がするぐらいだ。
悪いが、覚えていないので話をしていても仕方がない。重要そうでもないし、とりあえずは捨ておくことにして俺が把握するべきは今の状況だ。
サクッと巫女を視線から外し、金髪野郎の方を向く。
「片付いたよ。一応な。つっても、俺らはほとんど何もしてねぇけどよ」
「は?」
呆れ半分の表情を浮かべ、飯を貪る巫女の方に視線を投げた。そんで俺が意識を飛ばしていた辺りの話を掻い摘んで話してくれる。それを聞いていくにつれ、俺の理解力はどんどん現実に追い抜かされていく。
「待って、待ってくれ。意味分かんない。どゆこと?」
「どういうことも何も、言った通りだ。正直俺もお手上げなんだよ」
「んだよそりゃあ。あの巫女が全部一人で片したことしか分かんなかったぞ……」
「俺らもそこで理解が止まってんだよ。だから雁首揃えて話すかってところで、お前が起きたんだ」
つまり、巫女がわけわからんことをして全てを片付けてしまったので、状況を整理するために話し合おうとみんな集まったわけだ。それで俺は今まで呑気に寝ていて、話そうかってタイミングで起きてしまったと。
うん、もう少し寝ておけば良かったと後悔したが、もう遅い。これは俺も参加しないと面倒になるヤツだ。正直詳しいことも気になるし、かなり嫌な予感もするがここは余計な波風を立てないようにするためにも、参加の意思表明はしておこう。
「あとさりげになかったことにしてるが、暴走したことに関して、お前も釈明してもらうからな? だからもう寝るんじゃねぇぞ」
全く今年の新人はどいつもこいつも……と金髪を掻きむしりながら背伸びをする。
絶対面倒だし、胸騒ぎレベルで嫌な予感もしていたから、このまま話を聞くだけ聞いて一切話題に挙げないようにしようと思っていたのに、やはりこのままスルーとはいかないようだ。
釈明と言われても俺が言うことは変わらないし、なるべく脚色するにしても、最悪いざとなったら馬鹿正直に言うしかないだろう。深く考えたって仕方ない。
「んで、まずは……だ。百代……っつったっけか。お前、ホントに今年来た新人なんだな?」
「一年からそう聞いとらんか?」
「まずよ、その``ひととせ``ってトト・タートのことでいいんだよな? そこから整理したいんだが」
キョトンとした顔で金髪野郎を見つめる巫女。そのリアクションに、金髪野郎は項垂れてため息をついた。
話の意味が分からなかったので、御玲の肩を肩で小突いて補足説明させる。俺が寝ている間に話していたことらしいが、いま金髪野郎が話している``モモヨ``と名乗る巫女は、どうやら俺らと同じぐらいの時期に北支部へ就職してきた新人らしい。
つまり俺らと同期なわけだが、それにしても俺らのときと違って金髪野郎の巫女に対する当たりが強いのが妙に気になった。
「そうじゃぞ。素性を知られるのは面倒でな、名を偽るようにと命じておったのじゃ」
「名を偽るように命じてた? それを速攻バラしてたのお前じゃなかったか?」
「姓から名まで全て変えとるとは思わなかったんじゃ! わっちとしては、姓さえ変えておれば名はそのままでも良かったのに!」
ぷんすかと頬を膨らませ、ソファの上でジタバタとし始める。
横でトトが「申し訳ありません、姉様」とか言っているが、完全にコイツの指示がガバガバだっただけではと、思わずにはいられない。
「ま、まあいい。お前とトトの関係はそういうことにしておこう。それでさっきの質問に戻るが」
金髪野郎も深く探る気はないのか、サクッと話題を切り替える。さっきの質問とは、モモヨとかいう巫女が北支部の新人って話である。
「確かにわっちは今年の六月末に北支部に就いた者じゃが、それの何が問題だというのじゃ?」
「問題だから話題にしてるんだろ? 第一、その頃の新人だっつーんなら、二週間前くらいに起こったアンドロイド防衛戦や魔生物のスタンピートのときは何してたんだ」
俺は女アンドロイドとの死闘や、無限に湧いてくるアぺス狩りを振り返る。
確かに六月末っていえば女アンドロイド率いる二万のアンドロイド兵団が、中威区を埋め尽くした時期とバッティングしているが、そのときに巫女姿をした女など、一度たりとも見かけはしなかった。
大半が大なり小なりある程度の装備を整えていた服装をしている中で、コスプレ紛いの巫女服なんぞ着ていたら、誰かは分からなくとも印象には残っていたはずだ。
ワンチャン俺がクソ間抜けにも見逃していたとして、御玲がマークしていないわけがないのである。俺は御玲に目線を投げるが、御玲は静かに首を左右に振った。
「そ、その! その事に関しては、私の方から説明をですね……」
「あ? なんでお前なんだ。俺はコイツに聞いてんだよ」
何故か百代を庇うように猫耳パーカーが、二人の間に割って入る。猫耳パーカーやモモヨと名乗る巫女からは、顔に汗が滲んでいるせいか、蛍光灯の光で顔がテカっているように見える。
金髪野郎は、やはりプロだ。彼女たちの表情の変化を見逃さない。眉間に大きく皺が寄った。
「……よい、一年」
モモヨと名乗る巫女はハンカチで顔にべったりと張り付いていたであろう汗を拭きとると、さっきまで焦りを感じさせていた表情は一瞬にして消え失せ、意を決したように深く深呼吸をした。
「あれはわっちの独断でやった事。そなたが責を負う必要はない」
「し、しかし姉様……」
「くどい。必要はないと言っている」
それは、凄まじい圧だった。
わけのわからなさに若干辟易していた俺や御玲も、怪訝な表情で二人を睨んでいた金髪野郎も、モモヨから放たれた、一際低い声音に含まれる圧力にグッと体を絞られるような感覚に襲われる。
口から全身にかけて、金縛りにでもあったかのように腕や足を動かすことも、言葉を発する事も一瞬だけだができなくなる。そんな圧力を間近に受けた猫耳パーカーなど、もはや蛇に睨まれた蛙だった。
「わっちから話そう。単刀直入に言うなれば、あのときは此処……南支部におったわ」
流石は北支部の万年監督請負人である。彼女の台詞を聞いた瞬間、百代の圧に気圧されていたことを悟らせず、圧をかけ返す。ポンチョ女も何故だか暗澹とした目でモモヨたちを睨み、粘り気の強い敵意を露にする。
北支部所属のモモヨが南支部にいた。それの何が問題だというのか。そういうこともありうるだろうに、金髪野郎たちから醸し出される雰囲気は俺の予想を超えて重く冷たいものだった。
「……一つ聞く。お前、``支部個人防衛の原則``と``緊急時所属支部防衛の義務``は知ってるな?」
俺は聞き覚えのない用語が出てきたので御玲に「なにそれ?」と小声で聞いてみる。御玲はすっごい呆れ顔を浮かべながらも、小声で解説してくれた。
まず``支部個人防衛の原則``っていうのは、その支部に所属する請負人は敵性勢力からの侵略を受けた際、原則所属している支部を自力で守るというルールのこと。
原則だから状況次第では強制じゃないらしいが、今回みたいにお互い合意の上で合同任務をするって前提がない限りは、その支部にふりかかる災禍は、その支部が自力でなんとかするのが筋なのだ。
確かに言われてみればそうで、各支部には各支部の都合ってもんがある。他の支部に構っている暇は基本的にないし、今回の合同任務だって南支部の即戦力が女アンドロイド戦でほとんど潰れちまったから、それを補填するっていう特別な理由があってこそ成り立った任務である。何も間違った話ではなく、めちゃくちゃ筋が通った話だった。
次に``緊急時所属支部防衛の義務``だが、これはフェーズS以上の緊急任務発令時、その支部に所属する請負人は、必ず所属している支部を守らなければならないっていうルールのことだ。
通常任務までは原則だったが、緊急任務発令時はお互いの支部代表が合意の上で、なおかつ各支部に緊急配属される本部所属の任務請負官同士の合意もあってようやく成り立つ``支部連合体制``を整えない限り、その支部から離脱して、請負官の指示を無視した勝手な行動をとってはならないってことである。
そういえば名前は忘れたけど、女アンドロイド戦のときに任務請負官が本部から派遣されていたことを思い出す。
あのときは俺たちも色々考えた結果、独断で動くことを決めたが、アレは結局金髪野郎たちに本部を支配しているさらに上の連中から指令が出たとかなんとかで俺らはお咎めなしになっていたわけだが、モモヨに関してはそうじゃなかったようだ。
心の中で、また機関則絡みの話かと半ば落胆する。
「就任時、目は通した。処するのなら、好きにするがよい」
「待てよ。お前もそこの新人に似て気が早ぇな……」
「ならば、そなたはわっちに何を望む?」
「いや、状況が朧げながら見えた。もう一つ確認する。トト、実は南支部、結構痛手食らってたんだろ?」
その一言に存在感を一切消していた猫耳パーカーがフードから顔を出した。そして、事の経緯を説明し始める。
二週間前に起きたアンドロイド防衛戦。俺たちが首魁だった女アンドロイドと戦っている間、南支部の連中もまた己の支部を守るため、女アンドロイドが召喚したアンドロイド軍団と戦っていた。
アンドロイド軍団は確か当時、二時間以内に北支部にカチコミかけられそうになっていたから、各支部を中心に二時間以内で侵略可能な範囲内に召喚されていたものと俺は予想していたのだが、実はアンドロイド軍団が最初に召喚された場所が南支部近辺だったらしい。
南支部は不幸にも各支部のうち最も早く襲撃を受けるハメになってしまったそうで、情報が全くない非常に不利な状況で立ち回ることになってしまった。
だが現実は容赦がない。南支部に更なる追い討ちをかけるように、非情な事実を突きつける。
南支部に所属するほとんどの請負人は五十をすぎたオッサンたちばかり。それも主戦力になりうるオッサンたちでさえ精々全能度は二百、三百あるかないかの奴が数人程度という有様で、数千を超えるアンドロイド軍団に対し、多勢に無勢であることは誰が見ても明白な状態だった。
それでも支部を放棄するわけにはいかない。オッサンたちにとって、南支部は自分たちの生活を繋ぐライフラインだ。陥落したら、路頭に迷うことになってしまう。多勢に無勢であることを知りながらも、オッサンたちは猫耳パーカーとともにアンドロイド軍団を迎え撃つことを決意する。
だがしかし。まあ、当然というべきか。結果は見えていた。
猫耳パーカー以外はロクに戦うこともできないまま次々に負傷。早々と撤退せざる得なくなり、最後は猫耳パーカーが孤軍奮闘するハメになってしまった。
それだけじゃない。猫耳パーカーはアンドロイド軍団をたった一人で相手する傍ら、アンドロイド軍団の攻めが緩んだ隙を見計らい、支部で休んでいたオッサンたちの治療を同時並行で行いつつ、隙が無くなり始めたら戦場に戻るという重労働を延々と繰り返していたという。
まさにギリギリの戦線をたった一人で維持していたわけだが、若い肉体にアンドロイド軍団の物量は流石に堪えるものがある。ほんの僅かでも疲れを見せてしまったら南支部の戦線は完全に崩壊してしまう状況で、猫耳パーカーは非常手段として姉であるモモヨに助けを求め、南支部の守りを固める判断を下した。
だがこの時点では、猫耳パーカーはモモヨが北支部に就職していることを知らず、時は一刻を争う状況だったので詳しい話をしなかったらしいのだが、戦況が落ち着いてきた頃合いで、実は北支部に就職していたことを暴露してしまったため、そのときになって「やばい」と冷汗をかいたという。
北支部のメンツに知られれば責任追及は免れない。どう言い訳しようか、それとも隠蔽すべきかを考えた頃に、金髪野郎から任務請負証の霊子通信が届いた場面に繋がるそうな。
俺は条件反射で「へー」と言いながら特に何も考えずぼけーっと聞いていたが、御玲が一人「あー、なるほど」と勝手に理解し始める。
「えっと……?」
「澄男さま、記憶にありませんか。女アンドロイド戦のとき……トト・タートの言葉」
記憶の戸棚を手当たり次第にこじ開けまくるが、全く思い出せない。あのときの会話はほぼ蚊帳の外だったから、覚えているわけがないのである。俺に話していたわけでもなし、完全に猫耳パーカーと金髪野郎の間で収束していた会話だったし、そんなのを俺が覚えていることに期待する方が、無理がある。
そんな俺を見て、御玲はこれまた全力呆れ顔で俺を睨みながら、大きくため息をついた。
「トト・タートは言ってました。『私の友人っす。結構腕っ節が強くて、余程のことがねー限り負けはしねーんで』と」
ご丁寧に声真似までやって、台詞を再現してくれる。
声真似が妙に上手い上によくもそんな一文字も違わず他人の台詞を覚えていることに心底驚いたが、寸分違わず再現されてもやはり思い出せはしなかった。そういやそんなこと言っていたような気がする、程度である。
「だからですね……要するにトト・タートは、モモヨの存在を隠ぺいする道を選んだわけです」
記憶に何も留まっていないせいで全然理解が進まない俺に、猫耳パーカーに変わって御玲が説明を始める。
当時、北支部の面々―――つまり俺たちは女アンドロイドの動向はおろか、アンドロイド軍団の情報すらほとんど得られていなかった。それは女アンドロイドの軍展開が速すぎたせいだが、俺たちもあのときは久三男が得た情報を、違和感なく金髪野郎たちにどうやって伝えるかを悩みあぐねていた。
それと同じく猫耳パーカーも本当のことを言うべきか悩んでいたが、既に北支部にもアンドロイド軍団の被害が出ている背景を、当時の任務請負証での霊子通信でやっていた金髪野郎との話し合いから読み取った上で、場を混乱させるのを防ぐために``北支部所属の請負人が南支部にいる``ことを隠すことに決めたのだ。
俺たちはなんとか四苦八苦した末に正しい情報を金髪野郎に伝えられたが、南支部には都合よく澄連みたいな使い魔がいるわけもなし。ただでさえ致命的な戦力不足の状況で、正しい情報を伝えるための労力を割く余裕はほとんど残されていなかった。
だから猫耳パーカーは南支部の未来と機関則を天秤にかけた上で、南支部の未来を選んだわけだ。
正直に話すという手も勿論あっただろうが、俺も請負人として活動する上で久三男の存在を隠さなければならないという名目がある以上、気持ちは凄く分かる。正直に話すというのは、ときにかなりのリスクを伴うものだ。余裕がないなら、尚更リスクなど背負いたくないと考えるのが道理ってものである。
この場合、ルール違反になるとはいえ、ある意味で猫耳パーカーは状況に応じた安牌な判断を下したと、俺は素直に思えた。
「南支部が予想以上の痛手を食らってたのは納得できるが……それでも、だ。モモヨ、お前は北支部所属だろ? 当時は緊急任務発令中だってのに他の支部で戦ってたのは、ちょっとばかし勝手がすぎるな」
金髪野郎は目を吊り上げ、ドスの利いた声でモモヨに凄む中、俺の胸中に言い知れないモヤモヤが渦巻いた。
機関則については粗方理解したし、モモヨたちの事情も理解した俺だからこそ、やはりモヤモヤは晴れない。
猫耳パーカーは純粋に南支部とオッサンたちの未来を思い、モモヨは妹分を助けるためにルールを犯してでも助けに行った。仲間は絶対に大切にするべき、そうしない奴は裏切り者と同じという考え方の俺から言わせれば、コイツらの行動はルール違反であれどスジは通っていると確信している。
だが、それを心の中で思っているだけじゃ仕方ない。口に出さないと伝わらないのは考えるまでもないことだが、この気持ちを伝えたくても自分の説明力など信用するだけアホである。今回は珍しく金髪野郎が擁護する気皆無っぽいし、いま言わなければずっとモヤモヤしたままになるだろう。
悪いが俺は言いたいことを我慢してその場は割り切ってみせるほどオトナじゃない。正直無理筋かもしれないが、無理を通せば道理が引っ込むという言葉もある。モヤモヤしてイライラするくらいなら―――。
「コイツはコイツで事情があったんだろうよ。第一、妹がいたんだ。そりゃそっちに肩入れするのが道理ってもの……」
「は? なめんなよ」
胸中に渦巻くモヤモヤを晴らすため、思わず反論してしまったが案の定噛みつかれる。
噛みつかれるところまでは予想はしていたし、ルールについては理解できてもモモヨたちの事情を何一つ汲み取れていないからこそ口に出したわけだが、まさか言い終える前に噛みつかれるのは流石に予想外だ。
俺は眉間に皺がより、思わず握り拳を強く握った。
「こんなにつえーやつがいたのなら、きたしぶのふたんをかるくできたはずだ。なんならおまえらのぬいぐるみどもだって、きたしぶぼーえーにさくひつよーもなかったかもしんねー。でもコイツはきたしぶにいなかった」
「いやだからそれは……」
「もしせんりょくがそろってたらあのとき……レクがしにかけにならずにすんでたかもしんねーんだぞ? それ、わかっていってんのか」
口から出かかった反論が、無造作に塞がれる。ポンチョ女には珍しく、正論をブチかましてきやがった。
確かにあのとき、金髪野郎は死にかけた。偶然雲隠れしていた百足野郎とポンチョ女のおかげで首の皮一枚繋げられたわけだが、もしもあのとき北支部に十分な個人戦力が揃っていて、澄連を北支部防衛に回す必要がなかったら―――金髪野郎は無傷で済んでいた可能性は十分にあった。
無傷とは言わずとも、生死の境を彷徨う可能性は限りなく低かっただろう。カエルが使える謎の回復魔法``蘇・生``なら腹をブチ抜かれた程度、簡単に治癒してしまえるはずだから。
「で、でもよ。それでもコイツらにはコイツらなりの……」
それでも俺の考えは変わらない。ルールについては理解できても、そのルールはモモヨたちの事情を全く汲みとってはくれないものだ。何もなかったなら、そのルールに従うことに異論なんてないけど、今回はモモヨたちにやむおえない事情があった。それを汲みとれるのはルールじゃない。人間の俺たちのはずだ。
「だったらオレらとみなみでれんごーくめばよかったんだ」
俺の思いも虚しく、ポンチョ女には全く届く様子がない。それどころか暗澹とした瞳に宿る闇で俺を蝕みながら、反論をどんどんヒートアップさせていく。
「みなみのうけおいかんとあーしらのうけおいかんにたのんで``しぶれんごーたいせー``をくむよーにせーきのてつづきふんでりゃあ、レクだってことわりゃあしなかっただろうよ。でもじっさいはかってにあーしらのしぶのせんりょくつかっちまったんだろ? だったらルールいはんいげーのなにもんでもねーんだよ」
「はぁ? お前さ、猫耳パーカーの話聞いてなかったのか? 要はその手続きとやらを踏む余裕がなかったってっこったろうが」
「よゆーがなかったのはウチだって、どこのしぶだっておなじだろ。よゆーがねーからって、よそのしぶのだいひょーが、てめーがってなはんだんで、よそのしぶのせんりょくをかってにつかっていーわけがねーだろーが。だから``きんきゅーじしょぞくしぶぼーえーのぎむ``と``しぶれんごーたいせー``ってのがあんだよ、わかったらいーかげんきかんそくよんでこいぺーぺーのしんざんクン」
いつもなら金髪野郎が仲裁に入るはずなのに、なぜだか今回ダンマリを決め込んでいた。御玲も特に反論する様子もない。
ものすごく言い方が癪に障るし、なんなら煽られてすらいるが、悔しいことに俺も反論することが表立って思いつかなかった。
百代と猫耳パーカーの顔を見る。アイツらはアイツらで守るべきものを守るために行動したんだ。俺だって久三男や弥平が危機に陥っていたら、たとえ自分の立場とか関係なく助けに向かうし、御玲が遠い場所で死にかけていたらなにもかもをかなぐり捨ててでも御玲を救い出しに行く。
モモヨとかいう奴も同じように、妹の猫耳パーカーが危機だったからこそルール違反であることを知りながら、北支部防衛につかなきゃならないところを無断で抜け出して、猫耳パーカーの所へ向かったんだ。
だからコイツのやり方は間違っちゃいない。機関則がどうのこうの以前に、コイツはコイツのやるべきをやったんだ。それなのにルール違反とかいう、そんな薄っぺらい言葉でこの巫女たちを断罪するってのか。
クソが。もういい。どっちみち拗れるが、俺はここで我慢するほど出来た人間じゃねぇ。もうなるようになれだ。
「ははは。ルール違反ルール違反とそれしか言う能がねぇのかテメェは」
何も考えず、ただ胸底に渦巻くどす黒い感情を、頭の中に浮かんだ言葉そのままに写して吐き捨てる。予想通り、ポンチョ女の眼光が光った。明確な敵意が、視線から痛いほど伝わってくる。
「いやぁ……コイツらにも事情があったろうに、それを汲み取らず機関則に振り回されてるとか、テメェはルールがないと生きてけねぇの? それがねぇと何が正しいか分かんねぇとか言っちゃうタチか?」
「みんながまもってこそいみがあんだよ、だれかがみだせばそこからなにもかもがほころびる。ただのむほーになりさがる。そこにただしさなんかあるわけねーだろ。だからルールってのがあんだよ」
「ハハハ!! 要するに自分で何が正しいか決めるだけのお頭がないヴァカってことですね分かります!! よくもまあその程度で先輩ヅラできたよなー、無自覚って怖い怖い」
「あーそーだよ、ばかだよ。にんげんみんなばかだから、なにがただしいかわかんねーから、みんなでがんくびそろえて、ちからあわせて、ちえだしあって、ルールってもんをきめるんだろ。そのルールのいみすらりかいできねーぶんざいで、ガタガタぬかしてんじゃねーよヒヨッコが」
「ガタガタぬかしてんのはテメェだろうがよ!! テメェが黙ってりゃ俺だってガタガタぬかす必要もなかったんだ、責任転嫁してんなよ?」
「せきにんてんこしてんのテメーだろうが!!」
ポンチョ女の顔が般若のように歪み、全身から暗黒の瘴気が薄っすらと漂う。
光が消えた瞳に映るのは、一切光を通さぬ漆黒の闇。その闇は沸騰し、刃となって俺に襲いかかる。
「テメーマジでいいかげんにしろよ? まえのあんどろいどのころからおもってたけどよ、わをみだしてんじゃねーよ!! きかんそくもよむきねーし、そのくせきにくわなかったらやぶろーとするし……いっとくけどな、レクがくそゆーのーってだけだからな? あーしだったらテメーみてーなむのー、すぐクビにしてやるわ!!」
「へぇ!! そいつァおもしれェ!! 要は後輩の面倒もロクに見れねぇ無能ってことじゃねぇかァ!! 都合が悪くなればコーハイのせいですかはいはいセンパイなんてえらいんでしょーか百足野郎がいなきゃ戦力外のクソザコナメクジなのに口だけは立派立派あーこの程度でセンパイヅラできるんならホントマジで楽な仕事だよなァ!!」
ばりん、とガラスが粉々になったかのような音が炸裂した。
顔中に冷たい液体がべちゃりとまとわりつく。俺らが座っていたテーブルの上に置いてあった花瓶がなくなっていたことに気づいた。そしてそれが、俺の顔面にブチ当てられたせいだってことも―――。
刹那、頭の中が真っ白になった。目の前のクソアマを亡き者にする。ただそれだけに思考が集約される。
ソファを蹴り壊し、テーブルを突進で踏み倒すと、一瞬でポンチョ女の胸ぐらを掴むが、同時に黒光りした巨大な何かが俺の身体に強く巻きついた。百足野郎の邪魔くせぇ尻尾である。
「やばい、むーさんよせよせよせよせ!!」
「澄男さまだめです!!」
気がつけば、右手に煉旺焔星を練り上げていた。背後からは御玲が振り上げた俺の右手を全力で押しとどめ、金髪野郎が百足野郎とポンチョ女の間に割って入る形で俺とポンチョ女を引き剝がそうと突っ張り棒のように立ち塞がる。
一瞬全てが真っ白に染まったと思いきや、御玲の一声で我に目覚めたわけだが、だからとこみ上げてくる感情がなくなったわけじゃない。
コイツをどうにか黙らせて、俺の主張が正しいって事を認めさせねぇと始まらねぇ。所詮話し合いで解決することなんぞたかが知れている。
さっきも言った気がするが、無理を通せば道理が引っ込む。結局は喧嘩の強ぇ奴の主張が正しい主張になるんだ。
「とりあえず落ち着け!! お前やむーさんがガチ喧嘩なんてしてみろ、この支部吹き飛ぶぞ!!」
「知ったことかよ!! 先に喧嘩売ってきたのはコイツだろうが!!」
「ざけんな!! テメーがナメたクチきいってからヤキいれてやってんじゃねぇか!!」
「ああ!? ヤキいれてやってるだぁ? テメェ誰に向かって口きいてやがる!! ヤキ入れてやるのはこっちだボケが!! 俺を怒らせるな!!」
「ちょ、だからマジでやめろって……!!」
「もうよい!!」
テーブルが粉砕された音が部屋中を走り回る。
テーブルを粉々にしたのは、つい数分前、猫耳パーカーの隣でおにぎりを呑気に頬張っていた、モモヨとかいう巫女だった。
ソイツの顔はいつになく真剣で、眼力から放たれる妙な威圧感がポンチョ女の胸倉を掴む手を緩めていく。胴体に巻き付いた百足野郎も同様だ。
「もうよい。わっちが罰を受ければ済む話。ここでそなたらが争う意味はない」
「ま、待てよ。お前が罰せられる必要は」
「じゃが実際、わっちがるーるとやらを破ったせいで、いま争いが起きておる」
「いやそれは俺が勝手にだな……」
「どちらでも同じことじゃ」
「いやいや……」
「ともかく庇ってくれた御恩だけは受け取ろう。じゃがこれはわっちの意志。無用な争いが治まるのならば、如何ような罰もこの身で受け入れようぞ」
色々言いたかったが、奴の目から放たれる、霊圧に似た尋常じゃない威圧感が、無造作に口を糸で縫いつけていく。
俺の直感も、これ以上の反論は野暮だと何故か叫んでいた。多分、俺が何を言ってもコイツの考えは変わらないと、なんとなーくだが予想がついてしまったからか。
頭を掻きむしり、ポンチョ女を向かい側のソファに突き飛ばす。そしてそのまま、南支部の執務室を後にする。
「澄男さまどちらへ」
「いやー、もうめんどくせぇなって思ってさ。俺の主張とおらねぇし、だったらここにいる意味ないし、気分悪りぃし、もう帰るわ。悪いけど、あとは頼める?」
「はぁ? ざけんな、そんなのゆるされるとおも」
「……うるせぇ黙れよ」
突き飛ばされて背中をソファに強く打ち、半ば咳き込みながら未だに俺につっかかってくるポンチョ女に、ありったけの霊圧をブチこむ。
霊圧の影響でガラス窓は次々と粉々に、壁にはヒビが入り始める。
今の俺は虫の居所がクッソ悪い。正直これ以上ガタガタぬかすようなら流石に目障りだし、本当に跡形もなく消えてもらわなきゃならなくなる。
機嫌の悪いときにやる話し合いほど無意味で無価値なものはない。どうせロクな結果になりゃあしないし、そもそも説明力皆無な俺にマトモな説明を期待するだけ無駄だし、御玲に説明させた方が速くて確実だ。尚更俺の口から語る意味がない。
どうしてさっさとこの事実に気づかなかったのか。それならポンチョ女と無駄に言い争う必要もなかったってぇのに。
「あー……もう分かった。お前は離席でいい……」
百足野郎を背にして、また俺に殴りかかろうと一歩前に足を踏み出しそうとしたポンチョ女の肩を鷲掴み、疲れ切った顔で金髪野郎は追い払うように手を払う。
ちょっとその仕草にムカついたが、それでこの胸糞悪い話し合いから抜けられるなら好都合。俺は鼻で笑ってその仕草に答えた。
「言われるまでもねぇよクソが!!」
とりあえず邪魔なので執務室の扉を蹴破り、俺は一階のロビーへと降りていった。
「んだよアイツ!!」
澄男がいなくなった後、最初に口を開いたのはブルーだった。
テーブルは百代の手によって粉々になってしまったが、もしテーブルが無事だったら足で蹴飛ばすぐらいの事はしていただろう。執務室内の空気は最悪の状態だった。
「えーと……どこまで話したっけか」
「百代さんの処罰に関してですね」
未だ怒りに震えるブルーをよそに、レクは疲れ切った表情で話の内容を思い出す。
澄男によって話を滅茶苦茶にされたため、話題が吹き飛んでしまった。場を荒らすだけ荒らしてさっさと離脱していく自分本位さには毎度のことながら脱帽ものだが、とりあえず澄男の事は捨ておくしかない。優先順位を決めて、一つ一つ処理していくのが一番の近道なのだ。
「そうだったな。とりあえず俺としてもブルーの言い分に賛成だ。悪いが庇う事はできない」
レクもまた、すんなりと自分の意見を述べた。
女アンドロイド戦のときは機関則の抜け道を探してくれた彼だったが、今回ばかりは情状酌量の余地がないとの判断らしい。かくいう自分も澄男の前では何も言わなかったが、百代を擁護する気は全くなかった。
確かに百代にもトトを助けたいという事由があったのは理解できるが、結局のところ百代が個人的な理由で勝手に南支部の都合に首を突っ込んだだけであって、自己責任の範疇を逸脱しない。
もしも公的な理由で南支部を助けたかったのなら、ブルーが言った通り北支部と連合を組むという選択肢もあったはずである。端的に言うなら百代は北支部の請負人との報告、連絡、相談を怠り、勝手な行動をしただけだとも言えるのだ。
彼女は親族を純粋に助けたかったのは本当だろうし、ブルーやレクもその想いを嘘だとは思っていないだろうが、ひどい話、ロボット軍団から北支部を守るために生死の狭間にあった北支部の人間からすれば、関係のない話であった。
「本部には俺から報告しておく。そのうちペナルティが発布されるから、それに従ってくれ」
心得た、と百代は静かに頷いた。
「そんで最後に聞きたいことなんだが……」
レクの視線がモモヨから外される。本来説明するべき人物がいない今、自ずと求められるのは必然だろう。確かにメイドと主人という関係だが、何故、という疑問がないわけではない。全く困った話である。
「あの新人が使ってた魔法? 魔術? みたいなやつ。アレは何だ。悪いが、はぐらかさずに教えてもらえると助かる」
あらかた予想はしていたが、予想は見事に的を穿つ。教えるべきかと一瞬思案するが、レクの表情から誤魔化しは効かなさそうだと判断する。
澄男が使っていた魔法。間違いなく``竜位魔法``のことだ。
はるか昔、竜人族の大国を滅亡寸前に追いやった大災厄``天災竜王``ゼヴルエーレが使っていたとされる大魔法。
彼は紆余曲折を経て、その魔法を継承し、自在に操ることができる。今回澄男は怒りに支配されて暴走し、思わず使ってしまった。効果が発動する前に百代によって阻止されたが、天空に描かれた魔法陣までは、どうにもならなかったのである。
さて、どこから説明したものか。
「……レクさんは``竜位魔法``というものをご存知ですか」
「知らんな。むーさん、なんか知らないか」
半ば不貞腐れているブルーに発破でもかけるように言い放つ。表面上は面倒くさがりながらも、ブルーはポンチョの袖から顔を出す小さな黒百足と対話する。
相変わらずどうやって話しているのか分からないが、表情を見るに対話が成り立っているようだった。いつ見ても不思議である。
「いまいましきさいはてのものどもがつかうみわざ。やはりあのこぞうには、さいはてのちがながれている」
「……ん? んー……と。つまり?」
「さいはてのものどもがつかうひおうだって。このせかいだと……ちょーのーりょく? とおなじもの」
「おいおいそれマジか。エグいってレベルじゃねぇぞ、それ」
超能力と言われてピンとこなければどうしたものかと思ったが、流石は北支部の古株。目を丸くして驚くあたり、その脅威をきちんと理解していたようだ。
「……で、そりゃどんな超能力なんだ?」
どうやら超能力にも種類があることも知っているらしい。これなら説明の手間も省けるというものである。
こほん、と咳払いをして一息ついてから話し出す。
「詳細は、私どももよく分かっていません。しかし、その片鱗なら数度見たことはあります」
説明の手間が省ける、そうは言ったが実のところ話せることは事の経緯を除けばほとんどない。
澄男が竜位魔法を使えることがわかってから、既に三ヶ月余りが過ぎようとしているが、その実体は不明のままだ。垣間見れたのは、彼が激情のままに力を振りかざしたときのみで、その結果どんなことが起こったのかを話せる程度である。
真剣な表情を崩さないレクに、澄男が未だ復讐に囚われていた頃にしでかした破壊の事柄を話した。
全てを話すと機密を漏らすことになってしまうため、あまり詳しい経緯などは話せない。したがって復讐などの込み入った事情は隠し、適当に理由をでっちあげた上で北の魔境大遠征に同伴することになり、全能度四桁の魔生物の軍団を一瞬で消滅させたことを話した。
それを語り終えたとき、レクのみならずブルーまでも、怪訝な表情を浮かべながら目を丸くして唖然としていた。
「おいおい、そんな嘘……なわけねぇか。そのツラ、嘘ついてるようには思えねぇし」
「いや、でもどーやって? そんなまね、できるとしたらむーちゃんぐれーしか……」
「んいや。超能力に原理とか理論とか、そんなもん考えたって無駄だ。そういうもんだと受け入れた方が理解は速い」
レクの冷静すぎる言葉に、ブルーは不満気だったが口を噤んだ。
一見思考放棄に見えるが、実際のところレクの言い分が正しいのだ。超能力など、その能力を持っている者にしか詳細は分からない。魔法や魔術などとは根本的に体系が異なるため、調べることができないのだ。
もしもその不可能を可能にするなら、それこそ超能力を持つ者が別途必要になるだろう。途方もなく阿呆らしい話であった。
「全能度四桁クラスを瞬殺できるとなると……無闇矢鱈に使われたら堪ったもんじゃないな。歩く戦略兵器だぞ」
「澄男さまは竜位魔法の使用を望んではいないようです。ただ、今回のように怒りに支配されたりなどすると、無意識で使用してしまうようですが」
「なら尚更厄介だぜ。要はカチキレたら本人の意志関係なく使っちまう可能性あるんだろ? 節操がないにも程がある」
ですよね、と盛大にため息をつく。
澄男自身、竜位魔法の使用は望んでいない。復讐を経て全てを破壊するよりも、仲間とともに困難を乗り越える道を選んだ彼ならば、怒りに支配されていない限り、自らの意志で破壊の魔法を使うことはないだろう。
しかし澄男の感情制御は、さっきの喧嘩を見ての通り、お世辞にも期待できたものではない。なにかしら考えの相違で意見が対立すれば、譲る精神が皆無な澄男では、どう足掻いても喧嘩は避けられないだろう。
それに、彼にはトラウマがある。大切なものを一気に失ってしまったトラウマ。それが刺激されたとき―――彼の理性は一瞬にして吹き飛ぶことになる。それこそ全てを破壊する、暴力の権化と化してしまう。
どうにかして対処法を考えなくてはならないのだが―――。
レクとともに頭を悩ますが、その反面、名案など簡単には浮かばない。極端な話、彼を怒らせないようにすればいいだけの話だが、そんな方法など。
「なぁ。もーめんどくせーし、ほんぶにみっこくしちまえば?」
沈黙を食い破るように、ブルーが眠たそうな目でこちらを見てきた。しかし、彼女の目を見てすぐさま身構える。その目には光が無かった。見覚えのある、淀んだ瞳だった。
「密告……というと?」
「よーはせーぎょきかねーってはなしだろ? いつなにでかすかわかんねーし、アイツはあんなんだし。だったらよ、かんぜんこーそくしちまえばよくね? って」
淀んだ瞳で、しかし怪しいほど真顔でそう言い放つブルー。驚く一同の中で、一人ため息をつく。彼女の言っていることが、驚くほど予想通りだっただけに。
「ブルー……それ本気で言ってんのか?」
レクの声音は驚くほど低い。声質が怒りに満ちているのは明白だが、ブルーは鼻で笑ってそっぽを向くのみである。
確かに合理的に考えれば、澄男の感情制御に頼るのは悪手だし、他の者がなんとか抑えるとしても、それは確実策とはいえない。
澄男は力だけは無駄に強いため、暴走すると抑えられる者はほとんどいないのだ。ブルーが使役している黒百足ならば拘束できるかもしれないが、今回のように戦場が分断され黒百足からの支援が期待できない場合、百代が救援に来なければ、彼の暴走が収まるのを待つ他ないというのが現状だった。
確実性を期するなら、最初から暴走するような状況に置けないように監視し、必要ならば``人類の存亡を脅かす脅威``として拘束してしまうのが手っ取り早い。リスクも少なく、確実に暴走による二次被害を防げるハイリターンな方法である。
理想的なやり方だ。誰も失わないし困らない。手間もかからないし、確実だ。澄男を人間として扱うのをやめなければならない点を除けば―――。
「……私は、反対です」
ぼそりと独り言のように、だが確固たる意志を持って力強く言い放った。それを感じ取れないほど空気の読めない連中ではない。誰もがこちらに視線を向けた。
「確かに合理的で確実な方法ではありますが、私は澄男さまの専属メイド。彼を裏切るような真似はできません」
ありのままの本心を言った。でも不思議な気持ちになっている自分もいた。
合理的で確実な方法。それを選ばない、選びたくない自分。もはやその選択をすることに今となっては迷いなどないけれど、だからこそかつてこの世の全てに心を閉ざしていた頃の自分が妙に疼き立ててくる。
ブルーが、かつての自分のように思えてくるのだ。昔の自分、澄男と腹を割って本音で語り合う前の自分なら、きっと迷いなくブルーの意見に賛同していただろう。
でも澄男と腹を割ったあの日から、今までとは違う``本当の自分``を見つけようと思ったのだ。自分でもこの変化には驚いているが、あんな自分本位な主人でも、裏切ろうという気にはなれなかった。
たとえどれだけ自分本位で阿呆な人だろうとも、本当の自分を見つけようと思わせてくれた人だから。
「……はーん。そーかよ」
ブルーの瞳から、澱みが消え失せた。尚も不満気だったが、全身から滲み出る敵意が、心なしか弱まった気がした。
レクもブルーからの敵意が弱まったことを悟ったのか、眼力を弱めた。
「ま、メイドが言うんなら仕方ねぇよな。悪いが俺も御玲に賛成だぜ」
仕方ないなどと言いながら、その表情は若干嬉しさに満ちていた。
どうやらレクとしても澄男を拘束するのは不本意だったらしい。ブルーは多数決に逆らう気はないのか、そっぽを向いて鼻で笑うだけであった。
「もし。一つよいかの」
さっきまで沈黙を守っていた百代が、綺麗に挙手をする。その顔は、我に名案ありという文字が、透けて見えるほどに快活な表情をしていた。
「わっち、後々にぺなるてー? じゃったか。そういうものをもらえるのじゃろ?」
「貰えるっつーか、課せられることになるな」
「ならばそのぺなるてーとやら、澄男とやらの暴走をわっちが責任もって食い止める、というのはどうじゃ?」
それを聞き、ブルーはハッと鼻で笑い、レクは顎に手を当てて考え始める。
確かに実力的には適任ではある。というか、現状彼女か黒百足しかいないと言っていい。
暴走した澄男とスケルトン・アークを二人同時に相手取って勝利してのけた強者である。言ってしまえば、暴走した澄男など敵ではないとも言えるのだ。
誰にもできない重労働を率先して行うわけなのだから、一応ペナルティとしての体裁は整う。問題は、それがペナルティとして受理されるかどうか。だが。
「……んー……まあ、ちとかけ合ってみるか」
黙り込んで考え込んでいたレクだったが、本当にそれでいいのかと内心驚く自分がいた。
レクが良いというのなら特に文句はない。ブルーほど機関則保守派というわけでなし、百代の実力も申し分ない。任務請負機関本部とレクが判断するのなら、それに従うまでのことである。
「まあこれで現状の疑問という疑問はなくなったか。色々あったが、解散って事でいいか?」
「澄男さまへの報告は私がしておきます」
「おう。頼んだぜ。ブルーからはなんかあるか?」
「んーや。べーつに」
百代たちも特になし。レクが立ち上がって「んじゃ解散!」と声をかけると、皆立ち上がって外に出た。こうして短かったような長かったような、微妙な反省会は幕を閉じたのだった。
一階のロビーで拗ねているであろう主人のもとへ向かうため、百代たちに挨拶して執務室を後にすると、メイド服の裾を誰かに引っ張られた気がした。
振り向くと裾を引っ張っていたのは、ポンチョの隙間から顔を出す、小型化した黒百足だった。そこから分かる人物は、自ずと知れている。
「おまえ……なんであんとき……あーしを?」
普通の人間ならこんなとき、年端もいかぬ少女が照れながら上目遣いでこちらを見てくるところを想像するだろう。特に男なら尚更かもしれない。だが、現実はそう甘くはないのだ。
彼女の表情からは照れだのなんだのといった甘ったるい感情とは無縁の、熾烈なまでの猜疑心に溢れていた。
あのとき、というのは間違いなくブルーを庇って怪我をしたときのことだろう。
結論から言うと、完全なる善意でやったことだ。他意などなく、自分でも驚くほど損得勘定は一切ない。むしろ損得で動くなら、レクたちは見捨てるのが妥当な判断だっただろう。
澄男の専属メイドであり、彼らを守る義務などありはしないのだから、死んだら死んだで戦死扱いにすればいいだけの話であった。
でも、それでも助けたのは彼女と友達になりたかったからであり、今までの自分なら絶対に選択しないことをしたかったからだが―――。
改めて彼女と視線を交わす。
彼女の顔色を見るに、正直に気持ちを伝えたとて信じてもらえる気がしない。むしろより強い猜疑心を与えてしまうような気がした。自分が逆の立場なら、向けられる義理もない善意を振り撒かれても、より強くその者を疑うだろう。
この世に何の対価なく善意を振りまいて生きていることを公表している者ほど、信用するに値しないのは火を見るより明らかだからだ。
ならば、彼女に言うべきことは既に分かっている。
「小銭稼ぎですよ。レク・ホーランに見捨てられたり、況してや戦死されたりすると、うちの主人のクビがとびかねませんからね。せめてメイドの私が、主人の不評を肩代わりしないと」
「……よーはただのメイドとしてのつとめっていーてーの?」
「そうですけど、何か?」
嘘寄りの本音をとりあえず投げておいた。
レク・ホーランへの小銭稼ぎ、というのは嘘ではない。彼がいてこそ活動できている節が多く、見捨てられれば活動を続けていくのは難しい。
自分本位な理由で所属している組織のルールを平気で破ろうとするような主人である。もはやレクなくして、本部昇進は絶望的と言っても過言ではない。懲戒解雇処分がすぐ隣に迫っているような感覚である。
懲戒解雇された者が復帰するのは難しい。彼の罷り知らぬルールだが、解雇されても組織に不利益を起こした記録は残るのだ。
メイドとしても、懲戒解雇からの復帰という面倒は踏みたくない。そうなるとレクとの繋がりは、自ずと切り離せないものだと充分に言える。
そして彼と行動を共にすることの多いブルーに恩を売っておくというのも、結果的にはレクへの小銭稼ぎの一環という理屈が成立するわけだ。
そういう損得を理解した上で行動してくれればいいのだが、常に直情的な澄男には無理な話であった。
「…………ふーん。まーいーや。せーぜーがんばれよ」
ブルーから警戒色が消えていく。予断許さぬ懐疑心は鳴りを潜め、ポンチョをくしゃくしゃしながら、俯き気にこちらを見てくる。
他人事のように吐き捨てているが、その言葉からは心地良さが感じられた。
「まー……その、なんだ。しんどくなったら、のみにつきあってやる」
「是非に、お願いします」
「いっとっけどおごらねーかんな? オレのかねはオレのもんだからよ」
先輩の癖に先輩らしさが全く感じられないその台詞に、少し笑みが溢れてしまうが、予想は当たったらしい。
これは自分にとって、初めての一歩だ。無駄にはしたくない。いつ叶うか分からないが、澄男の専属メイドとして以外のやりたいことができたのだ。それは純粋に嬉しいことだった。
「では澄男さまの所へ行ってきます」
今すぐにでも彼女と飲みに行きたいが、それはまた今度だ。メイドとしての仕事がまだ残っている。キレにキレ散らかした、澄男の世話である。
誰かの声が聞こえる。心地いい。女の子の声だろうか。
「……みお……!」
聞き覚えがあるような、ないような。そういえば俺、どうなったんだっけ。すっげぇ深く眠っていたような感覚だ。眠い。
「すみお……!」
この声、もしかして澪華。澪華なのか。すまん、寝てた。今行くぜ。
「れいがッ!?」
「あだっ!!」
「何やってんだお前ら……」
御玲が額に手を当てながらプルプルと震える。どうやら俺が勢い余って起き上がり、御玲のおでこに頭突きしちまったらしい。結構勢いつけたから、相当痛かったかもしれない。
「えっと……す、すまん。勢い余って……」
「んもうっ!」
「あだッ、ご、ごめんて!」
おでこに手を当てながら、片手で肩を引っ叩かれた。やっぱ結構痛かったらしい。割と本気で叩かれてしまった。
「まったく、おめでたい野郎だぜ。俺らがどんな目にあったかもしらねぇでよ」
金髪野郎の皮肉めいた言葉で、俺は初めて周囲の状況に気づいた。みんなの顔色が何故かあんまり良くない。というかどんよりしている。
見るからに南支部の執務室のようだが、戻ってきているということは、戦いは終わったってことだろう。なのにまるで戦いに負けたかのような雰囲気。戦死者が出たとでも言うのだろうか。
「あっ、そういや御玲!! お前怪我!!」
眠気が覚めてきた影響で、思考もはっきりしてくる。
そういえば俺が覚えている最後の情景は、御玲の腹に真っ黒の矢がぶっ刺さって、まるで死んだかのように倒れこんだ場面だった。
なにがなんでも仲間は守ると誓ったはずなのにそれができなくて自分を責めて、色々後悔して、精神がドス黒い何かに埋め尽くされて、視界が赤黒く染まって―――。
また俺は、溢れ出てくる破壊衝動に身を任せたんだった。
「それなら大丈夫ですよ、カエルが治してくれましたので。というか、見て分かりません?」
俺の表情から抱いている感情を悟ったのか、まだ額をごしごしと撫でながら、小さくため息を吐いてジト目で見つめてきた。言われてみればそうだった。
スケルトン系魔生物の攻撃は魔法毒とかいう劇物に塗れている以上、治療できてなかったら、呑気に膝枕できているわけがない。
むしろ俺よりも大怪我をしたはずの御玲が、無事でいてくれたことに例えようのない嬉しさを感じると同時、自分の凄まじい不甲斐なさでメンタルが死にそうになる。
今回もまた仲間に助けられた。明日にでも澄連に礼を言っておく必要がある。いつもはふざけていて何を考えているのか分からない連中だが、やっぱりここぞというときの頼もしさは凄まじいものである。
「ようやく起きたか。まちくたびれたぞ」
メン死寸前の心を保つため、澄連が先に家に帰ったことを御玲から聞くことで話題を逸らしていると、猫耳パーカーの隣で軽い定食を食っている身に覚えのない巫女が目に入った。
猫耳パーカーより背が高いだろうか。下手したら俺と同じくらいありそうな体躯だが、ソイツはお通夜みたいな雰囲気などなんのその、特に周りなんぞ気にせず、むしゃくしゃと飯を食うのみである。
こんな奴、メンバーにいなかったはず。何故だろう。全く身に覚えもないし、顔を見たところで名前も全く思い浮かばないのだが、どこか謎に親近感を感じるのは―――。
「ああ! 今朝、北支部の駐車場にいた奴じゃねぇか!」
頭がぼんやりしていて思い出すのに時間がかかったが間違いない。南支部に行く直前、暑がりの御玲のために清涼飲料水を買いに行くべく北支部の駐車場に行ったとき、チンピラをボコボコにしていたあの巫女である。服装や顔、髪型からして確実だ。
「そなたには西に行った後、南に向かうと言うたはずじゃがの」
澄まし顔で答える巫女。記憶の戸棚を漁るが記憶にない。ぼんやりとそんなこと言っていたような、そんな気がするぐらいだ。
悪いが、覚えていないので話をしていても仕方がない。重要そうでもないし、とりあえずは捨ておくことにして俺が把握するべきは今の状況だ。
サクッと巫女を視線から外し、金髪野郎の方を向く。
「片付いたよ。一応な。つっても、俺らはほとんど何もしてねぇけどよ」
「は?」
呆れ半分の表情を浮かべ、飯を貪る巫女の方に視線を投げた。そんで俺が意識を飛ばしていた辺りの話を掻い摘んで話してくれる。それを聞いていくにつれ、俺の理解力はどんどん現実に追い抜かされていく。
「待って、待ってくれ。意味分かんない。どゆこと?」
「どういうことも何も、言った通りだ。正直俺もお手上げなんだよ」
「んだよそりゃあ。あの巫女が全部一人で片したことしか分かんなかったぞ……」
「俺らもそこで理解が止まってんだよ。だから雁首揃えて話すかってところで、お前が起きたんだ」
つまり、巫女がわけわからんことをして全てを片付けてしまったので、状況を整理するために話し合おうとみんな集まったわけだ。それで俺は今まで呑気に寝ていて、話そうかってタイミングで起きてしまったと。
うん、もう少し寝ておけば良かったと後悔したが、もう遅い。これは俺も参加しないと面倒になるヤツだ。正直詳しいことも気になるし、かなり嫌な予感もするがここは余計な波風を立てないようにするためにも、参加の意思表明はしておこう。
「あとさりげになかったことにしてるが、暴走したことに関して、お前も釈明してもらうからな? だからもう寝るんじゃねぇぞ」
全く今年の新人はどいつもこいつも……と金髪を掻きむしりながら背伸びをする。
絶対面倒だし、胸騒ぎレベルで嫌な予感もしていたから、このまま話を聞くだけ聞いて一切話題に挙げないようにしようと思っていたのに、やはりこのままスルーとはいかないようだ。
釈明と言われても俺が言うことは変わらないし、なるべく脚色するにしても、最悪いざとなったら馬鹿正直に言うしかないだろう。深く考えたって仕方ない。
「んで、まずは……だ。百代……っつったっけか。お前、ホントに今年来た新人なんだな?」
「一年からそう聞いとらんか?」
「まずよ、その``ひととせ``ってトト・タートのことでいいんだよな? そこから整理したいんだが」
キョトンとした顔で金髪野郎を見つめる巫女。そのリアクションに、金髪野郎は項垂れてため息をついた。
話の意味が分からなかったので、御玲の肩を肩で小突いて補足説明させる。俺が寝ている間に話していたことらしいが、いま金髪野郎が話している``モモヨ``と名乗る巫女は、どうやら俺らと同じぐらいの時期に北支部へ就職してきた新人らしい。
つまり俺らと同期なわけだが、それにしても俺らのときと違って金髪野郎の巫女に対する当たりが強いのが妙に気になった。
「そうじゃぞ。素性を知られるのは面倒でな、名を偽るようにと命じておったのじゃ」
「名を偽るように命じてた? それを速攻バラしてたのお前じゃなかったか?」
「姓から名まで全て変えとるとは思わなかったんじゃ! わっちとしては、姓さえ変えておれば名はそのままでも良かったのに!」
ぷんすかと頬を膨らませ、ソファの上でジタバタとし始める。
横でトトが「申し訳ありません、姉様」とか言っているが、完全にコイツの指示がガバガバだっただけではと、思わずにはいられない。
「ま、まあいい。お前とトトの関係はそういうことにしておこう。それでさっきの質問に戻るが」
金髪野郎も深く探る気はないのか、サクッと話題を切り替える。さっきの質問とは、モモヨとかいう巫女が北支部の新人って話である。
「確かにわっちは今年の六月末に北支部に就いた者じゃが、それの何が問題だというのじゃ?」
「問題だから話題にしてるんだろ? 第一、その頃の新人だっつーんなら、二週間前くらいに起こったアンドロイド防衛戦や魔生物のスタンピートのときは何してたんだ」
俺は女アンドロイドとの死闘や、無限に湧いてくるアぺス狩りを振り返る。
確かに六月末っていえば女アンドロイド率いる二万のアンドロイド兵団が、中威区を埋め尽くした時期とバッティングしているが、そのときに巫女姿をした女など、一度たりとも見かけはしなかった。
大半が大なり小なりある程度の装備を整えていた服装をしている中で、コスプレ紛いの巫女服なんぞ着ていたら、誰かは分からなくとも印象には残っていたはずだ。
ワンチャン俺がクソ間抜けにも見逃していたとして、御玲がマークしていないわけがないのである。俺は御玲に目線を投げるが、御玲は静かに首を左右に振った。
「そ、その! その事に関しては、私の方から説明をですね……」
「あ? なんでお前なんだ。俺はコイツに聞いてんだよ」
何故か百代を庇うように猫耳パーカーが、二人の間に割って入る。猫耳パーカーやモモヨと名乗る巫女からは、顔に汗が滲んでいるせいか、蛍光灯の光で顔がテカっているように見える。
金髪野郎は、やはりプロだ。彼女たちの表情の変化を見逃さない。眉間に大きく皺が寄った。
「……よい、一年」
モモヨと名乗る巫女はハンカチで顔にべったりと張り付いていたであろう汗を拭きとると、さっきまで焦りを感じさせていた表情は一瞬にして消え失せ、意を決したように深く深呼吸をした。
「あれはわっちの独断でやった事。そなたが責を負う必要はない」
「し、しかし姉様……」
「くどい。必要はないと言っている」
それは、凄まじい圧だった。
わけのわからなさに若干辟易していた俺や御玲も、怪訝な表情で二人を睨んでいた金髪野郎も、モモヨから放たれた、一際低い声音に含まれる圧力にグッと体を絞られるような感覚に襲われる。
口から全身にかけて、金縛りにでもあったかのように腕や足を動かすことも、言葉を発する事も一瞬だけだができなくなる。そんな圧力を間近に受けた猫耳パーカーなど、もはや蛇に睨まれた蛙だった。
「わっちから話そう。単刀直入に言うなれば、あのときは此処……南支部におったわ」
流石は北支部の万年監督請負人である。彼女の台詞を聞いた瞬間、百代の圧に気圧されていたことを悟らせず、圧をかけ返す。ポンチョ女も何故だか暗澹とした目でモモヨたちを睨み、粘り気の強い敵意を露にする。
北支部所属のモモヨが南支部にいた。それの何が問題だというのか。そういうこともありうるだろうに、金髪野郎たちから醸し出される雰囲気は俺の予想を超えて重く冷たいものだった。
「……一つ聞く。お前、``支部個人防衛の原則``と``緊急時所属支部防衛の義務``は知ってるな?」
俺は聞き覚えのない用語が出てきたので御玲に「なにそれ?」と小声で聞いてみる。御玲はすっごい呆れ顔を浮かべながらも、小声で解説してくれた。
まず``支部個人防衛の原則``っていうのは、その支部に所属する請負人は敵性勢力からの侵略を受けた際、原則所属している支部を自力で守るというルールのこと。
原則だから状況次第では強制じゃないらしいが、今回みたいにお互い合意の上で合同任務をするって前提がない限りは、その支部にふりかかる災禍は、その支部が自力でなんとかするのが筋なのだ。
確かに言われてみればそうで、各支部には各支部の都合ってもんがある。他の支部に構っている暇は基本的にないし、今回の合同任務だって南支部の即戦力が女アンドロイド戦でほとんど潰れちまったから、それを補填するっていう特別な理由があってこそ成り立った任務である。何も間違った話ではなく、めちゃくちゃ筋が通った話だった。
次に``緊急時所属支部防衛の義務``だが、これはフェーズS以上の緊急任務発令時、その支部に所属する請負人は、必ず所属している支部を守らなければならないっていうルールのことだ。
通常任務までは原則だったが、緊急任務発令時はお互いの支部代表が合意の上で、なおかつ各支部に緊急配属される本部所属の任務請負官同士の合意もあってようやく成り立つ``支部連合体制``を整えない限り、その支部から離脱して、請負官の指示を無視した勝手な行動をとってはならないってことである。
そういえば名前は忘れたけど、女アンドロイド戦のときに任務請負官が本部から派遣されていたことを思い出す。
あのときは俺たちも色々考えた結果、独断で動くことを決めたが、アレは結局金髪野郎たちに本部を支配しているさらに上の連中から指令が出たとかなんとかで俺らはお咎めなしになっていたわけだが、モモヨに関してはそうじゃなかったようだ。
心の中で、また機関則絡みの話かと半ば落胆する。
「就任時、目は通した。処するのなら、好きにするがよい」
「待てよ。お前もそこの新人に似て気が早ぇな……」
「ならば、そなたはわっちに何を望む?」
「いや、状況が朧げながら見えた。もう一つ確認する。トト、実は南支部、結構痛手食らってたんだろ?」
その一言に存在感を一切消していた猫耳パーカーがフードから顔を出した。そして、事の経緯を説明し始める。
二週間前に起きたアンドロイド防衛戦。俺たちが首魁だった女アンドロイドと戦っている間、南支部の連中もまた己の支部を守るため、女アンドロイドが召喚したアンドロイド軍団と戦っていた。
アンドロイド軍団は確か当時、二時間以内に北支部にカチコミかけられそうになっていたから、各支部を中心に二時間以内で侵略可能な範囲内に召喚されていたものと俺は予想していたのだが、実はアンドロイド軍団が最初に召喚された場所が南支部近辺だったらしい。
南支部は不幸にも各支部のうち最も早く襲撃を受けるハメになってしまったそうで、情報が全くない非常に不利な状況で立ち回ることになってしまった。
だが現実は容赦がない。南支部に更なる追い討ちをかけるように、非情な事実を突きつける。
南支部に所属するほとんどの請負人は五十をすぎたオッサンたちばかり。それも主戦力になりうるオッサンたちでさえ精々全能度は二百、三百あるかないかの奴が数人程度という有様で、数千を超えるアンドロイド軍団に対し、多勢に無勢であることは誰が見ても明白な状態だった。
それでも支部を放棄するわけにはいかない。オッサンたちにとって、南支部は自分たちの生活を繋ぐライフラインだ。陥落したら、路頭に迷うことになってしまう。多勢に無勢であることを知りながらも、オッサンたちは猫耳パーカーとともにアンドロイド軍団を迎え撃つことを決意する。
だがしかし。まあ、当然というべきか。結果は見えていた。
猫耳パーカー以外はロクに戦うこともできないまま次々に負傷。早々と撤退せざる得なくなり、最後は猫耳パーカーが孤軍奮闘するハメになってしまった。
それだけじゃない。猫耳パーカーはアンドロイド軍団をたった一人で相手する傍ら、アンドロイド軍団の攻めが緩んだ隙を見計らい、支部で休んでいたオッサンたちの治療を同時並行で行いつつ、隙が無くなり始めたら戦場に戻るという重労働を延々と繰り返していたという。
まさにギリギリの戦線をたった一人で維持していたわけだが、若い肉体にアンドロイド軍団の物量は流石に堪えるものがある。ほんの僅かでも疲れを見せてしまったら南支部の戦線は完全に崩壊してしまう状況で、猫耳パーカーは非常手段として姉であるモモヨに助けを求め、南支部の守りを固める判断を下した。
だがこの時点では、猫耳パーカーはモモヨが北支部に就職していることを知らず、時は一刻を争う状況だったので詳しい話をしなかったらしいのだが、戦況が落ち着いてきた頃合いで、実は北支部に就職していたことを暴露してしまったため、そのときになって「やばい」と冷汗をかいたという。
北支部のメンツに知られれば責任追及は免れない。どう言い訳しようか、それとも隠蔽すべきかを考えた頃に、金髪野郎から任務請負証の霊子通信が届いた場面に繋がるそうな。
俺は条件反射で「へー」と言いながら特に何も考えずぼけーっと聞いていたが、御玲が一人「あー、なるほど」と勝手に理解し始める。
「えっと……?」
「澄男さま、記憶にありませんか。女アンドロイド戦のとき……トト・タートの言葉」
記憶の戸棚を手当たり次第にこじ開けまくるが、全く思い出せない。あのときの会話はほぼ蚊帳の外だったから、覚えているわけがないのである。俺に話していたわけでもなし、完全に猫耳パーカーと金髪野郎の間で収束していた会話だったし、そんなのを俺が覚えていることに期待する方が、無理がある。
そんな俺を見て、御玲はこれまた全力呆れ顔で俺を睨みながら、大きくため息をついた。
「トト・タートは言ってました。『私の友人っす。結構腕っ節が強くて、余程のことがねー限り負けはしねーんで』と」
ご丁寧に声真似までやって、台詞を再現してくれる。
声真似が妙に上手い上によくもそんな一文字も違わず他人の台詞を覚えていることに心底驚いたが、寸分違わず再現されてもやはり思い出せはしなかった。そういやそんなこと言っていたような気がする、程度である。
「だからですね……要するにトト・タートは、モモヨの存在を隠ぺいする道を選んだわけです」
記憶に何も留まっていないせいで全然理解が進まない俺に、猫耳パーカーに変わって御玲が説明を始める。
当時、北支部の面々―――つまり俺たちは女アンドロイドの動向はおろか、アンドロイド軍団の情報すらほとんど得られていなかった。それは女アンドロイドの軍展開が速すぎたせいだが、俺たちもあのときは久三男が得た情報を、違和感なく金髪野郎たちにどうやって伝えるかを悩みあぐねていた。
それと同じく猫耳パーカーも本当のことを言うべきか悩んでいたが、既に北支部にもアンドロイド軍団の被害が出ている背景を、当時の任務請負証での霊子通信でやっていた金髪野郎との話し合いから読み取った上で、場を混乱させるのを防ぐために``北支部所属の請負人が南支部にいる``ことを隠すことに決めたのだ。
俺たちはなんとか四苦八苦した末に正しい情報を金髪野郎に伝えられたが、南支部には都合よく澄連みたいな使い魔がいるわけもなし。ただでさえ致命的な戦力不足の状況で、正しい情報を伝えるための労力を割く余裕はほとんど残されていなかった。
だから猫耳パーカーは南支部の未来と機関則を天秤にかけた上で、南支部の未来を選んだわけだ。
正直に話すという手も勿論あっただろうが、俺も請負人として活動する上で久三男の存在を隠さなければならないという名目がある以上、気持ちは凄く分かる。正直に話すというのは、ときにかなりのリスクを伴うものだ。余裕がないなら、尚更リスクなど背負いたくないと考えるのが道理ってものである。
この場合、ルール違反になるとはいえ、ある意味で猫耳パーカーは状況に応じた安牌な判断を下したと、俺は素直に思えた。
「南支部が予想以上の痛手を食らってたのは納得できるが……それでも、だ。モモヨ、お前は北支部所属だろ? 当時は緊急任務発令中だってのに他の支部で戦ってたのは、ちょっとばかし勝手がすぎるな」
金髪野郎は目を吊り上げ、ドスの利いた声でモモヨに凄む中、俺の胸中に言い知れないモヤモヤが渦巻いた。
機関則については粗方理解したし、モモヨたちの事情も理解した俺だからこそ、やはりモヤモヤは晴れない。
猫耳パーカーは純粋に南支部とオッサンたちの未来を思い、モモヨは妹分を助けるためにルールを犯してでも助けに行った。仲間は絶対に大切にするべき、そうしない奴は裏切り者と同じという考え方の俺から言わせれば、コイツらの行動はルール違反であれどスジは通っていると確信している。
だが、それを心の中で思っているだけじゃ仕方ない。口に出さないと伝わらないのは考えるまでもないことだが、この気持ちを伝えたくても自分の説明力など信用するだけアホである。今回は珍しく金髪野郎が擁護する気皆無っぽいし、いま言わなければずっとモヤモヤしたままになるだろう。
悪いが俺は言いたいことを我慢してその場は割り切ってみせるほどオトナじゃない。正直無理筋かもしれないが、無理を通せば道理が引っ込むという言葉もある。モヤモヤしてイライラするくらいなら―――。
「コイツはコイツで事情があったんだろうよ。第一、妹がいたんだ。そりゃそっちに肩入れするのが道理ってもの……」
「は? なめんなよ」
胸中に渦巻くモヤモヤを晴らすため、思わず反論してしまったが案の定噛みつかれる。
噛みつかれるところまでは予想はしていたし、ルールについては理解できてもモモヨたちの事情を何一つ汲み取れていないからこそ口に出したわけだが、まさか言い終える前に噛みつかれるのは流石に予想外だ。
俺は眉間に皺がより、思わず握り拳を強く握った。
「こんなにつえーやつがいたのなら、きたしぶのふたんをかるくできたはずだ。なんならおまえらのぬいぐるみどもだって、きたしぶぼーえーにさくひつよーもなかったかもしんねー。でもコイツはきたしぶにいなかった」
「いやだからそれは……」
「もしせんりょくがそろってたらあのとき……レクがしにかけにならずにすんでたかもしんねーんだぞ? それ、わかっていってんのか」
口から出かかった反論が、無造作に塞がれる。ポンチョ女には珍しく、正論をブチかましてきやがった。
確かにあのとき、金髪野郎は死にかけた。偶然雲隠れしていた百足野郎とポンチョ女のおかげで首の皮一枚繋げられたわけだが、もしもあのとき北支部に十分な個人戦力が揃っていて、澄連を北支部防衛に回す必要がなかったら―――金髪野郎は無傷で済んでいた可能性は十分にあった。
無傷とは言わずとも、生死の境を彷徨う可能性は限りなく低かっただろう。カエルが使える謎の回復魔法``蘇・生``なら腹をブチ抜かれた程度、簡単に治癒してしまえるはずだから。
「で、でもよ。それでもコイツらにはコイツらなりの……」
それでも俺の考えは変わらない。ルールについては理解できても、そのルールはモモヨたちの事情を全く汲みとってはくれないものだ。何もなかったなら、そのルールに従うことに異論なんてないけど、今回はモモヨたちにやむおえない事情があった。それを汲みとれるのはルールじゃない。人間の俺たちのはずだ。
「だったらオレらとみなみでれんごーくめばよかったんだ」
俺の思いも虚しく、ポンチョ女には全く届く様子がない。それどころか暗澹とした瞳に宿る闇で俺を蝕みながら、反論をどんどんヒートアップさせていく。
「みなみのうけおいかんとあーしらのうけおいかんにたのんで``しぶれんごーたいせー``をくむよーにせーきのてつづきふんでりゃあ、レクだってことわりゃあしなかっただろうよ。でもじっさいはかってにあーしらのしぶのせんりょくつかっちまったんだろ? だったらルールいはんいげーのなにもんでもねーんだよ」
「はぁ? お前さ、猫耳パーカーの話聞いてなかったのか? 要はその手続きとやらを踏む余裕がなかったってっこったろうが」
「よゆーがなかったのはウチだって、どこのしぶだっておなじだろ。よゆーがねーからって、よそのしぶのだいひょーが、てめーがってなはんだんで、よそのしぶのせんりょくをかってにつかっていーわけがねーだろーが。だから``きんきゅーじしょぞくしぶぼーえーのぎむ``と``しぶれんごーたいせー``ってのがあんだよ、わかったらいーかげんきかんそくよんでこいぺーぺーのしんざんクン」
いつもなら金髪野郎が仲裁に入るはずなのに、なぜだか今回ダンマリを決め込んでいた。御玲も特に反論する様子もない。
ものすごく言い方が癪に障るし、なんなら煽られてすらいるが、悔しいことに俺も反論することが表立って思いつかなかった。
百代と猫耳パーカーの顔を見る。アイツらはアイツらで守るべきものを守るために行動したんだ。俺だって久三男や弥平が危機に陥っていたら、たとえ自分の立場とか関係なく助けに向かうし、御玲が遠い場所で死にかけていたらなにもかもをかなぐり捨ててでも御玲を救い出しに行く。
モモヨとかいう奴も同じように、妹の猫耳パーカーが危機だったからこそルール違反であることを知りながら、北支部防衛につかなきゃならないところを無断で抜け出して、猫耳パーカーの所へ向かったんだ。
だからコイツのやり方は間違っちゃいない。機関則がどうのこうの以前に、コイツはコイツのやるべきをやったんだ。それなのにルール違反とかいう、そんな薄っぺらい言葉でこの巫女たちを断罪するってのか。
クソが。もういい。どっちみち拗れるが、俺はここで我慢するほど出来た人間じゃねぇ。もうなるようになれだ。
「ははは。ルール違反ルール違反とそれしか言う能がねぇのかテメェは」
何も考えず、ただ胸底に渦巻くどす黒い感情を、頭の中に浮かんだ言葉そのままに写して吐き捨てる。予想通り、ポンチョ女の眼光が光った。明確な敵意が、視線から痛いほど伝わってくる。
「いやぁ……コイツらにも事情があったろうに、それを汲み取らず機関則に振り回されてるとか、テメェはルールがないと生きてけねぇの? それがねぇと何が正しいか分かんねぇとか言っちゃうタチか?」
「みんながまもってこそいみがあんだよ、だれかがみだせばそこからなにもかもがほころびる。ただのむほーになりさがる。そこにただしさなんかあるわけねーだろ。だからルールってのがあんだよ」
「ハハハ!! 要するに自分で何が正しいか決めるだけのお頭がないヴァカってことですね分かります!! よくもまあその程度で先輩ヅラできたよなー、無自覚って怖い怖い」
「あーそーだよ、ばかだよ。にんげんみんなばかだから、なにがただしいかわかんねーから、みんなでがんくびそろえて、ちからあわせて、ちえだしあって、ルールってもんをきめるんだろ。そのルールのいみすらりかいできねーぶんざいで、ガタガタぬかしてんじゃねーよヒヨッコが」
「ガタガタぬかしてんのはテメェだろうがよ!! テメェが黙ってりゃ俺だってガタガタぬかす必要もなかったんだ、責任転嫁してんなよ?」
「せきにんてんこしてんのテメーだろうが!!」
ポンチョ女の顔が般若のように歪み、全身から暗黒の瘴気が薄っすらと漂う。
光が消えた瞳に映るのは、一切光を通さぬ漆黒の闇。その闇は沸騰し、刃となって俺に襲いかかる。
「テメーマジでいいかげんにしろよ? まえのあんどろいどのころからおもってたけどよ、わをみだしてんじゃねーよ!! きかんそくもよむきねーし、そのくせきにくわなかったらやぶろーとするし……いっとくけどな、レクがくそゆーのーってだけだからな? あーしだったらテメーみてーなむのー、すぐクビにしてやるわ!!」
「へぇ!! そいつァおもしれェ!! 要は後輩の面倒もロクに見れねぇ無能ってことじゃねぇかァ!! 都合が悪くなればコーハイのせいですかはいはいセンパイなんてえらいんでしょーか百足野郎がいなきゃ戦力外のクソザコナメクジなのに口だけは立派立派あーこの程度でセンパイヅラできるんならホントマジで楽な仕事だよなァ!!」
ばりん、とガラスが粉々になったかのような音が炸裂した。
顔中に冷たい液体がべちゃりとまとわりつく。俺らが座っていたテーブルの上に置いてあった花瓶がなくなっていたことに気づいた。そしてそれが、俺の顔面にブチ当てられたせいだってことも―――。
刹那、頭の中が真っ白になった。目の前のクソアマを亡き者にする。ただそれだけに思考が集約される。
ソファを蹴り壊し、テーブルを突進で踏み倒すと、一瞬でポンチョ女の胸ぐらを掴むが、同時に黒光りした巨大な何かが俺の身体に強く巻きついた。百足野郎の邪魔くせぇ尻尾である。
「やばい、むーさんよせよせよせよせ!!」
「澄男さまだめです!!」
気がつけば、右手に煉旺焔星を練り上げていた。背後からは御玲が振り上げた俺の右手を全力で押しとどめ、金髪野郎が百足野郎とポンチョ女の間に割って入る形で俺とポンチョ女を引き剝がそうと突っ張り棒のように立ち塞がる。
一瞬全てが真っ白に染まったと思いきや、御玲の一声で我に目覚めたわけだが、だからとこみ上げてくる感情がなくなったわけじゃない。
コイツをどうにか黙らせて、俺の主張が正しいって事を認めさせねぇと始まらねぇ。所詮話し合いで解決することなんぞたかが知れている。
さっきも言った気がするが、無理を通せば道理が引っ込む。結局は喧嘩の強ぇ奴の主張が正しい主張になるんだ。
「とりあえず落ち着け!! お前やむーさんがガチ喧嘩なんてしてみろ、この支部吹き飛ぶぞ!!」
「知ったことかよ!! 先に喧嘩売ってきたのはコイツだろうが!!」
「ざけんな!! テメーがナメたクチきいってからヤキいれてやってんじゃねぇか!!」
「ああ!? ヤキいれてやってるだぁ? テメェ誰に向かって口きいてやがる!! ヤキ入れてやるのはこっちだボケが!! 俺を怒らせるな!!」
「ちょ、だからマジでやめろって……!!」
「もうよい!!」
テーブルが粉砕された音が部屋中を走り回る。
テーブルを粉々にしたのは、つい数分前、猫耳パーカーの隣でおにぎりを呑気に頬張っていた、モモヨとかいう巫女だった。
ソイツの顔はいつになく真剣で、眼力から放たれる妙な威圧感がポンチョ女の胸倉を掴む手を緩めていく。胴体に巻き付いた百足野郎も同様だ。
「もうよい。わっちが罰を受ければ済む話。ここでそなたらが争う意味はない」
「ま、待てよ。お前が罰せられる必要は」
「じゃが実際、わっちがるーるとやらを破ったせいで、いま争いが起きておる」
「いやそれは俺が勝手にだな……」
「どちらでも同じことじゃ」
「いやいや……」
「ともかく庇ってくれた御恩だけは受け取ろう。じゃがこれはわっちの意志。無用な争いが治まるのならば、如何ような罰もこの身で受け入れようぞ」
色々言いたかったが、奴の目から放たれる、霊圧に似た尋常じゃない威圧感が、無造作に口を糸で縫いつけていく。
俺の直感も、これ以上の反論は野暮だと何故か叫んでいた。多分、俺が何を言ってもコイツの考えは変わらないと、なんとなーくだが予想がついてしまったからか。
頭を掻きむしり、ポンチョ女を向かい側のソファに突き飛ばす。そしてそのまま、南支部の執務室を後にする。
「澄男さまどちらへ」
「いやー、もうめんどくせぇなって思ってさ。俺の主張とおらねぇし、だったらここにいる意味ないし、気分悪りぃし、もう帰るわ。悪いけど、あとは頼める?」
「はぁ? ざけんな、そんなのゆるされるとおも」
「……うるせぇ黙れよ」
突き飛ばされて背中をソファに強く打ち、半ば咳き込みながら未だに俺につっかかってくるポンチョ女に、ありったけの霊圧をブチこむ。
霊圧の影響でガラス窓は次々と粉々に、壁にはヒビが入り始める。
今の俺は虫の居所がクッソ悪い。正直これ以上ガタガタぬかすようなら流石に目障りだし、本当に跡形もなく消えてもらわなきゃならなくなる。
機嫌の悪いときにやる話し合いほど無意味で無価値なものはない。どうせロクな結果になりゃあしないし、そもそも説明力皆無な俺にマトモな説明を期待するだけ無駄だし、御玲に説明させた方が速くて確実だ。尚更俺の口から語る意味がない。
どうしてさっさとこの事実に気づかなかったのか。それならポンチョ女と無駄に言い争う必要もなかったってぇのに。
「あー……もう分かった。お前は離席でいい……」
百足野郎を背にして、また俺に殴りかかろうと一歩前に足を踏み出しそうとしたポンチョ女の肩を鷲掴み、疲れ切った顔で金髪野郎は追い払うように手を払う。
ちょっとその仕草にムカついたが、それでこの胸糞悪い話し合いから抜けられるなら好都合。俺は鼻で笑ってその仕草に答えた。
「言われるまでもねぇよクソが!!」
とりあえず邪魔なので執務室の扉を蹴破り、俺は一階のロビーへと降りていった。
「んだよアイツ!!」
澄男がいなくなった後、最初に口を開いたのはブルーだった。
テーブルは百代の手によって粉々になってしまったが、もしテーブルが無事だったら足で蹴飛ばすぐらいの事はしていただろう。執務室内の空気は最悪の状態だった。
「えーと……どこまで話したっけか」
「百代さんの処罰に関してですね」
未だ怒りに震えるブルーをよそに、レクは疲れ切った表情で話の内容を思い出す。
澄男によって話を滅茶苦茶にされたため、話題が吹き飛んでしまった。場を荒らすだけ荒らしてさっさと離脱していく自分本位さには毎度のことながら脱帽ものだが、とりあえず澄男の事は捨ておくしかない。優先順位を決めて、一つ一つ処理していくのが一番の近道なのだ。
「そうだったな。とりあえず俺としてもブルーの言い分に賛成だ。悪いが庇う事はできない」
レクもまた、すんなりと自分の意見を述べた。
女アンドロイド戦のときは機関則の抜け道を探してくれた彼だったが、今回ばかりは情状酌量の余地がないとの判断らしい。かくいう自分も澄男の前では何も言わなかったが、百代を擁護する気は全くなかった。
確かに百代にもトトを助けたいという事由があったのは理解できるが、結局のところ百代が個人的な理由で勝手に南支部の都合に首を突っ込んだだけであって、自己責任の範疇を逸脱しない。
もしも公的な理由で南支部を助けたかったのなら、ブルーが言った通り北支部と連合を組むという選択肢もあったはずである。端的に言うなら百代は北支部の請負人との報告、連絡、相談を怠り、勝手な行動をしただけだとも言えるのだ。
彼女は親族を純粋に助けたかったのは本当だろうし、ブルーやレクもその想いを嘘だとは思っていないだろうが、ひどい話、ロボット軍団から北支部を守るために生死の狭間にあった北支部の人間からすれば、関係のない話であった。
「本部には俺から報告しておく。そのうちペナルティが発布されるから、それに従ってくれ」
心得た、と百代は静かに頷いた。
「そんで最後に聞きたいことなんだが……」
レクの視線がモモヨから外される。本来説明するべき人物がいない今、自ずと求められるのは必然だろう。確かにメイドと主人という関係だが、何故、という疑問がないわけではない。全く困った話である。
「あの新人が使ってた魔法? 魔術? みたいなやつ。アレは何だ。悪いが、はぐらかさずに教えてもらえると助かる」
あらかた予想はしていたが、予想は見事に的を穿つ。教えるべきかと一瞬思案するが、レクの表情から誤魔化しは効かなさそうだと判断する。
澄男が使っていた魔法。間違いなく``竜位魔法``のことだ。
はるか昔、竜人族の大国を滅亡寸前に追いやった大災厄``天災竜王``ゼヴルエーレが使っていたとされる大魔法。
彼は紆余曲折を経て、その魔法を継承し、自在に操ることができる。今回澄男は怒りに支配されて暴走し、思わず使ってしまった。効果が発動する前に百代によって阻止されたが、天空に描かれた魔法陣までは、どうにもならなかったのである。
さて、どこから説明したものか。
「……レクさんは``竜位魔法``というものをご存知ですか」
「知らんな。むーさん、なんか知らないか」
半ば不貞腐れているブルーに発破でもかけるように言い放つ。表面上は面倒くさがりながらも、ブルーはポンチョの袖から顔を出す小さな黒百足と対話する。
相変わらずどうやって話しているのか分からないが、表情を見るに対話が成り立っているようだった。いつ見ても不思議である。
「いまいましきさいはてのものどもがつかうみわざ。やはりあのこぞうには、さいはてのちがながれている」
「……ん? んー……と。つまり?」
「さいはてのものどもがつかうひおうだって。このせかいだと……ちょーのーりょく? とおなじもの」
「おいおいそれマジか。エグいってレベルじゃねぇぞ、それ」
超能力と言われてピンとこなければどうしたものかと思ったが、流石は北支部の古株。目を丸くして驚くあたり、その脅威をきちんと理解していたようだ。
「……で、そりゃどんな超能力なんだ?」
どうやら超能力にも種類があることも知っているらしい。これなら説明の手間も省けるというものである。
こほん、と咳払いをして一息ついてから話し出す。
「詳細は、私どももよく分かっていません。しかし、その片鱗なら数度見たことはあります」
説明の手間が省ける、そうは言ったが実のところ話せることは事の経緯を除けばほとんどない。
澄男が竜位魔法を使えることがわかってから、既に三ヶ月余りが過ぎようとしているが、その実体は不明のままだ。垣間見れたのは、彼が激情のままに力を振りかざしたときのみで、その結果どんなことが起こったのかを話せる程度である。
真剣な表情を崩さないレクに、澄男が未だ復讐に囚われていた頃にしでかした破壊の事柄を話した。
全てを話すと機密を漏らすことになってしまうため、あまり詳しい経緯などは話せない。したがって復讐などの込み入った事情は隠し、適当に理由をでっちあげた上で北の魔境大遠征に同伴することになり、全能度四桁の魔生物の軍団を一瞬で消滅させたことを話した。
それを語り終えたとき、レクのみならずブルーまでも、怪訝な表情を浮かべながら目を丸くして唖然としていた。
「おいおい、そんな嘘……なわけねぇか。そのツラ、嘘ついてるようには思えねぇし」
「いや、でもどーやって? そんなまね、できるとしたらむーちゃんぐれーしか……」
「んいや。超能力に原理とか理論とか、そんなもん考えたって無駄だ。そういうもんだと受け入れた方が理解は速い」
レクの冷静すぎる言葉に、ブルーは不満気だったが口を噤んだ。
一見思考放棄に見えるが、実際のところレクの言い分が正しいのだ。超能力など、その能力を持っている者にしか詳細は分からない。魔法や魔術などとは根本的に体系が異なるため、調べることができないのだ。
もしもその不可能を可能にするなら、それこそ超能力を持つ者が別途必要になるだろう。途方もなく阿呆らしい話であった。
「全能度四桁クラスを瞬殺できるとなると……無闇矢鱈に使われたら堪ったもんじゃないな。歩く戦略兵器だぞ」
「澄男さまは竜位魔法の使用を望んではいないようです。ただ、今回のように怒りに支配されたりなどすると、無意識で使用してしまうようですが」
「なら尚更厄介だぜ。要はカチキレたら本人の意志関係なく使っちまう可能性あるんだろ? 節操がないにも程がある」
ですよね、と盛大にため息をつく。
澄男自身、竜位魔法の使用は望んでいない。復讐を経て全てを破壊するよりも、仲間とともに困難を乗り越える道を選んだ彼ならば、怒りに支配されていない限り、自らの意志で破壊の魔法を使うことはないだろう。
しかし澄男の感情制御は、さっきの喧嘩を見ての通り、お世辞にも期待できたものではない。なにかしら考えの相違で意見が対立すれば、譲る精神が皆無な澄男では、どう足掻いても喧嘩は避けられないだろう。
それに、彼にはトラウマがある。大切なものを一気に失ってしまったトラウマ。それが刺激されたとき―――彼の理性は一瞬にして吹き飛ぶことになる。それこそ全てを破壊する、暴力の権化と化してしまう。
どうにかして対処法を考えなくてはならないのだが―――。
レクとともに頭を悩ますが、その反面、名案など簡単には浮かばない。極端な話、彼を怒らせないようにすればいいだけの話だが、そんな方法など。
「なぁ。もーめんどくせーし、ほんぶにみっこくしちまえば?」
沈黙を食い破るように、ブルーが眠たそうな目でこちらを見てきた。しかし、彼女の目を見てすぐさま身構える。その目には光が無かった。見覚えのある、淀んだ瞳だった。
「密告……というと?」
「よーはせーぎょきかねーってはなしだろ? いつなにでかすかわかんねーし、アイツはあんなんだし。だったらよ、かんぜんこーそくしちまえばよくね? って」
淀んだ瞳で、しかし怪しいほど真顔でそう言い放つブルー。驚く一同の中で、一人ため息をつく。彼女の言っていることが、驚くほど予想通りだっただけに。
「ブルー……それ本気で言ってんのか?」
レクの声音は驚くほど低い。声質が怒りに満ちているのは明白だが、ブルーは鼻で笑ってそっぽを向くのみである。
確かに合理的に考えれば、澄男の感情制御に頼るのは悪手だし、他の者がなんとか抑えるとしても、それは確実策とはいえない。
澄男は力だけは無駄に強いため、暴走すると抑えられる者はほとんどいないのだ。ブルーが使役している黒百足ならば拘束できるかもしれないが、今回のように戦場が分断され黒百足からの支援が期待できない場合、百代が救援に来なければ、彼の暴走が収まるのを待つ他ないというのが現状だった。
確実性を期するなら、最初から暴走するような状況に置けないように監視し、必要ならば``人類の存亡を脅かす脅威``として拘束してしまうのが手っ取り早い。リスクも少なく、確実に暴走による二次被害を防げるハイリターンな方法である。
理想的なやり方だ。誰も失わないし困らない。手間もかからないし、確実だ。澄男を人間として扱うのをやめなければならない点を除けば―――。
「……私は、反対です」
ぼそりと独り言のように、だが確固たる意志を持って力強く言い放った。それを感じ取れないほど空気の読めない連中ではない。誰もがこちらに視線を向けた。
「確かに合理的で確実な方法ではありますが、私は澄男さまの専属メイド。彼を裏切るような真似はできません」
ありのままの本心を言った。でも不思議な気持ちになっている自分もいた。
合理的で確実な方法。それを選ばない、選びたくない自分。もはやその選択をすることに今となっては迷いなどないけれど、だからこそかつてこの世の全てに心を閉ざしていた頃の自分が妙に疼き立ててくる。
ブルーが、かつての自分のように思えてくるのだ。昔の自分、澄男と腹を割って本音で語り合う前の自分なら、きっと迷いなくブルーの意見に賛同していただろう。
でも澄男と腹を割ったあの日から、今までとは違う``本当の自分``を見つけようと思ったのだ。自分でもこの変化には驚いているが、あんな自分本位な主人でも、裏切ろうという気にはなれなかった。
たとえどれだけ自分本位で阿呆な人だろうとも、本当の自分を見つけようと思わせてくれた人だから。
「……はーん。そーかよ」
ブルーの瞳から、澱みが消え失せた。尚も不満気だったが、全身から滲み出る敵意が、心なしか弱まった気がした。
レクもブルーからの敵意が弱まったことを悟ったのか、眼力を弱めた。
「ま、メイドが言うんなら仕方ねぇよな。悪いが俺も御玲に賛成だぜ」
仕方ないなどと言いながら、その表情は若干嬉しさに満ちていた。
どうやらレクとしても澄男を拘束するのは不本意だったらしい。ブルーは多数決に逆らう気はないのか、そっぽを向いて鼻で笑うだけであった。
「もし。一つよいかの」
さっきまで沈黙を守っていた百代が、綺麗に挙手をする。その顔は、我に名案ありという文字が、透けて見えるほどに快活な表情をしていた。
「わっち、後々にぺなるてー? じゃったか。そういうものをもらえるのじゃろ?」
「貰えるっつーか、課せられることになるな」
「ならばそのぺなるてーとやら、澄男とやらの暴走をわっちが責任もって食い止める、というのはどうじゃ?」
それを聞き、ブルーはハッと鼻で笑い、レクは顎に手を当てて考え始める。
確かに実力的には適任ではある。というか、現状彼女か黒百足しかいないと言っていい。
暴走した澄男とスケルトン・アークを二人同時に相手取って勝利してのけた強者である。言ってしまえば、暴走した澄男など敵ではないとも言えるのだ。
誰にもできない重労働を率先して行うわけなのだから、一応ペナルティとしての体裁は整う。問題は、それがペナルティとして受理されるかどうか。だが。
「……んー……まあ、ちとかけ合ってみるか」
黙り込んで考え込んでいたレクだったが、本当にそれでいいのかと内心驚く自分がいた。
レクが良いというのなら特に文句はない。ブルーほど機関則保守派というわけでなし、百代の実力も申し分ない。任務請負機関本部とレクが判断するのなら、それに従うまでのことである。
「まあこれで現状の疑問という疑問はなくなったか。色々あったが、解散って事でいいか?」
「澄男さまへの報告は私がしておきます」
「おう。頼んだぜ。ブルーからはなんかあるか?」
「んーや。べーつに」
百代たちも特になし。レクが立ち上がって「んじゃ解散!」と声をかけると、皆立ち上がって外に出た。こうして短かったような長かったような、微妙な反省会は幕を閉じたのだった。
一階のロビーで拗ねているであろう主人のもとへ向かうため、百代たちに挨拶して執務室を後にすると、メイド服の裾を誰かに引っ張られた気がした。
振り向くと裾を引っ張っていたのは、ポンチョの隙間から顔を出す、小型化した黒百足だった。そこから分かる人物は、自ずと知れている。
「おまえ……なんであんとき……あーしを?」
普通の人間ならこんなとき、年端もいかぬ少女が照れながら上目遣いでこちらを見てくるところを想像するだろう。特に男なら尚更かもしれない。だが、現実はそう甘くはないのだ。
彼女の表情からは照れだのなんだのといった甘ったるい感情とは無縁の、熾烈なまでの猜疑心に溢れていた。
あのとき、というのは間違いなくブルーを庇って怪我をしたときのことだろう。
結論から言うと、完全なる善意でやったことだ。他意などなく、自分でも驚くほど損得勘定は一切ない。むしろ損得で動くなら、レクたちは見捨てるのが妥当な判断だっただろう。
澄男の専属メイドであり、彼らを守る義務などありはしないのだから、死んだら死んだで戦死扱いにすればいいだけの話であった。
でも、それでも助けたのは彼女と友達になりたかったからであり、今までの自分なら絶対に選択しないことをしたかったからだが―――。
改めて彼女と視線を交わす。
彼女の顔色を見るに、正直に気持ちを伝えたとて信じてもらえる気がしない。むしろより強い猜疑心を与えてしまうような気がした。自分が逆の立場なら、向けられる義理もない善意を振り撒かれても、より強くその者を疑うだろう。
この世に何の対価なく善意を振りまいて生きていることを公表している者ほど、信用するに値しないのは火を見るより明らかだからだ。
ならば、彼女に言うべきことは既に分かっている。
「小銭稼ぎですよ。レク・ホーランに見捨てられたり、況してや戦死されたりすると、うちの主人のクビがとびかねませんからね。せめてメイドの私が、主人の不評を肩代わりしないと」
「……よーはただのメイドとしてのつとめっていーてーの?」
「そうですけど、何か?」
嘘寄りの本音をとりあえず投げておいた。
レク・ホーランへの小銭稼ぎ、というのは嘘ではない。彼がいてこそ活動できている節が多く、見捨てられれば活動を続けていくのは難しい。
自分本位な理由で所属している組織のルールを平気で破ろうとするような主人である。もはやレクなくして、本部昇進は絶望的と言っても過言ではない。懲戒解雇処分がすぐ隣に迫っているような感覚である。
懲戒解雇された者が復帰するのは難しい。彼の罷り知らぬルールだが、解雇されても組織に不利益を起こした記録は残るのだ。
メイドとしても、懲戒解雇からの復帰という面倒は踏みたくない。そうなるとレクとの繋がりは、自ずと切り離せないものだと充分に言える。
そして彼と行動を共にすることの多いブルーに恩を売っておくというのも、結果的にはレクへの小銭稼ぎの一環という理屈が成立するわけだ。
そういう損得を理解した上で行動してくれればいいのだが、常に直情的な澄男には無理な話であった。
「…………ふーん。まーいーや。せーぜーがんばれよ」
ブルーから警戒色が消えていく。予断許さぬ懐疑心は鳴りを潜め、ポンチョをくしゃくしゃしながら、俯き気にこちらを見てくる。
他人事のように吐き捨てているが、その言葉からは心地良さが感じられた。
「まー……その、なんだ。しんどくなったら、のみにつきあってやる」
「是非に、お願いします」
「いっとっけどおごらねーかんな? オレのかねはオレのもんだからよ」
先輩の癖に先輩らしさが全く感じられないその台詞に、少し笑みが溢れてしまうが、予想は当たったらしい。
これは自分にとって、初めての一歩だ。無駄にはしたくない。いつ叶うか分からないが、澄男の専属メイドとして以外のやりたいことができたのだ。それは純粋に嬉しいことだった。
「では澄男さまの所へ行ってきます」
今すぐにでも彼女と飲みに行きたいが、それはまた今度だ。メイドとしての仕事がまだ残っている。キレにキレ散らかした、澄男の世話である。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説
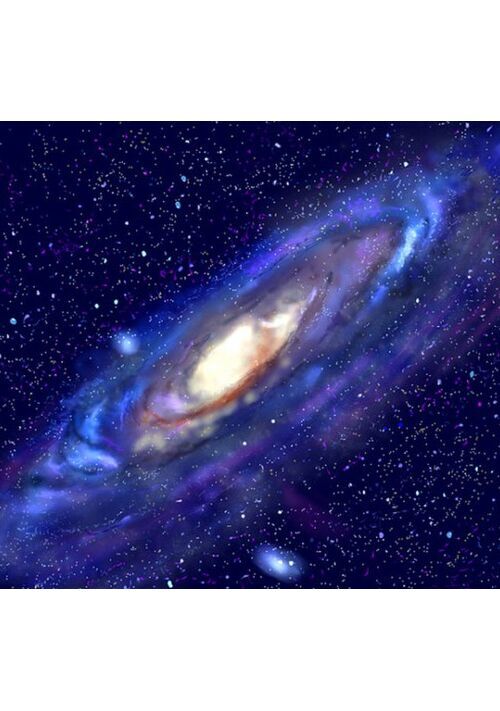
銀河文芸部伝説~UFOに攫われてアンドロメダに連れて行かれたら寝ている間に銀河最強になっていました~
まきノ助
SF
高校の文芸部が夏キャンプ中にUFOに攫われてアンドロメダ星雲の大宇宙帝国に連れて行かれてしまうが、そこは魔物が支配する星と成っていた。

異世界で穴掘ってます!
KeyBow
ファンタジー
修学旅行中のバスにいた筈が、異世界召喚にバスの全員が突如されてしまう。主人公の聡太が得たスキルは穴掘り。外れスキルとされ、屑の外れ者として抹殺されそうになるもしぶとく生き残り、救ってくれた少女と成り上がって行く。不遇といわれるギフトを駆使して日の目を見ようとする物語

『収納』は異世界最強です 正直すまんかったと思ってる
農民ヤズ―
ファンタジー
「ようこそおいでくださいました。勇者さま」
そんな言葉から始まった異世界召喚。
呼び出された他の勇者は複数の<スキル>を持っているはずなのに俺は収納スキル一つだけ!?
そんなふざけた事になったうえ俺たちを呼び出した国はなんだか色々とヤバそう!
このままじゃ俺は殺されてしまう。そうなる前にこの国から逃げ出さないといけない。
勇者なら全員が使える収納スキルのみしか使うことのできない勇者の出来損ないと呼ばれた男が収納スキルで無双して世界を旅する物語(予定
私のメンタルは金魚掬いのポイと同じ脆さなので感想を送っていただける際は語調が強くないと嬉しく思います。
ただそれでも初心者故、度々間違えることがあるとは思いますので感想にて教えていただけるとありがたいです。
他にも今後の進展や投稿済みの箇所でこうしたほうがいいと思われた方がいらっしゃったら感想にて待ってます。
なお、書籍化に伴い内容の齟齬がありますがご了承ください。

落ちこぼれの烙印を押された少年、唯一無二のスキルを開花させ世界に裁きの鉄槌を!
酒井 曳野
ファンタジー
この世界ニードにはスキルと呼ばれる物がある。
スキルは、生まれた時に全員が神から授けられ
個人差はあるが5〜8歳で開花する。
そのスキルによって今後の人生が決まる。
しかし、極めて稀にスキルが開花しない者がいる。
世界はその者たちを、ドロップアウト(落ちこぼれ)と呼んで差別し、見下した。
カイアスもスキルは開花しなかった。
しかし、それは気付いていないだけだった。
遅咲きで開花したスキルは唯一無二の特異であり最強のもの!!
それを使い、自分を蔑んだ世界に裁きを降す!

異世界でぺったんこさん!〜無限収納5段階活用で無双する〜
KeyBow
ファンタジー
間もなく50歳になる銀行マンのおっさんは、高校生達の異世界召喚に巻き込まれた。
何故か若返り、他の召喚者と同じ高校生位の年齢になっていた。
召喚したのは、魔王を討ち滅ぼす為だと伝えられる。自分で2つのスキルを選ぶ事が出来ると言われ、おっさんが選んだのは無限収納と飛翔!
しかし召喚した者達はスキルを制御する為の装飾品と偽り、隷属の首輪を装着しようとしていた・・・
いち早くその嘘に気が付いたおっさんが1人の少女を連れて逃亡を図る。
その後おっさんは無限収納の5段階活用で無双する!・・・はずだ。
上空に飛び、そこから大きな岩を落として押しつぶす。やがて救った少女は口癖のように言う。
またぺったんこですか?・・・


仮想空間のなかだけでもモフモフと戯れたかった
夏男
SF
動物から嫌われる体質のヒロインがモフモフを求めて剣と魔法のVRオンラインゲームでテイマーを目指す話です。(なれるとは言っていない)
※R-15は保険です。
※小説家になろう様、カクヨム様でも同タイトルで投稿しております。

8分間のパピリオ
横田コネクタ
SF
人間の血管内に寄生する謎の有機構造体”ソレウス構造体”により、人類はその尊厳を脅かされていた。
蒲生里大学「ソレウス・キラー操縦研究会」のメンバーは、20マイクロメートルのマイクロマシーンを操りソレウス構造体を倒すことに青春を捧げるーー。
というSFです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















