お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説
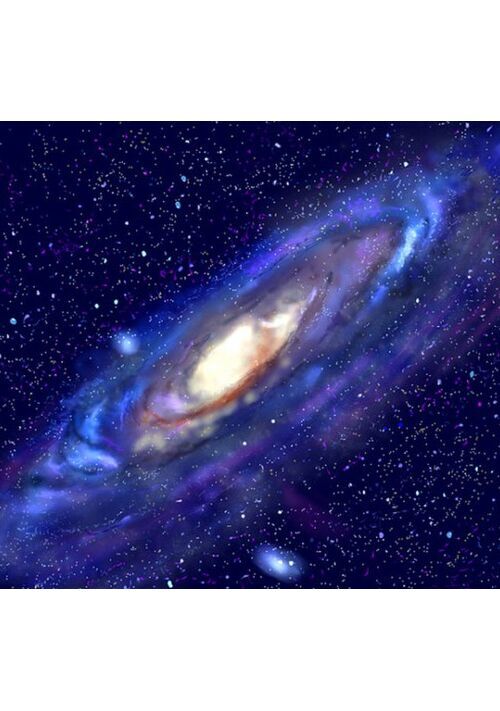
銀河文芸部伝説~UFOに攫われてアンドロメダに連れて行かれたら寝ている間に銀河最強になっていました~
まきノ助
SF
高校の文芸部が夏キャンプ中にUFOに攫われてアンドロメダ星雲の大宇宙帝国に連れて行かれてしまうが、そこは魔物が支配する星と成っていた。

異世界で穴掘ってます!
KeyBow
ファンタジー
修学旅行中のバスにいた筈が、異世界召喚にバスの全員が突如されてしまう。主人公の聡太が得たスキルは穴掘り。外れスキルとされ、屑の外れ者として抹殺されそうになるもしぶとく生き残り、救ってくれた少女と成り上がって行く。不遇といわれるギフトを駆使して日の目を見ようとする物語

『収納』は異世界最強です 正直すまんかったと思ってる
農民ヤズ―
ファンタジー
「ようこそおいでくださいました。勇者さま」
そんな言葉から始まった異世界召喚。
呼び出された他の勇者は複数の<スキル>を持っているはずなのに俺は収納スキル一つだけ!?
そんなふざけた事になったうえ俺たちを呼び出した国はなんだか色々とヤバそう!
このままじゃ俺は殺されてしまう。そうなる前にこの国から逃げ出さないといけない。
勇者なら全員が使える収納スキルのみしか使うことのできない勇者の出来損ないと呼ばれた男が収納スキルで無双して世界を旅する物語(予定
私のメンタルは金魚掬いのポイと同じ脆さなので感想を送っていただける際は語調が強くないと嬉しく思います。
ただそれでも初心者故、度々間違えることがあるとは思いますので感想にて教えていただけるとありがたいです。
他にも今後の進展や投稿済みの箇所でこうしたほうがいいと思われた方がいらっしゃったら感想にて待ってます。
なお、書籍化に伴い内容の齟齬がありますがご了承ください。

落ちこぼれの烙印を押された少年、唯一無二のスキルを開花させ世界に裁きの鉄槌を!
酒井 曳野
ファンタジー
この世界ニードにはスキルと呼ばれる物がある。
スキルは、生まれた時に全員が神から授けられ
個人差はあるが5〜8歳で開花する。
そのスキルによって今後の人生が決まる。
しかし、極めて稀にスキルが開花しない者がいる。
世界はその者たちを、ドロップアウト(落ちこぼれ)と呼んで差別し、見下した。
カイアスもスキルは開花しなかった。
しかし、それは気付いていないだけだった。
遅咲きで開花したスキルは唯一無二の特異であり最強のもの!!
それを使い、自分を蔑んだ世界に裁きを降す!

異世界でぺったんこさん!〜無限収納5段階活用で無双する〜
KeyBow
ファンタジー
間もなく50歳になる銀行マンのおっさんは、高校生達の異世界召喚に巻き込まれた。
何故か若返り、他の召喚者と同じ高校生位の年齢になっていた。
召喚したのは、魔王を討ち滅ぼす為だと伝えられる。自分で2つのスキルを選ぶ事が出来ると言われ、おっさんが選んだのは無限収納と飛翔!
しかし召喚した者達はスキルを制御する為の装飾品と偽り、隷属の首輪を装着しようとしていた・・・
いち早くその嘘に気が付いたおっさんが1人の少女を連れて逃亡を図る。
その後おっさんは無限収納の5段階活用で無双する!・・・はずだ。
上空に飛び、そこから大きな岩を落として押しつぶす。やがて救った少女は口癖のように言う。
またぺったんこですか?・・・


My² Gene❇︎マイジーン ~URAZMARY~
泥色の卵
SF
【お知らせ】
他サイトで完結したので、定期的に投稿していきます。
【長期連載】
1話大体3〜5分で読めます。
▼あらすじ
My² Gene 第1部
広大な銀河の中。“My Gene”という何でも願いを叶える万能遺伝子が存在するとの御伽話があった。
ある星に薄金髪で能天気な学生が暮らしていた。彼の名はサンダー・パーマー=ウラズマリー。
電撃系の遺伝子能力を操る彼は、高等部卒業試験に向けて姉のような師匠と幼馴染の力を借りて奮闘していた。
そんな中ウラズマリーは突然何者かにさらわれ、“My Gene”と彼との関係を聞かされる。
そして彼は“My Gene”を探すために銀河へと旅立つことを決意する。
これは、電撃の能力を操る青年『ウラズマリー』が、仲間と共に万能遺伝子『My Gene』を巡って織りなす壮大な物語。
異能力×スペースアドベンチャー!!
第一部「万能遺伝子と宵闇の光」【完結】
現在第二部「血を喰らう獣」も連載中です。
-------------------------------------
少年漫画風な冒険もの小説です。
しっかりと読んでいただけるような物語を目指します。
楽しんでいただけるように頑張りますのでよろしくお願いします。
少数でも誰かにハマって面白いとおもっていただけたら嬉しいです。
第一章時点では純粋な冒険物語として見ていただけたらと思います。
チート、無双、ハーレムはありません。
【おそらく楽しんでいただける方】
・少年漫画とかが好きな方
・異能力バトルが好きな方
・細かめの戦闘描写がいける方
・仲間が増えていく冒険ものが好きな方
・伏線が好きな方
・ちょっとダークなのが好きな方
章が進むと色んな種類の悪い人や死の表現がでます。苦手な方は薄目での閲覧をお願いいたします。
誤字脱字や表現おかしいところは随時更新します。
ヒューマンエラーの多いザ・ヒューマンですのでご勘弁を…
※各話の表紙を随時追加していっています
異能力×スペースアドベンチャー×少年漫画風ストーリー!!
練りに練った物語です。
文章は拙いですが、興味を持っていただいた方に楽しんでいただけただけるよう執筆がんばります。
本編 序盤は毎日21〜24時くらいまでの間
間話 毎日21〜24時くらいまでの間
(努力目標)
一章が終わるごとに調整期間をいただく場合があります。ご了承ください。
古参読者であることが自慢できるほどの作品になれるよう努力していきますのでよろしくお願いいたします。

仮想空間のなかだけでもモフモフと戯れたかった
夏男
SF
動物から嫌われる体質のヒロインがモフモフを求めて剣と魔法のVRオンラインゲームでテイマーを目指す話です。(なれるとは言っていない)
※R-15は保険です。
※小説家になろう様、カクヨム様でも同タイトルで投稿しております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















