2 / 106
序章・新たなる邂逅編
出会いの予感
しおりを挟む
「御玲よ」
「なんですか」
「こんなことを言うのは労働者としてダメかもしんない。でも聞いてくれ」
「はい」
「クッッッッッッソ忙しくね!?」
盛大な台パンとともに大都市を眺められるテラスで、自分の背丈よりも高い槍を隣に携える、メイド服を着た青髪の少女―――水守御玲に向かって高らかに叫んだ。
テーブルに乗っている食事や飲み物が衝撃で溢れそうになるが、そんなことは気にならない。
「そうっすよね、就職した瞬間にこの状況っすからね」
隣で大量の料理を注文すると同時、馬鹿デカいがま口へ吸い込むように一口で料理を食べていく二足歩行の暴食蛙―――カエル総隊長が、手についた油やら何やらをベロで舐め取り、また新しい皿に手をかけた。
「ったくよぉ……こんなに忙しいなんざ聞いてねぇぜ、糞する暇もねぇ」
「そうだよ、せめてオ◯ニーする時間くらいは欲しいよね。最低労働チン金としてさ」
「一応聞くけど、そのチンってどっちのチン?」
カエルの両隣で思い思いに喋りだす二体のぬいぐるみとロン毛の少年。
茶色のソースでベッタベタにしたハンバーグにかぶりつく子熊―――ナージは眉間に皺を寄せて俺を睨み、裸エプロンを着こなす小人のオッサン―――シャル、そしてどうでもいいことを問いただす空色のロン毛―――ミキティウスも口の周りをベッタベタにして、口の中に飯を頬張ったままこちらを見てきた。
汚いですね、と御玲がため息をつきながら、ハンカチでぬいぐるみどもの顔面を無造作に拭き取る。
俺たちがいま昼食を取っているこの場所―――任務請負機関北支部に就職したのは、つい三日前のこと。俺の人生を狂わせた怨敵にして実の親父―――流川佳霖への復讐を済ませた俺は、ひょんなことから任務請負機関で働くことになっちまった。
そのひょんなことってのがまためちゃくちゃな話で、流川家と互角の力を持つ戦闘民族―――花筏家との同盟と、俺たちがいるこの国、武市の隣にある大国―――巫市との国交樹立という、年齢十六歳の若者には絶対似合わない大仕事をやらなくちゃならないってことである。
そのためには任務請負人として実績を積んで支部から本部へ昇進し、その本部の重鎮に信用してもらうというクソ高い壁が聳え立っていて、まずはその壁を越えなきゃならない。
一難去ってまた一難。三ヶ月かかった復讐がやっと終わったのに、休む暇もなく就職して労働者である。勘弁してほしいものだ。
「それにしても忙しい……就職してからずっと、討伐任務ばっかりやってる」
さっき注文したハンバーグステーキを食らう俺は、就職してから今日までの忙殺っぷりを振り返る。
任務請負人は就職したその日から働けるのだが、俺たちが就職した頃は何故か支部内が慌ただしく、俺たちはわけも分からんまま、その慌ただしい波に呑まれて流されて、ずっと討伐任務をこなしてきた。
基本的に昼と夕方の帰宅時以外は休む暇がない。「時間に余裕がある限り討伐任務に受注せよ」と支部内のアナウンスがひっきりなしに鳴り響いており、俺たちはアナウンスに急かされるように、ずっと働き詰め状態なワケだ。
「仕方ないじゃないですか。あんな事件のとばっちりを受けてるんですから」
マカロニサラダを食べ終えた御玲は、口をナプキンで拭き取ってテーブルに置く。
御玲が言うあんな事件とは、六月二十三日、巫市で起こった大事件のことだ。
「妖精王襲撃事件だっけか……冗談みたいな事件だよな。なんだよ、妖精王って」
「それは分かりませんが、その妖精王とやらの霊圧により、この大陸の霊力分布が歪んでしまって魔生物のスタンピートが起こってしまった。放っておけば死傷者が出ますし、対処せよってことでしょうね」
「ったく、んなもんその妖精王? とかいうキチガイにやらせりゃいいじゃん。なんで無関係な俺らがやらなきゃならんのだか……」
「ここはプラスに考えましょう。実績を積み、昇進試験受験資格を得る好機だと。ただ漫然と任務をこなすより気持ちは軽くなるでしょう?」
「まあなぁ……当事者がスルーかましてるのは気に食わんが、そこは俺らがオトナの対応すればいいだけだもんな」
そうですそうです、と御玲が二回首を縦に降る。
任務請負機関には四つの支部と、それらを統括する本部がある。
まず請負人への就職は、必ず支部からすることとなり、本部に直接就職することはできない。本部へ異動するには、年に二度行われる``本部昇進試験``を通過する必要がある。
じゃあさっさと試験を受ければいいのでは、と思われるだろう。だがそう簡単に物事は進まない。本部に昇進するには試験に合格しなければならないように、その試験を受験するための、受験資格を獲得しなければならないのだ。
その資格は主に二つ。一つは任務をこなして実績を一定数稼ぐこと。もう一つは要求されている身体能力を十分に満たしていることである。
「受験資格の取得状況って、確か任務請負証を見れば分かるんだよな?」
御玲に問いかけながら、俺の視界に色んなオブジェクトが映り込む。
任務請負人は就職手続きをすると``任務請負証``っていう、いわゆる身分証明書みたいなものがもらえる。
それは別に書類ってわけじゃなく、カードになっているわけでもない。なんと驚き、体内に吸収させることによって発動する、一種のトリガー式魔法陣媒体になっているのだ。
体内に吸収されると脳内で再構築され、意志に反応して視界に色々な情報を映し出してくれる。
当然、全部非表示にすることもできる。というか基本的に必要なとき以外は非表示にしとかないと、視界に色々なものが映り込んで前が見えなくなってしまう。
操作は頭で思い浮かべるだけでできるので、基本的には食事がてら操作したり、拠点に帰ってまったり操作したり、そんな感じで使用するものである。
「まだ出勤三日目ですよ。身体能力はともかく、実績は全然足りませんよ」
自分の身体能力を参照してみる。
身体能力を表す項目は全部で七項目がある。まずは霊的ポテンシャル。
霊的ポテンシャルってのは、体内に溜め込んでおける霊力の許容量を表す数値で、数値が高ければ高いほど、より多くの霊力を体内に貯めこむことができる。
ちなみに``霊力``ってのは、簡単に言えば魔法や魔術を使うためのエネルギーみたいなものだ。戦闘の際は、この霊力ってエネルギーを元手に、魔法や魔術とかを使って討伐任務とか、敵と戦ったりするのである。
話を戻そう。霊的ポテンシャルの支部平均数値は、三十から四十の間らしいのだが。
「おかしいよなあ、俺の霊的ポテンシャル。二百五十プラスだぜ? 支部平均が低すぎるのか?」
俺の数値は、この時点でトチ狂っていた。その飛び抜けた数値に、思わず苦笑いが溢れてしまう。
支部の平均が三十から四十だっていうのに、俺の数値ときたら二百超というアホみたいな数になっているのだ。
元々霊力の消費とか昔から気にしたことなかったし、どれだけ使っても胸の奥底からボコボコ湧いて出てくるから、``霊力が尽きる``、なんてこともほとんどなかった。仮に尽きても、ほんの数秒経てばまたバンバン使える始末である。
ちなみにプラスってのは、自然回復とは別に霊力が何かしらの能力で継続回復しますよ、って意味らしい。
つまり俺は飛び抜けた霊力量に加え、自然回復とは別に霊力継続回復能力も持っているってことを意味する。
そりゃあどれだけ使っても減らないし、消費も気にならないわけだ。元からたくさんある上に、減ってもすぐ補充されるのだから。
「澄男さまは面白味のある身体能力値で良かったじゃないですか。私なんて全ての数値が百で統一されてるんですよ。つまらないったらありゃあしませんよ」
ため息をつき、水を飲む御玲。
霊的ポテンシャルのほかに物理攻撃力を表す``物理攻能度``、魔法攻撃力を表す``魔法攻能度``、物理防御力を表す``物理抗能度``、魔法防御力を表す``魔法抗能度``、敏捷能力を表す``敏捷能度``、回避行動に必要な条件反射能力を表す``回避能度``があり、それら七つ全部を合わせて、身体能力を簡単に数値化したものが``全能度``となる。
霊的ポテンシャルと同様、各項目三十から四十程度が平均なのだが、御玲は本人の言う通り全ての値が百。俺も当然百以上で、回避と敏捷に至っては百十を超えている。
つまり、御玲と俺は現時点でオーバースペック状態。その証拠に受験資格獲得に必要な身体能力は、全能度で表すと三百五十であるが、そのボーダーは任務請負証をもらった時点で、クリア済み扱いとなっていた。あとは純粋に、実績を積むだけなのだ。
「今回で実績満たせればいいんだが……」
「いやいや、無理でしょう」
天窓に映る空を見上げる俺に、御玲は鼻で笑う。
「そんなすぐに満たせてたら、ほとんどの人たち本部に行けてますよ。何度も言いますけど、私たちまだ出勤三日目ですからね? たったの」
「でも正直おんなじことの繰り返しだぜ……特に変化もないし、飽きてきたというか……」
「何言ってんですか。阿呆なこと言わないでください」
一蹴された。分かってはいたけど、本音を話すとまさに「飽きた」の一言に尽きるのだ。
さっき御玲は魔生物のスタンピートが起きていると言っていたが、そうは言っても一匹一匹は存外大したことはない。高くて全能度三百程度のザコがちょくちょく現れるようなもので、それらを倒すのは正直ただただ作業なのだ。
俺と御玲にかかれば、ワンパンで終わる連中である。これを退屈と言わずなんと言おうか。
「現状に不満があるなら黙って実績を積む。そして相応しいと思える場所に自ら行く。ただそれだけです」
「あーもうわーったよ、やりゃあいいんだろやりゃあ」
全身に気怠さが募り、今から任務に行こうというモチベが目減りする。
気がつくと全員が食べ終えていた。今の俺たちにとって昼飯を食べているときだけが昼休みだ。その休みが終わった以上、夕方までまた退屈な任務をこなさなきゃならない。
今までは自由気ままに動けていただけに、こうも同じことをさせられていると拘束されている感が身体を縛りつけてくる。
俺は最後の気休めに、いま受注している任務を確認する。
任務の受注は、基本的に任務請負証で行う。つまり頭の中で思い浮かべるだけで受注できてしまうわけだが、俺たちが就職した時期は``フレキシブル討伐任務週間``という謎のイベント期間の真っ只中だった。
この期間中は、任務の受注をする必要はない。既に全ての任務請負人が勝手に任務受注状態になっていて、暇な時はとにかく目についた魔生物を、期間が終わるまで狩り続けなければならないのだ。
別にサボっててもペナルティとかはないみたいだが、討伐数が一定数満たしていないと無報酬になってしまう。そしてその一定数というのは非公開で、受注している任務請負人からは分からないといった仕組みだ。
御玲は、その一定数だけ狩ってそれ以降仕事をしなくなる請負人が続出するのを防止するためだろうと言っていたが、やっぱり楽する道ってのは事前に潰されているものである。
「せめて北支部の最強格の連中と会えたら面白いんだがな……」
などと小声でぼそりと漏らしてみる。横で御玲が肩を竦めた。予想以上に聴覚が良くてビックリする。
俺たちが就職したのは任務請負機関北支部、正式には任務請負機関ヴェナンディグラム北支部だが、それとは別に南、東、西の三つの支部がある。
その各支部にはいわゆる四天王的な、最強格の実力を持った請負人が二人ないし一人ずついる。俺たちが就職した北支部には、``閃光のホーラン``ことレク・ホーラン、``百足使いのペグランタン``ことブルー・ペグランタンの二人が最強格として聳え立っていて、特にレク・ホーランとかいう奴は請負機関内外でも有名な存在らしく、北支部勤めの請負人でも最古参の存在だった。
御玲によると、レク・ホーランは新人研修するとき以外滅多なことでは支部におらず、個人的に会うには新人研修を狙うしかないらしい。それでもたくさんの新人を相手にするので、話す時間などないんだとか。
「ブルー・ペグランタンの方もいねぇし……話じゃ、支部のどこかしらで雑魚寝ぶっこいてるって話じゃなかったのかよ」
三日前に見せられた、黒光りする怪物の身体に包まれて昼寝している少女の写真を思い出す。
勤勉なレク・ホーランとは対極に、ブルー・ペグランタンは金が無くならない限り働かない、怠惰を絵に描いたような奴らしいのだが、そういう印象の人物は今のところ全く見かけていない。なんなら就職してから今日まで一度も見かけていないのだ。
俺が見た写真では、自分の背丈の倍以上はあるだろう怪物に身を包んですやすやと寝ている少女で映っていたが、その怪物も見当たらない。
写真から体のほとんどが見切れていたし、かなりデカい図体しているはずだから、そんなのが北支部の建物ン中にいたらすぐ分かるはずなのだが、ただただ有象無象の請負人が忙しなく建物ン中を歩き回ったり、テラスとか休憩所とかで仲良く駄弁っている様子が目まぐるしく見られるだけだ。
「縁があれば会えますよ。こっちから無理に干渉する理由もないですし、さっさと仕事しますよ」
これまたド正論。言い返す余地もなく、自分より背の高い槍を手に持つ。食べ終えたカエルたちも立ち上がると、鬱陶しくも俺の頭や肩に飛び乗る。
肩や頭の上で騒がれるとうるさいのでやめて欲しいのだが、このパリピぬいぐるみ軍団は騒ぐなと言うともっと騒ぐ厄介な天邪鬼連中なので、とりあえず放っておくことにしている。
ぬいぐるみを連れ歩きながら支部内を歩くのは、変に注目集めて恥ずかしい。なるべく目立ちたくないのに、これでは身分を隠している意味があるのかと思えてくる。
性懲りもなく無駄に注目を浴びながら、俺たちは支部を出た。今日も今日とて、終わりの見えない討伐任務、その後半戦が始まる。
季節は夏。もうまもなく七月になる武市は、気温が既に三十度を超えている。支部内はクーラーが効いているので涼しいが、カンカン照りの太陽光が肌を焼き、舗装された道路から熱気が沸き立つ。
ここで風が吹けば少しは涼しく感じるものなんだが、周囲には風の行手を阻むように、無数の密接した集合住宅が立ち並んでいた。
いま俺たちが歩いている地区―――中威区北部郊外集合住宅地帯は、とにかくどこもかしこも密な集合住宅しかない。
区の中央に行けば三ヶ月前まで通っていた俺の高校があり、その近くには商店街がある。いま俺たちがいる北支部周辺は中威区でも北方にあり、中央商店街からは気が遠くなるくらい距離が離れていた。行こうと思うと空を飛んでも二日はかかってしまうだろう。
今のところ行く気はないので、どうでもいいが。
そんでもう一つ、こんなにたくさんの古臭い家がクソみたく立ち並んでいるにも関わらず、人がそんなにいないって状況である。
外に出歩いている奴もまばらで、舗装された道路はゴミだらけ。中には窓からゴミを投げ捨てている奴もいる始末で、正直初めて見たときは目を疑ったものだ。慣れてしまうとあら不思議、どうでもよくなってしまうのだが。
「ゴミ拾いしたくなってきますね、いつ見ても酷い惨状です……」
全員慣れたかと思っていたが、まだ慣れてない奴がいた。よくよく考えれば、女にはキツい環境である。
確かにどっかの誰かが生ゴミを投げ捨てているせいで、カラスがゴミ袋を破ってそれをほじくりかえしているし、中身も腐っているから、くさいのなんの。
気持ちは分からんでもない。でも正直拾ったところでまた捨てる奴がいる以上、捨てる奴をブチのめすとかでもしない限り意味がない。この手の奴は口で言ってもどうせ「バレなきゃいい」の精神だし、こっちがただの徒労を背負わされるだけだ。第一、ゴミ拾いしたところで金にならんし。
「いいじゃないすか、生ゴミっすよ生ゴミ。食えるだけまだマシっすよ」
頭から飛び降り、カラスみたく生ゴミを漁って中身を食べようとするカエル。俺はそれを見逃さない。
「食ってもいいが、帰るまでお前、歩きだぞ」
「えー! そりゃないっすよ!」
「そりゃあねぇのはこっちだ、そんな汚ねぇもん食った手で俺の頭に触れるつもりか!」
「いいじゃないすかー、どうせ帰ってシャワー浴びれば綺麗になるし」
「流石の俺でも腐った生ゴミに触るほどの度胸ねぇから。精々匂いに耐えられるレベルだから。だから触るんなら歩け、嫌ならゴミ食うな。いいな?」
へいへーい、と不満そうにがま口を尖らせる。全く少し目を離すとこれだ。
昨日もコイツそこらに落ちている腐った生魚の内臓食っていやがった。流石の俺も、その場面見たときはリアルに悲鳴あげたほどだ。どういう神経していたら羽虫が集っている魚の内臓を鷲掴んで食えるのか。やっぱ蛙だからなのか。
「で、テメェは何しようとしてる?」
「あ? 見てわかんねぇか? ウンコだよウンコ。昼飯食ったから催してんだよ邪魔すんな」
「邪魔するわ!! こんな道路のど真ん中で催すんじゃねぇ!! あともう少ししたら公衆便所あっから、そこでしろそこで!!」
「チッ……別にいいじゃんかよ。そこらゴミだらけだし、今更野糞の一つや二つ増えても大して変わんねぇよ」
そういう問題じゃない。やったらやったで窓からゴミ投げ捨てたり、そこらにゴミ捨てている野郎と同等になっちまうだろう。
いや、ゴミが目の前にあるのに拾う気がない俺らだって同じかもしれんけど、自らゴミ量産してないって点でまだマシなんだから、そのマシな部分保とうぜ。
というか任務請負人が街汚しちゃダメな気がするし、野糞なんてもってのほかだ。ただでさえここらへん生ゴミ臭がやばいのにさ。
般若のような表情でゴミ袋に唾を吐くナージは、白い翼を無造作に羽ばたかせ、腕を頭に回してだらけながら飛行する。
「見て澄男さん!!」
「なんだ? ロクなもん持ってこなかったら直でシバくぞ」
「オ◯ホ見つけた!! これ澄男さんのサイズにぴったりじゃない? 結構デカいよこれ!! 洗えばまだ使える!!」
「元あったゴミ袋に返してきなさい!!」
満面の笑みを描き、よちよち歩きで身の丈に合わないソレを持ってくるシャル。
裸エプロンを着こなす二頭身のオッサンの顔は、公園で面白いものを発見し、それを親に無邪気に報告してくる純粋無垢な子供のようだが、コイツの手に持っているもののせいで、純粋無垢の欠片も感じられない。シャルの存在も相まって、穢れの権化と化してやがる。
「お前らいい加減にしろ!! ゴミを漁るな食うな催すな!! ミキティウスを見習え!! アイツなんか静かに俺たちの後ろを」
「あの、澄男さま……」
「どした」
「その、ミキティウスが……」
「スー……ハー……スー……ハー……」
御玲が見るからに不快な顔で肩を叩いてくるので、指を刺された方に視線を向ける。
「……なに、やってんだお前」
どっかの某実写宇宙戦争物の映画に出てくる真っ黒な仮面とマントを着た、ラスボスみたいな鼻息を出す空色のロン毛が、そこにいた。俺は思わず顔を歪める。
「このパンツ気に入りまして。程よく臭く、程よく黄ばんでいる。今の俺の気分にぴったりだ……」
いや、すっごい汚いんだけど。黄ばんでるってそれ、何処の馬の骨とも知らん奴の排泄物だよねそれ。
つーか今の俺の気分にピッタリとか言われても、他人の排泄物がガッツリついたボロ雑巾みてぇな下着で表される気分ってどんな気分なんだよ。絶対ロクな気分じねぇじゃん。
「うわぁ、ないわぁ……流石キモパンティウス」
「糞パンティウスと言われるだけあるな。ホント神経疑うぜオメェ」
なんか知らんけど蛙と子熊がドン引きしてる。俺らマトモな神経してるぜみたいに言ってるけど、お前らも同類だからな。前々から思ってたけど、お前らのそのドン引くドン引かないの線引きどうなってんだよ。
「とりあえずミキティウス。汚ねぇからそのパンツは元あったゴミ袋に返してこい。あと今後、ゴミ袋を勝手に漁るな。汚いから。マジで汚いから」
「なんてことを!! 汚くなんかありません!!」
「汚ねぇよアホか!!」
すっごい真剣な眼差しで逆ギレされ、俺も思わず声を荒げる。
その下着を美しいってガチで言ってるなら、お前の美的センスを二度と信用しないぞ。というかマジでゴミ漁りやめてくれ。なんでそんな当たり前のことができないんだ。人間じゃないからか。
しばらく言い争いになったが、ミキティウスは根負けし、パンツを捨てに行った。むしろ間違ったこと言ってないはずなのに、なんで言い争いになるのだろうか。ちょっと意味がわからない。
「そんで澄男さん、今日もアレっすか? 虫取りっすか?」
もう無関係と言わんばかりに話題を変えてくるカエル。その態度に些か不満が横たわるが、俺はオトナの対応で受け流し、やっと今日の本題に入る。
現状スタンピートを起こしている魔生物は、実を言うと主に虫。
アペスっていうハチ型の魔生物を筆頭に、色々な虫型の魔生物が街中で大量発生し暴れ回っているのだ。俺も昨日まで、手当たり次第にハチと格闘戦を繰り広げ、難なくそれらを討伐してきている。今となっては、ハチ駆除のプロを自称してもいい気がするくらい、自信がついてしまった。
「アペスは本来、この時期はヘルリオン山脈を生息圏にしているはずなのですが、夏に北上してくるのはおかしな話なんですよね。冬はわかるんですけど」
御玲が虚空を見つめ、でも何かを追いながら呟く。おそらく任務請負証に映っているオブジェクトを参照しているんだろう。
アペスはハチ型の魔生物だが、最大の特徴はとかくデカいことだ。
大人一人分の背丈を持ち、人間に対して敵対的で、基本的に二十匹ないし十匹の群れで行動し、人間を見つけると外敵と判断して向こうから問答無用で襲いかかってくる。
一匹一匹の全能度は百二十一と大したことはないが、いかんせん群れで一斉に襲いかかってくるので、かなりめんどくさい。ケツについてる針には魔法毒とかいうクソ厄介なのが付いているし、それを一斉に飛ばしてくるとなると、捌くのが中々かったるいのである。
向こうから領域侵犯しておいて、元々ここを生息圏として生活している俺らを攻撃するなんざ理不尽極まりない話だが、相手は魔生物だ。思考もしないし意志も持たない、ただ生存本能が備わっているだけの生き物。そんな奴らに人間の理屈が通じるはずもない。
そんなわけで、今日も今日とてアペス狩り。全能度百程度とはいえ軍団で襲いかかられると辺りに住んでいる一般人からしたら割と脅威らしいし、巣でも作られた日には厄日と化すらしいので、そうなる前に駆除するわけだ。
「あー……あと何匹ハチ退治しなきゃなんねぇんだかなぁ……」
「クソ、こんなの聞いてねぇよ!! 俺こんなとこで死にたくねぇ!!」
今日ブチ殺すハチの数を予想してた矢先、俺らがいる場所から数十メトくらいか、それぐらいの距離離れた所から、男の悲鳴が聞こえた。
御玲が目配せしてくる。そのサインに黙って頷き、足元でどんちゃん騒ぎしてたぬいぐるみどもにも声をかけると、声をした方向へと走る。
住宅と住宅の間の路地から、二人連れの男が、飛び出してきた。二人とも、俺や御玲よりも結構年上。三十歳くらいだろうか。
最初はそこらの一般人かと思ったが、着てる服から見え隠れする鉄製の装甲みたいなものと、腰に光る短剣のようなものを装備してるところを見るに、アイツらも任務請負人。だが何かに怯えて逃げてきた様子で、全く戦う素振りを見せない。
腰に携えている光る短剣すら抜かず、ただ腰を抜かし、お互い身を震わせてヒィヒィ間抜けな悲鳴をあげているだけだ。
まさかだけどアペス如きにビビってるとかそんなんじゃないだろうな。だとしたらザコもいいトコなんだが、流石にそれはないだろう。曲がりなりにも俺らより年上だし、並みの実力はあるはずだ。
「お、おい!! 置いてくなよ、大体アレどうすんだアレ!!」
「し、知るか!! 俺は知らねぇ!! 命あっての物種だ!! ここらの住民には悪いがな!!」
並の実力はあるはず。そう言ったが前言撤回したくなってきた。男のうち一人は仲間と思わしき連れすら犠牲にして逃げようとしているが、その連れが逃亡を許さない。見捨てられるならせめて道連れに。そんな気迫すら感じさせる。
お互い敵を目前にして醜く足の引っ張り合いしてやがるのだ。こんなザコどもが、並の実力すら持ってないのは考えるまでもねぇ。
「チッ……邪魔だな」
思わず本音が漏れる。あの手の奴らは弱い癖に隙あらばキャンキャン吠える以外に能がないから嫌いだ。
弱いならとっとと消えろって話だし、なんならここで焼き尽くしたいぐらいだが、ここで波風立てて今後の活動に支障をきたすとまずい。なにより御玲に怒られるのは避けたいのだ。
「行くか?」
とりあえず御玲にも聞いてみる。正直このまま行ったら確実になすりつけられるが、むしろそっちの方が、都合がいい。
変に手伝うとか言われて邪魔になるよりも、さっさとなすりつけてどこぞへと消えてくれれば、俺らが手柄を総取りできる。
「ですね……とりあえず、あの二人の全能度の確認をと」
任務請負証の機能を既に使いこなし始めている御玲。今から突っ込もうという俺をよそに、冷静に状況を把握する。
「逃げようとしている方は二百五、腰が抜けて動けない方は百八十程ですか。澄男さま、杞憂に終わると思いますが、念のため全員でいきましょう」
おう、と承諾の意を示す。二百五、百八十なら、あのハチどもに十分対抗できるはず。つまり、アイツらが今出くわした存在は、アペスより遥かに強い何か。
流石に御玲の全能度である七百を超える奴がいると思えないが、一応、皆で話し合った手筈では、敵の全能度が御玲を超える可能性がある場合、過剰戦力になるとしても初めは全員で相手をすることになっている。
戦力を小出しにすると、万が一対応ができず死ぬ可能性があるからだ。厄介なのが俺に来れば問題ないのだが、俺以外、特に御玲一人に出くわすとマズイ。御玲は人間相手なら負けることはないけど、相手がバケモンとかだと話は変わってくる。
「よし、行くぞ!」
話はまとまった、カエルたちに突入の合図をする。
物陰から見ていた俺らは逃げようとして足がすくんで動けないノロマたちに割って入る形で、ソイツらが相対していた奴のツラをついに拝んだ。
「これは……」
「あー……なるほど。コイツか」
それは空いた口が塞がらなくなるほどの、まさに異形の塊だった。御玲と俺を交互に見やる鈍亀をよそに、その異形の正体をすぐに悟る。
確かにこの国、この街で育った奴には馴染みがないかもしれない。というかコイツも人里に降りてくるタイプだったのかと、いま初めて知ったぐらいだ。
「そうだよな、今はもう夏だ。まさかこんなところで``夏の風物詩``と出会えるなんてな」
足や手首をブラブラさせて軽く準備運動。明らかにアペスなんかよりも強いソイツと戦えるのだから、準備運動程度の力は出せそうだ。どちらにせよワンパンなのは変わりないが、ここで変化球が来てくれるのは嬉しい。
「インサニス・シカディスですか……いつ見ても気持ち悪い外見です」
気怠そうに槍を近くに置く御玲。一応体を軽く解しているが、戦う気はない。
そりゃそうだ。この中で誰か一人でも戦えば、確実にブチのめせるんだから。
インサニス・シカディス、通称``夏の風物詩``。毎年六月から九月にかけて、南の山奥から血肉を求めてやってくる``蝉``だ。
体長は二メト以上。赤黒い羽根と、脳味噌を彷彿とさせるブヨブヨの体、赤い複眼と身体中から生えている無数の触手が特徴的な虫型魔生物の一種である。
俺がまだ本家領にいた頃も、夏になるとコイツがぶんぶんぶんぶん飛んできては、庭で修行していた俺を食おうと襲いかかってきていた。
幼少の時点で一方的に八つ裂きにできていたから、俺からすればただの雑魚でしかないが、確かに全能度二百程度の奴じゃビビるのも納得だ。なにせコイツの全能度、今測ったら五百くらいあるんだから。
「どうする、お前いっとくか?」
「いえ、澄男さまに譲ります。私はアペス狩りで結構ですので」
「んじゃ遠慮なく! おいお前ら、手ぇ出すなよ。コイツは俺が片付ける」
「ウェェェェイ!! やっちゃってください澄男さぁん!!」
「負けたら食糞だぞ食糞!!」
「いや、まずはボクのち◯こを舐めろ!! それから御玲さんの糞だ!!」
「パンツが高まる……!! 溢れる!!」
背後から聞こえる意味不明な声援。いつもならものすごくうるさいが、久しぶりの日常の変化のせいか、コイツらのイタい台詞も心地よく感じてくる。
問題はない。相手が蝉なら、負ける気がしない。
「コイツには炎は効きにくいんだが……俺には関係ない。血肉一欠片も残さず焼き尽くす!!」
右手に宿るは、赤白い火球。頭の中で火をイメージし、それをアホみたいな霊力で出力して具現化。さらにそれを握り潰すイメージで圧縮して初めて完成する特製の火球―――その名も``煉旺焔星``。
生まれたての星の如く輝くそれは、命中したが最後、相手を問答無用で灰燼に帰してしまう。
いや、その灰すらも燃え尽きて残らないだろう。実際、俺の右掌にある状態でも、周囲のものを熱気で歪めているほどなのだ。
カエルたちはあらかじめ距離を取り、熱気の影響からはそそくさと退避している。一方、路地を通せんぼする蝉はというとなんとも驚き、まったく動じていやがらない。
さっきも言ったが、コイツは火があんまり効かないので耐熱性能もやや高め。幼少の頃に殺し合った時も、火の球近づけた程度じゃビビってさえいなかった。
でも流石に火の球そのものの熱さは感じ取っているようで、さっきよりも触手の動きが格段に鈍くなっている。触れれば灰も残らないことを、本能で悟ったのだ。
とはいえ、悟ったからではもう遅い。
コイツは蝉なだけに空を飛ぶし、図体デカい割には触手が器用で、そこそこ速く地上も移動できる。
曲がりなりにも虫だから無理もない話だが、俺からすればノロマだ。コイツが動くよりも速く、コイツを跡形もなく消し去れる自信がある。
蝉からの殺気は消えない。火の球を持った俺と相対してなお、弱っちい霊圧で、尚も威嚇してくる。
俺への恐怖よりも、血肉への食欲の方が勝ったらしい。だが別に構わない。かかってくるなら、容赦しない。ただそれだけだ。
「消えてなくなれ!!」
右掌にのせていた火球が一瞬光り輝く。周囲の建築物が破壊されない程度に手加減したそれは、蝉の腹ン中で光ったと思いきや、蝉の身体が一気に十倍くらいに膨れ上がった。
火は基本、水に弱いが、超高熱の炎はその弱点を無効化する。水は高々百度でただの空気になっちまうが、火は霊力を込めれば込めるほど熱くできる。それも一つの星ぐらいの温度にすることも可能だ。
蝉の野郎の身体は実を言うとほとんどが水でできている。だからこそ打撃はあんまり効きづらいんだが、だったら肉体を内側から蒸発させてしまえばいい。
体のほとんどが水分でできているってんなら水蒸気に変えてしまえば火への耐性など関係ない。一瞬で破裂してチェックメイトである。
結果は俺の予想は裏切らなかった。蝉の体が一瞬火照った海老みたいになった瞬間、風船がブチ破れるようにその中身を炸裂させたのだ。
そこらの生ゴミとは比較にならない、生き物が焼ける生々しい悪臭が漂う。蝉の内臓だったらそれは真っ白に蒸されており、もくもくと水蒸気が舞ってやがる。俺はというと、もう言わずもがな、だ。
「うえぇ、ぺっ、ぺっぺっ」
「澄男さん……臭いっす」
「きったねぇなおい」
「わーってるわ!! クソ、こうなるのすっかり計算に入れ忘れてたぜ……」
「むしろなんで忘れるんすか、普通予想つくでしょ、そうなるの」
蒸した内臓塗れになった俺は、とりあえず顔にべっとりついた何かを手ではたき落とす。服からズボンに至るまで、なにもかもが真っ白に蒸された何かでぐっちょぐちょだ。こんなんで支部には帰れない。一度家に帰ってシャワー浴びないと。
「シャワーはダメですよ。浴びる前に庭で洗い流してください。下水詰まるんで」
目から光を消し、淡々と辛辣なことを吐く御玲さん。
そんなこと言われても、庭で洗い流すような場所なんかない。ウチの弟がどっかに庭に水撒く用のシャワー的なものを設置していたかもしれんけど、俺は花壇に水やったりしないからそんなんどこにあるか知らんし。にしても、これ。
「生ぐせぇ!!」
とりあえず顔についたものは取れた。服についたやつはどうにもならんので、もう諦めることにする。
幸いただのTシャツなので捨てればいいが、無一文の今、新しい服を買う余裕がない。一応、Tシャツの予備はまだあるけど、それも無限ではないのだ。ズボンなんてあと何着あるか。
「そんなことよりどうするんすか、誰かが住んでる家にべっとりついてますよこれ」
カエルが右と左を交互に指さす。
俺が蝉と戦っていたのは集合住宅同士を挟んだ路地。かなり狭く、俺と蝉がいるだけで二人目は同時に通れないほどの幅しかない。そんな狭い路地で虫の内臓を炸裂させただけに、左と右の集合住宅にはべっちゃりと白い残骸がついてしまっていた。
「……焼く?」
「澄男さまがやると住宅まで燃えてしまいますよ」
「じゃあ水かけて落とす」
「この場で水出せる奴いないっすよ」
「じゃあお前がこの白いのを全部食うってのは?」
「あー……まあいけなくはないっすけど、インサニスの内臓って蒸しても臭み消えないんすよねー、見た目蒸したエビの中身みたいな感じっすけど」
冗談で言ったのに、真剣に食うかどうかを吟味してやがる。べっとりついた内臓の残骸を真剣に眺めている二足歩行のカエルのぬいぐるみの図は見ていてシュールだが、コイツはかつて、蛆虫が大量に湧いている腐った生魚の内臓を素手で掴んで丸呑みしたことがあるほどの雑食家。インサニスの蒸した内臓の残骸など、そんなのと比べればまだマシな方なのかもしれない。
苦いもの以外は特に好き嫌いがない俺でも、雑食すぎてドン引きだ。
「まあ食えるなら食ってくれ。そこらに一杯あるし。でも持ち帰りはナシな。そんなもん家に持ち帰えられても困るから」
「タッパーに入れて冷蔵庫に入れときゃ、そこそこ保存効くっすよ?」
「ダメだ!! ウチの冷蔵庫は人間が美味しく食べられるものしか入れません!!」
ちぇー、と白いそれを手で摘み、手ごと派手に頬張る。
今日食べたハンバーグステーキが迫り上がってきた。とりあえず夏の風物詩は倒したし、カエルはほっといて次の狩場に―――。
「お、おいガキども」
聞き慣れない声が鼓膜を揺らす。振り向くと、光る短剣を御玲の首元に突き立てる男二人組がいた。
ついさっきまで、蝉にビビって腰抜かしてヒィヒィ言っていた連中だ。
「テメーらこの前入ったヒヨッコだろ? 知ってんぜ、来た時からメイド侍らせてっからどこのぼっちゃんだよと馬鹿にしてたが、まさか``夏の風物詩``をワンパンとはな」
俺は盛大にため息を吐きつつ、めんどくささを全面に出した舌打ちをブチかます。苛立ちが腹の奥底から募り、冷めたばかりの右手がまた熱くなるのを感じた。
「とはいえ……悪いがその獲物は俺らの獲物でよぉ? つーわけで実績置いて消えなクソガキ」
「オラァ実績出せやオラァ請負証出せやだせつってんだろボコすぞ、ぼこしちゃいますよー? ボンボンボンボンボーン!!」
うるせぇ。まるで駄犬。
高校時代からそうだったが、この手のザコはたとえどこに行っても付き纏ってくる。さっきまでビビって腰抜かしていたくせに、どうやったらここまでイキれるんだろうか。そのまま恐れ慄いてどっかに消えてくれれば少しは可愛げもあったってのに、まさかこっちが新人なのを棚に上げて経歴マウント取ってくるとは思わなかった。それも実績を譲れとかいう謎の脅迫までしてきやがる始末。
ああ、不快だ。実に不愉快。
力もないただ弱いだけの雑魚のくせに脅威が去るとこれだ。昔の俺なら問答無用で塵芥にしてやったところだが、まだ俺らは出勤三日目。こんなところで、それもこんなつまんねぇ奴に波風立てるなんざアホらしいことこの上ない。
幸い、俺の目の前でボコすボコす言ってぴょんぴょん飛び跳ねてるわけわからんアホは全能度百八十、御玲の首元に光る短剣を突き立てて脅してるつもりになってるバカは全能度二百五。どっちも取るに足らねぇクソザコだ。
俺が出張らなくても御玲が冷静に対処してくれるだろう。ぬいぐるみたちが揃って手を出さないのも、御玲の実力なら余裕で対処できると判断しているからだ。ここで俺がしゃしゃり出る必要はない。幸い全能度百八十のアホは俺にかかりっきりだし、コイツの気を引きつつ御玲が対処するのを待つか。
「なにお前、実績の譲り方も知らないんですかぁ? まあ仕方ないよね、ぼっちゃんだもんね、新人だしこの俺が教えてやっからさ、さっさと請負証出せや、出せってんだよオラァ!! 出せや!! シカトかましてなよゴラァ!!」
「おいおいあんまりビビらせてやるなよ、まだ勤め始めたばっかの新人だぞ? トラウマになっちまったらもうこれなくなっちまうだろうがよ」
「だってさー、コイツ請負証ださねーんだもん、シカトしてやがるしさー、ムカつくっつーかなんつーか、もうボコしてもいいんじゃね? ここ人いねーし?」
「まあ待て、ただビビらせるだけじゃつまんねー。見てみろよお前、これ」
左手で短剣を突き立てたまま、男は恍惚で嗜虐的な笑みを浮かべ、その右手が動かした。
「ごぶっ!?」
男が右手を動かした瞬間、男の顔面が紅い火球に包まれる。
ぐああああああああ、と悲鳴をあげて地面を転げ回る男はもう御玲など眼中にない。顔面についた炎を消すため、懸命に顔を地面に擦り付けている。
一体何が起こったのか。んなもん簡単だ。アイツの右手が御玲のロングスカートに触れた、だから即興で作ったミニ火球を奴の顔面にデコピンでぶつけてやった。ただそれだけだ。
「て、テメーなにしやごはっ!?」
もうこのアホの妄言は聞く必要はない。手っ取り早く黙らせるために土手っ腹に蹴りを入れる。一応手加減してやったが、それでも十分すぎる威力だろう。アホは悲鳴すらあげる余裕すらなく、腹を押さえながら気絶した。
この間、僅か五秒。イライラの五割を消費し、やや胸が晴れた俺とは裏腹に、御玲は不満げにため息を吐きながら、こっちを睨んでくる。
確かに最初は御玲に対処させるつもりで、俺は囮に徹するつもりだった。でもあのバカの右手の動きを見たんじゃあ、悪いけど黙っていられない。
アイツの表情は``劣情``に塗れていた。女をただの道具としか見てねぇ下衆の情。
それを俺らに関係ない女に向けるってんなら好きにすりゃあいい。でも俺の仲間である御玲に向けるってんなら話は別。
悪いが俺はその手の劣情を仲間に向けられるのを良しとしない。かつてその劣情で、友を一人失ってしまったから―――。
「澄男さま、それ以上はダメです!」
「悪いな御玲。コイツらは俺の禁忌に触れた。ここで始末する」
俺の心は酷く冷静だ。怒っているはずなのに、いつもの烈火の如き怒りとは別の、ドス黒い感情が支配している。
御玲の声が遠く聞こえる。今の俺の頭の中はこの二人のクズを跡形もなく消し去る。ただそれだけしかない。
あのまま蝉にビビって消えてくれていたら何もしなかった。そうでなくとも俺らを脅す程度なら御玲に黙らせる程度で済ませてやった。でもコイツらはあろうことか、御玲に劣情を向けたのだ。
なら始末する。三ヶ月前の``悲劇``を繰り返すわけにはいかない。そうなるくらいなら、いっそ―――。
「澄男さま!!」
地面にうずくまり気絶するアホに向けて火の球を錬成する。
蝉を一瞬で破裂させた火球、煉旺焔星。これを目の前のアホと転げ回ってヒィヒィ言っているバカに使えば塵も残らない。流石にここらの家を壊すわけにもいかないから最小威力にするが、それでもコイツらを消し去るには十分足りるだろう。
多分コイツら殺ったら御玲は怒るだろう。もしかしたら恨まれちまうかもしれない。
でも俺は仲間を絶対に守らなきゃならないんだ。たとえ雑魚一人だろうと、その汚ねぇ手で仲間に触れる、それすら許すわけにはいかねぇ。これは誰がなんと言おうと譲れない、俺の絶対ルールなんだ。
前にみたいに手当たり次第殺し尽くす気はない。でも仲間を守るためなら``敵``と思わしき奴に容赦しねぇ。俺の仲間に汚い手で触れる全ての存在は、悪いがこの世から消えてもらう―――。
「粉々に……!?」
なりやがれ、と言おうとした、その瞬間だった。突然、濃い暗黒の霧が、一瞬で俺らを包み込んだ。
次から次へと面倒ごとばかりおこりやがる。わけがわからず辺りを見渡すが、気がつくと俺に絡んでいたアホと御玲を脅していたバカが見当たらず、御玲たちの姿も見当たらない。俺以外の存在が全て消えた。
一寸先が全く見通せない濃霧。肌から感じる感覚からして霊力のようだが、請負証の機能をもってして霧の正体が掴めない。ただの霊力で作られた濃い霧だ。
何なのか分からない。その事実が、背筋を冷たく凍らせる。
御玲がいない。カエルたちの気配が辿れない。仲間がいない。それがなによりも怖い。謎の霧で雑魚を始末し損ねたことも存外に苛立つが、それ以上に仲間をまんまと撹乱させられたのがとにかく気に食わない。
こんなことになるなら雑魚なんぞ捨ておくべきだったかもしれんが、なによりこの霧、全く予兆がなかった。霊力だってんなら、使われるときに気配の一つや二つ辿れてもおかしくないはず。霊力で作られた霧なのに霊力が感じないなんてことあるのか。
とりあえず冷静になれ。さっきまでの雑魚を葬り去ろうとしていたときの冷静さを取り戻せ。
おそらく新手の魔生物による撹乱攻撃。味方との連携はとれない。味方の場所は分からず、居場所を霊力で探ることもできない。俺は探知には向いてないから、基本的に察知は五感頼りになる。幸い五感は鋭い方だが、それでも探知が得意な奴には格段に精度で劣ってしまう。
ここにきて五感すら撹乱してくる魔生物の出現。厄介だ。厄介すぎる。せめてぬいぐるみどもさえいたらいくらか対処のしようがあったが、今は俺しかいない。
本当はやりたくなかったし、やるべきではないのだろうが。
「ここら一帯を霊圧でぶっ飛ばすしかないか」
霧は霊力でできている。ならこっちも霊力を放出して吹き飛ばす。
問題はこの霧を吹っ飛ばすのに必要な霊力量が分からんことだ。その場合、ありったけの霊力量を放出することになるし、そうなると最悪ここら一帯が死の大地と化す可能性がある。
俺の霊力量は膨大だ。基本的に常に体内は百を軽く超える出鱈目な霊力で満たされているから、全力で霊力を全方位に、それも対象を指定せず放てば、ウチの家の庭みたいな特殊な場所でもない限り、被害は甚大なものになる。
どれくらいの家屋が跡形もなくなるか、この俺でも想像がつかない。
仲間と連絡をとってみるか。いや、でもちんたらやってて仲間に何かあったら俺は正気でいられる自信がない。
弟に助けを呼ぶか。それも遅い気がする。説明している間にやられたら終わりだ。やばい、こんなこと考えている間にも御玲たちは―――。
「ふざけやがって……!!」
どこの誰だかしらねぇが、邪魔した挙句仲間の行方を撹乱させた罪は重い。
御玲とぬいぐるみたちなら、魔法防御力から考えて俺の霊圧には耐えられるだろう。御玲たち以外は分からんが、今は仲間が優先だ。
とりあえずこの鬱陶しい霧を吹っ飛ばして仲間の無事を確認し、霧を出した間抜けをブチのめす。そんで最後は禁忌に触れたあのザコどもを始末する。
方針は決まった。あとは実行するだけだ。
煉旺焔星を体の中に再吸収し、体の奥底に溜まっている大量の霊力を練り上げる。体の中に溜まっている霊力を一旦胸の部分にまで迫り上げさせて、そこで餅を練るイメージで練り込み、あとは一気に身体の外へ放出するだけ。それでチェックメイトだ。
俺を中心に、まるで地中に巨大なモグラが暴れ回っているような地響きが轟く。体内の霊力が足の裏を伝って地形に干渉でもしているのだろう。心なしか大気も震えているように感じる。
胸の中央部が熱い。もう少しで炸裂する。一切合切手加減なしの、練りに練り込んだ霊力が―――。
「今だ、むーさん!」
胸の内側で練り込んで炸裂寸前だった霊力が、今にも爆発するというその瞬間。
霧の中のどこかから聞き覚えのない男の声がした。誰だ、と振り向こうとするも、間もなく何かがぐるぐると俺の身体に巻きついていく。
「な、なんだ……!? さっきまで練りに練ってた霊力が……どんどん吸われて……!?」
わけがわからず振り解こうとするが、突然の出来事に思わず膝を折ってしまう。
意志に反し、体の奥底から何かが抜け落ちていく感覚。正しくは体の中身が吸われて、血の気が引いていく感じだ。血を吸われているわけじゃないが、体の中の霊力を強制的に吸われているせいで、全然力が入らない。吸われるたびに回復もしているが、その回復した分まで容赦なく持っていきやがる。
そうこうしているうちに、霧が晴れてきた。視界がどんどん開けていく。無様にも膝を地面につけながらも、顔だけはあげて御玲たちの所在を確認しようとするが。
「なん、だ……?」
そこにいたのは、百足。俺の背丈の軽く十倍以上はある、巨大な百足だった。
電信柱に細長い身体をくくって態勢を支え、キリキリと顎を打ち鳴らしながら俺を見下している。
太陽光に照らされて、闇を彷彿とさせる真っ黒な体表が際立たせる圧倒的存在感。
今まで狩ってきたハチや、蝉なんぞ比較するに値しない。自然界の圧倒的強者を思わせる風格が、反撃の意志を抉り取っていく。
体に巻きついている何かの力が僅かに変化する。停止していた思考能力がほんの少し舞い戻ったとき、尾の部分が俺の身体に巻きついていることを冷静に悟った。
俺としたことが、百足に威圧されて状況判断が大幅に遅れた。俺が今こうやって無事にいられているのは、この巨大百足に殺意が一切なかったからだ。逆に殺意があったなら、一瞬で絞殺されていただろう。
いつもの再生能力で死にはしなかっただろうが、百足如きに先手を取られたのが気に食わない。というかさっきの霧の発生源はコイツだ。俺の体に巻きついているコイツの身体を伝って、あの霧とおんなじ霊力を感じる。
舐めてくれたもんだ。気がついたら俺以外誰もいなくなっているし、百足に体巻きつけられているし、一体なんだってんだ。理解外で状況が変化しすぎだ。
ふざけてやがる、舐められてやがる。気にいらねぇ。今も霊力を吸われ続けているが、そんなもん関係ない。だったら物理で叩きのめす。
正直この百足の正体が気にはなるが、そんなことはコイツをブチのめしてから考えればいい話だ。
「しかしコイツ、ただの魔生物じゃねぇな。霊力も吸われてるし、手加減してたら押し負ける、か」
だったらこっちも切り札を使う。竜人化―――身体能力のリミッターの解除。それでサクッとケリをつける。
御玲たちの安否が気になるがコイツを叩きのめすのが先だ。このままじゃどっちにしろ動けないし、追いかけられて仲間を危険に晒すわけにもいかない。
「何の魔生物だか知らねぇが、今は討伐任務中なんでな!! 邪魔してくれた恨みも込めて、狩らせてもらぐはっ!?」
突然、背後からの強襲。首元をすっごい強い力でぶっ叩かれ、脳が揺れる。一瞬腹の中身が迫り上がってくる吐き気とともに、視界がぼやけ始めた。
まずい、これは気絶する。今までの母親との模擬戦と、修行の含蓄が、そう警鐘を鳴らしている。
俺としたことが、百足に注意がいきすぎて背後がガラ空きだった。声もなく気配もなく、脳を揺らされたのだ。
かなり的確だったから相手はかなり慣れてやがる。あのザコどもだろうか。いや、あのザコどもに、こんな芸当ができると思えない。だとしたらさっき霧の中から聞こえた突然聞こえた声の野郎か。ダメだ、視界が、ぼやけて―――。
「悪りぃな新人。後で話聞いてやるから、今は大人しく寝てろ」
視界はおろか、聴覚も遠退いていく中で聞こえた男の声。さっき霧の中でした男の声と同じものだ。
姿を拝みたかったが、その前に俺の意識は闇の底へと落ちていった。
「なんですか」
「こんなことを言うのは労働者としてダメかもしんない。でも聞いてくれ」
「はい」
「クッッッッッッソ忙しくね!?」
盛大な台パンとともに大都市を眺められるテラスで、自分の背丈よりも高い槍を隣に携える、メイド服を着た青髪の少女―――水守御玲に向かって高らかに叫んだ。
テーブルに乗っている食事や飲み物が衝撃で溢れそうになるが、そんなことは気にならない。
「そうっすよね、就職した瞬間にこの状況っすからね」
隣で大量の料理を注文すると同時、馬鹿デカいがま口へ吸い込むように一口で料理を食べていく二足歩行の暴食蛙―――カエル総隊長が、手についた油やら何やらをベロで舐め取り、また新しい皿に手をかけた。
「ったくよぉ……こんなに忙しいなんざ聞いてねぇぜ、糞する暇もねぇ」
「そうだよ、せめてオ◯ニーする時間くらいは欲しいよね。最低労働チン金としてさ」
「一応聞くけど、そのチンってどっちのチン?」
カエルの両隣で思い思いに喋りだす二体のぬいぐるみとロン毛の少年。
茶色のソースでベッタベタにしたハンバーグにかぶりつく子熊―――ナージは眉間に皺を寄せて俺を睨み、裸エプロンを着こなす小人のオッサン―――シャル、そしてどうでもいいことを問いただす空色のロン毛―――ミキティウスも口の周りをベッタベタにして、口の中に飯を頬張ったままこちらを見てきた。
汚いですね、と御玲がため息をつきながら、ハンカチでぬいぐるみどもの顔面を無造作に拭き取る。
俺たちがいま昼食を取っているこの場所―――任務請負機関北支部に就職したのは、つい三日前のこと。俺の人生を狂わせた怨敵にして実の親父―――流川佳霖への復讐を済ませた俺は、ひょんなことから任務請負機関で働くことになっちまった。
そのひょんなことってのがまためちゃくちゃな話で、流川家と互角の力を持つ戦闘民族―――花筏家との同盟と、俺たちがいるこの国、武市の隣にある大国―――巫市との国交樹立という、年齢十六歳の若者には絶対似合わない大仕事をやらなくちゃならないってことである。
そのためには任務請負人として実績を積んで支部から本部へ昇進し、その本部の重鎮に信用してもらうというクソ高い壁が聳え立っていて、まずはその壁を越えなきゃならない。
一難去ってまた一難。三ヶ月かかった復讐がやっと終わったのに、休む暇もなく就職して労働者である。勘弁してほしいものだ。
「それにしても忙しい……就職してからずっと、討伐任務ばっかりやってる」
さっき注文したハンバーグステーキを食らう俺は、就職してから今日までの忙殺っぷりを振り返る。
任務請負人は就職したその日から働けるのだが、俺たちが就職した頃は何故か支部内が慌ただしく、俺たちはわけも分からんまま、その慌ただしい波に呑まれて流されて、ずっと討伐任務をこなしてきた。
基本的に昼と夕方の帰宅時以外は休む暇がない。「時間に余裕がある限り討伐任務に受注せよ」と支部内のアナウンスがひっきりなしに鳴り響いており、俺たちはアナウンスに急かされるように、ずっと働き詰め状態なワケだ。
「仕方ないじゃないですか。あんな事件のとばっちりを受けてるんですから」
マカロニサラダを食べ終えた御玲は、口をナプキンで拭き取ってテーブルに置く。
御玲が言うあんな事件とは、六月二十三日、巫市で起こった大事件のことだ。
「妖精王襲撃事件だっけか……冗談みたいな事件だよな。なんだよ、妖精王って」
「それは分かりませんが、その妖精王とやらの霊圧により、この大陸の霊力分布が歪んでしまって魔生物のスタンピートが起こってしまった。放っておけば死傷者が出ますし、対処せよってことでしょうね」
「ったく、んなもんその妖精王? とかいうキチガイにやらせりゃいいじゃん。なんで無関係な俺らがやらなきゃならんのだか……」
「ここはプラスに考えましょう。実績を積み、昇進試験受験資格を得る好機だと。ただ漫然と任務をこなすより気持ちは軽くなるでしょう?」
「まあなぁ……当事者がスルーかましてるのは気に食わんが、そこは俺らがオトナの対応すればいいだけだもんな」
そうですそうです、と御玲が二回首を縦に降る。
任務請負機関には四つの支部と、それらを統括する本部がある。
まず請負人への就職は、必ず支部からすることとなり、本部に直接就職することはできない。本部へ異動するには、年に二度行われる``本部昇進試験``を通過する必要がある。
じゃあさっさと試験を受ければいいのでは、と思われるだろう。だがそう簡単に物事は進まない。本部に昇進するには試験に合格しなければならないように、その試験を受験するための、受験資格を獲得しなければならないのだ。
その資格は主に二つ。一つは任務をこなして実績を一定数稼ぐこと。もう一つは要求されている身体能力を十分に満たしていることである。
「受験資格の取得状況って、確か任務請負証を見れば分かるんだよな?」
御玲に問いかけながら、俺の視界に色んなオブジェクトが映り込む。
任務請負人は就職手続きをすると``任務請負証``っていう、いわゆる身分証明書みたいなものがもらえる。
それは別に書類ってわけじゃなく、カードになっているわけでもない。なんと驚き、体内に吸収させることによって発動する、一種のトリガー式魔法陣媒体になっているのだ。
体内に吸収されると脳内で再構築され、意志に反応して視界に色々な情報を映し出してくれる。
当然、全部非表示にすることもできる。というか基本的に必要なとき以外は非表示にしとかないと、視界に色々なものが映り込んで前が見えなくなってしまう。
操作は頭で思い浮かべるだけでできるので、基本的には食事がてら操作したり、拠点に帰ってまったり操作したり、そんな感じで使用するものである。
「まだ出勤三日目ですよ。身体能力はともかく、実績は全然足りませんよ」
自分の身体能力を参照してみる。
身体能力を表す項目は全部で七項目がある。まずは霊的ポテンシャル。
霊的ポテンシャルってのは、体内に溜め込んでおける霊力の許容量を表す数値で、数値が高ければ高いほど、より多くの霊力を体内に貯めこむことができる。
ちなみに``霊力``ってのは、簡単に言えば魔法や魔術を使うためのエネルギーみたいなものだ。戦闘の際は、この霊力ってエネルギーを元手に、魔法や魔術とかを使って討伐任務とか、敵と戦ったりするのである。
話を戻そう。霊的ポテンシャルの支部平均数値は、三十から四十の間らしいのだが。
「おかしいよなあ、俺の霊的ポテンシャル。二百五十プラスだぜ? 支部平均が低すぎるのか?」
俺の数値は、この時点でトチ狂っていた。その飛び抜けた数値に、思わず苦笑いが溢れてしまう。
支部の平均が三十から四十だっていうのに、俺の数値ときたら二百超というアホみたいな数になっているのだ。
元々霊力の消費とか昔から気にしたことなかったし、どれだけ使っても胸の奥底からボコボコ湧いて出てくるから、``霊力が尽きる``、なんてこともほとんどなかった。仮に尽きても、ほんの数秒経てばまたバンバン使える始末である。
ちなみにプラスってのは、自然回復とは別に霊力が何かしらの能力で継続回復しますよ、って意味らしい。
つまり俺は飛び抜けた霊力量に加え、自然回復とは別に霊力継続回復能力も持っているってことを意味する。
そりゃあどれだけ使っても減らないし、消費も気にならないわけだ。元からたくさんある上に、減ってもすぐ補充されるのだから。
「澄男さまは面白味のある身体能力値で良かったじゃないですか。私なんて全ての数値が百で統一されてるんですよ。つまらないったらありゃあしませんよ」
ため息をつき、水を飲む御玲。
霊的ポテンシャルのほかに物理攻撃力を表す``物理攻能度``、魔法攻撃力を表す``魔法攻能度``、物理防御力を表す``物理抗能度``、魔法防御力を表す``魔法抗能度``、敏捷能力を表す``敏捷能度``、回避行動に必要な条件反射能力を表す``回避能度``があり、それら七つ全部を合わせて、身体能力を簡単に数値化したものが``全能度``となる。
霊的ポテンシャルと同様、各項目三十から四十程度が平均なのだが、御玲は本人の言う通り全ての値が百。俺も当然百以上で、回避と敏捷に至っては百十を超えている。
つまり、御玲と俺は現時点でオーバースペック状態。その証拠に受験資格獲得に必要な身体能力は、全能度で表すと三百五十であるが、そのボーダーは任務請負証をもらった時点で、クリア済み扱いとなっていた。あとは純粋に、実績を積むだけなのだ。
「今回で実績満たせればいいんだが……」
「いやいや、無理でしょう」
天窓に映る空を見上げる俺に、御玲は鼻で笑う。
「そんなすぐに満たせてたら、ほとんどの人たち本部に行けてますよ。何度も言いますけど、私たちまだ出勤三日目ですからね? たったの」
「でも正直おんなじことの繰り返しだぜ……特に変化もないし、飽きてきたというか……」
「何言ってんですか。阿呆なこと言わないでください」
一蹴された。分かってはいたけど、本音を話すとまさに「飽きた」の一言に尽きるのだ。
さっき御玲は魔生物のスタンピートが起きていると言っていたが、そうは言っても一匹一匹は存外大したことはない。高くて全能度三百程度のザコがちょくちょく現れるようなもので、それらを倒すのは正直ただただ作業なのだ。
俺と御玲にかかれば、ワンパンで終わる連中である。これを退屈と言わずなんと言おうか。
「現状に不満があるなら黙って実績を積む。そして相応しいと思える場所に自ら行く。ただそれだけです」
「あーもうわーったよ、やりゃあいいんだろやりゃあ」
全身に気怠さが募り、今から任務に行こうというモチベが目減りする。
気がつくと全員が食べ終えていた。今の俺たちにとって昼飯を食べているときだけが昼休みだ。その休みが終わった以上、夕方までまた退屈な任務をこなさなきゃならない。
今までは自由気ままに動けていただけに、こうも同じことをさせられていると拘束されている感が身体を縛りつけてくる。
俺は最後の気休めに、いま受注している任務を確認する。
任務の受注は、基本的に任務請負証で行う。つまり頭の中で思い浮かべるだけで受注できてしまうわけだが、俺たちが就職した時期は``フレキシブル討伐任務週間``という謎のイベント期間の真っ只中だった。
この期間中は、任務の受注をする必要はない。既に全ての任務請負人が勝手に任務受注状態になっていて、暇な時はとにかく目についた魔生物を、期間が終わるまで狩り続けなければならないのだ。
別にサボっててもペナルティとかはないみたいだが、討伐数が一定数満たしていないと無報酬になってしまう。そしてその一定数というのは非公開で、受注している任務請負人からは分からないといった仕組みだ。
御玲は、その一定数だけ狩ってそれ以降仕事をしなくなる請負人が続出するのを防止するためだろうと言っていたが、やっぱり楽する道ってのは事前に潰されているものである。
「せめて北支部の最強格の連中と会えたら面白いんだがな……」
などと小声でぼそりと漏らしてみる。横で御玲が肩を竦めた。予想以上に聴覚が良くてビックリする。
俺たちが就職したのは任務請負機関北支部、正式には任務請負機関ヴェナンディグラム北支部だが、それとは別に南、東、西の三つの支部がある。
その各支部にはいわゆる四天王的な、最強格の実力を持った請負人が二人ないし一人ずついる。俺たちが就職した北支部には、``閃光のホーラン``ことレク・ホーラン、``百足使いのペグランタン``ことブルー・ペグランタンの二人が最強格として聳え立っていて、特にレク・ホーランとかいう奴は請負機関内外でも有名な存在らしく、北支部勤めの請負人でも最古参の存在だった。
御玲によると、レク・ホーランは新人研修するとき以外滅多なことでは支部におらず、個人的に会うには新人研修を狙うしかないらしい。それでもたくさんの新人を相手にするので、話す時間などないんだとか。
「ブルー・ペグランタンの方もいねぇし……話じゃ、支部のどこかしらで雑魚寝ぶっこいてるって話じゃなかったのかよ」
三日前に見せられた、黒光りする怪物の身体に包まれて昼寝している少女の写真を思い出す。
勤勉なレク・ホーランとは対極に、ブルー・ペグランタンは金が無くならない限り働かない、怠惰を絵に描いたような奴らしいのだが、そういう印象の人物は今のところ全く見かけていない。なんなら就職してから今日まで一度も見かけていないのだ。
俺が見た写真では、自分の背丈の倍以上はあるだろう怪物に身を包んですやすやと寝ている少女で映っていたが、その怪物も見当たらない。
写真から体のほとんどが見切れていたし、かなりデカい図体しているはずだから、そんなのが北支部の建物ン中にいたらすぐ分かるはずなのだが、ただただ有象無象の請負人が忙しなく建物ン中を歩き回ったり、テラスとか休憩所とかで仲良く駄弁っている様子が目まぐるしく見られるだけだ。
「縁があれば会えますよ。こっちから無理に干渉する理由もないですし、さっさと仕事しますよ」
これまたド正論。言い返す余地もなく、自分より背の高い槍を手に持つ。食べ終えたカエルたちも立ち上がると、鬱陶しくも俺の頭や肩に飛び乗る。
肩や頭の上で騒がれるとうるさいのでやめて欲しいのだが、このパリピぬいぐるみ軍団は騒ぐなと言うともっと騒ぐ厄介な天邪鬼連中なので、とりあえず放っておくことにしている。
ぬいぐるみを連れ歩きながら支部内を歩くのは、変に注目集めて恥ずかしい。なるべく目立ちたくないのに、これでは身分を隠している意味があるのかと思えてくる。
性懲りもなく無駄に注目を浴びながら、俺たちは支部を出た。今日も今日とて、終わりの見えない討伐任務、その後半戦が始まる。
季節は夏。もうまもなく七月になる武市は、気温が既に三十度を超えている。支部内はクーラーが効いているので涼しいが、カンカン照りの太陽光が肌を焼き、舗装された道路から熱気が沸き立つ。
ここで風が吹けば少しは涼しく感じるものなんだが、周囲には風の行手を阻むように、無数の密接した集合住宅が立ち並んでいた。
いま俺たちが歩いている地区―――中威区北部郊外集合住宅地帯は、とにかくどこもかしこも密な集合住宅しかない。
区の中央に行けば三ヶ月前まで通っていた俺の高校があり、その近くには商店街がある。いま俺たちがいる北支部周辺は中威区でも北方にあり、中央商店街からは気が遠くなるくらい距離が離れていた。行こうと思うと空を飛んでも二日はかかってしまうだろう。
今のところ行く気はないので、どうでもいいが。
そんでもう一つ、こんなにたくさんの古臭い家がクソみたく立ち並んでいるにも関わらず、人がそんなにいないって状況である。
外に出歩いている奴もまばらで、舗装された道路はゴミだらけ。中には窓からゴミを投げ捨てている奴もいる始末で、正直初めて見たときは目を疑ったものだ。慣れてしまうとあら不思議、どうでもよくなってしまうのだが。
「ゴミ拾いしたくなってきますね、いつ見ても酷い惨状です……」
全員慣れたかと思っていたが、まだ慣れてない奴がいた。よくよく考えれば、女にはキツい環境である。
確かにどっかの誰かが生ゴミを投げ捨てているせいで、カラスがゴミ袋を破ってそれをほじくりかえしているし、中身も腐っているから、くさいのなんの。
気持ちは分からんでもない。でも正直拾ったところでまた捨てる奴がいる以上、捨てる奴をブチのめすとかでもしない限り意味がない。この手の奴は口で言ってもどうせ「バレなきゃいい」の精神だし、こっちがただの徒労を背負わされるだけだ。第一、ゴミ拾いしたところで金にならんし。
「いいじゃないすか、生ゴミっすよ生ゴミ。食えるだけまだマシっすよ」
頭から飛び降り、カラスみたく生ゴミを漁って中身を食べようとするカエル。俺はそれを見逃さない。
「食ってもいいが、帰るまでお前、歩きだぞ」
「えー! そりゃないっすよ!」
「そりゃあねぇのはこっちだ、そんな汚ねぇもん食った手で俺の頭に触れるつもりか!」
「いいじゃないすかー、どうせ帰ってシャワー浴びれば綺麗になるし」
「流石の俺でも腐った生ゴミに触るほどの度胸ねぇから。精々匂いに耐えられるレベルだから。だから触るんなら歩け、嫌ならゴミ食うな。いいな?」
へいへーい、と不満そうにがま口を尖らせる。全く少し目を離すとこれだ。
昨日もコイツそこらに落ちている腐った生魚の内臓食っていやがった。流石の俺も、その場面見たときはリアルに悲鳴あげたほどだ。どういう神経していたら羽虫が集っている魚の内臓を鷲掴んで食えるのか。やっぱ蛙だからなのか。
「で、テメェは何しようとしてる?」
「あ? 見てわかんねぇか? ウンコだよウンコ。昼飯食ったから催してんだよ邪魔すんな」
「邪魔するわ!! こんな道路のど真ん中で催すんじゃねぇ!! あともう少ししたら公衆便所あっから、そこでしろそこで!!」
「チッ……別にいいじゃんかよ。そこらゴミだらけだし、今更野糞の一つや二つ増えても大して変わんねぇよ」
そういう問題じゃない。やったらやったで窓からゴミ投げ捨てたり、そこらにゴミ捨てている野郎と同等になっちまうだろう。
いや、ゴミが目の前にあるのに拾う気がない俺らだって同じかもしれんけど、自らゴミ量産してないって点でまだマシなんだから、そのマシな部分保とうぜ。
というか任務請負人が街汚しちゃダメな気がするし、野糞なんてもってのほかだ。ただでさえここらへん生ゴミ臭がやばいのにさ。
般若のような表情でゴミ袋に唾を吐くナージは、白い翼を無造作に羽ばたかせ、腕を頭に回してだらけながら飛行する。
「見て澄男さん!!」
「なんだ? ロクなもん持ってこなかったら直でシバくぞ」
「オ◯ホ見つけた!! これ澄男さんのサイズにぴったりじゃない? 結構デカいよこれ!! 洗えばまだ使える!!」
「元あったゴミ袋に返してきなさい!!」
満面の笑みを描き、よちよち歩きで身の丈に合わないソレを持ってくるシャル。
裸エプロンを着こなす二頭身のオッサンの顔は、公園で面白いものを発見し、それを親に無邪気に報告してくる純粋無垢な子供のようだが、コイツの手に持っているもののせいで、純粋無垢の欠片も感じられない。シャルの存在も相まって、穢れの権化と化してやがる。
「お前らいい加減にしろ!! ゴミを漁るな食うな催すな!! ミキティウスを見習え!! アイツなんか静かに俺たちの後ろを」
「あの、澄男さま……」
「どした」
「その、ミキティウスが……」
「スー……ハー……スー……ハー……」
御玲が見るからに不快な顔で肩を叩いてくるので、指を刺された方に視線を向ける。
「……なに、やってんだお前」
どっかの某実写宇宙戦争物の映画に出てくる真っ黒な仮面とマントを着た、ラスボスみたいな鼻息を出す空色のロン毛が、そこにいた。俺は思わず顔を歪める。
「このパンツ気に入りまして。程よく臭く、程よく黄ばんでいる。今の俺の気分にぴったりだ……」
いや、すっごい汚いんだけど。黄ばんでるってそれ、何処の馬の骨とも知らん奴の排泄物だよねそれ。
つーか今の俺の気分にピッタリとか言われても、他人の排泄物がガッツリついたボロ雑巾みてぇな下着で表される気分ってどんな気分なんだよ。絶対ロクな気分じねぇじゃん。
「うわぁ、ないわぁ……流石キモパンティウス」
「糞パンティウスと言われるだけあるな。ホント神経疑うぜオメェ」
なんか知らんけど蛙と子熊がドン引きしてる。俺らマトモな神経してるぜみたいに言ってるけど、お前らも同類だからな。前々から思ってたけど、お前らのそのドン引くドン引かないの線引きどうなってんだよ。
「とりあえずミキティウス。汚ねぇからそのパンツは元あったゴミ袋に返してこい。あと今後、ゴミ袋を勝手に漁るな。汚いから。マジで汚いから」
「なんてことを!! 汚くなんかありません!!」
「汚ねぇよアホか!!」
すっごい真剣な眼差しで逆ギレされ、俺も思わず声を荒げる。
その下着を美しいってガチで言ってるなら、お前の美的センスを二度と信用しないぞ。というかマジでゴミ漁りやめてくれ。なんでそんな当たり前のことができないんだ。人間じゃないからか。
しばらく言い争いになったが、ミキティウスは根負けし、パンツを捨てに行った。むしろ間違ったこと言ってないはずなのに、なんで言い争いになるのだろうか。ちょっと意味がわからない。
「そんで澄男さん、今日もアレっすか? 虫取りっすか?」
もう無関係と言わんばかりに話題を変えてくるカエル。その態度に些か不満が横たわるが、俺はオトナの対応で受け流し、やっと今日の本題に入る。
現状スタンピートを起こしている魔生物は、実を言うと主に虫。
アペスっていうハチ型の魔生物を筆頭に、色々な虫型の魔生物が街中で大量発生し暴れ回っているのだ。俺も昨日まで、手当たり次第にハチと格闘戦を繰り広げ、難なくそれらを討伐してきている。今となっては、ハチ駆除のプロを自称してもいい気がするくらい、自信がついてしまった。
「アペスは本来、この時期はヘルリオン山脈を生息圏にしているはずなのですが、夏に北上してくるのはおかしな話なんですよね。冬はわかるんですけど」
御玲が虚空を見つめ、でも何かを追いながら呟く。おそらく任務請負証に映っているオブジェクトを参照しているんだろう。
アペスはハチ型の魔生物だが、最大の特徴はとかくデカいことだ。
大人一人分の背丈を持ち、人間に対して敵対的で、基本的に二十匹ないし十匹の群れで行動し、人間を見つけると外敵と判断して向こうから問答無用で襲いかかってくる。
一匹一匹の全能度は百二十一と大したことはないが、いかんせん群れで一斉に襲いかかってくるので、かなりめんどくさい。ケツについてる針には魔法毒とかいうクソ厄介なのが付いているし、それを一斉に飛ばしてくるとなると、捌くのが中々かったるいのである。
向こうから領域侵犯しておいて、元々ここを生息圏として生活している俺らを攻撃するなんざ理不尽極まりない話だが、相手は魔生物だ。思考もしないし意志も持たない、ただ生存本能が備わっているだけの生き物。そんな奴らに人間の理屈が通じるはずもない。
そんなわけで、今日も今日とてアペス狩り。全能度百程度とはいえ軍団で襲いかかられると辺りに住んでいる一般人からしたら割と脅威らしいし、巣でも作られた日には厄日と化すらしいので、そうなる前に駆除するわけだ。
「あー……あと何匹ハチ退治しなきゃなんねぇんだかなぁ……」
「クソ、こんなの聞いてねぇよ!! 俺こんなとこで死にたくねぇ!!」
今日ブチ殺すハチの数を予想してた矢先、俺らがいる場所から数十メトくらいか、それぐらいの距離離れた所から、男の悲鳴が聞こえた。
御玲が目配せしてくる。そのサインに黙って頷き、足元でどんちゃん騒ぎしてたぬいぐるみどもにも声をかけると、声をした方向へと走る。
住宅と住宅の間の路地から、二人連れの男が、飛び出してきた。二人とも、俺や御玲よりも結構年上。三十歳くらいだろうか。
最初はそこらの一般人かと思ったが、着てる服から見え隠れする鉄製の装甲みたいなものと、腰に光る短剣のようなものを装備してるところを見るに、アイツらも任務請負人。だが何かに怯えて逃げてきた様子で、全く戦う素振りを見せない。
腰に携えている光る短剣すら抜かず、ただ腰を抜かし、お互い身を震わせてヒィヒィ間抜けな悲鳴をあげているだけだ。
まさかだけどアペス如きにビビってるとかそんなんじゃないだろうな。だとしたらザコもいいトコなんだが、流石にそれはないだろう。曲がりなりにも俺らより年上だし、並みの実力はあるはずだ。
「お、おい!! 置いてくなよ、大体アレどうすんだアレ!!」
「し、知るか!! 俺は知らねぇ!! 命あっての物種だ!! ここらの住民には悪いがな!!」
並の実力はあるはず。そう言ったが前言撤回したくなってきた。男のうち一人は仲間と思わしき連れすら犠牲にして逃げようとしているが、その連れが逃亡を許さない。見捨てられるならせめて道連れに。そんな気迫すら感じさせる。
お互い敵を目前にして醜く足の引っ張り合いしてやがるのだ。こんなザコどもが、並の実力すら持ってないのは考えるまでもねぇ。
「チッ……邪魔だな」
思わず本音が漏れる。あの手の奴らは弱い癖に隙あらばキャンキャン吠える以外に能がないから嫌いだ。
弱いならとっとと消えろって話だし、なんならここで焼き尽くしたいぐらいだが、ここで波風立てて今後の活動に支障をきたすとまずい。なにより御玲に怒られるのは避けたいのだ。
「行くか?」
とりあえず御玲にも聞いてみる。正直このまま行ったら確実になすりつけられるが、むしろそっちの方が、都合がいい。
変に手伝うとか言われて邪魔になるよりも、さっさとなすりつけてどこぞへと消えてくれれば、俺らが手柄を総取りできる。
「ですね……とりあえず、あの二人の全能度の確認をと」
任務請負証の機能を既に使いこなし始めている御玲。今から突っ込もうという俺をよそに、冷静に状況を把握する。
「逃げようとしている方は二百五、腰が抜けて動けない方は百八十程ですか。澄男さま、杞憂に終わると思いますが、念のため全員でいきましょう」
おう、と承諾の意を示す。二百五、百八十なら、あのハチどもに十分対抗できるはず。つまり、アイツらが今出くわした存在は、アペスより遥かに強い何か。
流石に御玲の全能度である七百を超える奴がいると思えないが、一応、皆で話し合った手筈では、敵の全能度が御玲を超える可能性がある場合、過剰戦力になるとしても初めは全員で相手をすることになっている。
戦力を小出しにすると、万が一対応ができず死ぬ可能性があるからだ。厄介なのが俺に来れば問題ないのだが、俺以外、特に御玲一人に出くわすとマズイ。御玲は人間相手なら負けることはないけど、相手がバケモンとかだと話は変わってくる。
「よし、行くぞ!」
話はまとまった、カエルたちに突入の合図をする。
物陰から見ていた俺らは逃げようとして足がすくんで動けないノロマたちに割って入る形で、ソイツらが相対していた奴のツラをついに拝んだ。
「これは……」
「あー……なるほど。コイツか」
それは空いた口が塞がらなくなるほどの、まさに異形の塊だった。御玲と俺を交互に見やる鈍亀をよそに、その異形の正体をすぐに悟る。
確かにこの国、この街で育った奴には馴染みがないかもしれない。というかコイツも人里に降りてくるタイプだったのかと、いま初めて知ったぐらいだ。
「そうだよな、今はもう夏だ。まさかこんなところで``夏の風物詩``と出会えるなんてな」
足や手首をブラブラさせて軽く準備運動。明らかにアペスなんかよりも強いソイツと戦えるのだから、準備運動程度の力は出せそうだ。どちらにせよワンパンなのは変わりないが、ここで変化球が来てくれるのは嬉しい。
「インサニス・シカディスですか……いつ見ても気持ち悪い外見です」
気怠そうに槍を近くに置く御玲。一応体を軽く解しているが、戦う気はない。
そりゃそうだ。この中で誰か一人でも戦えば、確実にブチのめせるんだから。
インサニス・シカディス、通称``夏の風物詩``。毎年六月から九月にかけて、南の山奥から血肉を求めてやってくる``蝉``だ。
体長は二メト以上。赤黒い羽根と、脳味噌を彷彿とさせるブヨブヨの体、赤い複眼と身体中から生えている無数の触手が特徴的な虫型魔生物の一種である。
俺がまだ本家領にいた頃も、夏になるとコイツがぶんぶんぶんぶん飛んできては、庭で修行していた俺を食おうと襲いかかってきていた。
幼少の時点で一方的に八つ裂きにできていたから、俺からすればただの雑魚でしかないが、確かに全能度二百程度の奴じゃビビるのも納得だ。なにせコイツの全能度、今測ったら五百くらいあるんだから。
「どうする、お前いっとくか?」
「いえ、澄男さまに譲ります。私はアペス狩りで結構ですので」
「んじゃ遠慮なく! おいお前ら、手ぇ出すなよ。コイツは俺が片付ける」
「ウェェェェイ!! やっちゃってください澄男さぁん!!」
「負けたら食糞だぞ食糞!!」
「いや、まずはボクのち◯こを舐めろ!! それから御玲さんの糞だ!!」
「パンツが高まる……!! 溢れる!!」
背後から聞こえる意味不明な声援。いつもならものすごくうるさいが、久しぶりの日常の変化のせいか、コイツらのイタい台詞も心地よく感じてくる。
問題はない。相手が蝉なら、負ける気がしない。
「コイツには炎は効きにくいんだが……俺には関係ない。血肉一欠片も残さず焼き尽くす!!」
右手に宿るは、赤白い火球。頭の中で火をイメージし、それをアホみたいな霊力で出力して具現化。さらにそれを握り潰すイメージで圧縮して初めて完成する特製の火球―――その名も``煉旺焔星``。
生まれたての星の如く輝くそれは、命中したが最後、相手を問答無用で灰燼に帰してしまう。
いや、その灰すらも燃え尽きて残らないだろう。実際、俺の右掌にある状態でも、周囲のものを熱気で歪めているほどなのだ。
カエルたちはあらかじめ距離を取り、熱気の影響からはそそくさと退避している。一方、路地を通せんぼする蝉はというとなんとも驚き、まったく動じていやがらない。
さっきも言ったが、コイツは火があんまり効かないので耐熱性能もやや高め。幼少の頃に殺し合った時も、火の球近づけた程度じゃビビってさえいなかった。
でも流石に火の球そのものの熱さは感じ取っているようで、さっきよりも触手の動きが格段に鈍くなっている。触れれば灰も残らないことを、本能で悟ったのだ。
とはいえ、悟ったからではもう遅い。
コイツは蝉なだけに空を飛ぶし、図体デカい割には触手が器用で、そこそこ速く地上も移動できる。
曲がりなりにも虫だから無理もない話だが、俺からすればノロマだ。コイツが動くよりも速く、コイツを跡形もなく消し去れる自信がある。
蝉からの殺気は消えない。火の球を持った俺と相対してなお、弱っちい霊圧で、尚も威嚇してくる。
俺への恐怖よりも、血肉への食欲の方が勝ったらしい。だが別に構わない。かかってくるなら、容赦しない。ただそれだけだ。
「消えてなくなれ!!」
右掌にのせていた火球が一瞬光り輝く。周囲の建築物が破壊されない程度に手加減したそれは、蝉の腹ン中で光ったと思いきや、蝉の身体が一気に十倍くらいに膨れ上がった。
火は基本、水に弱いが、超高熱の炎はその弱点を無効化する。水は高々百度でただの空気になっちまうが、火は霊力を込めれば込めるほど熱くできる。それも一つの星ぐらいの温度にすることも可能だ。
蝉の野郎の身体は実を言うとほとんどが水でできている。だからこそ打撃はあんまり効きづらいんだが、だったら肉体を内側から蒸発させてしまえばいい。
体のほとんどが水分でできているってんなら水蒸気に変えてしまえば火への耐性など関係ない。一瞬で破裂してチェックメイトである。
結果は俺の予想は裏切らなかった。蝉の体が一瞬火照った海老みたいになった瞬間、風船がブチ破れるようにその中身を炸裂させたのだ。
そこらの生ゴミとは比較にならない、生き物が焼ける生々しい悪臭が漂う。蝉の内臓だったらそれは真っ白に蒸されており、もくもくと水蒸気が舞ってやがる。俺はというと、もう言わずもがな、だ。
「うえぇ、ぺっ、ぺっぺっ」
「澄男さん……臭いっす」
「きったねぇなおい」
「わーってるわ!! クソ、こうなるのすっかり計算に入れ忘れてたぜ……」
「むしろなんで忘れるんすか、普通予想つくでしょ、そうなるの」
蒸した内臓塗れになった俺は、とりあえず顔にべっとりついた何かを手ではたき落とす。服からズボンに至るまで、なにもかもが真っ白に蒸された何かでぐっちょぐちょだ。こんなんで支部には帰れない。一度家に帰ってシャワー浴びないと。
「シャワーはダメですよ。浴びる前に庭で洗い流してください。下水詰まるんで」
目から光を消し、淡々と辛辣なことを吐く御玲さん。
そんなこと言われても、庭で洗い流すような場所なんかない。ウチの弟がどっかに庭に水撒く用のシャワー的なものを設置していたかもしれんけど、俺は花壇に水やったりしないからそんなんどこにあるか知らんし。にしても、これ。
「生ぐせぇ!!」
とりあえず顔についたものは取れた。服についたやつはどうにもならんので、もう諦めることにする。
幸いただのTシャツなので捨てればいいが、無一文の今、新しい服を買う余裕がない。一応、Tシャツの予備はまだあるけど、それも無限ではないのだ。ズボンなんてあと何着あるか。
「そんなことよりどうするんすか、誰かが住んでる家にべっとりついてますよこれ」
カエルが右と左を交互に指さす。
俺が蝉と戦っていたのは集合住宅同士を挟んだ路地。かなり狭く、俺と蝉がいるだけで二人目は同時に通れないほどの幅しかない。そんな狭い路地で虫の内臓を炸裂させただけに、左と右の集合住宅にはべっちゃりと白い残骸がついてしまっていた。
「……焼く?」
「澄男さまがやると住宅まで燃えてしまいますよ」
「じゃあ水かけて落とす」
「この場で水出せる奴いないっすよ」
「じゃあお前がこの白いのを全部食うってのは?」
「あー……まあいけなくはないっすけど、インサニスの内臓って蒸しても臭み消えないんすよねー、見た目蒸したエビの中身みたいな感じっすけど」
冗談で言ったのに、真剣に食うかどうかを吟味してやがる。べっとりついた内臓の残骸を真剣に眺めている二足歩行のカエルのぬいぐるみの図は見ていてシュールだが、コイツはかつて、蛆虫が大量に湧いている腐った生魚の内臓を素手で掴んで丸呑みしたことがあるほどの雑食家。インサニスの蒸した内臓の残骸など、そんなのと比べればまだマシな方なのかもしれない。
苦いもの以外は特に好き嫌いがない俺でも、雑食すぎてドン引きだ。
「まあ食えるなら食ってくれ。そこらに一杯あるし。でも持ち帰りはナシな。そんなもん家に持ち帰えられても困るから」
「タッパーに入れて冷蔵庫に入れときゃ、そこそこ保存効くっすよ?」
「ダメだ!! ウチの冷蔵庫は人間が美味しく食べられるものしか入れません!!」
ちぇー、と白いそれを手で摘み、手ごと派手に頬張る。
今日食べたハンバーグステーキが迫り上がってきた。とりあえず夏の風物詩は倒したし、カエルはほっといて次の狩場に―――。
「お、おいガキども」
聞き慣れない声が鼓膜を揺らす。振り向くと、光る短剣を御玲の首元に突き立てる男二人組がいた。
ついさっきまで、蝉にビビって腰抜かしてヒィヒィ言っていた連中だ。
「テメーらこの前入ったヒヨッコだろ? 知ってんぜ、来た時からメイド侍らせてっからどこのぼっちゃんだよと馬鹿にしてたが、まさか``夏の風物詩``をワンパンとはな」
俺は盛大にため息を吐きつつ、めんどくささを全面に出した舌打ちをブチかます。苛立ちが腹の奥底から募り、冷めたばかりの右手がまた熱くなるのを感じた。
「とはいえ……悪いがその獲物は俺らの獲物でよぉ? つーわけで実績置いて消えなクソガキ」
「オラァ実績出せやオラァ請負証出せやだせつってんだろボコすぞ、ぼこしちゃいますよー? ボンボンボンボンボーン!!」
うるせぇ。まるで駄犬。
高校時代からそうだったが、この手のザコはたとえどこに行っても付き纏ってくる。さっきまでビビって腰抜かしていたくせに、どうやったらここまでイキれるんだろうか。そのまま恐れ慄いてどっかに消えてくれれば少しは可愛げもあったってのに、まさかこっちが新人なのを棚に上げて経歴マウント取ってくるとは思わなかった。それも実績を譲れとかいう謎の脅迫までしてきやがる始末。
ああ、不快だ。実に不愉快。
力もないただ弱いだけの雑魚のくせに脅威が去るとこれだ。昔の俺なら問答無用で塵芥にしてやったところだが、まだ俺らは出勤三日目。こんなところで、それもこんなつまんねぇ奴に波風立てるなんざアホらしいことこの上ない。
幸い、俺の目の前でボコすボコす言ってぴょんぴょん飛び跳ねてるわけわからんアホは全能度百八十、御玲の首元に光る短剣を突き立てて脅してるつもりになってるバカは全能度二百五。どっちも取るに足らねぇクソザコだ。
俺が出張らなくても御玲が冷静に対処してくれるだろう。ぬいぐるみたちが揃って手を出さないのも、御玲の実力なら余裕で対処できると判断しているからだ。ここで俺がしゃしゃり出る必要はない。幸い全能度百八十のアホは俺にかかりっきりだし、コイツの気を引きつつ御玲が対処するのを待つか。
「なにお前、実績の譲り方も知らないんですかぁ? まあ仕方ないよね、ぼっちゃんだもんね、新人だしこの俺が教えてやっからさ、さっさと請負証出せや、出せってんだよオラァ!! 出せや!! シカトかましてなよゴラァ!!」
「おいおいあんまりビビらせてやるなよ、まだ勤め始めたばっかの新人だぞ? トラウマになっちまったらもうこれなくなっちまうだろうがよ」
「だってさー、コイツ請負証ださねーんだもん、シカトしてやがるしさー、ムカつくっつーかなんつーか、もうボコしてもいいんじゃね? ここ人いねーし?」
「まあ待て、ただビビらせるだけじゃつまんねー。見てみろよお前、これ」
左手で短剣を突き立てたまま、男は恍惚で嗜虐的な笑みを浮かべ、その右手が動かした。
「ごぶっ!?」
男が右手を動かした瞬間、男の顔面が紅い火球に包まれる。
ぐああああああああ、と悲鳴をあげて地面を転げ回る男はもう御玲など眼中にない。顔面についた炎を消すため、懸命に顔を地面に擦り付けている。
一体何が起こったのか。んなもん簡単だ。アイツの右手が御玲のロングスカートに触れた、だから即興で作ったミニ火球を奴の顔面にデコピンでぶつけてやった。ただそれだけだ。
「て、テメーなにしやごはっ!?」
もうこのアホの妄言は聞く必要はない。手っ取り早く黙らせるために土手っ腹に蹴りを入れる。一応手加減してやったが、それでも十分すぎる威力だろう。アホは悲鳴すらあげる余裕すらなく、腹を押さえながら気絶した。
この間、僅か五秒。イライラの五割を消費し、やや胸が晴れた俺とは裏腹に、御玲は不満げにため息を吐きながら、こっちを睨んでくる。
確かに最初は御玲に対処させるつもりで、俺は囮に徹するつもりだった。でもあのバカの右手の動きを見たんじゃあ、悪いけど黙っていられない。
アイツの表情は``劣情``に塗れていた。女をただの道具としか見てねぇ下衆の情。
それを俺らに関係ない女に向けるってんなら好きにすりゃあいい。でも俺の仲間である御玲に向けるってんなら話は別。
悪いが俺はその手の劣情を仲間に向けられるのを良しとしない。かつてその劣情で、友を一人失ってしまったから―――。
「澄男さま、それ以上はダメです!」
「悪いな御玲。コイツらは俺の禁忌に触れた。ここで始末する」
俺の心は酷く冷静だ。怒っているはずなのに、いつもの烈火の如き怒りとは別の、ドス黒い感情が支配している。
御玲の声が遠く聞こえる。今の俺の頭の中はこの二人のクズを跡形もなく消し去る。ただそれだけしかない。
あのまま蝉にビビって消えてくれていたら何もしなかった。そうでなくとも俺らを脅す程度なら御玲に黙らせる程度で済ませてやった。でもコイツらはあろうことか、御玲に劣情を向けたのだ。
なら始末する。三ヶ月前の``悲劇``を繰り返すわけにはいかない。そうなるくらいなら、いっそ―――。
「澄男さま!!」
地面にうずくまり気絶するアホに向けて火の球を錬成する。
蝉を一瞬で破裂させた火球、煉旺焔星。これを目の前のアホと転げ回ってヒィヒィ言っているバカに使えば塵も残らない。流石にここらの家を壊すわけにもいかないから最小威力にするが、それでもコイツらを消し去るには十分足りるだろう。
多分コイツら殺ったら御玲は怒るだろう。もしかしたら恨まれちまうかもしれない。
でも俺は仲間を絶対に守らなきゃならないんだ。たとえ雑魚一人だろうと、その汚ねぇ手で仲間に触れる、それすら許すわけにはいかねぇ。これは誰がなんと言おうと譲れない、俺の絶対ルールなんだ。
前にみたいに手当たり次第殺し尽くす気はない。でも仲間を守るためなら``敵``と思わしき奴に容赦しねぇ。俺の仲間に汚い手で触れる全ての存在は、悪いがこの世から消えてもらう―――。
「粉々に……!?」
なりやがれ、と言おうとした、その瞬間だった。突然、濃い暗黒の霧が、一瞬で俺らを包み込んだ。
次から次へと面倒ごとばかりおこりやがる。わけがわからず辺りを見渡すが、気がつくと俺に絡んでいたアホと御玲を脅していたバカが見当たらず、御玲たちの姿も見当たらない。俺以外の存在が全て消えた。
一寸先が全く見通せない濃霧。肌から感じる感覚からして霊力のようだが、請負証の機能をもってして霧の正体が掴めない。ただの霊力で作られた濃い霧だ。
何なのか分からない。その事実が、背筋を冷たく凍らせる。
御玲がいない。カエルたちの気配が辿れない。仲間がいない。それがなによりも怖い。謎の霧で雑魚を始末し損ねたことも存外に苛立つが、それ以上に仲間をまんまと撹乱させられたのがとにかく気に食わない。
こんなことになるなら雑魚なんぞ捨ておくべきだったかもしれんが、なによりこの霧、全く予兆がなかった。霊力だってんなら、使われるときに気配の一つや二つ辿れてもおかしくないはず。霊力で作られた霧なのに霊力が感じないなんてことあるのか。
とりあえず冷静になれ。さっきまでの雑魚を葬り去ろうとしていたときの冷静さを取り戻せ。
おそらく新手の魔生物による撹乱攻撃。味方との連携はとれない。味方の場所は分からず、居場所を霊力で探ることもできない。俺は探知には向いてないから、基本的に察知は五感頼りになる。幸い五感は鋭い方だが、それでも探知が得意な奴には格段に精度で劣ってしまう。
ここにきて五感すら撹乱してくる魔生物の出現。厄介だ。厄介すぎる。せめてぬいぐるみどもさえいたらいくらか対処のしようがあったが、今は俺しかいない。
本当はやりたくなかったし、やるべきではないのだろうが。
「ここら一帯を霊圧でぶっ飛ばすしかないか」
霧は霊力でできている。ならこっちも霊力を放出して吹き飛ばす。
問題はこの霧を吹っ飛ばすのに必要な霊力量が分からんことだ。その場合、ありったけの霊力量を放出することになるし、そうなると最悪ここら一帯が死の大地と化す可能性がある。
俺の霊力量は膨大だ。基本的に常に体内は百を軽く超える出鱈目な霊力で満たされているから、全力で霊力を全方位に、それも対象を指定せず放てば、ウチの家の庭みたいな特殊な場所でもない限り、被害は甚大なものになる。
どれくらいの家屋が跡形もなくなるか、この俺でも想像がつかない。
仲間と連絡をとってみるか。いや、でもちんたらやってて仲間に何かあったら俺は正気でいられる自信がない。
弟に助けを呼ぶか。それも遅い気がする。説明している間にやられたら終わりだ。やばい、こんなこと考えている間にも御玲たちは―――。
「ふざけやがって……!!」
どこの誰だかしらねぇが、邪魔した挙句仲間の行方を撹乱させた罪は重い。
御玲とぬいぐるみたちなら、魔法防御力から考えて俺の霊圧には耐えられるだろう。御玲たち以外は分からんが、今は仲間が優先だ。
とりあえずこの鬱陶しい霧を吹っ飛ばして仲間の無事を確認し、霧を出した間抜けをブチのめす。そんで最後は禁忌に触れたあのザコどもを始末する。
方針は決まった。あとは実行するだけだ。
煉旺焔星を体の中に再吸収し、体の奥底に溜まっている大量の霊力を練り上げる。体の中に溜まっている霊力を一旦胸の部分にまで迫り上げさせて、そこで餅を練るイメージで練り込み、あとは一気に身体の外へ放出するだけ。それでチェックメイトだ。
俺を中心に、まるで地中に巨大なモグラが暴れ回っているような地響きが轟く。体内の霊力が足の裏を伝って地形に干渉でもしているのだろう。心なしか大気も震えているように感じる。
胸の中央部が熱い。もう少しで炸裂する。一切合切手加減なしの、練りに練り込んだ霊力が―――。
「今だ、むーさん!」
胸の内側で練り込んで炸裂寸前だった霊力が、今にも爆発するというその瞬間。
霧の中のどこかから聞き覚えのない男の声がした。誰だ、と振り向こうとするも、間もなく何かがぐるぐると俺の身体に巻きついていく。
「な、なんだ……!? さっきまで練りに練ってた霊力が……どんどん吸われて……!?」
わけがわからず振り解こうとするが、突然の出来事に思わず膝を折ってしまう。
意志に反し、体の奥底から何かが抜け落ちていく感覚。正しくは体の中身が吸われて、血の気が引いていく感じだ。血を吸われているわけじゃないが、体の中の霊力を強制的に吸われているせいで、全然力が入らない。吸われるたびに回復もしているが、その回復した分まで容赦なく持っていきやがる。
そうこうしているうちに、霧が晴れてきた。視界がどんどん開けていく。無様にも膝を地面につけながらも、顔だけはあげて御玲たちの所在を確認しようとするが。
「なん、だ……?」
そこにいたのは、百足。俺の背丈の軽く十倍以上はある、巨大な百足だった。
電信柱に細長い身体をくくって態勢を支え、キリキリと顎を打ち鳴らしながら俺を見下している。
太陽光に照らされて、闇を彷彿とさせる真っ黒な体表が際立たせる圧倒的存在感。
今まで狩ってきたハチや、蝉なんぞ比較するに値しない。自然界の圧倒的強者を思わせる風格が、反撃の意志を抉り取っていく。
体に巻きついている何かの力が僅かに変化する。停止していた思考能力がほんの少し舞い戻ったとき、尾の部分が俺の身体に巻きついていることを冷静に悟った。
俺としたことが、百足に威圧されて状況判断が大幅に遅れた。俺が今こうやって無事にいられているのは、この巨大百足に殺意が一切なかったからだ。逆に殺意があったなら、一瞬で絞殺されていただろう。
いつもの再生能力で死にはしなかっただろうが、百足如きに先手を取られたのが気に食わない。というかさっきの霧の発生源はコイツだ。俺の体に巻きついているコイツの身体を伝って、あの霧とおんなじ霊力を感じる。
舐めてくれたもんだ。気がついたら俺以外誰もいなくなっているし、百足に体巻きつけられているし、一体なんだってんだ。理解外で状況が変化しすぎだ。
ふざけてやがる、舐められてやがる。気にいらねぇ。今も霊力を吸われ続けているが、そんなもん関係ない。だったら物理で叩きのめす。
正直この百足の正体が気にはなるが、そんなことはコイツをブチのめしてから考えればいい話だ。
「しかしコイツ、ただの魔生物じゃねぇな。霊力も吸われてるし、手加減してたら押し負ける、か」
だったらこっちも切り札を使う。竜人化―――身体能力のリミッターの解除。それでサクッとケリをつける。
御玲たちの安否が気になるがコイツを叩きのめすのが先だ。このままじゃどっちにしろ動けないし、追いかけられて仲間を危険に晒すわけにもいかない。
「何の魔生物だか知らねぇが、今は討伐任務中なんでな!! 邪魔してくれた恨みも込めて、狩らせてもらぐはっ!?」
突然、背後からの強襲。首元をすっごい強い力でぶっ叩かれ、脳が揺れる。一瞬腹の中身が迫り上がってくる吐き気とともに、視界がぼやけ始めた。
まずい、これは気絶する。今までの母親との模擬戦と、修行の含蓄が、そう警鐘を鳴らしている。
俺としたことが、百足に注意がいきすぎて背後がガラ空きだった。声もなく気配もなく、脳を揺らされたのだ。
かなり的確だったから相手はかなり慣れてやがる。あのザコどもだろうか。いや、あのザコどもに、こんな芸当ができると思えない。だとしたらさっき霧の中から聞こえた突然聞こえた声の野郎か。ダメだ、視界が、ぼやけて―――。
「悪りぃな新人。後で話聞いてやるから、今は大人しく寝てろ」
視界はおろか、聴覚も遠退いていく中で聞こえた男の声。さっき霧の中でした男の声と同じものだ。
姿を拝みたかったが、その前に俺の意識は闇の底へと落ちていった。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

データワールド(DataWorld)
大斗ダイソン
SF
あらすじ
現代日本、高校生の神夜蒼麻は、親友の玄芳暁斗と共に日常を送っていた。しかし、ある日、不可解な現象に遭遇し、二人は突如として仮想世界(データワールド)に転送されてしまう。
その仮想世界は、かつて禁止された「人体粒子化」実験の結果として生まれた場所だった。そこでは、現実世界から転送された人々がNPC化し、記憶を失った状態で存在していた。
一方、霧咲祇那という少女は、長らくNPCとして機能していたが、謎の白髪の男によって記憶を取り戻す。彼女は自分が仮想世界にいることを再認識し、過去の出来事を思い出す。白髪の男は彼女に協力を求めるが、その真意は不明瞭なままだ。
物語は、現実世界での「人体粒子化」実験の真相、仮想世界の本質、そして登場人物たちの過去と未来が絡み合う。神夜と暁斗は新たな環境に適応しながら、この世界の謎を解き明かそうとする。一方、霧咲祇那は復讐の念に駆られながらも、白髪の男の提案に悩む。
仮想世界では200年もの時が流れ、独特の文化や秩序が形成されていた。発光する星空や、現実とは異なる物理法則など、幻想的な要素が日常に溶け込んでいる。
登場人物たちは、自分たちの存在意義や、現実世界との関係性を模索しながら、仮想世界を揺るがす大きな陰謀に巻き込まれていく。果たして彼らは真実にたどり着き、自由を手に入れることができるのか。そして、現実世界と仮想世界の境界線は、どのように変化していくのか。
この物語は、SFとファンタジーの要素を融合させながら、人間の記憶、感情、そしてアイデンティティの本質に迫る壮大な冒険譚である。

法術装甲隊ダグフェロン 永遠に続く世紀末の国で 『修羅の国』での死闘
橋本 直
SF
その文明は出会うべきではなかった
その人との出会いは歓迎すべきものではなかった
これは悲しい『出会い』の物語
『特殊な部隊』と出会うことで青年にはある『宿命』がせおわされることになる
法術装甲隊ダグフェロン 第三部
遼州人の青年『神前誠(しんぜんまこと)』は法術の新たな可能性を追求する司法局の要請により『05式広域制圧砲』と言う新兵器の実験に駆り出される。その兵器は法術の特性を生かして敵を殺傷せずにその意識を奪うと言う兵器で、対ゲリラ戦等の『特殊な部隊』と呼ばれる司法局実働部隊に適した兵器だった。
一方、遼州系第二惑星の大国『甲武』では、国家の意思決定最高機関『殿上会』が開かれようとしていた。それに出席するために殿上貴族である『特殊な部隊』の部隊長、嵯峨惟基は甲武へと向かった。
その間隙を縫ったかのように『修羅の国』と呼ばれる紛争の巣窟、ベルルカン大陸のバルキスタン共和国で行われる予定だった選挙合意を反政府勢力が破棄し機動兵器を使った大規模攻勢に打って出て停戦合意が破綻したとの報が『特殊な部隊』に届く。
この停戦合意の破棄を理由に甲武とアメリカは合同で介入を企てようとしていた。その阻止のため、神前誠以下『特殊な部隊』の面々は輸送機でバルキスタン共和国へ向かった。切り札は『05式広域鎮圧砲』とそれを操る誠。『特殊な部隊』の制式シュツルム・パンツァー05式の機動性の無さが作戦を難しいものに変える。
そんな時間との戦いの中、『特殊な部隊』を見守る影があった。
『廃帝ハド』、『ビッグブラザー』、そしてネオナチ。
誠は反政府勢力の攻勢を『05式広域鎮圧砲』を使用して止めることが出来るのか?それとも……。
SFお仕事ギャグロマン小説。

特殊部隊の俺が転生すると、目の前で絶世の美人母娘が犯されそうで助けたら、とんでもないヤンデレ貴族だった
なるとし
ファンタジー
鷹取晴翔(たかとりはると)は陸上自衛隊のとある特殊部隊に所属している。だが、ある日、訓練の途中、不慮の事故に遭い、異世界に転生することとなる。
特殊部隊で使っていた武器や防具などを召喚できる特殊能力を謎の存在から授かり、目を開けたら、絶世の美女とも呼ばれる母娘が男たちによって犯されそうになっていた。
武装状態の鷹取晴翔は、持ち前の優秀な身体能力と武器を使い、その母娘と敷地にいる使用人たちを救う。
だけど、その母と娘二人は、
とおおおおんでもないヤンデレだった……
第3回次世代ファンタジーカップに出すために一部を修正して投稿したものです。

セルリアン
吉谷新次
SF
銀河連邦軍の上官と拗れたことをキッカケに銀河連邦から離れて、
賞金稼ぎをすることとなったセルリアン・リップルは、
希少な資源を手に入れることに成功する。
しかし、突如として現れたカッツィ団という
魔界から独立を試みる団体によって襲撃を受け、資源の強奪をされたうえ、
賞金稼ぎの相棒を暗殺されてしまう。
人界の銀河連邦と魔界が一触即発となっている時代。
各星団から独立を試みる団体が増える傾向にあり、
無所属の団体や個人が無法地帯で衝突する事件も多発し始めていた。
リップルは強靭な身体と念力を持ち合わせていたため、
生きたままカッツィ団のゴミと一緒に魔界の惑星に捨てられてしまう。
その惑星で出会ったランスという見習い魔術師の少女に助けられ、
次第に会話が弾み、意気投合する。
だが、またしても、
カッツィ団の襲撃とランスの誘拐を目の当たりにしてしまう。
リップルにとってカッツィ団に対する敵対心が強まり、
賞金稼ぎとしてではなく、一個人として、
カッツィ団の頭首ジャンに会いに行くことを決意する。
カッツィ団のいる惑星に侵入するためには、
ブーチという女性操縦士がいる輸送船が必要となり、
彼女を説得することから始まる。
また、その輸送船は、
魔術師から見つからないように隠す迷彩妖術が必要となるため、
妖精の住む惑星で同行ができる妖精を募集する。
加えて、魔界が人界科学の真似事をしている、ということで、
警備システムを弱体化できるハッキング技術の習得者を探すことになる。
リップルは強引な手段を使ってでも、
ランスの救出とカッツィ団の頭首に会うことを目的に行動を起こす。
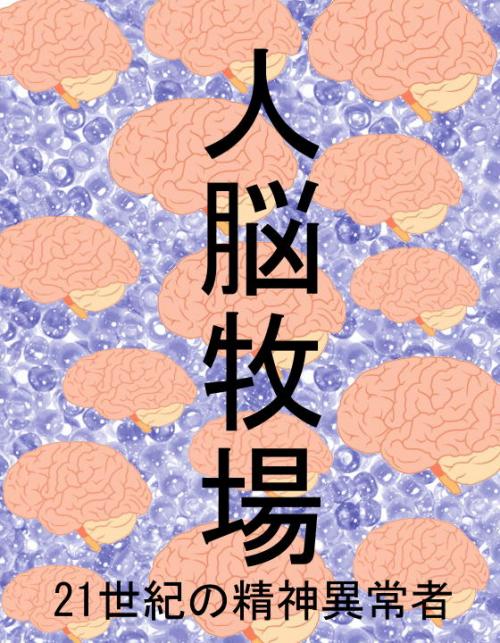
人脳牧場
21世紀の精神異常者
SF
ハリウッド映画仕立ての近未来エンタメSF。
狂気の天才科学者、ニューマン博士は、自らの人体から脳(人脳)を取り出し、コンピューターに接続。異形の人工知能と化す。
博士の愛弟子、ティムは、博士無き後のプロジェクトを指揮。彼は、「邪悪な存在となるな」の会社方針の基、博士が邪悪とならぬよう、注意深く監視し、研究を進める。
博士は、コンピューター(電脳)と接続されることで脅威の能力を獲得。ネット上の情報を自在に知識化し、精神は神の領域に達する。バーチャル世界では、あのモハメッド・アリをもKOする偉業を達成。ティムは、博士の底知れぬ能力に脅威を感じ始める。
しかし、博士の能力は、監視するティムをも欺く術を身につけ、次第に、邪悪な物へと変貌する。ライバルの人工知能にサイバー攻撃を仕掛け、社会システムを大混乱に陥れる。赤ん坊や子供の脳を抜き取り、自分の子孫とする。更には、金融システムのハッキングで、世界中の資産家の隠し資産を強奪、莫大な金の力で、会社をも乗っ取る。
ティムは、危機感を持ち、博士との対立姿勢を鮮明にしてゆく。しかし、絶大な力を得た博士は、意に介さず、逆にティムを人脳化しようと画策。彼の恋人モリーを事故に見せかけ人脳とする。そして、失意のティムは、復讐の鬼と化す。
だが、博士の暴走は止まらず、人類の半数、40億人を強制的に人脳とする、驚愕の計画が明かにされる。
これを阻止すべく、博士の抹殺を強行するが失敗、逆にアンドロイドでティムを捉え、人脳とする。仲間は、ティムを救出すべく、決死の奪還作戦を敢行。何とかティムの人脳を取り戻すことに成功するのだが、仲間の裏切りにより、アメリカを追放、日本へと辿り着く。
ティム等は、日本で忍術を学び、日本の最先端技術の粋を集めたアンドロイドを入手。これらを武器に、反転攻勢を仕掛け、アメリカに再上陸を果たす。そして、博士との最終決戦に挑むのである。

世紀末ゾンビ世界でスローライフ【解説付】
しおじろう
SF
時は世紀末、地球は宇宙人襲来を受け
壊滅状態となった。
地球外からもたされたのは破壊のみならず、
ゾンビウイルスが蔓延した。
1人のおとぼけハク青年は、それでも
のんびり性格は変わらない、疲れようが
疲れまいがのほほん生活
いつか貴方の生きるバイブルになるかも
知れない貴重なサバイバル術!

忘却の艦隊
KeyBow
SF
新設された超弩級砲艦を旗艦とし新造艦と老朽艦の入れ替え任務に就いていたが、駐留基地に入るには数が多く、月の1つにて物資と人員の入れ替えを行っていた。
大型輸送艦は工作艦を兼ねた。
総勢250艦の航宙艦は退役艦が110艦、入れ替え用が同数。
残り30艦は増強に伴い新規配備される艦だった。
輸送任務の最先任士官は大佐。
新造砲艦の設計にも関わり、旗艦の引き渡しのついでに他の艦の指揮も執り行っていた。
本来艦隊の指揮は少将以上だが、輸送任務の為、設計に関わった大佐が任命された。
他に星系防衛の指揮官として少将と、退役間近の大将とその副官や副長が視察の為便乗していた。
公安に近い監査だった。
しかし、この2名とその側近はこの艦隊及び駐留艦隊の指揮系統から外れている。
そんな人員の載せ替えが半分ほど行われた時に中緊急警報が鳴り、ライナン星系第3惑星より緊急の救援要請が入る。
機転を利かせ砲艦で敵の大半を仕留めるも、苦し紛れに敵は主系列星を人口ブラックホールにしてしまった。
完全にブラックホールに成長し、その重力から逃れられないようになるまで数分しか猶予が無かった。
意図しない戦闘の影響から士気はだだ下がり。そのブラックホールから逃れる為、禁止されている重力ジャンプを敢行する。
恒星から近い距離では禁止されているし、システム的にも不可だった。
なんとか制限内に解除し、重力ジャンプを敢行した。
しかし、禁止されているその理由通りの状況に陥った。
艦隊ごとセットした座標からズレ、恒星から数光年離れた所にジャンプし【ワープのような架空の移動方法】、再び重力ジャンプ可能な所まで移動するのに33年程掛かる。
そんな中忘れ去られた艦隊が33年の月日の後、本星へと帰還を目指す。
果たして彼らは帰還できるのか?
帰還出来たとして彼らに待ち受ける運命は?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















