10 / 15
Chapter 2 The [C]apricious
Act10:安心、それが人間の最も近くにいる敵である
しおりを挟む
他愛ない話をしながら、リアンとダリアはいくつかの店を回った。何も買いはしなかったが、リアンはその時間を楽しんでいた。
「あなたって、こういうの慣れてるの?」
人通りの多い道を歩いていた時、不意に彼女がそう訊いて来た。
「うん? まーね」
特に考えもせず、すぐにそう答えたリアンにダリアは笑う。
「素直なのね。引かれると思わないの?」
「だって、嘘吐いたって意味ないでしょ?」
「変な人」
くすくすと笑いながら、ダリアは先を歩く。赤みがかった茶髪が風に揺れる。
「ほーんと変な人ね。下心が見え見えなのに嫌な感じがしないのよ」
「女の子には優しくしないと。楽しいことはするけど、嫌なことはしないよ」
「そう。紳士なのね」
コン、コン、とヒールブーツが音を立て、くるりとロングスカートを翻して彼女は振り返った。
「ね。最後に一ヶ所。私の好きな所に連れて行ってあげる」
その目はとても、蠱惑的だった。
*
高いビル群の間を進む。表通りの喧騒は遠くなりつつある。コッコッという前を進む彼女の足音と、自分の鈍い足音が響いている。
ビルの間から覗く青空を見上げながら、リアンは言う。
「ねぇ。どこ行くの? 路地の隠れたお店とか?」
「着いてからのお楽しみ。本当に素敵な所だから」
「ふーん、それは楽しみだね」
彼女の足取りは楽しそうだった。薄暗い路地に似合わない。白いワンピースでも着て、満開の花畑でも歩いていて欲しい。折角名前も花の名前なのだから。リアンはそんなことを思う。
「……あなたって、この街の人じゃないわよね」
「え、分かる?」
「いかにも田舎ものだもの。警戒心が薄いところとかね」
「えぇ~、そうかな。俺、人を見る目はあると思うんだけど……」
ダリアが立ち止まる。リアンも遅れて立ち止まった。振り向いた彼女はおかしそうに笑っている。
「そういう所よ。ほんと、本当に………」
赤紫の瞳とばちりと目が合った。その時、リアンはいつか誰かに聞いたダリアの花言葉を思い出した。それが、何の関係があるのか──。
動いたのは、ほとんど反射だった。ダリアの右手に何かが閃いたのを見て、咄嗟に身を翻した。
脇を銀色の刃が通り抜けた。背筋が凍る。後退りながら、リアンは苦笑を浮かべる。
「……物騒なもの持ってんね?」
「避けた……避けたわね。私も見る目がなかった……か」
ダリアはがっかりしたように手に握った刃を見る。そして、リアンの顔を見て薄っすらと笑う。
「あなた、自分の認識を改めた方がいいわ。……でも、まぁ、もう遅いか」
「……俺、君に刺されるようなことしたっけ?」
「そうね。強いて言うなら、私に関わったこと、よ」
そう言う彼女の顔は猟奇的だった。一歩、二歩とにじり寄ってくる。リアンは左手を前に出しながら、ゆっくりと後ずさる。
「ねえ、考え直そ? もっと楽しいことあるでしょ」
「これが私の一番楽しいことよ。ふふ。あなたみたいな、無警戒な男を殺すことがね」
「常習犯なの? そっか……」
「……なぁに? その反応……もっと絶望してよ」
「うーん、何と言うか……」
右手をズボンのポケットに突っ込んだ。そこには折りたたみナイフがある。だが、それを出すのをリアンは躊躇った。
「……助けでも呼ぶつもり?」
「呼ばないよ」
「じゃあ、死んで。この際何でもいいわ。あなたなら悦く泣き叫んでくれると思ったんだけど。期待外れだわ」
いわゆる所の快楽犯、彼女の正体は殺人鬼だ。人は見かけによらない、とはよく言ったものだ。そう言えばアルヴァーロは見かけどころか中身だって良い人だ。家庭だって持っている。それでも世にも恐ろしき殺人者だ。人間っていうのは本当に分からない。彼女の言う通り、リアンは自分の人を見る目の認識を改めないといけないなと思った。……なんと悠長なことか。
明確に殺意を向けられている。ルチアーノを怒らせた時より怖い。殺気の種類が違う。これは怒りや何でもなく、悦楽による、這い寄るような、まとわりつく様な、気持ちの悪いものだった。
「……頼むよ、引いてくれない? 君を傷付けたくないんだ」
「そういう……女なら簡単に抑えられると思ってるの、嫌いよ」
彼女が突っ込んでくる。ナイフを避けて、その右手を右手で捕まえた。ブンブンと彼女が振るのをなんとか抑える。
「思ったより……力強いね……!」
腕の勢いを利用し、突き放すようにして距離を取る。再び彼女が突っ込んで来るのを避けて、身を翻す。位置が逆転する。
「……避けるだけ? 抵抗しないの? 腰抜けね」
「嫌なことはしないって言っただろ。痛いこともね」
「言ってる場合?」
切りつけ。左肩を浅く切り裂かれる。右手で傷口を抑えた。
「つッ……」
「そう、その顔……でも、最初に絡んで来た男の方が、良い顔してくれたかもね」
「特殊性癖ってこと……はは。イヤだね。痛くないことで楽しもうよ。どうせならベッドの上とかでさ」
「そういうことも、あったわよ。せっかく家出少女を装ったんだから、もう少し堪えても良かったんだけど。あなたがあまりにも……男らしいものだから。我慢出来なくなっちゃった」
右手を離して見ると、べったりと紅い血がついている。気持ちがくらりとする。切られるってこんな感じなんだ、と思う。刺されたらもっと痛いんだろうな、とそんな事を考えながら────己が初めて刺した男のことを思い出しながら、そんなことを思う。
「……人を刺すのってさ……すごく、イヤな感じがするだろ」
「────知ったようなことを言うのね。私は好きよ」
「知ってるよ。あぁ、そうか。そう……あの感触を、好きだと思う人間もいるのか。……どうかしてる」
「……あなた、何者?」
ダリアは怪訝な顔をした。リアンは目を伏せた。
「さぁね」
次の瞬間、ダリアは後ろから誰かに口を抑えられ、右手を掴まれて自分が持っている刃を首筋に突き立てられた。声を上げる間もなく、彼女は糸の切れた人間の様に地面に崩れ落ちた。
「……ルチアーノ!」
リアンは思わず叫ぶ。彼が後ろからそっと近付いて来ているのには気付いていたが、そんな凶行に及ぶとは思っていなかった。
ルチアーノはダリアを見下ろしている。彼女は僅かに口をぱくぱくさせたあと、目から光を失った。
「……なんで! 殺すことないだろ!」
「ある。お前の命を狙った。そういうのは置いておいちゃいけない。アルヴァーロさんの教えだ」
「─────」
リアンは言葉を失って、冷徹な目をしたルチアーノを見た後──視線を落として、物言わぬ屍と化した狂気の女を見た。赤い血溜まりが首元から広がって行く。……あまりにもあっさりと人は死んでしまうものだと、リアンは思った。もしかしたら、自分がこうなっていたかもしれないのだ。
「……何でここに……」
「ずっと後つけてたんだよ」
「……ほんとに?」
「どう考えても怪しいだろ。……で、お前がどうにかするのかと思って見てたらこのザマだ。何で抵抗しない」
「……俺は女の子に手は上げない」
「────アホか。死んだら元も子もないだろうが」
ルチアーノはダリアの死体を跨いで、リアンの方へ歩いて来る。
「……怪我しただろ。見せろ」
「大したことないよ……ちょっと掠っただけ」
とは言え痛い。服が裂けてしまった。折角買ってもらったのにな、と思う。傷はすぐに治るが、これは治らない。
ルチアーノは傷を見ると頷いた。
「本当に掠っただけだな。縫う必要は無さそうだ」
「……縫う時ってお前が縫うの?」
「まさか。医者のところに連れてくよ。…ここから結構遠いけど……」
「頼れる医者がいるんだ?」
「まぁな。変わった人だけど、頼りになる」
そしてルチアーノは続けて口を開こうとして────リアンの顔を見て、やめた。そのまま踵を返して歩き出したルチアーノをリアンは追う。
「な、何だよ!」
「……会ってからのお楽しみにしておこうと思って」
「何が⁈」
美人だなどと言ったら、リアンが浮かれるのが目に見えている。何だか腹立たしかったし、彼が何か余計なことをしそうな気がして口を閉ざした。大体、彼女はいくつかも分からないし、少なくとも自分やリアンよりは遥かに歳上だ。
彼女に会いに行く時は大抵何か(主にルチアーノが)怪我をやらかした時だ。行かないに越したことはない。彼女は寂しがるが。
「人目につく前に帰るぞ」
「……う、うん」
「ったく、これに懲りたら大人しくしてろ」
「……分かったよ……」
命を助けられたのだから、言うことを聞く他ない。リアンはそう思って頷くと、ルチアーノの後について帰路についた。
*
帰ると、テーブルの上に新聞が出ているのが目に入った。それをルチアーノが取り上げると、中の紙面を指した。
「ほら見ろ、これ」
「何」
リアンはソファに座りながらそれを見る。ウィスタリアで起こった事件の記事だった。
「……連続…殺人事件……」
「路地裏で男の死体が見つかる事件が何件も上がってる。それもこの二ヶ月の間に五件だ」
「…………これが、彼女ってこと?」
「そうだろ」
断定的に言うルチアーノに、リアンは首を捻る。
「分かんないじゃん……」
「お前があのまま刺し殺されてたら、この記事に仲間入りだ」
「……」
そう言われたら、そうなのかもしれない。リアンはぐぅの音も出なかった。
「本来なら、俺たちは無闇に外の人間と関係を作るべきじゃない」
「こういうことがあるから?」
「それだけじゃない。カタギの人間の方が、関係を持つのは危うい。俺たちは彼らの理解出来ないところにいる。……正体がバレたら、場合によっては消さなきゃならない。……だから、お前の立ち回りは俺たちにとっては危険なことなんだよ」
「……」
リアンが情報屋でいるには、人との関わりは欠かせない。自分の行動の責任の重さを、リアンはそこで改めて感じた。
「女を傷つけたくないんだろ。だったら、関わり方は考えるんだな。俺たちが、手を下さなくてもいいように」
ルチアーノはリアンを指差してそう言う。冷たくも聞こえる言葉だが、彼なりの優しさなのだろうとリアンは感じた。
「……そう思うとアルヴァーロさんって……」
リアンはふと、今ここにいない彼のことを思った。ルチアーノは頷く。
「そうだな。最も身近な人間に、正体を隠し続けてる」
それは、とても恐ろしいことだ。愛する人たちに、自分の所業がバレて、拒絶されたら……リアンは考えただけで背筋が凍った。……それを自業自得と言うのなら、そうだろうが。
「そういう、一本の細い綱の上にいるんだよ。それでもあの人は家族のことを話す時に幸せそうな顔をする────本当は、たまらなく怖いはずなのにさ」
ルチアーノはそう言って、大きく息を吐いて首を振った。
*
見慣れた門扉を見た時、彼は仄かに安堵した。
キイ、と音を立てて門が開く。その敷地に足を踏み入れた時、彼はそれまで纏っていた気配を一変させた。
柔和な、普通の人間。一家の父親として、アルヴァーロ・ビアンキはその家に帰って来た。
「ただいま。誰かいないか」
玄関を入ってすぐのところで、そう声を掛けた。やがて、奥からバタバタと音がして、女性が出て来た。彼女はアルヴァーロの顔を見るなり顔を綻ばせると、抱きついた。
「アルヴァーロさん! お帰りなさい!」
「ただいまメアリー……元気だったかい?」
愛する妻を抱き止めて、アルヴァーロは微笑む。
「帰って来るなら一つ連絡を下さってもいいのに」
「はは、驚かせたくって」
「さぁ、早く子どもたちにも顔を見せてやって下さいな」
メアリーが手を引いて振り向くと、開けっ放しの扉のところに少年が二人いた。
「ウィリアム、ギルバート! また大きくなったんじゃないか?」
アルヴァーロは笑って、息子たちの元へ歩み寄る。屈むと、その腕で二人を抱き寄せた。
「ただいま」
その温もりを一身に感じたくて、アルヴァーロは強く抱きしめた。
「と、父さん、くるしい」
ぺしぺし、とウィリアムが腕の下から背中を叩いて来た。アルヴァーロは笑って彼らを放すと、二人の息子の顔を見た。
「はは、ごめんよ。さぁ、何して遊ぼうか」
「お話が聞きたい。それから、ぼくたちの話を聞いて」
ウィリアムが大きな紫色の瞳を向けて、そう言う。ギルバートも隣でこくこくと頷いた。よく似た兄弟だ。二人とも、母よりも父である自分に似ている。色素の薄い二人は、儚げに見えた。
「いいよ。さぁ、お部屋に行こうか」
立ち上がって、二人の背中に手を添える。メアリーに目配せし、微笑んだ彼女を尻目に息子たちと二階へと向かった。ウィリアムの小さな手が手首を掴んでくる。
「父さん、早く早く」
「おおっと、そう急がなくても逃げないよ」
思っていたより強い力に、アルヴァーロは笑う。見ていない間にまた大きくなったものだ。帰って来るのは半年ぶりくらいになる。子どもの成長は早い。それを近くで見られないことを惜しくも感じたが、アルヴァーロはこの仕事を、そして拾った二人の青年のことを見捨てるわけには行かなかった。だからせめて、今だけでも。
変わらない子供部屋の中で、アルヴァーロはしばし己の血に汚れた性さがを忘れることにした。
#10 END
「あなたって、こういうの慣れてるの?」
人通りの多い道を歩いていた時、不意に彼女がそう訊いて来た。
「うん? まーね」
特に考えもせず、すぐにそう答えたリアンにダリアは笑う。
「素直なのね。引かれると思わないの?」
「だって、嘘吐いたって意味ないでしょ?」
「変な人」
くすくすと笑いながら、ダリアは先を歩く。赤みがかった茶髪が風に揺れる。
「ほーんと変な人ね。下心が見え見えなのに嫌な感じがしないのよ」
「女の子には優しくしないと。楽しいことはするけど、嫌なことはしないよ」
「そう。紳士なのね」
コン、コン、とヒールブーツが音を立て、くるりとロングスカートを翻して彼女は振り返った。
「ね。最後に一ヶ所。私の好きな所に連れて行ってあげる」
その目はとても、蠱惑的だった。
*
高いビル群の間を進む。表通りの喧騒は遠くなりつつある。コッコッという前を進む彼女の足音と、自分の鈍い足音が響いている。
ビルの間から覗く青空を見上げながら、リアンは言う。
「ねぇ。どこ行くの? 路地の隠れたお店とか?」
「着いてからのお楽しみ。本当に素敵な所だから」
「ふーん、それは楽しみだね」
彼女の足取りは楽しそうだった。薄暗い路地に似合わない。白いワンピースでも着て、満開の花畑でも歩いていて欲しい。折角名前も花の名前なのだから。リアンはそんなことを思う。
「……あなたって、この街の人じゃないわよね」
「え、分かる?」
「いかにも田舎ものだもの。警戒心が薄いところとかね」
「えぇ~、そうかな。俺、人を見る目はあると思うんだけど……」
ダリアが立ち止まる。リアンも遅れて立ち止まった。振り向いた彼女はおかしそうに笑っている。
「そういう所よ。ほんと、本当に………」
赤紫の瞳とばちりと目が合った。その時、リアンはいつか誰かに聞いたダリアの花言葉を思い出した。それが、何の関係があるのか──。
動いたのは、ほとんど反射だった。ダリアの右手に何かが閃いたのを見て、咄嗟に身を翻した。
脇を銀色の刃が通り抜けた。背筋が凍る。後退りながら、リアンは苦笑を浮かべる。
「……物騒なもの持ってんね?」
「避けた……避けたわね。私も見る目がなかった……か」
ダリアはがっかりしたように手に握った刃を見る。そして、リアンの顔を見て薄っすらと笑う。
「あなた、自分の認識を改めた方がいいわ。……でも、まぁ、もう遅いか」
「……俺、君に刺されるようなことしたっけ?」
「そうね。強いて言うなら、私に関わったこと、よ」
そう言う彼女の顔は猟奇的だった。一歩、二歩とにじり寄ってくる。リアンは左手を前に出しながら、ゆっくりと後ずさる。
「ねえ、考え直そ? もっと楽しいことあるでしょ」
「これが私の一番楽しいことよ。ふふ。あなたみたいな、無警戒な男を殺すことがね」
「常習犯なの? そっか……」
「……なぁに? その反応……もっと絶望してよ」
「うーん、何と言うか……」
右手をズボンのポケットに突っ込んだ。そこには折りたたみナイフがある。だが、それを出すのをリアンは躊躇った。
「……助けでも呼ぶつもり?」
「呼ばないよ」
「じゃあ、死んで。この際何でもいいわ。あなたなら悦く泣き叫んでくれると思ったんだけど。期待外れだわ」
いわゆる所の快楽犯、彼女の正体は殺人鬼だ。人は見かけによらない、とはよく言ったものだ。そう言えばアルヴァーロは見かけどころか中身だって良い人だ。家庭だって持っている。それでも世にも恐ろしき殺人者だ。人間っていうのは本当に分からない。彼女の言う通り、リアンは自分の人を見る目の認識を改めないといけないなと思った。……なんと悠長なことか。
明確に殺意を向けられている。ルチアーノを怒らせた時より怖い。殺気の種類が違う。これは怒りや何でもなく、悦楽による、這い寄るような、まとわりつく様な、気持ちの悪いものだった。
「……頼むよ、引いてくれない? 君を傷付けたくないんだ」
「そういう……女なら簡単に抑えられると思ってるの、嫌いよ」
彼女が突っ込んでくる。ナイフを避けて、その右手を右手で捕まえた。ブンブンと彼女が振るのをなんとか抑える。
「思ったより……力強いね……!」
腕の勢いを利用し、突き放すようにして距離を取る。再び彼女が突っ込んで来るのを避けて、身を翻す。位置が逆転する。
「……避けるだけ? 抵抗しないの? 腰抜けね」
「嫌なことはしないって言っただろ。痛いこともね」
「言ってる場合?」
切りつけ。左肩を浅く切り裂かれる。右手で傷口を抑えた。
「つッ……」
「そう、その顔……でも、最初に絡んで来た男の方が、良い顔してくれたかもね」
「特殊性癖ってこと……はは。イヤだね。痛くないことで楽しもうよ。どうせならベッドの上とかでさ」
「そういうことも、あったわよ。せっかく家出少女を装ったんだから、もう少し堪えても良かったんだけど。あなたがあまりにも……男らしいものだから。我慢出来なくなっちゃった」
右手を離して見ると、べったりと紅い血がついている。気持ちがくらりとする。切られるってこんな感じなんだ、と思う。刺されたらもっと痛いんだろうな、とそんな事を考えながら────己が初めて刺した男のことを思い出しながら、そんなことを思う。
「……人を刺すのってさ……すごく、イヤな感じがするだろ」
「────知ったようなことを言うのね。私は好きよ」
「知ってるよ。あぁ、そうか。そう……あの感触を、好きだと思う人間もいるのか。……どうかしてる」
「……あなた、何者?」
ダリアは怪訝な顔をした。リアンは目を伏せた。
「さぁね」
次の瞬間、ダリアは後ろから誰かに口を抑えられ、右手を掴まれて自分が持っている刃を首筋に突き立てられた。声を上げる間もなく、彼女は糸の切れた人間の様に地面に崩れ落ちた。
「……ルチアーノ!」
リアンは思わず叫ぶ。彼が後ろからそっと近付いて来ているのには気付いていたが、そんな凶行に及ぶとは思っていなかった。
ルチアーノはダリアを見下ろしている。彼女は僅かに口をぱくぱくさせたあと、目から光を失った。
「……なんで! 殺すことないだろ!」
「ある。お前の命を狙った。そういうのは置いておいちゃいけない。アルヴァーロさんの教えだ」
「─────」
リアンは言葉を失って、冷徹な目をしたルチアーノを見た後──視線を落として、物言わぬ屍と化した狂気の女を見た。赤い血溜まりが首元から広がって行く。……あまりにもあっさりと人は死んでしまうものだと、リアンは思った。もしかしたら、自分がこうなっていたかもしれないのだ。
「……何でここに……」
「ずっと後つけてたんだよ」
「……ほんとに?」
「どう考えても怪しいだろ。……で、お前がどうにかするのかと思って見てたらこのザマだ。何で抵抗しない」
「……俺は女の子に手は上げない」
「────アホか。死んだら元も子もないだろうが」
ルチアーノはダリアの死体を跨いで、リアンの方へ歩いて来る。
「……怪我しただろ。見せろ」
「大したことないよ……ちょっと掠っただけ」
とは言え痛い。服が裂けてしまった。折角買ってもらったのにな、と思う。傷はすぐに治るが、これは治らない。
ルチアーノは傷を見ると頷いた。
「本当に掠っただけだな。縫う必要は無さそうだ」
「……縫う時ってお前が縫うの?」
「まさか。医者のところに連れてくよ。…ここから結構遠いけど……」
「頼れる医者がいるんだ?」
「まぁな。変わった人だけど、頼りになる」
そしてルチアーノは続けて口を開こうとして────リアンの顔を見て、やめた。そのまま踵を返して歩き出したルチアーノをリアンは追う。
「な、何だよ!」
「……会ってからのお楽しみにしておこうと思って」
「何が⁈」
美人だなどと言ったら、リアンが浮かれるのが目に見えている。何だか腹立たしかったし、彼が何か余計なことをしそうな気がして口を閉ざした。大体、彼女はいくつかも分からないし、少なくとも自分やリアンよりは遥かに歳上だ。
彼女に会いに行く時は大抵何か(主にルチアーノが)怪我をやらかした時だ。行かないに越したことはない。彼女は寂しがるが。
「人目につく前に帰るぞ」
「……う、うん」
「ったく、これに懲りたら大人しくしてろ」
「……分かったよ……」
命を助けられたのだから、言うことを聞く他ない。リアンはそう思って頷くと、ルチアーノの後について帰路についた。
*
帰ると、テーブルの上に新聞が出ているのが目に入った。それをルチアーノが取り上げると、中の紙面を指した。
「ほら見ろ、これ」
「何」
リアンはソファに座りながらそれを見る。ウィスタリアで起こった事件の記事だった。
「……連続…殺人事件……」
「路地裏で男の死体が見つかる事件が何件も上がってる。それもこの二ヶ月の間に五件だ」
「…………これが、彼女ってこと?」
「そうだろ」
断定的に言うルチアーノに、リアンは首を捻る。
「分かんないじゃん……」
「お前があのまま刺し殺されてたら、この記事に仲間入りだ」
「……」
そう言われたら、そうなのかもしれない。リアンはぐぅの音も出なかった。
「本来なら、俺たちは無闇に外の人間と関係を作るべきじゃない」
「こういうことがあるから?」
「それだけじゃない。カタギの人間の方が、関係を持つのは危うい。俺たちは彼らの理解出来ないところにいる。……正体がバレたら、場合によっては消さなきゃならない。……だから、お前の立ち回りは俺たちにとっては危険なことなんだよ」
「……」
リアンが情報屋でいるには、人との関わりは欠かせない。自分の行動の責任の重さを、リアンはそこで改めて感じた。
「女を傷つけたくないんだろ。だったら、関わり方は考えるんだな。俺たちが、手を下さなくてもいいように」
ルチアーノはリアンを指差してそう言う。冷たくも聞こえる言葉だが、彼なりの優しさなのだろうとリアンは感じた。
「……そう思うとアルヴァーロさんって……」
リアンはふと、今ここにいない彼のことを思った。ルチアーノは頷く。
「そうだな。最も身近な人間に、正体を隠し続けてる」
それは、とても恐ろしいことだ。愛する人たちに、自分の所業がバレて、拒絶されたら……リアンは考えただけで背筋が凍った。……それを自業自得と言うのなら、そうだろうが。
「そういう、一本の細い綱の上にいるんだよ。それでもあの人は家族のことを話す時に幸せそうな顔をする────本当は、たまらなく怖いはずなのにさ」
ルチアーノはそう言って、大きく息を吐いて首を振った。
*
見慣れた門扉を見た時、彼は仄かに安堵した。
キイ、と音を立てて門が開く。その敷地に足を踏み入れた時、彼はそれまで纏っていた気配を一変させた。
柔和な、普通の人間。一家の父親として、アルヴァーロ・ビアンキはその家に帰って来た。
「ただいま。誰かいないか」
玄関を入ってすぐのところで、そう声を掛けた。やがて、奥からバタバタと音がして、女性が出て来た。彼女はアルヴァーロの顔を見るなり顔を綻ばせると、抱きついた。
「アルヴァーロさん! お帰りなさい!」
「ただいまメアリー……元気だったかい?」
愛する妻を抱き止めて、アルヴァーロは微笑む。
「帰って来るなら一つ連絡を下さってもいいのに」
「はは、驚かせたくって」
「さぁ、早く子どもたちにも顔を見せてやって下さいな」
メアリーが手を引いて振り向くと、開けっ放しの扉のところに少年が二人いた。
「ウィリアム、ギルバート! また大きくなったんじゃないか?」
アルヴァーロは笑って、息子たちの元へ歩み寄る。屈むと、その腕で二人を抱き寄せた。
「ただいま」
その温もりを一身に感じたくて、アルヴァーロは強く抱きしめた。
「と、父さん、くるしい」
ぺしぺし、とウィリアムが腕の下から背中を叩いて来た。アルヴァーロは笑って彼らを放すと、二人の息子の顔を見た。
「はは、ごめんよ。さぁ、何して遊ぼうか」
「お話が聞きたい。それから、ぼくたちの話を聞いて」
ウィリアムが大きな紫色の瞳を向けて、そう言う。ギルバートも隣でこくこくと頷いた。よく似た兄弟だ。二人とも、母よりも父である自分に似ている。色素の薄い二人は、儚げに見えた。
「いいよ。さぁ、お部屋に行こうか」
立ち上がって、二人の背中に手を添える。メアリーに目配せし、微笑んだ彼女を尻目に息子たちと二階へと向かった。ウィリアムの小さな手が手首を掴んでくる。
「父さん、早く早く」
「おおっと、そう急がなくても逃げないよ」
思っていたより強い力に、アルヴァーロは笑う。見ていない間にまた大きくなったものだ。帰って来るのは半年ぶりくらいになる。子どもの成長は早い。それを近くで見られないことを惜しくも感じたが、アルヴァーロはこの仕事を、そして拾った二人の青年のことを見捨てるわけには行かなかった。だからせめて、今だけでも。
変わらない子供部屋の中で、アルヴァーロはしばし己の血に汚れた性さがを忘れることにした。
#10 END
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

ヴァーチャル・プライベート・ネットワーク・ガールズ:VPNGs
吉野茉莉
キャラ文芸
【キャライラストつき】【40文字×17行で300Pほど】
2024/01/15更新完了しました。
2042年。
瞳に装着されたレンズを通してネットに接続されている世界。
人々の暮らしは大きく変わり、世界中、月や火星まで家にいながら旅行できるようになった世界。
それでも、かろうじてリアルに学校制度が残っている世界。
これはそこで暮らす彼女たちの物語。
半ひきこもりでぼっちの久慈彩花は、週に一度の登校の帰り、寄り道をした場所で奇妙な指輪を受け取る。なんの気になしにその指輪をはめたとき、システムが勝手に起動し、女子高校生内で密かに行われているゲームに参加することになってしまう。
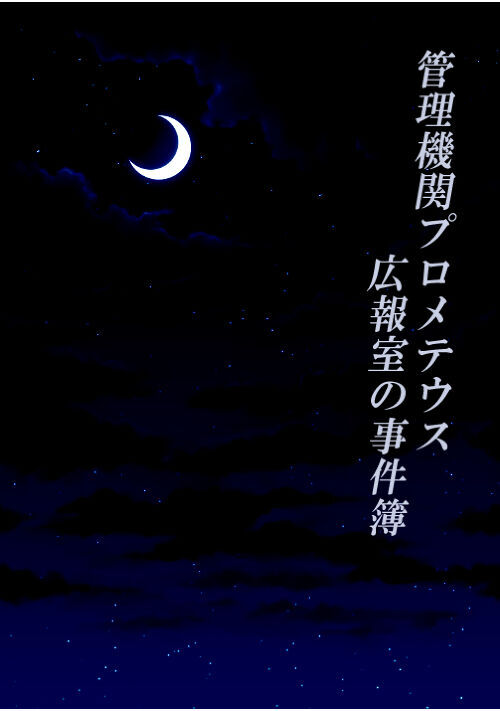
管理機関プロメテウス広報室の事件簿
石動なつめ
キャラ文芸
吸血鬼と人間が共存する世界――という建前で、実際には吸血鬼が人間を支配する世の中。
これは吸血鬼嫌いの人間の少女と、どうしようもなくこじらせた人間嫌いの吸血鬼が、何とも不安定な平穏を守るために暗躍したりしなかったりするお話。
小説家になろう様、ノベルアップ+様にも掲載しています。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

胡蝶の夢に生け
乃南羽緒
キャラ文芸
『栄枯盛衰の常の世に、不滅の名作と謳われる──』
それは、小倉百人一首。
現代の高校生や大学生の男女、ときどき大人が織りなす恋物語。
千年むかしも人は人──想うことはみな同じ。
情に寄りくる『言霊』をあつめるために今宵また、彼は夢路にやってくる。

ローリン・マイハニー!
鯨井イルカ
キャラ文芸
主人公マサヨシと壺から出てきた彼女のハートフル怪奇コメディ
下記の続編として執筆しています。
「君に★首ったけ!」https://www.alphapolis.co.jp/novel/771412269/602178787
2018.10.16ジャンルをキャラ文芸に変更しました
2018.12.21完結いたしました

カフェぱんどらの逝けない面々
来栖もよもよ&来栖もよりーぬ
キャラ文芸
奄美の霊媒師であるユタの血筋の小春。霊が見え、話も出来たりするのだが、周囲には胡散臭いと思われるのが嫌で言っていない。ごく普通に生きて行きたいし、母と結託して親族には素質がないアピールで一般企業への就職が叶うことになった。
大学の卒業を間近に控え、就職のため田舎から東京に越し、念願の都会での一人暮らしを始めた小春だが、昨今の不況で就職予定の会社があっさり倒産してしまう。大学時代のバイトの貯金で数カ月は食いつなげるものの、早急に別の就職先を探さなければ詰む。だが、不況は根深いのか別の理由なのか、新卒でも簡単には見つからない。
就活中のある日、コーヒーの香りに誘われて入ったカフェ。おっそろしく美形なオネエ言葉を話すオーナーがいる店の隅に、地縛霊がたむろしているのが見えた。目の保養と、疲れた体に美味しいコーヒーが飲めてリラックスさせて貰ったお礼に、ちょっとした親切心で「悪意はないので大丈夫だと思うが、店の中に霊が複数いるので一応除霊してもらった方がいいですよ」と帰り際に告げたら何故か捕獲され、バイトとして働いて欲しいと懇願される。正社員の仕事が決まるまで、と念押しして働くことになるのだが……。
ジバティーと呼んでくれと言う思ったより明るい地縛霊たちと、彼らが度々店に連れ込む他の霊が巻き起こす騒動に、虎雄と小春もいつしか巻き込まれる羽目になる。ほんのりラブコメ、たまにシリアス。

遊女の私が水揚げ直前に、お狐様に貰われた話
新条 カイ
キャラ文芸
子供の頃に売られた私は、今晩、遊女として通過儀礼の水揚げをされる。男の人が苦手で、嫌で仕方なかった。子供の頃から神社へお参りしている私は、今日もいつもの様にお参りをした。そして、心の中で逃げたいとも言った。そうしたら…何故かお狐様へ嫁入りしていたようで!?

煙みたいに残る Smoldering
梅室しば
キャラ文芸
剣道有段者の兄の伝手を使って、潟杜大学剣道部の合宿に同伴した生物科学科の学生・佐倉川利玖。宿舎の近くにある貴重な生態系を有する名山・葦賦岳を散策する利玖の目論見は天候の悪化によって脆くも崩れ、付き添いで呼ばれた工学部の友人・熊野史岐と共にマネージャーの東御汐子をサポートするが、そんな中、稽古中の部員の足の裏に誰のものかわからない血痕が付着するという奇妙な現象が発生した──。
※本作は「pixiv」「カクヨム」「小説家になろう」「エブリスタ」にも掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















