5 / 44
1-4
しおりを挟む
こんなことが本当にありえるのだろうか。
一人ならばぼくの願望がありえない妄想を見せたのかもしれない、って疑った。
でも松川君も彼女を見ている以上、これはぼくの頭の中だけの出来事ではない。
つまり、目の前にいる彼女は本物のライト――。
自分の心臓がばくばくと音を立てている。
いつものように不安によるものではなく、信じられないものを見ている興奮の為だ。
ライトはぼくが演劇のキャラクターとして作り出したんだ。
性格や姿形はいうまでもなく、声や仕草だって鮮明に思い浮かぶ。
「ねえさっきからどうしてわたしが見えるか聞いているんだけど。それとも君、わたしが誰からも姿に気づかれない理由を知っているの」
ぼくの知っている彼女の声に、なんだか心の奥がこみ上げてくる。
「君はぼくが作り出したからだ。だからきっとぼくと、この台本を見た松川君以外に見えないんだよ。作り出された存在だから」
ライトは目を見開くと、何度か瞬きをする。それもぼくがよく知る、彼女の驚いたときの表情だった。
それから顔を松川君の方へと向けた。
「……ねえ、彼は何を言っているの?」
「うーん、オレもどう説明していいかわからないな。君は本当にライトで間違いないのかい?」
「そうだよ。だから君らがどうしてわたしを知っているのさ」
「説明するより、見てもらった方が早いな」
松川君はそういうなりぼくのノートをすっと取り上げる。
それをそのままライトに手渡した。
ライトはいぶかしげに首をかしげながらも受け取ると、ページをめくり始めた。
松川君に読まれたときとは違う緊張感で、なんだか体中が熱くなってきた。
いくらなんでも自分の作りだした登場人物に、自分の脚本を見られるのはなんだろう? 子供のことを書いた日記を子供に読まれるようなもの……だろうか。
彼女はぱらぱらとページをめくっては、じっくりと一つのページを読み込むを何回か繰り返す。
それからぱたりとノートを閉じるとぼくらにまっすぐに目を向けた。
「確かによくできているね。わたしと同じ名前だなんて偶然だね。で、これがどうしたの」
「トヨジは君がこの脚本から出てきたんじゃないか、と思っているんだよ」
「はあ?」
目を見開いて妙な声をあげる彼女に、ぼくは何度も頷いた。
「オレもそう思っているんだけど」
「そんなわけないじゃん。わたしはわたしだよ。ちゃんと十四年間生きているし、家には親も、学校には友達だっている。わたしの人生を君……トヨジ君だっけ? 君が作ったなんてそんな馬鹿なわけないでしょ。君らが何を言っているかわからないよ」
ライトは感情を隠すことも無く、ぼくらに挑発的な目を交互に向ける。
「だいたいここどこ? わたしはそんなに遠くに来た覚えはないよ」
彼女は自分の住んでいる街の住所を読み上げる。
最後の町名こそわからなかったものの、間違いなくぼくらが住んでいる県の、ぼくらの住んでいる市だった。
だとしたら、彼女はたまたま来ただけの似た誰かだったのか。
ぼくは自分の作り出したキャラが突然現れたことに思わず感情的になったけど、彼女がそんなこととは関係が無いのなら、それはとても失礼なことだ。
……でもこれほどイメージがそのままで、名前も何もかもが同じだなんてあり得るのだろうか。それに他の人から姿が見えないって。
「誰からも姿を見られないっていうのは本当なのかい?」
「そうだよ」
松川君からの質問に、ライトはおもむろにぼくの手を握った。
突然女の子に身体を触れれることにどきりとしたけど、次に伝わる感触に思わず声をあげた。
それは石膏のような、ひどく無機質な感触だった。
彼女は手に力を入れているのがわかるけど、それはぼくにまったく伝わってこなかった。
「こんな風に何も触れないし、誰の声を聞くことも、声や姿を届けることもできないんだ」
「さっきは脚本を読んでたじゃないか」
「・・・・・・そういえばそうだね。何気に渡されて気がつかなかったけど、どうしてこのノートだけ読めたんだろう」
やっぱり彼女はぼくの妄想が生み出したのでは?
松川君にも見えるのが不思議だけど、見ず知らずの女の子がぼくの想像とうり二つで、しかもぼくら以外には誰も見えない、というよりはまだ説得力があるように思える。
後者だと問題はいろいろあるけども、前者だと松川君がたまたまぼくと同じ幻覚を見ていると、無理矢理納得できるからだ。
「――トヨジの台本から出てきたのじゃないならさ」
ぼくらは同時に松川君に視線を向ける。じっと何かを考えていた彼は、ぼくらの視線に気づいて自信ありげに口を開いた。
「だったらこういうのはどうだい。ライトはオレ達とは違う平行世界の人間なんだよ」
「へい……なにそれ?」
「パラレルワールド。自分たちの住んでいる世界と同じだけど、ちょっとだけ何かが違う無限の可能性の中にある一つの世界だ」
松川君は平行世界の説明を始めた。
それは自分が選ばなかったもう一つの選択肢の世界だという。
例えばアイスクリームを食べて、バニラを選ぶかチョコレートを選ぶかで未来が変わるかもしれない。
朝にパンを食べるか、ご飯を食べるかの選択で、その日も変わるかもしれない。
そしてそれらの選ばなかった世界は、どこかに存在しているという。
「なんらかの選択肢の中で、オレ達がいる世界と、ライトのいる世界ができたんだよ。それがなにかのきっかけで混じり合って彼女がこうしているんじゃないかな」
松川君の言っていることの全てがわかったわけじゃあ無い。
ライトが本当に存在する世界がどこかにあって、ぼくらの世界に迷い込んできたということ。
彼女がぼくらの世界で姿を見られることも、何かに干渉することができないのも、彼女がぼくらの世界の住人ではないからだということは理解できた。
ライトの方はぽかんとした表情で、曖昧な笑みを浮かべていた。
彼女の仕草がぼくの台本と同じなら、これはよくわかっていないことをごまかす顔だ。
「どうかな。いい線行っていると思うんだけど」
「ああ、そうだね。へへへ」
ライトはニコリと笑みを浮かべた。
わからないことをおくびにも出さない笑顔を向けることができるのも、彼女の特技だ。
ぼくの創作では、だけど。
でもその仕草はやっぱり魅力的だと思った。
「こんなエスエフ的な展開に巡り会うなんて今日は運がいい」
「じゃあマツカワ君はさ」
「翔。松川翔って言うんだ、オレ」
松川君は楽しくて仕方が無い、って感じの声でそう言った。
「ショウね、了解。ショウはさ、わたしが姿が見えないこととか、そのパラソル世界ができている原因とか全部わかるんだね。じゃあどうやって帰れるか教えてよ」
「知らないよ、そこまでは」
ライトが目をつり上げて松川君を睨む。
「さっきまでの偉そうな自説はどうしたの!」
「そういうもんだって。そんなに簡単に中学生が全てを解明できたら、世の中なんか面白くない」
「ああ、そう……」
「でもきっかけはわかるよ。それはトヨジの脚本だ」
ライトがぼくの方を振り向いた。
髪の毛が揺れ、耳元と眉毛を少しなでるように動く。そして横顔からまっすぐにぼくを見つめた
ああ、振り向くときの仕草もやっぱりぼくの想像通りだ。
どきりとしてなんともいえない気分だった。
「ライトも読んだだろ」
続いて松川君もこっちを見る。
あまり人に注目されたことがないので、二人に同時に見つめられるとどきどきを通りこして妙な胸騒ぎが起こってしまう。
思わず後ずさった。
「あの脚本のキャラクターが無数にある平行世界の住人である君と合致したんだ。それで君の世界との垣根みたいなのが緩くなってつながったに違いないよ。他になにかこの世界に来る前にやったことはあるかい?」
ライトは腕を組み、口をへの字にして「むむむ」とうなる。
あ、それもぼくが作った設定だ。
思わずクスリと笑いかけると、おもむろにライトは顔を上げた。
「ああ、そうだ! 電車だよ」
「電車って、この?」
どぎまぎしつつすぐそばの路面電車の駅を指さすと、ライトは頷いた。
勢いがついて、ショートヘアーがふわりと上下に揺れる
「わたし電車に乗って降りたらここ、パラソル世界についていたんだ。それで帰ろうと思ってここまで戻ってきたんだった」
僕と松川君は顔を見合わせ、そして三人同時に寂れた駅に視線を向けた。
一人ならばぼくの願望がありえない妄想を見せたのかもしれない、って疑った。
でも松川君も彼女を見ている以上、これはぼくの頭の中だけの出来事ではない。
つまり、目の前にいる彼女は本物のライト――。
自分の心臓がばくばくと音を立てている。
いつものように不安によるものではなく、信じられないものを見ている興奮の為だ。
ライトはぼくが演劇のキャラクターとして作り出したんだ。
性格や姿形はいうまでもなく、声や仕草だって鮮明に思い浮かぶ。
「ねえさっきからどうしてわたしが見えるか聞いているんだけど。それとも君、わたしが誰からも姿に気づかれない理由を知っているの」
ぼくの知っている彼女の声に、なんだか心の奥がこみ上げてくる。
「君はぼくが作り出したからだ。だからきっとぼくと、この台本を見た松川君以外に見えないんだよ。作り出された存在だから」
ライトは目を見開くと、何度か瞬きをする。それもぼくがよく知る、彼女の驚いたときの表情だった。
それから顔を松川君の方へと向けた。
「……ねえ、彼は何を言っているの?」
「うーん、オレもどう説明していいかわからないな。君は本当にライトで間違いないのかい?」
「そうだよ。だから君らがどうしてわたしを知っているのさ」
「説明するより、見てもらった方が早いな」
松川君はそういうなりぼくのノートをすっと取り上げる。
それをそのままライトに手渡した。
ライトはいぶかしげに首をかしげながらも受け取ると、ページをめくり始めた。
松川君に読まれたときとは違う緊張感で、なんだか体中が熱くなってきた。
いくらなんでも自分の作りだした登場人物に、自分の脚本を見られるのはなんだろう? 子供のことを書いた日記を子供に読まれるようなもの……だろうか。
彼女はぱらぱらとページをめくっては、じっくりと一つのページを読み込むを何回か繰り返す。
それからぱたりとノートを閉じるとぼくらにまっすぐに目を向けた。
「確かによくできているね。わたしと同じ名前だなんて偶然だね。で、これがどうしたの」
「トヨジは君がこの脚本から出てきたんじゃないか、と思っているんだよ」
「はあ?」
目を見開いて妙な声をあげる彼女に、ぼくは何度も頷いた。
「オレもそう思っているんだけど」
「そんなわけないじゃん。わたしはわたしだよ。ちゃんと十四年間生きているし、家には親も、学校には友達だっている。わたしの人生を君……トヨジ君だっけ? 君が作ったなんてそんな馬鹿なわけないでしょ。君らが何を言っているかわからないよ」
ライトは感情を隠すことも無く、ぼくらに挑発的な目を交互に向ける。
「だいたいここどこ? わたしはそんなに遠くに来た覚えはないよ」
彼女は自分の住んでいる街の住所を読み上げる。
最後の町名こそわからなかったものの、間違いなくぼくらが住んでいる県の、ぼくらの住んでいる市だった。
だとしたら、彼女はたまたま来ただけの似た誰かだったのか。
ぼくは自分の作り出したキャラが突然現れたことに思わず感情的になったけど、彼女がそんなこととは関係が無いのなら、それはとても失礼なことだ。
……でもこれほどイメージがそのままで、名前も何もかもが同じだなんてあり得るのだろうか。それに他の人から姿が見えないって。
「誰からも姿を見られないっていうのは本当なのかい?」
「そうだよ」
松川君からの質問に、ライトはおもむろにぼくの手を握った。
突然女の子に身体を触れれることにどきりとしたけど、次に伝わる感触に思わず声をあげた。
それは石膏のような、ひどく無機質な感触だった。
彼女は手に力を入れているのがわかるけど、それはぼくにまったく伝わってこなかった。
「こんな風に何も触れないし、誰の声を聞くことも、声や姿を届けることもできないんだ」
「さっきは脚本を読んでたじゃないか」
「・・・・・・そういえばそうだね。何気に渡されて気がつかなかったけど、どうしてこのノートだけ読めたんだろう」
やっぱり彼女はぼくの妄想が生み出したのでは?
松川君にも見えるのが不思議だけど、見ず知らずの女の子がぼくの想像とうり二つで、しかもぼくら以外には誰も見えない、というよりはまだ説得力があるように思える。
後者だと問題はいろいろあるけども、前者だと松川君がたまたまぼくと同じ幻覚を見ていると、無理矢理納得できるからだ。
「――トヨジの台本から出てきたのじゃないならさ」
ぼくらは同時に松川君に視線を向ける。じっと何かを考えていた彼は、ぼくらの視線に気づいて自信ありげに口を開いた。
「だったらこういうのはどうだい。ライトはオレ達とは違う平行世界の人間なんだよ」
「へい……なにそれ?」
「パラレルワールド。自分たちの住んでいる世界と同じだけど、ちょっとだけ何かが違う無限の可能性の中にある一つの世界だ」
松川君は平行世界の説明を始めた。
それは自分が選ばなかったもう一つの選択肢の世界だという。
例えばアイスクリームを食べて、バニラを選ぶかチョコレートを選ぶかで未来が変わるかもしれない。
朝にパンを食べるか、ご飯を食べるかの選択で、その日も変わるかもしれない。
そしてそれらの選ばなかった世界は、どこかに存在しているという。
「なんらかの選択肢の中で、オレ達がいる世界と、ライトのいる世界ができたんだよ。それがなにかのきっかけで混じり合って彼女がこうしているんじゃないかな」
松川君の言っていることの全てがわかったわけじゃあ無い。
ライトが本当に存在する世界がどこかにあって、ぼくらの世界に迷い込んできたということ。
彼女がぼくらの世界で姿を見られることも、何かに干渉することができないのも、彼女がぼくらの世界の住人ではないからだということは理解できた。
ライトの方はぽかんとした表情で、曖昧な笑みを浮かべていた。
彼女の仕草がぼくの台本と同じなら、これはよくわかっていないことをごまかす顔だ。
「どうかな。いい線行っていると思うんだけど」
「ああ、そうだね。へへへ」
ライトはニコリと笑みを浮かべた。
わからないことをおくびにも出さない笑顔を向けることができるのも、彼女の特技だ。
ぼくの創作では、だけど。
でもその仕草はやっぱり魅力的だと思った。
「こんなエスエフ的な展開に巡り会うなんて今日は運がいい」
「じゃあマツカワ君はさ」
「翔。松川翔って言うんだ、オレ」
松川君は楽しくて仕方が無い、って感じの声でそう言った。
「ショウね、了解。ショウはさ、わたしが姿が見えないこととか、そのパラソル世界ができている原因とか全部わかるんだね。じゃあどうやって帰れるか教えてよ」
「知らないよ、そこまでは」
ライトが目をつり上げて松川君を睨む。
「さっきまでの偉そうな自説はどうしたの!」
「そういうもんだって。そんなに簡単に中学生が全てを解明できたら、世の中なんか面白くない」
「ああ、そう……」
「でもきっかけはわかるよ。それはトヨジの脚本だ」
ライトがぼくの方を振り向いた。
髪の毛が揺れ、耳元と眉毛を少しなでるように動く。そして横顔からまっすぐにぼくを見つめた
ああ、振り向くときの仕草もやっぱりぼくの想像通りだ。
どきりとしてなんともいえない気分だった。
「ライトも読んだだろ」
続いて松川君もこっちを見る。
あまり人に注目されたことがないので、二人に同時に見つめられるとどきどきを通りこして妙な胸騒ぎが起こってしまう。
思わず後ずさった。
「あの脚本のキャラクターが無数にある平行世界の住人である君と合致したんだ。それで君の世界との垣根みたいなのが緩くなってつながったに違いないよ。他になにかこの世界に来る前にやったことはあるかい?」
ライトは腕を組み、口をへの字にして「むむむ」とうなる。
あ、それもぼくが作った設定だ。
思わずクスリと笑いかけると、おもむろにライトは顔を上げた。
「ああ、そうだ! 電車だよ」
「電車って、この?」
どぎまぎしつつすぐそばの路面電車の駅を指さすと、ライトは頷いた。
勢いがついて、ショートヘアーがふわりと上下に揺れる
「わたし電車に乗って降りたらここ、パラソル世界についていたんだ。それで帰ろうと思ってここまで戻ってきたんだった」
僕と松川君は顔を見合わせ、そして三人同時に寂れた駅に視線を向けた。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

隣人の女性がDVされてたから助けてみたら、なぜかその人(年下の女子大生)と同棲することになった(なんで?)
チドリ正明@不労所得発売中!!
青春
マンションの隣の部屋から女性の悲鳴と男性の怒鳴り声が聞こえた。
主人公 時田宗利(ときたむねとし)の判断は早かった。迷わず訪問し時間を稼ぎ、確証が取れた段階で警察に通報。DV男を現行犯でとっちめることに成功した。
ちっぽけな勇気と小心者が持つ単なる親切心でやった宗利は日常に戻る。
しかし、しばらくして宗時は見覚えのある女性が部屋の前にしゃがみ込んでいる姿を発見した。
その女性はDVを受けていたあの時の隣人だった。
「頼れる人がいないんです……私と一緒に暮らしてくれませんか?」
これはDVから女性を守ったことで始まる新たな恋物語。

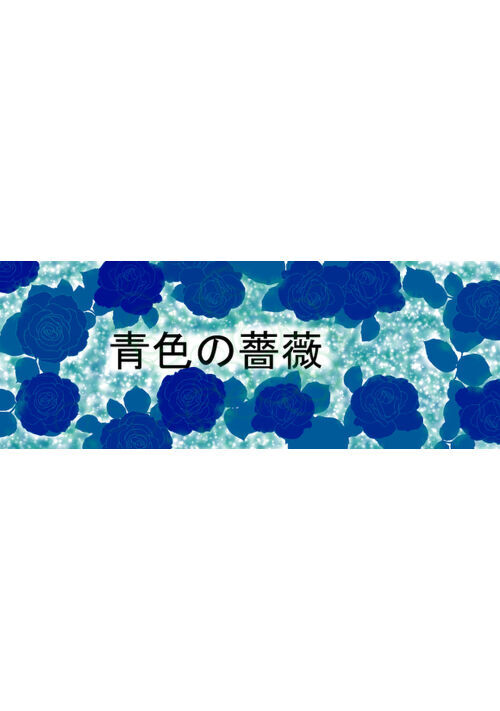
青色の薔薇
キハ
青春
栄生は小学6年生。自分の将来の夢がない。
しかし、クラスメイトは夢がある。
将来の夢をテーマにした学園物語。
6年生の始業式から始まるので、小学生時代を思い出したい方にはオススメです。
恋愛や友情も入っています!

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく


【完結】彼女はボクを狂おしいほど愛する ー超絶美少女の転校生がなぜかボクにだけぞっこんな件ー
竜竜
青春
————最後のページにたどり着いたとき、この物語の価値観は逆転する。
子どもの頃から周りと馴染めず、一人で過ごすことが多いボク。
そんなボクにも、心を許せる女の子がいた。
幼い頃に離れ離れになってしまったけど、同じ高校に転校して再開を果たした朱宮結葉。
ボクと結葉は恋人関係ではなかったけど、好き同士なことは確かだった。
再び紡がれる二人だけの幸せな日々。だけどそれは、狂おしい日常の始まりだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















