お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説
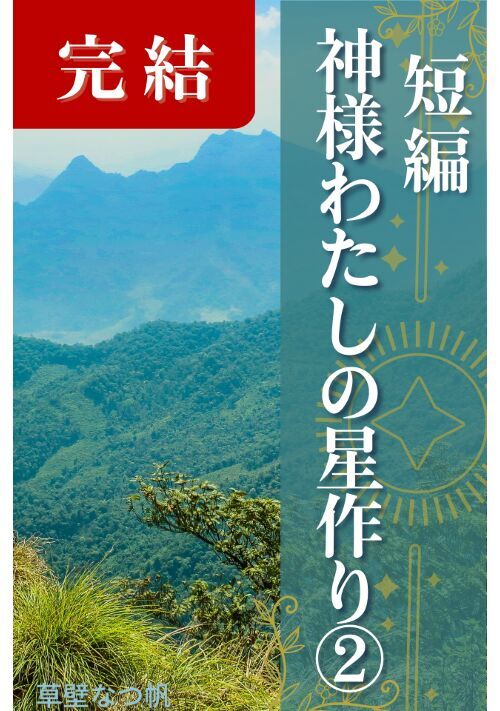
神様わたしの星作り_chapter Two【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
神様わたしの星作り chapter One の続きの物語。
ここは私が見守る砂地の星。ゾンビさんたちが暮らす小さな楽園です。
穏やかな暮らしは平和だけど少しつまらない。それに私が作ろうとしたのって、ゾンビの惑星でしたっけ?
では、神様らしく滅ぼそうではありませんか!
その決断は実行されるわけですが。予期せぬ自体もおこりまして……。
さくっと読める文字量です。ぜひお目を通しください。
(((小説家になろう、アルファポリスに投稿しています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

鋼と甘夏【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
ルーナとマーカスによるラブロマンス短編小説。
売れないピアニストだったルーナは初めての大舞台で失敗をしてしまう。そのとき出会ったマーカスという指揮官は、冷酷な顔と瞳で人を寄せ付けない雰囲気を纏っていた。
ルーナはセルジオ王国での徴兵期間彼に入る。そこで再びマーカスと出会うと、彼に惹かれていた心を知ることになった。だがしかし恋は、つぼみを付ける前に萎れてしまった。悪運の運びによってもう二度と二人が出会うことはないと、どちらも思っていた……。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)
シリーズあらすじと各小説へのアクセスをまとめました!是非ご確認下さい。

フェンディー海峡【読み切り・創作神話】
草壁なつ帆
ファンタジー
不漁により移動を余儀なくされた民族がある。その中でメイという少年は、夜中の海辺で人魚と出会う。
ひとりであると寂しそうにメイに寄り添う彼女だが。
「あなたも行ってしまうのね」
人魚との別れ。そしてこの出会いにより、メイと民族の未来は……。
(((小説家になろうとアルファポリスで投稿しています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。
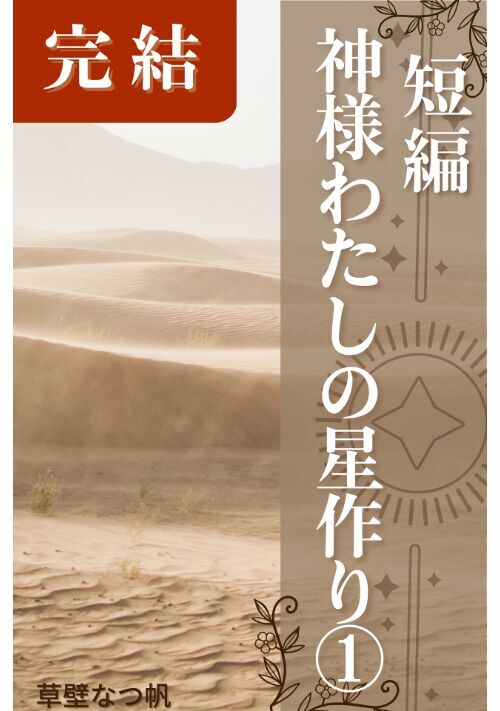
神様わたしの星作り_chapter One【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
人間の短い生涯を終えて、神様となった私の成長記。
そして私が見守る小さな惑星の物語です。
ただただ静かに回る砂漠の星は、未知なる生命体を育てて文明を作っていく。そんなロマンストーリーをお届け。
……いいえ。そう上手くは行きますまい。
失敗続きの新米神様も学ぶのです。もうこれ以上ゴミを増やしてはならないと。見守る神に徹するものだと。
短編。さくっと読めます。
続編は chapter Two へ。
(((小説家になろう、アルファポリスに上げています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

少年少女たちの日々
原口源太郎
恋愛
とある大国が隣国へ武力侵攻した。
世界の人々はその行為を大いに非難したが、争いはその二国間だけで終わると思っていた。
しかし、その数週間後に別の大国が自国の領土を主張する国へと攻め入った。それに対し、列国は武力でその行いを押さえ込もうとした。
世界の二カ所で起こった戦争の火は、やがてあちこちで燻っていた紛争を燃え上がらせ、やがて第三次世界戦争へと突入していった。
戦争は三年目を迎えたが、国連加盟国の半数以上の国で戦闘状態が続いていた。
大海を望み、二つの大国のすぐ近くに位置するとある小国は、激しい戦闘に巻き込まれていた。
その国の六人の少年少女も戦いの中に巻き込まれていく。

秘密の娘スピカの夢~黄金を示す羅針盤のありか【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
怪盗レオナルドが狙うのは、黄金を示す『アルゴ船の羅針盤』だった。
慣れた手で屋敷に侵入すると、そこには色素の薄い少女の姿が。
少女は怪盗を見るなり別人の名を口にする。
「おかえり、アンジェ」
レオナルドはこの屋敷で思いもしない体験をする。
(((小説家になろう、アルファポリスに上げています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。
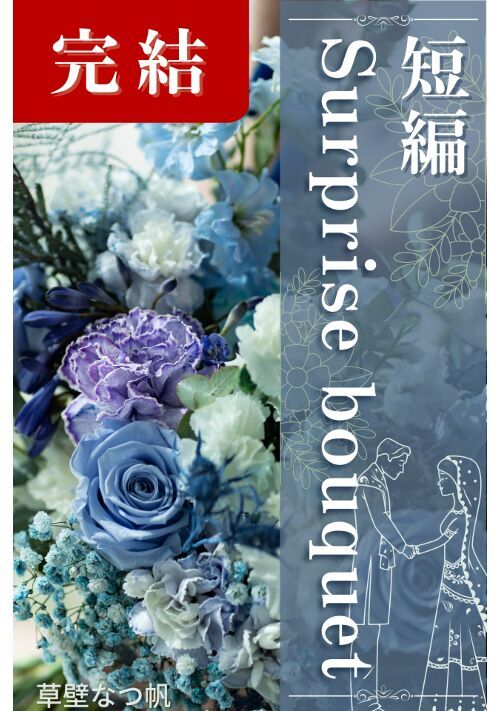
Surprise bouquet【短編・スピンオフ】
草壁なつ帆
ファンタジー
長編小説『クランクビスト』より2年前。メルチ王国リュンヒン王子と、婚約者セシリア姫によるラブロマンス。
『episode.サプライズ・ブーケ』クランクビストよりスピンオフ短編です。
「サプライズが欲しい」とセシリアに頼まれたリュンヒン。彼女の誕生日を前にプレゼントの内容に迷っていた。
いつも彼女を喜ばす術を持っていたリュンヒンだが、彼の完璧以上のサプライズはいったいどんな贈り物になるのか?
(((小説家になろう、アルファポリスに上げています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

クランクビスト‐終戦した隠居諸国王子が、軍事国家王の隠し子を娶る。愛と政治に奔走する物語です‐ 【長編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
レイヴン・バルは秘境国と呼ばれる国の王子である。
戦争で王が亡くなった後は、民も兵士も武器を捨てた。もう戦いはしないと秘境国は誓い今日に至る。
そこへ政略結婚としてバルのもとへやってきたのは、軍事国として拡大中のネザリア王国。ネザリア・エセルである。
彼女は侍女と見間違うほど華が無い。そこからバルは彼女を怪しむが、国務として関係も深めていこうとする。
エセルを取り巻くネザリア王の思惑や、それに関わる他国の王子や王の意志。各行動はバタフライ・エフェクトとなり大きな波紋を作っていく。
策略と陰謀による国取り戦争。秘境国はいったい誰の物
に? そして、バルとエセルの絆は何を変えられるのか。
(((小説家になろう、アルファポリスに上げています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















