お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

秘密の娘スピカの夢~黄金を示す羅針盤のありか【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
怪盗レオナルドが狙うのは、黄金を示す『アルゴ船の羅針盤』だった。
慣れた手で屋敷に侵入すると、そこには色素の薄い少女の姿が。
少女は怪盗を見るなり別人の名を口にする。
「おかえり、アンジェ」
レオナルドはこの屋敷で思いもしない体験をする。
(((小説家になろう、アルファポリスに上げています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

鋼と甘夏【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
ルーナとマーカスによるラブロマンス短編小説。
売れないピアニストだったルーナは初めての大舞台で失敗をしてしまう。そのとき出会ったマーカスという指揮官は、冷酷な顔と瞳で人を寄せ付けない雰囲気を纏っていた。
ルーナはセルジオ王国での徴兵期間彼に入る。そこで再びマーカスと出会うと、彼に惹かれていた心を知ることになった。だがしかし恋は、つぼみを付ける前に萎れてしまった。悪運の運びによってもう二度と二人が出会うことはないと、どちらも思っていた……。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)
シリーズあらすじと各小説へのアクセスをまとめました!是非ご確認下さい。
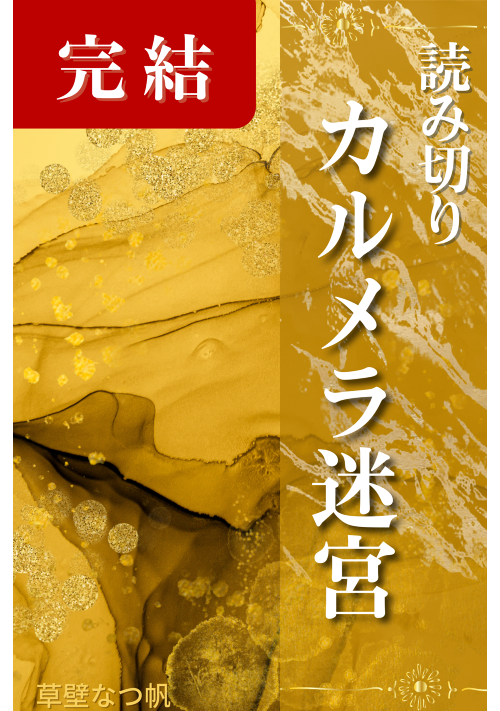
カルメラ迷宮【読み切り・創作神話】
草壁なつ帆
ファンタジー
階段は上に登るも下に降るも無数だ。皆、何かがあってそのカルメラ迷宮に迷い込むのだろうが、何も嘆く必要はない。魔物に食われるか、はたまたたった一つの出口を見つけることが出来るのか。そんなこともひと掬いの水を飲めば何も考える必要もなくなる。
(((小説家になろうとアルファポリスで投稿しています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。
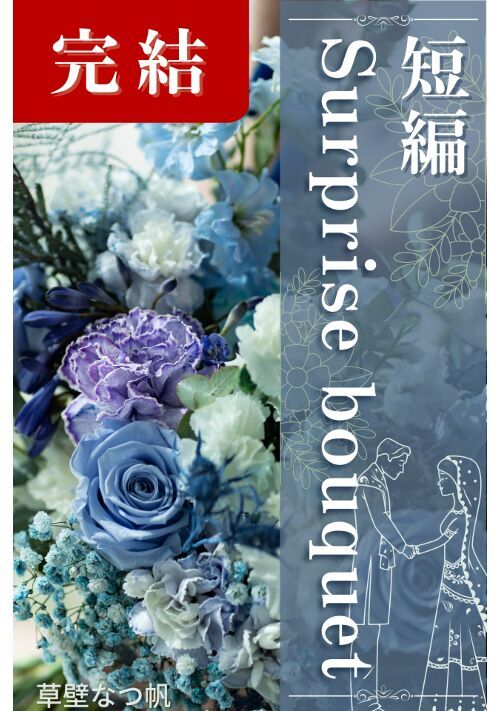
Surprise bouquet【短編・スピンオフ】
草壁なつ帆
ファンタジー
長編小説『クランクビスト』より2年前。メルチ王国リュンヒン王子と、婚約者セシリア姫によるラブロマンス。
『episode.サプライズ・ブーケ』クランクビストよりスピンオフ短編です。
「サプライズが欲しい」とセシリアに頼まれたリュンヒン。彼女の誕生日を前にプレゼントの内容に迷っていた。
いつも彼女を喜ばす術を持っていたリュンヒンだが、彼の完璧以上のサプライズはいったいどんな贈り物になるのか?
(((小説家になろう、アルファポリスに上げています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。
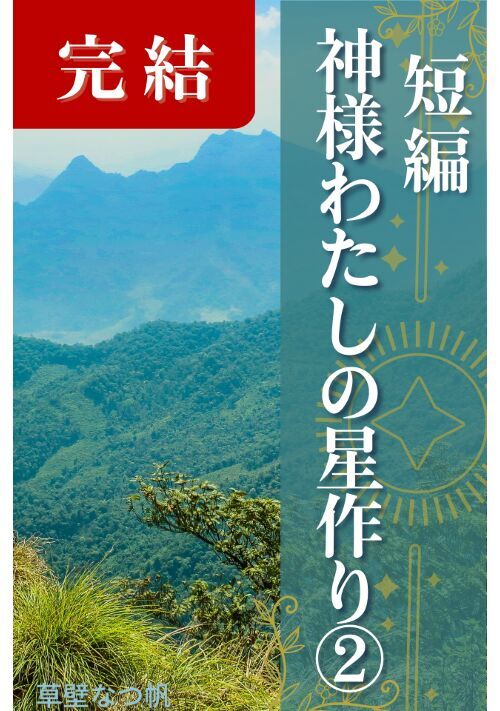
神様わたしの星作り_chapter Two【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
神様わたしの星作り chapter One の続きの物語。
ここは私が見守る砂地の星。ゾンビさんたちが暮らす小さな楽園です。
穏やかな暮らしは平和だけど少しつまらない。それに私が作ろうとしたのって、ゾンビの惑星でしたっけ?
では、神様らしく滅ぼそうではありませんか!
その決断は実行されるわけですが。予期せぬ自体もおこりまして……。
さくっと読める文字量です。ぜひお目を通しください。
(((小説家になろう、アルファポリスに投稿しています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。
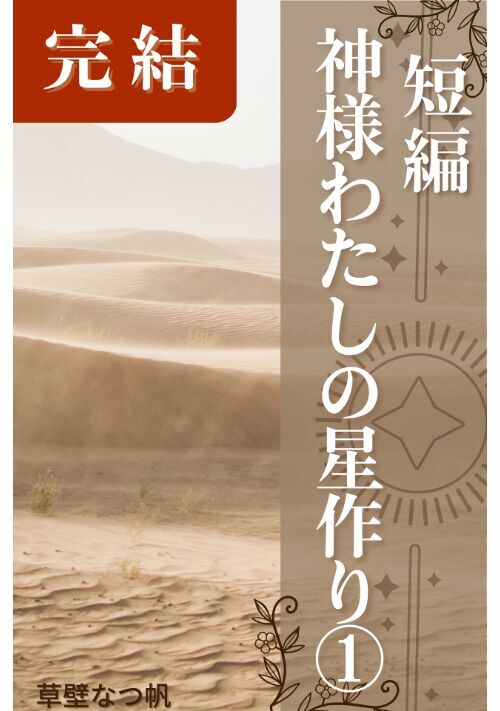
神様わたしの星作り_chapter One【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
人間の短い生涯を終えて、神様となった私の成長記。
そして私が見守る小さな惑星の物語です。
ただただ静かに回る砂漠の星は、未知なる生命体を育てて文明を作っていく。そんなロマンストーリーをお届け。
……いいえ。そう上手くは行きますまい。
失敗続きの新米神様も学ぶのです。もうこれ以上ゴミを増やしてはならないと。見守る神に徹するものだと。
短編。さくっと読めます。
続編は chapter Two へ。
(((小説家になろう、アルファポリスに上げています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

ユークとリオの黄金の羊【読み切り・創作神話】
草壁なつ帆
ファンタジー
ユークとリオは自分たちのお母さんを知りたかった。
ある日出会った天使は悪く笑ってこのように言う。
「高価なものと欲しいものを交換してやろう」
集落で最も高価な黄金の羊。それと交換で二人が得たものは……。
(((小説家になろうとアルファポリスで投稿しています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















