147 / 172
lll.ニューリアン王国、セルジオ王国
異色の会談
しおりを挟む
今回は戦闘も無くセルジオ城へと到着となった。一行は案内の者に連れられてアルゴブレロが待つ部屋へと足を進めている。
俺はその道中で何人かの兵士とすれ違い、その度にひとりひとりの顔をこっそり伺っていた。
ただ一人いたはずの知ってる顔が見当たらないのだ。内戦中は城門近くの橋で指揮官を務めていたガーネットという兵士である。
居ないということはもうアルゴブレロに殺されたのだろうかと、当然の流れのように考えていた。
それとは絶対関係無いだろうが、隣ではマルク王が人とすれ違うたびに身震いを起こしていた。
「風邪ですか?」
気になって問う。
気温は寒くは無いはずだ。昨夜、王がシーツを蹴落とし腹を出して寝ていたせいですか、とは口から出てこないよう留めてある。
「あの子と出くわしたらと思うとね……」
見ると顔は青ざめていた。訳を聞かなければ明らかに体調不良の顔をしている。
「シャーロットとは何か」
「ああ。その名前を出さないでくれ……」
セルジオに居そうな女性名を言うと当たっていたようだ。マルク王は吐きそうなのか、えづきもした。
「怪我人と病人で何を話し合うってんだよ!」
席についた途端に豪快な笑いが起こった。この応接間で俺とマルク王を待っていたアルゴブレロである。
あの時包帯に撒かれていたアルゴブレロはすっかり元気であり、包帯も取れていた。しかし机には松葉杖が立てかけられている。
それも机をバシバシ叩いて笑われることで床にバラバラ転がっていった。
「でよ、その時俺がシャーロットに言ってやったんだ」
「うっ……」
「そりゃお前。いくらなんでも俺には合わねえだろ。なあ、シャーロットってな」
「ううえ……」
酷い状況だ。アルゴブレロがわざと「シャーロットがな」と言う度にマルク王が「ううっ」とえずくという謎のゲームが繰り広げられている。
一方は辛そうであるが、もう一方は大変愉快そうだ。扱い方が分からん方が愉快な状態にあるのは、俺にとって若干助かっているのであるが。
「……親善大使とは上手くやっているみたいですね」
俺からはあえて職業名で述べることにした。
この流れに乗ってさぞかし良い話が聞けるだろうと期待したのだが、あろうことかアルゴブレロは大きく開いていた口を急に閉じ出す。
舌打ちをし「あの女……」と、いつもの殺人鬼のような顔に戻ってしまった。
「薬を塗るにしても包帯巻くにしても雑だし、要らねえって言ってんのに甘ったるい食いもんばかり運んで来やがる。気に入らねえ」
……と、嫌そうに言っている。
しかし俺が目に行ってしまうのは、そのアルゴブレロの口端についた白いクリームのような汚れだった。
虫の居所が悪そうに膝をガタガタ揺らしているその男が、今さっきいったい何が気に入らないと言っていた? と、俺はすぐに分からなくなった。
「まあ。上手くいっているならそれで」
「いってねえって言ってんだろうが!」
知らずにキレられてしまう。
「それで。こんな野郎が集まって何を話し合うってんだよ」
ボリボリ頭を掻きながらアルゴブレロが話を進めようとしてきた。この中では一番不真面目に見えてそうで無いのがたぶんこの男の性格なのである。
でなければ俺達など召集状の段階で門前払いにすればいい。
「手紙に書いたとおりです。王権放棄を目指す同盟軍に備えてこちらも団結しよう、という内容です」
「……」
アルゴブレロは椅子の前足が浮くほど踏ん反り返っていた。やがてその姿勢のまま俺のことをフッと鼻で笑った。
「ふわっと言ってくれるねぇ。前のお前の方がハッキリした物言いで好感触だったがな」
その原因がこれなんだろう? と、マルク王のことを目線で示してくる。
俺の横に座るマルク王は水分を欲しており、城の使いがなかなか水を運んで来ないことが気掛かりのようだ。
何箇所かある扉の方を順々に見ているからこちらの会話には気付いていない。
「目上にへりくだって何が悪い」
「ふん。ご苦労なこったな」
闇取引でもするかのように二言が瞬時に交わされた。
しっかりと冷えた水が運ばれてくる。マルク王はそれをすぐに飲み干した。喉が潤されると顔は笑顔になり「さあ、始めようか」と言った。
それで俺から続きを告げることにする。
「メルチとベンブルクの激戦化に備えて、ニューリアンとセルジオにご協力願いたいのです」
俺が何日かの徹夜で用意した書類を二人に配る。
マルク王はその場でペラペラとめくり出したが、アルゴブレロは指ですら触れようとしなかった。
いちいち身勝手な王の機嫌を伺うのも面倒であるし、もうこのまま続けることにした。
「レイヴン・アレンがベンブルクと繋がっていることは明らかです。今後クランクビストがベンブルクと一体化すれば、ベンブルク、カイロニア、クランクビストでベルト状になり、我々の連携が取れなくなる恐れが出ます。そうならないために、先手を打つ必要があります」
唸るのはマルク王だけである。
やけに静かなアルゴブレロはちゃんと参加しているだろうか、と資料からそっちへ目を向けてみる。ヤツは考え込んでいるのか目をつぶっていた。
病み上がりでも眠ってはいないらしい。
「そこの同盟国がそんなに脅威なのかい」
面倒臭そうに言う声だけはちゃんと参加している。
「メルチとロンドの軍だけで二国と対戦するのは現実的ではありません」
「トートタスの野郎はいつもの見送りだろ?」
「カイロニアには呼び出しを受けました」
それを言えばアルゴブレロが目を開ける。
天井を見上げたまま「へえー」と意味深のようで何も考えていないような適当な声を発していた。
「メルチ今はどういう状態なんだい?」
マルク王が入って問う。
「兵士の士気は高まりつつありますが、それでもリュンヒン殿が健在だった頃よりかなり落ち込んでいます。テダム殿のネザリアも再建に奮闘中ですし、私だけの立場ではテダム殿を引き込む力もありません」
改めて口に出すと絶望感を痛感する。
マルク王とて両肘をついてため息を吐くくらいだ。
「メルチとネザリアの統合も夢だったろうに……。二国に挟まれていたベンブルクは胸を撫で下ろしているね」
「……ですね」
もしくはリュンヒンを仕留めて万々歳かのどちらかだ。
二人して落ち込んでしまうと、マルク王が明るめの声色で場を取り持とうと努力する。
「直近の戦争はメルチが勝利で終わっているんだ。もしかしたらベンブルクは結構痛手をくらっていて、今頃アタフタしているかもしれないよ」
そのパターンはあり得ないだろうと俺は心の中で思っている。だが、マルク王の気遣いだけは貰っておこうと明るく返事をしたつもりだ。
その流れを受け取らず、アルゴブレロがやけに真面目に「おい」と声を上げる。
「ジョーサンの息子。お前はメルチの人間になったって事で良いんだな?」
会話の流れも無視した問い掛けであった。
祖国を出た俺にあえて父親の名を聞かせて来るのは、まるで未練に揺さぶりでもかけているかのようだ。
「それで結構」
即答で返した。
「クランクビストは兄……アレンのものです。私の居場所はもうそこにはありません」
同情を求める気などさらさら無い。切り落とすように清々しく告げたのである。
「そうか。なら話は早い。今すぐクランクビストを潰しておけば良い」
急に結論が出される。
いきなり耳鳴りが駆け巡るかのようだった。
俺はその道中で何人かの兵士とすれ違い、その度にひとりひとりの顔をこっそり伺っていた。
ただ一人いたはずの知ってる顔が見当たらないのだ。内戦中は城門近くの橋で指揮官を務めていたガーネットという兵士である。
居ないということはもうアルゴブレロに殺されたのだろうかと、当然の流れのように考えていた。
それとは絶対関係無いだろうが、隣ではマルク王が人とすれ違うたびに身震いを起こしていた。
「風邪ですか?」
気になって問う。
気温は寒くは無いはずだ。昨夜、王がシーツを蹴落とし腹を出して寝ていたせいですか、とは口から出てこないよう留めてある。
「あの子と出くわしたらと思うとね……」
見ると顔は青ざめていた。訳を聞かなければ明らかに体調不良の顔をしている。
「シャーロットとは何か」
「ああ。その名前を出さないでくれ……」
セルジオに居そうな女性名を言うと当たっていたようだ。マルク王は吐きそうなのか、えづきもした。
「怪我人と病人で何を話し合うってんだよ!」
席についた途端に豪快な笑いが起こった。この応接間で俺とマルク王を待っていたアルゴブレロである。
あの時包帯に撒かれていたアルゴブレロはすっかり元気であり、包帯も取れていた。しかし机には松葉杖が立てかけられている。
それも机をバシバシ叩いて笑われることで床にバラバラ転がっていった。
「でよ、その時俺がシャーロットに言ってやったんだ」
「うっ……」
「そりゃお前。いくらなんでも俺には合わねえだろ。なあ、シャーロットってな」
「ううえ……」
酷い状況だ。アルゴブレロがわざと「シャーロットがな」と言う度にマルク王が「ううっ」とえずくという謎のゲームが繰り広げられている。
一方は辛そうであるが、もう一方は大変愉快そうだ。扱い方が分からん方が愉快な状態にあるのは、俺にとって若干助かっているのであるが。
「……親善大使とは上手くやっているみたいですね」
俺からはあえて職業名で述べることにした。
この流れに乗ってさぞかし良い話が聞けるだろうと期待したのだが、あろうことかアルゴブレロは大きく開いていた口を急に閉じ出す。
舌打ちをし「あの女……」と、いつもの殺人鬼のような顔に戻ってしまった。
「薬を塗るにしても包帯巻くにしても雑だし、要らねえって言ってんのに甘ったるい食いもんばかり運んで来やがる。気に入らねえ」
……と、嫌そうに言っている。
しかし俺が目に行ってしまうのは、そのアルゴブレロの口端についた白いクリームのような汚れだった。
虫の居所が悪そうに膝をガタガタ揺らしているその男が、今さっきいったい何が気に入らないと言っていた? と、俺はすぐに分からなくなった。
「まあ。上手くいっているならそれで」
「いってねえって言ってんだろうが!」
知らずにキレられてしまう。
「それで。こんな野郎が集まって何を話し合うってんだよ」
ボリボリ頭を掻きながらアルゴブレロが話を進めようとしてきた。この中では一番不真面目に見えてそうで無いのがたぶんこの男の性格なのである。
でなければ俺達など召集状の段階で門前払いにすればいい。
「手紙に書いたとおりです。王権放棄を目指す同盟軍に備えてこちらも団結しよう、という内容です」
「……」
アルゴブレロは椅子の前足が浮くほど踏ん反り返っていた。やがてその姿勢のまま俺のことをフッと鼻で笑った。
「ふわっと言ってくれるねぇ。前のお前の方がハッキリした物言いで好感触だったがな」
その原因がこれなんだろう? と、マルク王のことを目線で示してくる。
俺の横に座るマルク王は水分を欲しており、城の使いがなかなか水を運んで来ないことが気掛かりのようだ。
何箇所かある扉の方を順々に見ているからこちらの会話には気付いていない。
「目上にへりくだって何が悪い」
「ふん。ご苦労なこったな」
闇取引でもするかのように二言が瞬時に交わされた。
しっかりと冷えた水が運ばれてくる。マルク王はそれをすぐに飲み干した。喉が潤されると顔は笑顔になり「さあ、始めようか」と言った。
それで俺から続きを告げることにする。
「メルチとベンブルクの激戦化に備えて、ニューリアンとセルジオにご協力願いたいのです」
俺が何日かの徹夜で用意した書類を二人に配る。
マルク王はその場でペラペラとめくり出したが、アルゴブレロは指ですら触れようとしなかった。
いちいち身勝手な王の機嫌を伺うのも面倒であるし、もうこのまま続けることにした。
「レイヴン・アレンがベンブルクと繋がっていることは明らかです。今後クランクビストがベンブルクと一体化すれば、ベンブルク、カイロニア、クランクビストでベルト状になり、我々の連携が取れなくなる恐れが出ます。そうならないために、先手を打つ必要があります」
唸るのはマルク王だけである。
やけに静かなアルゴブレロはちゃんと参加しているだろうか、と資料からそっちへ目を向けてみる。ヤツは考え込んでいるのか目をつぶっていた。
病み上がりでも眠ってはいないらしい。
「そこの同盟国がそんなに脅威なのかい」
面倒臭そうに言う声だけはちゃんと参加している。
「メルチとロンドの軍だけで二国と対戦するのは現実的ではありません」
「トートタスの野郎はいつもの見送りだろ?」
「カイロニアには呼び出しを受けました」
それを言えばアルゴブレロが目を開ける。
天井を見上げたまま「へえー」と意味深のようで何も考えていないような適当な声を発していた。
「メルチ今はどういう状態なんだい?」
マルク王が入って問う。
「兵士の士気は高まりつつありますが、それでもリュンヒン殿が健在だった頃よりかなり落ち込んでいます。テダム殿のネザリアも再建に奮闘中ですし、私だけの立場ではテダム殿を引き込む力もありません」
改めて口に出すと絶望感を痛感する。
マルク王とて両肘をついてため息を吐くくらいだ。
「メルチとネザリアの統合も夢だったろうに……。二国に挟まれていたベンブルクは胸を撫で下ろしているね」
「……ですね」
もしくはリュンヒンを仕留めて万々歳かのどちらかだ。
二人して落ち込んでしまうと、マルク王が明るめの声色で場を取り持とうと努力する。
「直近の戦争はメルチが勝利で終わっているんだ。もしかしたらベンブルクは結構痛手をくらっていて、今頃アタフタしているかもしれないよ」
そのパターンはあり得ないだろうと俺は心の中で思っている。だが、マルク王の気遣いだけは貰っておこうと明るく返事をしたつもりだ。
その流れを受け取らず、アルゴブレロがやけに真面目に「おい」と声を上げる。
「ジョーサンの息子。お前はメルチの人間になったって事で良いんだな?」
会話の流れも無視した問い掛けであった。
祖国を出た俺にあえて父親の名を聞かせて来るのは、まるで未練に揺さぶりでもかけているかのようだ。
「それで結構」
即答で返した。
「クランクビストは兄……アレンのものです。私の居場所はもうそこにはありません」
同情を求める気などさらさら無い。切り落とすように清々しく告げたのである。
「そうか。なら話は早い。今すぐクランクビストを潰しておけば良い」
急に結論が出される。
いきなり耳鳴りが駆け巡るかのようだった。
0
お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?
gacchi
恋愛
13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。
そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて
「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」
もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?
3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。
4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。
1章が書籍になりました。

閉架な君はアルゼレアという‐冷淡な司書との出会いが不遇の渦を作る。政治陰謀・革命・純愛にも男が奮励する物語です‐【長編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
フォルクス・ティナーは平凡な精神医の男。優柔不断で断れない性格により、悪友の勧めから仕事に失敗して医師免許を停止されていた。
不幸に悩むフォルクスは実家への帰省を決断する。しかしその前に司書アルゼレアと出会うことで運命が変わった。彼女は少女にしては冷淡で落ち着いている。黒レース地の手袋で両手を覆い、一冊の本を抱えていたのが印象的だった。
この本を巡った一連騒動をきっかけに不遇の渦は巻き始める。平凡を求めるフォルクスには、踏み込んだ事情は関心の無いことだ。しかしアルゼレアの若い好奇心と、悪友の粗相が彼を逃さない。もしくは政治家による陰謀の手も伸ばされた。
120年の停戦時代。経済成長期とは表向きだろうか。平和を疑えない世代が直面する断片的な不穏はいかに。フォルクスとアルゼレアに課された使命が果たされた時、世界は新しい時代への幕開けになる。
※この小説は戦争を推進するものではなく、また実在する宗教や団体とは無関係です。フィクションとしてお楽しみ下さい。
(((小説家になろう、アルファポリスに上げています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)
シリーズあらすじと各小説へのアクセスをまとめました!連載中作品の中からご覧になれます。気になった方は是非ご確認下さい。

貴方が側妃を望んだのです
cyaru
恋愛
「君はそれでいいのか」王太子ハロルドは言った。
「えぇ。勿論ですわ」婚約者の公爵令嬢フランセアは答えた。
誠の愛に気がついたと言われたフランセアは微笑んで答えた。
※2022年6月12日。一部書き足しました。
※架空のお話です。現実世界の話ではありません。
史実などに基づいたものではない事をご理解ください。
※話の都合上、残酷な描写がありますがそれがざまぁなのかは受け取り方は人それぞれです。
表現的にどうかと思う回は冒頭に注意喚起を書き込むようにしますが有無は作者の判断です。
※更新していくうえでタグは幾つか増えます。
※作者都合のご都合主義です。
※リアルで似たようなものが出てくると思いますが気のせいです。
※爵位や言葉使いなど現実世界、他の作者さんの作品とは異なります(似てるモノ、同じものもあります)
※誤字脱字結構多い作者です(ごめんなさい)コメント欄より教えて頂けると非常に助かります。

鋼と甘夏【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
ルーナとマーカスによるラブロマンス短編小説。
売れないピアニストだったルーナは初めての大舞台で失敗をしてしまう。そのとき出会ったマーカスという指揮官は、冷酷な顔と瞳で人を寄せ付けない雰囲気を纏っていた。
ルーナはセルジオ王国での徴兵期間彼に入る。そこで再びマーカスと出会うと、彼に惹かれていた心を知ることになった。だがしかし恋は、つぼみを付ける前に萎れてしまった。悪運の運びによってもう二度と二人が出会うことはないと、どちらも思っていた……。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)
シリーズあらすじと各小説へのアクセスをまとめました!是非ご確認下さい。

秋月の鬼
凪子
ファンタジー
時は昔。吉野の国の寒村に生まれ育った少女・常盤(ときわ)は、主都・白鴎(はくおう)を目指して旅立つ。領主秋月家では、当主である京次郎が正室を娶るため、国中の娘から身分を問わず花嫁候補を募っていた。
安曇城へたどりついた常盤は、美貌の花魁・夕霧や、高貴な姫君・容花、おきゃんな町娘・春日、おしとやかな令嬢・清子らと出会う。
境遇も立場もさまざまな彼女らは候補者として大部屋に集められ、その日から当主の嫁選びと称する試練が始まった。
ところが、その試練は死者が出るほど苛酷なものだった……。
常盤は試練を乗り越え、領主の正妻の座を掴みとれるのか?

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。
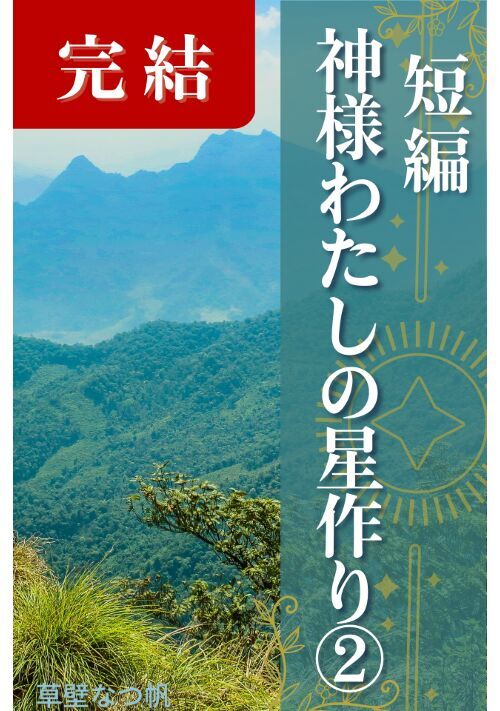
神様わたしの星作り_chapter Two【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
神様わたしの星作り chapter One の続きの物語。
ここは私が見守る砂地の星。ゾンビさんたちが暮らす小さな楽園です。
穏やかな暮らしは平和だけど少しつまらない。それに私が作ろうとしたのって、ゾンビの惑星でしたっけ?
では、神様らしく滅ぼそうではありませんか!
その決断は実行されるわけですが。予期せぬ自体もおこりまして……。
さくっと読める文字量です。ぜひお目を通しください。
(((小説家になろう、アルファポリスに投稿しています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。
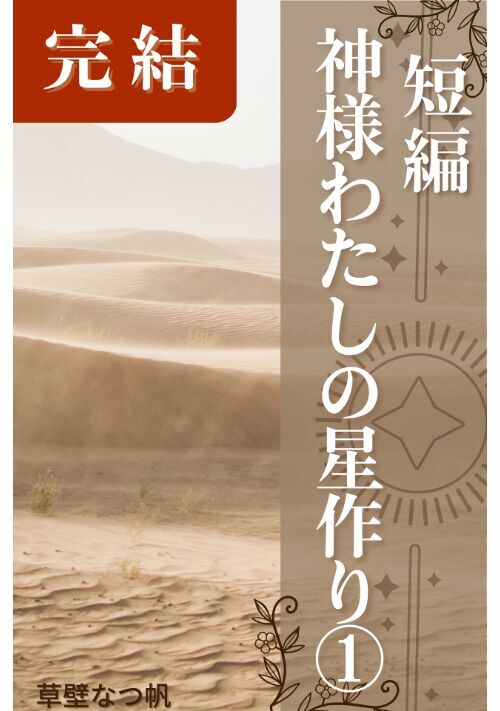
神様わたしの星作り_chapter One【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
人間の短い生涯を終えて、神様となった私の成長記。
そして私が見守る小さな惑星の物語です。
ただただ静かに回る砂漠の星は、未知なる生命体を育てて文明を作っていく。そんなロマンストーリーをお届け。
……いいえ。そう上手くは行きますまい。
失敗続きの新米神様も学ぶのです。もうこれ以上ゴミを増やしてはならないと。見守る神に徹するものだと。
短編。さくっと読めます。
続編は chapter Two へ。
(((小説家になろう、アルファポリスに上げています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















