お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

絵の具と切符とペンギンと【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
少年と女の子の出会いの物語。彼女は不思議な絵を描くし、連れている相棒も不思議生物だった。飛び出した二人の冒険は絆と小さな夢をはぐくむ。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
始まりは創造神の手先の不器用さ……。
『神と神人と人による大テーマ』
他タイトルの短編・長編小説が、歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編小説「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

挙式後すぐに離婚届を手渡された私は、この結婚は予め捨てられることが確定していた事実を知らされました
結城芙由奈@12/27電子書籍配信
恋愛
【結婚した日に、「君にこれを預けておく」と離婚届を手渡されました】
今日、私は子供の頃からずっと大好きだった人と結婚した。しかし、式の後に絶望的な事を彼に言われた。
「ごめん、本当は君とは結婚したくなかったんだ。これを預けておくから、その気になったら提出してくれ」
そう言って手渡されたのは何と離婚届けだった。
そしてどこまでも冷たい態度の夫の行動に傷つけられていく私。
けれどその裏には私の知らない、ある深い事情が隠されていた。
その真意を知った時、私は―。
※暫く鬱展開が続きます
※他サイトでも投稿中
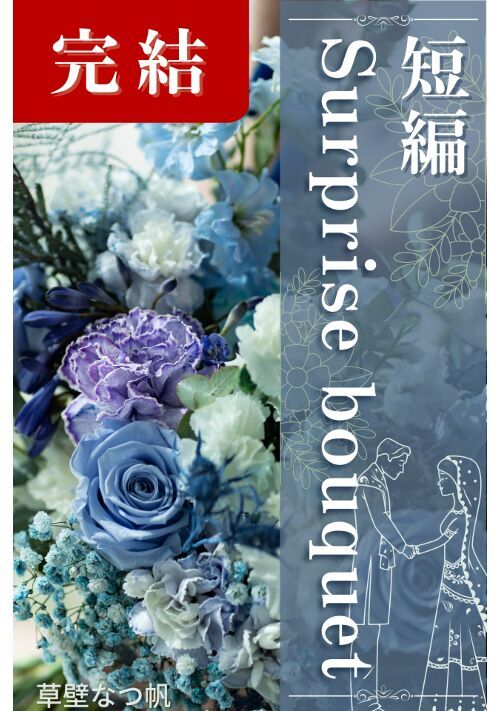
Surprise bouquet【短編・スピンオフ】
草壁なつ帆
ファンタジー
長編小説『クランクビスト』より2年前。メルチ王国リュンヒン王子と、婚約者セシリア姫によるラブロマンス。
『episode.サプライズ・ブーケ』クランクビストよりスピンオフ短編です。
「サプライズが欲しい」とセシリアに頼まれたリュンヒン。彼女の誕生日を前にプレゼントの内容に迷っていた。
いつも彼女を喜ばす術を持っていたリュンヒンだが、彼の完璧以上のサプライズはいったいどんな贈り物になるのか?
(((小説家になろう、アルファポリスに上げています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

断る――――前にもそう言ったはずだ
鈴宮(すずみや)
恋愛
「寝室を分けませんか?」
結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。
周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。
けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。
他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。
(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)
そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。
ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。
そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?

【完結】悪役令嬢に転生したけど、王太子妃にならない方が幸せじゃない?
みちこ
ファンタジー
12歳の時に前世の記憶を思い出し、自分が悪役令嬢なのに気が付いた主人公。
ずっと王太子に片思いしていて、将来は王太子妃になることしか頭になかった主人公だけど、前世の記憶を思い出したことで、王太子の何が良かったのか疑問に思うようになる
色々としがらみがある王太子妃になるより、このまま公爵家の娘として暮らす方が幸せだと気が付く

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?
gacchi
恋愛
13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。
そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて
「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」
もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?
3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。
4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。
1章が書籍になりました。

元侯爵令嬢は冷遇を満喫する
cyaru
恋愛
第三王子の不貞による婚約解消で王様に拝み倒され、渋々嫁いだ侯爵令嬢のエレイン。
しかし教会で結婚式を挙げた後、夫の口から開口一番に出た言葉は
「王命だから君を娶っただけだ。愛してもらえるとは思わないでくれ」
夫となったパトリックの側には長年の恋人であるリリシア。
自分もだけど、向こうだってわたくしの事は見たくも無いはず!っと早々の別居宣言。
お互いで交わす契約書にほっとするパトリックとエレイン。ほくそ笑む愛人リリシア。
本宅からは屋根すら見えない別邸に引きこもりお1人様生活を満喫する予定が・・。
※専門用語は出来るだけ注釈をつけますが、作者が専門用語だと思ってない専門用語がある場合があります
※作者都合のご都合主義です。
※リアルで似たようなものが出てくると思いますが気のせいです。
※架空のお話です。現実世界の話ではありません。
※爵位や言葉使いなど現実世界、他の作者さんの作品とは異なります(似てるモノ、同じものもあります)
※誤字脱字結構多い作者です(ごめんなさい)コメント欄より教えて頂けると非常に助かります。

【完結】もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?
冬馬亮
恋愛
公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。
オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・
「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」
「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















