123 / 172
lll.ロンド小国、旧ネザリア
日陰の庭
しおりを挟む
(((リュンヒン王子と婚約者セシリア姫の
(((スピンオフ短編小説もございます。
(((ご興味がありましたら、
(((下部作者マイページからご覧下さい。
(((全4部/短編小説/完結済み
元居た城より広いメルチ城の敷地を案内された。生活するのに欠かせない主要な部屋を巡ったが覚え切れるわけがないし、かなりの時間がかかった。
千年大国のかの昔からある古い城である。当時は多くの貴族らが集まって暮らしていたのだろうが今は王族一人。
そのうちこんな膨大な部屋数で暮らす世の中ではなくなるような気がしてならない。
「リュンヒン様の葬儀のこと、何から何まで本当にありがとうございました」
そのように俺に言うのはリュンヒンの執事である。歳のせいで背中が丸くなり歩くのも亀の歩みであった。
執事は「国よりも長生きして見せますよ」と可笑しなことを言うが、不思議と応援してやりたくなるような愛嬌のあるじじいだ。
俺と執事は二十個もの部屋と四つの庭をまわり終えた。
そして最後に、リュンヒンの墓が城にもあると言うのでそこへ向かっている。
国葬後は王家代々が眠る丘に葬られたはずであるが、どういうわけだか墓が二つあるらしい。
「こちらです。足元にお気をつけください」
そう言いながらも頼りない足取りなのは執事の方だ。
しかもこれから進もうとする道は、広大な庭から建物の隙間を入っていく小道よりも路地に近いような道である。
人が歩くことを想定されていないために土の地面はガタガタだ。
仕舞い忘れのジョウロなどが転がされており、雨水が溜まった中に藻が生えていた。
執事がよろけているので俺は咄嗟にその丸い背を支えた。
「ありがとうございます」
「ゆっくり進んでくれ」
「ありがとうございます」
全く同じニュアンスで言ってペコペコと頭を下げられた。
狭い道を通り、建物の壁を突き抜けると小さくまとまった裏庭に出た。
木柵が覆っているがそのすぐ下は崖であり、正面は開けてあるから森を上から見下ろせ、遠くに連なる剣山が美しい。
しかし裏庭全域が建物の影になっているから、この場でまったり茶を飲もうなどとは思わないだろう。
「リュンヒン様はこちらに」
景色に見惚れていると執事が隣で言った。
そっちを見ると確かに墓が置いてあった。
白木の墓だ。小さな花束もいくつか供えてある。
「こんなところに人が来るのか」
「ええ。城に住む者は時々訪れるようです」
「だったらもっと通いやすい場所にした方がよかったのではないか?」
そう告げると、執事は微笑んでいるような顔をあの美しい剣山の方へ向けた。
特に何も言わないので俺も同じ方向を見てみる。しかしリュンヒンがこの場所を気に入っていた以外の理由が見つからない。
再び墓の方に目をやり、本当に死んでしまったのかと胸を痛くしていた。
だがふと、墓の刻字に別の名前が刻まれているのが目についたのだ。もちろんリュンヒンの名も刻まれている。
「二人の墓なのか?」
執事は「ええ」と答えた。
「リュンヒン様の奥様であらせられます」
「お、奥様!?」
俺の声は剣山に反響し、遅れて返ってきた。
意図せずデカい声をあげてしまったことを恥ずかしく思い、俺はもう一度通常の声量で「リュンヒンに妻がいたのか?」と問う。
「正しくはリュンヒン様の許嫁でございました。生前お二人があまりにも仲睦まじい様子でしたので、城内で働く者の間では秘密裏に『奥様』とお呼びしていたのです。リュンヒン様も時々ご自身でもそのように呼んでおられました」
その仲睦まじい二人の様子を思い浮かべてか、執事はうっとりとした表情で語った。
しかし俺としては一ミリも聞かされたことの無い新事実であり、そんな大事を口にしなかったリュンヒンを呪いたいくらいである。
「その姫君が亡くなった理由は聞いてもいいのか?」
「もちろんでございます」
執事の神妙な顔を俺は見守った。
「このお方の美しさや気丈なところはもちろんですが、リュンヒン様と通じ合っているという点で、現ベンブルクの国議長であらせられるレッセル様のお目に止まったのです。そしてこのお方は心を痛まれ自害を……」
横取りに遭ったというのか。
それも命を絶つぐらいだ。リュンヒンの負い目に遭うような事態だったのだろう。
「……関係を持ったか」
「それは誰にも分かりません。リュンヒン様にだけは本当のことを打ち明けていたかもしれませんね」
辛い話の最後には執事は明るい表情で言うのである。
それだけこの二人の絆が本物であり深かったという証言だ。
「そうか。それなら少し嬉しい」
死人を呪うのはやめておくことにする。
この場所はリュンヒンの許嫁が好きでよく訪れる場所だったらしい。
日陰である暗い場所から見ると山の景色がより美しいのだと許嫁は周りに教えたそうだ。
確かに。色味がくっきりとし、森の緑や山肌と空の青色が際立っていて美しかった。
土を踏む足音に気付いて俺も執事も後ろを振り返った。
「これはこれは、ジギルス様」
執事は後ろに控えた。
リュンヒン捜索の前に関所で出会った門番兵士である。この墓に花を手向けに来たのかと思えば、あろうことか俺にむけてきたのは銃口だ。
執事の息を呑む音だけが聞こえる。
「真実をお話し下さい」
爽やかな風が吹き抜ける時、その兵士は俺に静かな声でこう言った。
兵士は銃の引き金に指をかけている。いつでも俺の顔面に弾丸を発射できるだろう。
「真実というのは何のことだか。説明も無しでは分からんのだが」
俺は冷静に答える。
俺と同じく兵士の方も冷静だ。特段取り乱しているというわけでは無いために、この経緯を話してくれる。
「ある一部が信じる噂です。リュンヒン様を殺めたのはバル殿、あなたであると世間は騒ついているのをご存知でしょう。それが真実であるならば……」
銃口は俺の顔面から離れて、兵士のこめかみに当てられた。
「あなたがリュンヒン様のところへ行く許可を出したのは私です」
「ジ、ジギルス様。どうかお止めになってください」
「どうなのです。レイヴン・バル殿」
俺と兵士は見つめあっていた。
山の方では大型の鳥が天空を旋回し、森の全土に聞かせるように美しい鳴き声を上げている。
俺もその声に呼ばれたみたいにそっちを見た。
上からでは崖の下に広がる森の内部までは見ることは出来ん。それなのに俺の脳裏には、血痕が残る雑木林の光景が映るし、リュンヒンを担いだ重く生ぬるい感覚も拭えないでいる。
「……リュンヒンはお前のことをえらく褒めていた。良心のある男であると。ちゃんと名前を覚えておけと言われたのだ」
大型の鳥はどこかへ飛んで帰ってこなくなった。
再び兵士の方に視線を戻し、その頬に伝う一筋の水を一瞥する。
「ここでお前も死んだら俺もリュンヒンも悲しい。悲しいことはもう今回ばかりでたくさんだ。お前もそうだろう。ジギルス」
俺はリュンヒンとその許嫁の墓の前でそっと胸を当て、これまでの苦労と苦痛を労い、祈った。
もしも生まれ変わるなら次は必ず幸せに結ばれてくれと願っている。
「神なんか信じないくせに」
リュンヒンが言う。
これからもずっとこんな声が聞こえてきそうだと思うと、俺は少し苦笑した。
「ではまた気が向いたら来る」
ひるがえして去ろうとすると、ジギルスはまだその場に立っていた。しかし拳銃と頬の水はもう仕舞ったようである。
「ロンドへ参ると小耳に挟みました。そこへはベンブルクを通りますし、何よりロンドは治安が定まっていない危険な地です。私がリュンヒン様に代わってあなたを護衛させて下さい」
見守っていた執事がひょこひょこと出てきた。
「ジギルス殿は騎兵隊隊長であらせられます」
「騎兵隊か。心強いな。では頼む」
ジギルスの前を通り過ぎ、小道から庭へと帰還した。
日向の庭から振り向いて様子を見てみると、建物の隙間でジギルスは俺の方を見ており、敬礼の姿勢を崩さず立っていた。
(((スピンオフ短編小説もございます。
(((ご興味がありましたら、
(((下部作者マイページからご覧下さい。
(((全4部/短編小説/完結済み
元居た城より広いメルチ城の敷地を案内された。生活するのに欠かせない主要な部屋を巡ったが覚え切れるわけがないし、かなりの時間がかかった。
千年大国のかの昔からある古い城である。当時は多くの貴族らが集まって暮らしていたのだろうが今は王族一人。
そのうちこんな膨大な部屋数で暮らす世の中ではなくなるような気がしてならない。
「リュンヒン様の葬儀のこと、何から何まで本当にありがとうございました」
そのように俺に言うのはリュンヒンの執事である。歳のせいで背中が丸くなり歩くのも亀の歩みであった。
執事は「国よりも長生きして見せますよ」と可笑しなことを言うが、不思議と応援してやりたくなるような愛嬌のあるじじいだ。
俺と執事は二十個もの部屋と四つの庭をまわり終えた。
そして最後に、リュンヒンの墓が城にもあると言うのでそこへ向かっている。
国葬後は王家代々が眠る丘に葬られたはずであるが、どういうわけだか墓が二つあるらしい。
「こちらです。足元にお気をつけください」
そう言いながらも頼りない足取りなのは執事の方だ。
しかもこれから進もうとする道は、広大な庭から建物の隙間を入っていく小道よりも路地に近いような道である。
人が歩くことを想定されていないために土の地面はガタガタだ。
仕舞い忘れのジョウロなどが転がされており、雨水が溜まった中に藻が生えていた。
執事がよろけているので俺は咄嗟にその丸い背を支えた。
「ありがとうございます」
「ゆっくり進んでくれ」
「ありがとうございます」
全く同じニュアンスで言ってペコペコと頭を下げられた。
狭い道を通り、建物の壁を突き抜けると小さくまとまった裏庭に出た。
木柵が覆っているがそのすぐ下は崖であり、正面は開けてあるから森を上から見下ろせ、遠くに連なる剣山が美しい。
しかし裏庭全域が建物の影になっているから、この場でまったり茶を飲もうなどとは思わないだろう。
「リュンヒン様はこちらに」
景色に見惚れていると執事が隣で言った。
そっちを見ると確かに墓が置いてあった。
白木の墓だ。小さな花束もいくつか供えてある。
「こんなところに人が来るのか」
「ええ。城に住む者は時々訪れるようです」
「だったらもっと通いやすい場所にした方がよかったのではないか?」
そう告げると、執事は微笑んでいるような顔をあの美しい剣山の方へ向けた。
特に何も言わないので俺も同じ方向を見てみる。しかしリュンヒンがこの場所を気に入っていた以外の理由が見つからない。
再び墓の方に目をやり、本当に死んでしまったのかと胸を痛くしていた。
だがふと、墓の刻字に別の名前が刻まれているのが目についたのだ。もちろんリュンヒンの名も刻まれている。
「二人の墓なのか?」
執事は「ええ」と答えた。
「リュンヒン様の奥様であらせられます」
「お、奥様!?」
俺の声は剣山に反響し、遅れて返ってきた。
意図せずデカい声をあげてしまったことを恥ずかしく思い、俺はもう一度通常の声量で「リュンヒンに妻がいたのか?」と問う。
「正しくはリュンヒン様の許嫁でございました。生前お二人があまりにも仲睦まじい様子でしたので、城内で働く者の間では秘密裏に『奥様』とお呼びしていたのです。リュンヒン様も時々ご自身でもそのように呼んでおられました」
その仲睦まじい二人の様子を思い浮かべてか、執事はうっとりとした表情で語った。
しかし俺としては一ミリも聞かされたことの無い新事実であり、そんな大事を口にしなかったリュンヒンを呪いたいくらいである。
「その姫君が亡くなった理由は聞いてもいいのか?」
「もちろんでございます」
執事の神妙な顔を俺は見守った。
「このお方の美しさや気丈なところはもちろんですが、リュンヒン様と通じ合っているという点で、現ベンブルクの国議長であらせられるレッセル様のお目に止まったのです。そしてこのお方は心を痛まれ自害を……」
横取りに遭ったというのか。
それも命を絶つぐらいだ。リュンヒンの負い目に遭うような事態だったのだろう。
「……関係を持ったか」
「それは誰にも分かりません。リュンヒン様にだけは本当のことを打ち明けていたかもしれませんね」
辛い話の最後には執事は明るい表情で言うのである。
それだけこの二人の絆が本物であり深かったという証言だ。
「そうか。それなら少し嬉しい」
死人を呪うのはやめておくことにする。
この場所はリュンヒンの許嫁が好きでよく訪れる場所だったらしい。
日陰である暗い場所から見ると山の景色がより美しいのだと許嫁は周りに教えたそうだ。
確かに。色味がくっきりとし、森の緑や山肌と空の青色が際立っていて美しかった。
土を踏む足音に気付いて俺も執事も後ろを振り返った。
「これはこれは、ジギルス様」
執事は後ろに控えた。
リュンヒン捜索の前に関所で出会った門番兵士である。この墓に花を手向けに来たのかと思えば、あろうことか俺にむけてきたのは銃口だ。
執事の息を呑む音だけが聞こえる。
「真実をお話し下さい」
爽やかな風が吹き抜ける時、その兵士は俺に静かな声でこう言った。
兵士は銃の引き金に指をかけている。いつでも俺の顔面に弾丸を発射できるだろう。
「真実というのは何のことだか。説明も無しでは分からんのだが」
俺は冷静に答える。
俺と同じく兵士の方も冷静だ。特段取り乱しているというわけでは無いために、この経緯を話してくれる。
「ある一部が信じる噂です。リュンヒン様を殺めたのはバル殿、あなたであると世間は騒ついているのをご存知でしょう。それが真実であるならば……」
銃口は俺の顔面から離れて、兵士のこめかみに当てられた。
「あなたがリュンヒン様のところへ行く許可を出したのは私です」
「ジ、ジギルス様。どうかお止めになってください」
「どうなのです。レイヴン・バル殿」
俺と兵士は見つめあっていた。
山の方では大型の鳥が天空を旋回し、森の全土に聞かせるように美しい鳴き声を上げている。
俺もその声に呼ばれたみたいにそっちを見た。
上からでは崖の下に広がる森の内部までは見ることは出来ん。それなのに俺の脳裏には、血痕が残る雑木林の光景が映るし、リュンヒンを担いだ重く生ぬるい感覚も拭えないでいる。
「……リュンヒンはお前のことをえらく褒めていた。良心のある男であると。ちゃんと名前を覚えておけと言われたのだ」
大型の鳥はどこかへ飛んで帰ってこなくなった。
再び兵士の方に視線を戻し、その頬に伝う一筋の水を一瞥する。
「ここでお前も死んだら俺もリュンヒンも悲しい。悲しいことはもう今回ばかりでたくさんだ。お前もそうだろう。ジギルス」
俺はリュンヒンとその許嫁の墓の前でそっと胸を当て、これまでの苦労と苦痛を労い、祈った。
もしも生まれ変わるなら次は必ず幸せに結ばれてくれと願っている。
「神なんか信じないくせに」
リュンヒンが言う。
これからもずっとこんな声が聞こえてきそうだと思うと、俺は少し苦笑した。
「ではまた気が向いたら来る」
ひるがえして去ろうとすると、ジギルスはまだその場に立っていた。しかし拳銃と頬の水はもう仕舞ったようである。
「ロンドへ参ると小耳に挟みました。そこへはベンブルクを通りますし、何よりロンドは治安が定まっていない危険な地です。私がリュンヒン様に代わってあなたを護衛させて下さい」
見守っていた執事がひょこひょこと出てきた。
「ジギルス殿は騎兵隊隊長であらせられます」
「騎兵隊か。心強いな。では頼む」
ジギルスの前を通り過ぎ、小道から庭へと帰還した。
日向の庭から振り向いて様子を見てみると、建物の隙間でジギルスは俺の方を見ており、敬礼の姿勢を崩さず立っていた。
0
お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?
gacchi
恋愛
13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。
そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて
「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」
もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?
3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。
4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。
1章が書籍になりました。

元侯爵令嬢は冷遇を満喫する
cyaru
恋愛
第三王子の不貞による婚約解消で王様に拝み倒され、渋々嫁いだ侯爵令嬢のエレイン。
しかし教会で結婚式を挙げた後、夫の口から開口一番に出た言葉は
「王命だから君を娶っただけだ。愛してもらえるとは思わないでくれ」
夫となったパトリックの側には長年の恋人であるリリシア。
自分もだけど、向こうだってわたくしの事は見たくも無いはず!っと早々の別居宣言。
お互いで交わす契約書にほっとするパトリックとエレイン。ほくそ笑む愛人リリシア。
本宅からは屋根すら見えない別邸に引きこもりお1人様生活を満喫する予定が・・。
※専門用語は出来るだけ注釈をつけますが、作者が専門用語だと思ってない専門用語がある場合があります
※作者都合のご都合主義です。
※リアルで似たようなものが出てくると思いますが気のせいです。
※架空のお話です。現実世界の話ではありません。
※爵位や言葉使いなど現実世界、他の作者さんの作品とは異なります(似てるモノ、同じものもあります)
※誤字脱字結構多い作者です(ごめんなさい)コメント欄より教えて頂けると非常に助かります。
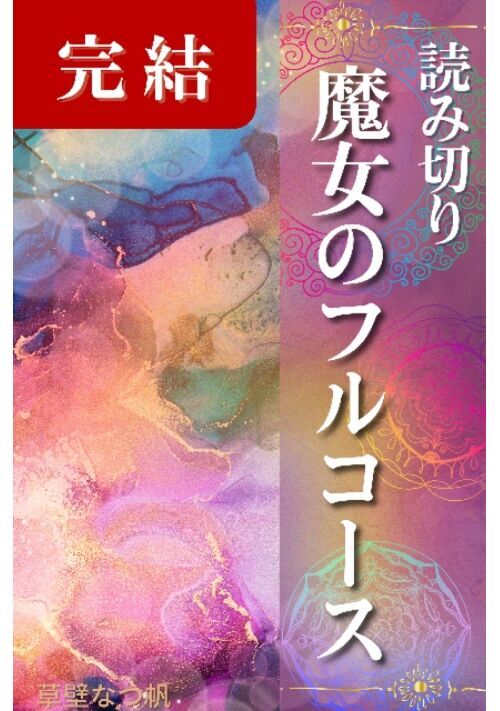
魔女のフルコース【読み切り•創作神話】
草壁なつ帆
ファンタジー
光る石を辿ればとあるレストランに辿り着く。注文は何でも揃えられるというシェフ『ミザリー』の店だ。摩訶不思議な料理を味わいたくば、厨房の方もぜひ覗きにいらしてください。きっとシェフも喜びますから……。
(((小説家になろうとアルファポリスで投稿しています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

【取り下げ予定】愛されない妃ですので。
ごろごろみかん。
恋愛
王妃になんて、望んでなったわけではない。
国王夫妻のリュシアンとミレーゼの関係は冷えきっていた。
「僕はきみを愛していない」
はっきりそう告げた彼は、ミレーゼ以外の女性を抱き、愛を囁いた。
『お飾り王妃』の名を戴くミレーゼだが、ある日彼女は側妃たちの諍いに巻き込まれ、命を落としてしまう。
(ああ、私の人生ってなんだったんだろう──?)
そう思って人生に終止符を打ったミレーゼだったが、気がつくと結婚前に戻っていた。
しかも、別の人間になっている?
なぜか見知らぬ伯爵令嬢になってしまったミレーゼだが、彼女は決意する。新たな人生、今度はリュシアンに関わることなく、平凡で優しい幸せを掴もう、と。
*年齢制限を18→15に変更しました。

貴方が側妃を望んだのです
cyaru
恋愛
「君はそれでいいのか」王太子ハロルドは言った。
「えぇ。勿論ですわ」婚約者の公爵令嬢フランセアは答えた。
誠の愛に気がついたと言われたフランセアは微笑んで答えた。
※2022年6月12日。一部書き足しました。
※架空のお話です。現実世界の話ではありません。
史実などに基づいたものではない事をご理解ください。
※話の都合上、残酷な描写がありますがそれがざまぁなのかは受け取り方は人それぞれです。
表現的にどうかと思う回は冒頭に注意喚起を書き込むようにしますが有無は作者の判断です。
※更新していくうえでタグは幾つか増えます。
※作者都合のご都合主義です。
※リアルで似たようなものが出てくると思いますが気のせいです。
※爵位や言葉使いなど現実世界、他の作者さんの作品とは異なります(似てるモノ、同じものもあります)
※誤字脱字結構多い作者です(ごめんなさい)コメント欄より教えて頂けると非常に助かります。

挙式後すぐに離婚届を手渡された私は、この結婚は予め捨てられることが確定していた事実を知らされました
結城芙由奈@12/27電子書籍配信
恋愛
【結婚した日に、「君にこれを預けておく」と離婚届を手渡されました】
今日、私は子供の頃からずっと大好きだった人と結婚した。しかし、式の後に絶望的な事を彼に言われた。
「ごめん、本当は君とは結婚したくなかったんだ。これを預けておくから、その気になったら提出してくれ」
そう言って手渡されたのは何と離婚届けだった。
そしてどこまでも冷たい態度の夫の行動に傷つけられていく私。
けれどその裏には私の知らない、ある深い事情が隠されていた。
その真意を知った時、私は―。
※暫く鬱展開が続きます
※他サイトでも投稿中

【完結】辺境伯令嬢は新聞で婚約破棄を知った
五色ひわ
恋愛
辺境伯令嬢としてのんびり領地で暮らしてきたアメリアは、カフェで見せられた新聞で自身の婚約破棄を知った。真実を確かめるため、アメリアは3年ぶりに王都へと旅立った。
※本編34話、番外編『皇太子殿下の苦悩』31+1話、おまけ4話

幼妻は、白い結婚を解消して国王陛下に溺愛される。
秋月乃衣
恋愛
旧題:幼妻の白い結婚
13歳のエリーゼは、侯爵家嫡男のアランの元へ嫁ぐが、幼いエリーゼに夫は見向きもせずに初夜すら愛人と過ごす。
歩み寄りは一切なく月日が流れ、夫婦仲は冷え切ったまま、相変わらず夫は愛人に夢中だった。
そしてエリーゼは大人へと成長していく。
※近いうちに婚約期間の様子や、結婚後の事も書く予定です。
小説家になろう様にも掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















