11 / 15
十一話 救い
しおりを挟む
太陽ちゃんは僕たちと昼ご飯を食べると、とくにこれといった会話はせず、パパとママにバレるとか言って、すぐに帰ってしまった。
食器を洗い終わった僕たちは、また無言の時間を日が暮れるまで続ける。
大変暇だから、改めて昔のことを思い出すことにした。
まあ思い出そうとしなくてもいつも自然に思い出しちゃうんだけど。
僕が小学校四年生のときだった。
まだクズな両親が息をしていたときだ。
彼らにとっての虐待に対する罪滅ぼしか知らないけど、街にある大型のショッピングモールに時々連れて行ってくれることがあった。
お母さんが連れて行ってくれるときは土曜日で、お父さんが連れて行ってくれるときは日曜日だった。
あの人たちは共働きをしていて、休みがそれぞれ土曜日、日曜日だったからだ。
昔、僕が住んでいたボロい一軒家はバックが全部木で、ジャングルみたいなところだった。
当然コンビニだとかスーパー、もちろんショッピングモールもかなり遠くに位置していた。
子供が行けるとしてもせいぜいスーパーまでだったと思う。
そんなド田舎だったから、ショッピングモールに連れて行ってもらえるというのは僕にとって、大変うれしいことだった。
ショッピングモールにはおいしそうな食べ物や飲み物があるし、いろんな服屋やたくさんの本、ゲーム、文房具、目を引くものは数えきれないほどあった。
それらを買ってもらうことはほとんどなかったけど。
よく晴れた、ある土曜日のことだ。
数ヶ月ぶりにお母さんがショッピングモール行こうと言った。
僕はテンションが上がり、急いで長袖のシャツと長ズボンに着替えた。
傷が見えるから。
そして、その行きで出会ったのが太陽ちゃんと太陽ちゃんのお父さんだった。
僕は、お母さんにお兄さんがいることを知らなかった。
親しげに話す二人を見て、とても不思議に思った。
僕の知るお母さんはいつも怒っていて、お父さんと言い争いになることが多いからだ。
ただ太陽ちゃんのお父さんは声が落ち着いていて、優しそうだと思った。
二人の性格は全然違うのかもしれない。
太陽ちゃんは長くてきれいな黒髪が特徴的で、スタイルが良く、一言で言えばかわいいと思った。
僕の初めての一目惚れだった。
それから、数分話した僕のお母さんと太陽ちゃんのお父さんは、ショッピングモール内の喫茶店に行こうかという話になったようだった。
もちろん僕と太陽ちゃんも同行する。
だけど、お母さんと太陽ちゃんのお父さんが話す中、連れてこられた僕たち二人は当然暇だった。
身長のせいで足のつかない椅子の上で、両足をブラブラさせたり、店員に運ばれてきたホットココアとにらめっこしたり。
「ねー。」
正面から聞こえた声に僕は顔を上げた。
太陽ちゃんがじっと僕を見ている。
「…何?」
「われとお外行かない?」
「お外?」
太陽ちゃんが大きくうなづいた。
「外行くの?」
横からも声が聞こえる。
お母さんが話に入り込んできた。
表情を見ると、怒ってはなさそうに見える。
「…行ってくる。」
僕は立ち上がって、太陽ちゃんに目配せすると、二人そろって喫茶店を出た。
それから、ショッピングモールとおさらばした僕たちが向かったのは、隣にある神社だった。
公園もないし、ショッピングモールの周りはスーパー銭湯とかガソリンスタンドとかしかないからだ。
薄汚れた鳥居をくぐると、苔まみれになった階段が二十段くらいある。
神様のところへ簡単には行かせないぞというお示しなのか。
「待って!」
後ろから太陽ちゃんの声が聞こえた。
「はあ…はあ…。」
どうやら早く歩きすぎたようだ。
小四男子と小一女子なんだから、もっと考えてあげればよかった。
「ごめんね。」
五段ほど下りて、右手を差し出す。
「ううん!」
太陽ちゃんが僕の手をぎゅっと掴んだ。
僕はなんだか少し心拍数が上がった気がする。
そして、手を繋いだまま頂上を目指した。
「スズキくんってさ…。」
太陽ちゃんが僕の名前を呼んだ。
なんかうれしくなる。
「…うん。」
その次の言葉さえ聞かなければ。
「ママと仲良いの?」
さっきより冷たい風が吹いた。
「えっと…。」
周りの樹木たちも僕の答えを待ってる。
僕だって答えられるものなら答えたい。
でも、小学校に入ったばかりの女の子に僕は虐待されてるんだと正直に言って何になる?
僕は笑って言った。
「仲良いよ。」
大丈夫。
こんな小さい子にバレるわけない。
上手く言えたと思った。
「嘘つかなくていいんだよ。」
「え…?」
太陽ちゃんは僕の目をまっすぐ見つめている。
心臓がビクンと跳ねた気がした。
知ってる。
僕は演技が下手だ。
初めて会った人にも嘘がバレてしまうくらいに。
それともこの子が鋭くて、賢いだけかもしれないけど。
誰かに気づいてほしいと思っていた。
助けてほしいと思っていた。
だけど、僕だけが我慢すれば済むこととも思っていた。
見返りやメリットなんて出せない。
それでも。
僕は握っていた手を離した。
同じところに立ち止まったままでいると、息がしづらい。
窒素死してしまいそうだ。
階段を一人で上りきった。
「スズキ…くん?」
目の前には石畳。
その先には古びた寺。
僕は後ろを振り返って、太陽ちゃんを見た。
今から口に出してしまう。
僕がずっと認められなかったことを。
「僕はお父さんとお母さんに嫌われてるんだ…。」
目から涙がこぼれ落ち、頬を伝うのが分かる。
なんだこれ。僕、恥ずかし。
くすぐったくて、右手でぬぐった。
「毎日殴られっ……。」
息がつっかえた。
「僕はっ……必要のない子供だって……。」
視界はグニャグニャで何も見えない。
人の顔が見えなくなるのは怖い。
太陽ちゃんの足音が聞こえてくる。
いつも人の顔色を窺わないと、嫌われちゃうから。
叩かれるし、蹴られるから。
優しく、そっと抱きしめられた。
「大丈夫だよ。もう頑張らなくていいよ。」
温かい。
人のことをそう感じたのは初めてで。
僕は、ずっと誰かにその言葉を言われたいと思っていたんだ。
食器を洗い終わった僕たちは、また無言の時間を日が暮れるまで続ける。
大変暇だから、改めて昔のことを思い出すことにした。
まあ思い出そうとしなくてもいつも自然に思い出しちゃうんだけど。
僕が小学校四年生のときだった。
まだクズな両親が息をしていたときだ。
彼らにとっての虐待に対する罪滅ぼしか知らないけど、街にある大型のショッピングモールに時々連れて行ってくれることがあった。
お母さんが連れて行ってくれるときは土曜日で、お父さんが連れて行ってくれるときは日曜日だった。
あの人たちは共働きをしていて、休みがそれぞれ土曜日、日曜日だったからだ。
昔、僕が住んでいたボロい一軒家はバックが全部木で、ジャングルみたいなところだった。
当然コンビニだとかスーパー、もちろんショッピングモールもかなり遠くに位置していた。
子供が行けるとしてもせいぜいスーパーまでだったと思う。
そんなド田舎だったから、ショッピングモールに連れて行ってもらえるというのは僕にとって、大変うれしいことだった。
ショッピングモールにはおいしそうな食べ物や飲み物があるし、いろんな服屋やたくさんの本、ゲーム、文房具、目を引くものは数えきれないほどあった。
それらを買ってもらうことはほとんどなかったけど。
よく晴れた、ある土曜日のことだ。
数ヶ月ぶりにお母さんがショッピングモール行こうと言った。
僕はテンションが上がり、急いで長袖のシャツと長ズボンに着替えた。
傷が見えるから。
そして、その行きで出会ったのが太陽ちゃんと太陽ちゃんのお父さんだった。
僕は、お母さんにお兄さんがいることを知らなかった。
親しげに話す二人を見て、とても不思議に思った。
僕の知るお母さんはいつも怒っていて、お父さんと言い争いになることが多いからだ。
ただ太陽ちゃんのお父さんは声が落ち着いていて、優しそうだと思った。
二人の性格は全然違うのかもしれない。
太陽ちゃんは長くてきれいな黒髪が特徴的で、スタイルが良く、一言で言えばかわいいと思った。
僕の初めての一目惚れだった。
それから、数分話した僕のお母さんと太陽ちゃんのお父さんは、ショッピングモール内の喫茶店に行こうかという話になったようだった。
もちろん僕と太陽ちゃんも同行する。
だけど、お母さんと太陽ちゃんのお父さんが話す中、連れてこられた僕たち二人は当然暇だった。
身長のせいで足のつかない椅子の上で、両足をブラブラさせたり、店員に運ばれてきたホットココアとにらめっこしたり。
「ねー。」
正面から聞こえた声に僕は顔を上げた。
太陽ちゃんがじっと僕を見ている。
「…何?」
「われとお外行かない?」
「お外?」
太陽ちゃんが大きくうなづいた。
「外行くの?」
横からも声が聞こえる。
お母さんが話に入り込んできた。
表情を見ると、怒ってはなさそうに見える。
「…行ってくる。」
僕は立ち上がって、太陽ちゃんに目配せすると、二人そろって喫茶店を出た。
それから、ショッピングモールとおさらばした僕たちが向かったのは、隣にある神社だった。
公園もないし、ショッピングモールの周りはスーパー銭湯とかガソリンスタンドとかしかないからだ。
薄汚れた鳥居をくぐると、苔まみれになった階段が二十段くらいある。
神様のところへ簡単には行かせないぞというお示しなのか。
「待って!」
後ろから太陽ちゃんの声が聞こえた。
「はあ…はあ…。」
どうやら早く歩きすぎたようだ。
小四男子と小一女子なんだから、もっと考えてあげればよかった。
「ごめんね。」
五段ほど下りて、右手を差し出す。
「ううん!」
太陽ちゃんが僕の手をぎゅっと掴んだ。
僕はなんだか少し心拍数が上がった気がする。
そして、手を繋いだまま頂上を目指した。
「スズキくんってさ…。」
太陽ちゃんが僕の名前を呼んだ。
なんかうれしくなる。
「…うん。」
その次の言葉さえ聞かなければ。
「ママと仲良いの?」
さっきより冷たい風が吹いた。
「えっと…。」
周りの樹木たちも僕の答えを待ってる。
僕だって答えられるものなら答えたい。
でも、小学校に入ったばかりの女の子に僕は虐待されてるんだと正直に言って何になる?
僕は笑って言った。
「仲良いよ。」
大丈夫。
こんな小さい子にバレるわけない。
上手く言えたと思った。
「嘘つかなくていいんだよ。」
「え…?」
太陽ちゃんは僕の目をまっすぐ見つめている。
心臓がビクンと跳ねた気がした。
知ってる。
僕は演技が下手だ。
初めて会った人にも嘘がバレてしまうくらいに。
それともこの子が鋭くて、賢いだけかもしれないけど。
誰かに気づいてほしいと思っていた。
助けてほしいと思っていた。
だけど、僕だけが我慢すれば済むこととも思っていた。
見返りやメリットなんて出せない。
それでも。
僕は握っていた手を離した。
同じところに立ち止まったままでいると、息がしづらい。
窒素死してしまいそうだ。
階段を一人で上りきった。
「スズキ…くん?」
目の前には石畳。
その先には古びた寺。
僕は後ろを振り返って、太陽ちゃんを見た。
今から口に出してしまう。
僕がずっと認められなかったことを。
「僕はお父さんとお母さんに嫌われてるんだ…。」
目から涙がこぼれ落ち、頬を伝うのが分かる。
なんだこれ。僕、恥ずかし。
くすぐったくて、右手でぬぐった。
「毎日殴られっ……。」
息がつっかえた。
「僕はっ……必要のない子供だって……。」
視界はグニャグニャで何も見えない。
人の顔が見えなくなるのは怖い。
太陽ちゃんの足音が聞こえてくる。
いつも人の顔色を窺わないと、嫌われちゃうから。
叩かれるし、蹴られるから。
優しく、そっと抱きしめられた。
「大丈夫だよ。もう頑張らなくていいよ。」
温かい。
人のことをそう感じたのは初めてで。
僕は、ずっと誰かにその言葉を言われたいと思っていたんだ。
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る





JOLENEジョリーン・鬼屋は人を許さない 『こわい』です。気を緩めると巻き込まれます。
尾駮アスマ(オブチアスマ おぶちあすま)
ホラー
ホラー・ミステリー+ファンタジー作品です。残酷描写ありです。苦手な方は御注意ください。
完全フィクション作品です。
実在する個人・団体等とは一切関係ありません。
あらすじ
趣味で怪談を集めていた主人公は、ある取材で怪しい物件での出来事を知る。
そして、その建物について探り始める。
あぁそうさ下らねぇ文章で何が小説だ的なダラダラした展開が
要所要所の事件の連続で主人公は性格が変わって行くわ
だんだーん強くうぅううー・・・大変なことになりすすぅーあうあうっうー
めちゃくちゃなラストに向かって、是非よんでくだせぇ・・・・え、あうあう
読みやすいように、わざと行間を開けて執筆しています。
もしよければお気に入り登録・イイネ・感想など、よろしくお願いいたします。
大変励みになります。
ありがとうございます。
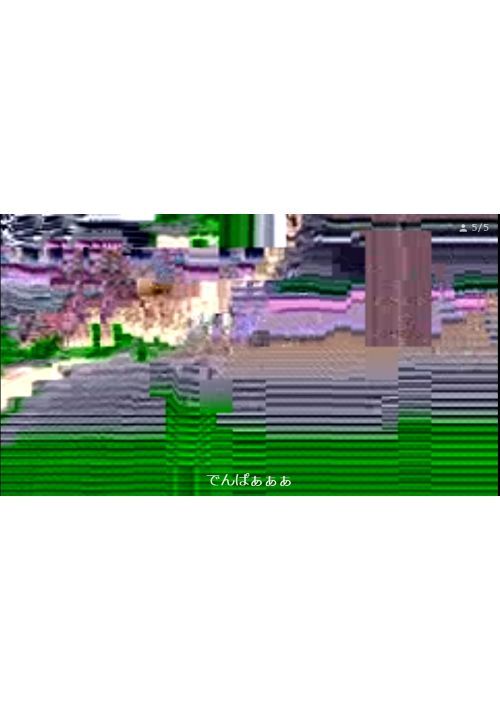

マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子
ちひろ
恋愛
マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子の話。
Fantiaでは他にもえっちなお話を書いてます。よかったら遊びに来てね。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















