140 / 142
シロ
〈4〉
しおりを挟む
二人は並んで歩道に立っていた。朝陽は空を見上げ、シロは両手を制服のポケットにつっこみ、俯いていた。
いつの間にか雨はやんでおり、分厚い雲が切れ、今はその隙間からわずかに星が見えるほどだ。雨の後だからか空気が澄んでいるようで、星の光が宝石のように輝いて見えた。
しばらく空を見上げていた朝陽が、シロに目を移した。
「さっきは思いとどまってくれてありがとう。おかげで事故が起きずに済んだ」
そう言うとシロがふんと鼻を鳴らした。
朝陽は背後にある公園の方を振り返る。公園を挟んだ向こう側にあるコンビニエンスストアから漏れ出る白い光が見えた。
(よく仕事の合間に、あのコンビニエンスストアで夕食を買って公園内で食べたものだな)
そう昔のことを思い出して朝陽は懐かしそうにその公園を眺めた。
気づけばシロもその公園の方を眺めていた。まるでエメラルドをはめ込んだようなその瞳からは彼が何を考えているかよく分からなかったが、朝陽にはその瞳がどこか哀愁を帯びているような気がしてならなかった。
「シロ」
そう声をかけるとちらりとシロが朝陽のことを見た。
「……なんだよ」
すっかり素に戻ってそっけない口調で話すシロのことを見ながら朝陽が再び口を開いた。
「事故が起きた当時のお前の苦しみはよく分かったよ。……大変だったな」
シロが疲れたように下を見て笑う。
「……ふん。安っぽい同情だな」
そう言って足下にあった小石を蹴っ飛ばした。その小石はころころ転がっていき、排水溝の隙間から下にことんと落ちた。それを目で追ってから朝陽がシロに視線を戻した。
「……あーあ、無駄にエネルギー使っちまった。あんたが俺の誘いを受けるまであそこから出さないつもりだったのにさ」
シロが制帽を深く被り、自嘲するように笑う。
「……あんなことしても、過去は何も変わらないのにな」
そう沈んだ声で言うシロに朝陽が口を開いた。
「そのことなんだが……。シロ、お前の前の運転手の『朝陽』は死んでなんかいない」
朝陽の言葉にシロが目を見開いた。そして次の瞬間、朝陽の胸ぐらをつかんだ。
「お前、どこで『朝陽』のことを知ったか知らないが、その名前を軽々しく呼ぶんじゃねえ!」
先ほどとは打って変わって頭に血が上ったようなシロの顔を、朝陽が見つめる。
「違う、本当に死んでなんかいないんだ。お前を惑わすためにその場限りの嘘をついているわけじゃない。お前だって俺の名前を知っているだろう。俺がお前の言っている『朝陽』だとは思わなかったのか?」
そう言うも、シロの耳には届いていないようだった。
「黙れ!“俺の”運転手の名前を、これ以上呼んだら轢き殺すぞ!」
そこまで言って、一度息を整える。そして、こちらを見ている朝陽をにらみつけながら再び口を開いた。
「俺はこの目で見たんだ!朝陽が頭から血を流してぐったりしていたところを!『あんな状態で助かる訳がない』って言っていた野次馬どもの声も!全部覚えてるんだよ!」
そのときのことを思い出したのか、シロが顔をゆがめた。
「朝陽は死んだんだ!お前は偽物だ!朝陽のフリをして俺の気持ちを変えようとしているんだ!これ以上あいつを騙るんじゃねえ!」
畳みかけるようにシロは続ける。
「俺は騙されない。俺はあのとき決めたんだ。全ての人間から運転免許を取り上げることを!」
一通り主張を聞き終えてから、朝陽がシロをにらみつけた。
「俺が、そんな簡単に死ぬか!」
そしてシロの胸ぐらをつかみかえす。強い力に少し面食らったのか、朝陽の胸ぐらをつかむシロの手の力が弱くなった。
「シロ!お前は自分の運転手のことが分からないのか!」
シロは様々な感情がいり混じった複雑な顔で朝陽のことを見つめていた。朝陽は荒げた息を整えると、再び口を開いた。
「……覚えているか?俺がお前の運転手になって、二年目くらいの時のことだ」
シロが黙って朝陽を見つめる。
「ある夜、小さな女の子がお母さんと一緒に乗ってきた。そのとき、その子はぬいぐるみを持っていてな、俺にそのぬいぐるみに名前があることを教えてくれた」
シロが聞いていることを確認しながら朝陽は続けた。
「一通り自分の持っているお気に入りのぬいぐるみの話をした後、その子は俺に『この車にも名前はあるの?』と尋ねてきた」
シロは何も言わない。
「俺はどう答えようかと思って迷ってな。そのとき、このタクシーの色を思い出したんだ」
シロの被っている、空に瞬く星のように真っ白な制帽を見て、朝陽は続けた。
「『この車はシロっていうんです。車体が白いから、シロ。いい名前でしょう?』。……俺は、こう答えた。そうだろ?」
最後の言葉でシロは体の力が抜けたようだった。そしてアスファルトに膝から崩れ落ちた。
そんなシロを朝陽は黙って見つめた。
「……そんな、まさか……」
シロが信じられないといったようにうわごとのように呟く。
「俺はずっと、朝陽が死んだって……」
事故に遭い、体も心もぼろぼろだったときに、無理矢理自分に信じ込ませた最愛の運転手が死んだという非情な“事実”。ここに至るまでの数年間、ずっと運転手を救えなかったやるせなさとこんな目に自分を合わせた彼への憎しみだけを糧にして生きてきたというのに、それが違うと突然知らされて、頭がついていかないのは当然のことだった。
朝陽はそんなシロをいたわるように黙って彼のことを見つめていた。
「少しは落ち着いたか?」
シロと共に縁石に腰掛けて、朝陽はシロに話しかけた。シロはちらりと朝陽を見た後、すねたようにそっぽをむいた。
「……あなた、途中から私がかつての担当車だと気づいていたんでしょう」
そう子供っぽくいじけているシロの背中を見て、朝陽は思わず苦笑する。
「まあな。黙っていて悪かった」
朝陽の言葉にシロが苦虫をかみつぶしたような顔をした。
「おかしいと思ったんだ。俺は自分の名前を言っていないはずなのにあんたは俺の名前が『シロ』だと知っていたし、突然なれなれしくしてきたし」
そうぶつぶつと文句をいうシロを見て朝陽が笑った。
「それにしてもお前、本当に俺のことが大好きなんだな。すこし照れくさいよ」
そう言うとシロがキッと朝陽を睨んだ。顔だけでなく耳まで真っ赤になってしまっている。
「別に俺は、あんたのことが好きなわけでも、あんたに再会できて喜んでるわけでもないんだからな」
「はいはい。そういうことは涙拭ってから言えよな」
そう言っていたずらっぽく朝陽が笑う。シロははっとしてから潤んだ目で朝陽をにらみつけた。
ごしごしと涙を拭うシロに朝陽は近づくと、口を開いた。
「シロ。心配かけて悪かったな」
そう言って優しく頭を撫でる。帽子の上から感じる朝陽の手の暖かみが、かつて自分のハンドルを握っていた物と全く同じで、シロはまた涙が出てくるのをこらえるようにぎゅっと唇を噛みしめた。
「……本当ですよ。あんたのせいで、俺は今日までこんなに苦しんで……」
「ああ、そうだな。……すまなかった」
しばらく、朝陽はシロの頭をなで続けていた。シロも特にその手を振り払うこともなく、なされるがままになっていた。
いつの間にか雨はやんでおり、分厚い雲が切れ、今はその隙間からわずかに星が見えるほどだ。雨の後だからか空気が澄んでいるようで、星の光が宝石のように輝いて見えた。
しばらく空を見上げていた朝陽が、シロに目を移した。
「さっきは思いとどまってくれてありがとう。おかげで事故が起きずに済んだ」
そう言うとシロがふんと鼻を鳴らした。
朝陽は背後にある公園の方を振り返る。公園を挟んだ向こう側にあるコンビニエンスストアから漏れ出る白い光が見えた。
(よく仕事の合間に、あのコンビニエンスストアで夕食を買って公園内で食べたものだな)
そう昔のことを思い出して朝陽は懐かしそうにその公園を眺めた。
気づけばシロもその公園の方を眺めていた。まるでエメラルドをはめ込んだようなその瞳からは彼が何を考えているかよく分からなかったが、朝陽にはその瞳がどこか哀愁を帯びているような気がしてならなかった。
「シロ」
そう声をかけるとちらりとシロが朝陽のことを見た。
「……なんだよ」
すっかり素に戻ってそっけない口調で話すシロのことを見ながら朝陽が再び口を開いた。
「事故が起きた当時のお前の苦しみはよく分かったよ。……大変だったな」
シロが疲れたように下を見て笑う。
「……ふん。安っぽい同情だな」
そう言って足下にあった小石を蹴っ飛ばした。その小石はころころ転がっていき、排水溝の隙間から下にことんと落ちた。それを目で追ってから朝陽がシロに視線を戻した。
「……あーあ、無駄にエネルギー使っちまった。あんたが俺の誘いを受けるまであそこから出さないつもりだったのにさ」
シロが制帽を深く被り、自嘲するように笑う。
「……あんなことしても、過去は何も変わらないのにな」
そう沈んだ声で言うシロに朝陽が口を開いた。
「そのことなんだが……。シロ、お前の前の運転手の『朝陽』は死んでなんかいない」
朝陽の言葉にシロが目を見開いた。そして次の瞬間、朝陽の胸ぐらをつかんだ。
「お前、どこで『朝陽』のことを知ったか知らないが、その名前を軽々しく呼ぶんじゃねえ!」
先ほどとは打って変わって頭に血が上ったようなシロの顔を、朝陽が見つめる。
「違う、本当に死んでなんかいないんだ。お前を惑わすためにその場限りの嘘をついているわけじゃない。お前だって俺の名前を知っているだろう。俺がお前の言っている『朝陽』だとは思わなかったのか?」
そう言うも、シロの耳には届いていないようだった。
「黙れ!“俺の”運転手の名前を、これ以上呼んだら轢き殺すぞ!」
そこまで言って、一度息を整える。そして、こちらを見ている朝陽をにらみつけながら再び口を開いた。
「俺はこの目で見たんだ!朝陽が頭から血を流してぐったりしていたところを!『あんな状態で助かる訳がない』って言っていた野次馬どもの声も!全部覚えてるんだよ!」
そのときのことを思い出したのか、シロが顔をゆがめた。
「朝陽は死んだんだ!お前は偽物だ!朝陽のフリをして俺の気持ちを変えようとしているんだ!これ以上あいつを騙るんじゃねえ!」
畳みかけるようにシロは続ける。
「俺は騙されない。俺はあのとき決めたんだ。全ての人間から運転免許を取り上げることを!」
一通り主張を聞き終えてから、朝陽がシロをにらみつけた。
「俺が、そんな簡単に死ぬか!」
そしてシロの胸ぐらをつかみかえす。強い力に少し面食らったのか、朝陽の胸ぐらをつかむシロの手の力が弱くなった。
「シロ!お前は自分の運転手のことが分からないのか!」
シロは様々な感情がいり混じった複雑な顔で朝陽のことを見つめていた。朝陽は荒げた息を整えると、再び口を開いた。
「……覚えているか?俺がお前の運転手になって、二年目くらいの時のことだ」
シロが黙って朝陽を見つめる。
「ある夜、小さな女の子がお母さんと一緒に乗ってきた。そのとき、その子はぬいぐるみを持っていてな、俺にそのぬいぐるみに名前があることを教えてくれた」
シロが聞いていることを確認しながら朝陽は続けた。
「一通り自分の持っているお気に入りのぬいぐるみの話をした後、その子は俺に『この車にも名前はあるの?』と尋ねてきた」
シロは何も言わない。
「俺はどう答えようかと思って迷ってな。そのとき、このタクシーの色を思い出したんだ」
シロの被っている、空に瞬く星のように真っ白な制帽を見て、朝陽は続けた。
「『この車はシロっていうんです。車体が白いから、シロ。いい名前でしょう?』。……俺は、こう答えた。そうだろ?」
最後の言葉でシロは体の力が抜けたようだった。そしてアスファルトに膝から崩れ落ちた。
そんなシロを朝陽は黙って見つめた。
「……そんな、まさか……」
シロが信じられないといったようにうわごとのように呟く。
「俺はずっと、朝陽が死んだって……」
事故に遭い、体も心もぼろぼろだったときに、無理矢理自分に信じ込ませた最愛の運転手が死んだという非情な“事実”。ここに至るまでの数年間、ずっと運転手を救えなかったやるせなさとこんな目に自分を合わせた彼への憎しみだけを糧にして生きてきたというのに、それが違うと突然知らされて、頭がついていかないのは当然のことだった。
朝陽はそんなシロをいたわるように黙って彼のことを見つめていた。
「少しは落ち着いたか?」
シロと共に縁石に腰掛けて、朝陽はシロに話しかけた。シロはちらりと朝陽を見た後、すねたようにそっぽをむいた。
「……あなた、途中から私がかつての担当車だと気づいていたんでしょう」
そう子供っぽくいじけているシロの背中を見て、朝陽は思わず苦笑する。
「まあな。黙っていて悪かった」
朝陽の言葉にシロが苦虫をかみつぶしたような顔をした。
「おかしいと思ったんだ。俺は自分の名前を言っていないはずなのにあんたは俺の名前が『シロ』だと知っていたし、突然なれなれしくしてきたし」
そうぶつぶつと文句をいうシロを見て朝陽が笑った。
「それにしてもお前、本当に俺のことが大好きなんだな。すこし照れくさいよ」
そう言うとシロがキッと朝陽を睨んだ。顔だけでなく耳まで真っ赤になってしまっている。
「別に俺は、あんたのことが好きなわけでも、あんたに再会できて喜んでるわけでもないんだからな」
「はいはい。そういうことは涙拭ってから言えよな」
そう言っていたずらっぽく朝陽が笑う。シロははっとしてから潤んだ目で朝陽をにらみつけた。
ごしごしと涙を拭うシロに朝陽は近づくと、口を開いた。
「シロ。心配かけて悪かったな」
そう言って優しく頭を撫でる。帽子の上から感じる朝陽の手の暖かみが、かつて自分のハンドルを握っていた物と全く同じで、シロはまた涙が出てくるのをこらえるようにぎゅっと唇を噛みしめた。
「……本当ですよ。あんたのせいで、俺は今日までこんなに苦しんで……」
「ああ、そうだな。……すまなかった」
しばらく、朝陽はシロの頭をなで続けていた。シロも特にその手を振り払うこともなく、なされるがままになっていた。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

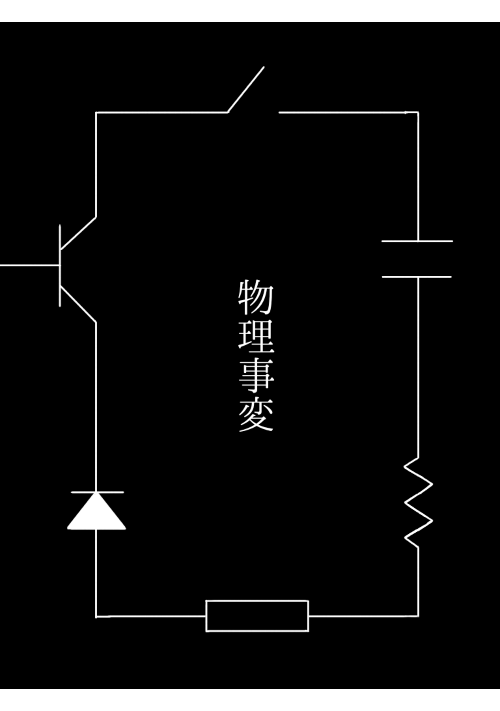
物理事変
シュレディンガーのうさぎ
キャラ文芸
住民たちと協力して、物理の公式を取り戻せ!
とある学校の物理教師が、真空放電管を盗んだ犯人を追いかけているうちに、理科の国の物理地方に入り込んでしまった。そこでは、物理の公式が何者かに次々と消されるという事件が起こっており、このままでは物理という教科自体が消えてしまうという危機に見舞われていた。物理教師は理科の国の王、ボルトに公式を取り戻すよう頼まれ、物理地方の住民たちと協力して公式を取り戻していくうちに、理科の国が抱える問題に巻き込まれていく。
*教科事変シリーズ二作目です。シリーズ物ですが前作の化学事変を知らなくても楽しめます。でも読んでおくともっと楽しめると思います。

百合系サキュバスにモテてしまっていると言う話
釧路太郎
キャラ文芸
名門零楼館高校はもともと女子高であったのだが、様々な要因で共学になって数年が経つ。
文武両道を掲げる零楼館高校はスポーツ分野だけではなく進学実績も全国レベルで見ても上位に食い込んでいるのであった。
そんな零楼館高校の歴史において今まで誰一人として選ばれたことのない“特別指名推薦”に選ばれたのが工藤珠希なのである。
工藤珠希は身長こそ平均を超えていたが、運動や学力はいたって平均クラスであり性格の良さはあるものの特筆すべき才能も無いように見られていた。
むしろ、彼女の幼馴染である工藤太郎は様々な部活の助っ人として活躍し、中学生でありながら様々な競技のプロ団体からスカウトが来るほどであった。更に、学力面においても優秀であり国内のみならず海外への進学も不可能ではないと言われるほどであった。
“特別指名推薦”の話が学校に来た時は誰もが相手を間違えているのではないかと疑ったほどであったが、零楼館高校関係者は工藤珠希で間違いないという。
工藤珠希と工藤太郎は血縁関係はなく、複雑な家庭環境であった工藤太郎が幼いころに両親を亡くしたこともあって彼は工藤家の養子として迎えられていた。
兄妹同然に育った二人ではあったが、お互いが相手の事を守ろうとする良き関係であり、恋人ではないがそれ以上に信頼しあっている。二人の関係性は苗字が同じという事もあって夫婦と揶揄されることも多々あったのだ。
工藤太郎は県外にあるスポーツ名門校からの推薦も来ていてほぼ内定していたのだが、工藤珠希が零楼館高校に入学することを決めたことを受けて彼も零楼館高校を受験することとなった。
スポーツ分野でも名をはせている零楼館高校に工藤太郎が入学すること自体は何の違和感もないのだが、本来入学する予定であった高校関係者は落胆の声をあげていたのだ。だが、彼の出自も相まって彼の意志を否定する者は誰もいなかったのである。
二人が入学する零楼館高校には外に出ていない秘密があるのだ。
零楼館高校に通う生徒のみならず、教員職員運営者の多くがサキュバスでありそのサキュバスも一般的に知られているサキュバスと違い女性を対象とした変異種なのである。
かつては“秘密の花園”と呼ばれた零楼館女子高等学校もそういった意味を持っていたのだった。
ちなみに、工藤珠希は工藤太郎の事を好きなのだが、それは誰にも言えない秘密なのである。
この作品は「小説家になろう」「カクヨム」「ノベルアッププラス」「ノベルバ」「ノベルピア」にも掲載しております。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















