お気に入りに追加
308
あなたにおすすめの小説

二人分働いてたのに、「聖女はもう時代遅れ。これからはヒーラーの時代」と言われてクビにされました。でも、ヒーラーは防御魔法を使えませんよ?
小平ニコ
ファンタジー
「ディーナ。お前には今日で、俺たちのパーティーを抜けてもらう。異論は受け付けない」
勇者ラジアスはそう言い、私をパーティーから追放した。……異論がないわけではなかったが、もうずっと前に僧侶と戦士がパーティーを離脱し、必死になって彼らの抜けた穴を埋めていた私としては、自分から頭を下げてまでパーティーに残りたいとは思わなかった。
ほとんど喧嘩別れのような形で勇者パーティーを脱退した私は、故郷には帰らず、戦闘もこなせる武闘派聖女としての力を活かし、賞金首狩りをして生活費を稼いでいた。
そんなある日のこと。
何気なく見た新聞の一面に、驚くべき記事が載っていた。
『勇者パーティー、またも敗走! 魔王軍四天王の前に、なすすべなし!』
どうやら、私がいなくなった後の勇者パーティーは、うまく機能していないらしい。最新の回復職である『ヒーラー』を仲間に加えるって言ってたから、心配ないと思ってたのに。
……あれ、もしかして『ヒーラー』って、完全に回復に特化した職業で、聖女みたいに、防御の結界を張ることはできないのかしら?
私がその可能性に思い至った頃。
勇者ラジアスもまた、自分の判断が間違っていたことに気がついた。
そして勇者ラジアスは、再び私の前に姿を現したのだった……

悪徳貴族の、イメージ改善、慈善事業
ウィリアム・ブロック
ファンタジー
現代日本から死亡したラスティは貴族に転生する。しかしその世界では貴族はあんまり良く思われていなかった。なのでノブリス・オブリージュを徹底させて、貴族のイメージ改善を目指すのだった。

大器晩成エンチャンター~Sランク冒険者パーティから追放されてしまったが、追放後の成長度合いが凄くて世界最強になる
遠野紫
ファンタジー
「な、なんでだよ……今まで一緒に頑張って来たろ……?」
「頑張って来たのは俺たちだよ……お前はお荷物だ。サザン、お前にはパーティから抜けてもらう」
S級冒険者パーティのエンチャンターであるサザンは或る時、パーティリーダーから追放を言い渡されてしまう。
村の仲良し四人で結成したパーティだったが、サザンだけはなぜか実力が伸びなかったのだ。他のメンバーに追いつくために日々努力を重ねたサザンだったが結局報われることは無く追放されてしまった。
しかしサザンはレアスキル『大器晩成』を持っていたため、ある時突然その強さが解放されたのだった。
とてつもない成長率を手にしたサザンの最強エンチャンターへの道が今始まる。

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~
おとら@ 書籍発売中
ファンタジー
アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。
どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。
そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。
その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。
その結果、様々な女性に迫られることになる。
元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。
「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」
今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。

システムバグで輪廻の輪から外れましたが、便利グッズ詰め合わせ付きで他の星に転生しました。
大国 鹿児
ファンタジー
輪廻転生のシステムのバグで輪廻の輪から外れちゃった!
でも神様から便利なチートグッズ(笑)の詰め合わせをもらって、
他の星に転生しました!特に使命も無いなら自由気ままに生きてみよう!
主人公はチート無双するのか!? それともハーレムか!?
はたまた、壮大なファンタジーが始まるのか!?
いえ、実は単なる趣味全開の主人公です。
色々な秘密がだんだん明らかになりますので、ゆっくりとお楽しみください。
*** 作品について ***
この作品は、真面目なチート物ではありません。
コメディーやギャグ要素やネタの多い作品となっております
重厚な世界観や派手な戦闘描写、ざまあ展開などをお求めの方は、
この作品をスルーして下さい。
*カクヨム様,小説家になろう様でも、別PNで先行して投稿しております。

スライム10,000体討伐から始まるハーレム生活
昼寝部
ファンタジー
この世界は12歳になったら神からスキルを授かることができ、俺も12歳になった時にスキルを授かった。
しかし、俺のスキルは【@&¥#%】と正しく表記されず、役に立たないスキルということが判明した。
そんな中、両親を亡くした俺は妹に不自由のない生活を送ってもらうため、冒険者として活動を始める。
しかし、【@&¥#%】というスキルでは強いモンスターを討伐することができず、3年間冒険者をしてもスライムしか倒せなかった。
そんなある日、俺がスライムを10,000体討伐した瞬間、スキル【@&¥#%】がチートスキルへと変化して……。
これは、ある日突然、最強の冒険者となった主人公が、今まで『スライムしか倒せないゴミ』とバカにしてきた奴らに“ざまぁ”し、美少女たちと幸せな日々を過ごす物語。
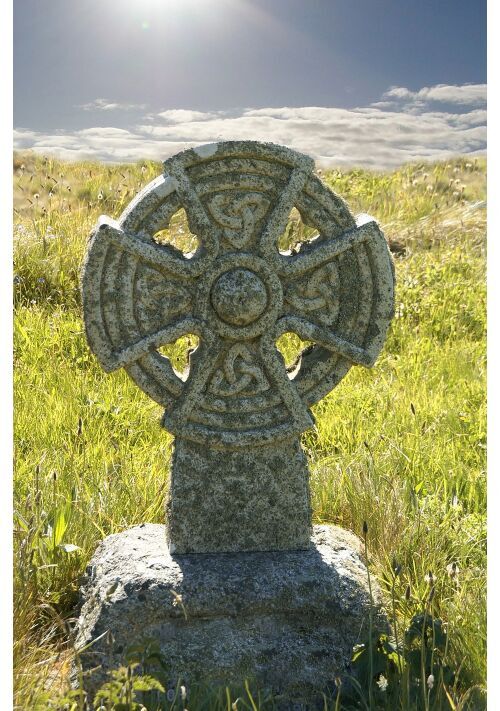
アンバランサー・ユウと世界の均衡 第三部「時の大伽藍」
かつエッグ
ファンタジー
「司るもの」の召命に応え、剣と魔法の世界に転移した篠崎裕一郎は、超絶の能力を持つ存在「アンバランサー」となる。920歳のエルフの大魔導師ルシア先生、その弟子の魔法使いの少女ライラ、魔剣を使う獣人少女ジーナとともに、世界を破滅から救う冒険に旅立つ。
第三部の本編では、150年まえルシア先生に瀕死の傷を負わせた魔獣が復活の胎動をはじめ、世界の「時」が乱れ始めます。「時」をめぐるアンバランサーの冒険をお楽しみください。

【完結】悪役令嬢に転生したけど、王太子妃にならない方が幸せじゃない?
みちこ
ファンタジー
12歳の時に前世の記憶を思い出し、自分が悪役令嬢なのに気が付いた主人公。
ずっと王太子に片思いしていて、将来は王太子妃になることしか頭になかった主人公だけど、前世の記憶を思い出したことで、王太子の何が良かったのか疑問に思うようになる
色々としがらみがある王太子妃になるより、このまま公爵家の娘として暮らす方が幸せだと気が付く
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















