5 / 9
第二章 またネズミが鳴きました
1 小さな訪問者
しおりを挟む
大通りから逸れて、歩道もない裏道に入るとすぐに、板金工場や寂れたスナックの先に三階建てのビルが見えてくる。二階の窓の横には『磯貝プリント株式会社』の看板。
営業車はすべて出払っていて、駐車スペースは広々としていた。僕は奥のブロック塀にできるだけ寄せて駐車した。詰めないとすべての車を停められないのだ。
運転席のドアが開く余裕すらないから、助手席側から降りる。二、三歩進んで足を止めた。
「あ。いけね」
閉めたばかりのドアを開け、紙パックジュースを手に取った。パートの大塚さんから納品の帰りに買ってこいと言われたやつだ。
電話がかかってきたのは客先で成果物を下ろしているときだった。
『石井くん、帰りにオレンジジュースを買ってきて』
給湯室の管理をしているのは庶務だから、大塚さんが飲み物を揃えておくことに不思議はないが、なぜ今まで買ったこともないオレンジジュースなのかわからない。
「1リットルのパックでいいですか?」
『それじゃあ多すぎね。200ミリのストローがついているやつ一つでいいわ』
大塚さんが飲むんですか?と尋ねるより早く「じゃあ石井くん、よろしくね!」と電話を切られたから、結局なんのために買わされたのかわからない。安定の人使いの荒さだ。
大塚さんはパート従業員だが、ほとんどの社員より古株で、社長の息子の専務より勤続年数は長い。そのせいか大塚さんは専務さえもパシリに使う。社員最年少の僕が断れるはずもないのだ。
コンビニに寄ったついでに自分もコーヒーを買ったし、まあいいかと思いつつ、入口の重いガラスドアを押す。
入ってすぐの階段を上ると、二階は仕切りのない事務所フロアが広がっている。一階は作業場、三階は社長や専務のオフィスだ。
磯貝プリント株式会社は、七十代の磯貝社長を筆頭に、家族経営から始まった小さな印刷会社だ。従業員は八十人程度。うち正社員は二十人ちょっとで、あとはパートとバイトの人たちで成り立っている。
事務所を覗いてみたけど大塚さんの姿がない。給湯室にもいない。
「なんだよ、もう」
ジュースは冷蔵庫に入れておけばいいかと足を踏み出そうとした瞬間、声がした。
「動かないで!」
とっさに上げかけた足を戻し、オレンジジュースを持ったまま両手を上げた。
何事かと考える間もなく、背後から僕の足元に手が伸びてきて、足を置くはずだった場所に落ちていたらしき物体を掴みとって引っ込んだ。
色といい大きさといい、それは大福に見えたけど、まさかそんなものが落ちているはずもない。気になるのは落ちていたものより掴みとっていった人の方だ。
振り向いた先には、その大福らしきものを両手で包み込んでいる人がいた。それは見慣れた顔……なのだが。
「えっと……」
なんて声をかけるべきか考えていると、あちらが先に挨拶した。
「お疲れ様です」
「あ、どうも。お疲れ様ですー」
「では、これで失礼します」
「え。あ、はい」
僕はひとり給湯室に取り残された。
え? 今の誰だ? 今村課長……じゃないよな。似てたけど、小さかったし。ものすごく小さかったぞ? それこそ小学生くらいに。
「石井くん戻ってたのね。お疲れ様~」
給湯室の入口に郵便物を抱えた大塚さんが立っていた。
「お疲れ様です。あ、オレンジジュース買ってきましたよ」
「ありがとう。こはるちゃんにあげて」
「こはるちゃん?」
「今村さんの娘さんよ。社長室にいるから」
さっきの子か。今村課長が小さくなっちゃったのかと思ったが、娘だったようだ。それにしても似てる。誰が見ても親子だとわかるくらいそっくりだ。それこそ一瞬本気で今村課長だと思ってしまったくらいに。って、待てよ?
「なんで今村課長のお子さんが会社にいるんですか?」
「今日、小学校が開校記念日でお休みだったらしいのよ。今村さん、今朝それを思い出したらしくて。旦那さんは今週いっぱい出張だし、預けるところもなくて連れてきたんだって」
「休暇は取らなかったんですね」
「私のせいなのよ」
大塚さんは急に声を落とした。
「え? どういうことですか?」
大塚さんはそれには答えず、顔を上げて声を張った。
「とにかく! こはるちゃんをよろしくね。私は、今村さんが定時で上がれるように手伝ってくるわ」
「あ、はい」
大塚さんは早足で事務所の方に去っていった。
勢いに押されて返事をしてしまったが、僕だって小口精算が溜まっているんだけどな。けどまあ仕方ないかと社長室のある三階へと向かった。
社長室に入ってまず目に入るのは、正面の窓際にある低いキャビネットの上に飾られたお城の模型だ。ラップの芯で作った西洋風のお城。以前こはるちゃんが図工の授業で作ったものだが、材料集めに会社の人たちが協力したこともあって、お礼として社長に贈られたのだった。
お城の製作者はメンテナンスでもしているのか、あちこち覗き込んでいる。
「こはるちゃん?」
「はい。今村こはるです」
さっき会ったことなど忘れているような自己紹介をした。それか、僕の顔など見ていなかったのかもしれない。
「あ、どうも。石井祐介です。……いま、ひとり?」
壁際に置かれたデスクにここの主の姿はない。
社長といえども事務所にあるのと同じ型のオフィスデスクを使っている。むしろこちらの方が古いのではないだろうか。側面にはいくつかの凹みと錆の浮いた傷が目立つ。脚がガタつくのか一本だけ折りたたんだ紙をかませているほどだ。
デスクの向かいの壁にはキャビネットが並んでいるが、そちらは粘着テープで補修されている部分がある。磯貝社長は現場の設備は利便性重視で入れ替えるのに、社長室は何十年もそのままだ。
どこもかしこも年季の入っている磯貝プリントだが、社長室は特に昭和感がすごい。デスクの後ろの壁にはレトロな温度計がかかっている。赤い液体が木製の板についた目盛りを指し示すやつだ。ゼンマイ式の壁掛け時計は故障して八時ちょっと過ぎで止まったままで、動いている置き時計はといえば、デジタルっぽい数字が印字されたフリップ時計だ。昔の映画などである駅の案内板がパタパタするあれだ。
時代遅れと言ってしまえばそれまでだけど、僕はこの社長室の雰囲気がなんとなく気に入っている。
「はい。社長さんは作業場に行きました。ここにいていいと言われたのですけど、だめでしたか?」
「いや。社長がいいと言うならいいんだと思うよ」
普段から人の出入りが多い部屋だ。機密性の高いものの保管場所は施錠されているはずだった。
「あ。そうだ。オレンジジュースをどうぞ」
「ありがとうございます。いただきます」
丁寧に両手で戴くように受け取り、頭を下げた。
小学三、四年生といったところだろうか。小学生ってこんなに礼儀正しかっただろうかと戸惑っていると、ドアが開く音がした。
磯貝社長は僕を認めると、厚みのある手をあげた。
「おう。石井ちゃん、おつかれ」
「お疲れ様です。不在のところお邪魔してすみません」
「いいって、いいって。お。こはるちゃん、いいもの飲んでるな」
「はい。石井さんにいただきました」
こはるちゃんが再びお城のチェックを始めたのを見て、僕は社長室を後にした。
営業車はすべて出払っていて、駐車スペースは広々としていた。僕は奥のブロック塀にできるだけ寄せて駐車した。詰めないとすべての車を停められないのだ。
運転席のドアが開く余裕すらないから、助手席側から降りる。二、三歩進んで足を止めた。
「あ。いけね」
閉めたばかりのドアを開け、紙パックジュースを手に取った。パートの大塚さんから納品の帰りに買ってこいと言われたやつだ。
電話がかかってきたのは客先で成果物を下ろしているときだった。
『石井くん、帰りにオレンジジュースを買ってきて』
給湯室の管理をしているのは庶務だから、大塚さんが飲み物を揃えておくことに不思議はないが、なぜ今まで買ったこともないオレンジジュースなのかわからない。
「1リットルのパックでいいですか?」
『それじゃあ多すぎね。200ミリのストローがついているやつ一つでいいわ』
大塚さんが飲むんですか?と尋ねるより早く「じゃあ石井くん、よろしくね!」と電話を切られたから、結局なんのために買わされたのかわからない。安定の人使いの荒さだ。
大塚さんはパート従業員だが、ほとんどの社員より古株で、社長の息子の専務より勤続年数は長い。そのせいか大塚さんは専務さえもパシリに使う。社員最年少の僕が断れるはずもないのだ。
コンビニに寄ったついでに自分もコーヒーを買ったし、まあいいかと思いつつ、入口の重いガラスドアを押す。
入ってすぐの階段を上ると、二階は仕切りのない事務所フロアが広がっている。一階は作業場、三階は社長や専務のオフィスだ。
磯貝プリント株式会社は、七十代の磯貝社長を筆頭に、家族経営から始まった小さな印刷会社だ。従業員は八十人程度。うち正社員は二十人ちょっとで、あとはパートとバイトの人たちで成り立っている。
事務所を覗いてみたけど大塚さんの姿がない。給湯室にもいない。
「なんだよ、もう」
ジュースは冷蔵庫に入れておけばいいかと足を踏み出そうとした瞬間、声がした。
「動かないで!」
とっさに上げかけた足を戻し、オレンジジュースを持ったまま両手を上げた。
何事かと考える間もなく、背後から僕の足元に手が伸びてきて、足を置くはずだった場所に落ちていたらしき物体を掴みとって引っ込んだ。
色といい大きさといい、それは大福に見えたけど、まさかそんなものが落ちているはずもない。気になるのは落ちていたものより掴みとっていった人の方だ。
振り向いた先には、その大福らしきものを両手で包み込んでいる人がいた。それは見慣れた顔……なのだが。
「えっと……」
なんて声をかけるべきか考えていると、あちらが先に挨拶した。
「お疲れ様です」
「あ、どうも。お疲れ様ですー」
「では、これで失礼します」
「え。あ、はい」
僕はひとり給湯室に取り残された。
え? 今の誰だ? 今村課長……じゃないよな。似てたけど、小さかったし。ものすごく小さかったぞ? それこそ小学生くらいに。
「石井くん戻ってたのね。お疲れ様~」
給湯室の入口に郵便物を抱えた大塚さんが立っていた。
「お疲れ様です。あ、オレンジジュース買ってきましたよ」
「ありがとう。こはるちゃんにあげて」
「こはるちゃん?」
「今村さんの娘さんよ。社長室にいるから」
さっきの子か。今村課長が小さくなっちゃったのかと思ったが、娘だったようだ。それにしても似てる。誰が見ても親子だとわかるくらいそっくりだ。それこそ一瞬本気で今村課長だと思ってしまったくらいに。って、待てよ?
「なんで今村課長のお子さんが会社にいるんですか?」
「今日、小学校が開校記念日でお休みだったらしいのよ。今村さん、今朝それを思い出したらしくて。旦那さんは今週いっぱい出張だし、預けるところもなくて連れてきたんだって」
「休暇は取らなかったんですね」
「私のせいなのよ」
大塚さんは急に声を落とした。
「え? どういうことですか?」
大塚さんはそれには答えず、顔を上げて声を張った。
「とにかく! こはるちゃんをよろしくね。私は、今村さんが定時で上がれるように手伝ってくるわ」
「あ、はい」
大塚さんは早足で事務所の方に去っていった。
勢いに押されて返事をしてしまったが、僕だって小口精算が溜まっているんだけどな。けどまあ仕方ないかと社長室のある三階へと向かった。
社長室に入ってまず目に入るのは、正面の窓際にある低いキャビネットの上に飾られたお城の模型だ。ラップの芯で作った西洋風のお城。以前こはるちゃんが図工の授業で作ったものだが、材料集めに会社の人たちが協力したこともあって、お礼として社長に贈られたのだった。
お城の製作者はメンテナンスでもしているのか、あちこち覗き込んでいる。
「こはるちゃん?」
「はい。今村こはるです」
さっき会ったことなど忘れているような自己紹介をした。それか、僕の顔など見ていなかったのかもしれない。
「あ、どうも。石井祐介です。……いま、ひとり?」
壁際に置かれたデスクにここの主の姿はない。
社長といえども事務所にあるのと同じ型のオフィスデスクを使っている。むしろこちらの方が古いのではないだろうか。側面にはいくつかの凹みと錆の浮いた傷が目立つ。脚がガタつくのか一本だけ折りたたんだ紙をかませているほどだ。
デスクの向かいの壁にはキャビネットが並んでいるが、そちらは粘着テープで補修されている部分がある。磯貝社長は現場の設備は利便性重視で入れ替えるのに、社長室は何十年もそのままだ。
どこもかしこも年季の入っている磯貝プリントだが、社長室は特に昭和感がすごい。デスクの後ろの壁にはレトロな温度計がかかっている。赤い液体が木製の板についた目盛りを指し示すやつだ。ゼンマイ式の壁掛け時計は故障して八時ちょっと過ぎで止まったままで、動いている置き時計はといえば、デジタルっぽい数字が印字されたフリップ時計だ。昔の映画などである駅の案内板がパタパタするあれだ。
時代遅れと言ってしまえばそれまでだけど、僕はこの社長室の雰囲気がなんとなく気に入っている。
「はい。社長さんは作業場に行きました。ここにいていいと言われたのですけど、だめでしたか?」
「いや。社長がいいと言うならいいんだと思うよ」
普段から人の出入りが多い部屋だ。機密性の高いものの保管場所は施錠されているはずだった。
「あ。そうだ。オレンジジュースをどうぞ」
「ありがとうございます。いただきます」
丁寧に両手で戴くように受け取り、頭を下げた。
小学三、四年生といったところだろうか。小学生ってこんなに礼儀正しかっただろうかと戸惑っていると、ドアが開く音がした。
磯貝社長は僕を認めると、厚みのある手をあげた。
「おう。石井ちゃん、おつかれ」
「お疲れ様です。不在のところお邪魔してすみません」
「いいって、いいって。お。こはるちゃん、いいもの飲んでるな」
「はい。石井さんにいただきました」
こはるちゃんが再びお城のチェックを始めたのを見て、僕は社長室を後にした。
0
お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る


就職面接の感ドコロ!?
フルーツパフェ
大衆娯楽
今や十年前とは真逆の、売り手市場の就職活動。
学生達は賃金と休暇を貪欲に追い求め、いつ送られてくるかわからない採用辞退メールに怯えながら、それでも優秀な人材を発掘しようとしていた。
その業務ストレスのせいだろうか。
ある面接官は、女子学生達のリクルートスーツに興奮する性癖を備え、仕事のストレスから面接の現場を愉しむことに決めたのだった。

駒込の七不思議
中村音音(なかむらねおん)
ミステリー
地元のSNSで気になったこと・モノをエッセイふうに書いている。そんな流れの中で、駒込の七不思議を書いてみない? というご提案をいただいた。
7話で完結する駒込のミステリー。



月明かりの儀式
葉羽
ミステリー
神藤葉羽と望月彩由美は、幼馴染でありながら、ある日、神秘的な洋館の探検に挑むことに決めた。洋館には、過去の住人たちの悲劇が秘められており、特に「月明かりの間」と呼ばれる部屋には不気味な伝説があった。二人はその場所で、古い肖像画や日記を通じて、禁断の儀式とそれに伴う呪いの存在を知る。
儀式を再現することで過去の住人たちを解放できるかもしれないと考えた葉羽は、仲間の彩由美と共に儀式を行うことを決意する。しかし、儀式の最中に影たちが現れ、彼らは過去の記憶を映し出しながら、真実を求めて叫ぶ。過去の住人たちの苦しみと後悔が明らかになる中、二人はその思いを受け止め、解放を目指す。
果たして、葉羽と彩由美は過去の悲劇を乗り越え、住人たちを解放することができるのか。そして、彼ら自身の運命はどうなるのか。月明かりの下で繰り広げられる、謎と感動の物語が展開されていく。
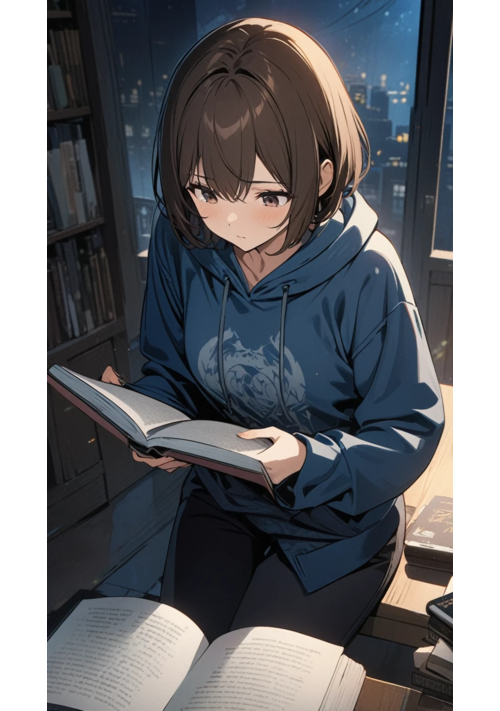
声の響く洋館
葉羽
ミステリー
神藤葉羽と望月彩由美は、友人の失踪をきっかけに不気味な洋館を訪れる。そこで彼らは、過去の住人たちの声を聞き、その悲劇に導かれる。失踪した友人たちの影を追い、葉羽と彩由美は声の正体を探りながら、過去の未練に囚われた人々の思いを解放するための儀式を行うことを決意する。
彼らは古びた日記を手掛かりに、恐れや不安を乗り越えながら、解放の儀式を成功させる。過去の住人たちが解放される中で、葉羽と彩由美は自らの成長を実感し、新たな未来へと歩み出す。物語は、過去の悲劇を乗り越え、希望に満ちた未来を切り開く二人の姿を描く。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















