10 / 29
3章
女性のプロ野球選手
しおりを挟む
1
ユキコはいま、ピッチャーズマウンドに立ち、明るい日差しを浴びている。ユニフォームは白の無地だ。
周囲は森林で、木々の匂いでいっぱいである。
覚えているわけではないが、どこか故郷に似た場所のような気がした。
数日前、秦からは、養子縁組の申請中だと告げられた。
「あなたは私の娘になる。日本名は秦ユキコだ。あなたを不法滞在者にしたくないからね」
上海のおっさん、劉は嘘をつかなかった。
用意されていた偽の書類に、微塵も問題はなかった。
「おーい、ユキ、なに考えてる。ここだ、ここだ」
キャッチャーの山崎が、ミットをかまえている。
レギュラーの捕手だ。今ここでユキコは、『ユキ』と呼ばれている。
追加補強された強化指定選手の登録名簿のなかに『ユキ』という文字を見つけても、女性に似た名前の選手だと思うだけだ。
山崎がミットを前にだし、腰を引く。
サインはインコースの低め、カーブだ。
キャッチャーの後ろには、畑中が立っている。アンパイア兼コーチである。
ユキは、どんなボールでも投げられた。
獲物はいつも空を飛んでいる訳ではなかったのだ。
地上のばあい、木立や岩のでっぱりが邪魔になる。
だから状況に応じ、左に曲げ、右に曲げ、沈みこんだり、浮き上がったりの石を投げた。足元の瓦礫を拾って投げるときは、重さや形を瞬間に判断し、投げ方を決める。
だからボールの縫い目に指をかける投げ方は、すぐにマスターできた。
ただし、最初に覚えた大きく足を上げる投げ方は、すこしだけ高さを調整し、低く変えた。
ユキは三本の指をかけ、握ったボールにスナップを効かせた。
フオームもビディオで研究したとおりだ。腕もスムースに振れ、左足の踏みだしにも問題はなかった。
ボールは、キャッチャーの手前できゅんと曲がる。
びしっと音をたて、ミットに消える。山崎は微動だにしない。
ユキは嬉しそうに笑う。投げる行為が楽しくてしょうがないのだ。
「ストラーイク。97」
あがったアンパイアの右腕の人差し指が、青空を差す。
コールの後に告げる数字は、投げたボールの順番である。
アンパイア兼選任コーチの畑中が、手帳を眺めながら呼びかける。
「80球めはどんな球だった?」
「直球、外角高め」
「65球めは?」
「スライダーでストライク。ど真ん中」
ユキはすらすら言い当てる。試合のとき、相手にどう攻めたかも大切だ。
「はははは。いやあ、みごと、みごと」
畑中は両手を腰に当て、のけぞった。
ユキも真似をして腰にグラブを当て、うふふと胸を反らして笑う。
父親になった秦がすごく喜んでくれるので、心ががはずみ、投球に力がこもった。
契約のとき、父親の秦は、個人情報の完全守秘義務と独自の自由契約を条件にした。
ユキやその関係者については、なにも語らないのだ。
秦の名も伏せ、畑中にマネージャを代わってもらった。
秦は、あたかも雑用係のように陰でユキに付き添った。
契約では、本人が休みたい、あるいは辞めたいと申し出たときにはいつでも休めるし、球界も去れる。
ユキ側の身勝手な言い分だったが、ユキがプロ野球を盛り上げ、確実に球団に利益をもたらすと分かったので、すべてが認められた。
なにしろ本場のアメリカもふくめ、プロ野球初の本格的な女性ピッチャーだった。
これらの契約は、通常の試合であるペナントレースでいきなりデビユーするという球団側の要望で締めくくられた。
梅里雪山で出会った謎の娘が、日本の有名球団のピッチャーになろうとしていたのだ。
強化選手枠で登録されたが、150キロ級の球を抜群のコントロールで投げる女性投手となれば、いやでも目につく。
だから、郊外のにわか球場のまわりを幕で囲い、建設現場を装った。
球団は、ユキの情報を完全にシャットアウトした。
球団としてはいきなりのデビューで、世間といわず、世界をあっと驚かせたかった。
前宣伝なしの方が、効果的と判断したのだ。
秦の家の近くの公営グランドや帝王高校の監督や選手、その他の目撃者もいたが、大マスコミの読日は見事に情報を封じた。あれはせいぜい一三〇キロだった、しかも本当は男で、女装だったという情報をながした。
練習を終え、白い天幕で囲まれた建設現場からバスが出発した。
都心まで、ハイウェイで約一時間半。
ユキの登板は、オールスター戦が終わった7月26日と決まっていた。
二週間後だ。
バスの窓の外に、ビルや民家が並びだす。
ユキは昨日の秦のつぶやきを思い出した。
「国立博物館の動物学者、湯川という人に会いにいったが、本人は不在だった。気になるので今日、また上野の博物館にいってみる」
一ヵ月ちょっと前、TGの畑中が初めて秦周一の家を訪れた日、秦のケイタイに電話をかけてきた男だ。
ユキが電話を取ったのでよく覚えていた。
秦のほうから上野の研究室にコンタクトを取ろうとしていたが、話し中が続き、突然半月ほど前からは『休みです』になり、いつしか『長期休暇をとっています』になった。
その日秦は、上野の国立博物館のオフィスに再度訪ねていったのに、いったきりユキのケイタイになにも連絡してこなかった。
投げ終えたばかりの肩には、少しだけ疲れが残っていた。
だが、温湿布した肩と、マッサージをし終えた肢体は心地よい。
ユキが他人と明らかに違うのは、手の指の長さだった。
ボールがしっかり握れるのだ。石を握っていたせいか、握力が普通の男性の二倍ほどもあった。
あとは右腕のしなりだ。スロービディオで見ると、投球のときの腕が弓のようにしなる。
その反動がボールに力を与える。
さらに、ユキが備えている全身のバネのような筋肉が、パワーを生んでいる。
そして勘のよさだ。
「優生民族なのに、どうして他を支配したり、生存範囲を拡大せず、謎のまま隠れるように住んでいるのだろうか?」
秦にはそれが気になった。もしユキの民族が、昔から梅里雪山の近辺に住んでいるとしたら、とっくにあたり一帯を支配していたはずである。
またユキの記憶喪失は、何らかの耐えがたい事故があったのではないのか。
心を破壊させるほどの危機を感じたとき、人の脳は自らの精神の均衡を保ち、生命体を守るため、その体験をなかったようにしまうのである。記憶失くしてしまうのだ。
しかし、精神科医の診断通り、今のところ日常生活に支障はないので、経過をみるということになった。
ユキは、ちらほらと夢を見る。緑の失せた島のあとは海ばかりの風景だ。
途切れながら音声も聞こえる。『長老』『BATARA』『超粘菌』という言葉の中に『三万年前を覚えているか』などと呼びかける言葉もあった。
自分が着ていた毛皮が、年代測定で三万年前のものと出たと秦も口にしていた。
わたしは、長い眠りから覚めた気分で、ようやく頭がかすかに過去の記憶を取り戻しそうな気配を感じている。でも、わたしがあの洞窟でずっと眠っていたなんて、三万年も……信じられない。
電動式のマッサージ機に揉まれながら、うとうとした。
⦅あなたの次の目標は、野球で有名になることです。有名になってアメリカ中に名前が知られるんです⦆
ユキはぼんやりその声を聞いていた。
頭の中でだれかが呟いているような気がした。
なぜ有名にならなければならないのですか、と問いかけたかったが手段がなかった。
「ユキさん、あと五分で溜池の駅です」
運転席側にあるスタッフ用の席から、畑中が車内マイクで報告してきた。
外の景色は、東京の真っただ中だった。
高架線のハイウェイの左右すれすれに、ビルがおおいかぶさっている。
やがてバスは、ハイウエイから脇道に入った。
下降すると、地下鉄の駅の真ん前だった。
その駅から地下鉄に乗って、二駅で降りる。
駅の脇の一車線の坂道を歩いて登る。
坂をあがりきり、秦家の門をくぐった。
玄関のドアを開けた。
背を丸くした秦が姿をあらわした。
ユキは、秦の笑顔の片隅にかすかな陰りを見つけた。
「国立博物館で、湯川さんに会えたんですか?」
秦は、日焼けした顔で左右に首をふった。
2
「私は漢方薬専門の龍玉堂の経営コンサルタントです。今回、ネパールの山岳地帯に生薬採取の調査に入りたいのですが、その地域に虎が出没するというので、あらかじめ湯川先生に意見をお伺にきました」
秦は上野の国立博物館に着くと、受付でそうに告げた。
とにかく、秘書でもいいから会って、湯川の情報を得たかった。
インターネットで調べてみると、虎についての著作が何冊かあった。
最新の著作は、ネパールの虎の生息環境などを調べたもので『標高三千メートルでの生息は可能か』などの副題がついていた。
秘書兼研究員の若い女性が待っていた。
滝川加奈子という名刺をもらった。
髪を短くカットし、白いブラウスが似合った。
秦は用意したネパールの地図をひろげ、偽の生薬採取地域を示した。
女性研究員は応えた。
「いままで虎がいるという噂とともに、足跡などの証拠もあったのですが、実際にはだれも姿を目撃していませんでした。しかし、数ヶ月前にヨーロッパの調査隊がついに録画に成功したんです。それを機に、どういう訳か、各地で次々と生息が確認されました」
説明する滝川の背後の壁には、研究室の地図が貼られている。
ヒマラヤ山脈のふもとの国、ネパールの地図の下側五分一ほどが、赤いマジックで囲まれていた。
「今見せてもらった秦さんの採取地域と重なりますので、出没地域の地名リストのコピーをさしあげます。でも実際の範囲はもっと広くなるかも知れません。その点は充分にご留意ください」
滝川は、英文で書かれた用紙を数枚手渡してくれた。
秦は感心したようにうなずきながら、部屋を見渡した。
「湯川先生には、以前もお世話になっているのですが、今はどちらなんでしょうか?」
思い出したように告げてみた。
「現在、お休みになっておられます」
滝川は、ぼそりと答えた。
「実は今回の件とは別に、個人的に用がありまして、何度か電話をさしあげたのですが、どうかなさったのでしょうか?」
滝川は息をのんだように、言葉に詰まった。
龍玉堂という漢方の薬屋の元経営者で、現在はコンサルタントということと、以前にもお世話になった、個人的に用があるという秦の言葉に、一瞬のとまどいのあと、吐露するように口にした。
「デスクの上に『研究調査のため、急用ででかける』と書いた紙と三ヶ月間の休暇願の用紙がありました。パスポートもなくなっていました。以前にもたびたび急に外国にでかけていましたので、またかと思いました。博物館の上司たちは、半分あきらめています。もう一ヶ月ほど連絡がありません」
最後の文言が、秦には訴えるようなつぶやきに聞こえた。
湯川と知り合いと称する来客者の秦に、助けを求めているようにも感じた。
「先生のご自宅の方では、どうおっしゃっていらっしゃるんですか?」
秦は、ためらいながら訊いてみた。
「そのうち帰ってきます。放っておいてください、でした」
「奥さんがですか?」
「はい。いままでにも色々あったようでして」
唇の端に、はにかみの笑みが浮かぶ。そんな場合の意味が、女性関係を意味するようにも受け取れた。
「最近、先生になにか変わったようすが見受けられたんでしょうか?」
滝川は首をかしげ、ちょっと考えた。
短くカットした髪の下に、白い項がのぞいた。
「出張するすこし前に、アメリカから電話があってそわそわしていました」
「アメリカですか。失礼ですがそれ、さしつかえ
「たぶん、年代測定の会社です。ただしどのような用件なのか、私には分りません。現地調査をしていると、いろんな人が様々な物を持ちこんできます。民族器具から人の骨、珍しいという動物の骨、毛皮もあります。ときどき当たりがありますが、ほとんどは外れです」
秦がなにくわぬ顔で、あとを続けた。
「じつは私も、そういう外国の会社をときどき利用したいと考えているのですが、アメリカのその会社の名前とか、電話番号とかを教えていただけないでしょうか?」
「普段ですと、年代測定のようなものは私が手続きを取ります。でも今回はいつもの会社ではありませんでした。ノートやそれらしい書類をめくって探してみたのですが、先生の手帳の中なのか、該当する会社は見当たりませんでした」
「大変にあつかましいのですが、そういうことでしたら、博士の奥さんに会って、現在、博士がどちらにいらっしゃるのかを教えてもらえたらと思うのですが、いかがでしょうか。急な話ですが、どうしても個人的な用件で連絡を取りたいのです。自宅のほうに、ヒントぐらいは残しているかもしれません」
漢方薬、龍玉堂の元経営者ということで信用してくれたのか、秦の熱気に負けたのか、住所を紙に書いてくれた。
湯川の家は茨城県の筑波にあった。東京から45分のベットタウンである。
奥さんは、大柄でアフロヘアのきれいな人だった。
「学術調査というのですが、女のところなのかどうかは私には分かりません。今回については勘ですが、女のところですね。女がどこにいるのかは、だいたい分かっています。私が留守のときに必要な資料を持ち、部屋を散らかし、あわててでていきました」
奥さんは、ふうん、という態度に終始しながら、その人の住所を教えてくれた。
秦はまた電車に乗って都内にもどり、日暮里の女のマンションを探しあてた。
湯川をいちばんよく知っている女ですよ、と奥さ嘲笑ぎみだった。
いつも午後の四時には帰るだろう、という。
名前とか歳とかを聞きたかったが、ありがとうございますと頭を下げ、急ぎ筑波の家をあとにした。
秦は教わったマンションのドアの前で、部屋の主を待った。
はたして四時を過ぎたとき、廊下に足音がした。
滝川加奈子だった。しかし、研究員の彼女は、今回の湯川の行動についてはほとんど知らなかった、とにかく急にいなくなってしまったのだ、と下を向いた。
3
東京ドームは満員だった。
外野席は一塁側も三塁側も、オールスター後の開戦を待ちわびたファンで埋まっていた。
ユキは、地下に設けられた室内の特別練習場で肩を慣らした。
畑中と一緒にベンチに移ったとき、はじめてメンバーと顔を合わせた。
選手のみんなは、女性アナウンサーがユニフォームを着てインタビューをしにきたのだと思った。
同時に監督の高原も姿を見せた。畑中がユキとともに監督の横に立った。
「みんな聞いてくれ。オールスター開けの投手、ユキだ」
監督がユキの肩を軽く叩き、先発メンバーに紹介した。
全員がぎょっとなって、ユキを見守った。
監督と特別コーチの畑中に挟まれ、ユキはちょっとはにかんだ。
が、すぐに頬をひきしめ、唇を噛んだ。
そして、閉じ込めた闘志が今にもはじけそうに、青味がかった瞳を宙にすえた。
TGの選手は口を開けたまま、だれも身動きができなかった。
自分の登板だとおもっていた当て馬のピッチャーが、あんぐり口を開け、ユキを見守った。
場内では、スタートメンバーの発表です、とアナウンスされていた。
バックスクリーンの掲示板に名前が点灯されると同時に、選手がグランドに飛びだすのだ。
六球団は、相変わらず三ゲーム内で白熱の首位争いを展開していた。
おかげで、野球界全体が熱くもりあがっていた。
名前を呼ばれた一番バッターが、グラウンドにとびだした。
二番、三番と選手たちが、弾む足取りでグランドにでていく。
最後の九番の電光掲示板が点灯し、ユキというカタカナ文字が浮かんだ。
同時に場内アナウンスが、高らかに『ピッチャー、ユキー』と呼んだ。
「本日予定していたスタメンピッチャーが故障のため、急遽新人ピッチャートと交代いたします」
アナウンサーの報告を聞き、観客は一斉に電光掲示とベンチに目をやった。
グラブを手に、ベンチからピッチャーズマウンドにユキが走った。
背中のポニーテールが揺れる。女性を強調するショートパンツ姿ではなかった。
本格的な選手を意味するように、男性と同じ上下のユニフォー-ム姿だ。
一瞬、ドーム内は静まり返った。
敵も味方もファンも、現れた女性を呆然と眺めた。
ユキは、ピッチャーズマウンドに立った。
帽子を取り、頭上にかざしながら、からだを一回転させた。
背番号は16、そして間違いなく『YUKI』と背中に書かれている。
だが、静かなどよめきは治まらない。
ピッチャーズマウンドに集った味方の選手も、訳が分からなかった。
表情を失い、ぼんやりユニフォーム姿の一人の女性を見守った。
キャッチャーの山崎がやってきて、公式ボールをユキに渡す。
その間に、相手チームのメンバーが発表される。
練習投球である。
女性ピッチャーが、山なりのボールを投げる。
公式のキャチャーの山崎が、何食わぬ顔でそれを受ける。
ピチャーズマウンドに集まっている味方の選手たちが、まだ呆然と二人を眺めている。
球場がざわつく。
報道陣さえ、なにが起こっているかが分らない。
正面に設けられた報道用の席では、全員がただきょろきょろしている。
「アップだ。アップだ」
記者の一人が叫んだ。
テーブル席に備えつけられたTV画面である。
「おっ、美人じゃないか」
「ほんとうに投げるのか」
もちろん資料は配られていない。
観客たちの視線を受けながら、二人はふざけたような山なりのボールを投げ合った。
とにかく正捕手の山崎が、公式の球場で相手にしているのだ。
冗談などである訳がなかった。
ユキは、球場の静寂の中に伝わる雑音を全身で聞いていた。
耳元に畑中コーチの、落ち着け、肩の力を抜け、という声が残っていた。
山崎が腰を下ろし、かまえたキャッチャーミットを右拳で、ぽんぽんと叩いた。
練習投球である。
ワインドアップでゆるい直球だ。
相変わらず客席は沈黙を守っている。
二球めは、一球めよりもスピードのあるボールだった。
弓なりの投球の軌跡が、やや直線に変わった。
まだ120キロというところか。
キャッチャーの山崎が、スローカーブのサインをだした。
続いてカットボール。次はスライダー。
ユキは静かに燃えていた。四万人の目が、自分の一挙一動を見守っているのだ。
いや、テレビ中継されているから、何百万人──もしかしたら何千万人だ。
からだは落ち着いていても、心の奥の芯が小刻みに震えた。
規定投球を終えた。
「プレーボール」
とうとうアンパイアの右手が、高々と上った。
試合開始である。しかし球場はしんとしている。
所々に湧く子供の叫び声。それが、ドームの屋根に反射する。
キャッチャーが腰をひき、ミットをかまえた。
ユキはゆっくりふりかぶった。
一瞬、白い直線がぱっと光った。
わあっ、きゃっと悲鳴をあげた女性の観客。
ど真ん中のストライクが、キャッチャーミットに吸いこまれた。
ストレートだ。バッターの呆気にとられた顔。
球場全体が、はっと息を呑んだ。
ついで、おおっとどよめく。
観客の全員が、バックスクリーンの電光掲示板に目をやる。
そこには『161』と表示されていた。
161キロメートルの球速である。
「おおおー」
どよめきが、大歓声に変わった。
湧きおこる拍手。
それまでデータもなにもなく、無言を要求されていたテレビやラジオのアナウンサーが、いっせいにマイクにかじりついた。
四万人の観客が放つ、叫び声や拍手や感動の溜息。のぞく
頬を赤らめたユキが、次の投球の準備に入る。
腰をかがめ、キャッチャーの股間をのぞく。
山崎の股のあいだから人差し指が一本、ぴんとでていた。同じストレートだ。
振りかぶって投げる。アンパイアの腕が勢いよく挙がる。
わあっと、また歓声。
球場を包みこむ大波のようなどよめき。
161キロ。
次のサインも指一本。今度は162キロ。
ストライクのコールとともに、アンパイアのオーバーなアクション。
アウトをコールされてもバッターは、バットをかまえたまま、目の前の空間をぼんやり眺めている。
一番バッターは、次の二番バッターに、おいと声をかけられるまで気がつかなかった。
キャッチャーの山崎は、またもストレートのサイン。
よし、いくぞとユキが振りかぶる。
もう不安はなくなった。代わりにぐんぐん力が込みあげてきた。
だが、冷静さを装った。
二番バッターは、さっそくストレートを狙ってきた。
だが三球三振。ボールは、161キロから160キロをキープしている。
二番バッターは、二度、三度と首をかしげ、三番バターと交代した。
三番バッターは、手元で浮きあがる、という助言を二番バッターから受けた。
でも、どうにもならなかった。
ユキは大柄な三番バッターのウイークポイントを、記憶から引きだした。
「いくぞ」
白糸を引いたように、ボールが山崎のミットに消える。
アンパイアが飛びあがって、空手の突きを演じる。バッターアウト。
ユキは唇を噛んだ。
こぼれる笑みを前歯の先で殺した。
三振を取っても、相手に笑顔を向けてはいけないと秦から教わった。
歓声が鳴り止まない。
やがてスタンドオーベーションに変わった。
TGのファンばかりではない。
名古屋ドラゴンズのファンも一緒になった。
秦はどこだろう。気になってプレイの邪魔になるだろうからホテルの部屋でテレビを見ている、といった。
でも、きっと来ていると目で探した。
(3-3 了)
8919
ユキコはいま、ピッチャーズマウンドに立ち、明るい日差しを浴びている。ユニフォームは白の無地だ。
周囲は森林で、木々の匂いでいっぱいである。
覚えているわけではないが、どこか故郷に似た場所のような気がした。
数日前、秦からは、養子縁組の申請中だと告げられた。
「あなたは私の娘になる。日本名は秦ユキコだ。あなたを不法滞在者にしたくないからね」
上海のおっさん、劉は嘘をつかなかった。
用意されていた偽の書類に、微塵も問題はなかった。
「おーい、ユキ、なに考えてる。ここだ、ここだ」
キャッチャーの山崎が、ミットをかまえている。
レギュラーの捕手だ。今ここでユキコは、『ユキ』と呼ばれている。
追加補強された強化指定選手の登録名簿のなかに『ユキ』という文字を見つけても、女性に似た名前の選手だと思うだけだ。
山崎がミットを前にだし、腰を引く。
サインはインコースの低め、カーブだ。
キャッチャーの後ろには、畑中が立っている。アンパイア兼コーチである。
ユキは、どんなボールでも投げられた。
獲物はいつも空を飛んでいる訳ではなかったのだ。
地上のばあい、木立や岩のでっぱりが邪魔になる。
だから状況に応じ、左に曲げ、右に曲げ、沈みこんだり、浮き上がったりの石を投げた。足元の瓦礫を拾って投げるときは、重さや形を瞬間に判断し、投げ方を決める。
だからボールの縫い目に指をかける投げ方は、すぐにマスターできた。
ただし、最初に覚えた大きく足を上げる投げ方は、すこしだけ高さを調整し、低く変えた。
ユキは三本の指をかけ、握ったボールにスナップを効かせた。
フオームもビディオで研究したとおりだ。腕もスムースに振れ、左足の踏みだしにも問題はなかった。
ボールは、キャッチャーの手前できゅんと曲がる。
びしっと音をたて、ミットに消える。山崎は微動だにしない。
ユキは嬉しそうに笑う。投げる行為が楽しくてしょうがないのだ。
「ストラーイク。97」
あがったアンパイアの右腕の人差し指が、青空を差す。
コールの後に告げる数字は、投げたボールの順番である。
アンパイア兼選任コーチの畑中が、手帳を眺めながら呼びかける。
「80球めはどんな球だった?」
「直球、外角高め」
「65球めは?」
「スライダーでストライク。ど真ん中」
ユキはすらすら言い当てる。試合のとき、相手にどう攻めたかも大切だ。
「はははは。いやあ、みごと、みごと」
畑中は両手を腰に当て、のけぞった。
ユキも真似をして腰にグラブを当て、うふふと胸を反らして笑う。
父親になった秦がすごく喜んでくれるので、心ががはずみ、投球に力がこもった。
契約のとき、父親の秦は、個人情報の完全守秘義務と独自の自由契約を条件にした。
ユキやその関係者については、なにも語らないのだ。
秦の名も伏せ、畑中にマネージャを代わってもらった。
秦は、あたかも雑用係のように陰でユキに付き添った。
契約では、本人が休みたい、あるいは辞めたいと申し出たときにはいつでも休めるし、球界も去れる。
ユキ側の身勝手な言い分だったが、ユキがプロ野球を盛り上げ、確実に球団に利益をもたらすと分かったので、すべてが認められた。
なにしろ本場のアメリカもふくめ、プロ野球初の本格的な女性ピッチャーだった。
これらの契約は、通常の試合であるペナントレースでいきなりデビユーするという球団側の要望で締めくくられた。
梅里雪山で出会った謎の娘が、日本の有名球団のピッチャーになろうとしていたのだ。
強化選手枠で登録されたが、150キロ級の球を抜群のコントロールで投げる女性投手となれば、いやでも目につく。
だから、郊外のにわか球場のまわりを幕で囲い、建設現場を装った。
球団は、ユキの情報を完全にシャットアウトした。
球団としてはいきなりのデビューで、世間といわず、世界をあっと驚かせたかった。
前宣伝なしの方が、効果的と判断したのだ。
秦の家の近くの公営グランドや帝王高校の監督や選手、その他の目撃者もいたが、大マスコミの読日は見事に情報を封じた。あれはせいぜい一三〇キロだった、しかも本当は男で、女装だったという情報をながした。
練習を終え、白い天幕で囲まれた建設現場からバスが出発した。
都心まで、ハイウェイで約一時間半。
ユキの登板は、オールスター戦が終わった7月26日と決まっていた。
二週間後だ。
バスの窓の外に、ビルや民家が並びだす。
ユキは昨日の秦のつぶやきを思い出した。
「国立博物館の動物学者、湯川という人に会いにいったが、本人は不在だった。気になるので今日、また上野の博物館にいってみる」
一ヵ月ちょっと前、TGの畑中が初めて秦周一の家を訪れた日、秦のケイタイに電話をかけてきた男だ。
ユキが電話を取ったのでよく覚えていた。
秦のほうから上野の研究室にコンタクトを取ろうとしていたが、話し中が続き、突然半月ほど前からは『休みです』になり、いつしか『長期休暇をとっています』になった。
その日秦は、上野の国立博物館のオフィスに再度訪ねていったのに、いったきりユキのケイタイになにも連絡してこなかった。
投げ終えたばかりの肩には、少しだけ疲れが残っていた。
だが、温湿布した肩と、マッサージをし終えた肢体は心地よい。
ユキが他人と明らかに違うのは、手の指の長さだった。
ボールがしっかり握れるのだ。石を握っていたせいか、握力が普通の男性の二倍ほどもあった。
あとは右腕のしなりだ。スロービディオで見ると、投球のときの腕が弓のようにしなる。
その反動がボールに力を与える。
さらに、ユキが備えている全身のバネのような筋肉が、パワーを生んでいる。
そして勘のよさだ。
「優生民族なのに、どうして他を支配したり、生存範囲を拡大せず、謎のまま隠れるように住んでいるのだろうか?」
秦にはそれが気になった。もしユキの民族が、昔から梅里雪山の近辺に住んでいるとしたら、とっくにあたり一帯を支配していたはずである。
またユキの記憶喪失は、何らかの耐えがたい事故があったのではないのか。
心を破壊させるほどの危機を感じたとき、人の脳は自らの精神の均衡を保ち、生命体を守るため、その体験をなかったようにしまうのである。記憶失くしてしまうのだ。
しかし、精神科医の診断通り、今のところ日常生活に支障はないので、経過をみるということになった。
ユキは、ちらほらと夢を見る。緑の失せた島のあとは海ばかりの風景だ。
途切れながら音声も聞こえる。『長老』『BATARA』『超粘菌』という言葉の中に『三万年前を覚えているか』などと呼びかける言葉もあった。
自分が着ていた毛皮が、年代測定で三万年前のものと出たと秦も口にしていた。
わたしは、長い眠りから覚めた気分で、ようやく頭がかすかに過去の記憶を取り戻しそうな気配を感じている。でも、わたしがあの洞窟でずっと眠っていたなんて、三万年も……信じられない。
電動式のマッサージ機に揉まれながら、うとうとした。
⦅あなたの次の目標は、野球で有名になることです。有名になってアメリカ中に名前が知られるんです⦆
ユキはぼんやりその声を聞いていた。
頭の中でだれかが呟いているような気がした。
なぜ有名にならなければならないのですか、と問いかけたかったが手段がなかった。
「ユキさん、あと五分で溜池の駅です」
運転席側にあるスタッフ用の席から、畑中が車内マイクで報告してきた。
外の景色は、東京の真っただ中だった。
高架線のハイウェイの左右すれすれに、ビルがおおいかぶさっている。
やがてバスは、ハイウエイから脇道に入った。
下降すると、地下鉄の駅の真ん前だった。
その駅から地下鉄に乗って、二駅で降りる。
駅の脇の一車線の坂道を歩いて登る。
坂をあがりきり、秦家の門をくぐった。
玄関のドアを開けた。
背を丸くした秦が姿をあらわした。
ユキは、秦の笑顔の片隅にかすかな陰りを見つけた。
「国立博物館で、湯川さんに会えたんですか?」
秦は、日焼けした顔で左右に首をふった。
2
「私は漢方薬専門の龍玉堂の経営コンサルタントです。今回、ネパールの山岳地帯に生薬採取の調査に入りたいのですが、その地域に虎が出没するというので、あらかじめ湯川先生に意見をお伺にきました」
秦は上野の国立博物館に着くと、受付でそうに告げた。
とにかく、秘書でもいいから会って、湯川の情報を得たかった。
インターネットで調べてみると、虎についての著作が何冊かあった。
最新の著作は、ネパールの虎の生息環境などを調べたもので『標高三千メートルでの生息は可能か』などの副題がついていた。
秘書兼研究員の若い女性が待っていた。
滝川加奈子という名刺をもらった。
髪を短くカットし、白いブラウスが似合った。
秦は用意したネパールの地図をひろげ、偽の生薬採取地域を示した。
女性研究員は応えた。
「いままで虎がいるという噂とともに、足跡などの証拠もあったのですが、実際にはだれも姿を目撃していませんでした。しかし、数ヶ月前にヨーロッパの調査隊がついに録画に成功したんです。それを機に、どういう訳か、各地で次々と生息が確認されました」
説明する滝川の背後の壁には、研究室の地図が貼られている。
ヒマラヤ山脈のふもとの国、ネパールの地図の下側五分一ほどが、赤いマジックで囲まれていた。
「今見せてもらった秦さんの採取地域と重なりますので、出没地域の地名リストのコピーをさしあげます。でも実際の範囲はもっと広くなるかも知れません。その点は充分にご留意ください」
滝川は、英文で書かれた用紙を数枚手渡してくれた。
秦は感心したようにうなずきながら、部屋を見渡した。
「湯川先生には、以前もお世話になっているのですが、今はどちらなんでしょうか?」
思い出したように告げてみた。
「現在、お休みになっておられます」
滝川は、ぼそりと答えた。
「実は今回の件とは別に、個人的に用がありまして、何度か電話をさしあげたのですが、どうかなさったのでしょうか?」
滝川は息をのんだように、言葉に詰まった。
龍玉堂という漢方の薬屋の元経営者で、現在はコンサルタントということと、以前にもお世話になった、個人的に用があるという秦の言葉に、一瞬のとまどいのあと、吐露するように口にした。
「デスクの上に『研究調査のため、急用ででかける』と書いた紙と三ヶ月間の休暇願の用紙がありました。パスポートもなくなっていました。以前にもたびたび急に外国にでかけていましたので、またかと思いました。博物館の上司たちは、半分あきらめています。もう一ヶ月ほど連絡がありません」
最後の文言が、秦には訴えるようなつぶやきに聞こえた。
湯川と知り合いと称する来客者の秦に、助けを求めているようにも感じた。
「先生のご自宅の方では、どうおっしゃっていらっしゃるんですか?」
秦は、ためらいながら訊いてみた。
「そのうち帰ってきます。放っておいてください、でした」
「奥さんがですか?」
「はい。いままでにも色々あったようでして」
唇の端に、はにかみの笑みが浮かぶ。そんな場合の意味が、女性関係を意味するようにも受け取れた。
「最近、先生になにか変わったようすが見受けられたんでしょうか?」
滝川は首をかしげ、ちょっと考えた。
短くカットした髪の下に、白い項がのぞいた。
「出張するすこし前に、アメリカから電話があってそわそわしていました」
「アメリカですか。失礼ですがそれ、さしつかえ
「たぶん、年代測定の会社です。ただしどのような用件なのか、私には分りません。現地調査をしていると、いろんな人が様々な物を持ちこんできます。民族器具から人の骨、珍しいという動物の骨、毛皮もあります。ときどき当たりがありますが、ほとんどは外れです」
秦がなにくわぬ顔で、あとを続けた。
「じつは私も、そういう外国の会社をときどき利用したいと考えているのですが、アメリカのその会社の名前とか、電話番号とかを教えていただけないでしょうか?」
「普段ですと、年代測定のようなものは私が手続きを取ります。でも今回はいつもの会社ではありませんでした。ノートやそれらしい書類をめくって探してみたのですが、先生の手帳の中なのか、該当する会社は見当たりませんでした」
「大変にあつかましいのですが、そういうことでしたら、博士の奥さんに会って、現在、博士がどちらにいらっしゃるのかを教えてもらえたらと思うのですが、いかがでしょうか。急な話ですが、どうしても個人的な用件で連絡を取りたいのです。自宅のほうに、ヒントぐらいは残しているかもしれません」
漢方薬、龍玉堂の元経営者ということで信用してくれたのか、秦の熱気に負けたのか、住所を紙に書いてくれた。
湯川の家は茨城県の筑波にあった。東京から45分のベットタウンである。
奥さんは、大柄でアフロヘアのきれいな人だった。
「学術調査というのですが、女のところなのかどうかは私には分かりません。今回については勘ですが、女のところですね。女がどこにいるのかは、だいたい分かっています。私が留守のときに必要な資料を持ち、部屋を散らかし、あわててでていきました」
奥さんは、ふうん、という態度に終始しながら、その人の住所を教えてくれた。
秦はまた電車に乗って都内にもどり、日暮里の女のマンションを探しあてた。
湯川をいちばんよく知っている女ですよ、と奥さ嘲笑ぎみだった。
いつも午後の四時には帰るだろう、という。
名前とか歳とかを聞きたかったが、ありがとうございますと頭を下げ、急ぎ筑波の家をあとにした。
秦は教わったマンションのドアの前で、部屋の主を待った。
はたして四時を過ぎたとき、廊下に足音がした。
滝川加奈子だった。しかし、研究員の彼女は、今回の湯川の行動についてはほとんど知らなかった、とにかく急にいなくなってしまったのだ、と下を向いた。
3
東京ドームは満員だった。
外野席は一塁側も三塁側も、オールスター後の開戦を待ちわびたファンで埋まっていた。
ユキは、地下に設けられた室内の特別練習場で肩を慣らした。
畑中と一緒にベンチに移ったとき、はじめてメンバーと顔を合わせた。
選手のみんなは、女性アナウンサーがユニフォームを着てインタビューをしにきたのだと思った。
同時に監督の高原も姿を見せた。畑中がユキとともに監督の横に立った。
「みんな聞いてくれ。オールスター開けの投手、ユキだ」
監督がユキの肩を軽く叩き、先発メンバーに紹介した。
全員がぎょっとなって、ユキを見守った。
監督と特別コーチの畑中に挟まれ、ユキはちょっとはにかんだ。
が、すぐに頬をひきしめ、唇を噛んだ。
そして、閉じ込めた闘志が今にもはじけそうに、青味がかった瞳を宙にすえた。
TGの選手は口を開けたまま、だれも身動きができなかった。
自分の登板だとおもっていた当て馬のピッチャーが、あんぐり口を開け、ユキを見守った。
場内では、スタートメンバーの発表です、とアナウンスされていた。
バックスクリーンの掲示板に名前が点灯されると同時に、選手がグランドに飛びだすのだ。
六球団は、相変わらず三ゲーム内で白熱の首位争いを展開していた。
おかげで、野球界全体が熱くもりあがっていた。
名前を呼ばれた一番バッターが、グラウンドにとびだした。
二番、三番と選手たちが、弾む足取りでグランドにでていく。
最後の九番の電光掲示板が点灯し、ユキというカタカナ文字が浮かんだ。
同時に場内アナウンスが、高らかに『ピッチャー、ユキー』と呼んだ。
「本日予定していたスタメンピッチャーが故障のため、急遽新人ピッチャートと交代いたします」
アナウンサーの報告を聞き、観客は一斉に電光掲示とベンチに目をやった。
グラブを手に、ベンチからピッチャーズマウンドにユキが走った。
背中のポニーテールが揺れる。女性を強調するショートパンツ姿ではなかった。
本格的な選手を意味するように、男性と同じ上下のユニフォー-ム姿だ。
一瞬、ドーム内は静まり返った。
敵も味方もファンも、現れた女性を呆然と眺めた。
ユキは、ピッチャーズマウンドに立った。
帽子を取り、頭上にかざしながら、からだを一回転させた。
背番号は16、そして間違いなく『YUKI』と背中に書かれている。
だが、静かなどよめきは治まらない。
ピッチャーズマウンドに集った味方の選手も、訳が分からなかった。
表情を失い、ぼんやりユニフォーム姿の一人の女性を見守った。
キャッチャーの山崎がやってきて、公式ボールをユキに渡す。
その間に、相手チームのメンバーが発表される。
練習投球である。
女性ピッチャーが、山なりのボールを投げる。
公式のキャチャーの山崎が、何食わぬ顔でそれを受ける。
ピチャーズマウンドに集まっている味方の選手たちが、まだ呆然と二人を眺めている。
球場がざわつく。
報道陣さえ、なにが起こっているかが分らない。
正面に設けられた報道用の席では、全員がただきょろきょろしている。
「アップだ。アップだ」
記者の一人が叫んだ。
テーブル席に備えつけられたTV画面である。
「おっ、美人じゃないか」
「ほんとうに投げるのか」
もちろん資料は配られていない。
観客たちの視線を受けながら、二人はふざけたような山なりのボールを投げ合った。
とにかく正捕手の山崎が、公式の球場で相手にしているのだ。
冗談などである訳がなかった。
ユキは、球場の静寂の中に伝わる雑音を全身で聞いていた。
耳元に畑中コーチの、落ち着け、肩の力を抜け、という声が残っていた。
山崎が腰を下ろし、かまえたキャッチャーミットを右拳で、ぽんぽんと叩いた。
練習投球である。
ワインドアップでゆるい直球だ。
相変わらず客席は沈黙を守っている。
二球めは、一球めよりもスピードのあるボールだった。
弓なりの投球の軌跡が、やや直線に変わった。
まだ120キロというところか。
キャッチャーの山崎が、スローカーブのサインをだした。
続いてカットボール。次はスライダー。
ユキは静かに燃えていた。四万人の目が、自分の一挙一動を見守っているのだ。
いや、テレビ中継されているから、何百万人──もしかしたら何千万人だ。
からだは落ち着いていても、心の奥の芯が小刻みに震えた。
規定投球を終えた。
「プレーボール」
とうとうアンパイアの右手が、高々と上った。
試合開始である。しかし球場はしんとしている。
所々に湧く子供の叫び声。それが、ドームの屋根に反射する。
キャッチャーが腰をひき、ミットをかまえた。
ユキはゆっくりふりかぶった。
一瞬、白い直線がぱっと光った。
わあっ、きゃっと悲鳴をあげた女性の観客。
ど真ん中のストライクが、キャッチャーミットに吸いこまれた。
ストレートだ。バッターの呆気にとられた顔。
球場全体が、はっと息を呑んだ。
ついで、おおっとどよめく。
観客の全員が、バックスクリーンの電光掲示板に目をやる。
そこには『161』と表示されていた。
161キロメートルの球速である。
「おおおー」
どよめきが、大歓声に変わった。
湧きおこる拍手。
それまでデータもなにもなく、無言を要求されていたテレビやラジオのアナウンサーが、いっせいにマイクにかじりついた。
四万人の観客が放つ、叫び声や拍手や感動の溜息。のぞく
頬を赤らめたユキが、次の投球の準備に入る。
腰をかがめ、キャッチャーの股間をのぞく。
山崎の股のあいだから人差し指が一本、ぴんとでていた。同じストレートだ。
振りかぶって投げる。アンパイアの腕が勢いよく挙がる。
わあっと、また歓声。
球場を包みこむ大波のようなどよめき。
161キロ。
次のサインも指一本。今度は162キロ。
ストライクのコールとともに、アンパイアのオーバーなアクション。
アウトをコールされてもバッターは、バットをかまえたまま、目の前の空間をぼんやり眺めている。
一番バッターは、次の二番バッターに、おいと声をかけられるまで気がつかなかった。
キャッチャーの山崎は、またもストレートのサイン。
よし、いくぞとユキが振りかぶる。
もう不安はなくなった。代わりにぐんぐん力が込みあげてきた。
だが、冷静さを装った。
二番バッターは、さっそくストレートを狙ってきた。
だが三球三振。ボールは、161キロから160キロをキープしている。
二番バッターは、二度、三度と首をかしげ、三番バターと交代した。
三番バッターは、手元で浮きあがる、という助言を二番バッターから受けた。
でも、どうにもならなかった。
ユキは大柄な三番バッターのウイークポイントを、記憶から引きだした。
「いくぞ」
白糸を引いたように、ボールが山崎のミットに消える。
アンパイアが飛びあがって、空手の突きを演じる。バッターアウト。
ユキは唇を噛んだ。
こぼれる笑みを前歯の先で殺した。
三振を取っても、相手に笑顔を向けてはいけないと秦から教わった。
歓声が鳴り止まない。
やがてスタンドオーベーションに変わった。
TGのファンばかりではない。
名古屋ドラゴンズのファンも一緒になった。
秦はどこだろう。気になってプレイの邪魔になるだろうからホテルの部屋でテレビを見ている、といった。
でも、きっと来ていると目で探した。
(3-3 了)
8919
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る


小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

蘇生魔法を授かった僕は戦闘不能の前衛(♀)を何度も復活させる
フルーツパフェ
大衆娯楽
転移した異世界で唯一、蘇生魔法を授かった僕。
一緒にパーティーを組めば絶対に死ぬ(死んだままになる)ことがない。
そんな口コミがいつの間にか広まって、同じく異世界転移した同業者(多くは女子)から引っ張りだこに!
寛容な僕は彼女達の申し出に快諾するが条件が一つだけ。
――実は僕、他の戦闘スキルは皆無なんです
そういうわけでパーティーメンバーが前衛に立って死ぬ気で僕を守ることになる。
大丈夫、一度死んでも蘇生魔法で復活させてあげるから。
相互利益はあるはずなのに、どこか鬼畜な匂いがするファンタジー、ここに開幕。

マイナー18禁乙女ゲームのヒロインになりました
東 万里央(あずま まりお)
恋愛
十六歳になったその日の朝、私は鏡の前で思い出した。この世界はなんちゃってルネサンス時代を舞台とした、18禁乙女ゲーム「愛欲のボルジア」だと言うことに……。私はそのヒロイン・ルクレツィアに転生していたのだ。
攻略対象のイケメンは五人。ヤンデレ鬼畜兄貴のチェーザレに男の娘のジョバンニ。フェロモン侍従のペドロに影の薄いアルフォンソ。大穴の変人両刀のレオナルド……。ハハッ、ロクなヤツがいやしねえ! こうなれば修道女ルートを目指してやる!
そんな感じで涙目で爆走するルクレツィアたんのお話し。

お持ち帰り召喚士磯貝〜なんでも持ち運び出来る【転移】スキルで異世界つまみ食い生活〜
双葉 鳴|◉〻◉)
ファンタジー
ひょんなことから男子高校生、磯貝章(いそがいあきら)は授業中、クラス毎異世界クラセリアへと飛ばされた。
勇者としての役割、与えられた力。
クラスメイトに協力的なお姫様。
しかし能力を開示する魔道具が発動しなかったことを皮切りに、お姫様も想像だにしない出来事が起こった。
突如鳴り出すメール音。SNSのメロディ。
そして学校前を包囲する警察官からの呼びかけにクラスが騒然とする。
なんと、いつの間にか元の世界に帰ってきてしまっていたのだ!
──王城ごと。
王様達は警察官に武力行為を示すべく魔法の詠唱を行うが、それらが発動することはなく、現行犯逮捕された!
そのあとクラスメイトも事情聴取を受け、翌日から普通の学校生活が再開する。
何故元の世界に帰ってきてしまったのか?
そして何故か使えない魔法。
どうも日本では魔法そのものが扱えない様で、異世界の貴族達は魔法を取り上げられた平民として最低限の暮らしを強いられた。
それを他所に内心あわてている生徒が一人。
それこそが磯貝章だった。
「やっべー、もしかしてこれ、俺のせい?」
目の前に浮かび上がったステータスボードには異世界の場所と、再転移するまでのクールタイムが浮かび上がっていた。
幸い、章はクラスの中ではあまり目立たない男子生徒という立ち位置。
もしあのまま帰って来なかったらどうなっていただろうというクラスメイトの話題には参加させず、この能力をどうするべきか悩んでいた。
そして一部のクラスメイトの独断によって明かされたスキル達。
当然章の能力も開示され、家族ごとマスコミからバッシングを受けていた。
日々注目されることに辟易した章は、能力を使う内にこう思う様になった。
「もしかして、この能力を金に変えて食っていけるかも?」
──これは転移を手に入れてしまった少年と、それに巻き込まれる現地住民の異世界ドタバタコメディである。
序章まで一挙公開。
翌日から7:00、12:00、17:00、22:00更新。
序章 異世界転移【9/2〜】
一章 異世界クラセリア【9/3〜】
二章 ダンジョンアタック!【9/5〜】
三章 発足! 異世界旅行業【9/8〜】
四章 新生活は異世界で【9/10〜】
五章 巻き込まれて異世界【9/12〜】
六章 体験! エルフの暮らし【9/17〜】
七章 探索! 並行世界【9/19〜】
95部で第一部完とさせて貰ってます。
※9/24日まで毎日投稿されます。
※カクヨムさんでも改稿前の作品が読めます。
おおよそ、起こりうるであろう転移系の内容を網羅してます。
勇者召喚、ハーレム勇者、巻き込まれ召喚、俺TUEEEE等々。
ダンジョン活動、ダンジョンマスターまでなんでもあります。
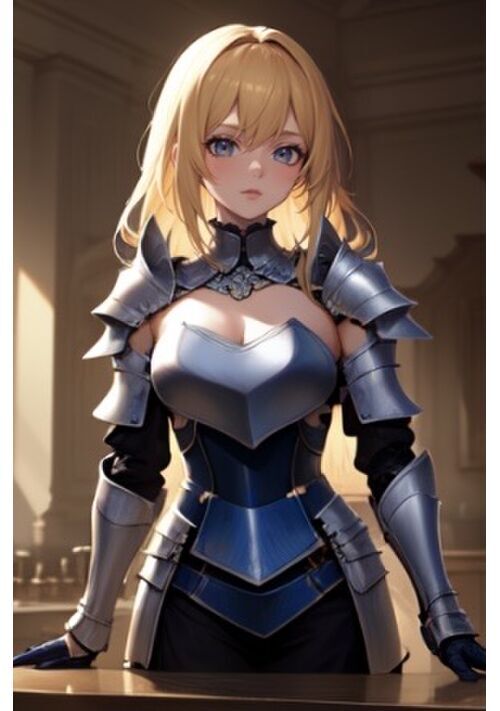
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!

ズボラ通販生活
ice
ファンタジー
西野桃(にしのもも)35歳の独身、オタクが神様のミスで異世界へ!貪欲に通販スキル、時間停止アイテムボックス容量無限、結界魔法…さらには、お金まで貰う。商人無双や!とか言いつつ、楽に、ゆるーく、商売をしていく。淋しい独身者、旦那という名の奴隷まで?!ズボラなオバサンが異世界に転移して好き勝手生活する!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















