27 / 39
急の章 天下一の女房、これにあり ──山崎の戦い──
27 光秀の出陣、秀吉の接近
しおりを挟む
明智光秀は出陣した。
出陣せざるを得なかった。
西へ。
「……チッ」
露骨に舌打ちした光秀。
その脳裏に浮かぶは、顔も知らぬ平島公方ではない。
よく知った細川藤孝である。
「……こうなりゃ、鞆の足利義昭でも、かまわんか」
捨てた相手だし、もれなく毛利の紐づきであるが、無いよりましだろう。
そんな考えが、光秀の脳内に浮かぶ。
「うむ。うまくすると毛利と、羽柴をはさみ撃ちができるやもしれんのう」
実際、足利義昭は(光秀と手を組んだかどうかは不明だが)毛利家に羽柴秀吉を討て、東上せよと要請している。
が、すげなく断られている。
毛利家としては、和睦を結んだ相手の羽柴秀吉に「賭けた」かたちになっており、それをふいにしたくないのだろう。
いずれにせよ、光秀は西進して、大和の筒井順慶に圧をかけることにした。
「そんなら、細川は」
光秀は再び、いや、もう数回にわたる書状をまたしたためようとした。
だが、書いている途中でそれをやめざるを得なくなった。
「羽柴がそこまで来ているだと?」
中国大返し。
その大詰めともいうべき、羽柴秀吉の摂津入りが確認されたからである。
*
中国大返し。
その姫路までの過程は、神速とでも称すべき速度であった。
だが、姫路からのそれは、それまでとはちがって、実に慎重な進み具合だった。
「信長さま、生存」
とは、先に述べた秀吉の策であるが、それを各所に伝えた。
特に、摂津の諸侯には。
「まあ実際は亡うなっておられる。そのかたき討ちのためじゃ、信長さまも泉下で苦笑いしておられるじゃろ」
秀吉は誰ともなくそう言っていたが、本当にそれを伝えたい相手は、今はそばにいない。
おそらく、京にいる。
「……したが、大坂は別じゃ。三七どの(織田信孝のこと)には、かたき討ちじゃとハッキリ言うておかんと」
「その点、抜かりはございません」
馬上、ブツブツとつぶやいていた秀吉の背後から、語りかける影があった。
影は陽光の下、なお一層その陰影を濃くしながら、秀吉に近づいた。
「官兵衛」
「はい。御前に」
黒田官兵衛その人である。
官兵衛は姫路出立前にふらりと「出る」と言い置いて行ってしまったが、いつの間にやらこうして秀吉のそばに侍している。
どこで、何をしていたか。
そう秀吉が問う前に、官兵衛はふところから十字架をまさぐり出した。
「大坂には、弟御の秀長さまが向かわれた。かの者は実直で鳴らしておられる。おそらく、大丈夫でしょう」
主君の弟を、それもその主君の面前でえらそうな評価を下す。
だが、それでこそ官兵衛。
そう言わせるだけの迫力の男である。
そしてそんな男が、おそらく銀製の十字架を、まるで童女が人形をかわいがるように、愛でている。
「……高山右近にでも、もらったのきゃあ? 十字架」
「ぜひにもお話をおうかがいしたい、と申し入れましてな」
*
摂津の有力国人・高山右近は、若年の時にキリシタンになったと、つとに知られている。
右近はこの動乱から距離を置いておこうと思っていたが、そこを官兵衛が「ぜひにも入信したい」と訪問した次第である。
これがただの勧誘なり調略であれば、右近も追い返すところであるが、なにぶん、入信といわれては無下にもできない。
「……本当に入信しに来たのでござるか?」
「さよう」
官兵衛の凄まじいところは、先に入信してしまったところにある。
むろん、正式な入信は「すべて片付いたあと」と断りを入れたが、十字架を押し戴く官兵衛の姿は真剣だった。
そこまでやるか、と右近は思ったが、もうここまで来たら、断ることはできない。
……官兵衛の語りを。
*
「……ま、こうなったらと、同輩の中川清秀も誘ってくださるとのこと」
十字架に口づけしかねない勢いの官兵衛に、若干引き気味の秀吉。
それでも「ようやった」と肩をたたくことは忘れなかった。
「これで大坂の三七どのの四国征伐軍も食えば、結構な兵数になる。でかした。あとは……」
「あとは……光秀めを、うまく釣り出すことができれば、ですな」
水魚の交わりとはこのことだろう。
官兵衛は、わがことながら思った。
秀吉は口ひげを引っ張りながら、思案する。
「……もう淡路の洲本を陥としている頃じゃろ」
「淡路。平島公方と、それに伴う長宗我部の援軍の道を断った……しかし」
「そう。しかし、逆に光秀に逃げられたら、困るのう。負かすことが面倒になる」
大きく出たな、と官兵衛は思ったが、聞こえないふりをしている近侍や将兵が聞き耳を立てている。
ここは「最もわかりやすい理由を」喧伝すべきだろうと判じた。
……「微妙な案件」は置いておいて。
「上様」
「何じゃ」
「光秀めは朝廷より、京を安んじよ、との勅をたまわったとのこと」
これは光秀が安土城を押さえた時のことである。
京の動静が落ち着かないことを憂慮した誠仁親王は、光秀に京の治安維持を任じた。
これを「京の差配を認めてくれた」と受け止め、光秀は朝廷に銀五百枚を献じて報いたという。
ねねと長谷川宗仁の書状からそれを知った秀吉は「ふうん」と言って、鼻をほじり出した。
いわば朝廷の自衛的な活動であり、光秀に襲われないための担保だろうと、軽く流していた。
「さればでござる」
官兵衛は大上段に両手を振り上げる。
十字架も上がる。
「一挙に京まで攻め上られませ。さすれば元幕臣で、さような勅命を受けた光秀のこと、必死になって京を守りましょう」
そんな確信はない。
五分五分といったところだろう。
だが、とりあえずの説得力があればいい。
周りの将兵たちが納得すればいい。
「官兵衛」
「はい」
「……汝は、悪人じゃの」
これにはどっと笑いが起きた。
そこで秀吉はわざとらしく、何だお前ら聞いてたんかいと、おどけた。
一方で官兵衛は、こういう勝ちに行く雰囲気をうまく作っていく秀吉の恐ろしさに、冷や汗をかいた。
出陣せざるを得なかった。
西へ。
「……チッ」
露骨に舌打ちした光秀。
その脳裏に浮かぶは、顔も知らぬ平島公方ではない。
よく知った細川藤孝である。
「……こうなりゃ、鞆の足利義昭でも、かまわんか」
捨てた相手だし、もれなく毛利の紐づきであるが、無いよりましだろう。
そんな考えが、光秀の脳内に浮かぶ。
「うむ。うまくすると毛利と、羽柴をはさみ撃ちができるやもしれんのう」
実際、足利義昭は(光秀と手を組んだかどうかは不明だが)毛利家に羽柴秀吉を討て、東上せよと要請している。
が、すげなく断られている。
毛利家としては、和睦を結んだ相手の羽柴秀吉に「賭けた」かたちになっており、それをふいにしたくないのだろう。
いずれにせよ、光秀は西進して、大和の筒井順慶に圧をかけることにした。
「そんなら、細川は」
光秀は再び、いや、もう数回にわたる書状をまたしたためようとした。
だが、書いている途中でそれをやめざるを得なくなった。
「羽柴がそこまで来ているだと?」
中国大返し。
その大詰めともいうべき、羽柴秀吉の摂津入りが確認されたからである。
*
中国大返し。
その姫路までの過程は、神速とでも称すべき速度であった。
だが、姫路からのそれは、それまでとはちがって、実に慎重な進み具合だった。
「信長さま、生存」
とは、先に述べた秀吉の策であるが、それを各所に伝えた。
特に、摂津の諸侯には。
「まあ実際は亡うなっておられる。そのかたき討ちのためじゃ、信長さまも泉下で苦笑いしておられるじゃろ」
秀吉は誰ともなくそう言っていたが、本当にそれを伝えたい相手は、今はそばにいない。
おそらく、京にいる。
「……したが、大坂は別じゃ。三七どの(織田信孝のこと)には、かたき討ちじゃとハッキリ言うておかんと」
「その点、抜かりはございません」
馬上、ブツブツとつぶやいていた秀吉の背後から、語りかける影があった。
影は陽光の下、なお一層その陰影を濃くしながら、秀吉に近づいた。
「官兵衛」
「はい。御前に」
黒田官兵衛その人である。
官兵衛は姫路出立前にふらりと「出る」と言い置いて行ってしまったが、いつの間にやらこうして秀吉のそばに侍している。
どこで、何をしていたか。
そう秀吉が問う前に、官兵衛はふところから十字架をまさぐり出した。
「大坂には、弟御の秀長さまが向かわれた。かの者は実直で鳴らしておられる。おそらく、大丈夫でしょう」
主君の弟を、それもその主君の面前でえらそうな評価を下す。
だが、それでこそ官兵衛。
そう言わせるだけの迫力の男である。
そしてそんな男が、おそらく銀製の十字架を、まるで童女が人形をかわいがるように、愛でている。
「……高山右近にでも、もらったのきゃあ? 十字架」
「ぜひにもお話をおうかがいしたい、と申し入れましてな」
*
摂津の有力国人・高山右近は、若年の時にキリシタンになったと、つとに知られている。
右近はこの動乱から距離を置いておこうと思っていたが、そこを官兵衛が「ぜひにも入信したい」と訪問した次第である。
これがただの勧誘なり調略であれば、右近も追い返すところであるが、なにぶん、入信といわれては無下にもできない。
「……本当に入信しに来たのでござるか?」
「さよう」
官兵衛の凄まじいところは、先に入信してしまったところにある。
むろん、正式な入信は「すべて片付いたあと」と断りを入れたが、十字架を押し戴く官兵衛の姿は真剣だった。
そこまでやるか、と右近は思ったが、もうここまで来たら、断ることはできない。
……官兵衛の語りを。
*
「……ま、こうなったらと、同輩の中川清秀も誘ってくださるとのこと」
十字架に口づけしかねない勢いの官兵衛に、若干引き気味の秀吉。
それでも「ようやった」と肩をたたくことは忘れなかった。
「これで大坂の三七どのの四国征伐軍も食えば、結構な兵数になる。でかした。あとは……」
「あとは……光秀めを、うまく釣り出すことができれば、ですな」
水魚の交わりとはこのことだろう。
官兵衛は、わがことながら思った。
秀吉は口ひげを引っ張りながら、思案する。
「……もう淡路の洲本を陥としている頃じゃろ」
「淡路。平島公方と、それに伴う長宗我部の援軍の道を断った……しかし」
「そう。しかし、逆に光秀に逃げられたら、困るのう。負かすことが面倒になる」
大きく出たな、と官兵衛は思ったが、聞こえないふりをしている近侍や将兵が聞き耳を立てている。
ここは「最もわかりやすい理由を」喧伝すべきだろうと判じた。
……「微妙な案件」は置いておいて。
「上様」
「何じゃ」
「光秀めは朝廷より、京を安んじよ、との勅をたまわったとのこと」
これは光秀が安土城を押さえた時のことである。
京の動静が落ち着かないことを憂慮した誠仁親王は、光秀に京の治安維持を任じた。
これを「京の差配を認めてくれた」と受け止め、光秀は朝廷に銀五百枚を献じて報いたという。
ねねと長谷川宗仁の書状からそれを知った秀吉は「ふうん」と言って、鼻をほじり出した。
いわば朝廷の自衛的な活動であり、光秀に襲われないための担保だろうと、軽く流していた。
「さればでござる」
官兵衛は大上段に両手を振り上げる。
十字架も上がる。
「一挙に京まで攻め上られませ。さすれば元幕臣で、さような勅命を受けた光秀のこと、必死になって京を守りましょう」
そんな確信はない。
五分五分といったところだろう。
だが、とりあえずの説得力があればいい。
周りの将兵たちが納得すればいい。
「官兵衛」
「はい」
「……汝は、悪人じゃの」
これにはどっと笑いが起きた。
そこで秀吉はわざとらしく、何だお前ら聞いてたんかいと、おどけた。
一方で官兵衛は、こういう勝ちに行く雰囲気をうまく作っていく秀吉の恐ろしさに、冷や汗をかいた。
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

夜の終わりまで何マイル? ~ラウンド・ヘッズとキャヴァリアーズ、その戦い~
四谷軒
歴史・時代
【あらすじ】
オリヴァーは議員として王の暴政に反抗し、抵抗運動に身を投じたものの、国王軍に敗北してしまう。その敗北の直後、オリヴァーは、必ずや国王軍に負けないだけの軍を作り上げる、と決意する。オリヴァーには、同じ質の兵があれば、国王軍に負けないだけの自負があった。
……のちに剛勇の人(Old Ironsides)として、そして国の守り人(Lord Protector)として名を上げる、とある男の物語。
【表紙画像・挿絵画像】
John Barker (1811-1886), Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

待庵(たいあん)
四谷軒
歴史・時代
【あらすじ】
千宗易(後の利休)は、山崎の戦いに臨む羽柴秀吉から、二畳の茶室を作るよう命じられる。この時代、茶室は三畳半ぐらいが常識だった。それよりも狭い茶室を作れと言われ、宗易はいろいろと考える。そして、秀吉の弟・羽柴秀長や、秀吉の正室・ねねに会い、語り、宗易はやがて茶室について「作ったる」と明言する。言葉どおり完成した茶室で、宗易は茶を点て、客を待つ。やって来た客は……。
【表紙画像】
「ぐったりにゃんこのホームページ」様より

年明けこそ鬼笑う ―東寺合戦始末記― ~足利尊氏、その最後の戦い~
四谷軒
歴史・時代
【あらすじ】
南北朝時代、南朝の宰相、そして軍師ともいうべき、准后(じゅごう)・北畠親房、死す。
その兇報と共に、親房の臨終の言葉として、まことしやかに「その一言」が伝わってきた。
「年明けこそ鬼笑う」――と。
親房の最期の言葉は何を意味するのか――
楠木正成、新田義貞、高師直、足利直義といった英傑たちが死し、時代は次世代へと向かう最中、ひとり生き残った足利尊氏は、北畠親房の最期の機略に、どう対するのか。
【登場人物】
北畠親房:南朝の宰相にして軍師。故人。
足利尊氏:北朝の征夷大将軍、足利幕府初代将軍。
足利義詮:尊氏の三男、北朝・足利幕府二代将軍。長兄夭折、次兄が庶子のため、嫡子となる。
足利基氏:尊氏の四男、北朝・初代関東公方。通称・鎌倉公方だが、防衛のため入間川に陣を構える。
足利直冬:尊氏の次男。庶子のため、尊氏の弟・直義の養子となる。南朝に与し、京へ攻め入る。
楠木正儀:楠木正成の三男、南朝の軍事指導者。直冬に連動して、京へ攻め入る。
【表紙画像】
「きまぐれアフター」様より

幕末短編集 ~生にあがく人たち~
四谷軒
歴史・時代
【あらすじ】
(第一章 真新しい靴がステップ ~竜馬、寺田屋にて遭難す~)
慶応2年1月23日(1866年3月9日)深夜2時、坂本竜馬とその護衛の三吉慎蔵は、寺田屋に投宿していたが、そこを伏見奉行の捕り方に襲撃される。
辛くも寺田屋の外へと逃れる竜馬と慎蔵だったが、竜馬が負傷により動けなくなり、慎蔵は決死の覚悟で伏見薩摩藩邸へと走る。
慎蔵は薩摩藩邸の手前まで来たところで、捕り方に追いつかれてしまう。
その時、藩邸から、ひとりの男が歩み出て来た。
中村半次郎という男が。
(第二章 王政復古の大号令、その陰に――)
慶応3年11月15日。中岡慎太郎は近江屋にいた坂本竜馬を訪ね、そこで刺客に襲われた。世にいう近江屋事件である。竜馬は死んでしまったが、慎太郎は2日間、生き延びることができた。それは刺客の過ち(ミステイク)だったかもしれない。なぜなら、慎太郎はその死の前に言葉を遺すことができたから――岩倉具視という、不世出の謀略家に。
(第三章 見上げれば降るかもしれない)
幕末、そして戊辰戦争──東北・北越の諸藩は、維新という荒波に抗うべく、奥羽越列藩同盟を結成。
その同盟の中に、八戸藩という小藩があった。藩主の名は南部信順(なんぶのぶゆき)。薩摩藩主・島津重豪(しまづしげひで)の息子である。
八戸藩南部家は後継ぎに恵まれず、そのため、信順は婿養子として南部家に入った。それゆえに──八戸藩は同盟から敵視されていた。
四方八方が八戸藩を敵視して来るこの難局。信順はどう乗り切るのか。
【表紙画像】
「きまぐれアフター」様より

平安短編集 ~説話集より~
四谷軒
歴史・時代
【あらすじ】
(第一章 夏が燻る ~ 源宛(みなもとのあつる)と平良文(たいらのよしふみ)と合戰(あひたたか)ふ語 ―「今昔物語集巻二十五第三」より― ~)
時は平安、坂東(ばんどう)――武蔵野がまだ未開の荒野であった時代、二人の兵(つわもの)がいた。
一人は、源宛(みなもとのあつる)。
一人は、平良文(たいらのよしふみ)。
二人の領地は接しており、郎等(ろうとう)たちの争いは絶えなかった。
ある夏の日。
燻ぶる郎等たちに押され、宛(あつる)と良文(よしふみ)は相見(まみ)える。
しかし――二人は、合戦(かっせん)ではなく、兵(つわもの)として合戦(あいたたか)う。
二人の対決は、坂東の地に、人と人との仲をつなぐ。
そしてその仲は――世代を越え、時代を越えて、語り継がれる。
(第二章 恋よりも恋に近しい ~京都祇園祭「保昌山(ほうしょうやま)」より~)
平安時代、御堂関白こと藤原道長が生きていた時代、道長四天王の一人、平井保昌はある想いを抱き、悩んでいた。宮中で見かけた和泉式部のことが気になって仕方なかったのだ。保昌は式部に「恋よりも恋に近しい」という文を書いた。そして、保昌以外の人たちは、保昌のために動き出す――「恋よりも恋に近しい」を成就させるために。
【表紙画像】
「ぐったりにゃんこのホームページ」様より

連戦 ~新田義貞の鎌倉攻め~
四谷軒
歴史・時代
【あらすじ】
鎌倉幕府末期。上野(こうずけ)新田荘の御家人・新田義貞は、後醍醐天皇や「悪党」楠木正成の起こした幕府への叛乱(元弘の乱)に対する多大な戦費の要求に反発し、幕府からの使者を斬る。
幕府は新田討伐を決意し、執権北条家の一門の桜田貞国に三万の軍を与えて出兵し、一方で義貞もこれに反抗して挙兵した。
義貞は挙兵時こそ百五十騎であったが、鎌倉へ向けて進軍するうちに、馳せ参じる将兵らを加え、七千もの兵を擁するようになった。
そして――ついに武蔵小手指原にて、入間川をはさんで、新田義貞と桜田貞国は対峙し、激突する。
【登場人物】
新田義貞:上野(こうずけ)の御家人
脇屋義助:義貞の弟にして腹心
桜田貞国:幕府執権北条家の一門
足利高氏:源氏名門・足利家当主、のちの尊氏
足利千寿王:高氏の嫡子、のちの義詮
高師直:足利家執事
紀五左衛門:足利家嫡子、千寿王(のちの足利義詮)の補佐役
楠木正成:河内の「悪党」(秩序に従わぬ者の意)
河越高重:武蔵野の名族・河越氏の当主にして、武蔵七党を率いる
大多和義勝:相模の名族・三浦氏の一門
【参考資料】
「埼玉の歴史ものがたり」(埼玉県社会科教育研究会/編)

帰る旅
七瀬京
歴史・時代
宣教師に「見世物」として飼われていた私は、この国の人たちにとって珍奇な姿をして居る。
それを織田信長という男が気に入り、私は、信長の側で飼われることになった・・・。
荘厳な安土城から世界を見下ろす信長は、その傲岸な態度とは裏腹に、深い孤独を抱えた人物だった・・。
『本能寺』へ至るまでの信長の孤独を、側に仕えた『私』の視点で浮き彫りにする。
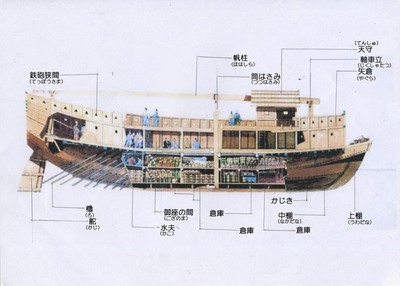
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















