1 / 7
Home,sweet home
1
しおりを挟む
「ただいま帰りました、先生」
「――大きくなったな」
ランノールは目の前の偉丈夫を見上げ、感嘆の溜め息をついた。街に送り出したときは、まだ自分よりも背の低い痩せっぽちの子供だったのだ。それがこんなに大きく、逞しくなって戻ってくるとは――。目を丸くしている師の顔を見て、元拾い子の立派な戦士は無精髭だらけの顔を破顔させた。
「もう二十五ですよ。大きくなった、はないでしょう。それに先生、どうせ俺がこの家に来ることは感知してたんでしょう? そこまで驚かなくったっていいじゃないですか」
「確かに、お前だということは気配で分かっていた。だからこそわざわざ視界を繋がなかったんだ」
人間が森に入り込めば、彼らの敵意や害意はランノールの張り巡らせた感知の糸ですぐに分かる。逆もまた然り。糸で感じたあたたかな気配はよく知る子供、ロイドのものだとすぐに分かっていた。
「だが、こんなに大きくなっているとは思いもしなかったんだ。人間の成長は早いな」
「そりゃ先生がエルフだからそう思うだけです」
「ハーフエルフだと何度言えば分かる?」
「人間の俺には似たようなもんですよ」
絹糸のような艶やかな金の髪の間から覗くランノールの尖った長い耳が笑うようにひこひこと動いた。美しく聡慧な先生の密かに可愛らしい点。ロイドは子供の頃から犬の尻尾のように率直な感情を伝えるその耳が大好きだった。
「――おかえり」
ランノールは少し恥ずかしげに小さな声で呟くと、ロイドを家の中に迎え入れた。短い黒髪を揺らし、ロイドは嬉しげに相好を崩した。
「ただいま、先生」
五つの頃、ロイドは親によってこの森の中に捨てられた。大規模な飢饉が起こり、食料に乏しい時代だったから、口減らしはどこにでもあるよくある話だった。奥には恐ろしい魔法使いが住んでいるという噂のある広大な森で、ロイドは一昼夜を過ごし、空きっ腹を抱えて暗い森の中を彷徨い歩いた。樹々をざわめかせる風の音。ひそやかな獣の息遣い。空腹と恐怖に霞む目でよろぼい歩く子供の目の前には、いつの間にか石造りの立派な屋敷がそびえ立っていた。
――あれは今思えば、先生が導いたんだろうな。
外套を脱ぎ、くつろいだ格好で卓についたロイドは狭くなった家の中を見回した。いや、師の言う通り、自分が大きくなったのだろう。相変わらず天井は高いが、今のロイドなら飛び上がればきっと手が届くだろう。試してみたくなって椅子から立ち上がり、膝を屈めたところで料理を運んできたランノールに見咎められた。
「何をしようとしていた? 全く、お前は図体は大きくなったが中身は子供のままじゃないか」
冷たい視線を浴びせかけるランノールに、悪戯が見つかった子供そのものの笑顔を見せ、ロイドはおとなしく椅子に座り直した。細く長い指がロイドの前に美味しそうに湯気を立てた皿を置く。鶏の香草焼き。ロイドの好きなものを覚えていてくれたのだ。きっと、ロイドが森に入ったときから、もてなすために調理してくれていたのだろう。初めて屋敷に迎え入れられたときも、こうしてすぐにあたたかな食事が出されたものだった。喜びに胸があたたかくなる。
「やっぱり先生の料理が一番美味しいです」
「そうか」
鶏の脂と肉の味を引き立てる香草を使ったソースは懐かしい味がした。ロイドが本心からそう言うと、ランノールの口調はひどくそっけなかったが、長い耳が嬉しげにピンと立つ。
「それで? お前は何をしにわざわざこんなところに戻ってきたんだ」
向かいの席に座ったランノールが自分の皿に手をつけながら言った。ロイドはその言葉に呆れたように目を剥く。
「手紙に書いたじゃないですか」
「……そうだったかな」
ランノールは先日、使い魔が持ってきたロイドからの手紙を思い出していた。要約すると、宮廷警備隊の隊長になった、という内容だった。他にもランノールの体調を案じたり、様子を伺うようなことも細かに書かれていたが、その辺りは彼にとっては些末なことだった。自分のことなどどうでも良かったし、遠くの街で暮らす元養い子が元気な便りをくれたということが大事だった。筆不精の彼は、それはおめでとう、と伝えるようにと言い含めて使い魔をロイドの元に返した。
「だが、帰ってくるとは書いてなかっただろう」
「そうでしたかね」
今度はロイドがとぼけると、くるりと大きな目を天井に向けた。ランノールは呆れたように一つ笑って立ち上がり、戸棚から酒瓶と杯を二つ取り出した。ロイドが嬉しげに笑う。
「そう言えば、先生と酒を酌み交わすのは初めてでしたね」
「……お前も立派な大人になったからな」
芳醇な果物の香りのする透明の液体がグラスに並々と注がれた。それはエルフに古くから伝わる伝統的な造りの酒で、子供の頃、ロイドは師が一人それを美味そうに飲んでいるのがとても羨ましかったものだ。
「――おめでとう、ロイド」
「ありがとうございます、先生」
一部を複雑に編み込んだ長い髪を掻き上げ、ランノールがグラスに口をつけた。ロイドも長年の憧れだった酒をゆっくりと口に含む。鼻へと抜けていく果物の香り、その後さわやかな甘みが来て、最後に意外と強い酒精が胃の腑をほわりとあたためる。これがまた香草焼きとよく合った。
「来ると知っていたら、ちゃんとしたご馳走を作ってやったのに」
酒精に頬を薄く染めたランノールが拗ねたような口調で言った。料理を作るのは嫌いではないのだが、いちいち街まで降りて材料を買い出しに行かないといけないのが難点だ。老人に姿を変え、街の近くまで移動魔法で降り立つのは簡単だ。だが、人間と交わるのがひどく億劫で、ロイドがいた頃は仕事と称してお使いに行かせていたものだ。
「お土産に食材をたくさん買ってきたじゃないですか。明日、あれでご馳走を作ってくださいよ」
「肉、肉、肉……。そんなものばかり買ってこられても困る。ちゃんと野菜は食べているのか? 均等に栄養素を摂らないと駄目だと散々教えただろう」
「野菜類はここで育ててるからいいと思ったんですよ」
口やかましく小言を繰る師を、ロイドは懐かしさに目を細めて見つめた。白い肌をほんのりと赤く染めたランノールの姿は、ロイドが子供の頃から変わらず美しかった。だが、そこに感じるのはもう美しさだけではない。
「――それに、俺はもう子供じゃないんですよ」
その低い声にランノールはつと目を上げた。目の前の男が愛おしげにこちらを見つめている。ランノールが二十年前に拾った子供。その面影は無精髭に埋もれてはいるが、確かにそこにあった。だが、向かいから慈しむ視線を投げかけてくる逞しいこの男は、もうランノールのよく知っていたか弱い子供ではなかった。複雑な思いで杯を干し、もう一杯注ぎ足す。
「私にとっては人間なんていつまでたっても子供のようなものだ」
「そりゃエルフは長寿ですからね……。で、実際のところ、お幾つなんですか、先生」
「百から数えるのをやめた」
「それ、俺が子供の頃から言ってるじゃないですか。エルフ族に伝わる冗談か何かですか」
「事実だから仕方ないだろう」
長い睫毛を伏せ、ランノールはぐいと杯を空けた。もう一杯注ぐ。ロイドが眉をしかめた。
「先生、そんなにお酒強くないでしょう。いい加減にしとかないと」
「いいんだ」
長く伸びた耳の先まで血の色を昇らせ、ランノールはグラスに口をつけた。呆れたようにロイドは肩をすくめ、空になった二人分の皿を慣れた手つきで片づけ始めた。合理的で冷静で、それでいて頑ななところがあるのは嫌というほどロイドは知っている。
――ここを追い出された時もそうだったな。
五つのときに拾われ、十五で金を持たされ街に出された。あの時、自分のことが嫌いなのかとロイドはランノールに泣きついた。師の傍から離れたくない、と言葉の限りを尽くしてランノールに訴えたが、最後までその首が縦に振られることはなかった。
――お前はもっと見識を広めなければならない。
本はたくさん読まされたし懇切丁寧に理念を教えてもらったが、残念ながらランノールのように高度な魔術を使えるようにはついぞならなかった。魔力を使うために必要な経脈がほとんどの人間には開かれていないから仕方がないのだ、と師は慰めてくれたが、幼心に悔しく思ったものだ。結局、魔術は軽度の治癒程度、人よりも医学、薬学に詳しくなった程度だった。
それならば、とロイドはこつこつと集めた駄賃で自ら街で剣を買い求めた。独力で訓練に精を出し、森で獲物を狩った。体力をつけるため買い出しの際は自分の足で歩けるだけ歩いた。そのうち体力とコツを掴み、大量の荷物を持って街から森までの長い道のりを平気で歩けるようになっていた。
そんな折、ランノールが急にそんなことを言い出したのだ。自分が魔法に向いていないからか、と詰め寄っても静かに首を振るばかり。師を守るために剣を覚え、身体を鍛えたのだ、とかき口説いてもそんなものは自分には必要ないとにべもない。最後には、俺のことが嫌いになったのか、と泣きついたロイドを抱き締め、ランノールはあらかじめ作っておいた荷物を押しつけると、黙って祝福の口づけをその額に落とした。
――大人になるまで戻ってきてはならない。
その言葉が終わる頃には、既にロイドは街の近くまで強制的に移動させられていた。よく買い物に来た街だ。遠くに黒々とわだかまる森をしばらく淋しい思いで見つめた後、ロイドは涙を拭いて、街へと歩き始めた。森への帰り道は知っている。だが、大人になるまで、先生に胸を張って堂々と会えるまで帰らない。少年はそう心に決めたのだった。
まずは住み込みで働けるところを探した。買い物をするだけで分かったような気になっていた街は、森とは違う刺激に常に満ち満ちていた。それらを適度に満喫しつつ、人に混じり生活をする。そこで分かったことは、自分が師の教育のおかげで他の人よりもかなり優れた能力を持っているということだった。自信をつけたロイドは宮廷警備隊の試験を受け、見事に合格した。
――とは言え。
思い出し、ロイドは綺麗に洗った皿を布巾で拭きながら微笑した。ある日、ほとんど小動物にしか見えないような使い魔がロイドの元を訪れてきたのだ。こんな心当たりはランノールしかない。試しに師宛に手紙を書いてみると、届けてくれた上に伝言を託かって帰ってきた。
――お前の無事をいつも祈っている。
あの祝福の口づけを思い出し、ロイドは胸を熱くした。大人になるまで、一人前になって師の前に堂々と立てるまで。常にそのことを思い描いて十年。齢二十五にして隊長になるとは警備隊の歴史において異例の出世だが、ロイドにとっては長い長い十年だった。
皿を片付けて戻ると、ランノールは机に突っ伏して眠っていた。金色の長い睫毛を呼吸の度に緩やかに上下させ、長い耳と頬が血色に染まる穏やかな寝顔が垂れた髪と腕の隙間から垣間見える。指でそっと金の髪を掬い上げ、ロイドは憧れの人の寝顔にしばらく見惚れた。耳元に唇を寄せ、そっと囁く。
「先生、起きてくださいよ」
かかる息がくすぐったかったのか長い耳がぴるぴると震え、小動物的な可愛さにロイドは思わず噴き出した。そして、軽々とランノールを抱き上げると寝室へと向かった。
「――大きくなったな」
ランノールは目の前の偉丈夫を見上げ、感嘆の溜め息をついた。街に送り出したときは、まだ自分よりも背の低い痩せっぽちの子供だったのだ。それがこんなに大きく、逞しくなって戻ってくるとは――。目を丸くしている師の顔を見て、元拾い子の立派な戦士は無精髭だらけの顔を破顔させた。
「もう二十五ですよ。大きくなった、はないでしょう。それに先生、どうせ俺がこの家に来ることは感知してたんでしょう? そこまで驚かなくったっていいじゃないですか」
「確かに、お前だということは気配で分かっていた。だからこそわざわざ視界を繋がなかったんだ」
人間が森に入り込めば、彼らの敵意や害意はランノールの張り巡らせた感知の糸ですぐに分かる。逆もまた然り。糸で感じたあたたかな気配はよく知る子供、ロイドのものだとすぐに分かっていた。
「だが、こんなに大きくなっているとは思いもしなかったんだ。人間の成長は早いな」
「そりゃ先生がエルフだからそう思うだけです」
「ハーフエルフだと何度言えば分かる?」
「人間の俺には似たようなもんですよ」
絹糸のような艶やかな金の髪の間から覗くランノールの尖った長い耳が笑うようにひこひこと動いた。美しく聡慧な先生の密かに可愛らしい点。ロイドは子供の頃から犬の尻尾のように率直な感情を伝えるその耳が大好きだった。
「――おかえり」
ランノールは少し恥ずかしげに小さな声で呟くと、ロイドを家の中に迎え入れた。短い黒髪を揺らし、ロイドは嬉しげに相好を崩した。
「ただいま、先生」
五つの頃、ロイドは親によってこの森の中に捨てられた。大規模な飢饉が起こり、食料に乏しい時代だったから、口減らしはどこにでもあるよくある話だった。奥には恐ろしい魔法使いが住んでいるという噂のある広大な森で、ロイドは一昼夜を過ごし、空きっ腹を抱えて暗い森の中を彷徨い歩いた。樹々をざわめかせる風の音。ひそやかな獣の息遣い。空腹と恐怖に霞む目でよろぼい歩く子供の目の前には、いつの間にか石造りの立派な屋敷がそびえ立っていた。
――あれは今思えば、先生が導いたんだろうな。
外套を脱ぎ、くつろいだ格好で卓についたロイドは狭くなった家の中を見回した。いや、師の言う通り、自分が大きくなったのだろう。相変わらず天井は高いが、今のロイドなら飛び上がればきっと手が届くだろう。試してみたくなって椅子から立ち上がり、膝を屈めたところで料理を運んできたランノールに見咎められた。
「何をしようとしていた? 全く、お前は図体は大きくなったが中身は子供のままじゃないか」
冷たい視線を浴びせかけるランノールに、悪戯が見つかった子供そのものの笑顔を見せ、ロイドはおとなしく椅子に座り直した。細く長い指がロイドの前に美味しそうに湯気を立てた皿を置く。鶏の香草焼き。ロイドの好きなものを覚えていてくれたのだ。きっと、ロイドが森に入ったときから、もてなすために調理してくれていたのだろう。初めて屋敷に迎え入れられたときも、こうしてすぐにあたたかな食事が出されたものだった。喜びに胸があたたかくなる。
「やっぱり先生の料理が一番美味しいです」
「そうか」
鶏の脂と肉の味を引き立てる香草を使ったソースは懐かしい味がした。ロイドが本心からそう言うと、ランノールの口調はひどくそっけなかったが、長い耳が嬉しげにピンと立つ。
「それで? お前は何をしにわざわざこんなところに戻ってきたんだ」
向かいの席に座ったランノールが自分の皿に手をつけながら言った。ロイドはその言葉に呆れたように目を剥く。
「手紙に書いたじゃないですか」
「……そうだったかな」
ランノールは先日、使い魔が持ってきたロイドからの手紙を思い出していた。要約すると、宮廷警備隊の隊長になった、という内容だった。他にもランノールの体調を案じたり、様子を伺うようなことも細かに書かれていたが、その辺りは彼にとっては些末なことだった。自分のことなどどうでも良かったし、遠くの街で暮らす元養い子が元気な便りをくれたということが大事だった。筆不精の彼は、それはおめでとう、と伝えるようにと言い含めて使い魔をロイドの元に返した。
「だが、帰ってくるとは書いてなかっただろう」
「そうでしたかね」
今度はロイドがとぼけると、くるりと大きな目を天井に向けた。ランノールは呆れたように一つ笑って立ち上がり、戸棚から酒瓶と杯を二つ取り出した。ロイドが嬉しげに笑う。
「そう言えば、先生と酒を酌み交わすのは初めてでしたね」
「……お前も立派な大人になったからな」
芳醇な果物の香りのする透明の液体がグラスに並々と注がれた。それはエルフに古くから伝わる伝統的な造りの酒で、子供の頃、ロイドは師が一人それを美味そうに飲んでいるのがとても羨ましかったものだ。
「――おめでとう、ロイド」
「ありがとうございます、先生」
一部を複雑に編み込んだ長い髪を掻き上げ、ランノールがグラスに口をつけた。ロイドも長年の憧れだった酒をゆっくりと口に含む。鼻へと抜けていく果物の香り、その後さわやかな甘みが来て、最後に意外と強い酒精が胃の腑をほわりとあたためる。これがまた香草焼きとよく合った。
「来ると知っていたら、ちゃんとしたご馳走を作ってやったのに」
酒精に頬を薄く染めたランノールが拗ねたような口調で言った。料理を作るのは嫌いではないのだが、いちいち街まで降りて材料を買い出しに行かないといけないのが難点だ。老人に姿を変え、街の近くまで移動魔法で降り立つのは簡単だ。だが、人間と交わるのがひどく億劫で、ロイドがいた頃は仕事と称してお使いに行かせていたものだ。
「お土産に食材をたくさん買ってきたじゃないですか。明日、あれでご馳走を作ってくださいよ」
「肉、肉、肉……。そんなものばかり買ってこられても困る。ちゃんと野菜は食べているのか? 均等に栄養素を摂らないと駄目だと散々教えただろう」
「野菜類はここで育ててるからいいと思ったんですよ」
口やかましく小言を繰る師を、ロイドは懐かしさに目を細めて見つめた。白い肌をほんのりと赤く染めたランノールの姿は、ロイドが子供の頃から変わらず美しかった。だが、そこに感じるのはもう美しさだけではない。
「――それに、俺はもう子供じゃないんですよ」
その低い声にランノールはつと目を上げた。目の前の男が愛おしげにこちらを見つめている。ランノールが二十年前に拾った子供。その面影は無精髭に埋もれてはいるが、確かにそこにあった。だが、向かいから慈しむ視線を投げかけてくる逞しいこの男は、もうランノールのよく知っていたか弱い子供ではなかった。複雑な思いで杯を干し、もう一杯注ぎ足す。
「私にとっては人間なんていつまでたっても子供のようなものだ」
「そりゃエルフは長寿ですからね……。で、実際のところ、お幾つなんですか、先生」
「百から数えるのをやめた」
「それ、俺が子供の頃から言ってるじゃないですか。エルフ族に伝わる冗談か何かですか」
「事実だから仕方ないだろう」
長い睫毛を伏せ、ランノールはぐいと杯を空けた。もう一杯注ぐ。ロイドが眉をしかめた。
「先生、そんなにお酒強くないでしょう。いい加減にしとかないと」
「いいんだ」
長く伸びた耳の先まで血の色を昇らせ、ランノールはグラスに口をつけた。呆れたようにロイドは肩をすくめ、空になった二人分の皿を慣れた手つきで片づけ始めた。合理的で冷静で、それでいて頑ななところがあるのは嫌というほどロイドは知っている。
――ここを追い出された時もそうだったな。
五つのときに拾われ、十五で金を持たされ街に出された。あの時、自分のことが嫌いなのかとロイドはランノールに泣きついた。師の傍から離れたくない、と言葉の限りを尽くしてランノールに訴えたが、最後までその首が縦に振られることはなかった。
――お前はもっと見識を広めなければならない。
本はたくさん読まされたし懇切丁寧に理念を教えてもらったが、残念ながらランノールのように高度な魔術を使えるようにはついぞならなかった。魔力を使うために必要な経脈がほとんどの人間には開かれていないから仕方がないのだ、と師は慰めてくれたが、幼心に悔しく思ったものだ。結局、魔術は軽度の治癒程度、人よりも医学、薬学に詳しくなった程度だった。
それならば、とロイドはこつこつと集めた駄賃で自ら街で剣を買い求めた。独力で訓練に精を出し、森で獲物を狩った。体力をつけるため買い出しの際は自分の足で歩けるだけ歩いた。そのうち体力とコツを掴み、大量の荷物を持って街から森までの長い道のりを平気で歩けるようになっていた。
そんな折、ランノールが急にそんなことを言い出したのだ。自分が魔法に向いていないからか、と詰め寄っても静かに首を振るばかり。師を守るために剣を覚え、身体を鍛えたのだ、とかき口説いてもそんなものは自分には必要ないとにべもない。最後には、俺のことが嫌いになったのか、と泣きついたロイドを抱き締め、ランノールはあらかじめ作っておいた荷物を押しつけると、黙って祝福の口づけをその額に落とした。
――大人になるまで戻ってきてはならない。
その言葉が終わる頃には、既にロイドは街の近くまで強制的に移動させられていた。よく買い物に来た街だ。遠くに黒々とわだかまる森をしばらく淋しい思いで見つめた後、ロイドは涙を拭いて、街へと歩き始めた。森への帰り道は知っている。だが、大人になるまで、先生に胸を張って堂々と会えるまで帰らない。少年はそう心に決めたのだった。
まずは住み込みで働けるところを探した。買い物をするだけで分かったような気になっていた街は、森とは違う刺激に常に満ち満ちていた。それらを適度に満喫しつつ、人に混じり生活をする。そこで分かったことは、自分が師の教育のおかげで他の人よりもかなり優れた能力を持っているということだった。自信をつけたロイドは宮廷警備隊の試験を受け、見事に合格した。
――とは言え。
思い出し、ロイドは綺麗に洗った皿を布巾で拭きながら微笑した。ある日、ほとんど小動物にしか見えないような使い魔がロイドの元を訪れてきたのだ。こんな心当たりはランノールしかない。試しに師宛に手紙を書いてみると、届けてくれた上に伝言を託かって帰ってきた。
――お前の無事をいつも祈っている。
あの祝福の口づけを思い出し、ロイドは胸を熱くした。大人になるまで、一人前になって師の前に堂々と立てるまで。常にそのことを思い描いて十年。齢二十五にして隊長になるとは警備隊の歴史において異例の出世だが、ロイドにとっては長い長い十年だった。
皿を片付けて戻ると、ランノールは机に突っ伏して眠っていた。金色の長い睫毛を呼吸の度に緩やかに上下させ、長い耳と頬が血色に染まる穏やかな寝顔が垂れた髪と腕の隙間から垣間見える。指でそっと金の髪を掬い上げ、ロイドは憧れの人の寝顔にしばらく見惚れた。耳元に唇を寄せ、そっと囁く。
「先生、起きてくださいよ」
かかる息がくすぐったかったのか長い耳がぴるぴると震え、小動物的な可愛さにロイドは思わず噴き出した。そして、軽々とランノールを抱き上げると寝室へと向かった。
11
お気に入りに追加
121
あなたにおすすめの小説


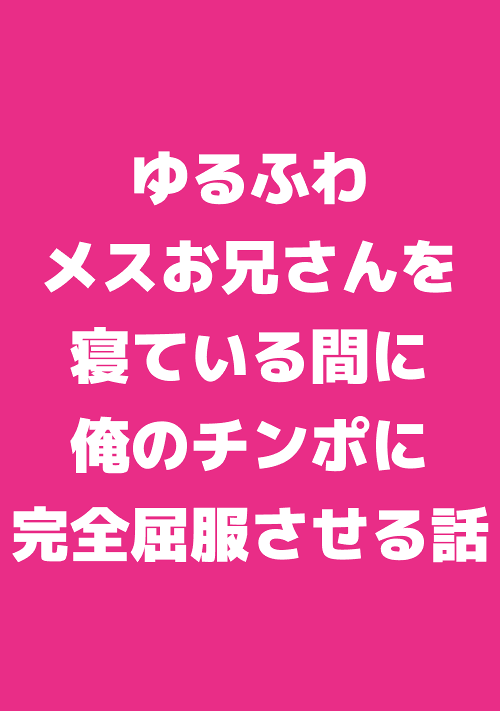
ゆるふわメスお兄さんを寝ている間に俺のチンポに完全屈服させる話
さくた
BL
攻め:浩介(こうすけ)
奏音とは大学の先輩後輩関係
受け:奏音(かなと)
同性と付き合うのは浩介が初めて
いつも以上に孕むだのなんだの言いまくってるし攻めのセリフにも♡がつく

年上が敷かれるタイプの短編集
あかさたな!
BL
年下が責める系のお話が多めです。
予告なくr18な内容に入ってしまうので、取扱注意です!
全話独立したお話です!
【開放的なところでされるがままな先輩】【弟の寝込みを襲うが返り討ちにあう兄】【浮気を疑われ恋人にタジタジにされる先輩】【幼い主人に狩られるピュアな執事】【サービスが良すぎるエステティシャン】【部室で思い出づくり】【No.1の女王様を屈服させる】【吸血鬼を拾ったら】【人間とヴァンパイアの逆転主従関係】【幼馴染の力関係って決まっている】【拗ねている弟を甘やかす兄】【ドSな執着系執事】【やはり天才には勝てない秀才】
------------------
新しい短編集を出しました。
詳しくはプロフィールをご覧いただけると幸いです。




ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















