10 / 91
二章
奇妙な少女①
しおりを挟む
一人で帰りの通学路を歩くのは久々だった。何か月、いや何年ぶりだろうか。
すぐ隣にみらいがいることにすっかり慣れきってしまっていたので、今もふとした拍子に何もない空間に向かって話しかけそうになってしまう。
傍から見るとかなりヤバイ奴だ。
そんな衝動を抑えながら、俺は今朝の出来事を思い返していた。
生徒が一人亡くなった。それも俺のクラスメイトが……。
何故彼女は、あんなところで亡くなっていたのだろう。死因はわかっていないとのことだったが、何らかの持病でも抱えていたのだろうか……?
今朝からそのことが頭の片隅にこびりついて離れなかった。
何故だか無性に、彼女の亡くなった原因について気になっている自分がいたのだ。理由はよくわからない。こうして色々詮索すること自体が、亡くなった彼女に対して失礼だという認識は持ち合わせているのだが、それでも、知りたいという欲求を俺は抑えきれずにいた。
今日何度目か、軽く頭を振る。
「どうしたんだろうな、俺は」
ポツリと呟き、俺は何となく近くの電柱を見る。
そこには一枚の張り紙が貼られていた。
今まで特に気に掛けたことはなかったが、もう随分と昔からそこに貼ってあるような気がする。
俺は引き寄せられるようにして、その張り紙が貼られた電柱へと近づいた。
しわくちゃのビニル袋に入れられたその張り紙は、風雨によって酸化し、十分すぎるほどに黄ばんでしまっていた。拳大ほどの染みがいくつもできている。
その張り紙には、少女の顔写真がアップで写し出されていた。写真の上には大きなゴシック体で
『探しています』
と印字してある。
どうやら行方不明になっている女の子のようだ。
俺はその写真の女の子をじっと見つめた。
インクが滲んで見にくくなっているが、ちょうど二年前の初音を思い出させるような、そんな容姿の女の子だった。
……はあと、小さくため息をつき、俺は夏の空を仰ぎ見る。
夏の昼は長い。頭上には雲一つない目に染みるような青空が広がっている。そんな透き通るような空の中を、トンビが一羽、羽を広げながら悠々と飛んでいた。
そんな光景を、俺はしばらくただ茫然と眺めた。
が、ふと、
『昨日この近くで火事があったみたいだな』
今朝の自分の言葉が、頭の中をよぎってきた。
そういえば、火事のあった現場ってこの近くだったような……
俺はズボンのポケットから携帯を取り出し、時刻を確認する。
時刻は午後四時を少し回ったところだった。
「………」
どうせ家に帰っても大してすることはない。夕飯までにもまだ時間はある。
俺の中で、小さな好奇心が芽生えた。
不謹慎かもしれないが、暇つぶしに寄ってみるにはちょうどいいかもしれない。
俺は火事のあった現場へと足を向けてみることにした。
だが、この時の軽率な判断が、後に俺の人生を大きく左右することになるとは、今の俺には知る由もなかった。
# # #
「ここ……か」
途中道に迷ったこともあり、俺は一時間ほどかけてようやく目的地に到着した。あれほど青かった空には既に赤みがかかり、眩しいほどの夕陽が俺の顔を照らしている。
だが現場を前にするや否や、俺は言葉を失っていた。
そこは、ひどく重々しい空気に包まれていた。まだ日は沈んでいないというのに周囲には人っ子一人見当たらず、辺りは閑散としている。まるでこの場所だけ、世界から隔絶された空間のようだった。
全焼した家は、俺が予想していたよりも遥かに無残な姿になっていた。
家の原形はない。木造だったのだろうか、屋根や壁は完全に剥がれ落ち、中の骨組みが露わになっている。その骨組みのほとんどは煤で真っ黒になり、灰の降り積もった地面に横たわっていた。
辛うじて残存している物といえば、家を土台から支えていた極太の支柱だけだった。それらは荒廃した土地の上に不気味なオブジェを作り出しており、真っ赤な夕陽とのコントラストを生み出すことで、今なお激しく燃え上がっているような光景を作り出していた。
思わず息を呑む。まるで地獄絵図のようだと思った。
こんな場所に軽い気持ちでやって来てしまったことを、俺は早くも後悔し始めていた。
……しかし、俺の足は自然とその荒廃した土地へと動いた。まるで見えない糸で引き寄せられるように、俺の意識はその土地へ吸い寄せられていた。
誰も見ていないことを確認すると、俺は真っ黒な土地へと足を踏み入れる。
が、その時、
「何をしているのですか」
前方から声を掛けられた。
ビクッ、と身体が跳ねる。
弾かれたように顔を上げた。
警察の人でもいたのかと焦った。
だが、そんな俺の不安は杞憂に終わった。
少し離れた場所に一人の少女の姿を認めたからだ。
その少女は夕日をバックにして、ちょうど荒廃した土地の真ん中あたりに佇んでいた。その横には煤で汚れきった大きな柱が立っている。
どうやら先ほどは、ちょうどその柱の影になって、彼女の姿は見えていなかったようだ。
彼女は、俺の高校と同じデザインの制服を着ていた。白のセーラー服に、膝上まで下ろされた紺のスカート。胸には藍色のスカーフを付けている。
同じ学校に通う学生だ。少なくとも警察官などではない。
俺はホッと肩を下ろし、その少女をまじまじと観察した。
……彼女は小柄で、そしてとても端正な顔つきをしていた。
前髪から除く、黒い大きな瞳。太陽光を反射させる綺麗な黒髪は肩のあたりまで伸びており、頭の両端には純白のリボンが結ばれていた。風が吹く度にそのリボンはひらひらと揺れ、軽やかなリズムを創り出している。
夏の夕日を背にそこに佇む少女の姿は、何故だかとても神秘的に見えた。
「何をしているのかと訊いているのですが」
思わず少女の姿に見とれていると、彼女の方から再び声を掛けられた。
そこで俺ははっと我に返り、
「あ、いや、何って……お前こそ、こんな所で何してるんだよ」
慌てて質問に質問で返してしまった。
すると、
「質問を質問で返さないでください。私が先に質問したのですから、まずは私の質問に答えるべきです」
淡々とした口調でそう窘められた。
怒っているような様子は……ない。しかし、怒っていない様子も……ない。表情がまるで読めないのだ。
目の前の少女は無表情だった。人としての感情がほとんど感じられない。何を考えているのかが全く読めない。
そんな彼女に、俺は少し戸惑いながら、
「俺は、別に何もしてないよ。ちょっと興味があったから、寄ってみただけだ。昨日のニュースでも取り上げられてたし、どんな感じになってるのかなって思って……」
と、曖昧な答えを返した。
すると、目の前の彼女は急に興味を失ったように、
「そうですか。では早いところこの場から立ち去ってください。そんなところに突っ立っていられると、集中できません」
と、抑揚のない口調でそう言ってきた。
「集中……?」
俺は思わず聞き返す。
「集中って、お前そこで何してたんだよ?」
俺がそう訊くと、彼女は少し気分を害したように眉を寄せ、
「先ほどからお前お前と失礼ですね。私と同じ学校の生徒のようですが、何年生ですか? 私は三年生です」
「えっ―――?」
俺は思わず、声に出して驚いてしまう。
「何ですか?」
少女の眉間の皺が深くなる。
「あ、いや……」
まさかこんな華奢な少女が、自分よりも一つ上の先輩だとは思いもしなかったのだ。
彼女のことは学校でも見かけたことがなかった。少なくとも同学年ではないことは確かであったので、てっきり後輩だと思い込んでいたのだ。
「……何か、失礼なことを考えていますね」
「あっ……いや、そんなことは……」
「隠さなくても結構です。どうせ小さくて三年生には見えない、とでも思っていたのでしょう」
ずばりと俺の心の中を当ててくる。
「……よくわかったな」
俺は素直に認めた。
「やっぱり……」
少女の眼光が少し鋭くなる。
「馬鹿にしないでください。これでも、普通の高校生よりは人生経験を積んできているつもりです」
「いや、別に馬鹿にはしてないけど……」
「……まあ、いいですけど」
ふっと彼女が息を吐く。
「……それで、あなたは一体どなたなのですか?」
仕切り直すように彼女が言った。
「えっ、あーえと……時坂だよ。二年の時坂だ」
「そうですか。ならちゃんと敬語を使ってください。年上の人を敬うことは大切なことです」
「あー……まあ、そうだな」
「……何か?」
「いや……何ていうかさ、あんたからは先輩らしいオーラが全然感じられないなと思って……」
「―――あなたは、本当に失礼な人ですね」
明らかにバカにされたとわかった彼女は、先ほどよりも鋭い眼光で俺のことを睨みつけてきた。
「あなたからは、教養というものがまるで感じられません」
「まあ、いいじゃねーか。こっちのほうがしっくりくるんだよ」
俺は笑って受け流した。
「てかそれを言ったら、何であんたは俺に対して敬語なんだよ」
「……私のことは気にしないでください。これは昔からの癖のようなものです……」
「へえ……親が厳しかったとか?」
「まあ、そんなところです」
「ふーん……」
親が厳しくて昔からの癖だということは、彼女は家でもこの口調なのだろうか。
少し変わった奴だなと思った。
「私のことはどうでもいいです。それよりも、あなたはもう少し礼節を弁えてください」
「いや、そんなに気にすることでもないだろ。歳の差一つで何が変わるっていうんだよ」
俺は肩をすくめてそう言った。
「……本当に、あなたからは教養が感じられませんね」
「それはお互い様だな。俺もあんたからは先輩としての風格が感じられないよ」
互いに憎まれ口を叩く。
しばらくの間、俺たちは睨み合うように視線をぶつけていた。
だがやがて、
「……はあ、もういいです。好きにしてください」
こんなことで、いつまでも言い争っているのがバカらしくなったのか、彼女の方が先に折れた。
「あなたには、何を言っても無駄だということがよくわかりました」
諦めたように視線を落とす。
……少し調子に乗りすぎただろうか……?
「悪い。ちょっと言い過ぎだよ」
「別に……気にしていません」
「ていうか、お前はここで何やってたんだよ。何かに集中してたみたいなこと言ってたけど……」
話題を変えるついでに、俺は気になっていたことを彼女に訊ねた。
「……私ですか?」
彼女が顔を上げる。
「もしかして、あんたも興味本位でここに寄ってみたのか?」
「………」
俺が訊くと、彼女はまた視線を地面に落としてしまった。
……相変わらずの無表情。そこから彼女の心情を読み解くことは難しい。しかし、今の彼女の顔には、どことなく暗い影が落ちているように見えた。
しばらくの間、彼女は黙っていたが、やがてゆっくりとその小さな口を開いた。
「私は……ここであることを調べていたんです」
「調べてた? って何を?」
「ここで起きた火事のことを、です」
「……そんなこと、調べてどうするんだよ?」
「もちろん犯人を見つけるんですよ」
「……は?」
予想していなかった彼女の答えに、俺は思わず素っ頓狂な声を上げてしまう。
「犯人を見つけるって……どういうことだよ……?」
「そのままの意味です。昨日ここで起こった火災は間違いなく放火です。私は、その犯人を見つけ出そうとしています」
真面目な顔で彼女は言った。
「えっ、いやいや、ちょっと待てよ」
俺は困惑する。
「放火って、何ではっきりそう言い切れるんだよ。朝のニュースでもまだ放火とは断定して―――」
「―――放火ですよ」
俺の言葉を遮り、静かな声音で彼女が言い切った。
ビクリと俺の身体が震える。
「少なくとも、私はそう確信しています」
有無を言わせない口調だった。
先ほどまでの彼女とは、何かが違った。
「だから……なんでそう言い切れるんだよ」
嫌な汗が額に滲む。身体が強張り、俺は無意識のうちに拳を握り締めていた。
彼女の答えを待つ。
しかし、次に彼女から返ってきたのは、拍子抜けする返答だった。
すぐ隣にみらいがいることにすっかり慣れきってしまっていたので、今もふとした拍子に何もない空間に向かって話しかけそうになってしまう。
傍から見るとかなりヤバイ奴だ。
そんな衝動を抑えながら、俺は今朝の出来事を思い返していた。
生徒が一人亡くなった。それも俺のクラスメイトが……。
何故彼女は、あんなところで亡くなっていたのだろう。死因はわかっていないとのことだったが、何らかの持病でも抱えていたのだろうか……?
今朝からそのことが頭の片隅にこびりついて離れなかった。
何故だか無性に、彼女の亡くなった原因について気になっている自分がいたのだ。理由はよくわからない。こうして色々詮索すること自体が、亡くなった彼女に対して失礼だという認識は持ち合わせているのだが、それでも、知りたいという欲求を俺は抑えきれずにいた。
今日何度目か、軽く頭を振る。
「どうしたんだろうな、俺は」
ポツリと呟き、俺は何となく近くの電柱を見る。
そこには一枚の張り紙が貼られていた。
今まで特に気に掛けたことはなかったが、もう随分と昔からそこに貼ってあるような気がする。
俺は引き寄せられるようにして、その張り紙が貼られた電柱へと近づいた。
しわくちゃのビニル袋に入れられたその張り紙は、風雨によって酸化し、十分すぎるほどに黄ばんでしまっていた。拳大ほどの染みがいくつもできている。
その張り紙には、少女の顔写真がアップで写し出されていた。写真の上には大きなゴシック体で
『探しています』
と印字してある。
どうやら行方不明になっている女の子のようだ。
俺はその写真の女の子をじっと見つめた。
インクが滲んで見にくくなっているが、ちょうど二年前の初音を思い出させるような、そんな容姿の女の子だった。
……はあと、小さくため息をつき、俺は夏の空を仰ぎ見る。
夏の昼は長い。頭上には雲一つない目に染みるような青空が広がっている。そんな透き通るような空の中を、トンビが一羽、羽を広げながら悠々と飛んでいた。
そんな光景を、俺はしばらくただ茫然と眺めた。
が、ふと、
『昨日この近くで火事があったみたいだな』
今朝の自分の言葉が、頭の中をよぎってきた。
そういえば、火事のあった現場ってこの近くだったような……
俺はズボンのポケットから携帯を取り出し、時刻を確認する。
時刻は午後四時を少し回ったところだった。
「………」
どうせ家に帰っても大してすることはない。夕飯までにもまだ時間はある。
俺の中で、小さな好奇心が芽生えた。
不謹慎かもしれないが、暇つぶしに寄ってみるにはちょうどいいかもしれない。
俺は火事のあった現場へと足を向けてみることにした。
だが、この時の軽率な判断が、後に俺の人生を大きく左右することになるとは、今の俺には知る由もなかった。
# # #
「ここ……か」
途中道に迷ったこともあり、俺は一時間ほどかけてようやく目的地に到着した。あれほど青かった空には既に赤みがかかり、眩しいほどの夕陽が俺の顔を照らしている。
だが現場を前にするや否や、俺は言葉を失っていた。
そこは、ひどく重々しい空気に包まれていた。まだ日は沈んでいないというのに周囲には人っ子一人見当たらず、辺りは閑散としている。まるでこの場所だけ、世界から隔絶された空間のようだった。
全焼した家は、俺が予想していたよりも遥かに無残な姿になっていた。
家の原形はない。木造だったのだろうか、屋根や壁は完全に剥がれ落ち、中の骨組みが露わになっている。その骨組みのほとんどは煤で真っ黒になり、灰の降り積もった地面に横たわっていた。
辛うじて残存している物といえば、家を土台から支えていた極太の支柱だけだった。それらは荒廃した土地の上に不気味なオブジェを作り出しており、真っ赤な夕陽とのコントラストを生み出すことで、今なお激しく燃え上がっているような光景を作り出していた。
思わず息を呑む。まるで地獄絵図のようだと思った。
こんな場所に軽い気持ちでやって来てしまったことを、俺は早くも後悔し始めていた。
……しかし、俺の足は自然とその荒廃した土地へと動いた。まるで見えない糸で引き寄せられるように、俺の意識はその土地へ吸い寄せられていた。
誰も見ていないことを確認すると、俺は真っ黒な土地へと足を踏み入れる。
が、その時、
「何をしているのですか」
前方から声を掛けられた。
ビクッ、と身体が跳ねる。
弾かれたように顔を上げた。
警察の人でもいたのかと焦った。
だが、そんな俺の不安は杞憂に終わった。
少し離れた場所に一人の少女の姿を認めたからだ。
その少女は夕日をバックにして、ちょうど荒廃した土地の真ん中あたりに佇んでいた。その横には煤で汚れきった大きな柱が立っている。
どうやら先ほどは、ちょうどその柱の影になって、彼女の姿は見えていなかったようだ。
彼女は、俺の高校と同じデザインの制服を着ていた。白のセーラー服に、膝上まで下ろされた紺のスカート。胸には藍色のスカーフを付けている。
同じ学校に通う学生だ。少なくとも警察官などではない。
俺はホッと肩を下ろし、その少女をまじまじと観察した。
……彼女は小柄で、そしてとても端正な顔つきをしていた。
前髪から除く、黒い大きな瞳。太陽光を反射させる綺麗な黒髪は肩のあたりまで伸びており、頭の両端には純白のリボンが結ばれていた。風が吹く度にそのリボンはひらひらと揺れ、軽やかなリズムを創り出している。
夏の夕日を背にそこに佇む少女の姿は、何故だかとても神秘的に見えた。
「何をしているのかと訊いているのですが」
思わず少女の姿に見とれていると、彼女の方から再び声を掛けられた。
そこで俺ははっと我に返り、
「あ、いや、何って……お前こそ、こんな所で何してるんだよ」
慌てて質問に質問で返してしまった。
すると、
「質問を質問で返さないでください。私が先に質問したのですから、まずは私の質問に答えるべきです」
淡々とした口調でそう窘められた。
怒っているような様子は……ない。しかし、怒っていない様子も……ない。表情がまるで読めないのだ。
目の前の少女は無表情だった。人としての感情がほとんど感じられない。何を考えているのかが全く読めない。
そんな彼女に、俺は少し戸惑いながら、
「俺は、別に何もしてないよ。ちょっと興味があったから、寄ってみただけだ。昨日のニュースでも取り上げられてたし、どんな感じになってるのかなって思って……」
と、曖昧な答えを返した。
すると、目の前の彼女は急に興味を失ったように、
「そうですか。では早いところこの場から立ち去ってください。そんなところに突っ立っていられると、集中できません」
と、抑揚のない口調でそう言ってきた。
「集中……?」
俺は思わず聞き返す。
「集中って、お前そこで何してたんだよ?」
俺がそう訊くと、彼女は少し気分を害したように眉を寄せ、
「先ほどからお前お前と失礼ですね。私と同じ学校の生徒のようですが、何年生ですか? 私は三年生です」
「えっ―――?」
俺は思わず、声に出して驚いてしまう。
「何ですか?」
少女の眉間の皺が深くなる。
「あ、いや……」
まさかこんな華奢な少女が、自分よりも一つ上の先輩だとは思いもしなかったのだ。
彼女のことは学校でも見かけたことがなかった。少なくとも同学年ではないことは確かであったので、てっきり後輩だと思い込んでいたのだ。
「……何か、失礼なことを考えていますね」
「あっ……いや、そんなことは……」
「隠さなくても結構です。どうせ小さくて三年生には見えない、とでも思っていたのでしょう」
ずばりと俺の心の中を当ててくる。
「……よくわかったな」
俺は素直に認めた。
「やっぱり……」
少女の眼光が少し鋭くなる。
「馬鹿にしないでください。これでも、普通の高校生よりは人生経験を積んできているつもりです」
「いや、別に馬鹿にはしてないけど……」
「……まあ、いいですけど」
ふっと彼女が息を吐く。
「……それで、あなたは一体どなたなのですか?」
仕切り直すように彼女が言った。
「えっ、あーえと……時坂だよ。二年の時坂だ」
「そうですか。ならちゃんと敬語を使ってください。年上の人を敬うことは大切なことです」
「あー……まあ、そうだな」
「……何か?」
「いや……何ていうかさ、あんたからは先輩らしいオーラが全然感じられないなと思って……」
「―――あなたは、本当に失礼な人ですね」
明らかにバカにされたとわかった彼女は、先ほどよりも鋭い眼光で俺のことを睨みつけてきた。
「あなたからは、教養というものがまるで感じられません」
「まあ、いいじゃねーか。こっちのほうがしっくりくるんだよ」
俺は笑って受け流した。
「てかそれを言ったら、何であんたは俺に対して敬語なんだよ」
「……私のことは気にしないでください。これは昔からの癖のようなものです……」
「へえ……親が厳しかったとか?」
「まあ、そんなところです」
「ふーん……」
親が厳しくて昔からの癖だということは、彼女は家でもこの口調なのだろうか。
少し変わった奴だなと思った。
「私のことはどうでもいいです。それよりも、あなたはもう少し礼節を弁えてください」
「いや、そんなに気にすることでもないだろ。歳の差一つで何が変わるっていうんだよ」
俺は肩をすくめてそう言った。
「……本当に、あなたからは教養が感じられませんね」
「それはお互い様だな。俺もあんたからは先輩としての風格が感じられないよ」
互いに憎まれ口を叩く。
しばらくの間、俺たちは睨み合うように視線をぶつけていた。
だがやがて、
「……はあ、もういいです。好きにしてください」
こんなことで、いつまでも言い争っているのがバカらしくなったのか、彼女の方が先に折れた。
「あなたには、何を言っても無駄だということがよくわかりました」
諦めたように視線を落とす。
……少し調子に乗りすぎただろうか……?
「悪い。ちょっと言い過ぎだよ」
「別に……気にしていません」
「ていうか、お前はここで何やってたんだよ。何かに集中してたみたいなこと言ってたけど……」
話題を変えるついでに、俺は気になっていたことを彼女に訊ねた。
「……私ですか?」
彼女が顔を上げる。
「もしかして、あんたも興味本位でここに寄ってみたのか?」
「………」
俺が訊くと、彼女はまた視線を地面に落としてしまった。
……相変わらずの無表情。そこから彼女の心情を読み解くことは難しい。しかし、今の彼女の顔には、どことなく暗い影が落ちているように見えた。
しばらくの間、彼女は黙っていたが、やがてゆっくりとその小さな口を開いた。
「私は……ここであることを調べていたんです」
「調べてた? って何を?」
「ここで起きた火事のことを、です」
「……そんなこと、調べてどうするんだよ?」
「もちろん犯人を見つけるんですよ」
「……は?」
予想していなかった彼女の答えに、俺は思わず素っ頓狂な声を上げてしまう。
「犯人を見つけるって……どういうことだよ……?」
「そのままの意味です。昨日ここで起こった火災は間違いなく放火です。私は、その犯人を見つけ出そうとしています」
真面目な顔で彼女は言った。
「えっ、いやいや、ちょっと待てよ」
俺は困惑する。
「放火って、何ではっきりそう言い切れるんだよ。朝のニュースでもまだ放火とは断定して―――」
「―――放火ですよ」
俺の言葉を遮り、静かな声音で彼女が言い切った。
ビクリと俺の身体が震える。
「少なくとも、私はそう確信しています」
有無を言わせない口調だった。
先ほどまでの彼女とは、何かが違った。
「だから……なんでそう言い切れるんだよ」
嫌な汗が額に滲む。身体が強張り、俺は無意識のうちに拳を握り締めていた。
彼女の答えを待つ。
しかし、次に彼女から返ってきたのは、拍子抜けする返答だった。
0
お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説

魂(たま)抜き地蔵
Hiroko
ホラー
遠い過去の記憶の中にある五体の地蔵。
暗く濡れた山の中、私はなぜ母親にそこに連れて行かれたのか。
このお話は私の考えたものですが、これは本当にある場所で、このお地蔵さまは実在します。写真はそのお地蔵さまです。あまりアップで見ない方がいいかもしれません。
短編ホラーです。
ああ、原稿用紙十枚くらいに収めるつもりだったのに……。
どんどん長くなってしまいました。

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る
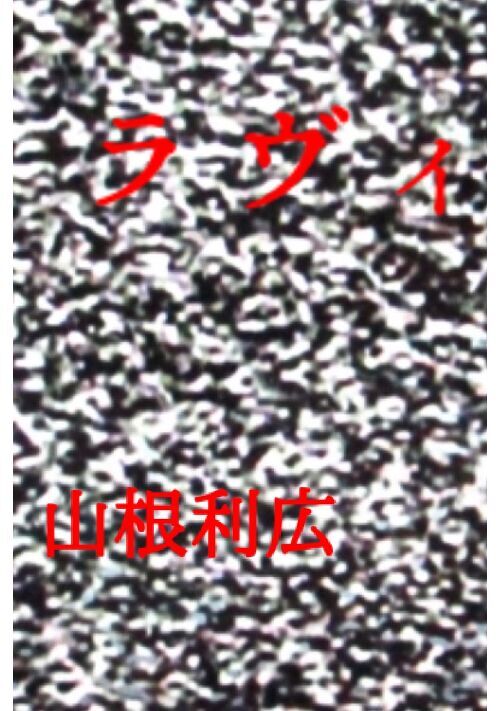
ラヴィ
山根利広
ホラー
男子高校生が不審死を遂げた。
現場から同じクラスの女子生徒のものと思しきペンが見つかる。
そして、解剖中の男子の遺体が突如消失してしまう。
捜査官の遠井マリナは、この事件の現場検証を行う中、奇妙な点に気づく。
「七年前にわたしが体験した出来事と酷似している——」
マリナは、まるで過去をなぞらえたような一連の展開に違和感を覚える。
そして、七年前同じように死んだクラスメイトの存在を思い出す。
だがそれは、連環する狂気の一端にすぎなかった……。

何かを喪失するAI話
月歌(ツキウタ)
ホラー
何かを喪失するAI話。AIが作ったので、喪失の意図は分かりませんw
☆月歌ってどんな人?こんな人↓↓☆
『嫌われ悪役令息は王子のベッドで前世を思い出す』が、アルファポリスの第9回BL小説大賞にて奨励賞を受賞(#^.^#)
その後、幸運な事に書籍化の話が進み、2023年3月13日に無事に刊行される運びとなりました。49歳で商業BL作家としてデビューさせていただく機会を得ました。
☆表紙絵、挿絵は全てAIイラスです
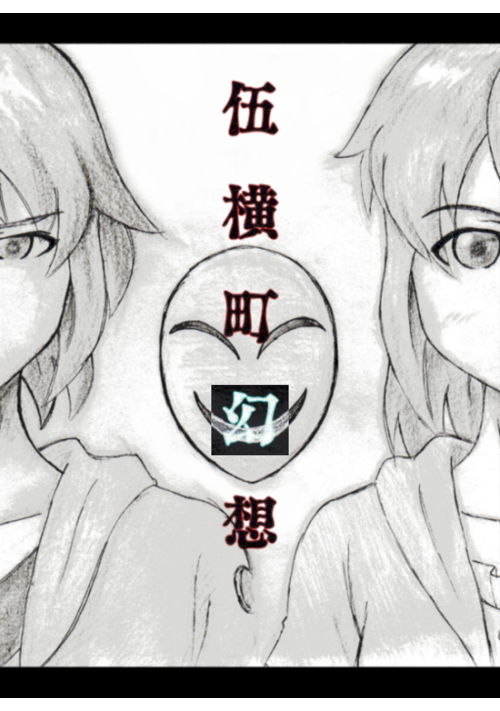
【連作ホラー】伍横町幻想 —Until the day we meet again—
至堂文斗
ホラー
――その幻想から、逃れられるか。
降霊術。それは死者を呼び出す禁忌の術式。
歴史を遡れば幾つも逸話はあれど、現実に死者を呼ぶことが出来たかは定かでない。
だがあるとき、長い実験の果てに、一人の男がその術式を生み出した。
降霊術は決して公に出ることはなかったものの、書物として世に残り続けた。
伍横町。そこは古くから気の流れが集まる場所と言われている小さな町。
そして、全ての始まりの町。
男が生み出した術式は、この町で幾つもの悲劇をもたらしていく。
運命を狂わされた者たちは、生と死の狭間で幾つもの涙を零す。
これは、四つの悲劇。
【魂】を巡る物語の始まりを飾る、四つの幻想曲――。
【霧夏邸幻想 ―Primal prayer-】
「――霧夏邸って知ってる?」
事故により最愛の娘を喪い、 降霊術に狂った男が住んでいた邸宅。
霊に会ってみたいと、邸内に忍び込んだ少年少女たちを待ち受けるものとは。
【三神院幻想 ―Dawn comes to the girl―】
「どうか、目を覚ましてはくれないだろうか」
眠りについたままの少女のために、 少年はただ祈り続ける。
その呼び声に呼応するかのように、 少女は記憶の世界に覚醒する。
【流刻園幻想 ―Omnia fert aetas―】
「……だから、違っていたんだ。沢山のことが」
七不思議の噂で有名な流刻園。夕暮れ時、教室には二人の少年少女がいた。
少年は、一通の便箋で呼び出され、少女と別れて屋上へと向かう。それが、悲劇の始まりであるとも知らずに。
【伍横町幻想 ―Until the day we meet again―】
「……ようやく、時が来た」
伍横町で降霊術の実験を繰り返してきた仮面の男。 最愛の女性のため、彼は最後の計画を始動する。
その計画を食い止めるべく、悲劇に巻き込まれた少年少女たちは苛酷な戦いに挑む。
伍横町の命運は、子どもたちの手に委ねられた。

怪異相談所の店主は今日も語る
くろぬか
ホラー
怪異相談所 ”語り部 結”。
人に言えない“怪異”のお悩み解決します、まずはご相談を。相談コース3000円~。除霊、その他オプションは状況によりお値段が変動いたします。
なんて、やけにポップな看板を掲げたおかしなお店。
普通の人なら入らない、入らない筈なのだが。
何故か今日もお客様は訪れる。
まるで導かれるかの様にして。
※※※
この物語はフィクションです。
実際に語られている”怖い話”なども登場致します。
その中には所謂”聞いたら出る”系のお話もございますが、そういうお話はかなり省略し内容までは描かない様にしております。
とはいえさわり程度は書いてありますので、自己責任でお読みいただければと思います。

シゴ語り
泡沫の
ホラー
治安も土地も悪い地域に建つ
「先端技術高校」
そこに通っている主人公
獅子目 麗と神陵 恵玲斗。
お互い、関わることがないと思っていたが、些細なことがきっかけで
この地域に伝わる都市伝説
「シシ語り」を調べることになる…。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















