40 / 46
届かぬ心(1)☆
しおりを挟む
「……え……」
そこには、それまでリーエンが見たことがない姿のアルフレドが立っていた。角はもう慣れた。だが。あると聞いていたが一度も見せてもらったことがなかった黒い翼、そして、形は想像すらしていなかったものの、きっと想像してもそうだとは思わなかった形の黒い尻尾。それは、コーバスのものよりは細く、けれども長さがあって床に這っている。彼は全裸だったが、不思議なもので角と翼と尻尾が揃っているせいか、服を着ていないことが当たり前にすら見える。
それから、これは聞いていなかったが、右の太ももの横と左のふくらはぎ外側に、見たことがない黒い文様が浮かび上がっている。もし、リーエンが「入れ墨」というものを知っていれば「そうなのかも」と思ったかもしれない。だが、彼のそれは生まれつきのもので、魔王の眷属でも力が強い者に時折見られる先天性の「何か」で、翼や尻尾のように普段は消している。リーエンは「何か」をそのまま素直に「よくわからない模様」と思うだけだ。
これが彼の本当の姿なのか、とリーエンは驚きつつ必死に声を絞り出した。
「ど、う、なさった、のですか。まだ……」
まだ、ヴィンスから作ってもらった工程表では会わないことになっていたのでは……そう続けようとしたが、アルフレドに言葉を遮られた。
「お前が俺を呼んだんだろう」
「え……」
「お前が俺に、お前を抱けと呼んだ」
「……っ!……」
次の瞬間、アルフレドはリーエンの腕を強引に掴むと、そのまま床に彼女をねじ伏せた。突然のことに何が起きているのかリーエンは理解が出来ず、床の硬さを背に感じながら唇をわななかせた。彼がここまで暴力的なことを自分にしたことはない、と思えば声が震える。
「アルフレド様っ……」
「違うか? 違うなら、違うと言え。俺はお前を抱きたくて、お前は俺に抱かれたくて俺を呼んだんだろう? 何もおかしいことはないはずだが、違うのか?」
「わ、わたし……わたしっ……」
「違わないだろうが。誘ったのはお前の方だ……泣いていたのか。どうした。泣くほど、抱かれたかったのか」
床で組み敷かれるような屈辱をリーエンは味わったことがなかった。だが、それよりも「泣くほど抱かれたかった」という彼の言葉を否定したくて仕方がない。
「ちが、違います、そうではありませんっ……」
「違うのか。では、何故泣いていた?」
「あっ……」
アルフレドの舌がリーエンの頬を這う。涙を舐めとられながら、彼の舌の感触に身をすくませるリーエン。怖い。でも、彼に会えて嬉しい。でも、怖い。アルフレドは片手でリーエンの腕を床に押しつけ、膝で彼女の腰を挟みこんで彼女を逃がすまいとする。そんな荒っぽいことをしているのに、慈しむようにリーエンの髪を撫でながら彼女の顎まで唇を這わせると、軽く首筋を噛む。
そうこうしているうちに、扉の外がやたら騒がしくなってきた。ヴィンスを先頭として何人かががやがやと集まって来たのだろう。
「アルフレド様! アルフレド様、おやめください!」
「アルフレド様、お戻りください!」
「リーエン様、ご無事ですか!?」
その声にアルフレドは舌打ちをする。そんな風に舌打ちをする彼は見たことがない。それは、彼がインキュバス寄りになっているからなのだろうとリーエンはそんなところだけやたらと冷静に理解をした。また、何かの術でこの部屋に人々が入れないようにしているのだろうとも。
「うるさいな……くそ、場所を移そうが、やつらは俺の魔力を追ってくるしどうしようもない。音を消すか。それとも蹴散らしてくるか……」
「待って、アルフレド様、待ってください」
「ん?」
「わたしがお話してきますから、すぐに、すぐに戻りますからお願いです……一度……放してください……」
「10秒だ。10秒で戻れ」
そんな乱暴なことを言うなんて、どれほどアルフレドは制御を手放してしまっているのか。リーエンはそう思いながら体を起こし、慌てて扉に駆け寄った。扉を開けようとしてもまったく動かないことに気付き、声を張り上げる。
「皆様! わたしは大丈夫です! 大丈夫ですから、お戻りください!」
扉の向こうは静まり返り、ヴィンスの声だけが返って来た。
「大丈夫ではありませんぞ。まだアルフレド様は安定していません。このままではあなた様を無理矢理……」
「わかっています。もう、覚悟は出来ています。アルフレド様の思うままに……していただこうと思っておりますから……」
リーエンのその言葉に扉の向こうは完全に静まり返った。彼女の言葉の意味を全員が理解したとは思えなかったが、少なくともヴィンスはわかってくれていると思う。
「遅い」
アルフレドはそう言って、扉に向かっているリーエンを後ろから扉に押し付けた。
「っ……」
寝間着越しのリーエンの尻に、既に固くなっている彼のものがあてがわれる。彼のペニスは人間のものと違って、ぼこぼこといぼのようなものに覆われており少しばかりグロテスクだ。それをぐいぐいと押し付けられる暴力的な行為にリーエンは一瞬だけ体を強張らせたが、もう一度ヴィンス達に向かって声をあげた。
「大丈夫ですから、お戻りになって……っ……んっ……」
後ろから強い力で抱きしめられ、熱を帯びた大きな手が無遠慮に布の上からリーエンの胸を鷲掴みにする。そのまま、もう片方の手はするりと寝間着の上を滑ってリーエンの股間に降りていく。ここまであからさまに体だけを求められたことは初日だってなかった、と思う。
「すぐにでも、お前を孕ませたい……」
首筋に彼の顔が埋められ、低い声が耳に届く。たったそれだけで、リーエンは体を震わせる。おしつけられる体から伝わる熱と耳の奥に響く粗暴な言葉は、どちらも体の奥でくすぶる官能を引き摺り出すようだ。だが、本当に体を求められるだけなら、すぐにでも寝間着を破かれ足を開かされるのだろうし、まだ話は出来るのではないかと気付く。リーエンはすがるように
「あの、あの……せめてっ……寝室へ」
と懇願した。
「寝室? そんなものになんの意味がある……?」
「わたしの体はアルフレド様ほど強くありませんので、負担を減らしていただけますと助かります……」
自分でもどうかと思う言い訳だったが、こういう形でしかきっと彼を納得させられないと思う。案の定、特に何も言わずにアルフレドはひょいとリーエンを小脇に抱え――今まで彼に抱き上げられる時は両腕で支えられていたのにまるで荷物のように――寝室へ向かった。こんな状態でも寝室がどこなのかは理解しているのだな、とか、片腕で自分を持ち上げるなんてとんでもない力だ、とか、リーエンは「比較的どうでもいいこと」を考えて自分を必死に落ち着かせようとする。
「……あ、あ、あ、あ……!」
ベッドに雑に投げ出されたと思うと、すぐさまアルフレドが覆い被さってきて性急にリーエンの体をまさぐる。やはり、そこには愛情を感じられない。体以外に興味がない、孕ませることしか考えていないようだ。駄目か……リーエンはいくばくかの悲しみを感じつつ唇を震わせた。
「アルフレド様、待って……脱ぎます、から」
このままではきっとすぐに寝間着を破られるだろう。それを女中に見られればアルフレドがリーエンに無体を強いたと思われるだろうし、いや、それは間違ってもいないのだが、この行為自体はもうリーエンの合意の上なのだし……とこんな時ですら気を回してしまう。
「自分で脱ぐほど、抱かれたくて仕方がないのか」
「そういう、そういうことでは、ない、です……」
「嘘だ。お前は俺に抱かれたいと思ったんだろうが。だから俺は来たのに、何故それを否定する? 恥ずかしいからか?」
「本当に……わたしが、抱かれたいと思ったから、アルフレド様はここにいらしたのですか……?」
「そうだ。ずっとずっと、お前がいることをわかっていて、だが、手を出してはいけないと止め続けていたのに。お前が、俺を呼んだんだろうが……早く脱げ」
最後の一言は彼にしては随分威圧的だったが、リーエンはそのことよりも、自分が彼に抱かれたいとそんなに強く思っていたのだろうか、という自問自答と、彼がずっと我慢をし続けていたことを今更ながら強く感じ、それらの感情のおかげで彼への恐れは強くは感じない。それに、どれほど人が変わっていてもアルフレドはアルフレドなのだし。
少し震える手で寝間着を脱ぐ。自分から男性の前で衣類をはだけることは初めてのことで、もう体を見られた相手だというのに、羞恥と緊張でリーエンの鼓動は高鳴る。思いのほかアルフレドは静かに彼女を待っているが、その視線はリーエンの体にまとわりつくようだ。
令嬢として大事に育てられた白い裸体。痩せすぎてもいなければ、ふくよかすぎでもない、何もかも平均といわれそうな女性らしい体。それを覆う最後の下着に手にかけ、ゆっくりと脱ぐ。少しでも時間が稼げれば、もしかしたらアルフレドはいつもの彼に戻ってくれるのではないかと一縷の望みをかけながら、するりと足をそれから抜いた。だが、アルフレドはリーエンのそんな思いは関係ないとばかりに、彼女が手にした下着を強引に奪ってすぐに床に投げ捨てる。
それから、リーエンの腕に光るバングルを見て「お前に触れるのに邪魔だ」と手をかざし、リーエンの意思とは関係なく消してしまった。
「あ、あ、アルフレド様……」
「脱いだなら、早く抱かせろ」
「ひとつ、だけ、先に、聞いて、ください」
「なんだ」
白い肌を彼の舐めるような視線に晒しながら、リーエンは胸元を恥ずかしそうに抑えつつ、必死に言葉を紡ぐ。
「どうして、わたしがあなたに抱かれたいと思ったのか、お分かりですか……?」
それに対して、アルフレドはぴくりと眉を動かした。
「わたし、あなたのことが」
「……」
「あなたのことが、好きです」
声が震える。声も、言葉も、そして、何もかも身に纏っていない生まれたままの姿をさらしていることもあいまって、なんて情けない告白だろうと思う。悲しみと違う感情に心が揺れて、また涙がせりあがってくる。彼への気持ちを言葉にしても、それだけでは足りないとばかりにまるで感情が涙になって溢れ出ているようだ。
「あなたに触れて欲しいと思ったのは、わたしがあなたのことを……きゃっ!」
やはり、心は通じないのだろうか。体だけが全てになってしまうのだろうか。アルフレドは最後までリーエンの言葉を聞かずに、彼女をベッドに押し倒して激しく唇を貪った。
(あ、あ、あ、激しい、息が、息が苦しい、熱い、熱い、熱い……!!)
乱暴に唇を深く重ねられ、リーエンは彼の熱い舌に自分の舌を絡み取られてくぐもった苦し気な声をあげた。だが、彼は彼女を解放しない。リーエンは体を強張らせてしまい、必死に受け入れようとしてもどうして良いかわからず呼吸をすることで精一杯だ。
アルフレドは執拗なキスを続けながら、何度も何度もリーエンの髪に指を絡ませ、頭を撫で、髪を梳いて、また指を髪に差し込んで撫で、梳いてと繰り返す。その感触はリーエンを少しだけ落ち着かせ、徐々に強張った体が緩んでいく。
「んっ、ん……」
体が緩めばリーエンの舌も柔らかくなって、自然にアルフレドの舌を受け止めることが出来るようになる。はあ、と荒い息をつきながらも、リーエンは「さっきまでと違う」とキスの変化を感じ取った。違うのは自分だけではない。彼の熱い舌に彼女が自分の舌を委ねたことをアルフレドは気付いて、よりゆっくりとその感触を楽しむように、じゅっ、じゅ、と音を立てつつ、リーエンの耳に指を這わせる。
あんなにも性急に床に押し倒され、すぐにでも入れたい、孕ませたい、と言っていたはずなのに、ようやくリーエンの唇を解放したアルフレドは彼女の耳を犯し始める。
「あ、あ、あ」
片耳を噛み、舐め、吸い、音をわざと立てて羞恥を煽りながら、もう片方の耳たぶを優しく擦るアルフレド。手順を踏んだ愛撫のようなのに、覆い被さる体はぴったりとリーエンの体に触れており、絶えず彼の熱くて硬いものは彼女の腹部に押し付けられる。合わさった肌と肌は既にしっとりと湿り気を帯びていて、互いに吸い付くようだ。
「ん、んっ……」
アルフレドが動くと、彼の胸板に軽く押しつぶされているリーエンの乳房が形を変える。彼はそれをわかっているようで、わざとリーエン自身が乳房の動きを意識するようにゆっくりと押し付けるように動いた。
「あっ、あ、あ、あ」
こんな風に、最初から裸体と裸体を重ねて愛し合うのは初めてだ。夢の中でリーエンは彼の腕の中で丸まっていたため、体を捩ろうとしても動けなかった。が、今度は体を動かすたびに自分の胸が、腹部が、股間が、彼の肌の上を擦るように動く。ぐちゅぐちゅと耳を嬲られ、息を吹き込まれるたびにびくりと体を跳ねさせて自分からアルフレドの体に自分の体を押し付けてしまう。なんて恥ずかしいことを、と思う気持ちもあったが、それ以上に、彼にこうやって触れてもらっていることが嬉しいと思っていることに気付く。
(こんな、どうしようもない状況なのに)
それでも、自分を好きな、自分が好きな人が自分を欲しているのだと思うと、たとえ彼であって彼ではない状態になっていても心が打ち震えるのだとリーエンは思い知らされ、熱い息を吐きだした。すると、アルフレドは一瞬体を起こす。
「……くっ……」
苦しそうに眉根を寄せながらうめき声をあげるアルフレド。熱にうかされそうになりながらも、リーエンはそれを見逃さなかった。
「アルフレド様」
「くそ……熱い……体の内側がっ……熱すぎる……くそっ」
「まだ、魔力が落ち着いていらっしゃらないのではないですか? それに、術の取り消しでペナルティをうけて……」
「うる、さい」
「でもっ……」
「止められると思っているのか。やっと、お前が俺を求めてくれたのに、抱かないでいられるわけがないだろうが!」
アルフレドは半ば睨むような表情で、リーエンに吐き捨てるように言った。いつも穏やかで優しい彼が声を荒げるのは、あの謁見の間近くで魔族を叱責している時しかリーエンは聞いたことがない。が、彼の言葉は怒りというよりも悲しみに近いものだった。
「……!」
「お前が、お前が、俺を呼んだんだ。俺に抱かれたいと。やっとお前からそう思ってもらったのに、我慢が出来るか……!」
そう言うと、アルフレドはリーエンの体をぐいと引き起こして、ベッドの上で強く抱きしめた。その抱擁はこれまでで一番強い。ただただ、腕の中のリーエンは自分のものだと、まるで子供が好きなおもちゃの所有を主張するかのように、奪おうとする何かから守ろうとするように、彼は力を入れる。リーエンは苦しいと思いつつも、彼のその力は自分を求める心の表れだと素直に感じ取り、瞳を閉じてその身を委ねた。
(本当に、今のこの方はどうしようもない……どうしようもないのに、愛しい。こんな状態なのに、ご自分がずっと我慢していらしたことを、ちゃんと自覚なさっているんですもの)
今の彼は滅茶苦茶だ、とリーエンは呆れつつも愛しく思う。ヴィンスが心配していたのも当然ではないか。何一つうまくいっていない。ペナルティとやらで彼は今も苦しんでいるはずだ。けれど、インキュバスの制御を手放したせいで自分を抑えることも出来ない。
それらがどれほど苦しいものなのか、リーエンにはわからない。だが、そんな状態でもどこかにはいつものアルフレドの意識が存在するのだ。それをリーエンは確信した。ここにいるアルフレドは、ずっと理性で自分を抱くことを我慢してくれていた彼なのだ、と。
「お前を抱きたい。ねじこんで、打ち付けて、突き上げて、泣こうが喚こうが、中に何度でも放ちたい。抱きたい。好きだ。好きだ。好きだ……! くそ、違う。そんなことをしたいわけじゃない……!」
リーエンは強く抱かれながらもなんとか圧迫されていた腕を抜いて、アルフレドの背に腕を回した。指先に彼の翼のつけねが触れ、リーエンは「本当のお姿を見せたかったのではなく、きっと、隠していられなかったのでしょうね」と思いながらも、少しだけをそれを嬉しいと思う。
「アルフレド様、もっと、もっとおっしゃって」
「何をだ」
「わたし、わたしのことを好きって。もっとおっしゃってください。もっと」
アルフレドは彼女の腕の中で、一瞬びくりと身を竦めた。
「そんなことはっ……」
「今、口にしてくださっていました」
ふっとアルフレドはリーエンを抱いた力を緩め、顔を離して彼女を見下ろす。まるで「何を言っているんだ?」と訝しむような表情でリーエンを見る彼を彼女は見上げた。
「わたしのことを好きって、お願い、言って……」
「くそっ……好きだ」
「もっと……お願い、もっと言ってください……!」
リーエンは必死に声を張り上げて、彼に懇願した。離れてしまう心と体を少しでも繋ぎとめるには、彼の心を彼に自覚してもらうしかない。こんな時でもなければ言わない我儘をリーエンが繰り返せば、アルフレドは苦しそうに言葉を吐き出す。
「好きだ。好きだ。熱い。苦しい。だが、そんなことはどうでもいい。俺は、早くお前を……」
「アルフレド様、もう一度」
「好きだ」
「わたしも、好きです」
「……っ」
「好きです。アルフレド様、好きです。あなたが、あなたが好きです。あなたが好きだから、あなたに抱かれたいんです。だから、あなたも……わたしが好きだから、わたしを抱きたいって、そうおっしゃって……?」
お願い、と祈るような気持ちでリーエンはそう言った。だが、彼女の祈りは通じなかったのか、アルフレドは再び「うるさい」と言って、彼女をベッドに押し倒した。
そこには、それまでリーエンが見たことがない姿のアルフレドが立っていた。角はもう慣れた。だが。あると聞いていたが一度も見せてもらったことがなかった黒い翼、そして、形は想像すらしていなかったものの、きっと想像してもそうだとは思わなかった形の黒い尻尾。それは、コーバスのものよりは細く、けれども長さがあって床に這っている。彼は全裸だったが、不思議なもので角と翼と尻尾が揃っているせいか、服を着ていないことが当たり前にすら見える。
それから、これは聞いていなかったが、右の太ももの横と左のふくらはぎ外側に、見たことがない黒い文様が浮かび上がっている。もし、リーエンが「入れ墨」というものを知っていれば「そうなのかも」と思ったかもしれない。だが、彼のそれは生まれつきのもので、魔王の眷属でも力が強い者に時折見られる先天性の「何か」で、翼や尻尾のように普段は消している。リーエンは「何か」をそのまま素直に「よくわからない模様」と思うだけだ。
これが彼の本当の姿なのか、とリーエンは驚きつつ必死に声を絞り出した。
「ど、う、なさった、のですか。まだ……」
まだ、ヴィンスから作ってもらった工程表では会わないことになっていたのでは……そう続けようとしたが、アルフレドに言葉を遮られた。
「お前が俺を呼んだんだろう」
「え……」
「お前が俺に、お前を抱けと呼んだ」
「……っ!……」
次の瞬間、アルフレドはリーエンの腕を強引に掴むと、そのまま床に彼女をねじ伏せた。突然のことに何が起きているのかリーエンは理解が出来ず、床の硬さを背に感じながら唇をわななかせた。彼がここまで暴力的なことを自分にしたことはない、と思えば声が震える。
「アルフレド様っ……」
「違うか? 違うなら、違うと言え。俺はお前を抱きたくて、お前は俺に抱かれたくて俺を呼んだんだろう? 何もおかしいことはないはずだが、違うのか?」
「わ、わたし……わたしっ……」
「違わないだろうが。誘ったのはお前の方だ……泣いていたのか。どうした。泣くほど、抱かれたかったのか」
床で組み敷かれるような屈辱をリーエンは味わったことがなかった。だが、それよりも「泣くほど抱かれたかった」という彼の言葉を否定したくて仕方がない。
「ちが、違います、そうではありませんっ……」
「違うのか。では、何故泣いていた?」
「あっ……」
アルフレドの舌がリーエンの頬を這う。涙を舐めとられながら、彼の舌の感触に身をすくませるリーエン。怖い。でも、彼に会えて嬉しい。でも、怖い。アルフレドは片手でリーエンの腕を床に押しつけ、膝で彼女の腰を挟みこんで彼女を逃がすまいとする。そんな荒っぽいことをしているのに、慈しむようにリーエンの髪を撫でながら彼女の顎まで唇を這わせると、軽く首筋を噛む。
そうこうしているうちに、扉の外がやたら騒がしくなってきた。ヴィンスを先頭として何人かががやがやと集まって来たのだろう。
「アルフレド様! アルフレド様、おやめください!」
「アルフレド様、お戻りください!」
「リーエン様、ご無事ですか!?」
その声にアルフレドは舌打ちをする。そんな風に舌打ちをする彼は見たことがない。それは、彼がインキュバス寄りになっているからなのだろうとリーエンはそんなところだけやたらと冷静に理解をした。また、何かの術でこの部屋に人々が入れないようにしているのだろうとも。
「うるさいな……くそ、場所を移そうが、やつらは俺の魔力を追ってくるしどうしようもない。音を消すか。それとも蹴散らしてくるか……」
「待って、アルフレド様、待ってください」
「ん?」
「わたしがお話してきますから、すぐに、すぐに戻りますからお願いです……一度……放してください……」
「10秒だ。10秒で戻れ」
そんな乱暴なことを言うなんて、どれほどアルフレドは制御を手放してしまっているのか。リーエンはそう思いながら体を起こし、慌てて扉に駆け寄った。扉を開けようとしてもまったく動かないことに気付き、声を張り上げる。
「皆様! わたしは大丈夫です! 大丈夫ですから、お戻りください!」
扉の向こうは静まり返り、ヴィンスの声だけが返って来た。
「大丈夫ではありませんぞ。まだアルフレド様は安定していません。このままではあなた様を無理矢理……」
「わかっています。もう、覚悟は出来ています。アルフレド様の思うままに……していただこうと思っておりますから……」
リーエンのその言葉に扉の向こうは完全に静まり返った。彼女の言葉の意味を全員が理解したとは思えなかったが、少なくともヴィンスはわかってくれていると思う。
「遅い」
アルフレドはそう言って、扉に向かっているリーエンを後ろから扉に押し付けた。
「っ……」
寝間着越しのリーエンの尻に、既に固くなっている彼のものがあてがわれる。彼のペニスは人間のものと違って、ぼこぼこといぼのようなものに覆われており少しばかりグロテスクだ。それをぐいぐいと押し付けられる暴力的な行為にリーエンは一瞬だけ体を強張らせたが、もう一度ヴィンス達に向かって声をあげた。
「大丈夫ですから、お戻りになって……っ……んっ……」
後ろから強い力で抱きしめられ、熱を帯びた大きな手が無遠慮に布の上からリーエンの胸を鷲掴みにする。そのまま、もう片方の手はするりと寝間着の上を滑ってリーエンの股間に降りていく。ここまであからさまに体だけを求められたことは初日だってなかった、と思う。
「すぐにでも、お前を孕ませたい……」
首筋に彼の顔が埋められ、低い声が耳に届く。たったそれだけで、リーエンは体を震わせる。おしつけられる体から伝わる熱と耳の奥に響く粗暴な言葉は、どちらも体の奥でくすぶる官能を引き摺り出すようだ。だが、本当に体を求められるだけなら、すぐにでも寝間着を破かれ足を開かされるのだろうし、まだ話は出来るのではないかと気付く。リーエンはすがるように
「あの、あの……せめてっ……寝室へ」
と懇願した。
「寝室? そんなものになんの意味がある……?」
「わたしの体はアルフレド様ほど強くありませんので、負担を減らしていただけますと助かります……」
自分でもどうかと思う言い訳だったが、こういう形でしかきっと彼を納得させられないと思う。案の定、特に何も言わずにアルフレドはひょいとリーエンを小脇に抱え――今まで彼に抱き上げられる時は両腕で支えられていたのにまるで荷物のように――寝室へ向かった。こんな状態でも寝室がどこなのかは理解しているのだな、とか、片腕で自分を持ち上げるなんてとんでもない力だ、とか、リーエンは「比較的どうでもいいこと」を考えて自分を必死に落ち着かせようとする。
「……あ、あ、あ、あ……!」
ベッドに雑に投げ出されたと思うと、すぐさまアルフレドが覆い被さってきて性急にリーエンの体をまさぐる。やはり、そこには愛情を感じられない。体以外に興味がない、孕ませることしか考えていないようだ。駄目か……リーエンはいくばくかの悲しみを感じつつ唇を震わせた。
「アルフレド様、待って……脱ぎます、から」
このままではきっとすぐに寝間着を破られるだろう。それを女中に見られればアルフレドがリーエンに無体を強いたと思われるだろうし、いや、それは間違ってもいないのだが、この行為自体はもうリーエンの合意の上なのだし……とこんな時ですら気を回してしまう。
「自分で脱ぐほど、抱かれたくて仕方がないのか」
「そういう、そういうことでは、ない、です……」
「嘘だ。お前は俺に抱かれたいと思ったんだろうが。だから俺は来たのに、何故それを否定する? 恥ずかしいからか?」
「本当に……わたしが、抱かれたいと思ったから、アルフレド様はここにいらしたのですか……?」
「そうだ。ずっとずっと、お前がいることをわかっていて、だが、手を出してはいけないと止め続けていたのに。お前が、俺を呼んだんだろうが……早く脱げ」
最後の一言は彼にしては随分威圧的だったが、リーエンはそのことよりも、自分が彼に抱かれたいとそんなに強く思っていたのだろうか、という自問自答と、彼がずっと我慢をし続けていたことを今更ながら強く感じ、それらの感情のおかげで彼への恐れは強くは感じない。それに、どれほど人が変わっていてもアルフレドはアルフレドなのだし。
少し震える手で寝間着を脱ぐ。自分から男性の前で衣類をはだけることは初めてのことで、もう体を見られた相手だというのに、羞恥と緊張でリーエンの鼓動は高鳴る。思いのほかアルフレドは静かに彼女を待っているが、その視線はリーエンの体にまとわりつくようだ。
令嬢として大事に育てられた白い裸体。痩せすぎてもいなければ、ふくよかすぎでもない、何もかも平均といわれそうな女性らしい体。それを覆う最後の下着に手にかけ、ゆっくりと脱ぐ。少しでも時間が稼げれば、もしかしたらアルフレドはいつもの彼に戻ってくれるのではないかと一縷の望みをかけながら、するりと足をそれから抜いた。だが、アルフレドはリーエンのそんな思いは関係ないとばかりに、彼女が手にした下着を強引に奪ってすぐに床に投げ捨てる。
それから、リーエンの腕に光るバングルを見て「お前に触れるのに邪魔だ」と手をかざし、リーエンの意思とは関係なく消してしまった。
「あ、あ、アルフレド様……」
「脱いだなら、早く抱かせろ」
「ひとつ、だけ、先に、聞いて、ください」
「なんだ」
白い肌を彼の舐めるような視線に晒しながら、リーエンは胸元を恥ずかしそうに抑えつつ、必死に言葉を紡ぐ。
「どうして、わたしがあなたに抱かれたいと思ったのか、お分かりですか……?」
それに対して、アルフレドはぴくりと眉を動かした。
「わたし、あなたのことが」
「……」
「あなたのことが、好きです」
声が震える。声も、言葉も、そして、何もかも身に纏っていない生まれたままの姿をさらしていることもあいまって、なんて情けない告白だろうと思う。悲しみと違う感情に心が揺れて、また涙がせりあがってくる。彼への気持ちを言葉にしても、それだけでは足りないとばかりにまるで感情が涙になって溢れ出ているようだ。
「あなたに触れて欲しいと思ったのは、わたしがあなたのことを……きゃっ!」
やはり、心は通じないのだろうか。体だけが全てになってしまうのだろうか。アルフレドは最後までリーエンの言葉を聞かずに、彼女をベッドに押し倒して激しく唇を貪った。
(あ、あ、あ、激しい、息が、息が苦しい、熱い、熱い、熱い……!!)
乱暴に唇を深く重ねられ、リーエンは彼の熱い舌に自分の舌を絡み取られてくぐもった苦し気な声をあげた。だが、彼は彼女を解放しない。リーエンは体を強張らせてしまい、必死に受け入れようとしてもどうして良いかわからず呼吸をすることで精一杯だ。
アルフレドは執拗なキスを続けながら、何度も何度もリーエンの髪に指を絡ませ、頭を撫で、髪を梳いて、また指を髪に差し込んで撫で、梳いてと繰り返す。その感触はリーエンを少しだけ落ち着かせ、徐々に強張った体が緩んでいく。
「んっ、ん……」
体が緩めばリーエンの舌も柔らかくなって、自然にアルフレドの舌を受け止めることが出来るようになる。はあ、と荒い息をつきながらも、リーエンは「さっきまでと違う」とキスの変化を感じ取った。違うのは自分だけではない。彼の熱い舌に彼女が自分の舌を委ねたことをアルフレドは気付いて、よりゆっくりとその感触を楽しむように、じゅっ、じゅ、と音を立てつつ、リーエンの耳に指を這わせる。
あんなにも性急に床に押し倒され、すぐにでも入れたい、孕ませたい、と言っていたはずなのに、ようやくリーエンの唇を解放したアルフレドは彼女の耳を犯し始める。
「あ、あ、あ」
片耳を噛み、舐め、吸い、音をわざと立てて羞恥を煽りながら、もう片方の耳たぶを優しく擦るアルフレド。手順を踏んだ愛撫のようなのに、覆い被さる体はぴったりとリーエンの体に触れており、絶えず彼の熱くて硬いものは彼女の腹部に押し付けられる。合わさった肌と肌は既にしっとりと湿り気を帯びていて、互いに吸い付くようだ。
「ん、んっ……」
アルフレドが動くと、彼の胸板に軽く押しつぶされているリーエンの乳房が形を変える。彼はそれをわかっているようで、わざとリーエン自身が乳房の動きを意識するようにゆっくりと押し付けるように動いた。
「あっ、あ、あ、あ」
こんな風に、最初から裸体と裸体を重ねて愛し合うのは初めてだ。夢の中でリーエンは彼の腕の中で丸まっていたため、体を捩ろうとしても動けなかった。が、今度は体を動かすたびに自分の胸が、腹部が、股間が、彼の肌の上を擦るように動く。ぐちゅぐちゅと耳を嬲られ、息を吹き込まれるたびにびくりと体を跳ねさせて自分からアルフレドの体に自分の体を押し付けてしまう。なんて恥ずかしいことを、と思う気持ちもあったが、それ以上に、彼にこうやって触れてもらっていることが嬉しいと思っていることに気付く。
(こんな、どうしようもない状況なのに)
それでも、自分を好きな、自分が好きな人が自分を欲しているのだと思うと、たとえ彼であって彼ではない状態になっていても心が打ち震えるのだとリーエンは思い知らされ、熱い息を吐きだした。すると、アルフレドは一瞬体を起こす。
「……くっ……」
苦しそうに眉根を寄せながらうめき声をあげるアルフレド。熱にうかされそうになりながらも、リーエンはそれを見逃さなかった。
「アルフレド様」
「くそ……熱い……体の内側がっ……熱すぎる……くそっ」
「まだ、魔力が落ち着いていらっしゃらないのではないですか? それに、術の取り消しでペナルティをうけて……」
「うる、さい」
「でもっ……」
「止められると思っているのか。やっと、お前が俺を求めてくれたのに、抱かないでいられるわけがないだろうが!」
アルフレドは半ば睨むような表情で、リーエンに吐き捨てるように言った。いつも穏やかで優しい彼が声を荒げるのは、あの謁見の間近くで魔族を叱責している時しかリーエンは聞いたことがない。が、彼の言葉は怒りというよりも悲しみに近いものだった。
「……!」
「お前が、お前が、俺を呼んだんだ。俺に抱かれたいと。やっとお前からそう思ってもらったのに、我慢が出来るか……!」
そう言うと、アルフレドはリーエンの体をぐいと引き起こして、ベッドの上で強く抱きしめた。その抱擁はこれまでで一番強い。ただただ、腕の中のリーエンは自分のものだと、まるで子供が好きなおもちゃの所有を主張するかのように、奪おうとする何かから守ろうとするように、彼は力を入れる。リーエンは苦しいと思いつつも、彼のその力は自分を求める心の表れだと素直に感じ取り、瞳を閉じてその身を委ねた。
(本当に、今のこの方はどうしようもない……どうしようもないのに、愛しい。こんな状態なのに、ご自分がずっと我慢していらしたことを、ちゃんと自覚なさっているんですもの)
今の彼は滅茶苦茶だ、とリーエンは呆れつつも愛しく思う。ヴィンスが心配していたのも当然ではないか。何一つうまくいっていない。ペナルティとやらで彼は今も苦しんでいるはずだ。けれど、インキュバスの制御を手放したせいで自分を抑えることも出来ない。
それらがどれほど苦しいものなのか、リーエンにはわからない。だが、そんな状態でもどこかにはいつものアルフレドの意識が存在するのだ。それをリーエンは確信した。ここにいるアルフレドは、ずっと理性で自分を抱くことを我慢してくれていた彼なのだ、と。
「お前を抱きたい。ねじこんで、打ち付けて、突き上げて、泣こうが喚こうが、中に何度でも放ちたい。抱きたい。好きだ。好きだ。好きだ……! くそ、違う。そんなことをしたいわけじゃない……!」
リーエンは強く抱かれながらもなんとか圧迫されていた腕を抜いて、アルフレドの背に腕を回した。指先に彼の翼のつけねが触れ、リーエンは「本当のお姿を見せたかったのではなく、きっと、隠していられなかったのでしょうね」と思いながらも、少しだけをそれを嬉しいと思う。
「アルフレド様、もっと、もっとおっしゃって」
「何をだ」
「わたし、わたしのことを好きって。もっとおっしゃってください。もっと」
アルフレドは彼女の腕の中で、一瞬びくりと身を竦めた。
「そんなことはっ……」
「今、口にしてくださっていました」
ふっとアルフレドはリーエンを抱いた力を緩め、顔を離して彼女を見下ろす。まるで「何を言っているんだ?」と訝しむような表情でリーエンを見る彼を彼女は見上げた。
「わたしのことを好きって、お願い、言って……」
「くそっ……好きだ」
「もっと……お願い、もっと言ってください……!」
リーエンは必死に声を張り上げて、彼に懇願した。離れてしまう心と体を少しでも繋ぎとめるには、彼の心を彼に自覚してもらうしかない。こんな時でもなければ言わない我儘をリーエンが繰り返せば、アルフレドは苦しそうに言葉を吐き出す。
「好きだ。好きだ。熱い。苦しい。だが、そんなことはどうでもいい。俺は、早くお前を……」
「アルフレド様、もう一度」
「好きだ」
「わたしも、好きです」
「……っ」
「好きです。アルフレド様、好きです。あなたが、あなたが好きです。あなたが好きだから、あなたに抱かれたいんです。だから、あなたも……わたしが好きだから、わたしを抱きたいって、そうおっしゃって……?」
お願い、と祈るような気持ちでリーエンはそう言った。だが、彼女の祈りは通じなかったのか、アルフレドは再び「うるさい」と言って、彼女をベッドに押し倒した。
37
お気に入りに追加
310
あなたにおすすめの小説

マイナー18禁乙女ゲームのヒロインになりました
東 万里央(あずま まりお)
恋愛
十六歳になったその日の朝、私は鏡の前で思い出した。この世界はなんちゃってルネサンス時代を舞台とした、18禁乙女ゲーム「愛欲のボルジア」だと言うことに……。私はそのヒロイン・ルクレツィアに転生していたのだ。
攻略対象のイケメンは五人。ヤンデレ鬼畜兄貴のチェーザレに男の娘のジョバンニ。フェロモン侍従のペドロに影の薄いアルフォンソ。大穴の変人両刀のレオナルド……。ハハッ、ロクなヤツがいやしねえ! こうなれば修道女ルートを目指してやる!
そんな感じで涙目で爆走するルクレツィアたんのお話し。
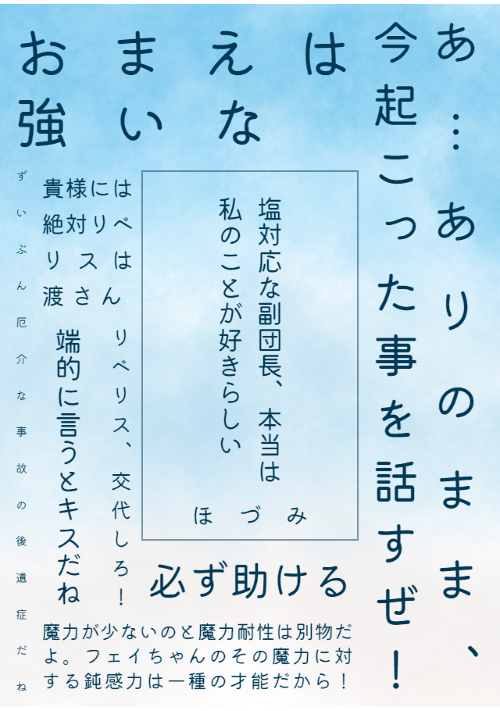
【R18】塩対応な副団長、本当は私のことが好きらしい
ほづみ
恋愛
騎士団の副団長グレアムは、事務官のフェイに塩対応する上司。魔法事故でそのグレアムと体が入れ替わってしまった! キスすれば一時的に元に戻るけれど、魔法石の影響が抜けるまではこのままみたい。その上、体が覚えているグレアムの気持ちが丸見えなんですけど!
上司だからとフェイへの気持ちを秘密にしていたのに、入れ替わりで何もかもバレたあげく開き直ったグレアムが、事務官のフェイをペロリしちゃうお話。ヒーローが片想い拗らせています。いつものようにふわふわ設定ですので、深く考えないでお付き合いください。
※大規模火災の描写が出てきます。苦手な方はご自衛をお願いします。
他サイトにも掲載しております。
2023/08/31 タイトル変更しました。

義兄様に弄ばれる私は溺愛され、その愛に堕ちる
一ノ瀬 彩音
恋愛
国王である義兄様に弄ばれる悪役令嬢の私は彼に溺れていく。
そして彼から与えられる快楽と愛情で心も身体も満たされていく……。
※この物語はフィクションです。
R18作品ですので性描写など苦手なお方や未成年のお方はご遠慮下さい。

腹黒王子は、食べ頃を待っている
月密
恋愛
侯爵令嬢のアリシア・ヴェルネがまだ五歳の時、自国の王太子であるリーンハルトと出会った。そしてその僅か一秒後ーー彼から跪かれ結婚を申し込まれる。幼いアリシアは思わず頷いてしまい、それから十三年間彼からの溺愛ならぬ執愛が止まらない。「ハンカチを拾って頂いただけなんです!」それなのに浮気だと言われてしまいーー「悪い子にはお仕置きをしないとね」また今日も彼から淫らなお仕置きをされてーー……。

中でトントンってして、ビューってしても、赤ちゃんはできません!
いちのにか
恋愛
はいもちろん嘘です。「ってことは、チューしちゃったら赤ちゃんできちゃうよねっ?」っていう、……つまりとても頭悪いお話です。
含み有りの嘘つき従者に溺愛される、騙され貴族令嬢モノになります。
♡多用、言葉責め有り、効果音付きの濃いめです。従者君、軽薄です。
★ハッピーエイプリルフール★
他サイトのエイプリルフール企画に投稿した作品です。期間終了したため、こちらに掲載します。
以下のキーワードをご確認の上、ご自愛ください。
◆近況ボードの同作品の投稿報告記事に蛇補足を追加しました。作品設定の記載(短め)のみですが、もしよろしければ٩( ᐛ )و

王女、騎士と結婚させられイかされまくる
ぺこ
恋愛
髪の色と出自から差別されてきた騎士さまにベタ惚れされて愛されまくる王女のお話。
性描写激しめですが、甘々の溺愛です。
※原文(♡乱舞淫語まみれバージョン)はpixivの方で見られます。
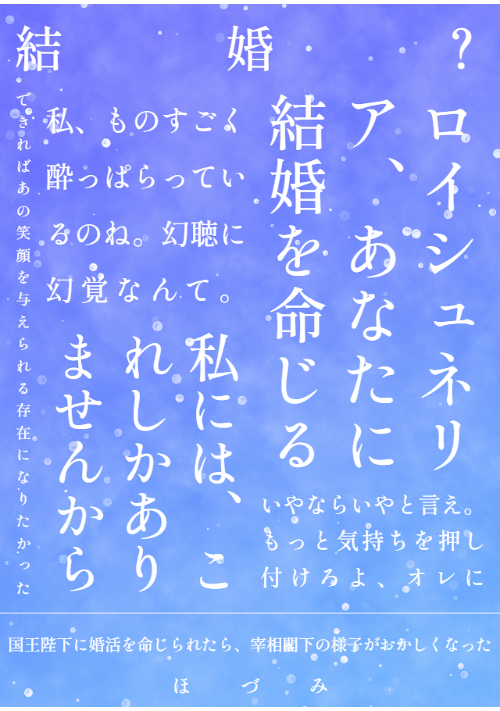
【R18】国王陛下に婚活を命じられたら、宰相閣下の様子がおかしくなった
ほづみ
恋愛
国王から「平和になったので婚活しておいで」と言われた月の女神シアに仕える女神官ロイシュネリア。彼女の持つ未来を視る力は、処女喪失とともに失われる。先視の力をほかの人間に利用されることを恐れた国王からの命令だった。好きな人がいるけどその人には好かれていないし、命令だからしかたがないね、と婚活を始めるロイシュネリアと、彼女のことをひそかに想っていた宰相リフェウスとのあれこれ。両片思いがこじらせています。
あいかわらずゆるふわです。雰囲気重視。
細かいことは気にしないでください!
他サイトにも掲載しています。
注意 ヒロインが腕を切る描写が出てきます。苦手な方はご自衛をお願いします。

悪役令嬢は国王陛下のモノ~蜜愛の中で淫らに啼く私~
一ノ瀬 彩音
恋愛
侯爵家の一人娘として何不自由なく育ったアリスティアだったが、
十歳の時に母親を亡くしてからというもの父親からの執着心が強くなっていく。
ある日、父親の命令により王宮で開かれた夜会に出席した彼女は
その帰り道で馬車ごと崖下に転落してしまう。
幸いにも怪我一つ負わずに助かったものの、
目を覚ました彼女が見たものは見知らぬ天井と心配そうな表情を浮かべる男性の姿だった。
彼はこの国の国王陛下であり、アリスティアの婚約者――つまりはこの国で最も強い権力を持つ人物だ。
訳も分からぬまま国王陛下の手によって半ば強引に結婚させられたアリスティアだが、
やがて彼に対して……?
※この物語はフィクションです。
R18作品ですので性描写など苦手なお方や未成年のお方はご遠慮下さい。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















