あなたにおすすめの小説

つまらない妃と呼ばれた日
柴田はつみ
恋愛
公爵令嬢リーシャは政略結婚で王妃に迎えられる。だが国王レオニスの隣には、幼馴染のセレスが“当然”のように立っていた。祝宴の夜、リーシャは国王が「つまらない妃だ」と語る声を聞いてしまい、心を閉ざす。
舞踏会で差し出された手を取らず、王弟アドリアンの助けで踊ったことで、噂は一気に燃え上がる――「王妃は王弟と」「国王の本命は幼馴染」と。
さらに宰相は儀礼と世論を操り、王妃を孤立させる策略を進める。監視の影、届かない贈り物、すり替えられた言葉、そして“白薔薇の香”が事件現場に残る冤罪の罠。
リーシャは微笑を鎧に「今日から、王の隣に立たない」と決めるが、距離を取るほど誤解は確定し、王宮は二人を引き裂いていく。
――つまらない妃とは、いったい誰が作ったのか。真実が露わになった時、失われた“隣”は戻るのか。

私と子供より、夫は幼馴染とその子供のほうが大切でした。
小野 まい
恋愛
結婚記念日のディナーに夫のオスカーは現れない。
「マリアが熱を出したらしい」
駆けつけた先で、オスカーがマリアと息子カイルと楽しげに食事をする姿を妻のエリザが目撃する。
「また裏切られた……」
いつも幼馴染を優先するオスカーに、エリザの不満は限界に達していた。
「あなたは家族よりも幼馴染のほうが大事なのね」
離婚する気持ちが固まっていく。

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~
Mio
ファンタジー
妻から手紙が来た。
妻が死んで18年目の今日。
息子の誕生日。
「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」
息子は…17年前に死んだ。
手紙はもう一通あった。
俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。
------------------------------

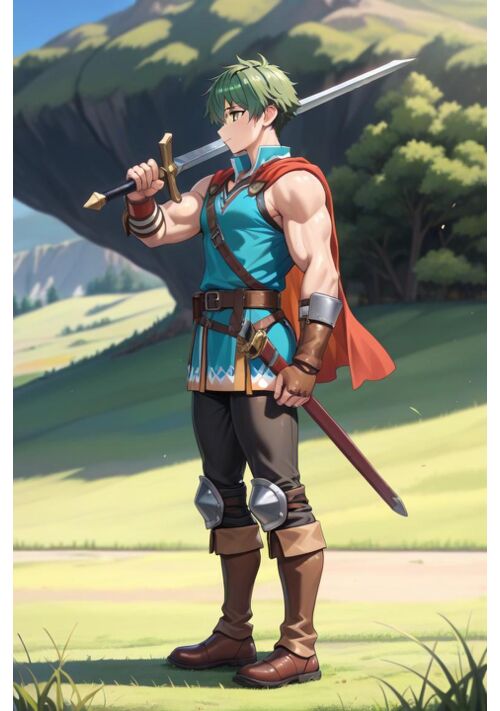
俺は、こんな力を望んでいなかった‼︎
アノマロカリス
ファンタジー
俺の名は、グレン。
転移前の名は、紅 蓮(くれない 蓮)という。
年齢は26歳……だった筈なのだが、異世界に来たら若返っていた。
魔物を倒せばレベルが上がるという話だったのだが、どうみてもこれは…オーバーキルの様な気がする。
もう…チートとか、そういうレベルでは無い。
そもそも俺は、こんな力を望んではいなかった。
何処かの田舎で、ひっそりとスローライフを送りたかった。
だけど、俺の考えとは対照的に戦いの日々に駆り出される事に。
………で、俺はこの世界で何をすれば良いんだ?

三十年後に届いた白い手紙
RyuChoukan
ファンタジー
三十年前、帝国は一人の少年を裏切り者として処刑した。
彼は最後まで、何も語らなかった。
その罪の真相を知る者は、ただ一人の女性だけだった。
戴冠舞踏会の夜。
公爵令嬢は、一通の白い手紙を手に、皇帝の前に立つ。
それは復讐でも、告発でもない。
三十年間、辺境の郵便局で待ち続けられていた、
「渡されなかった約束」のための手紙だった。
沈黙のまま命を捨てた男と、
三十年、ただ待ち続けた女。
そして、すべてを知った上で扉を開く、次の世代。
これは、
遅れて届いた手紙が、
人生と運命を静かに書き換えていく物語。

ボクが追放されたら飢餓に陥るけど良いですか?
音爽(ネソウ)
ファンタジー
美味しい果実より食えない石ころが欲しいなんて、人間て変わってますね。
役に立たないから出ていけ?
わかりました、緑の加護はゴッソリ持っていきます!
さようなら!
5月4日、ファンタジー1位!HOTランキング1位獲得!!ありがとうございました!

私を裏切った夫が、後悔しているようですが知りません
藤原遊
恋愛
政略結婚として、公爵家に嫁いだ私は
愛のない夫婦関係を「仕事」だと思い、正妻の役目を果たしてきた。
夫が愛人を持つことも、
その子を屋敷に迎え入れることも、黙って受け入れてきた。
けれど――
跡取りを、正妻の子ではなく愛人の子にする。
その言葉を、人前で軽く口にした瞬間。
私は悟ったのだ。
この家では、息子を守れないと。
元々、実家との間には
「嫡子以外の子は実家の跡取りにする」という取り決めがあった。
ならば話は簡単だ。
役目を終えた私は、離縁を選ぶ。
息子と共に、この家を去るだけ。
後悔しているようですが――
もう、私の知るところではありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















