お気に入りに追加
15
あなたにおすすめの小説

暑苦しい方程式
空川億里
SF
すでにアルファポリスに掲載中の『クールな方程式』に引き続き、再び『方程式物』を書かせていただきました。
アメリカのSF作家トム・ゴドウィンの短編小説に『冷たい方程式』という作品があります。
これに着想を得て『方程式物』と呼ばれるSF作品のバリエーションが数多く書かれてきました。
以前私も微力ながら挑戦し『クールな方程式』を書きました。今回は2度目の挑戦です。
舞台は22世紀の宇宙。ぎりぎりの燃料しか積んでいない緊急艇に密航者がいました。
この密航者を宇宙空間に遺棄しないと緊急艇は目的地の惑星で墜落しかねないのですが……。

The Outer Myth :Ⅰ -The Girl of Awakening and The God of Lament-
とちのとき
SF
Summary:
The girls weave a continuation of bonds and mythology...
The protagonist, high school girl Inaho Toyouke, lives an ordinary life in the land of Akitsukuni, where gods and humans coexist as a matter of course. However, peace is being eroded by unknown dangerous creatures called 'Kubanda.' With no particular talents, she begins investigating her mother's secrets, gradually getting entangled in the vortex of fate. Amidst this, a mysterious AGI (Artificial General Intelligence) girl named Tsugumi, who has lost her memories, washes ashore in the enigmatic Mist Lake, where drifts from all over Japan accumulate. The encounter with Tsugumi leads the young boys and girls into an unexpected adventure.
Illustrations & writings:Tochinotoki
**The text in this work has been translated using AI. The original text is in Japanese. There may be difficult expressions or awkwardness in the English translation. Please understand. Currently in serialization. Updates will be irregular.
※この作品は「The Outer Myth :Ⅰ~目覚めの少女と嘆きの神~」の英語版です。海外向けに、一部内容が編集・変更されている箇所があります。

モニターに応募したら、系外惑星に来てしまった。~どうせ地球には帰れないし、ロボ娘と猫耳魔法少女を連れて、惑星侵略を企む帝国軍と戦います。
津嶋朋靖(つしまともやす)
SF
近未来、物体の原子レベルまでの三次元構造を読みとるスキャナーが開発された。
とある企業で、そのスキャナーを使って人間の三次元データを集めるプロジェクトがスタートする。
主人公、北村海斗は、高額の報酬につられてデータを取るモニターに応募した。
スキャナーの中に入れられた海斗は、いつの間にか眠ってしまう。
そして、目が覚めた時、彼は見知らぬ世界にいたのだ。
いったい、寝ている間に何が起きたのか?
彼の前に現れたメイド姿のアンドロイドから、驚愕の事実を聞かされる。
ここは、二百年後の太陽系外の地球類似惑星。
そして、海斗は海斗であって海斗ではない。
二百年前にスキャナーで読み取られたデータを元に、三次元プリンターで作られたコピー人間だったのだ。
この惑星で生きていかざるを得なくなった海斗は、次第にこの惑星での争いに巻き込まれていく。
(この作品は小説家になろうとマグネットにも投稿してます)

SMART CELL
MASAHOM
SF
全世界の超高度AIを結集した演算能力をたった1基で遥かに凌駕する超超高度AIが誕生し、第2のシンギュラリティを迎えた2155年末。大晦日を翌日に控え17歳の高校生、来栖レンはオカルト研究部の深夜の極秘集会の買い出し中に謎の宇宙船が東京湾に墜落したことを知る。翌日、突如として来栖家にアメリカ人の少女がレンの学校に留学するためホームステイしに来ることになった。少女の名前はエイダ・ミラー。冬休み中に美少女のエイダはレンと親しい関係性を築いていったが、登校初日、エイダは衝撃的な自己紹介を口にする。東京湾に墜落した宇宙船の生き残りであるというのだ。親しく接していたエイダの言葉に不穏な空気を感じ始めるレン。エイダと出会ったのを境にレンは地球深部から届くオカルト界隈では有名な謎のシグナル・通称Z信号にまつわる地球の真実と、人類の隠された機能について知ることになる。
※この作品はアナログハック・オープンリソースを使用しています。 https://www63.atwiki.jp/analoghack/
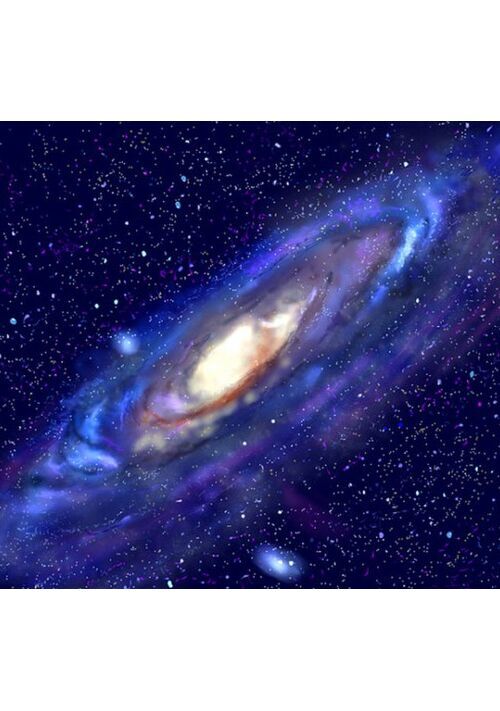
銀河文芸部伝説~UFOに攫われてアンドロメダに連れて行かれたら寝ている間に銀河最強になっていました~
まきノ助
SF
高校の文芸部が夏キャンプ中にUFOに攫われてアンドロメダ星雲の大宇宙帝国に連れて行かれてしまうが、そこは魔物が支配する星と成っていた。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

ヒットマン VS サイキッカーズ
神泉灯
SF
男が受けた依頼は、超能力の実験体となっている二人の子供を救出し、指定時間までに港に送り届けること。
しかし実戦投入段階の五人の超能力者が子供を奪還しようと追跡する。
最強のヒットマンVS五人の超能力者。
終わらない戦いの夜が始まる……

シーフードミックス
黒はんぺん
SF
ある日あたしはロブスターそっくりの宇宙人と出会いました。出会ったその日にハンバーガーショップで話し込んでしまいました。
以前からあたしに憑依する何者かがいたけれど、それは宇宙人さんとは無関係らしい。でも、その何者かさんはあたしに警告するために、とうとうあたしの内宇宙に乗り込んできたの。
ちょっとびっくりだけど、あたしの内宇宙には天の川銀河やアンドロメダ銀河があります。よかったら見物してってね。
内なる宇宙にもあたしの住むご町内にも、未知の生命体があふれてる。遭遇の日々ですね。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















