16 / 39
土曜日~来客~
しおりを挟む
――ええと、なんて名前だっけ?
ほんの数秒前に斎夜月に紹介されて忘れてはいないハズの、日本人なら聞き間違えのような気がするたいそう胡散臭い名前を畑中純一は頭の中で反芻した。
たしか――
「学習院英麻呂です。はじめまして、畑中純一さん」
目の前の色黒の、日本人としては異常とも言えるほどの色黒の男性の差し出す右手を受け取り、握手した。
「はじめまして。畑中です。よろしくお願いいたします」
黒檀を磨いたような肌は日本人の色ではないが、表情やあごのラインは日本人といえなくもないし、通ったまっすぐな鼻梁もヨーロッパ人のちょっと胡座というか三角座りに近い形よりは正座に近く、沖縄辺りの人がそのまま黒くなったのか、という気がしないでもない。身体は仕立てのいいスーツが細く見えるような長身で、純一よりも一回り背が高い。陸上やスキーの選手みたいな体型だ。
全体に黒豹が立ち上がって人懐こく笑うとこんな感じなのかというような印象の人物だった。
ただやはり真っ黒い肌に、金髪、真っ赤な目という組み合わせは、日本人である純一にはインパクトが強すぎて、流暢な日本語といかにも偽名くさい名前を名乗られると、なんと反応して良いのか困る。街中で道を聞かれたら、あいきゃのとすぴーくいんぐりっしゅ、ととりあえず言いたくなるような外見をしている。
普段この印象で損をしているか得をしているか分からないが、さぞかし奇異の目で見られるだろう、と同情混じりに思いつつ、しかしやはり異貌の美形というのは気がつかずに色々観察してしまう。おそらく本人もそうあるのに今更苦痛を感じるわけでもないようで、純一の困惑しつつも遠慮のきかない視線を面白そうに観察している。
そう、学習院と名乗った配色を完全に誤った日本語の極めて流暢な人物は、その色合いの異常さを除けば十分に日本人の美的バランスに即した美形といえる造形であった。
「因みにお名前は本名ですか。目白にそんな大学があったような」
純一は失礼とは思ったが圧倒されっぱなしでは話も始まらず、この程度で不機嫌になられるようなら逆に逃げ出すキッカケになると敢えて踏んでみた。
学習院と名乗った男は笑った。バカにしたというよりはいきなりそこか、という不意をつかれた好手に思わず笑ったという感じだった。
「うん。本名だ。だが、あの有名な大学とはなんの縁もない。いや、縁がないというのはへんかな。もともと私は古い亡命者の家系でね。グダニスク辺りに領地を持っていた貴族だったことになっている。その後ナポレオンに追われるようにロシアに逃げ込み、開国で一世を風靡していた神戸に病院を構えた。曽祖父は日露戦争で日本軍に従軍した医官だったらしいよ。革命の薫りが焦げ臭くなり始めたので親戚をまとめて呼び、日本が日清日露と良い感じだったのでそのまま帰化した。大雑把にそんな感じで明治のアタマ頃にロシア人医師として日本に来て帰化したわけだが、姓がたまたま学習院という当時宮内庁が預かっていた学校の名に音に近かったので地方の役場の人間が勘違いをしてそのまま、帰化するときにその名になった、と聞いている。もちろん元の綴りは全く違うがね」
と、黒い男は子音が沢山並ぶ綴りを書いてみせた。そして改めて、その発音で名前を自己紹介をした。唇を複雑に宙吊りにしたまま、舌を口の中で動かす発音は、いかにも異国のものだったが、学習院と名乗った男がいうには本来そういう音だそうで、何度か練習して純一が滑らかに出るようになると嬉しそうに喜んだ。
しばらく雑談という風なこともなく、お互いの最近の話を話すことになった。
彼は財閥というほど目立ったものではないが、病院や養護施設、製薬化学薬品会社、総合貿易商社など幾つかの会社の大きめの株主で、幾つかの会社についてはソコソコの融通がきく立場にあり、それなりに顔がきくという。純一が前回採用を断られた会社についても、その気があれば改めて別の部署で話を聞いてもらうことをセッティングできると思う。というようなことを言ってくれた。
「それはたいそうありがたいのですが――」
無礼は承知で、そこまで買っていただく理由が今ひとつ分からないのですが、と純一は学習院に訊いてみた。
「まぁ、そうだろう」
と、笑いを含んだ言葉で学習院は言った。
「強いてあげれば、夜月の目に止まって、女の子四人に捕まって、あの鬱陶しい水本が気にかけている、ってところでまぁ私が気に入ったというのが理由かな。――」
学習院は掌まで黒い手で自分の頬をなでると少し表情を消して純一に向き直った。
「――いやね。すると、君は自分がどれほど平凡なつもりで居るのかな。平原の真ん中でポツンと木が立っていれば、気になるものだろう。木の実が欲しいか、木陰が欲しいか、薪がほしいか、タダの道標か、それはさておき、人が何かを気にするキッカケというのはそんなようなものだ」
学習院は赤い瞳で純一の顔を眺めていた。純一が弁解の言葉を探していると、黒い男は表情を少し緩めて続けた。
「――実際に君が会社のナニかの役に立つかどうかは私には全く分からンので、私は夜月がしたように、卒業見込みの知り合いがいるんだが新卒を採る気があるか、と訊いてみる、いや、みようかと思っているのだが、君がなにか私に不安があるようならとりあえず辞めてもいい。初対面の人間にいきなり将来の話を託すのも気持ち悪いというのも分からンではないからね。私だったらとりあえず、調べる。だが――」
学習院は身を乗り出した。
「私の個人的な感覚から言えば、同時に複数の固有の女性と連続して付き合うのは少なくとも大変な体力が必要だし、よほど恥知らずか慎重な人間でなければなかなか続かない。慎重で体力のある人間というのは、物事を預けるのに向いているので、友人としては貴重だと思う。君はそういう人間だ」
そう言うと、学習院は深く腰を座り直した。
「とりあえず、今日は名刺を差し上げることにしよう。特に会社のナニというわけでないからトランプにもならないかもしれないが、連絡をくれれば一緒に何かを考えてあげることはできる。夜月がどこを気に入ったかはともかく、私は色々君のことが気に入った。――夜月、若い人と話す機会をもらって嬉しかった。今日はありがとう。けっこう楽しかった。また寄るよ」
「それはたいそう良かった。時間はどうとでもといっても、忙しいと思ってましたから」
「どこで寄り道をしてお茶を飲むかくらいは決められるさ」
そう言うと学習院は席を立った。
二人して事務所の外まで見送ると、黒いパンツスーツ姿の女性がエレベータ脇にいた。秘書か運転手らしい。妙に静かな雰囲気の女性で少々怖い。怒りとか殺意とかそういうものでないのは間違いないが、そう感じた。
そうして黒い男は去っていった。
ほんの数秒前に斎夜月に紹介されて忘れてはいないハズの、日本人なら聞き間違えのような気がするたいそう胡散臭い名前を畑中純一は頭の中で反芻した。
たしか――
「学習院英麻呂です。はじめまして、畑中純一さん」
目の前の色黒の、日本人としては異常とも言えるほどの色黒の男性の差し出す右手を受け取り、握手した。
「はじめまして。畑中です。よろしくお願いいたします」
黒檀を磨いたような肌は日本人の色ではないが、表情やあごのラインは日本人といえなくもないし、通ったまっすぐな鼻梁もヨーロッパ人のちょっと胡座というか三角座りに近い形よりは正座に近く、沖縄辺りの人がそのまま黒くなったのか、という気がしないでもない。身体は仕立てのいいスーツが細く見えるような長身で、純一よりも一回り背が高い。陸上やスキーの選手みたいな体型だ。
全体に黒豹が立ち上がって人懐こく笑うとこんな感じなのかというような印象の人物だった。
ただやはり真っ黒い肌に、金髪、真っ赤な目という組み合わせは、日本人である純一にはインパクトが強すぎて、流暢な日本語といかにも偽名くさい名前を名乗られると、なんと反応して良いのか困る。街中で道を聞かれたら、あいきゃのとすぴーくいんぐりっしゅ、ととりあえず言いたくなるような外見をしている。
普段この印象で損をしているか得をしているか分からないが、さぞかし奇異の目で見られるだろう、と同情混じりに思いつつ、しかしやはり異貌の美形というのは気がつかずに色々観察してしまう。おそらく本人もそうあるのに今更苦痛を感じるわけでもないようで、純一の困惑しつつも遠慮のきかない視線を面白そうに観察している。
そう、学習院と名乗った配色を完全に誤った日本語の極めて流暢な人物は、その色合いの異常さを除けば十分に日本人の美的バランスに即した美形といえる造形であった。
「因みにお名前は本名ですか。目白にそんな大学があったような」
純一は失礼とは思ったが圧倒されっぱなしでは話も始まらず、この程度で不機嫌になられるようなら逆に逃げ出すキッカケになると敢えて踏んでみた。
学習院と名乗った男は笑った。バカにしたというよりはいきなりそこか、という不意をつかれた好手に思わず笑ったという感じだった。
「うん。本名だ。だが、あの有名な大学とはなんの縁もない。いや、縁がないというのはへんかな。もともと私は古い亡命者の家系でね。グダニスク辺りに領地を持っていた貴族だったことになっている。その後ナポレオンに追われるようにロシアに逃げ込み、開国で一世を風靡していた神戸に病院を構えた。曽祖父は日露戦争で日本軍に従軍した医官だったらしいよ。革命の薫りが焦げ臭くなり始めたので親戚をまとめて呼び、日本が日清日露と良い感じだったのでそのまま帰化した。大雑把にそんな感じで明治のアタマ頃にロシア人医師として日本に来て帰化したわけだが、姓がたまたま学習院という当時宮内庁が預かっていた学校の名に音に近かったので地方の役場の人間が勘違いをしてそのまま、帰化するときにその名になった、と聞いている。もちろん元の綴りは全く違うがね」
と、黒い男は子音が沢山並ぶ綴りを書いてみせた。そして改めて、その発音で名前を自己紹介をした。唇を複雑に宙吊りにしたまま、舌を口の中で動かす発音は、いかにも異国のものだったが、学習院と名乗った男がいうには本来そういう音だそうで、何度か練習して純一が滑らかに出るようになると嬉しそうに喜んだ。
しばらく雑談という風なこともなく、お互いの最近の話を話すことになった。
彼は財閥というほど目立ったものではないが、病院や養護施設、製薬化学薬品会社、総合貿易商社など幾つかの会社の大きめの株主で、幾つかの会社についてはソコソコの融通がきく立場にあり、それなりに顔がきくという。純一が前回採用を断られた会社についても、その気があれば改めて別の部署で話を聞いてもらうことをセッティングできると思う。というようなことを言ってくれた。
「それはたいそうありがたいのですが――」
無礼は承知で、そこまで買っていただく理由が今ひとつ分からないのですが、と純一は学習院に訊いてみた。
「まぁ、そうだろう」
と、笑いを含んだ言葉で学習院は言った。
「強いてあげれば、夜月の目に止まって、女の子四人に捕まって、あの鬱陶しい水本が気にかけている、ってところでまぁ私が気に入ったというのが理由かな。――」
学習院は掌まで黒い手で自分の頬をなでると少し表情を消して純一に向き直った。
「――いやね。すると、君は自分がどれほど平凡なつもりで居るのかな。平原の真ん中でポツンと木が立っていれば、気になるものだろう。木の実が欲しいか、木陰が欲しいか、薪がほしいか、タダの道標か、それはさておき、人が何かを気にするキッカケというのはそんなようなものだ」
学習院は赤い瞳で純一の顔を眺めていた。純一が弁解の言葉を探していると、黒い男は表情を少し緩めて続けた。
「――実際に君が会社のナニかの役に立つかどうかは私には全く分からンので、私は夜月がしたように、卒業見込みの知り合いがいるんだが新卒を採る気があるか、と訊いてみる、いや、みようかと思っているのだが、君がなにか私に不安があるようならとりあえず辞めてもいい。初対面の人間にいきなり将来の話を託すのも気持ち悪いというのも分からンではないからね。私だったらとりあえず、調べる。だが――」
学習院は身を乗り出した。
「私の個人的な感覚から言えば、同時に複数の固有の女性と連続して付き合うのは少なくとも大変な体力が必要だし、よほど恥知らずか慎重な人間でなければなかなか続かない。慎重で体力のある人間というのは、物事を預けるのに向いているので、友人としては貴重だと思う。君はそういう人間だ」
そう言うと、学習院は深く腰を座り直した。
「とりあえず、今日は名刺を差し上げることにしよう。特に会社のナニというわけでないからトランプにもならないかもしれないが、連絡をくれれば一緒に何かを考えてあげることはできる。夜月がどこを気に入ったかはともかく、私は色々君のことが気に入った。――夜月、若い人と話す機会をもらって嬉しかった。今日はありがとう。けっこう楽しかった。また寄るよ」
「それはたいそう良かった。時間はどうとでもといっても、忙しいと思ってましたから」
「どこで寄り道をしてお茶を飲むかくらいは決められるさ」
そう言うと学習院は席を立った。
二人して事務所の外まで見送ると、黒いパンツスーツ姿の女性がエレベータ脇にいた。秘書か運転手らしい。妙に静かな雰囲気の女性で少々怖い。怒りとか殺意とかそういうものでないのは間違いないが、そう感じた。
そうして黒い男は去っていった。
0
お気に入りに追加
12
あなたにおすすめの小説

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

王が気づいたのはあれから十年後
基本二度寝
恋愛
王太子は妃の肩を抱き、反対の手には息子の手を握る。
妃はまだ小さい娘を抱えて、夫に寄り添っていた。
仲睦まじいその王族家族の姿は、国民にも評判がよかった。
側室を取ることもなく、子に恵まれた王家。
王太子は妃を優しく見つめ、妃も王太子を愛しく見つめ返す。
王太子は今日、父から王の座を譲り受けた。
新たな国王の誕生だった。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

最愛の側妃だけを愛する旦那様、あなたの愛は要りません
abang
恋愛
私の旦那様は七人の側妃を持つ、巷でも噂の好色王。
後宮はいつでも女の戦いが絶えない。
安心して眠ることもできない後宮に、他の妃の所にばかり通う皇帝である夫。
「どうして、この人を愛していたのかしら?」
ずっと静観していた皇后の心は冷めてしまいう。
それなのに皇帝は急に皇后に興味を向けて……!?
「あの人に興味はありません。勝手になさい!」

あなたの子ですが、内緒で育てます
椿蛍
恋愛
「本当にあなたの子ですか?」
突然現れた浮気相手、私の夫である国王陛下の子を身籠っているという。
夫、王妃の座、全て奪われ冷遇される日々――王宮から、追われた私のお腹には陛下の子が宿っていた。
私は強くなることを決意する。
「この子は私が育てます!」
お腹にいる子供は王の子。
王の子だけが不思議な力を持つ。
私は育った子供を連れて王宮へ戻る。
――そして、私を追い出したことを後悔してください。
※夫の後悔、浮気相手と虐げられからのざまあ
※他サイト様でも掲載しております。
※hotランキング1位&エールありがとうございます!


貧乏男爵家の末っ子が眠り姫になるまでとその後
空月
恋愛
貧乏男爵家の末っ子・アルティアの婚約者は、何故か公爵家嫡男で非の打ち所のない男・キースである。
魔術学院の二年生に進学して少し経った頃、「君と俺とでは釣り合わないと思わないか」と言われる。
そのときは曖昧な笑みで流したアルティアだったが、その数日後、倒れて眠ったままの状態になってしまう。
すると、キースの態度が豹変して……?
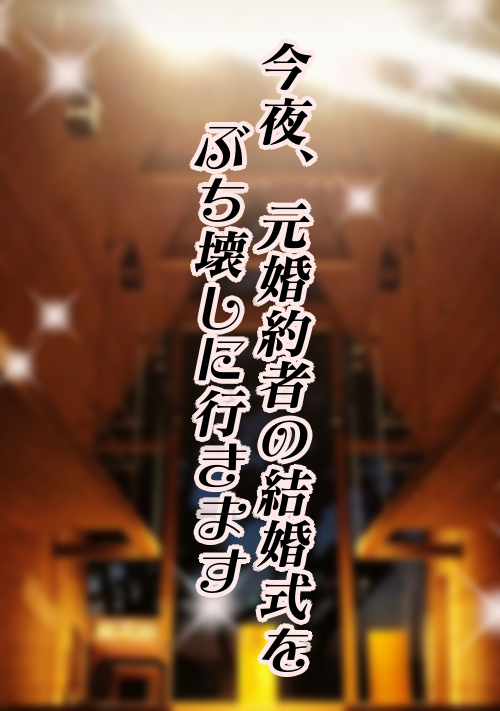
今夜、元婚約者の結婚式をぶち壊しに行きます
結城芙由奈
恋愛
【今夜は元婚約者と友人のめでたい結婚式なので、盛大に祝ってあげましょう】
交際期間5年を経て、半年後にゴールインするはずだった私と彼。それなのに遠距離恋愛になった途端彼は私の友人と浮気をし、友人は妊娠。結果捨てられた私の元へ、図々しくも結婚式の招待状が届けられた。面白い…そんなに私に祝ってもらいたいのなら、盛大に祝ってやろうじゃないの。そして私は結婚式場へと向かった。
※他サイトでも投稿中
※苦手な短編ですがお読みいただけると幸いです
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















