5 / 19
4 シング・シング・シング
しおりを挟む
高田くんは、やっぱり優しい。
少し、ヘンだけど、いい子だ。
僕は、高田くんがハーフだということを知らなかった。
皆、きっと、知らなくて、それで、高田くんのこと、誤解してるところがある。
あの外見は、不良だからじゃなかった。
彼が、ハーフだってこと、いわれたら、何だか、納得してしまった。
だって、高田くんは、すごくきれいだから。
きっと。
高田くんは、孤独なんだ。
彼は、友達がほしくて、僕に、あんなことをしているのに違いない。
そのうち、学校に馴染んで、友達が何人かできれば、僕のことなんて忘れてしまうだろう。
それまで。
僕は、高田くんに付き合ってあげるべきなんだろう。
だって、僕は、高田くんの先生なんだから。
その日も、高田くんから、いつもの、ラインがきていた。
『放課後、音楽室で、待ってろ』
何だろう。
僕は、ため息をつく。
この上から目線は、やっぱり、お坊っちゃまだからかな。
そう思って、僕は、くすっと笑ってしまった。
その時。
「雪」
その声に、僕は、びくっ、と、体を強ばらせる。
振り向かなくても、わかった。
長井先輩だった。
僕は、何も言えずに、ただ、その場で立ち止まっていた。
長井先輩の手が、僕の方に触れた。
「雪、あの時は、すまなかった」
長井先輩は、僕の耳元で囁いた。
「だけど、昔から、お前も、俺の気持ちを知ってた筈だろ」
長井先輩とは、高校のときからの付き合いだった。
僕は、正直、勉強ができて、かっこいい長井先輩に憧れていた。
あんなふうになれたらな、って思っていたんだ。
僕は、あの頃、孤独だった。
学校でも、家でも、居場所がなくて。
隣町にあったジャズバーだけが、僕に居場所をくれた。
そこは、僕の兄さんの友達の店だった。
僕は、中学3年の冬に兄さんにつれられて、初めて、その店に行った。
そこで、ジャズに出会った。
僕は、もともとピアノをやっていたんだけど、その頃は、受験のために、少し、ピアノから離れていた。
でも。
僕は、ジャズを知って、再び、ピアノに向き合うようになった。
それに。
店のオーナーで、兄さんの友達の小島さんにも、夢中になった。
僕は、兄さんとは、10才も年が離れている。
そのせいか、僕のまわりは、物心ついた時から、大人ばかりだった。
だからかな。
僕は、いつも、一人ぼっちだった。
家は、その地方では、老舗の旅館だったこともあって、余計に、僕は、孤独の中に生きていた。
それは、両親も、わかってくれてた。
僕の両親は、僕にピアノを与えてくれた。
それからは、ピアノだけが、僕の友達だった。
悲しいときも、嬉しいときも、僕は、ピアノと一緒だった。
あのとき。
中学2年生の時、ピアノの先生に言われるまでは。
先生は、言った。
「君は、手が小さすぎる。ピアノには、むいていない」
確かに、僕は、小柄で、手もそんなに、大きくは、なかった。
すごく、僕は、ショックを受けて、先生のところに行くのが嫌になった。
ちょうど、高校受験の頃だったこともあって、僕は、ピアノから距離をとるようになってた。
兄さんが、友達の小島さんの店に僕を連れていってくれたのは、そんな頃のことだった。
小島さんは、僕より、10才年上で、サックスの名プレーヤーだった。
僕は、小島さんに導かれて、ジャズにのめり込んでいった。
それと同時に、小島さんにも、ひかれていった。
僕は、それを、ただの憧れにすぎないと信じていた。
だけど、それは、違っていたんだ。
小島さんへの思いが、ただの憧れなんかでないということを思い知らされたのは、高校1年の夏のことだった。
その夏、長井先輩が転校してきた。
2才年上の長井先輩は、僕にとっては、あまり興味のない人だった。
ただ、女子たちが、騒いでるのが耳に入ってくるぐらいだった。
なのに。
ある日突然、長井先輩は、小島さんの店に現れて言ったんだ。
「ドラマー、募集してるって、張り紙みたんだけど」
長井先輩と小島さんの演奏は、素晴らしかった。
僕は、二人のセッションをきいて、思わず、長井先輩に嫉妬していた。
僕は、長井先輩になりたかった。
彼は、僕にないものを全部持っている人だった。
僕は、小島さんに恋して、二人の後を追いかけて、ピアノを弾いていた。
僕は、もっともっと、うまくなりたかった。
そうすれば、小島さんが、僕を見てくれると信じていた。
長井先輩を見るように。
春には、長井先輩は、大学に入学して、町を出ていった。
時々、帰ってきたときに、小島さんとセッションしていた長井先輩。
二人のセッションは、すごかった。
燃え上がる炎のように、二人は、絡み合い、お互いをリスペクトしあっているのが僕にも、伝わったきた。
僕も、あの中に入りたいと、思った。
僕は、もっとうまくなりたいと思った。
だから、僕は、音楽を続けることを選んだ。
僕が、音大に進学したとき、小島さんは、言った。
「すごいな、雪は」
だけど。
僕は、気づいてしまった。
僕は、技術がいくら向上しても、上には、いけないってことに。
僕には、あの二人のようには歌えない。
僕の中には、音楽は、流れていなかったんだ。
僕は、長井先輩が苦手だった。
僕と違って、魂に音楽を持っている、長井先輩が嫌いだった。
僕と違って、小島さんと魂で語り合える長井先輩のことを僕は、憎んでいた。
僕は、段々、彼を避けるようになった。
今の学校で再会したのは、偶然だった。
長井先輩が数学の教師になっていることは、きいていたけれど、まさか、こんなところで出会うとは思っていなかった。
そして。
あの事件があった。
僕は、それから、長井先輩を避けていた。
高田くんのこともあった。
高田くんは、僕と長井先輩が接触することをとにかく、嫌がっていた。
僕は、高田くんを刺激したくは、なかった。
「雪、俺の方を見てくれ、頼む」
長井先輩に言われて、僕は、顔をあげた。
長井先輩と目があった。
長井先輩は、僕に、言った。
「今夜、ここで、待ってる」
彼は、僕に一枚のカードを渡した。
そこには、この辺で有名なジャズバーの名前があった。
僕は、断ろうとしたけど、もう、そのときには、長井先輩の姿は、なかった。
長井先輩は、今でも、ドラムを続けているんだろうか。
もしそうなら。
彼は、小島さんと、今も、会ってるのかな。
僕が、そんなことを、考えていたときだった。
「何、ぼぉっとしてんだ?」
高田くんが、音楽室へと入ってきた。
僕は、慌てて、カードを隠した。
「別に」
「見せろよ」
高田くんは、僕が隠したカードを取り上げて見ると、言った。
「ジャズ、か。そういや、雪先生は、俺と初めてあったときも、そんな曲を弾いてたよな」
「そうだったかな」
僕が言うと、高田くんが言った。
「確か、『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』だった」
「よく、覚えてえるな」
僕が感心して言うと、高田くんが、椅子に座って言った。
「久しぶりに、ききたいな。雪先生のピアノ」
「いいよ」
僕は、頷いた。
「何がいい?」
「何でも」
「じゃあ」
僕は、ピアノの前に座ってから、言った。
「君なら、この曲とか、どうかな」
僕は、シング・シング・シングを演奏した。
高田くんは、僕の演奏を静かにきいていた。
曲が終わってから、彼は、僕にきいた。
「これは、誰の曲なの?」
「この曲は」
僕は、言った。
「スウィングの王様と呼ばれたベニー・グッドマンの曲だよ」
「ベニー・グッドマンは」
小島さんは、昔、僕に言った。
「あの人種差別のひどい時代に、白人と黒人の区別なくバンドにプレイヤーを入れていた」
「自分の音楽に忠実だった人の歌、だ」
「へぇ」
高田くんがきいた。
「なんで、俺なら、その曲なんだ?」
「だって、君は」
ある意味、自分に忠実な人だから。
僕は、いいかけて、やめた。
「君は、ジャズのことをあまり知らないから。この曲は、初心者でも、わかりやすいからね」
「そうなんだ」
高田くんは、言った。
「もう一度、弾いてくれよ。もしかしたら、好きになれるかもしれないから」
「いいよ」
僕は、もう一度、同じ曲を演奏した。
少し、ヘンだけど、いい子だ。
僕は、高田くんがハーフだということを知らなかった。
皆、きっと、知らなくて、それで、高田くんのこと、誤解してるところがある。
あの外見は、不良だからじゃなかった。
彼が、ハーフだってこと、いわれたら、何だか、納得してしまった。
だって、高田くんは、すごくきれいだから。
きっと。
高田くんは、孤独なんだ。
彼は、友達がほしくて、僕に、あんなことをしているのに違いない。
そのうち、学校に馴染んで、友達が何人かできれば、僕のことなんて忘れてしまうだろう。
それまで。
僕は、高田くんに付き合ってあげるべきなんだろう。
だって、僕は、高田くんの先生なんだから。
その日も、高田くんから、いつもの、ラインがきていた。
『放課後、音楽室で、待ってろ』
何だろう。
僕は、ため息をつく。
この上から目線は、やっぱり、お坊っちゃまだからかな。
そう思って、僕は、くすっと笑ってしまった。
その時。
「雪」
その声に、僕は、びくっ、と、体を強ばらせる。
振り向かなくても、わかった。
長井先輩だった。
僕は、何も言えずに、ただ、その場で立ち止まっていた。
長井先輩の手が、僕の方に触れた。
「雪、あの時は、すまなかった」
長井先輩は、僕の耳元で囁いた。
「だけど、昔から、お前も、俺の気持ちを知ってた筈だろ」
長井先輩とは、高校のときからの付き合いだった。
僕は、正直、勉強ができて、かっこいい長井先輩に憧れていた。
あんなふうになれたらな、って思っていたんだ。
僕は、あの頃、孤独だった。
学校でも、家でも、居場所がなくて。
隣町にあったジャズバーだけが、僕に居場所をくれた。
そこは、僕の兄さんの友達の店だった。
僕は、中学3年の冬に兄さんにつれられて、初めて、その店に行った。
そこで、ジャズに出会った。
僕は、もともとピアノをやっていたんだけど、その頃は、受験のために、少し、ピアノから離れていた。
でも。
僕は、ジャズを知って、再び、ピアノに向き合うようになった。
それに。
店のオーナーで、兄さんの友達の小島さんにも、夢中になった。
僕は、兄さんとは、10才も年が離れている。
そのせいか、僕のまわりは、物心ついた時から、大人ばかりだった。
だからかな。
僕は、いつも、一人ぼっちだった。
家は、その地方では、老舗の旅館だったこともあって、余計に、僕は、孤独の中に生きていた。
それは、両親も、わかってくれてた。
僕の両親は、僕にピアノを与えてくれた。
それからは、ピアノだけが、僕の友達だった。
悲しいときも、嬉しいときも、僕は、ピアノと一緒だった。
あのとき。
中学2年生の時、ピアノの先生に言われるまでは。
先生は、言った。
「君は、手が小さすぎる。ピアノには、むいていない」
確かに、僕は、小柄で、手もそんなに、大きくは、なかった。
すごく、僕は、ショックを受けて、先生のところに行くのが嫌になった。
ちょうど、高校受験の頃だったこともあって、僕は、ピアノから距離をとるようになってた。
兄さんが、友達の小島さんの店に僕を連れていってくれたのは、そんな頃のことだった。
小島さんは、僕より、10才年上で、サックスの名プレーヤーだった。
僕は、小島さんに導かれて、ジャズにのめり込んでいった。
それと同時に、小島さんにも、ひかれていった。
僕は、それを、ただの憧れにすぎないと信じていた。
だけど、それは、違っていたんだ。
小島さんへの思いが、ただの憧れなんかでないということを思い知らされたのは、高校1年の夏のことだった。
その夏、長井先輩が転校してきた。
2才年上の長井先輩は、僕にとっては、あまり興味のない人だった。
ただ、女子たちが、騒いでるのが耳に入ってくるぐらいだった。
なのに。
ある日突然、長井先輩は、小島さんの店に現れて言ったんだ。
「ドラマー、募集してるって、張り紙みたんだけど」
長井先輩と小島さんの演奏は、素晴らしかった。
僕は、二人のセッションをきいて、思わず、長井先輩に嫉妬していた。
僕は、長井先輩になりたかった。
彼は、僕にないものを全部持っている人だった。
僕は、小島さんに恋して、二人の後を追いかけて、ピアノを弾いていた。
僕は、もっともっと、うまくなりたかった。
そうすれば、小島さんが、僕を見てくれると信じていた。
長井先輩を見るように。
春には、長井先輩は、大学に入学して、町を出ていった。
時々、帰ってきたときに、小島さんとセッションしていた長井先輩。
二人のセッションは、すごかった。
燃え上がる炎のように、二人は、絡み合い、お互いをリスペクトしあっているのが僕にも、伝わったきた。
僕も、あの中に入りたいと、思った。
僕は、もっとうまくなりたいと思った。
だから、僕は、音楽を続けることを選んだ。
僕が、音大に進学したとき、小島さんは、言った。
「すごいな、雪は」
だけど。
僕は、気づいてしまった。
僕は、技術がいくら向上しても、上には、いけないってことに。
僕には、あの二人のようには歌えない。
僕の中には、音楽は、流れていなかったんだ。
僕は、長井先輩が苦手だった。
僕と違って、魂に音楽を持っている、長井先輩が嫌いだった。
僕と違って、小島さんと魂で語り合える長井先輩のことを僕は、憎んでいた。
僕は、段々、彼を避けるようになった。
今の学校で再会したのは、偶然だった。
長井先輩が数学の教師になっていることは、きいていたけれど、まさか、こんなところで出会うとは思っていなかった。
そして。
あの事件があった。
僕は、それから、長井先輩を避けていた。
高田くんのこともあった。
高田くんは、僕と長井先輩が接触することをとにかく、嫌がっていた。
僕は、高田くんを刺激したくは、なかった。
「雪、俺の方を見てくれ、頼む」
長井先輩に言われて、僕は、顔をあげた。
長井先輩と目があった。
長井先輩は、僕に、言った。
「今夜、ここで、待ってる」
彼は、僕に一枚のカードを渡した。
そこには、この辺で有名なジャズバーの名前があった。
僕は、断ろうとしたけど、もう、そのときには、長井先輩の姿は、なかった。
長井先輩は、今でも、ドラムを続けているんだろうか。
もしそうなら。
彼は、小島さんと、今も、会ってるのかな。
僕が、そんなことを、考えていたときだった。
「何、ぼぉっとしてんだ?」
高田くんが、音楽室へと入ってきた。
僕は、慌てて、カードを隠した。
「別に」
「見せろよ」
高田くんは、僕が隠したカードを取り上げて見ると、言った。
「ジャズ、か。そういや、雪先生は、俺と初めてあったときも、そんな曲を弾いてたよな」
「そうだったかな」
僕が言うと、高田くんが言った。
「確か、『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』だった」
「よく、覚えてえるな」
僕が感心して言うと、高田くんが、椅子に座って言った。
「久しぶりに、ききたいな。雪先生のピアノ」
「いいよ」
僕は、頷いた。
「何がいい?」
「何でも」
「じゃあ」
僕は、ピアノの前に座ってから、言った。
「君なら、この曲とか、どうかな」
僕は、シング・シング・シングを演奏した。
高田くんは、僕の演奏を静かにきいていた。
曲が終わってから、彼は、僕にきいた。
「これは、誰の曲なの?」
「この曲は」
僕は、言った。
「スウィングの王様と呼ばれたベニー・グッドマンの曲だよ」
「ベニー・グッドマンは」
小島さんは、昔、僕に言った。
「あの人種差別のひどい時代に、白人と黒人の区別なくバンドにプレイヤーを入れていた」
「自分の音楽に忠実だった人の歌、だ」
「へぇ」
高田くんがきいた。
「なんで、俺なら、その曲なんだ?」
「だって、君は」
ある意味、自分に忠実な人だから。
僕は、いいかけて、やめた。
「君は、ジャズのことをあまり知らないから。この曲は、初心者でも、わかりやすいからね」
「そうなんだ」
高田くんは、言った。
「もう一度、弾いてくれよ。もしかしたら、好きになれるかもしれないから」
「いいよ」
僕は、もう一度、同じ曲を演奏した。
11
お気に入りに追加
37
あなたにおすすめの小説

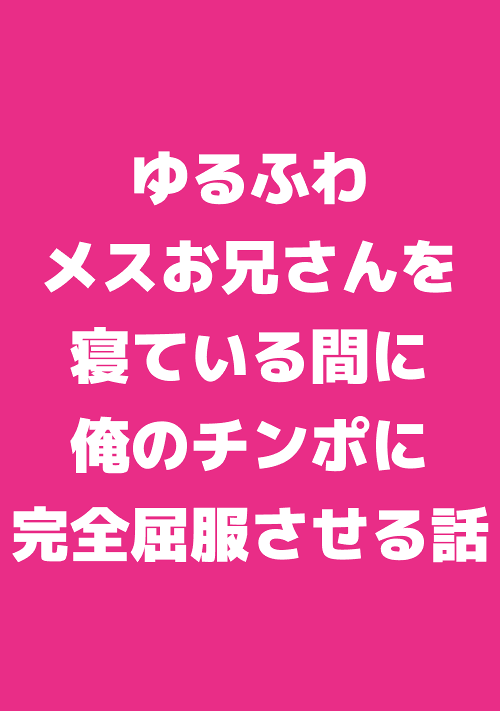
ゆるふわメスお兄さんを寝ている間に俺のチンポに完全屈服させる話
さくた
BL
攻め:浩介(こうすけ)
奏音とは大学の先輩後輩関係
受け:奏音(かなと)
同性と付き合うのは浩介が初めて
いつも以上に孕むだのなんだの言いまくってるし攻めのセリフにも♡がつく



部室強制監獄
裕光
BL
夜8時に毎日更新します!
高校2年生サッカー部所属の祐介。
先輩・後輩・同級生みんなから親しく人望がとても厚い。
ある日の夜。
剣道部の同級生 蓮と夜飯に行った所途中からプチッと記憶が途切れてしまう
気づいたら剣道部の部室に拘束されて身動きは取れなくなっていた
現れたのは蓮ともう1人。
1個上の剣道部蓮の先輩の大野だ。
そして大野は裕介に向かって言った。
大野「お前も肉便器に改造してやる」
大野は蓮に裕介のサッカーの練習着を渡すと中を開けて―…

肌が白くて女の子みたいに綺麗な先輩。本当におしっこするのか気になり過ぎて…?
こじらせた処女
BL
槍本シュン(やりもとしゅん)の所属している部活、機器操作部は2つ上の先輩、白井瑞稀(しらいみずき)しか居ない。
自分より身長の高い大男のはずなのに、足の先まで綺麗な先輩。彼が近くに来ると、何故か落ち着かない槍本は、これが何なのか分からないでいた。
ある日の冬、大雪で帰れなくなった槍本は、一人暮らしをしている白井の家に泊まることになる。帰り道、おしっこしたいと呟く白井に、本当にトイレするのかと何故か疑問に思ってしまい…?


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















