お気に入りに追加
26
あなたにおすすめの小説

NPCが俺の嫁~リアルに連れ帰る為に攻略す~
ゆる弥
SF
親友に誘われたVRMMOゲーム現天獄《げんてんごく》というゲームの中で俺は運命の人を見つける。
それは現地人(NPC)だった。
その子にいい所を見せるべく活躍し、そして最終目標はゲームクリアの報酬による願い事をなんでも一つ叶えてくれるというもの。
「人が作ったVR空間のNPCと結婚なんて出来るわけねーだろ!?」
「誰が不可能だと決めたんだ!? 俺はネムさんと結婚すると決めた!」
こんなヤバいやつの話。

ヒトの世界にて
ぽぽたむ
SF
「Astronaut Peace Hope Seek……それが貴方(お主)の名前なのよ?(なんじゃろ?)」
西暦2132年、人々は道徳のタガが外れた戦争をしていた。
その時代の技術を全て集めたロボットが作られたがそのロボットは戦争に出ること無く封印された。
そのロボットが目覚めると世界は中世時代の様なファンタジーの世界になっており……
SFとファンタジー、その他諸々をごった煮にした冒険物語になります。
ありきたりだけどあまりに混ぜすぎた世界観でのお話です。
どうぞお楽しみ下さい。
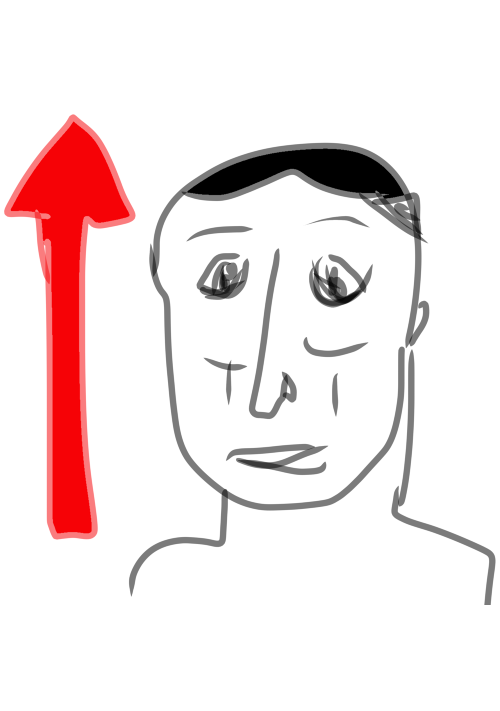
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

鉄錆の女王機兵
荻原数馬
SF
戦車と一体化した四肢無き女王と、荒野に生きる鉄騎士の物語。
荒廃した世界。
暴走したDNA、ミュータントの跳梁跋扈する荒野。
恐るべき異形の化け物の前に、命は無残に散る。
ミュータントに攫われた少女は
闇の中で、赤く光る無数の目に囲まれ
絶望の中で食われ死ぬ定めにあった。
奇跡か、あるいはさらなる絶望の罠か。
死に場所を求めた男によって助け出されたが
美しき四肢は無残に食いちぎられた後である。
慈悲無き世界で二人に迫る、甘美なる死の誘惑。
その先に求めた生、災厄の箱に残ったものは
戦車と一体化し、戦い続ける宿命。
愛だけが、か細い未来を照らし出す。

雨上がりに僕らは駆けていく Part1
平木明日香
恋愛
「隕石衝突の日(ジャイアント・インパクト)」
そう呼ばれた日から、世界は雲に覆われた。
明日は来る
誰もが、そう思っていた。
ごくありふれた日常の真後ろで、穏やかな陽に照らされた世界の輪郭を見るように。
風は時の流れに身を任せていた。
時は風の音の中に流れていた。
空は青く、どこまでも広かった。
それはまるで、雨の降る予感さえ、消し去るようで
世界が滅ぶのは、運命だった。
それは、偶然の産物に等しいものだったが、逃れられない「時間」でもあった。
未来。
——数えきれないほどの膨大な「明日」が、世界にはあった。
けれども、その「時間」は来なかった。
秒速12kmという隕石の落下が、成層圏を越え、地上へと降ってきた。
明日へと流れる「空」を、越えて。
あの日から、決して止むことがない雨が降った。
隕石衝突で大気中に巻き上げられた塵や煤が、巨大な雲になったからだ。
その雲は空を覆い、世界を暗闇に包んだ。
明けることのない夜を、もたらしたのだ。
もう、空を飛ぶ鳥はいない。
翼を広げられる場所はない。
「未来」は、手の届かないところまで消え去った。
ずっと遠く、光さえも追いつけない、距離の果てに。
…けれども「今日」は、まだ残されていた。
それは「明日」に届き得るものではなかったが、“そうなれるかもしれない可能性“を秘めていた。
1995年、——1月。
世界の運命が揺らいだ、あの場所で。



幻想遊撃隊ブレイド・ダンサーズ
黒陽 光
SF
その日、1973年のある日。空から降りてきたのは神の祝福などではなく、終わりのない戦いをもたらす招かれざる来訪者だった。
現れた地球外の不明生命体、"幻魔"と名付けられた異形の怪異たちは地球上の六ヶ所へ巣を落着させ、幻基巣と呼ばれるそこから無尽蔵に湧き出て地球人類に対しての侵略行動を開始した。コミュニケーションを取ることすら叶わぬ異形を相手に、人類は嘗てない絶滅戦争へと否応なく突入していくこととなる。
そんな中、人類は全高8mの人型機動兵器、T.A.M.S(タムス)の開発に成功。遂に人類は幻魔と対等に渡り合えるようにはなったものの、しかし戦いは膠着状態に陥り。四十年あまりの長きに渡り続く戦いは、しかし未だにその終わりが見えないでいた。
――――これは、絶望に抗う少年少女たちの物語。多くの犠牲を払い、それでも生きて。いなくなってしまった愛しい者たちの遺した想いを道標とし、抗い続ける少年少女たちの物語だ。
表紙は頂き物です、ありがとうございます。
※カクヨムさんでも重複掲載始めました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















