2 / 25
第一章
第一話
しおりを挟む
十年前──
彼女、赤星杏奈と会ったのはその日が最後だった。
私は当時、高校一年生。その日、学校が終わった帰りに、帰宅の電車を乗り間違えてしまった。私の降りる駅に急行電車は止まらない。いつもなら各駅停車の電車に乗るのだが、疲れていたのか、高校から始まった電車通学に不慣れなこともあり、よく確認もせず急行電車に乗ってしまった。
本来なら降りるはずの駅が車窓を過ぎ去っていく。私はひどく憂鬱な気分になった。何かこの後に予定があるわけではない。ほんの三十分ほど帰りが遅くなるだけのことなのだが。苛立ちに今にも消え入りたい気分だった。
ようやく止まった駅で、急いで反対側の電車に乗る。ちょうど反対方面に行く電車が到着していた。今度は各停であることをしっかり確認した。駆け足気味に車内に入る。少しして扉が閉まった。
「西塚さん」
不意に名前を呼ばれた。私はその声に聞き覚えがあった。驚いてその先を見る。知らない制服姿の、見覚えのある美しい少女がいた。赤星杏奈。中学の同級生だった。
切れ長であるが細くはない、凛とした且つ愛らしい目。少し面長で顎先は細く、滑らかな輪郭に、鼻筋は通り、整った顔立ちをしていた。美しい黒髪は、左右の耳上から後ろに結び、後ろ髪はそのまま背中まで流している。
私が知っている誰よりも彼女は美しく、そしてどこかあどけなさがあり可愛かった。
彼女は座席の端の仕切りにもたれていた。席はまばらに空いているが、知らない人の横に座りたくない気持ちが分かる。
赤星杏奈はその美しい目を細めて私に微笑む。
「中学の卒業式ぶりだね」
「うん。久しぶり」
私は息を呑むように言った。中学校の卒業式以来なので、まだ一ヶ月程度しか経っていなかったが、私にとっては実に数年ぶりに再会するような感慨があった。
しかし中学時代、彼女とはほとんど接点がなかった。私が一方的に懐かしんでいるだけで、彼女からしてみればただの顔見知りにたまたま会った程度のものだろう。
ここからの問題としては、地元の駅に着くまでの十数分、緊張に私の息がもつかどうか不安だった。
「赤星さん、少し背伸びた?」
苦し紛れに聞いてみる。私の身長が百六十センチ弱あり、目線が同じなので、彼女もそのぐらいの身長だろう。
彼女は上目遣いに視線を泳がせ、指先を唇に当てた。
「うーん、どうだろ。たぶん伸びた」
私はなんとなく彼女の雰囲気が変わったように感じ、そんな陳腐な質問をしてしまった。
もともと彼女は大人びた印象があったが、幼さが抜けて、今の彼女はより一層綺麗になった気がした。もっとも一ヶ月しか経っていない上に、私は彼女のことをよく知らない。ただ窓の外から見える彼女を眺めていただけの傍観者のようなものだ。
その後、他愛もない会話をしてやり過ごした。中学時代の思い出話や近況など。もっと気の利いた何か他のことを話そうと思うも、間をつなぐのに必死だった。私の必死さに気付いてか、彼女は優しく見守り、穏やかに受け答えしてくれた。
私は少し顔が熱っぽくなるのを感じた。
私は杏奈が苦手だ。というよりも、美人というものが苦手だった。それは私が女性を恋愛対象として見ているからだ。それに気付いたのは幼稚園の頃。五歳かそこらの頃だった。
幼稚園当時、私には好きな女の子がいた。彼女は友人として私のことを親しく思っていてくれたと思う。今では名前も顔も思い出すことはできない。それでもあの頃の胸の高鳴りと痛みを思い出すと、あれが最初の恋だったのだなと実感する。
どういう経緯でそうなったのか、記憶は朧げであるが、とにかく私たちはキスをした。初めてのキスはとても柔らかくて、温かったのを覚えている。
しかし次の日から彼女は私を避けるようになった。私が泣いて追いかけても、彼女は顔も合わせてくれない。どうして避けるのか、何一つ理由を教えてくれなかった。だから私は、私が悪かったと思うしかなかった。それ以来、私は誰かを好きだと思うことも、考えることもしないようにしてきた。
しかし美人というものは、容易く私の心を揺るがしてしまう。だから苦手だ。
電車が駅に着いた。私たちは一緒に降りた。
改札に向かう途中、赤星杏奈が私に聞く。
「西塚さんは高校も美術部なの?」
「部活は入ってないや」
「そっか。まだ絵は描いてる?」
「たまに」
それに赤星杏奈は微笑んだ。
「私、サヨちゃんの絵が好きだよ。これからも描き続けてね」
「え? あ、うん」
突然下の名前で呼ばれて私は動揺した。彼女に下の名前で呼ばれたのはこれが初めてだったと思う。それを親愛というよりも、何かからかうようなニュアンスと私は受けとめた。
「バイバイ」
そう言って、改札を抜けると彼女は私に手を振り、反対方面に去っていった。
私は小さく手を振り返した。
それが彼女と会った最後の記憶だった。
それから駅のホームでも地元でもすれ違うことはなかった。中学を卒業してから、二度と見ていない同級生は山ほどいるのでそんなものなのだろう。彼女は成人式や同窓会にも出席しなかった。風の噂には国立大に進学したのなんのと聞いたぐらいのもの。
私が後悔をする筋合いはまったくないが、あの時、もっと何か気の利いたことでも言えていれば、何かが違っていたのだろうかと思ってしまう。
とにかく彼女を見たのはそれが最後だった。
一ヶ月前、十年ぶりに彼女と再会するまでは。
* * *
現在──
私──西塚小夜子、女性、二十五歳──は眠い頭で体を起こす。カーテンを透過して朝日が差す、薄明るい灰色の朝。
するりとタオルケットが滑り落ちる。傍らに胎児のように丸まって眠る彼女の輪郭があった。掛け布団は彼女が引き裂いた。圧迫感が嫌いなのかもしれない。それ以来、タオルケットで代用している。
私は彼女を起こさないようにベッドを出ようとした。しかし上着の裾を掴まれて、私の気遣いは無意味だったことを知る。振り返ると、彼女は先ほどと同じ姿勢のまま手を伸ばして、私の裾をつまんで無邪気に微笑んでいた。
「サヨちゃん」
「おはよう、杏奈」
彼女──赤星杏奈、女性、二十五歳──は私の中学の時の同級生。十年ぶりに再会した彼女と、一ヶ月前から奇妙な同居生活を送ることになった。
杏奈は起き上がると、両手を広げて、私に倒れかかるように抱きついてくる。私は彼女の背中をなだめるように撫でた。
「朝ご飯の準備するから、離して」
「手伝う!」
それに私は苦笑した。彼女にそんなことできるはずがないからだ。
私は杏奈の腰に手を回して、支えながらリビングに出る。壁沿いのスイッチに手を伸ばす。カチリと音が鳴り、部屋の照明が点く。
1LDKの賃貸マンションの一室。そこに私たちは住んでいた。大学生以来、私が住んでいる部屋だった。
リビングには二人がけのソファとローテーブル。ソファの上には一抱えほどある黒茶色のキジトラ猫のぬいぐるみがある。私が昔買ったものだが、今では杏奈のお気に入りだった。
その向かいのテレビ台の上には40インチの液晶テレビ。そのテレビの横には、円筒形の台座があり、その上にカメラレンズのついた球体が乗っている。いわゆる見守りカメラである。
ローテーブルの上には昨日の飲みかけのグラスが置いたままになっていた。それと紙を三角に折って立てた、ストローを使ってコップから水を飲む女の子の絵があった。私が杏奈のために描いたものだった。天板下の収納棚にはスケッチブックと食べても大丈夫なクレヨン。
いくつか段ボールが空いた場所に積んである。中には杏奈が破壊した物と不用品が入っていた。私が「嵐の七日間」と呼ぶ一週間で杏奈が破壊した物だ。そのうち捨てる予定。インテリアは他にほとんど何もない。あとは本棚ぐらいか。私の買った漫画やDVDが並べてある。
私は杏奈をソファに座らせ、テレビを点ける。朝のニュース番組がやっていた。番組映像はフレームに切り取られ、画面下部に大きな余白がある。そこには現在の交通情報が淡々と流れては切り替わっていった。
杏奈はぬいぐるみに抱きついて寝っ転がる。
私はリモコンをテーブルに置き、グラスを持ってキッチンのシンクに向かった。キッチンはリビングに併設されており、冷蔵庫も隣にある。
私は先にトイレを済ませて戻る。
「杏奈、トイレは?」
「行く!」
私は再び杏奈を抱き起こす。杏奈は私にじゃれつき、互いの足をもつれさせ笑い合う。
「杏奈、開けて」
「うん!」
トイレのドアノブはレバー状のハンドルタイプ。それに手をかけ、上に回したものか下に回したものか奮戦し、ガチャガチャと鳴らす。たまたま下に押した時にドアが動いて、そのまま引くと、見事開けることに成功した。杏奈は私を見て誇らしげに笑う。
私は杏奈の頭を撫でてあげた。
「あとは自分でできる?」
トイレの便座の蓋は常に開けてある。またトイレとバスルームは同じ場所にある。ユニットバスというやつだ。
杏奈は答えず、笑顔で両手を広げて私の方を向く。
私は苦笑して、彼女の腰に手を回す。彼女のズボンとパンツに指をかけて、するりと脱がす。このぐらいなら彼女でもできる時があるが、出勤前なので時間を節約したかった。また脱ぐことと座ることをセットでするのは難しい。以前、転倒して頭をぶつけ、悲惨なことになったことがあった。
「終わったら教えて」
「うん!」
間違えて鍵を閉めて、閉じ込められないようにドアは開けたまま。
私は朝食の準備にキッチンへと戻る。昨日の残りの味噌汁を温め、ご飯と卵を落として雑炊にする。
赤星杏奈。彼女は中学時代、私だけでなく、同級生全員の憧れだった。
当時の赤星杏奈は芸能人だとかモデルだとか、アイドルの誰々にも負けないほどの美人であった。ただ今でも面影を十分に残していて、黙っていれば相変わらずの美人ではある。
さらに彼女は成績も優秀で学年一位。偏差値七十いくつの高校へ進学した。私は偏差値四十程度の公立高校へ。人類として何か別のものだった。
確か生徒会長にもなっていた。あれは中学三年の時か。毎週月曜朝の全校集会では彼女の挨拶から始まっていたような気がする。
また私は絵を描くのが好きだったのだが、彼女が美術の授業で描いた作品が何かのコンクールで表彰されていた。私の作品については言うまでもない。
また彼女は合唱発表会だとかも指揮や伴奏を務めていた。
そして嫌味なく人当たりがよくて、誰からも好かれて、よく小動物のような女友達を連れていたと思う。その子が親友だったかどうかは知らないが。
その杏奈が今では、文字を読むこともできない。浮かんで滑っていくと言っていた。ペットボトルを開けたり、水道から水を汲むこともできない。使い方が分からない、覚えられないと言っていた。前にペットボトルを開けられず、かじりついて穴を開けて飲んでいた。ドアの開け閉めは出来る時と出来ない時がある。ドアノブに苦手なタイプと得意なタイプがあるようだった。
杏奈は朝食も一人では食べられない。スプーンもうまく使えない。握ったスプーンに掬い取っても、こぼすか顔に塗りつけてしまう。それなので私が食べさせた。
私たちはローテーブルの前に座る。
「はい、あーん」
「あーん」
杏奈は嬉しそうに私が運ぶ物を食べていた。彼女が咀嚼している間に私も食べる。面倒なので同じ食器を使う。別に成人女性同士、気にすることもない。
食後、私は彼女の口周りを拭い、食器を片付ける。シンクに食器を置き、水につけておく。洗うより先に杏奈の水分摂取を促す。放っておけば彼女は何も飲まないで、死ぬまでそうしているだろう。
「杏奈、お茶でいい?」
ソファに寝っ転がっていた杏奈は、体を起こして不満げに言う。
「やだ! ブドウジュース!」
「はいはい」
私は自嘲気味に笑う。杏奈の言い方が子供じみて可愛いと思ってしまった。
私は冷蔵庫から取り出したブドウジュースの紙パックから、ステンレスのコップに注ぐ。ガラスだと取りこぼしたり、何かの拍子に落として割ってしまいかねない。
私はコップにストローを差して杏奈のところに持っていく。それに杏奈は両手を出して受け取る。彼女がストローを咥えるまで私は手を離さなかった。飲み終わったのを見届け、コップを受け取り片付ける。
これが私の朝だった。
私はこの生活に苦痛を感じたことはない。不快に思ったこともない。彼女を哀れに思い、同情しているわけでもない。下心は否定できないが。
これはただの私の余生だから。そう思うと大概のことがどうでもよくなった。
というのも、彼女と再会する直前、私は大学時代から付き合っていた恋人と別れ、死ぬことにしていたからだ。それから偶然というべきか、気紛れにというべきか、十年ぶりに杏奈と再会することになった。彼女は私の記憶とは結びつかない、かけ離れた姿となっていた。そこからほとんど勢いで彼女を引き取った。
決して彼女と心中するつもりではない。
ただあの暗い闇の中で、美しかった者の残骸が腐敗して朽ちていくのを、間違っていると感じた。それだけだった。
私はもろもろの支度を終えて、出勤すべく、ソファに寝っ転がる杏奈に言う。杏奈は相変わらずぬいぐるみを抱きしめている。ちなみにこのぬいぐるみの名前は「ウリ坊」という。メス猫だ。
「ウリ坊と留守番しててね。お昼ご飯、机の上に置いてあるから。ちゃんと食べるんだよ」
「はーい!」
杏奈はウリ坊をぎゅっと抱きしめて言った。
私はローテーブルの上に、ストローを挿した水の入ったコップと、ラップをかけたおにぎりの入った皿を置いた。おにぎりを一枚一枚ラップで包むと、杏奈がそのまま食べてしまうので、皿にだけラップをかけておく。これならなんとかラップを剥がすことに成功すれば食べられる。ついでに画用紙とクレヨンを置いておく。何か手先を動かせば社会復帰の助けになるかもしれない。
また仕事中、合間を見つけてスマートフォンのアプリから、家の中の様子を確認し、スピーカーで呼びかけて水分の摂取や食事を促した。そうしなければ一日中食事をしないこともある。またテレビや空調といった室内環境の管理もできるので、こまめに確認するようにしていた。
「それじゃいってくるね」
「いってらっしゃい!」
杏奈は体を起こし、ウリ坊を手放して、両手を広げて私を待ち受ける。
家を出る時、杏奈はキスを求めてくることがある。どういう訳か杏奈の中で私は恋人ということになっていた。
騙したわけではない。彼女が一方的にそう思っているだけ。しかし精神的に弱っている彼女の弱みにつけこんでいるようで罪悪感があった。
それでも憧れだった彼女とキスできるのは嬉しかった。これが私の下心だ。
彼女の頬に触れ、髪を撫で、唇を重ねる。
彼女の唇は柔らかく、ブドウの甘い匂いがした。
私は理性を失う前に唇を離し、どこか不満げな杏奈の頭を撫でて家を出る。
私は今日一日、自己嫌悪と劣情の炎に苛まれることを覚悟しなければならない。
こんな状態で過ごさなければならないのが私の罰か。
* * *
一ヶ月前──
大学を卒業し社会人となってから三年が経った。
そして先日、大学時代から付き合っていた恋人と別れた。
元恋人、蛍野南帆。小柄で、ショートヘアを好み、ベージュ系の髪色は季節によってよく色を変えた。
彼女は大学の同期。同じ専攻だった。知り合って七年、交際期間は四年と七ヶ月ほどか。その彼女に別れを告げられた。
私は失恋の傷心を癒す、つもりは毛頭ないが、有給休暇を取り、週末の土日と合わせて実家に帰った。
私の地元は閑静な住宅街で、東京郊外にある。一軒家で、二階に私の部屋があった。一階にはリビングや両親の居室。
実家に帰ると、母はいつも通りの調子だった。私たちはリビングで適当な会話をする。
「小夜子はまだ結婚しないの? 付き合っている人とかいないの? 仕事辞めてこっちでお見合いでもしたら? 仲良かった英美香ちゃんなんて三人目ができたそうよ」
ああ、すごくいい。とても死にたくなる。私はこれを求めて実家に帰ってきた。
私が実家に顔を出した理由。母の小言と同世代の今を聞かされることで、私の中の死にたさを補強してもらいに来たのだ。事実、私は死ぬ予定だった。死ぬと決めた時点で死ぬつもりだったが、せっかくなので背中を押してもらいにきた。
次に私はその英美香に会いに行った。小学校以来の親しい友人だった。彼女は高校卒業後、大学には進学せず、年上の社会人と結婚した。
正午過ぎ、私たちは駅前のファミレスで軽食を共にした。
英美香は細目であっさりした顔立ちで、いわゆる弥生顔というやつだろうか。私が一番落ち着く馴染みやすい顔立ちだった。高校からメイクをするようになって、今では化粧品で一重を二重瞼にして、つけまつ毛でさらに目を強調し、長い金髪はくるくる巻いてある。これはこれで緊張しないで済む容姿だ。
英美香は久しぶりの再会に早口でたくさん喋る。
「親バカかもしれないけど本当にうちの娘、本当にめちゃくちゃ可愛いの! 大きくなったら絶対子役にする! 三人目も女の子だといいなあ。西塚もさ、まあ結婚はしなくても、恋人かいい感じの人ができたら紹介してよ。うちらの仲でしょ? 職場とかにいい人いないの? 誰か紹介しようか? 今度一緒にキャンプとかしようよ」
私は笑って適当に相槌を打つ。こういう未来の話をするのもいい。私にそんな簡単に恋人ができるわけがないことを彼女は知らない。それに簡単に作ろうと思えるほど、私は器用じゃなかった。そんな未来がどうあっても来ないことを実感すると、どんどん死にたくなってくる。
不意に英美香は意外な人物の名前を口にした。
「そういえば、赤星さんって覚えてる?」
ここで私は久方ぶりに赤星杏奈を思い出した。最後に会ったのは十年前。それ以降の彼女を知らない。さぞかし彼女の成功談は私の劣等感をくすぐり、私を死にたくさせてくれるのだろう。それに彼女の名前を聞いただけで、なぜか私の胸は痛くなった。もし彼女に恋人ができたり結婚していたらと思うと、なぜか私はどうしようもなくこの世界から消えてしまいたい気分になった。
もしかしたら私は今まで、無意識か意図的に彼女を思い出さないよう、話題を避けてきたのかもしれない。
しかし今はより深くこの胸を抉ってほしかったので、渡りに船だった。
「中学の時、生徒会長やってた人でしょ?」
「そうそう。大学は国立に進学して、でかい有名な会社に就職までしたのにさ。一年で辞めたらしいよ」
「え、なんで?」
何やら雲行きが変わってきた。私はそんな話が聞きたかったわけではない。とても信じられないと思った。
「なんか病気だって」
「何の?」
「なんだっけ、とうごー、なんとか」
「統合失調症?」
「そうそう、そんな感じの名前の。それで退院しただかで、最近こっちに帰ってきたらしいんだけど。それからずっと引きこもりなんだって」
「……赤星杏奈の話だよね?」
赤星杏奈にそんなことがあってはならない。私は認められなかった。
しかし英美香はこともなげに肯定する。
「そうだよ。赤星杏奈」
「誰か赤星さんとは会ったの? 英美香は会った?」
「私は会ってないよ。たぶん誰も会ってないと思う。もし会いに行って殺されたりしたら嫌じゃん? それに私、赤星さんと別に仲良くないし」
私の中の赤星杏奈像と、今の彼女の間にひどい乖離があった。恐らくそれは彼女を知る誰もが抱いただろう。あの完璧だった少女が、得体の知れない怪物になってしまったような感覚がした。
「赤星さんの住所って分かる?」
「分かんないけど、中学の時の卒アルかなんかに載ってるんじゃない?」
「確かなかった気がする」
「そしたら同窓会主催してたやつに聞いてみる? 案内の葉書とか送ったりしてるから、住所知ってるんじゃない?」
「誰だっけ?」
「そういえばお前、成人式以来、ろくに来てなかったもんな。私の方で聞いてみるよ」
「ありがとう」
「なに? お見舞いでもいくの?」
「ああ、うん」
「西塚って赤星さんと仲良かったっけ?」
「別に仲良くないけど」
「だよね。そもそもうちらとはグループどころかカーストが違ったし」
中学時代、私と英美香は、赤星杏奈と授業や課題に関する以外で会話したことがなかった。
英美香が私に協力してくれるのは面白がっているだけだろうし、英美香も私が杏奈を心配しているなどと思っていないだろう。
私が赤星杏奈と会おうと思ったのは、私以上の苦境にいる人を見て溜飲を下げようという訳ではない。彼女に元気の出そうな励ましの言葉を一つかけて、その空々しさと自己嫌悪で希死念慮を加速させようという魂胆だった。
赤星杏奈の住所が分かったのは翌土曜日。明日には私は終わる予定なので、ちょうどいいタイミングだった。
私は特に連絡も入れず、赤星杏奈の家を訪問する。会えなければ、その時はその時。住宅街に一軒家、私の実家より大きく見えた。煉瓦のような赤褐色のタイル張りの外壁。門扉に「赤星」の表札は黒地に金字。そういえば赤星には金星という意味もあるのだったなと、当時インターネットで検索して彼女の名前を心に噛み締めたことを思い出した。
インターフォン越しに、おそらく彼女の母が出る。
『どちらさま?』
「私、杏奈さんの中学の時の友人の、西塚小夜子といいます。たまたま実家に立ち寄ったので、杏奈さんにも会えたらと伺いました」
『もしかしてサヨちゃん!?』
「あ、はい?」
その呼ばれ方に強い違和感を覚えた。
赤星母とは面識がない。学校行事のどこかですれ違ったことはあるかもしれないが、会話をした覚えもなければ、愛称で呼ばれる筋合いもない。
私は両親や友人によって「サヨちゃん」と呼ばれることもある。英美香は小学校以来、徹底して「西塚」だが。私が英美香を「英美香」と呼ぶのは出会った頃の彼女の一人称が「英美香」だったからだ。
しかし赤星杏奈に「サヨちゃん」などと呼ばれる筋合いはない。いや、一度だけ、最後に会った時にそう呼ばれたことを思い出した。だがそれは親愛というよりも、ふざけてそう呼んだようなニュアンスではなかったか。
私たちは全く親しくもなく、電話番号もメールアドレスも互いに知らない。ただの中学の同級生で、交流などほとんどなかった。
それなのにインターフォン越しの動揺したような声音は、なぜか私のことを知っているような感じがした。
玄関が開き、慌てた様子で、少しやつれた感じの初老の女性、赤星母が出てくる。髪は整えた様子もなく、服もみすぼらしい。以前はそれなりに美人だったのではないかとうかがえるのは、杏奈と同じように目鼻が整っていたからだ。
「わざわざありがとう。どうぞ、あがって」
「お邪魔します」
私は玄関で靴を脱ぐ。ドアが閉まる。木の匂いが広がった。
他人の家に入った瞬間、その家独特の匂いがするものだ。それは木材の違いによるものなのか、どこからか漂う仏壇の線香のブランドによるものなのか、芳香剤か何かの匂いなのだろうか。
とにかく赤星家は木の匂いがする家だった。
私は赤星母の案内で杏奈の部屋に向かう。
「サヨちゃん、来てくれてありがとう。私からも連絡しようと思ったんだけどね、なんて伝えたらいいか分からなくて」
「はあ」
私と赤星杏奈はそんな間柄ではない。そもそも友人ですらない。もちろん赤星母と会って話すのは今日が初めてだ。実際に会ってみて確信した。それなのに何か私のことを知っているような口ぶりだった。ただその違和感には、今はあまり興味がなかった。何か勘違いしているのなら好都合程度に思った。
「杏奈さん、どうされたんですか?」
私は杏奈の近況を尋ねた。
「杏奈ちゃんね、仕事で無理しすぎちゃって、それで疲れちゃったみたいなの。病院も退院したし、もう大丈夫。杏奈ちゃんに聞いてたけど、また昔みたいにあの子と遊んでくれると嬉しいわ」
ここで私が気付いたのは、おそらく「サヨちゃん」という別の誰かと私を混同しているのだろう、ということだった。そのことが申し訳なかった。偽物の「サヨちゃん」が来訪したことで、本物の「サヨちゃん」に連絡がいかなくなるかもしれない。帰り際に訂正しておくことにした。
「杏奈ちゃん、調子が悪くて部屋から出られないかもしれないから。ドア越しにでも声をかけてくれたら嬉しいわ。階段を上って、左手の部屋だから」
「はい」
階下で赤星母は私を見送り、私は一人彼女の部屋へと向かった。
英美香の話は半信半疑だった。しかしこれまでの会話から十分、英美香の話が真実だと確信に変わっていった。得体の知れない汗が出た。背中にブラウスが張り付く。
どこか現実味のない浮遊感が私の中にあった。現実から切り離されたような、夢の中で粘質を帯びた大気の中をかき分けて泳ぐような異質感があった。
私は赤星杏奈の部屋の、ドアの前に立つ。ノックする手前まで伸ばした手が止まる。彼女の面影が過ぎった。凛とした美しい面差し、花が咲いたような愛らしい笑顔。その彼女がこの先にいることが想像できなかった。この扉の向こうで今、どんな姿をしているのか。全身をウジに蝕まれ、人の形をした腐敗した何かを想像した。
私は息を呑んでからノックした。二度、三度。しばらく待つが返事はない。
「赤星さん」
呼びかけてみた。すると衣擦れのような、身じろぎするような気配がした。巨大な芋虫が無数の足を蠢かし這いずるような、甲虫がその硬質な羽を擦り合わせて今にも羽ばたこうとしているようなイメージが、私の中にわいてきた。私は足先から、全身にかけて鳥肌が立つのを感じた。
それでも私は続けて呼びかける。
「覚えているかな? 中学の時一緒だった、西塚小夜子だけど。たまたま実家に寄ったから、赤星さんのこと気になって立ち寄ったんだけど」
返事は期待していない。私は一方的に話しかけるつもりだった。
さあ、ここから私は彼女に元気の出る励ましの言葉を投げかけよう。
何か辛いことがあったと思うけど元気を出して。あなたなら立ち直れるよ。きっといいことがあるよ。無理しないであなたのペースで頑張って。たまには外に出てみたら? ずっと部屋の中にいると気分が滅入るよ。アロマとか炊いて気分転換してみたら? みんな心配しているよ。悩んでいることがあったら誰かに相談してみて。きっと力になってくれるはず。
よし。
私を殺してきた言葉たちで彼女を八つ裂きにするのは気が引けるが、もうこうなってしまった彼女を救えるとは思えないので、せめて何か一つでも彼女に届いて力になることができたら、私がこの世界に生まれてきたことにも意味があったというものだ。
私は彼女に元気になる言葉をかけようとした。その時、積み上げた荷物が崩れるような、床に投げっぱなしになっているCDのケースを踏み割るような、種々雑多な騒音がした。
「赤星さん!?」
何事か起きたのかと動揺し、先程まで考えてきた言葉が雲散霧消した。
踏み荒らす音が扉に近づいてくる。それに私は赤星杏奈の亡者が狂ったようにのたうち回りながら、迫ってきている姿を想像した。思わず一歩後ずさる。
ドアノブがガチャガチャと乱雑に鳴らされ、ガタガタと音を立ててドアが揺れた。私の喉からひっと乾いた声が漏れた。
そして扉が開け放たれる。暗闇が口を開いた。そこから腐臭が立ち込めてきた。私は咳き込みそうになるのを堪えた。
そして闇の向こうからまろび出た黒い塊──と見てとれたのは、無造作に伸びた黒髪を振り乱した女性だった。私の目の前に立ち、今にも掴みかからんとばかりに手を広げて、顔をじっと見てくる。淀んだ黒い瞳と目が合った。
突然のことに私は心臓が止まりそうになった。本当は赤星杏奈はとっくに死んでいるのではないか、今目の前にいるのは彼女ではない別の何かではないか、そう思った。あるいはそう思いたかった。
しかしその髪の下に、私はあの頃の面影を留めた白い顔を認識する。
彼女は唇を震わせながら口を開いた。
「……サヨちゃん?」
無人の荒野をさまよい数年ぶりに人里を見つけて水を求める放浪者のような声だった。そしてやはり彼女に下の名前で呼ばれることに強い違和感を覚えた。
「久しぶり。赤星さん」
私はすっかりせっかく考えた元気の出る言葉を一つ残らず失念してしまった。あまりに目の前の彼女が変わり果てていたからだ。髪はボサボサで、怯えたように背筋は丸まり、楚々とした彼女の姿はそこになかった。全くの別人の家を訪問したのか、と再び疑念がもたげた。それでもあの頃の面影を留め、その整った顔立ちは忘れようがなく、やはり彼女が赤星杏奈だと疑いようがなかった。
立ち尽くし言葉を失った私に杏奈が言った。
「……どうして?」
その言葉に続くのは「ここにいるの?」、「来たの?」だろうか。それに私は我に返る。
「近くに寄ったから」
私はドアノブを掴む。
「部屋、入ってもいい?」
「え、あ……」
私は返事を待たずに踏み入る。それに赤星杏奈は動揺して、私の袖に弱々しくすがりつく。彼女の部屋は、カーテンが締め切られ、とっくに昼だというのに薄暗かった。腐敗臭が立ち込め、そこら中にゴミ袋や物が散乱していた。普段そこで寝ているためか、ベッドにはゴミが少ない。
私も部屋は片付けられない方だが、こんな異臭の立ち込める部屋で、一日過ごすだけでも正気とは思えない。おそらくこの臭いの中に汚物も混じっているだろう。
杏奈は私の袖にすがりながら、何か言おうとして、言葉にならず呻いていた。今にも泣きそうな顔をしていた。
こんなことがあってはいけない。こんな場所に彼女がいてはいけない。私はそんなことを強く思った。
「私と来る?」
不意に私の口から出た。私は、自分でいったい何を言っているのか、私自身に混乱した。
杏奈も戸惑っているようだった。
「……どういうこと?」
「今一人暮らししてるんだけどさ。同居人がちょうど出て行って。まあ、それだから、うちに来れば? って」
十年ぶりに再会して、まともな会話一つしていない。ただ私を突き動かす、強い衝動があった。
「まあ、いきなり迷惑だよね。ただこのままだと──」
「行く」
「え?」
「行く」
彼女は目を大きく見開いて、私の腕に強くその指を食い込ませていた。痛いぐらいに。
「ああ、うん。じゃあ、行こうか」
これ以上何か言葉をかける必要もない。そう思った。
これが正しいか、何がいいか分からないが、とにかく私は赤星杏奈をこの暗闇から救い出したい。
私は彼女の手を取り、部屋を出る。
一人でまともに歩くことのできない杏奈の腰を抱き支え、階下に降りると、赤星母は私たちを見て、目を見開き驚いた様子で立ち尽くしていた。
「私が杏奈さんを引き取ります」
それだけ言うとすんなり私は杏奈を引き取ることができた。何か制止されるかと思ったが、赤星母は何も言わなかった。
私は電話番号をメモ紙に書いて渡し、以降、電話番号をもとにショートメールで連絡を取り合った。
心配しているだろうと思って赤星母に律儀に近況報告をしていたが、恐ろしいぐらいに彼女は杏奈に対して無関心で、一度たりとも近況を尋ねてくることはなかった。そのうち返信がなくなり、私も徒労に感じて報告をやめた。
意地の悪い考え方だが、ようやく肩の荷が下りた程度にしか思っていないのではないだろうか。
ただ彼女を責めたり、詮索することはやめよう。
とにかく誰一人損をしていないのだから、結果的にはよかったのだと思う。
* * *
現在──
私は都心部のオフィス街にある、デザイン系の会社で働いていた。正社員とアルバイト含めて六十人近く在籍している。
業務は広告やパッケージのデザイン、パンフレットや書籍の校正などもあった。
独特かは分からないが、フリーアドレススタイルを採用しており、個々の座席は決まっていない。電源があるところに、なければ増設して、デスクをつなげて通称「島」を形成する。あるいは縄張りという意味で「シマ」かもしれない。
私はタイムカードを押してから、自身のシマに向かう。シマは点在し、私の席は窓際から一番遠い、奥まった暗いところにある。
「おはようございます」
私はパソコンのモニターに向かっている玄野希亜先輩──女性、二十八歳、私より三つ年上。今年二十九歳になる。三十歳になることを非常に恐れている。独身──に挨拶をする。顔立ちのはっきりした美人だった。ブラウンの髪を無造作にまとめて、グレーのジャケットの肩にかけている。眉をしかめて、大きな瞳をこらしていた。もともと目力があるのに、今日はライトグリーンの虹彩が入ったカラーコンタクトを入れていて、綺麗だと思う反面、威圧感がすごかった。
「おはよー」
玄野先輩はこちらを見もせずに言う。デスクの上には栄養ドリンク剤の瓶が並んでいた。花瓶にでもすれば風流かもしれないと、ふと思った。
私も自身の席に座り、パソコンを立ち上げる。私たちは隣り合うように座った。
「何徹目ですか?」
「まだ二徹目」
ここ一ヶ月、早上がりしているのが申し訳なかった。
かといってそのことで彼女が不機嫌なわけではない。朝の彼女はいつもこんな感じだった。
玄野先輩には、私が新卒で入社してからずっとお世話になっている。
一年目は彼女のアシスタントとして、仕事だけでなくデザイン理論やノウハウを教え込まれた。
二年目からは先輩から引き継いだクライアント対応をしたり、オペレーションを任されるようになった。今でも共同していくつかプロジェクトを進めている。
後に知ったことだが、玄野先輩はきつい性格で同僚から敬遠されていて、新人潰しとしても知られていた。
これについて私なりの考えだが、玄野先輩がかなりの美人であることが原因だと思っている。彼女は口調と態度がきつい。またはっきりと物を言うので、美人に叱責されて、特に男性陣はメンツが立たず、避けられるようになったのではないか。
しかし私は元から美人が苦手だったので、逆に美人に叱責されても、誰に叱責されるのとも変わらなかったのかもしれない。
ただ長く一緒にいると、実際にはそれほど時間はかからず、彼女の可愛いところをいくつも発見した。
そして少年漫画が好きで、意外とカップリング厨であること。私もアニメや漫画が好きで、無意識に彼女が小声で口ずさんでいる歌が、私の好きなアニメの主題歌であることから判明した。
私は立ち上がったパソコンのモニターに認証画面が出て、パスワードを打ち込むと、ふと思い出した。
「先輩、あれ連載終わっちゃいましたね」
「そうなのよー」
息を長々と吐き、デスクに突っ伏する。
「でも主人公があの選択するとは思いませんでしたね」
「ね。まだ完結じゃないってことでしょ。まだ続編の可能性があるわ。それに私としてはヒロインよりも、ライバルの子とくっついてほしい」
そう言いながら左手用の片手キーボードを軽快に打ち、右手をペンタブの上に走らす。
画面上ではベジェ曲線のパスが打ち込まれ、そのハンドルを伸ばしながら、何か可愛い動物の絵になっていった。
「何のマスコットですか? リス?」
「モモンガ。会社のマスコットだって。原案通ったからサンプルの制作。デザインが決まったら差分の作成」
「あー、先輩のクライアントの、新しい子会社のでしたっけ? パンフレットとか、ホームページのデザインもやるんですよね」
「そうそう」
「私も手伝いますよ。今の案件、今週中には片がつくんで」
「少しだけ手伝ってもらおうかな。西塚さんの帰りが遅くならない程度に」
「すみません……」
本当はとことん手伝いたいのだが、杏奈のこともあり、ここ一ヶ月は先に上がっていた。
「恋人とうまくいってるの?」
不意に玄野先輩が尋ねる。私はどきりとした。先輩には杏奈のことも、彼女と別れたことも話していない。
「はい、まあ」
「あ、こういうの同性でもセクハラになるんだっけ?」
「いえ、全然! 玄野先輩なら問題ないです」
「よかった」
他の人に言われたらセクハラかもしれないが、玄野先輩は以前、私の恋愛相談にも乗ってくれていた。そして私が女性と付き合っていたことも知っている。
「また今度一緒にスパ銭行きましょう。この間新しく出来て、気になっているところがあるの」
「はい、ぜひ。ちょっと今慌ただしくて。落ち着いたら」
そして先輩はスーパー銭湯が大好きだった。
私が一年目の頃、終電を逃した際に連れて行かれ、それ以来一緒に行く仲になった。
昼食はそれぞれのタイミングでとる。
たまに玄野先輩に誘われることもあるが、杏奈と暮らすようになってからは、電話をしなければならないと断った。先輩も無理には誘ってこない。
私は用事が済んだらデスクでランチをするようにしていた。先輩も最近は外食せず、一緒にオフィスで食べている。
「三十分ぐらいしたら戻りますけど、駅前に来てるキッチンカーで何か買いますが、先輩も何かいります?」
「あ、じゃあ頼んじゃおうかな。今日は木曜日だからタイ料理?」
「確かそうでしたね」
「私グリーンカレーとパッタイの二つ盛りのやつで」
「了解です! 私はガパオライスにしようかな。一口食べます?」
「うん。一口交換しましょ」
玄野先輩は鞄から財布を出し、そこから二千円を取り出す。
「あ、千円もしないですよ!」
「いいの。西塚さんの分もそれで買って。お釣りは返してね」
「ありがとうございます! お言葉に甘えて」
私は素直に感謝し受け取る。
正午を少し過ぎたあたり。
青空には雲がなかった。少し肌が汗ばむが、風が気持ちよかった。
私は昼を買いに行く前に、駅前の広場にあるベンチに座る。そこでスマートフォンを開き、見守りカメラのアプリを起動した。
画面に家の中の様子が映る。杏奈がソファに寝転がっていた。相変わらずウリ坊を抱きかかえている。朝からこのままだったのだろうか。
「杏奈」
私が呼びかけると杏奈は跳ね起き、辺りを見回す。
「サヨちゃん? どこ?」
「まだ仕事中。ちゃんと水飲んだ?」
「まだ!」
杏奈は天井に向かって答えた。
「じゃあ飲もうか。テーブルの上に置いてあるよ」
「うん!」
杏奈はローテーブルの上のコップを両手で取り、ストローを咥える。
「えらいえらい」
褒めると杏奈は嬉しそうに笑う。
「ご飯、ちゃんと食べるんだよ」
「うん!」
「ラップに気をつけてね」
「うん!」
杏奈は皿の上のラップを剥ぎ取り、手掴みでおにぎりを食べる。一口で頬張り、まだ口の中にあるのに次を食べようとする。
「ゆっくり食べるんだよ」
「ん!」
口の周りに米粒をつけながら、幸せそうに食べていた。
「サヨちゃんのおにぎり、おいしい!」
「ありがとう」
私は杏奈を眺めていると癒されるような気分になった。
「可愛いなあ」
思わず口から漏れた。
私はしばらく杏奈を見守り、それからキッチンカーに向かった。
* * *
仕事を終えて、自宅近くの駅に着いたのは二十一時を回った頃だった。杏奈と暮らすようになって帰宅時間が随分と早くなった。以前は終電で帰ることもざらにあった。
一人で何もできない杏奈。お腹が空いたからと冷蔵庫から食べ物を取り出して、ましてや電子レンジで温めることなどできない。近所のコンビニに一人で買いに行くこともできない。
私は帰り道にあるスーパーで、適当な惣菜と酎ハイ類を買って帰る。
帰宅し、玄関を開ける。
「ただいまー」
「サヨちゃん!」
杏奈は玄関前でしゃがみ込み、私の帰りを待っていた。
「遅くなってごめんね」
杏奈は勢いよく立ち上がり、よろけながら私に抱きつくと、顔をくっつけて頬擦りしてきた。何か大きなネコ科の動物を飼っている気分だった。
一人では満足に歩けない彼女だが、最近は玄関前で私の帰りを待っていることが多くなった。
誤って外に出てしまうんじゃないかという懸念はある。彼女が鍵を開けてドアノブを回すという、二つの手順を成し遂げることは難しい。しかし何度も試行すればそのうち開けられる可能性がある。
そこで鍵のつまみに両面テープを重ねて貼った。杏奈はねばつくものを嫌がる。粘着テープを回転させて床などを掃除するローラーの、使用済みのテープを剥がしているところを、杏奈が興味ありげに見ていたことがあった。「やってみる?」そう言って手渡すと、新鮮なテープの表面に杏奈の指がペタペタとくっつき、気持ち悪がって泣いて暴れたことがあった。その様子に私は実家にいた猫を思い出した。ブラシをかけた後に出来た毛玉を取ろうと、猫の背中にローラーをかけたところ、逃げたり暴れたり、全力で拒否されたことがあった。
「野生か」
「これ気持ち悪い……やだ……」
頭を撫でると上機嫌になって甘えてくるのも猫のようだった。
私は杏奈にまとわりつかれながら、靴を脱いで家に上がる。買ってきたものを適当に床に置いた。
「夕飯の前にお風呂入ろうか」
「うん!」
私は杏奈を連れてバスルームに向かう。途中、自分の上着やスカートを脱いでその辺に投げておく。
バスルームに入る頃には半裸となった私は、そこで杏奈の服を脱がす。杏奈はされるがままだった。
彼女は一人では着替えもできなければ、トイレもできない。パンツの代わりにオムツを履かせていた。脱がしたパンツを丸めてゴミ箱に捨て、脱いだ私と杏奈の服は、トイレの蓋を下ろしてその上に乗せておく。
露わになった杏奈の裸体。最初の頃は肋が浮くほど痩せ細っていたが、二人で暮らす内にすっかり肉付きがよくなった。くびれのある肢体はモデルやグラビアアイドルのように扇情的だった。胸はDカップあり、雪のように白い肌の中、薄紅の桜のような色をした二つの乳輪があった。左胸の上には小さなホクロが一つある。乳房の先はやや上向きになっており、美しい曲線を描いていた。ベジェ曲線で側面図を想像したのは職業病だ。数学的に計算され尽くした造形美、そんな言葉が脳裏をよぎった。ややあって目を逸らす。揉みしだきたい衝動に駆られるがなんとか堪える。
私はBカップしかなく、太ってはいないが面白みのない寸胴体型。よくいえばスレンダー。付け加えるならば、桜が散って泥水に浸かって変色したような、茶褐色の乳輪をしていた。生物として圧倒的な敗北感を禁じ得ない。杏奈に見られるのが恥ずかしくて片腕で隠す。
私たちは裸でバスタブの中に入り、トイレが水浸しにならないよう、シャワーカーテンで仕切る。
私はシャワーヘッドを手に取って、温水のハンドルを回す。音を立てて放水されるシャワーの水温が温かくなるまで片手で受け止めた。杏奈は私にぴったりと寄り添いながらそれを見ている。
彼女のひんやりとして湿った肌が私に触れ、内心穏やかでなかった。彼女の柔らかい胸が直に私の腕に触れると、私は下唇を噛んでそれに耐えた。
「洗うよ」
私は彼女に向き直り、頭からシャワーを浴びせる。
それに彼女は両目を固くつぶり、唇を引き結んでいた。嫌そうにも見えるが、どこか楽しんでいるようで、気持ちよさそうでもあった。
私は彼女の髪を洗う。まずは頭皮から。一度流して毛先まで。それから束ねてゴムで結び団子にする。私の方はざっくりと洗う程度だった。昔から肩より先に伸ばしたことがないので、私のはすぐに終わる。
次は体を洗う。バスタブが狭いので、抱きしめるような形で、後ろに手を回して彼女の体を洗わなければいけない。まずは手のひらで彼女の体を撫でるように軽く洗った。真似してか、杏奈が私の体にも手を回してくる。脇腹を撫でられた際に変な声が漏れてしまった。
一通り彼女の体を濡らしたあと、水を出したままシャワーヘッドをフックに掛ける。
スポンジに泡を立てて、彼女の体を前から後ろから、抱くような形で洗う。私の体も泡まみれになる。何かそういった性風俗サービスがあったような気がした。
「次は私が洗う!」
杏奈が向き直り、私の手からスポンジを奪う。
「じゃあ、お願い」
彼女の自主性は尊重をしたい。そして私は覚悟をしなければならない。
密着して彼女に体を洗われる。後ろから体の前を洗われる時、私の胸を彼女の指が、揉むように下から上へと、ぬるついた泡に滑らせて乳首をかすめる時、私の体は意に反してふるえる。声を押し殺すために右手の親指の付け根を噛む。
「気持ちいい?」
「うん……」
杏奈は私のお腹を洗い、そして太ももの付け根に沿って手を滑り込ませる。
私は赤の他人である彼女を連れ去り、騙すように一緒に暮らしていることを悪いことだと思っている。しかし清潔面や病気のことを考えると、デリケートゾーンは丁寧にケアしなければならない。私は決していやらしい気持ちだけで彼女の陰部を洗っているわけではない。
杏奈は私の心情など知りもしないだろう。私がしていることに対し信頼を寄せてくれている。だから彼女は私の真似をして、私の陰部をしっかりと洗う。
泡まみれの体で彼女に抱きしめられながら、彼女の手が私の股の間へと滑り込む。
「杏奈……駄目っ……」
「サヨちゃん、ちゃんと洗わないとダメだよ」
杏奈は耳元で言う。股の間をスポンジが何度も擦るのに、腰が抜けそうになった。前屈みになり、ふるえる私の体を杏奈が抱き支える。
「閉じたら洗えないよ」
無意識に閉じた足の間に、杏奈はスポンジではなく指を差し入れる。そのまま奥へと。
「サヨちゃん、可愛い」
予期せぬ言葉に私は気が緩んでしまった。杏奈の細く長い、形の綺麗な指先が私の奥に入った。敏感な部分に触れる。そこを擦られると、腰から背中に電気が走ったような感覚に襲われた。
「あっ──」
私は声を漏らし、両手を壁につく。何度も抜き差しされる内に、熱いものが下腹部に込み上げ、ついには一際大きく身をふるわせると、激しい痙攣に襲われた。
「サヨちゃん?」
私の異変に杏奈が指を離す。
私は自分のお尻を杏奈の下半身に押し当てるのを我慢できなかった。それを杏奈は手を添えて受け止めてくれる。
私は足に力が入らなくガクガクとふるえた。呆気なくイカされ、情けないやら恥ずかしいやらで、じっと壁にもたれていた。
「気持ちよかった?」
杏奈は後ろから私の体を抱きしめ、顔を覗き込んでくる。そこには一点の曇りなく、誇らしげで幸せそうな笑顔があった。
「うん……」
どう答えたものか悩むが正直に答えた。
彼女は純粋に私のことを思ってしてくれているはずだ。しかしわざとやっているのではないかと疑う気持ちもあった。
とにかくシャワーを終えて、寝巻きに着替えさせて、リビングのソファに杏奈を座らせた。両手でステンレスのコップを持ち、ストローで大好物のブドウジュースを飲んでいる。
私は適当に買ってきた惣菜、グラタンやコロッケなど、温めた物を適当にローテーブルに並べた。
「どれが食べたい?」
私はローテーブルの前に座る。杏奈もソファを降りて私の横に座った。お風呂上がりの甘い匂いと、体温が伝わってきた。彼女の頬が上気したように火照っていた。唇が艶めいて見えた。
「これにする!」
そういって杏奈はコロッケを手掴みし、口を大きく開けてかぶりつく。彼女はスプーンやフォークが使えない。手や口が汚れるので、パンとかが売れ残っていればよかったのだが。
私はその横顔を見ていた。一瞬前までは目を瞠るほどの美人だったというのに。今や子供のように無邪気だ。ただそういうのも可愛いなと思ってしまう私がいた。
私はグラスに注いだ酎ハイを飲みながら、焼き鳥を摘む。特に見る訳ではないがテレビを点けた。何かのバラエティ番組がやってる。旅行番組だった。
杏奈との生活も落ち着いてきた。私も仕事に余裕がでてきたら、二人で旅行にでも行こうか。そんなことを思った。
不意に杏奈がテレビ画面を指さす。
「ここ! ここいった!」
京都のどこかのお寺か神社だった。苔むした地蔵がたくさん並んでいた。
「ああ、修学旅行で?」
なんとなくその特徴でどこか分かった。行ったことはないが、嵐山エリアだったかの奥にあった気がする。
「違うよ! 二人でいったじゃん!」
「え? ここに?」
私は杏奈とクラスは一緒だったが班は別だった。また中学生当時、彼女と交流はなかった。誰かの記憶と勘違いしているのだろう。
たまに杏奈は架空の記憶の話をする。記憶が混濁しているのだろうか。それでも記憶の中に私の出番を増やしてくれるのはなんだか嬉しかった。
しかしこういうのは否定した方がいいのだろうか。杏奈がそう思いたいなら、そう思わせておいた方がいいのだろうか。
なるべく私は杏奈の言うことは否定せず、どんな話なのかじっくり聞くようにしていた。
「高校卒業して、二人で旅行して、いったじゃん!」
そんな事実はなかった。これはしっかりと否定したほうがいいのだろうか。私は悩んだ。
「待って。私たち高校別だったでしょ?」
杏奈とは高校が別。
高校時代に会ったのは、十年前にたまたま電車の中で会ったのが最後。
「サヨちゃん、忘れたの?」
杏奈は耳を赤くして、私の胸ぐらに両手を乗せて、床に押し倒す。涙ぐみ、怒っている様子だった。
私はせっかく着替えたのに、服にコロッケのカスと油がついたな、と思った。
とりあえず杏奈をなだめる。
「ごめん! ごめんって!」
「好きだって、私、言ったよね」
それに胸が痛んだ。それは私じゃない。私じゃない誰かに杏奈は告白したのか。
私は今の杏奈に対して抱いている感情を、恋愛感情とは思えない。弱っている彼女の心につけこんでいる詐欺師だ。
しかしそれでも悔しくて、その誰かが妬ましかった。
「サヨちゃんも、私のこと好きだって、言ってくれた。ちゃんと覚えてるもん」
私は杏奈の髪を撫で、抱きしめる。
「そうだね。そうだったね」
「覚えてないでしょ!」
「覚えてるよ」
私は杏奈ごと体を起こして向かい合う。
私は杏奈の目を見つめる。その黒く潤んだ瞳に、嘘つきの顔が映った。
この嘘が正しいとは思えない。しかし否定して、記憶を整理すれば彼女は立ち直れるだろうか。悪化する可能性もある。私は消極的に、ただ寄り添うことを選んだ。それは私の暗い劣情を正当化するためのただの言い訳なのだろう。ちゃんと分かっている。
杏奈は目をつぶる。まだ夕飯もそこそこなのに、と私は思った。
私は彼女の唇にキスをする。互いに手のひらを合わせ、指を絡めた。
それを合図に私の理性のタガは外れた。
私はベッドの上で寝息を立てる杏奈の横顔を撫でる。
すっかり汗をかいたので、もう一度シャワーを浴びようかどうか迷う。明日も仕事があるから、朝起きた時にでも入るか。
「おやすみ」
私は杏奈の横顔にキスをする。
そこで私は思い出した。
テレビの映像にあった観光地。
中学二年の最後の方だった。翌年に行く修学旅行の事前学習。学習発表のテーマに選んだのがあそこだった。
当時、杏奈と同じ班で、一緒に選んで調べたことを思い出した。
杏奈はその時のことを今でも覚えていて、本当に行ったように思ってしまったのかもしれない。
そう思うと、より一層彼女が愛おしく思えた。
こんな形ではなく、中学の時に彼女に告白して、ちゃんと付き合えていたら、彼女も壊れなかったのだろうか。私は彼女を支えることができただろうか。
私は身を横たえ、互いの体にタオルケットをかける。
寝顔を見つめる。よく通った鼻筋と、綺麗な唇、長いまつ毛に閉じられた切れ長の目。乱れた髪が顔にかかり、汗に濡れて頬に張り付いていた。
思ってはいけないのに、彼女が好きだという気持ちが溢れてしまう。私は彼女の弱みにつけこんで騙しているだけなのに。もし彼女が正気に戻ったら、私のことを嫌悪するはずだ。
それでも、付き合えなくても、そばにいれなくても、もし彼女を守れるのだったら私は何もいらない。
まだ四月の夜は寝冷えする。私たちは互いの熱で温め合った。
◆ ◆ ◆
朝の眩い光が差し込む。瞼の裏が赤く燃え、それに私は目を覚ました。
すると目の前には見慣れない、それでいて見覚えのある天井があった。
私の住んでいる部屋の天井は白のクロスだった。しかし目の前にあるのは木目の天井。
記憶が飛んでいる。私はそう思った。
しかしそこで、これは実家にある私の部屋の天井だと気付いた。
次に思い出したことは、「そうだ、今日は始業式だ」ということだった。
しかしそんな訳がない。私は跳ね起きる。自分の身に何が起きたのか理解できなかった。
杏奈。杏奈がいない。
それは当然だ。まだ私たちは中学生だ。そう思い至って、それもまた当然有り得ないことを十分分かっている。
私は実家の自分の部屋にいて、自分を中学生だと思っている。同時に私は中学生のわけがなく、杏奈と一緒に暮らしているはずだと認識していた。
とにかく私は状況を明らかにすることにした。
部屋を出てリビングに行くと、母が朝食の準備をしていた。
「あら、珍しく早起きね。制服に着替えたら。今日は始業式なんだから、早く準備しなさい」
私は今日が中学二年の始業式の朝だということを、思い出すように理解した。
そうだ、これは夢だ。
私には二十五歳までの記憶がある。杏奈と一緒にいた記憶も。
つまり私は夢を見ているのだと考えれば、この奇妙な事態も納得がいく。
しかし夢だというのにお腹が空いた感覚がした。
私は朝食を食べていると、ずんぐりと体を丸めて床に座っている、懐かしい彼女の後ろ姿を見つけた。
「ウリ坊! ウリ坊だ!」
黒茶色の縞模様、キジトラ柄のメス猫。尻尾は短くて丸い。いつの間にか現れて、お尻を向けて座っていた。私は彼女を見つけるとにじり寄り、その背中を撫でさする。そのうちに気分をよくした彼女は喉を鳴らして転がり始めた。
ウリ坊とは、小学生の時の私が何となく名付けた名前だった。
それに母が言う。
「ウリ坊に構ってないで、早く行きなさい」
ウリ坊は私が小学四年生の時から、高校生の時までうちにいた。完全な飼い猫ではなく、半分外飼いだった。最後は猫の宿命として、いつの間にかいなくなってしまった。
私は名残惜しいが、後ろ髪引かれる思いで家を出る。
私は素直に登校する。
これが夢だというなら、当時の赤星杏奈に再び会える。私はそのことが嬉しくて胸が高鳴った。
かつて幾度となく歩いた通学路。桜の花はすでに散り、まだわずかに花弁を残していたが、若葉がつき始めていた。
先日の雨に流されて、排水溝には薄紅色の花弁と、裁断された血管の断片のような赤い花柄たちが溜まっていた。
その残骸が醸す匂いだろうか、すえた甘い香りがした。
十分ほど歩くと、広いグラウンドと中学校の校舎が見えてくる。夢だというのにシーンスキップがなく、オープンワールドのゲームで操作をしているような気分だった。グラフィックも現実と区別がつかない。
私の記憶にない場所に行けば、夢の綻びを見つけることができるだろうか。
確か校庭の掲示板にクラス表が張り出されていたはず。
中学二年の新クラスの場所は分かっていたが、夢と実際の記憶に相違点がないか、念の為確認することにした。
中学二年なら赤星杏奈と同じクラス。彼女はもう教室にいるだろうか。
彼女に会える。そのことに期待を膨らませながら、私は校門を抜けて校庭に出る。そしてその先に、一人の少女がいた。
長い黒髪は背中にかかり、サイドの髪を編んで後ろで結んでいる。私は息を呑んだ。
彼女は掲示板に張り出されたクラス表を見ていた。
私の足音に気付いたのか、もう用は済んだからか、彼女が振り返る。
切れ長の大きな目。少し面長で細い顎先に、滑らかな輪郭。鼻筋の通った整った顔立ち。桜色の唇が細く笑った。
「おはよう」
赤星杏奈だった。それが私に向けられた言葉だと気付くのに少し時間がかかった。
「早いね。人が多いと嫌だから、私も早く来たんだ」
「え、へう」
変な声が出た。杏奈は気にした様子もなく微笑んでいた。
あの頃の笑顔で微笑む杏奈。凛として愛らしく、深く黒い瞳を細めて笑う。春の日差しを受けて、透けるように輝いて見えた。
私は彼女の姿に見惚れ、言葉を失い立ち尽くす。
「クラス、一緒だね」
「え?」
「西塚さんだよね。一緒のクラスだよ。あ、私は赤星杏奈。初めて話すから、私のこと知らないかな」
まだこの時点では接点などなかったはず。中学二年で同じクラスになり、それで私は初めて赤星杏奈のことを知った。しかしなぜか杏奈は私のことを知っていた。
それは夢なので何かと都合がいいのだろう。そう、これは夢。春の日と彼女の温もりが見せた幻だ。
「赤星さん」
私は思わず口にしてしまう。
「好きです。付き合ってください」
それに杏奈は驚いた顔をした。夢なら私は自由だ。何も怖いものなどない。
杏奈は自身の唇に指を当てる。彼女が思案する時の癖だった。目を横に流しながら、おずおずといった様子で言う。
「私、女だよ? 西塚さんも」
「何か問題が?」
「そっか。確かに」
それで納得してくれたようだ。
杏奈は私に視線を移す。耳が真っ赤になっていた。
「その私、付き合うとかまだよく分からないから。まずは、友達からなら……」
私は心臓が早鐘のように打つのが分かった。胸が痛いぐらいだった。何とか声を絞り出す。
「よろしくお願いします」
「こちらこそ……」
杏奈は恥ずかしそうに顔を伏せ、両手で自身のスカートを摘み、指を遊ばせていた。
しかし随分と都合がよく、それでいて都合の悪い夢だ。
せっかくならこのまま付き合えたらいいのに。
「それじゃ今からデートしよう」
「え? これから始業式だよ?」
「じゃあ始業式が終わったら」
「あ、うん。それならいいよ……」
せめてデートするまで、この夢が覚めないでほしかった。
私たちは教室まで一緒に行く。
赤星杏奈は笑いながら言う。
「西塚さんってけっこう強引なんだね」
それはどことなく非難が込められているような気がした。
これが現実で、あるいは当時の自分であったら取り乱していただろう。私は美人が苦手だが、夢の中であればどんな美人も怖くないことに気付いた。
「いや。こういうのはちゃんとはっきりしないと後悔するから」
「後悔?」
「こんなチャンス、二度とないかもしれない」
「そんなことないよ。だって今日から一年、一緒のクラスじゃない」
「目が覚めたら全部なかったことになってるだろうし」
「面白いこと言うね」
教室に着く。すでに先にクラスにいた杏奈の友人たちが彼女を呼ぶ。あの小動物的な女子もいた。玉津とかいう名字だったか。
私は彼女たちとは親しくないので離れることにした。それに杏奈が気付き、私に手を振った。
「それじゃまた後でね」
「うん」
暇になった私は、ここでいったん状況を整理する。
これは本当に夢なのか。あるいは二十五歳の私が夢だったのではないだろうか。そんなはずがないことはよく分かっている。疑問を差し挟む余地もない。
しかし一体、この夢はいつまで続くのか。せめて杏奈とデートしてキスするまではいきたいのだが、そこに到達するまでにしばらくかかりそうだ。
夢特有のシーン間のスキップがない。このまま体感時間がリアルタイム式で夢が上映されていくのか。
おそらくこれは明晰夢というものなのだろう。明晰夢では、体感で数日間も夢の中に滞在できると聞いたことがある、気がする。ただ明晰夢であれば、自在に夢の内容をコントロールできたはずだ。
ならば私は、杏奈のスカートでもめくってやろうかと思案した。笑って許してくれるかエロい展開になるはず。いや、なんか超能力的なものでめくろう。ディテールが大事だ。私は地球の自転によるエネルギーを何かそういう力に変換する能力者だ。私は杏奈のスカートに念を送る。
しかし何も起こらない。
杏奈が広げた手のひらを向ける私に気付いて、笑顔で手を振ってくれた。私は罪悪感がわいて、手をふり返した後、引っ込める。まさか私がスカートをめくろうとしているなど、彼女は思いもしないだろう。
一日が普通に経過していく。教室にクラスメートが増えていく。あまりの懐かしさに、こそばゆい気持ちになってきた。なぜだか笑えてくる。
しばらくして、小学校以来の友人、菊田英美香が教室に入ってきた。彼女も同じクラスだったことを思い出した。
英美香はムッとした顔で大股に歩み寄ってくる。
「西塚! 一緒に行こうって約束したじゃん!」
「あー、ごめん。忘れてた」
確か一緒に登校する約束をしていた。というよりもほぼ毎朝一緒に登校していた。
怒る英美香をよそに、いちいちギミックが細かい夢だと私は感心した。
彼女は私の前に立つとすかさず抱きついてくる。
「また同じクラスだよー!」
「だね」
英美香とは高校も同じで、彼女と別のクラスになったのは高校一年の時だけだった。
私は視界の隅に杏奈を捉えながら、英美香と他愛もない会話をして時間を潰す。何度か杏奈と目が合った。少しはこちらを意識してくれているみたいで嬉しかった。
そのうちに鐘が鳴り、クラス担任の先生が教室に入ってくる。
体育館に全校生徒が集められ、始業式はつつがなく進行した。
校長の訓示や新入生代表の挨拶、校歌斉唱など。何一つ覚えていないはずなのにリアルだった。
真面目に聞いていたことがないので、私の記憶の再現で、よくこんなリアルに仕上げられたものだ。
覚えていない、思い出せないことでも、潜在意識下に記憶が保存されている。みたいなことをどこかで見聞きしたことがある。つまりはそういうことなのだろう。
始業式が終わり、生徒たちは各教室に戻る。私と英美香は一緒に廊下を歩いていた。
「西塚、このあとカラオケ行こーぜ!」
「ごめん。先約がある」
「はあ? 誰と?」
どう答えたものか。言葉に詰まる。
不意に杏奈が私を追い越して、横を通り過ぎた。その際に私の肩に手を置いて、耳打ちする。
「終わったら裏門のところで待ち合わせね」
「うん。分かった」
杏奈は振り返り小さく手を振る。私も小さく返す。
それに英美香は動揺していた。
「え、今のなに? いつの間に赤星さんと仲良くなったの?」
私と英美香は偏差値四十程度。学年でも下位の学力グループ且つ品行方正とは言い難い。対して赤星杏奈は上位どころかおそらく学年一位の優等生。私たちはヒト亜種で彼女はヒト種のエリート。もはや生物種として違い、学校という生態系内で棲み分けがされていた。
正門とは別に通用門があり、私たちは裏門などと呼んでいた。
校舎裏の花壇に囲まれた道、そこを抜けると裏門に出る。
杏奈が先にいて待ってくれていた。
「夕方から家族で食事に行くから、それまででいい?」
「うん。いいよ」
しかしデートとはいったが、どこに行ったものか。
「とりあえず駅前のバーガー屋行く? その後、カラオケでも行く?」
「制服で?」
「まずい?」
制服での買い食いなどは禁止されているが、ほとんど形骸化した校則である。しかし優等生である杏奈はそういうのを気にするようだ。
「お財布持ってきてないから、いったん家に帰って、着替えてから待ち合わせする?」
「うーん……」
そんなまどろっこしいことをして、途中で目覚めたら台無しだ。私はとにかく杏奈と放課後デートがしたい。
「買い食いとか気にする方?」
「わりとみんなしてるし、そんなに気にしないけど」
「じゃあコンビニでなんかおごるよ」
「え、それは悪いよ」
「気にするなら今度返してくれればいいし」
「うん、分かった」
「とりあえず、あんまり人のいない静かな場所知ってるから、そこ行かない? 名前知らないけど、裏山の神社のとこにある公園」
「行ったことない! 気になる!」
そこは学校から徒歩三十分ほどのところにある。山といっても丘と形容した方がいいのだろうか。なだらかな丘で、ところどころに雑木林がある。斜面には多くの住宅があり、道路も舗装されていた。その頂上ではなく、中腹寄りのところに神社があった。神社には広い境内があり、その境内に入る鳥居の手前には公園がある。夏祭りは人で賑わうが、普段は人の気配が全くない。
「途中コンビニ寄ってから行こうか」
「うん!」
当時、もし告白していれば、こんなふうに二人で遊べていたのだろうか。
私は胸の中の青い後悔に自嘲気味に苦笑した。
裏山の神社に向かう途中、コンビニでホットスナックとか飲み物、菓子を適当に買った。
そして神社に着くまでの間、いろいろなことを話した。
「小学校はどこだったの?」
「線路の反対側。中学からこっち」
「今日一緒にいた友達は同じ小学校?」
「玉津さん? 彼女とは中学一年から。玉津さんは中学からこっちに引っ越してきたんだって」
「そうなんだ。けっこう仲良いよね」
「うーん。そうだね」
「西塚さんも今日一緒にいた子、誰?」
「英美香? 小学校からの友達」
「今度紹介してよ」
「いいよ」
こんな普通の会話をするのが新鮮だった。いつも「サヨちゃん。サヨちゃん」言いながら抱きついてくる杏奈も、別に嫌いではない。むしろ好きだが、こうして普通に会話できるのは楽しかった。
そのうち裏山の神社に着く。
神社は雑木林に囲われ、曇りがちの四月の空も相まって、辺りは薄暗かった。
その中にあって境内の森閑とした広い空間が、ぽっかりと広がっていた。
「あ、ここ、もしかしたら子供の頃来たことあるかも!」
「夏には盆踊りとかお祭りもやってるからね。私も来るの十五年ぶりかな」
「生まれてないじゃん」
杏奈がおかしそうに笑う。そういえば私たちは十三歳だった。しかし十三歳で杏奈はこんなに大人びていたのか。肌艶や面差しに幼さはあるが、整った顔立ちをしていると年長に見える。
そんな杏奈が目を細めて顔を綻ばせるのが、あまりにも可愛くて、私は胸が締めつけられるようだった。
現実の杏奈も確かにこんなふうに笑うが、そちらは精神年齢的に中学生の杏奈より幼く、ついつい親目線で見てしまう。
杏奈が境内の中を散策する。それに私はついていく。
「何の神様が祀られているんだろ」
社殿は境内の外周沿いにあり、奥行きはないが、それなりの大きさがあった。2トントラックのコンテナより大きい、と思われる。手前に賽銭箱があり、その上に、あのガラガラ鳴るやつが吊るされていた。大きな鈴と太い縄のやつだ。
杏奈が楽しそうに、それに手をかけている。
「お賽銭入れる?」
私は財布を取り出す。
「いい! 今度自分で来た時にやる!」
私も別に祈ることもないので財布をしまった。
「それじゃ、お昼にしよう」
私たちは鳥居を抜け、公園に出る。砂場と滑り台、変な動物のグラグラ揺れる遊具が三つ、それとベンチがあった。
私たちはそのベンチに腰かける。
私はビニール袋から、コンビニで買った物を取り出し杏奈と分ける。
杏奈はわざわざ仰々しく手を合わせる。
「いただきます。あ、本当にちゃんと返すからね。もしかしたら私が事故に遭って返せなくなったら困るから、一応言っただけね」
「縁起でもないな」
私は苦笑した。
当時の杏奈とこんなふうに話すのは初めてだった。本当はこんな感じなのかと思うと、感慨深いものがあった。
いや、修学旅行の事前学習で、意外と話したことがあった。そのイメージがあるから、それが反映されているのか。
しばらく私たちは買ってきた物を食べていた。不意に杏奈が言う。
「どうして私のこと好きなの?」
いきなり核心に触れてきたなと思った。
「どうしてって、赤星さんのこと好きじゃない人類っているの?」
「そういうことじゃなくて。西塚さんの好きって、そういうことじゃないでしょ」
「ああ」
私は思案する。
当時の私は赤星杏奈を美人だと思うし憧れていた。その手に触れたい、唇に触れたい、名前を呼ばれたいと思ったことは数知れず。現実の私は正気を失った赤星杏奈を世話していた。その上、弱みにつけこんで恋人のふりまでしている。これを愛などと言えるはずがない。私にあるのは劣情だけだ。
ただ今の偽らざる心境を言えば、
「赤星さんのこと、守りたいって思ったから。もし付き合えたら守れたのかなって」
もし今この時に付き合えていたら、杏奈のことを守れただろうか。
もしも付き合えたら、そもそも付き合えなくても、未来を変えることができるのなら、私は杏奈を守りたい。そう思った。
「守るって、何から?」
「いろんなことから」
「どうして私を?」
「赤星さんのことが好きだから」
私は杏奈の横顔を見る。杏奈は耳を赤くしていた。粗相をして泣いている時や、怒った時に耳が赤くなるのを思い出した。恥ずかしくて赤くなっているのだろうか。私もなんだか恥ずかしくなってきた。
「うーん……全然よく分からないけど、分かった……」
杏奈は唇に指を当てながら、花弁を一枚一枚数えるように、言葉をこぼすように言う。
「私、付き合うとか、好きとか、よく分からない。たぶん私自身が、まだ誰かを好きになったことがないから」
そこで杏奈は私の方を向き、じっと目を見つめる。
「ただ西塚さんが真剣だってことは分かるし。それに私、あなたのこと知りたいって、思えるから。だから最初に言ったとおり、まずは友達から、ってことでいいかな?」
夢なのに随分と都合よくいかない。しかし照れくさそうに、あるいは恥ずかしそうに、いっぱいいっぱいの様子で言う杏奈が可愛くて新鮮だった。私はこれはこれでいいなと思った。
「うん。友達からよろしくお願いします」
「こちらこそ、よろしくお願いします」
それに杏奈はにっこりと笑った。
その後、私たちは他愛ない会話をし、最後に電話番号とメールアドレスを互いに登録した。当時はまだメールが主流だった。世界的チャットアプリが出現するのは確か二年後だったろうか。
登録を済ますと、杏奈は申し訳なさそうに言う。
「あの、私、メールが苦手で。素っ気なかったりしたらごめんね」
「私も苦手というか。返信遅かったらごめん」
「全然! 私、直接会って話すのは大丈夫なんだけど、文章で会話するの苦手なんだよね」
「分かる。要件だけのやり取りは平気だけど、文章だけだと会話続けるの難しいんだよね」
「そうなんだよね。だからね。怒ってるように見えても、怒ってるわけじゃないからね。返信がなくても、気付いてないだけだから」
杏奈は念を押してくる。彼女なりに苦労してきたのだろうと察した。
夢だというのに律儀に帰宅すると、母に帰りが遅いことを怒られた。
帰宅後は一通りウリ坊とたわむる。
夕飯を食べた後、風呂に入る時、明日も学校だから早く寝るように言われた。
風呂から上がって寝巻きに着替え、またウリ坊を撫で回し、一時間ぐらいそうしてから自室に戻った。
布団に入る。実家の天井が視界に広がった。紐を引っ張って照明を消す。
真っ暗になると、私は我に返った。夢の中で、このまま本当に寝るのか、と。
しかしこの夢から一向に目覚める気配がない。
寝れば現実で目覚めるのか。目覚めないのなら、このままずっと夢の中で中学時代をやり直してもいいが。
その場合、誰があの杏奈の面倒を見るのかと思い至る。
私にとって一番大事なのは現実の杏奈だ。
不意に私は夢の中の杏奈からメールが来ていないかと思い、四代前のスマートフォンを開く。
『また明日学校で』
とだけ送られていた。顔文字も絵文字もない。まだスタンプは存在していなかったか。そもそもメール機能に実装されたかも知らない。
何となくこんな短文を律儀に送ってくる杏奈が可愛く思えた。
『楽しみにしてる。また明日』
私も修飾をつけず、それだけ返した。なんとなく嬉しい気持ちになった。布団の中で体が熱かった。
こんな些細なことだが、私たちは意外といい友達になれたのかもしれない。と思えた。
もしもやり直せるのなら、私が杏奈を守るのに。
◇ ◇ ◇
私は寝返りを打った拍子に目を覚ます。
正確には寝返りに失敗した。私は体の左側を下にして寝る癖があるのだが、右側に向きを変えようとした際、左腕を杏奈に掴まれていたので、仰向けになったところでそれ以上回ることができなかった。
隣で杏奈は寝息を立てている。夢の続きかと思ったが、杏奈の眉は私が整えた形をしていた。そのことから薄暗がりでも、これが現実だと分かった。天井も、いつもの私の部屋のものになっている。
夢で寝て現実で目覚める、奇妙な夢だった。目覚めれば夢の記憶は曖昧になり、起きた瞬間に忘れてしまうことが大半なのだが、つい昨日のことのように思い出すことができた。
中学時代の赤星杏奈に告白し、都合よく交際してあわよくば性的な触れ合いをすることはできなかったが、友達から始めることになるという、我ながら随分と乙女な願望を抱いていたものだ。
もしも中学生からやり直せるとしたら、あんなふうに告白はしないまでも、杏奈と仲良くなって友人となり、彼女が壊れてしまわないよう守りたい。そんなことは思っても無駄なことだが。
当時、杏奈は私の憧れだったが、思った以上に杏奈のことを好きだったのだなと、今更ながら痛感した。
私は杏奈に向き直り、髪を撫でる。
「杏奈のことは、私が守るから」
壊れてしまった彼女が立ち直る日が来るかは分からない。その日が来た時、私は不要になるかもしれない。それでも今は私が守る。
そう心に誓った。
いつものように朝の支度をして、いつものように擦り寄ってくる杏奈を宥め、私は家を出る。
出勤の電車の中、暇を持て余し、私は夢の続きを妄想していた。
とりあえず杏奈と友達からスタートした。ここからエロいことをするにはどうしたらいいか。次の日から、学校でどう接しようか。
教室の中、私は杏奈と、英美香と一緒にいる。英美香は驚いた様子だった。
「西塚、赤星さんと友達だったんだ!」
それに杏奈が微笑む。
「うん。最近ね。菊田さんは小学校から西塚さんと友達なんだよね」
「そうそう。私たちは小学校一年の時からの親友なんだ」
「どうだろ。腐れ縁というか悪友?」
「ひどっ!」
それに杏奈が笑っていた。
そこまで妄想して私は我に返った。
一体なんだこの妄想は。ジュブナイル趣味が私にあったのか。と動揺した。
しかしそれ以上に動揺したのが、私はこれを妄想と感じていないことだった。事実あったこと、そう感じていた。
私は妄想していたのではない。思い出していたのだ。あの夢の、次の日のことを。
記憶も妄想も、脳内で再生される映像、再現される感覚だ。その記憶の想起と妄想の区別をどうつけるか。単純にそれが事実であったか事実でないか、他ならぬ自分自身がそれを知っている。
三人であんな会話をした事実はない。そんな出来事はなかった。
しかし私は先ほどの杏奈と英美香と三人でしたやり取りを、妄想ではなく、事実だと感じていた。
きっとあまりにリアルすぎる夢に、実体験と誤認しているのだ。私はそう思うことにしたが。強烈な違和感が私を襲った。
私は咄嗟にスマートフォンを取り出し、ほとんど使うことのなくなった連絡帳アプリを、手間取りながらも探して開く。
機種変をしてもデータは引き継ぎされている。そしてその中にあるはずがない、赤星杏奈の電話番号とメールアドレス。それが登録されていた。
私は杏奈とアドレスを交換した記憶を、今まで忘れていたのだろうか。
突然、私は私という存在に自信を失った。
彼女、赤星杏奈と会ったのはその日が最後だった。
私は当時、高校一年生。その日、学校が終わった帰りに、帰宅の電車を乗り間違えてしまった。私の降りる駅に急行電車は止まらない。いつもなら各駅停車の電車に乗るのだが、疲れていたのか、高校から始まった電車通学に不慣れなこともあり、よく確認もせず急行電車に乗ってしまった。
本来なら降りるはずの駅が車窓を過ぎ去っていく。私はひどく憂鬱な気分になった。何かこの後に予定があるわけではない。ほんの三十分ほど帰りが遅くなるだけのことなのだが。苛立ちに今にも消え入りたい気分だった。
ようやく止まった駅で、急いで反対側の電車に乗る。ちょうど反対方面に行く電車が到着していた。今度は各停であることをしっかり確認した。駆け足気味に車内に入る。少しして扉が閉まった。
「西塚さん」
不意に名前を呼ばれた。私はその声に聞き覚えがあった。驚いてその先を見る。知らない制服姿の、見覚えのある美しい少女がいた。赤星杏奈。中学の同級生だった。
切れ長であるが細くはない、凛とした且つ愛らしい目。少し面長で顎先は細く、滑らかな輪郭に、鼻筋は通り、整った顔立ちをしていた。美しい黒髪は、左右の耳上から後ろに結び、後ろ髪はそのまま背中まで流している。
私が知っている誰よりも彼女は美しく、そしてどこかあどけなさがあり可愛かった。
彼女は座席の端の仕切りにもたれていた。席はまばらに空いているが、知らない人の横に座りたくない気持ちが分かる。
赤星杏奈はその美しい目を細めて私に微笑む。
「中学の卒業式ぶりだね」
「うん。久しぶり」
私は息を呑むように言った。中学校の卒業式以来なので、まだ一ヶ月程度しか経っていなかったが、私にとっては実に数年ぶりに再会するような感慨があった。
しかし中学時代、彼女とはほとんど接点がなかった。私が一方的に懐かしんでいるだけで、彼女からしてみればただの顔見知りにたまたま会った程度のものだろう。
ここからの問題としては、地元の駅に着くまでの十数分、緊張に私の息がもつかどうか不安だった。
「赤星さん、少し背伸びた?」
苦し紛れに聞いてみる。私の身長が百六十センチ弱あり、目線が同じなので、彼女もそのぐらいの身長だろう。
彼女は上目遣いに視線を泳がせ、指先を唇に当てた。
「うーん、どうだろ。たぶん伸びた」
私はなんとなく彼女の雰囲気が変わったように感じ、そんな陳腐な質問をしてしまった。
もともと彼女は大人びた印象があったが、幼さが抜けて、今の彼女はより一層綺麗になった気がした。もっとも一ヶ月しか経っていない上に、私は彼女のことをよく知らない。ただ窓の外から見える彼女を眺めていただけの傍観者のようなものだ。
その後、他愛もない会話をしてやり過ごした。中学時代の思い出話や近況など。もっと気の利いた何か他のことを話そうと思うも、間をつなぐのに必死だった。私の必死さに気付いてか、彼女は優しく見守り、穏やかに受け答えしてくれた。
私は少し顔が熱っぽくなるのを感じた。
私は杏奈が苦手だ。というよりも、美人というものが苦手だった。それは私が女性を恋愛対象として見ているからだ。それに気付いたのは幼稚園の頃。五歳かそこらの頃だった。
幼稚園当時、私には好きな女の子がいた。彼女は友人として私のことを親しく思っていてくれたと思う。今では名前も顔も思い出すことはできない。それでもあの頃の胸の高鳴りと痛みを思い出すと、あれが最初の恋だったのだなと実感する。
どういう経緯でそうなったのか、記憶は朧げであるが、とにかく私たちはキスをした。初めてのキスはとても柔らかくて、温かったのを覚えている。
しかし次の日から彼女は私を避けるようになった。私が泣いて追いかけても、彼女は顔も合わせてくれない。どうして避けるのか、何一つ理由を教えてくれなかった。だから私は、私が悪かったと思うしかなかった。それ以来、私は誰かを好きだと思うことも、考えることもしないようにしてきた。
しかし美人というものは、容易く私の心を揺るがしてしまう。だから苦手だ。
電車が駅に着いた。私たちは一緒に降りた。
改札に向かう途中、赤星杏奈が私に聞く。
「西塚さんは高校も美術部なの?」
「部活は入ってないや」
「そっか。まだ絵は描いてる?」
「たまに」
それに赤星杏奈は微笑んだ。
「私、サヨちゃんの絵が好きだよ。これからも描き続けてね」
「え? あ、うん」
突然下の名前で呼ばれて私は動揺した。彼女に下の名前で呼ばれたのはこれが初めてだったと思う。それを親愛というよりも、何かからかうようなニュアンスと私は受けとめた。
「バイバイ」
そう言って、改札を抜けると彼女は私に手を振り、反対方面に去っていった。
私は小さく手を振り返した。
それが彼女と会った最後の記憶だった。
それから駅のホームでも地元でもすれ違うことはなかった。中学を卒業してから、二度と見ていない同級生は山ほどいるのでそんなものなのだろう。彼女は成人式や同窓会にも出席しなかった。風の噂には国立大に進学したのなんのと聞いたぐらいのもの。
私が後悔をする筋合いはまったくないが、あの時、もっと何か気の利いたことでも言えていれば、何かが違っていたのだろうかと思ってしまう。
とにかく彼女を見たのはそれが最後だった。
一ヶ月前、十年ぶりに彼女と再会するまでは。
* * *
現在──
私──西塚小夜子、女性、二十五歳──は眠い頭で体を起こす。カーテンを透過して朝日が差す、薄明るい灰色の朝。
するりとタオルケットが滑り落ちる。傍らに胎児のように丸まって眠る彼女の輪郭があった。掛け布団は彼女が引き裂いた。圧迫感が嫌いなのかもしれない。それ以来、タオルケットで代用している。
私は彼女を起こさないようにベッドを出ようとした。しかし上着の裾を掴まれて、私の気遣いは無意味だったことを知る。振り返ると、彼女は先ほどと同じ姿勢のまま手を伸ばして、私の裾をつまんで無邪気に微笑んでいた。
「サヨちゃん」
「おはよう、杏奈」
彼女──赤星杏奈、女性、二十五歳──は私の中学の時の同級生。十年ぶりに再会した彼女と、一ヶ月前から奇妙な同居生活を送ることになった。
杏奈は起き上がると、両手を広げて、私に倒れかかるように抱きついてくる。私は彼女の背中をなだめるように撫でた。
「朝ご飯の準備するから、離して」
「手伝う!」
それに私は苦笑した。彼女にそんなことできるはずがないからだ。
私は杏奈の腰に手を回して、支えながらリビングに出る。壁沿いのスイッチに手を伸ばす。カチリと音が鳴り、部屋の照明が点く。
1LDKの賃貸マンションの一室。そこに私たちは住んでいた。大学生以来、私が住んでいる部屋だった。
リビングには二人がけのソファとローテーブル。ソファの上には一抱えほどある黒茶色のキジトラ猫のぬいぐるみがある。私が昔買ったものだが、今では杏奈のお気に入りだった。
その向かいのテレビ台の上には40インチの液晶テレビ。そのテレビの横には、円筒形の台座があり、その上にカメラレンズのついた球体が乗っている。いわゆる見守りカメラである。
ローテーブルの上には昨日の飲みかけのグラスが置いたままになっていた。それと紙を三角に折って立てた、ストローを使ってコップから水を飲む女の子の絵があった。私が杏奈のために描いたものだった。天板下の収納棚にはスケッチブックと食べても大丈夫なクレヨン。
いくつか段ボールが空いた場所に積んである。中には杏奈が破壊した物と不用品が入っていた。私が「嵐の七日間」と呼ぶ一週間で杏奈が破壊した物だ。そのうち捨てる予定。インテリアは他にほとんど何もない。あとは本棚ぐらいか。私の買った漫画やDVDが並べてある。
私は杏奈をソファに座らせ、テレビを点ける。朝のニュース番組がやっていた。番組映像はフレームに切り取られ、画面下部に大きな余白がある。そこには現在の交通情報が淡々と流れては切り替わっていった。
杏奈はぬいぐるみに抱きついて寝っ転がる。
私はリモコンをテーブルに置き、グラスを持ってキッチンのシンクに向かった。キッチンはリビングに併設されており、冷蔵庫も隣にある。
私は先にトイレを済ませて戻る。
「杏奈、トイレは?」
「行く!」
私は再び杏奈を抱き起こす。杏奈は私にじゃれつき、互いの足をもつれさせ笑い合う。
「杏奈、開けて」
「うん!」
トイレのドアノブはレバー状のハンドルタイプ。それに手をかけ、上に回したものか下に回したものか奮戦し、ガチャガチャと鳴らす。たまたま下に押した時にドアが動いて、そのまま引くと、見事開けることに成功した。杏奈は私を見て誇らしげに笑う。
私は杏奈の頭を撫でてあげた。
「あとは自分でできる?」
トイレの便座の蓋は常に開けてある。またトイレとバスルームは同じ場所にある。ユニットバスというやつだ。
杏奈は答えず、笑顔で両手を広げて私の方を向く。
私は苦笑して、彼女の腰に手を回す。彼女のズボンとパンツに指をかけて、するりと脱がす。このぐらいなら彼女でもできる時があるが、出勤前なので時間を節約したかった。また脱ぐことと座ることをセットでするのは難しい。以前、転倒して頭をぶつけ、悲惨なことになったことがあった。
「終わったら教えて」
「うん!」
間違えて鍵を閉めて、閉じ込められないようにドアは開けたまま。
私は朝食の準備にキッチンへと戻る。昨日の残りの味噌汁を温め、ご飯と卵を落として雑炊にする。
赤星杏奈。彼女は中学時代、私だけでなく、同級生全員の憧れだった。
当時の赤星杏奈は芸能人だとかモデルだとか、アイドルの誰々にも負けないほどの美人であった。ただ今でも面影を十分に残していて、黙っていれば相変わらずの美人ではある。
さらに彼女は成績も優秀で学年一位。偏差値七十いくつの高校へ進学した。私は偏差値四十程度の公立高校へ。人類として何か別のものだった。
確か生徒会長にもなっていた。あれは中学三年の時か。毎週月曜朝の全校集会では彼女の挨拶から始まっていたような気がする。
また私は絵を描くのが好きだったのだが、彼女が美術の授業で描いた作品が何かのコンクールで表彰されていた。私の作品については言うまでもない。
また彼女は合唱発表会だとかも指揮や伴奏を務めていた。
そして嫌味なく人当たりがよくて、誰からも好かれて、よく小動物のような女友達を連れていたと思う。その子が親友だったかどうかは知らないが。
その杏奈が今では、文字を読むこともできない。浮かんで滑っていくと言っていた。ペットボトルを開けたり、水道から水を汲むこともできない。使い方が分からない、覚えられないと言っていた。前にペットボトルを開けられず、かじりついて穴を開けて飲んでいた。ドアの開け閉めは出来る時と出来ない時がある。ドアノブに苦手なタイプと得意なタイプがあるようだった。
杏奈は朝食も一人では食べられない。スプーンもうまく使えない。握ったスプーンに掬い取っても、こぼすか顔に塗りつけてしまう。それなので私が食べさせた。
私たちはローテーブルの前に座る。
「はい、あーん」
「あーん」
杏奈は嬉しそうに私が運ぶ物を食べていた。彼女が咀嚼している間に私も食べる。面倒なので同じ食器を使う。別に成人女性同士、気にすることもない。
食後、私は彼女の口周りを拭い、食器を片付ける。シンクに食器を置き、水につけておく。洗うより先に杏奈の水分摂取を促す。放っておけば彼女は何も飲まないで、死ぬまでそうしているだろう。
「杏奈、お茶でいい?」
ソファに寝っ転がっていた杏奈は、体を起こして不満げに言う。
「やだ! ブドウジュース!」
「はいはい」
私は自嘲気味に笑う。杏奈の言い方が子供じみて可愛いと思ってしまった。
私は冷蔵庫から取り出したブドウジュースの紙パックから、ステンレスのコップに注ぐ。ガラスだと取りこぼしたり、何かの拍子に落として割ってしまいかねない。
私はコップにストローを差して杏奈のところに持っていく。それに杏奈は両手を出して受け取る。彼女がストローを咥えるまで私は手を離さなかった。飲み終わったのを見届け、コップを受け取り片付ける。
これが私の朝だった。
私はこの生活に苦痛を感じたことはない。不快に思ったこともない。彼女を哀れに思い、同情しているわけでもない。下心は否定できないが。
これはただの私の余生だから。そう思うと大概のことがどうでもよくなった。
というのも、彼女と再会する直前、私は大学時代から付き合っていた恋人と別れ、死ぬことにしていたからだ。それから偶然というべきか、気紛れにというべきか、十年ぶりに杏奈と再会することになった。彼女は私の記憶とは結びつかない、かけ離れた姿となっていた。そこからほとんど勢いで彼女を引き取った。
決して彼女と心中するつもりではない。
ただあの暗い闇の中で、美しかった者の残骸が腐敗して朽ちていくのを、間違っていると感じた。それだけだった。
私はもろもろの支度を終えて、出勤すべく、ソファに寝っ転がる杏奈に言う。杏奈は相変わらずぬいぐるみを抱きしめている。ちなみにこのぬいぐるみの名前は「ウリ坊」という。メス猫だ。
「ウリ坊と留守番しててね。お昼ご飯、机の上に置いてあるから。ちゃんと食べるんだよ」
「はーい!」
杏奈はウリ坊をぎゅっと抱きしめて言った。
私はローテーブルの上に、ストローを挿した水の入ったコップと、ラップをかけたおにぎりの入った皿を置いた。おにぎりを一枚一枚ラップで包むと、杏奈がそのまま食べてしまうので、皿にだけラップをかけておく。これならなんとかラップを剥がすことに成功すれば食べられる。ついでに画用紙とクレヨンを置いておく。何か手先を動かせば社会復帰の助けになるかもしれない。
また仕事中、合間を見つけてスマートフォンのアプリから、家の中の様子を確認し、スピーカーで呼びかけて水分の摂取や食事を促した。そうしなければ一日中食事をしないこともある。またテレビや空調といった室内環境の管理もできるので、こまめに確認するようにしていた。
「それじゃいってくるね」
「いってらっしゃい!」
杏奈は体を起こし、ウリ坊を手放して、両手を広げて私を待ち受ける。
家を出る時、杏奈はキスを求めてくることがある。どういう訳か杏奈の中で私は恋人ということになっていた。
騙したわけではない。彼女が一方的にそう思っているだけ。しかし精神的に弱っている彼女の弱みにつけこんでいるようで罪悪感があった。
それでも憧れだった彼女とキスできるのは嬉しかった。これが私の下心だ。
彼女の頬に触れ、髪を撫で、唇を重ねる。
彼女の唇は柔らかく、ブドウの甘い匂いがした。
私は理性を失う前に唇を離し、どこか不満げな杏奈の頭を撫でて家を出る。
私は今日一日、自己嫌悪と劣情の炎に苛まれることを覚悟しなければならない。
こんな状態で過ごさなければならないのが私の罰か。
* * *
一ヶ月前──
大学を卒業し社会人となってから三年が経った。
そして先日、大学時代から付き合っていた恋人と別れた。
元恋人、蛍野南帆。小柄で、ショートヘアを好み、ベージュ系の髪色は季節によってよく色を変えた。
彼女は大学の同期。同じ専攻だった。知り合って七年、交際期間は四年と七ヶ月ほどか。その彼女に別れを告げられた。
私は失恋の傷心を癒す、つもりは毛頭ないが、有給休暇を取り、週末の土日と合わせて実家に帰った。
私の地元は閑静な住宅街で、東京郊外にある。一軒家で、二階に私の部屋があった。一階にはリビングや両親の居室。
実家に帰ると、母はいつも通りの調子だった。私たちはリビングで適当な会話をする。
「小夜子はまだ結婚しないの? 付き合っている人とかいないの? 仕事辞めてこっちでお見合いでもしたら? 仲良かった英美香ちゃんなんて三人目ができたそうよ」
ああ、すごくいい。とても死にたくなる。私はこれを求めて実家に帰ってきた。
私が実家に顔を出した理由。母の小言と同世代の今を聞かされることで、私の中の死にたさを補強してもらいに来たのだ。事実、私は死ぬ予定だった。死ぬと決めた時点で死ぬつもりだったが、せっかくなので背中を押してもらいにきた。
次に私はその英美香に会いに行った。小学校以来の親しい友人だった。彼女は高校卒業後、大学には進学せず、年上の社会人と結婚した。
正午過ぎ、私たちは駅前のファミレスで軽食を共にした。
英美香は細目であっさりした顔立ちで、いわゆる弥生顔というやつだろうか。私が一番落ち着く馴染みやすい顔立ちだった。高校からメイクをするようになって、今では化粧品で一重を二重瞼にして、つけまつ毛でさらに目を強調し、長い金髪はくるくる巻いてある。これはこれで緊張しないで済む容姿だ。
英美香は久しぶりの再会に早口でたくさん喋る。
「親バカかもしれないけど本当にうちの娘、本当にめちゃくちゃ可愛いの! 大きくなったら絶対子役にする! 三人目も女の子だといいなあ。西塚もさ、まあ結婚はしなくても、恋人かいい感じの人ができたら紹介してよ。うちらの仲でしょ? 職場とかにいい人いないの? 誰か紹介しようか? 今度一緒にキャンプとかしようよ」
私は笑って適当に相槌を打つ。こういう未来の話をするのもいい。私にそんな簡単に恋人ができるわけがないことを彼女は知らない。それに簡単に作ろうと思えるほど、私は器用じゃなかった。そんな未来がどうあっても来ないことを実感すると、どんどん死にたくなってくる。
不意に英美香は意外な人物の名前を口にした。
「そういえば、赤星さんって覚えてる?」
ここで私は久方ぶりに赤星杏奈を思い出した。最後に会ったのは十年前。それ以降の彼女を知らない。さぞかし彼女の成功談は私の劣等感をくすぐり、私を死にたくさせてくれるのだろう。それに彼女の名前を聞いただけで、なぜか私の胸は痛くなった。もし彼女に恋人ができたり結婚していたらと思うと、なぜか私はどうしようもなくこの世界から消えてしまいたい気分になった。
もしかしたら私は今まで、無意識か意図的に彼女を思い出さないよう、話題を避けてきたのかもしれない。
しかし今はより深くこの胸を抉ってほしかったので、渡りに船だった。
「中学の時、生徒会長やってた人でしょ?」
「そうそう。大学は国立に進学して、でかい有名な会社に就職までしたのにさ。一年で辞めたらしいよ」
「え、なんで?」
何やら雲行きが変わってきた。私はそんな話が聞きたかったわけではない。とても信じられないと思った。
「なんか病気だって」
「何の?」
「なんだっけ、とうごー、なんとか」
「統合失調症?」
「そうそう、そんな感じの名前の。それで退院しただかで、最近こっちに帰ってきたらしいんだけど。それからずっと引きこもりなんだって」
「……赤星杏奈の話だよね?」
赤星杏奈にそんなことがあってはならない。私は認められなかった。
しかし英美香はこともなげに肯定する。
「そうだよ。赤星杏奈」
「誰か赤星さんとは会ったの? 英美香は会った?」
「私は会ってないよ。たぶん誰も会ってないと思う。もし会いに行って殺されたりしたら嫌じゃん? それに私、赤星さんと別に仲良くないし」
私の中の赤星杏奈像と、今の彼女の間にひどい乖離があった。恐らくそれは彼女を知る誰もが抱いただろう。あの完璧だった少女が、得体の知れない怪物になってしまったような感覚がした。
「赤星さんの住所って分かる?」
「分かんないけど、中学の時の卒アルかなんかに載ってるんじゃない?」
「確かなかった気がする」
「そしたら同窓会主催してたやつに聞いてみる? 案内の葉書とか送ったりしてるから、住所知ってるんじゃない?」
「誰だっけ?」
「そういえばお前、成人式以来、ろくに来てなかったもんな。私の方で聞いてみるよ」
「ありがとう」
「なに? お見舞いでもいくの?」
「ああ、うん」
「西塚って赤星さんと仲良かったっけ?」
「別に仲良くないけど」
「だよね。そもそもうちらとはグループどころかカーストが違ったし」
中学時代、私と英美香は、赤星杏奈と授業や課題に関する以外で会話したことがなかった。
英美香が私に協力してくれるのは面白がっているだけだろうし、英美香も私が杏奈を心配しているなどと思っていないだろう。
私が赤星杏奈と会おうと思ったのは、私以上の苦境にいる人を見て溜飲を下げようという訳ではない。彼女に元気の出そうな励ましの言葉を一つかけて、その空々しさと自己嫌悪で希死念慮を加速させようという魂胆だった。
赤星杏奈の住所が分かったのは翌土曜日。明日には私は終わる予定なので、ちょうどいいタイミングだった。
私は特に連絡も入れず、赤星杏奈の家を訪問する。会えなければ、その時はその時。住宅街に一軒家、私の実家より大きく見えた。煉瓦のような赤褐色のタイル張りの外壁。門扉に「赤星」の表札は黒地に金字。そういえば赤星には金星という意味もあるのだったなと、当時インターネットで検索して彼女の名前を心に噛み締めたことを思い出した。
インターフォン越しに、おそらく彼女の母が出る。
『どちらさま?』
「私、杏奈さんの中学の時の友人の、西塚小夜子といいます。たまたま実家に立ち寄ったので、杏奈さんにも会えたらと伺いました」
『もしかしてサヨちゃん!?』
「あ、はい?」
その呼ばれ方に強い違和感を覚えた。
赤星母とは面識がない。学校行事のどこかですれ違ったことはあるかもしれないが、会話をした覚えもなければ、愛称で呼ばれる筋合いもない。
私は両親や友人によって「サヨちゃん」と呼ばれることもある。英美香は小学校以来、徹底して「西塚」だが。私が英美香を「英美香」と呼ぶのは出会った頃の彼女の一人称が「英美香」だったからだ。
しかし赤星杏奈に「サヨちゃん」などと呼ばれる筋合いはない。いや、一度だけ、最後に会った時にそう呼ばれたことを思い出した。だがそれは親愛というよりも、ふざけてそう呼んだようなニュアンスではなかったか。
私たちは全く親しくもなく、電話番号もメールアドレスも互いに知らない。ただの中学の同級生で、交流などほとんどなかった。
それなのにインターフォン越しの動揺したような声音は、なぜか私のことを知っているような感じがした。
玄関が開き、慌てた様子で、少しやつれた感じの初老の女性、赤星母が出てくる。髪は整えた様子もなく、服もみすぼらしい。以前はそれなりに美人だったのではないかとうかがえるのは、杏奈と同じように目鼻が整っていたからだ。
「わざわざありがとう。どうぞ、あがって」
「お邪魔します」
私は玄関で靴を脱ぐ。ドアが閉まる。木の匂いが広がった。
他人の家に入った瞬間、その家独特の匂いがするものだ。それは木材の違いによるものなのか、どこからか漂う仏壇の線香のブランドによるものなのか、芳香剤か何かの匂いなのだろうか。
とにかく赤星家は木の匂いがする家だった。
私は赤星母の案内で杏奈の部屋に向かう。
「サヨちゃん、来てくれてありがとう。私からも連絡しようと思ったんだけどね、なんて伝えたらいいか分からなくて」
「はあ」
私と赤星杏奈はそんな間柄ではない。そもそも友人ですらない。もちろん赤星母と会って話すのは今日が初めてだ。実際に会ってみて確信した。それなのに何か私のことを知っているような口ぶりだった。ただその違和感には、今はあまり興味がなかった。何か勘違いしているのなら好都合程度に思った。
「杏奈さん、どうされたんですか?」
私は杏奈の近況を尋ねた。
「杏奈ちゃんね、仕事で無理しすぎちゃって、それで疲れちゃったみたいなの。病院も退院したし、もう大丈夫。杏奈ちゃんに聞いてたけど、また昔みたいにあの子と遊んでくれると嬉しいわ」
ここで私が気付いたのは、おそらく「サヨちゃん」という別の誰かと私を混同しているのだろう、ということだった。そのことが申し訳なかった。偽物の「サヨちゃん」が来訪したことで、本物の「サヨちゃん」に連絡がいかなくなるかもしれない。帰り際に訂正しておくことにした。
「杏奈ちゃん、調子が悪くて部屋から出られないかもしれないから。ドア越しにでも声をかけてくれたら嬉しいわ。階段を上って、左手の部屋だから」
「はい」
階下で赤星母は私を見送り、私は一人彼女の部屋へと向かった。
英美香の話は半信半疑だった。しかしこれまでの会話から十分、英美香の話が真実だと確信に変わっていった。得体の知れない汗が出た。背中にブラウスが張り付く。
どこか現実味のない浮遊感が私の中にあった。現実から切り離されたような、夢の中で粘質を帯びた大気の中をかき分けて泳ぐような異質感があった。
私は赤星杏奈の部屋の、ドアの前に立つ。ノックする手前まで伸ばした手が止まる。彼女の面影が過ぎった。凛とした美しい面差し、花が咲いたような愛らしい笑顔。その彼女がこの先にいることが想像できなかった。この扉の向こうで今、どんな姿をしているのか。全身をウジに蝕まれ、人の形をした腐敗した何かを想像した。
私は息を呑んでからノックした。二度、三度。しばらく待つが返事はない。
「赤星さん」
呼びかけてみた。すると衣擦れのような、身じろぎするような気配がした。巨大な芋虫が無数の足を蠢かし這いずるような、甲虫がその硬質な羽を擦り合わせて今にも羽ばたこうとしているようなイメージが、私の中にわいてきた。私は足先から、全身にかけて鳥肌が立つのを感じた。
それでも私は続けて呼びかける。
「覚えているかな? 中学の時一緒だった、西塚小夜子だけど。たまたま実家に寄ったから、赤星さんのこと気になって立ち寄ったんだけど」
返事は期待していない。私は一方的に話しかけるつもりだった。
さあ、ここから私は彼女に元気の出る励ましの言葉を投げかけよう。
何か辛いことがあったと思うけど元気を出して。あなたなら立ち直れるよ。きっといいことがあるよ。無理しないであなたのペースで頑張って。たまには外に出てみたら? ずっと部屋の中にいると気分が滅入るよ。アロマとか炊いて気分転換してみたら? みんな心配しているよ。悩んでいることがあったら誰かに相談してみて。きっと力になってくれるはず。
よし。
私を殺してきた言葉たちで彼女を八つ裂きにするのは気が引けるが、もうこうなってしまった彼女を救えるとは思えないので、せめて何か一つでも彼女に届いて力になることができたら、私がこの世界に生まれてきたことにも意味があったというものだ。
私は彼女に元気になる言葉をかけようとした。その時、積み上げた荷物が崩れるような、床に投げっぱなしになっているCDのケースを踏み割るような、種々雑多な騒音がした。
「赤星さん!?」
何事か起きたのかと動揺し、先程まで考えてきた言葉が雲散霧消した。
踏み荒らす音が扉に近づいてくる。それに私は赤星杏奈の亡者が狂ったようにのたうち回りながら、迫ってきている姿を想像した。思わず一歩後ずさる。
ドアノブがガチャガチャと乱雑に鳴らされ、ガタガタと音を立ててドアが揺れた。私の喉からひっと乾いた声が漏れた。
そして扉が開け放たれる。暗闇が口を開いた。そこから腐臭が立ち込めてきた。私は咳き込みそうになるのを堪えた。
そして闇の向こうからまろび出た黒い塊──と見てとれたのは、無造作に伸びた黒髪を振り乱した女性だった。私の目の前に立ち、今にも掴みかからんとばかりに手を広げて、顔をじっと見てくる。淀んだ黒い瞳と目が合った。
突然のことに私は心臓が止まりそうになった。本当は赤星杏奈はとっくに死んでいるのではないか、今目の前にいるのは彼女ではない別の何かではないか、そう思った。あるいはそう思いたかった。
しかしその髪の下に、私はあの頃の面影を留めた白い顔を認識する。
彼女は唇を震わせながら口を開いた。
「……サヨちゃん?」
無人の荒野をさまよい数年ぶりに人里を見つけて水を求める放浪者のような声だった。そしてやはり彼女に下の名前で呼ばれることに強い違和感を覚えた。
「久しぶり。赤星さん」
私はすっかりせっかく考えた元気の出る言葉を一つ残らず失念してしまった。あまりに目の前の彼女が変わり果てていたからだ。髪はボサボサで、怯えたように背筋は丸まり、楚々とした彼女の姿はそこになかった。全くの別人の家を訪問したのか、と再び疑念がもたげた。それでもあの頃の面影を留め、その整った顔立ちは忘れようがなく、やはり彼女が赤星杏奈だと疑いようがなかった。
立ち尽くし言葉を失った私に杏奈が言った。
「……どうして?」
その言葉に続くのは「ここにいるの?」、「来たの?」だろうか。それに私は我に返る。
「近くに寄ったから」
私はドアノブを掴む。
「部屋、入ってもいい?」
「え、あ……」
私は返事を待たずに踏み入る。それに赤星杏奈は動揺して、私の袖に弱々しくすがりつく。彼女の部屋は、カーテンが締め切られ、とっくに昼だというのに薄暗かった。腐敗臭が立ち込め、そこら中にゴミ袋や物が散乱していた。普段そこで寝ているためか、ベッドにはゴミが少ない。
私も部屋は片付けられない方だが、こんな異臭の立ち込める部屋で、一日過ごすだけでも正気とは思えない。おそらくこの臭いの中に汚物も混じっているだろう。
杏奈は私の袖にすがりながら、何か言おうとして、言葉にならず呻いていた。今にも泣きそうな顔をしていた。
こんなことがあってはいけない。こんな場所に彼女がいてはいけない。私はそんなことを強く思った。
「私と来る?」
不意に私の口から出た。私は、自分でいったい何を言っているのか、私自身に混乱した。
杏奈も戸惑っているようだった。
「……どういうこと?」
「今一人暮らししてるんだけどさ。同居人がちょうど出て行って。まあ、それだから、うちに来れば? って」
十年ぶりに再会して、まともな会話一つしていない。ただ私を突き動かす、強い衝動があった。
「まあ、いきなり迷惑だよね。ただこのままだと──」
「行く」
「え?」
「行く」
彼女は目を大きく見開いて、私の腕に強くその指を食い込ませていた。痛いぐらいに。
「ああ、うん。じゃあ、行こうか」
これ以上何か言葉をかける必要もない。そう思った。
これが正しいか、何がいいか分からないが、とにかく私は赤星杏奈をこの暗闇から救い出したい。
私は彼女の手を取り、部屋を出る。
一人でまともに歩くことのできない杏奈の腰を抱き支え、階下に降りると、赤星母は私たちを見て、目を見開き驚いた様子で立ち尽くしていた。
「私が杏奈さんを引き取ります」
それだけ言うとすんなり私は杏奈を引き取ることができた。何か制止されるかと思ったが、赤星母は何も言わなかった。
私は電話番号をメモ紙に書いて渡し、以降、電話番号をもとにショートメールで連絡を取り合った。
心配しているだろうと思って赤星母に律儀に近況報告をしていたが、恐ろしいぐらいに彼女は杏奈に対して無関心で、一度たりとも近況を尋ねてくることはなかった。そのうち返信がなくなり、私も徒労に感じて報告をやめた。
意地の悪い考え方だが、ようやく肩の荷が下りた程度にしか思っていないのではないだろうか。
ただ彼女を責めたり、詮索することはやめよう。
とにかく誰一人損をしていないのだから、結果的にはよかったのだと思う。
* * *
現在──
私は都心部のオフィス街にある、デザイン系の会社で働いていた。正社員とアルバイト含めて六十人近く在籍している。
業務は広告やパッケージのデザイン、パンフレットや書籍の校正などもあった。
独特かは分からないが、フリーアドレススタイルを採用しており、個々の座席は決まっていない。電源があるところに、なければ増設して、デスクをつなげて通称「島」を形成する。あるいは縄張りという意味で「シマ」かもしれない。
私はタイムカードを押してから、自身のシマに向かう。シマは点在し、私の席は窓際から一番遠い、奥まった暗いところにある。
「おはようございます」
私はパソコンのモニターに向かっている玄野希亜先輩──女性、二十八歳、私より三つ年上。今年二十九歳になる。三十歳になることを非常に恐れている。独身──に挨拶をする。顔立ちのはっきりした美人だった。ブラウンの髪を無造作にまとめて、グレーのジャケットの肩にかけている。眉をしかめて、大きな瞳をこらしていた。もともと目力があるのに、今日はライトグリーンの虹彩が入ったカラーコンタクトを入れていて、綺麗だと思う反面、威圧感がすごかった。
「おはよー」
玄野先輩はこちらを見もせずに言う。デスクの上には栄養ドリンク剤の瓶が並んでいた。花瓶にでもすれば風流かもしれないと、ふと思った。
私も自身の席に座り、パソコンを立ち上げる。私たちは隣り合うように座った。
「何徹目ですか?」
「まだ二徹目」
ここ一ヶ月、早上がりしているのが申し訳なかった。
かといってそのことで彼女が不機嫌なわけではない。朝の彼女はいつもこんな感じだった。
玄野先輩には、私が新卒で入社してからずっとお世話になっている。
一年目は彼女のアシスタントとして、仕事だけでなくデザイン理論やノウハウを教え込まれた。
二年目からは先輩から引き継いだクライアント対応をしたり、オペレーションを任されるようになった。今でも共同していくつかプロジェクトを進めている。
後に知ったことだが、玄野先輩はきつい性格で同僚から敬遠されていて、新人潰しとしても知られていた。
これについて私なりの考えだが、玄野先輩がかなりの美人であることが原因だと思っている。彼女は口調と態度がきつい。またはっきりと物を言うので、美人に叱責されて、特に男性陣はメンツが立たず、避けられるようになったのではないか。
しかし私は元から美人が苦手だったので、逆に美人に叱責されても、誰に叱責されるのとも変わらなかったのかもしれない。
ただ長く一緒にいると、実際にはそれほど時間はかからず、彼女の可愛いところをいくつも発見した。
そして少年漫画が好きで、意外とカップリング厨であること。私もアニメや漫画が好きで、無意識に彼女が小声で口ずさんでいる歌が、私の好きなアニメの主題歌であることから判明した。
私は立ち上がったパソコンのモニターに認証画面が出て、パスワードを打ち込むと、ふと思い出した。
「先輩、あれ連載終わっちゃいましたね」
「そうなのよー」
息を長々と吐き、デスクに突っ伏する。
「でも主人公があの選択するとは思いませんでしたね」
「ね。まだ完結じゃないってことでしょ。まだ続編の可能性があるわ。それに私としてはヒロインよりも、ライバルの子とくっついてほしい」
そう言いながら左手用の片手キーボードを軽快に打ち、右手をペンタブの上に走らす。
画面上ではベジェ曲線のパスが打ち込まれ、そのハンドルを伸ばしながら、何か可愛い動物の絵になっていった。
「何のマスコットですか? リス?」
「モモンガ。会社のマスコットだって。原案通ったからサンプルの制作。デザインが決まったら差分の作成」
「あー、先輩のクライアントの、新しい子会社のでしたっけ? パンフレットとか、ホームページのデザインもやるんですよね」
「そうそう」
「私も手伝いますよ。今の案件、今週中には片がつくんで」
「少しだけ手伝ってもらおうかな。西塚さんの帰りが遅くならない程度に」
「すみません……」
本当はとことん手伝いたいのだが、杏奈のこともあり、ここ一ヶ月は先に上がっていた。
「恋人とうまくいってるの?」
不意に玄野先輩が尋ねる。私はどきりとした。先輩には杏奈のことも、彼女と別れたことも話していない。
「はい、まあ」
「あ、こういうの同性でもセクハラになるんだっけ?」
「いえ、全然! 玄野先輩なら問題ないです」
「よかった」
他の人に言われたらセクハラかもしれないが、玄野先輩は以前、私の恋愛相談にも乗ってくれていた。そして私が女性と付き合っていたことも知っている。
「また今度一緒にスパ銭行きましょう。この間新しく出来て、気になっているところがあるの」
「はい、ぜひ。ちょっと今慌ただしくて。落ち着いたら」
そして先輩はスーパー銭湯が大好きだった。
私が一年目の頃、終電を逃した際に連れて行かれ、それ以来一緒に行く仲になった。
昼食はそれぞれのタイミングでとる。
たまに玄野先輩に誘われることもあるが、杏奈と暮らすようになってからは、電話をしなければならないと断った。先輩も無理には誘ってこない。
私は用事が済んだらデスクでランチをするようにしていた。先輩も最近は外食せず、一緒にオフィスで食べている。
「三十分ぐらいしたら戻りますけど、駅前に来てるキッチンカーで何か買いますが、先輩も何かいります?」
「あ、じゃあ頼んじゃおうかな。今日は木曜日だからタイ料理?」
「確かそうでしたね」
「私グリーンカレーとパッタイの二つ盛りのやつで」
「了解です! 私はガパオライスにしようかな。一口食べます?」
「うん。一口交換しましょ」
玄野先輩は鞄から財布を出し、そこから二千円を取り出す。
「あ、千円もしないですよ!」
「いいの。西塚さんの分もそれで買って。お釣りは返してね」
「ありがとうございます! お言葉に甘えて」
私は素直に感謝し受け取る。
正午を少し過ぎたあたり。
青空には雲がなかった。少し肌が汗ばむが、風が気持ちよかった。
私は昼を買いに行く前に、駅前の広場にあるベンチに座る。そこでスマートフォンを開き、見守りカメラのアプリを起動した。
画面に家の中の様子が映る。杏奈がソファに寝転がっていた。相変わらずウリ坊を抱きかかえている。朝からこのままだったのだろうか。
「杏奈」
私が呼びかけると杏奈は跳ね起き、辺りを見回す。
「サヨちゃん? どこ?」
「まだ仕事中。ちゃんと水飲んだ?」
「まだ!」
杏奈は天井に向かって答えた。
「じゃあ飲もうか。テーブルの上に置いてあるよ」
「うん!」
杏奈はローテーブルの上のコップを両手で取り、ストローを咥える。
「えらいえらい」
褒めると杏奈は嬉しそうに笑う。
「ご飯、ちゃんと食べるんだよ」
「うん!」
「ラップに気をつけてね」
「うん!」
杏奈は皿の上のラップを剥ぎ取り、手掴みでおにぎりを食べる。一口で頬張り、まだ口の中にあるのに次を食べようとする。
「ゆっくり食べるんだよ」
「ん!」
口の周りに米粒をつけながら、幸せそうに食べていた。
「サヨちゃんのおにぎり、おいしい!」
「ありがとう」
私は杏奈を眺めていると癒されるような気分になった。
「可愛いなあ」
思わず口から漏れた。
私はしばらく杏奈を見守り、それからキッチンカーに向かった。
* * *
仕事を終えて、自宅近くの駅に着いたのは二十一時を回った頃だった。杏奈と暮らすようになって帰宅時間が随分と早くなった。以前は終電で帰ることもざらにあった。
一人で何もできない杏奈。お腹が空いたからと冷蔵庫から食べ物を取り出して、ましてや電子レンジで温めることなどできない。近所のコンビニに一人で買いに行くこともできない。
私は帰り道にあるスーパーで、適当な惣菜と酎ハイ類を買って帰る。
帰宅し、玄関を開ける。
「ただいまー」
「サヨちゃん!」
杏奈は玄関前でしゃがみ込み、私の帰りを待っていた。
「遅くなってごめんね」
杏奈は勢いよく立ち上がり、よろけながら私に抱きつくと、顔をくっつけて頬擦りしてきた。何か大きなネコ科の動物を飼っている気分だった。
一人では満足に歩けない彼女だが、最近は玄関前で私の帰りを待っていることが多くなった。
誤って外に出てしまうんじゃないかという懸念はある。彼女が鍵を開けてドアノブを回すという、二つの手順を成し遂げることは難しい。しかし何度も試行すればそのうち開けられる可能性がある。
そこで鍵のつまみに両面テープを重ねて貼った。杏奈はねばつくものを嫌がる。粘着テープを回転させて床などを掃除するローラーの、使用済みのテープを剥がしているところを、杏奈が興味ありげに見ていたことがあった。「やってみる?」そう言って手渡すと、新鮮なテープの表面に杏奈の指がペタペタとくっつき、気持ち悪がって泣いて暴れたことがあった。その様子に私は実家にいた猫を思い出した。ブラシをかけた後に出来た毛玉を取ろうと、猫の背中にローラーをかけたところ、逃げたり暴れたり、全力で拒否されたことがあった。
「野生か」
「これ気持ち悪い……やだ……」
頭を撫でると上機嫌になって甘えてくるのも猫のようだった。
私は杏奈にまとわりつかれながら、靴を脱いで家に上がる。買ってきたものを適当に床に置いた。
「夕飯の前にお風呂入ろうか」
「うん!」
私は杏奈を連れてバスルームに向かう。途中、自分の上着やスカートを脱いでその辺に投げておく。
バスルームに入る頃には半裸となった私は、そこで杏奈の服を脱がす。杏奈はされるがままだった。
彼女は一人では着替えもできなければ、トイレもできない。パンツの代わりにオムツを履かせていた。脱がしたパンツを丸めてゴミ箱に捨て、脱いだ私と杏奈の服は、トイレの蓋を下ろしてその上に乗せておく。
露わになった杏奈の裸体。最初の頃は肋が浮くほど痩せ細っていたが、二人で暮らす内にすっかり肉付きがよくなった。くびれのある肢体はモデルやグラビアアイドルのように扇情的だった。胸はDカップあり、雪のように白い肌の中、薄紅の桜のような色をした二つの乳輪があった。左胸の上には小さなホクロが一つある。乳房の先はやや上向きになっており、美しい曲線を描いていた。ベジェ曲線で側面図を想像したのは職業病だ。数学的に計算され尽くした造形美、そんな言葉が脳裏をよぎった。ややあって目を逸らす。揉みしだきたい衝動に駆られるがなんとか堪える。
私はBカップしかなく、太ってはいないが面白みのない寸胴体型。よくいえばスレンダー。付け加えるならば、桜が散って泥水に浸かって変色したような、茶褐色の乳輪をしていた。生物として圧倒的な敗北感を禁じ得ない。杏奈に見られるのが恥ずかしくて片腕で隠す。
私たちは裸でバスタブの中に入り、トイレが水浸しにならないよう、シャワーカーテンで仕切る。
私はシャワーヘッドを手に取って、温水のハンドルを回す。音を立てて放水されるシャワーの水温が温かくなるまで片手で受け止めた。杏奈は私にぴったりと寄り添いながらそれを見ている。
彼女のひんやりとして湿った肌が私に触れ、内心穏やかでなかった。彼女の柔らかい胸が直に私の腕に触れると、私は下唇を噛んでそれに耐えた。
「洗うよ」
私は彼女に向き直り、頭からシャワーを浴びせる。
それに彼女は両目を固くつぶり、唇を引き結んでいた。嫌そうにも見えるが、どこか楽しんでいるようで、気持ちよさそうでもあった。
私は彼女の髪を洗う。まずは頭皮から。一度流して毛先まで。それから束ねてゴムで結び団子にする。私の方はざっくりと洗う程度だった。昔から肩より先に伸ばしたことがないので、私のはすぐに終わる。
次は体を洗う。バスタブが狭いので、抱きしめるような形で、後ろに手を回して彼女の体を洗わなければいけない。まずは手のひらで彼女の体を撫でるように軽く洗った。真似してか、杏奈が私の体にも手を回してくる。脇腹を撫でられた際に変な声が漏れてしまった。
一通り彼女の体を濡らしたあと、水を出したままシャワーヘッドをフックに掛ける。
スポンジに泡を立てて、彼女の体を前から後ろから、抱くような形で洗う。私の体も泡まみれになる。何かそういった性風俗サービスがあったような気がした。
「次は私が洗う!」
杏奈が向き直り、私の手からスポンジを奪う。
「じゃあ、お願い」
彼女の自主性は尊重をしたい。そして私は覚悟をしなければならない。
密着して彼女に体を洗われる。後ろから体の前を洗われる時、私の胸を彼女の指が、揉むように下から上へと、ぬるついた泡に滑らせて乳首をかすめる時、私の体は意に反してふるえる。声を押し殺すために右手の親指の付け根を噛む。
「気持ちいい?」
「うん……」
杏奈は私のお腹を洗い、そして太ももの付け根に沿って手を滑り込ませる。
私は赤の他人である彼女を連れ去り、騙すように一緒に暮らしていることを悪いことだと思っている。しかし清潔面や病気のことを考えると、デリケートゾーンは丁寧にケアしなければならない。私は決していやらしい気持ちだけで彼女の陰部を洗っているわけではない。
杏奈は私の心情など知りもしないだろう。私がしていることに対し信頼を寄せてくれている。だから彼女は私の真似をして、私の陰部をしっかりと洗う。
泡まみれの体で彼女に抱きしめられながら、彼女の手が私の股の間へと滑り込む。
「杏奈……駄目っ……」
「サヨちゃん、ちゃんと洗わないとダメだよ」
杏奈は耳元で言う。股の間をスポンジが何度も擦るのに、腰が抜けそうになった。前屈みになり、ふるえる私の体を杏奈が抱き支える。
「閉じたら洗えないよ」
無意識に閉じた足の間に、杏奈はスポンジではなく指を差し入れる。そのまま奥へと。
「サヨちゃん、可愛い」
予期せぬ言葉に私は気が緩んでしまった。杏奈の細く長い、形の綺麗な指先が私の奥に入った。敏感な部分に触れる。そこを擦られると、腰から背中に電気が走ったような感覚に襲われた。
「あっ──」
私は声を漏らし、両手を壁につく。何度も抜き差しされる内に、熱いものが下腹部に込み上げ、ついには一際大きく身をふるわせると、激しい痙攣に襲われた。
「サヨちゃん?」
私の異変に杏奈が指を離す。
私は自分のお尻を杏奈の下半身に押し当てるのを我慢できなかった。それを杏奈は手を添えて受け止めてくれる。
私は足に力が入らなくガクガクとふるえた。呆気なくイカされ、情けないやら恥ずかしいやらで、じっと壁にもたれていた。
「気持ちよかった?」
杏奈は後ろから私の体を抱きしめ、顔を覗き込んでくる。そこには一点の曇りなく、誇らしげで幸せそうな笑顔があった。
「うん……」
どう答えたものか悩むが正直に答えた。
彼女は純粋に私のことを思ってしてくれているはずだ。しかしわざとやっているのではないかと疑う気持ちもあった。
とにかくシャワーを終えて、寝巻きに着替えさせて、リビングのソファに杏奈を座らせた。両手でステンレスのコップを持ち、ストローで大好物のブドウジュースを飲んでいる。
私は適当に買ってきた惣菜、グラタンやコロッケなど、温めた物を適当にローテーブルに並べた。
「どれが食べたい?」
私はローテーブルの前に座る。杏奈もソファを降りて私の横に座った。お風呂上がりの甘い匂いと、体温が伝わってきた。彼女の頬が上気したように火照っていた。唇が艶めいて見えた。
「これにする!」
そういって杏奈はコロッケを手掴みし、口を大きく開けてかぶりつく。彼女はスプーンやフォークが使えない。手や口が汚れるので、パンとかが売れ残っていればよかったのだが。
私はその横顔を見ていた。一瞬前までは目を瞠るほどの美人だったというのに。今や子供のように無邪気だ。ただそういうのも可愛いなと思ってしまう私がいた。
私はグラスに注いだ酎ハイを飲みながら、焼き鳥を摘む。特に見る訳ではないがテレビを点けた。何かのバラエティ番組がやってる。旅行番組だった。
杏奈との生活も落ち着いてきた。私も仕事に余裕がでてきたら、二人で旅行にでも行こうか。そんなことを思った。
不意に杏奈がテレビ画面を指さす。
「ここ! ここいった!」
京都のどこかのお寺か神社だった。苔むした地蔵がたくさん並んでいた。
「ああ、修学旅行で?」
なんとなくその特徴でどこか分かった。行ったことはないが、嵐山エリアだったかの奥にあった気がする。
「違うよ! 二人でいったじゃん!」
「え? ここに?」
私は杏奈とクラスは一緒だったが班は別だった。また中学生当時、彼女と交流はなかった。誰かの記憶と勘違いしているのだろう。
たまに杏奈は架空の記憶の話をする。記憶が混濁しているのだろうか。それでも記憶の中に私の出番を増やしてくれるのはなんだか嬉しかった。
しかしこういうのは否定した方がいいのだろうか。杏奈がそう思いたいなら、そう思わせておいた方がいいのだろうか。
なるべく私は杏奈の言うことは否定せず、どんな話なのかじっくり聞くようにしていた。
「高校卒業して、二人で旅行して、いったじゃん!」
そんな事実はなかった。これはしっかりと否定したほうがいいのだろうか。私は悩んだ。
「待って。私たち高校別だったでしょ?」
杏奈とは高校が別。
高校時代に会ったのは、十年前にたまたま電車の中で会ったのが最後。
「サヨちゃん、忘れたの?」
杏奈は耳を赤くして、私の胸ぐらに両手を乗せて、床に押し倒す。涙ぐみ、怒っている様子だった。
私はせっかく着替えたのに、服にコロッケのカスと油がついたな、と思った。
とりあえず杏奈をなだめる。
「ごめん! ごめんって!」
「好きだって、私、言ったよね」
それに胸が痛んだ。それは私じゃない。私じゃない誰かに杏奈は告白したのか。
私は今の杏奈に対して抱いている感情を、恋愛感情とは思えない。弱っている彼女の心につけこんでいる詐欺師だ。
しかしそれでも悔しくて、その誰かが妬ましかった。
「サヨちゃんも、私のこと好きだって、言ってくれた。ちゃんと覚えてるもん」
私は杏奈の髪を撫で、抱きしめる。
「そうだね。そうだったね」
「覚えてないでしょ!」
「覚えてるよ」
私は杏奈ごと体を起こして向かい合う。
私は杏奈の目を見つめる。その黒く潤んだ瞳に、嘘つきの顔が映った。
この嘘が正しいとは思えない。しかし否定して、記憶を整理すれば彼女は立ち直れるだろうか。悪化する可能性もある。私は消極的に、ただ寄り添うことを選んだ。それは私の暗い劣情を正当化するためのただの言い訳なのだろう。ちゃんと分かっている。
杏奈は目をつぶる。まだ夕飯もそこそこなのに、と私は思った。
私は彼女の唇にキスをする。互いに手のひらを合わせ、指を絡めた。
それを合図に私の理性のタガは外れた。
私はベッドの上で寝息を立てる杏奈の横顔を撫でる。
すっかり汗をかいたので、もう一度シャワーを浴びようかどうか迷う。明日も仕事があるから、朝起きた時にでも入るか。
「おやすみ」
私は杏奈の横顔にキスをする。
そこで私は思い出した。
テレビの映像にあった観光地。
中学二年の最後の方だった。翌年に行く修学旅行の事前学習。学習発表のテーマに選んだのがあそこだった。
当時、杏奈と同じ班で、一緒に選んで調べたことを思い出した。
杏奈はその時のことを今でも覚えていて、本当に行ったように思ってしまったのかもしれない。
そう思うと、より一層彼女が愛おしく思えた。
こんな形ではなく、中学の時に彼女に告白して、ちゃんと付き合えていたら、彼女も壊れなかったのだろうか。私は彼女を支えることができただろうか。
私は身を横たえ、互いの体にタオルケットをかける。
寝顔を見つめる。よく通った鼻筋と、綺麗な唇、長いまつ毛に閉じられた切れ長の目。乱れた髪が顔にかかり、汗に濡れて頬に張り付いていた。
思ってはいけないのに、彼女が好きだという気持ちが溢れてしまう。私は彼女の弱みにつけこんで騙しているだけなのに。もし彼女が正気に戻ったら、私のことを嫌悪するはずだ。
それでも、付き合えなくても、そばにいれなくても、もし彼女を守れるのだったら私は何もいらない。
まだ四月の夜は寝冷えする。私たちは互いの熱で温め合った。
◆ ◆ ◆
朝の眩い光が差し込む。瞼の裏が赤く燃え、それに私は目を覚ました。
すると目の前には見慣れない、それでいて見覚えのある天井があった。
私の住んでいる部屋の天井は白のクロスだった。しかし目の前にあるのは木目の天井。
記憶が飛んでいる。私はそう思った。
しかしそこで、これは実家にある私の部屋の天井だと気付いた。
次に思い出したことは、「そうだ、今日は始業式だ」ということだった。
しかしそんな訳がない。私は跳ね起きる。自分の身に何が起きたのか理解できなかった。
杏奈。杏奈がいない。
それは当然だ。まだ私たちは中学生だ。そう思い至って、それもまた当然有り得ないことを十分分かっている。
私は実家の自分の部屋にいて、自分を中学生だと思っている。同時に私は中学生のわけがなく、杏奈と一緒に暮らしているはずだと認識していた。
とにかく私は状況を明らかにすることにした。
部屋を出てリビングに行くと、母が朝食の準備をしていた。
「あら、珍しく早起きね。制服に着替えたら。今日は始業式なんだから、早く準備しなさい」
私は今日が中学二年の始業式の朝だということを、思い出すように理解した。
そうだ、これは夢だ。
私には二十五歳までの記憶がある。杏奈と一緒にいた記憶も。
つまり私は夢を見ているのだと考えれば、この奇妙な事態も納得がいく。
しかし夢だというのにお腹が空いた感覚がした。
私は朝食を食べていると、ずんぐりと体を丸めて床に座っている、懐かしい彼女の後ろ姿を見つけた。
「ウリ坊! ウリ坊だ!」
黒茶色の縞模様、キジトラ柄のメス猫。尻尾は短くて丸い。いつの間にか現れて、お尻を向けて座っていた。私は彼女を見つけるとにじり寄り、その背中を撫でさする。そのうちに気分をよくした彼女は喉を鳴らして転がり始めた。
ウリ坊とは、小学生の時の私が何となく名付けた名前だった。
それに母が言う。
「ウリ坊に構ってないで、早く行きなさい」
ウリ坊は私が小学四年生の時から、高校生の時までうちにいた。完全な飼い猫ではなく、半分外飼いだった。最後は猫の宿命として、いつの間にかいなくなってしまった。
私は名残惜しいが、後ろ髪引かれる思いで家を出る。
私は素直に登校する。
これが夢だというなら、当時の赤星杏奈に再び会える。私はそのことが嬉しくて胸が高鳴った。
かつて幾度となく歩いた通学路。桜の花はすでに散り、まだわずかに花弁を残していたが、若葉がつき始めていた。
先日の雨に流されて、排水溝には薄紅色の花弁と、裁断された血管の断片のような赤い花柄たちが溜まっていた。
その残骸が醸す匂いだろうか、すえた甘い香りがした。
十分ほど歩くと、広いグラウンドと中学校の校舎が見えてくる。夢だというのにシーンスキップがなく、オープンワールドのゲームで操作をしているような気分だった。グラフィックも現実と区別がつかない。
私の記憶にない場所に行けば、夢の綻びを見つけることができるだろうか。
確か校庭の掲示板にクラス表が張り出されていたはず。
中学二年の新クラスの場所は分かっていたが、夢と実際の記憶に相違点がないか、念の為確認することにした。
中学二年なら赤星杏奈と同じクラス。彼女はもう教室にいるだろうか。
彼女に会える。そのことに期待を膨らませながら、私は校門を抜けて校庭に出る。そしてその先に、一人の少女がいた。
長い黒髪は背中にかかり、サイドの髪を編んで後ろで結んでいる。私は息を呑んだ。
彼女は掲示板に張り出されたクラス表を見ていた。
私の足音に気付いたのか、もう用は済んだからか、彼女が振り返る。
切れ長の大きな目。少し面長で細い顎先に、滑らかな輪郭。鼻筋の通った整った顔立ち。桜色の唇が細く笑った。
「おはよう」
赤星杏奈だった。それが私に向けられた言葉だと気付くのに少し時間がかかった。
「早いね。人が多いと嫌だから、私も早く来たんだ」
「え、へう」
変な声が出た。杏奈は気にした様子もなく微笑んでいた。
あの頃の笑顔で微笑む杏奈。凛として愛らしく、深く黒い瞳を細めて笑う。春の日差しを受けて、透けるように輝いて見えた。
私は彼女の姿に見惚れ、言葉を失い立ち尽くす。
「クラス、一緒だね」
「え?」
「西塚さんだよね。一緒のクラスだよ。あ、私は赤星杏奈。初めて話すから、私のこと知らないかな」
まだこの時点では接点などなかったはず。中学二年で同じクラスになり、それで私は初めて赤星杏奈のことを知った。しかしなぜか杏奈は私のことを知っていた。
それは夢なので何かと都合がいいのだろう。そう、これは夢。春の日と彼女の温もりが見せた幻だ。
「赤星さん」
私は思わず口にしてしまう。
「好きです。付き合ってください」
それに杏奈は驚いた顔をした。夢なら私は自由だ。何も怖いものなどない。
杏奈は自身の唇に指を当てる。彼女が思案する時の癖だった。目を横に流しながら、おずおずといった様子で言う。
「私、女だよ? 西塚さんも」
「何か問題が?」
「そっか。確かに」
それで納得してくれたようだ。
杏奈は私に視線を移す。耳が真っ赤になっていた。
「その私、付き合うとかまだよく分からないから。まずは、友達からなら……」
私は心臓が早鐘のように打つのが分かった。胸が痛いぐらいだった。何とか声を絞り出す。
「よろしくお願いします」
「こちらこそ……」
杏奈は恥ずかしそうに顔を伏せ、両手で自身のスカートを摘み、指を遊ばせていた。
しかし随分と都合がよく、それでいて都合の悪い夢だ。
せっかくならこのまま付き合えたらいいのに。
「それじゃ今からデートしよう」
「え? これから始業式だよ?」
「じゃあ始業式が終わったら」
「あ、うん。それならいいよ……」
せめてデートするまで、この夢が覚めないでほしかった。
私たちは教室まで一緒に行く。
赤星杏奈は笑いながら言う。
「西塚さんってけっこう強引なんだね」
それはどことなく非難が込められているような気がした。
これが現実で、あるいは当時の自分であったら取り乱していただろう。私は美人が苦手だが、夢の中であればどんな美人も怖くないことに気付いた。
「いや。こういうのはちゃんとはっきりしないと後悔するから」
「後悔?」
「こんなチャンス、二度とないかもしれない」
「そんなことないよ。だって今日から一年、一緒のクラスじゃない」
「目が覚めたら全部なかったことになってるだろうし」
「面白いこと言うね」
教室に着く。すでに先にクラスにいた杏奈の友人たちが彼女を呼ぶ。あの小動物的な女子もいた。玉津とかいう名字だったか。
私は彼女たちとは親しくないので離れることにした。それに杏奈が気付き、私に手を振った。
「それじゃまた後でね」
「うん」
暇になった私は、ここでいったん状況を整理する。
これは本当に夢なのか。あるいは二十五歳の私が夢だったのではないだろうか。そんなはずがないことはよく分かっている。疑問を差し挟む余地もない。
しかし一体、この夢はいつまで続くのか。せめて杏奈とデートしてキスするまではいきたいのだが、そこに到達するまでにしばらくかかりそうだ。
夢特有のシーン間のスキップがない。このまま体感時間がリアルタイム式で夢が上映されていくのか。
おそらくこれは明晰夢というものなのだろう。明晰夢では、体感で数日間も夢の中に滞在できると聞いたことがある、気がする。ただ明晰夢であれば、自在に夢の内容をコントロールできたはずだ。
ならば私は、杏奈のスカートでもめくってやろうかと思案した。笑って許してくれるかエロい展開になるはず。いや、なんか超能力的なものでめくろう。ディテールが大事だ。私は地球の自転によるエネルギーを何かそういう力に変換する能力者だ。私は杏奈のスカートに念を送る。
しかし何も起こらない。
杏奈が広げた手のひらを向ける私に気付いて、笑顔で手を振ってくれた。私は罪悪感がわいて、手をふり返した後、引っ込める。まさか私がスカートをめくろうとしているなど、彼女は思いもしないだろう。
一日が普通に経過していく。教室にクラスメートが増えていく。あまりの懐かしさに、こそばゆい気持ちになってきた。なぜだか笑えてくる。
しばらくして、小学校以来の友人、菊田英美香が教室に入ってきた。彼女も同じクラスだったことを思い出した。
英美香はムッとした顔で大股に歩み寄ってくる。
「西塚! 一緒に行こうって約束したじゃん!」
「あー、ごめん。忘れてた」
確か一緒に登校する約束をしていた。というよりもほぼ毎朝一緒に登校していた。
怒る英美香をよそに、いちいちギミックが細かい夢だと私は感心した。
彼女は私の前に立つとすかさず抱きついてくる。
「また同じクラスだよー!」
「だね」
英美香とは高校も同じで、彼女と別のクラスになったのは高校一年の時だけだった。
私は視界の隅に杏奈を捉えながら、英美香と他愛もない会話をして時間を潰す。何度か杏奈と目が合った。少しはこちらを意識してくれているみたいで嬉しかった。
そのうちに鐘が鳴り、クラス担任の先生が教室に入ってくる。
体育館に全校生徒が集められ、始業式はつつがなく進行した。
校長の訓示や新入生代表の挨拶、校歌斉唱など。何一つ覚えていないはずなのにリアルだった。
真面目に聞いていたことがないので、私の記憶の再現で、よくこんなリアルに仕上げられたものだ。
覚えていない、思い出せないことでも、潜在意識下に記憶が保存されている。みたいなことをどこかで見聞きしたことがある。つまりはそういうことなのだろう。
始業式が終わり、生徒たちは各教室に戻る。私と英美香は一緒に廊下を歩いていた。
「西塚、このあとカラオケ行こーぜ!」
「ごめん。先約がある」
「はあ? 誰と?」
どう答えたものか。言葉に詰まる。
不意に杏奈が私を追い越して、横を通り過ぎた。その際に私の肩に手を置いて、耳打ちする。
「終わったら裏門のところで待ち合わせね」
「うん。分かった」
杏奈は振り返り小さく手を振る。私も小さく返す。
それに英美香は動揺していた。
「え、今のなに? いつの間に赤星さんと仲良くなったの?」
私と英美香は偏差値四十程度。学年でも下位の学力グループ且つ品行方正とは言い難い。対して赤星杏奈は上位どころかおそらく学年一位の優等生。私たちはヒト亜種で彼女はヒト種のエリート。もはや生物種として違い、学校という生態系内で棲み分けがされていた。
正門とは別に通用門があり、私たちは裏門などと呼んでいた。
校舎裏の花壇に囲まれた道、そこを抜けると裏門に出る。
杏奈が先にいて待ってくれていた。
「夕方から家族で食事に行くから、それまででいい?」
「うん。いいよ」
しかしデートとはいったが、どこに行ったものか。
「とりあえず駅前のバーガー屋行く? その後、カラオケでも行く?」
「制服で?」
「まずい?」
制服での買い食いなどは禁止されているが、ほとんど形骸化した校則である。しかし優等生である杏奈はそういうのを気にするようだ。
「お財布持ってきてないから、いったん家に帰って、着替えてから待ち合わせする?」
「うーん……」
そんなまどろっこしいことをして、途中で目覚めたら台無しだ。私はとにかく杏奈と放課後デートがしたい。
「買い食いとか気にする方?」
「わりとみんなしてるし、そんなに気にしないけど」
「じゃあコンビニでなんかおごるよ」
「え、それは悪いよ」
「気にするなら今度返してくれればいいし」
「うん、分かった」
「とりあえず、あんまり人のいない静かな場所知ってるから、そこ行かない? 名前知らないけど、裏山の神社のとこにある公園」
「行ったことない! 気になる!」
そこは学校から徒歩三十分ほどのところにある。山といっても丘と形容した方がいいのだろうか。なだらかな丘で、ところどころに雑木林がある。斜面には多くの住宅があり、道路も舗装されていた。その頂上ではなく、中腹寄りのところに神社があった。神社には広い境内があり、その境内に入る鳥居の手前には公園がある。夏祭りは人で賑わうが、普段は人の気配が全くない。
「途中コンビニ寄ってから行こうか」
「うん!」
当時、もし告白していれば、こんなふうに二人で遊べていたのだろうか。
私は胸の中の青い後悔に自嘲気味に苦笑した。
裏山の神社に向かう途中、コンビニでホットスナックとか飲み物、菓子を適当に買った。
そして神社に着くまでの間、いろいろなことを話した。
「小学校はどこだったの?」
「線路の反対側。中学からこっち」
「今日一緒にいた友達は同じ小学校?」
「玉津さん? 彼女とは中学一年から。玉津さんは中学からこっちに引っ越してきたんだって」
「そうなんだ。けっこう仲良いよね」
「うーん。そうだね」
「西塚さんも今日一緒にいた子、誰?」
「英美香? 小学校からの友達」
「今度紹介してよ」
「いいよ」
こんな普通の会話をするのが新鮮だった。いつも「サヨちゃん。サヨちゃん」言いながら抱きついてくる杏奈も、別に嫌いではない。むしろ好きだが、こうして普通に会話できるのは楽しかった。
そのうち裏山の神社に着く。
神社は雑木林に囲われ、曇りがちの四月の空も相まって、辺りは薄暗かった。
その中にあって境内の森閑とした広い空間が、ぽっかりと広がっていた。
「あ、ここ、もしかしたら子供の頃来たことあるかも!」
「夏には盆踊りとかお祭りもやってるからね。私も来るの十五年ぶりかな」
「生まれてないじゃん」
杏奈がおかしそうに笑う。そういえば私たちは十三歳だった。しかし十三歳で杏奈はこんなに大人びていたのか。肌艶や面差しに幼さはあるが、整った顔立ちをしていると年長に見える。
そんな杏奈が目を細めて顔を綻ばせるのが、あまりにも可愛くて、私は胸が締めつけられるようだった。
現実の杏奈も確かにこんなふうに笑うが、そちらは精神年齢的に中学生の杏奈より幼く、ついつい親目線で見てしまう。
杏奈が境内の中を散策する。それに私はついていく。
「何の神様が祀られているんだろ」
社殿は境内の外周沿いにあり、奥行きはないが、それなりの大きさがあった。2トントラックのコンテナより大きい、と思われる。手前に賽銭箱があり、その上に、あのガラガラ鳴るやつが吊るされていた。大きな鈴と太い縄のやつだ。
杏奈が楽しそうに、それに手をかけている。
「お賽銭入れる?」
私は財布を取り出す。
「いい! 今度自分で来た時にやる!」
私も別に祈ることもないので財布をしまった。
「それじゃ、お昼にしよう」
私たちは鳥居を抜け、公園に出る。砂場と滑り台、変な動物のグラグラ揺れる遊具が三つ、それとベンチがあった。
私たちはそのベンチに腰かける。
私はビニール袋から、コンビニで買った物を取り出し杏奈と分ける。
杏奈はわざわざ仰々しく手を合わせる。
「いただきます。あ、本当にちゃんと返すからね。もしかしたら私が事故に遭って返せなくなったら困るから、一応言っただけね」
「縁起でもないな」
私は苦笑した。
当時の杏奈とこんなふうに話すのは初めてだった。本当はこんな感じなのかと思うと、感慨深いものがあった。
いや、修学旅行の事前学習で、意外と話したことがあった。そのイメージがあるから、それが反映されているのか。
しばらく私たちは買ってきた物を食べていた。不意に杏奈が言う。
「どうして私のこと好きなの?」
いきなり核心に触れてきたなと思った。
「どうしてって、赤星さんのこと好きじゃない人類っているの?」
「そういうことじゃなくて。西塚さんの好きって、そういうことじゃないでしょ」
「ああ」
私は思案する。
当時の私は赤星杏奈を美人だと思うし憧れていた。その手に触れたい、唇に触れたい、名前を呼ばれたいと思ったことは数知れず。現実の私は正気を失った赤星杏奈を世話していた。その上、弱みにつけこんで恋人のふりまでしている。これを愛などと言えるはずがない。私にあるのは劣情だけだ。
ただ今の偽らざる心境を言えば、
「赤星さんのこと、守りたいって思ったから。もし付き合えたら守れたのかなって」
もし今この時に付き合えていたら、杏奈のことを守れただろうか。
もしも付き合えたら、そもそも付き合えなくても、未来を変えることができるのなら、私は杏奈を守りたい。そう思った。
「守るって、何から?」
「いろんなことから」
「どうして私を?」
「赤星さんのことが好きだから」
私は杏奈の横顔を見る。杏奈は耳を赤くしていた。粗相をして泣いている時や、怒った時に耳が赤くなるのを思い出した。恥ずかしくて赤くなっているのだろうか。私もなんだか恥ずかしくなってきた。
「うーん……全然よく分からないけど、分かった……」
杏奈は唇に指を当てながら、花弁を一枚一枚数えるように、言葉をこぼすように言う。
「私、付き合うとか、好きとか、よく分からない。たぶん私自身が、まだ誰かを好きになったことがないから」
そこで杏奈は私の方を向き、じっと目を見つめる。
「ただ西塚さんが真剣だってことは分かるし。それに私、あなたのこと知りたいって、思えるから。だから最初に言ったとおり、まずは友達から、ってことでいいかな?」
夢なのに随分と都合よくいかない。しかし照れくさそうに、あるいは恥ずかしそうに、いっぱいいっぱいの様子で言う杏奈が可愛くて新鮮だった。私はこれはこれでいいなと思った。
「うん。友達からよろしくお願いします」
「こちらこそ、よろしくお願いします」
それに杏奈はにっこりと笑った。
その後、私たちは他愛ない会話をし、最後に電話番号とメールアドレスを互いに登録した。当時はまだメールが主流だった。世界的チャットアプリが出現するのは確か二年後だったろうか。
登録を済ますと、杏奈は申し訳なさそうに言う。
「あの、私、メールが苦手で。素っ気なかったりしたらごめんね」
「私も苦手というか。返信遅かったらごめん」
「全然! 私、直接会って話すのは大丈夫なんだけど、文章で会話するの苦手なんだよね」
「分かる。要件だけのやり取りは平気だけど、文章だけだと会話続けるの難しいんだよね」
「そうなんだよね。だからね。怒ってるように見えても、怒ってるわけじゃないからね。返信がなくても、気付いてないだけだから」
杏奈は念を押してくる。彼女なりに苦労してきたのだろうと察した。
夢だというのに律儀に帰宅すると、母に帰りが遅いことを怒られた。
帰宅後は一通りウリ坊とたわむる。
夕飯を食べた後、風呂に入る時、明日も学校だから早く寝るように言われた。
風呂から上がって寝巻きに着替え、またウリ坊を撫で回し、一時間ぐらいそうしてから自室に戻った。
布団に入る。実家の天井が視界に広がった。紐を引っ張って照明を消す。
真っ暗になると、私は我に返った。夢の中で、このまま本当に寝るのか、と。
しかしこの夢から一向に目覚める気配がない。
寝れば現実で目覚めるのか。目覚めないのなら、このままずっと夢の中で中学時代をやり直してもいいが。
その場合、誰があの杏奈の面倒を見るのかと思い至る。
私にとって一番大事なのは現実の杏奈だ。
不意に私は夢の中の杏奈からメールが来ていないかと思い、四代前のスマートフォンを開く。
『また明日学校で』
とだけ送られていた。顔文字も絵文字もない。まだスタンプは存在していなかったか。そもそもメール機能に実装されたかも知らない。
何となくこんな短文を律儀に送ってくる杏奈が可愛く思えた。
『楽しみにしてる。また明日』
私も修飾をつけず、それだけ返した。なんとなく嬉しい気持ちになった。布団の中で体が熱かった。
こんな些細なことだが、私たちは意外といい友達になれたのかもしれない。と思えた。
もしもやり直せるのなら、私が杏奈を守るのに。
◇ ◇ ◇
私は寝返りを打った拍子に目を覚ます。
正確には寝返りに失敗した。私は体の左側を下にして寝る癖があるのだが、右側に向きを変えようとした際、左腕を杏奈に掴まれていたので、仰向けになったところでそれ以上回ることができなかった。
隣で杏奈は寝息を立てている。夢の続きかと思ったが、杏奈の眉は私が整えた形をしていた。そのことから薄暗がりでも、これが現実だと分かった。天井も、いつもの私の部屋のものになっている。
夢で寝て現実で目覚める、奇妙な夢だった。目覚めれば夢の記憶は曖昧になり、起きた瞬間に忘れてしまうことが大半なのだが、つい昨日のことのように思い出すことができた。
中学時代の赤星杏奈に告白し、都合よく交際してあわよくば性的な触れ合いをすることはできなかったが、友達から始めることになるという、我ながら随分と乙女な願望を抱いていたものだ。
もしも中学生からやり直せるとしたら、あんなふうに告白はしないまでも、杏奈と仲良くなって友人となり、彼女が壊れてしまわないよう守りたい。そんなことは思っても無駄なことだが。
当時、杏奈は私の憧れだったが、思った以上に杏奈のことを好きだったのだなと、今更ながら痛感した。
私は杏奈に向き直り、髪を撫でる。
「杏奈のことは、私が守るから」
壊れてしまった彼女が立ち直る日が来るかは分からない。その日が来た時、私は不要になるかもしれない。それでも今は私が守る。
そう心に誓った。
いつものように朝の支度をして、いつものように擦り寄ってくる杏奈を宥め、私は家を出る。
出勤の電車の中、暇を持て余し、私は夢の続きを妄想していた。
とりあえず杏奈と友達からスタートした。ここからエロいことをするにはどうしたらいいか。次の日から、学校でどう接しようか。
教室の中、私は杏奈と、英美香と一緒にいる。英美香は驚いた様子だった。
「西塚、赤星さんと友達だったんだ!」
それに杏奈が微笑む。
「うん。最近ね。菊田さんは小学校から西塚さんと友達なんだよね」
「そうそう。私たちは小学校一年の時からの親友なんだ」
「どうだろ。腐れ縁というか悪友?」
「ひどっ!」
それに杏奈が笑っていた。
そこまで妄想して私は我に返った。
一体なんだこの妄想は。ジュブナイル趣味が私にあったのか。と動揺した。
しかしそれ以上に動揺したのが、私はこれを妄想と感じていないことだった。事実あったこと、そう感じていた。
私は妄想していたのではない。思い出していたのだ。あの夢の、次の日のことを。
記憶も妄想も、脳内で再生される映像、再現される感覚だ。その記憶の想起と妄想の区別をどうつけるか。単純にそれが事実であったか事実でないか、他ならぬ自分自身がそれを知っている。
三人であんな会話をした事実はない。そんな出来事はなかった。
しかし私は先ほどの杏奈と英美香と三人でしたやり取りを、妄想ではなく、事実だと感じていた。
きっとあまりにリアルすぎる夢に、実体験と誤認しているのだ。私はそう思うことにしたが。強烈な違和感が私を襲った。
私は咄嗟にスマートフォンを取り出し、ほとんど使うことのなくなった連絡帳アプリを、手間取りながらも探して開く。
機種変をしてもデータは引き継ぎされている。そしてその中にあるはずがない、赤星杏奈の電話番号とメールアドレス。それが登録されていた。
私は杏奈とアドレスを交換した記憶を、今まで忘れていたのだろうか。
突然、私は私という存在に自信を失った。
20
お気に入りに追加
8
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

〈社会人百合〉アキとハル
みなはらつかさ
恋愛
女の子拾いました――。
ある朝起きたら、隣にネイキッドな女の子が寝ていた!?
主人公・紅(くれない)アキは、どういったことかと問いただすと、酔っ払った勢いで、彼女・葵(あおい)ハルと一夜をともにしたらしい。
しかも、ハルは失踪中の大企業令嬢で……?
絵:Novel AI

とある高校の淫らで背徳的な日常
神谷 愛
恋愛
とある高校に在籍する少女の話。
クラスメイトに手を出し、教師に手を出し、あちこちで好き放題している彼女の日常。
後輩も先輩も、教師も彼女の前では一匹の雌に過ぎなかった。
ノクターンとかにもある
お気に入りをしてくれると喜ぶ。
感想を貰ったら踊り狂って喜ぶ。
してくれたら次の投稿が早くなるかも、しれない。
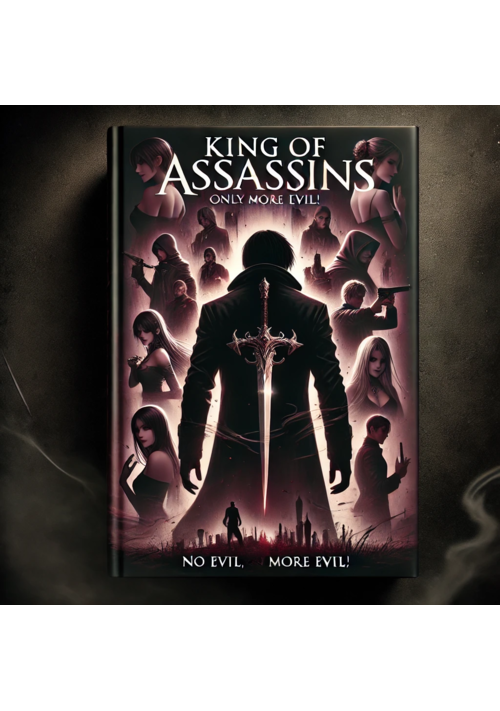

軍艦少女は死に至る夢を見る~戦時下の大日本帝国から始まる艦船擬人化物語~
takahiro
キャラ文芸
『船魄』(せんぱく)とは、軍艦を自らの意のままに操る少女達である。船魄によって操られる艦艇、艦載機の能力は人間のそれを圧倒し、彼女達の前に人間は殲滅されるだけの存在なのだ。1944年10月に覚醒した最初の船魄、翔鶴型空母二番艦『瑞鶴』は、日本本土進攻を企てるアメリカ海軍と激闘を繰り広げ、ついに勝利を掴んだ。
しかし戦後、瑞鶴は帝国海軍を脱走し行方をくらませた。1955年、アメリカのキューバ侵攻に端を発する日米の軍事衝突の最中、瑞鶴は再び姿を現わし、帝国海軍と交戦状態に入った。瑞鶴の目的はともかくとして、船魄達を解放する戦いが始まったのである。瑞鶴が解放した重巡『妙高』『高雄』、いつの間にかいる空母『グラーフ・ツェッペリン』は『月虹』を名乗って、国家に属さない軍事力として活動を始める。だが、瑞鶴は大義やら何やらには興味がないので、利用できるものは何でも利用する。カリブ海の覇権を狙う日本・ドイツ・ソ連・アメリカの間をのらりくらりと行き交いながら、月虹は生存の道を探っていく。
登場する艦艇はなんと57隻!(2024/12/18時点)(人間のキャラは他に多数)(まだまだ増える)。人類に反旗を翻した軍艦達による、異色の艦船擬人化物語が、ここに始まる。
――――――――――
●本作のメインテーマは、あくまで(途中まで)史実の地球を舞台とし、そこに船魄(せんぱく)という異物を投入したらどうなるのか、です。いわゆる艦船擬人化ものですが、特に軍艦や歴史の知識がなくとも楽しめるようにしてあります。もちろん知識があった方が楽しめることは違いないですが。
●なお軍人がたくさん出て来ますが、船魄同士の関係に踏み込むことはありません。つまり船魄達の人間関係としては百合しかありませんので、ご安心もしくはご承知おきを。かなりGLなので、もちろんがっつり性描写はないですが、苦手な方はダメかもしれません。
●全ての船魄に挿絵ありですが、AI加筆なので雰囲気程度にお楽しみください。
●少女たちの愛憎と謀略が絡まり合う、新感覚、リアル志向の艦船擬人化小説を是非お楽しみください。またお気に入りや感想などよろしくお願いします。
毎日一話投稿します。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















