あなたにおすすめの小説

下っ端宮女のひたむき後宮恋譚 ~前世の夢を追いかけていたらいつのまにか寵愛されていました~
紀本明
キャラ文芸
妃嬪から嫌がらせを受けつつも耐え忍んでいた下っ端宮女の鈴風(りんふぁ)はある日突然前世の記憶を取り戻す。料理人になるのが夢だった彼女は、今世でもその夢を叶えようと決意した矢先、ぼさぼさ頭の宦官・雲嵐(うんらん)と出会い、毎晩夕飯をつくることになる。料理人になるべく奮闘するも、妃嬪からの嫌がらせはひどくなる一方だった。そんなある日、事件が起こり、鈴風は窮地に立たされるが……――?

お隣さんはヤのつくご職業
古亜
恋愛
佐伯梓は、日々平穏に過ごしてきたOL。
残業から帰り夜食のカップ麺を食べていたら、突然壁に穴が空いた。
元々薄い壁だと思ってたけど、まさか人が飛んでくるなんて……ん?そもそも人が飛んでくるっておかしくない?それにお隣さんの顔、初めて見ましたがだいぶ強面でいらっしゃいますね。
……え、ちゃんとしたもん食え?
ちょ、冷蔵庫漁らないでくださいっ!!
ちょっとアホな社畜OLがヤクザさんとご飯を食べるラブコメ
建築基準法と物理法則なんて知りません
登場人物や団体の名称や設定は作者が適当に生み出したものであり、現実に類似のものがあったとしても一切関係ありません。
2020/5/26 完結

花嫁御寮 ―江戸の妻たちの陰影― :【第11回歴史・時代小説大賞 奨励賞】
naomikoryo
歴史・時代
名家に嫁いだ若き妻が、夫の失踪をきっかけに、江戸の奥向きに潜む権力、謀略、女たちの思惑に巻き込まれてゆく――。
舞台は江戸中期。表には見えぬ女の戦(いくさ)が、美しく、そして静かに燃え広がる。
結城澪は、武家の「御寮人様」として嫁いだ先で、愛と誇りのはざまで揺れることになる。
失踪した夫・宗真が追っていたのは、幕府中枢を揺るがす不正金の記録。
やがて、志を同じくする同心・坂東伊織、かつて宗真の婚約者だった篠原志乃らとの交錯の中で、澪は“妻”から“女”へと目覚めてゆく。
男たちの義、女たちの誇り、名家のしがらみの中で、澪が最後に選んだのは――“名を捨てて生きること”。
これは、名もなき光の中で、真実を守り抜いたひと組の夫婦の物語。
静謐な筆致で描く、江戸奥向きの愛と覚悟の長編時代小説。
全20話、読み終えた先に見えるのは、声高でない確かな「生」の姿。

神様がくれた時間―余命半年のボクと記憶喪失のキミの話―
コハラ
ライト文芸
余命半年の夫と記憶喪失の妻のラブストーリー!
愛妻の推しと同じ病にかかった夫は余命半年を告げられる。妻を悲しませたくなく病気を打ち明けられなかったが、病気のことが妻にバレ、妻は家を飛び出す。そして妻は駅の階段から転落し、病院で目覚めると、夫のことを全て忘れていた。妻に悲しい思いをさせたくない夫は妻との離婚を決意し、妻が入院している間に、自分の痕跡を消し出て行くのだった。一ヶ月後、千葉県の海辺の町で生活を始めた夫は妻と遭遇する。なぜか妻はカフェ店員になっていた。はたして二人の運命は?
――――――――
※第8回ほっこりじんわり大賞奨励賞ありがとうございました!
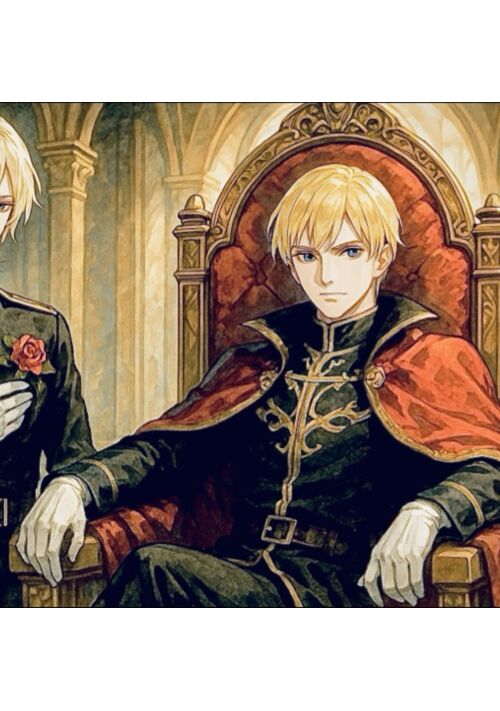
魅了持ちの執事と侯爵令嬢【完結済】
tii
恋愛
あらすじ
――その執事は、完璧にして美しき存在。
だが、彼が仕えるのは、”魅了の魔”に抗う血を継ぐ、高貴なる侯爵令嬢だった。
舞踏会、陰謀、政略の渦巻く宮廷で、誰もが心を奪われる彼の「美」は、決して無害なものではない。
その美貌に隠された秘密が、ひとりの少女を、ひとりの弟を、そして侯爵家、はたまた国家の運命さえも狂わせていく。
愛とは何か。忠誠とは、自由とは――
これは、決して交わることを許されぬ者たちが、禁忌に触れながらも惹かれ合う、宮廷幻想譚。

新しい家族は保護犬きーちゃん
ゆきむらさり
エッセイ・ノンフィクション
〔あらすじ〕📝初めて🐶保護犬ちゃんを迎え入れる我が家。
過去の哀しい実情のせいで人間不信で怯える保護犬きーちゃん。
初日から試行錯誤の日々と保護犬きーちゃんがもたらす至福の日々。
◇
🔶保護犬ちゃん達の過去・現在の実情の記述もあります🐾
🔶日々の些細な出来事を綴っています。現在進行形のお話となります🐾
🔶🐶挿絵画像入りです。
🔶拙いエッセイにもかかわらず、HOTランキングに入れて頂き(2025.7.1、最高位31位)ありがとうございます🙇♀️

自由を愛する妖精姫と、番にすべてを捧げた竜人王子〜すれ違いと絆の先に、恋を知る〜
来栖れいな
ファンタジー
妖精女王と精霊王の間に生まれた特別な存在――セレスティア。
自由を愛し、気ままに生きる彼女のもとに現れたのは、竜人族の王子・サイファルト。
「お前は俺の番だ」
番という名の誓いにすべてを捧げた彼は、王族の地位も未来も捨てて森に現れた。
一方のセレスティアは、まだ“番”の意味すら知らない。
執着と守護。すれ違いと絆。
――これは、ひとりの妖精姫が“特別”に気づいていく物語。
甘さ控えめ、でも確かに溺愛。
異種族の距離を越えて紡がれる、成長と守護のファンタジー。

【㊗️受賞!】神のミスで転生したけど、幼児化しちゃった!〜もふもふと一緒に、異世界ライフを楽しもう!〜
一ノ蔵(いちのくら)
ファンタジー
※第18回ファンタジー小説大賞にて、奨励賞を受賞しました!投票して頂いた皆様には、感謝申し上げますm(_ _)m
✩物語は、ゆっくり進みます。冒険より、日常に重きありの異世界ライフです。
【あらすじ】
神のミスにより、異世界転生が決まったミオ。調子に乗って、スキルを欲張り過ぎた結果、幼児化してしまった!
そんなハプニングがありつつも、ミオは、大好きな異世界で送る第二の人生に、希望いっぱい!
事故のお詫びに遣わされた、守護獣神のジョウとともに、ミオは異世界ライフを楽しみます!
仕事繁忙期の為、2月中旬まで更新を週一に致します。
カクヨム(吉野 ひな)様にも投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















