16 / 396
第一章 輪廻のアルケミスト
第16話 託児所の初日
しおりを挟む
託児所の初日は、はっきり言って酷いものだった。
酷いと一言で言っても、今の僕にとっての酷さであって、それがあったとしてもグラスとしての人生とは比べるまでもなく天国ではあるのだけれど。
それでも、僕よりも小さなアルフェを護りながら、遠慮を知らない子供たちの輪の中で一日を過ごすのはかなりのハードモードだった。
アルフェの浄眼はお人形さんみたいだと、僕たちよりもお姉さんな子供たちに人気だったし、アルフェは僕以外には拒絶反応を示して泣きじゃくるので大変だった。
最終的にジュディさんの従姉らしい託児所の職員が、僕とアルフェをバリケードの中に入れてくれて安寧を得たのだが、それまでが大変過ぎて、滅多にしない昼寝を寝落ちという不本意なかたちですることになった。
「アルフェってば、託児所でもリーフちゃんにべったりだったみたいね」
「一緒に入れて良かったわ。明日からも宜しくね、アルフェちゃん」
目が覚めた時、アルフェがしっかりと僕に抱きついていたのが印象的だったらしく、迎えに来た母親たちがしきりにその話題を口にしている。
二人きりになった後のアルフェは、いつもよりも興奮気味に遊んでいて、普段よりも僕へのスキンシップが多かった。多分彼女なりに、環境の変化に戸惑っていたのだろうな。
「それにしても大きな子もたくさんいたのね。びっくりしちゃった」
「そうなの。これから小さい赤ちゃんたちも預かる予定だから、アルフェとリーフが来てくれて従姉も色々改善点を見つけたみたいよ」
なるほど。トントン拍子に話が進んだのが気になっていたが、どうやら僕とアルフェは実験台のようだ。
「しばらくは二人だけを別室で預かって、この年齢向けに工夫してみるって」
このままでは僕の身が保たないので、是非そうしてもらいたい。
「よかったわね、リーフ」
「あー……」
母に微笑みかけられて返事をしようとしたが、間の抜けた声が漏れた。
「リーフ?」
「リーフちゃん、どうしたの?」
どうも僕の様子がおかしいらしく、母親たちが揃って顔を覗き込んでくる。その顔も涙かなにかで滲んでぼやけて見えた。
「らいよー……」
大丈夫、ちょっと疲れただけだから。そう言おうと思ったが、舌がもつれて上手くいかなかった。熱が出る予兆なのか、あるいは既に熱が出ているのか身体の末端が冷えて酷く寒い。どういうわけか眠くて仕方がなく、そのことが酷く怖かった。
◇◇◇
深い闇に落ちるような眠りだった。僕の目を覚まさせたのは、両親が話す声だった。
「――そろそろ君も休んだらどうだい、ナタル」
「いいえ。私がリーフに無理をさせてしまったの。私が責任をもって看病しなきゃ」
いつの間にか夜になったらしい。まだ熱が上がっているのか、毛布にくるまれているのに身体の震えが止まらなかった。
――ああ、嫌だな、この感覚……。
大抵の不快なものは我慢できるが、この発熱の状況だけは本能的な危機を感じて嫌だった。熱が出るという感覚は、黒石病の初期症状を彷彿とさせ、グラスとしての僕の人生との因果を想像させるからだ。
女神が転生させたこのリーフとしての命が、こんなところで終わるなんて思いたくないものだが……。
「家のことを任せきりにしていた私の責任でもある。とにかく休みなさい」
「あなたは外で大切なお仕事をしてきたのよ、ルドラ。そんなふうに言わないで」
こうして父の声を聞くのも久しぶりだ。もしかして僕の不調を聞いて駆けつけてきてくれたのかな。だったらかなり申し訳ないのだが。
「……君には頭が上がらないな。では、こうしよう。君の言う通り先に休む。ただし、起きたら君と交代だ。いいね?」
「……ええ」
父の提案に母は渋々と言った感じで了承している。僕のことが心配でならないのだろうな、と素直に思った。
「……部下も話していたが、赤ん坊の発熱なんてしょっちゅうだよ。これまで熱も出さずに過ごしてくれたリーフに感謝こそすれ、自分を責める必要はないんだ」
「……でも、私、育児から少し離れたら錬金術の仕事を――。なんて自分のことを考えてしまって」
確かに僕を託児所に預けられれば、母は自分のために時間を使える。それはなにも悪くないし普通のことだ。そう伝えたいが、僕がいきなり喋り出したら気味悪がられるだろうな。
「それは、君のためでもあり、我々家族のためでもある。気に病むことはなにもないよ」
僕の考えていることと、父の考えが偶然にも一致する。やはり、父が居た方が母も心強いのだろう、相槌を打つ声に安堵の響きが混じっていた。
「……そもそも君の錬金術がなければ、この命はなかっただろうからね。君は命の恩人でもあるんだよ、ナタル」
「私たちもあなたに日々守られているんですから、おあいこですよ」
会話の端々に両親の馴れそめが散らばっている。軍人の父と錬金術師の母の出逢いに、少しだけ興味が湧き、耳をそばだてながら身体の向きを変えた。
「そうだといいな。この先も――」
寝返りを打つ僅かな衣擦れの音に気づいたのか、父が言葉を切る。そしてそのまま、僕のベッドへと大股で歩み寄ってきた。
「リーフ、目が覚めたか?」
久しぶりに見る父の顔だった。その目は今にも泣きそうに潤んでいる。
――これ以上、心配をかけてはいけないな。
そう思って僕は笑顔を作り、父に向けて手を伸ばした。
「……おかえり」
「ははは、リーフ! パパにお帰りが言えるのか!? 凄いぞ!」
だが、逆効果だったらしい。
「本当に、リーフ……。優しい子……」
父も母も僕の手を握り、溢れる涙を隠そうともせず泣いている。やっぱり大丈夫、と伝えた方がよかったのだろうか。熱に浮かされながら自分の判断について悩んでいると、額に母が手を当てた。
「まだ少し熱が高いわ。冷やしましょうね」
そう言って、母は前掛けで涙を拭くと、手際良く新しい氷嚢を用意して頭と首の後ろに当て、氷水に浸して絞った冷たい布を額に乗せてくれた。
「できるだけ眠って、ゆっくり休んでね」
頭が冷やされたことでかなりすっきりした。あれほど酷かった寒気も引き、熱が身体に回っているような感覚がある。だが、その熱もすぐに下がりそうな予感がして、希望が持てた。
「早く熱がさがりますように」
おまじないのように唱えながら、母が額の布が温くなる前に冷たく冷やしたものに取り替えてくれる。
僕は冷たい布と氷嚢の心地良さにウトウトと目を閉じた。
そのまま細切れの眠りの中に落ちた僕は、短い覚醒で両親の存在に安堵してまた眠るのを繰り返した。
目覚めている間、頭の布は交換され、常に冷たいままだった。
あるときは母が、あるときは父が交互に世話をしていたらしい。朝になって目を覚ますと、二人が自分の傍に寄り添うようにして眠っていた。
熱はすっかり下がっている。
こんなに大事にされることは、本性を現す前の養父でさえやらなかったことだ。
――養父……。
もうすっかり忘れていたと思ったが、前世の記憶はそっくりそのまま残されているらしい。
乾いたパンと水が食料として部屋の前に置かれて、床を這いながらそれを取りに行く。声をかけられることもなく、個室に何日も放置される――。僕がグラスだった頃に唯一受けた看病だ。
両親の看病はそれとは全く違う。
――この二人は、僕にかなりの愛情を注いでくれてる。
そのことが改めて有り難く、彼らに対する信頼を強いものにしていた。だが、同時に自分はそれにどうやって応えられるのだろうか。どうやったらこの恩に報いることができるのだろうかという不安めいた問いを僕は自らに与えることになった。
早く成長して、その術を見いだせると良いのだが。
酷いと一言で言っても、今の僕にとっての酷さであって、それがあったとしてもグラスとしての人生とは比べるまでもなく天国ではあるのだけれど。
それでも、僕よりも小さなアルフェを護りながら、遠慮を知らない子供たちの輪の中で一日を過ごすのはかなりのハードモードだった。
アルフェの浄眼はお人形さんみたいだと、僕たちよりもお姉さんな子供たちに人気だったし、アルフェは僕以外には拒絶反応を示して泣きじゃくるので大変だった。
最終的にジュディさんの従姉らしい託児所の職員が、僕とアルフェをバリケードの中に入れてくれて安寧を得たのだが、それまでが大変過ぎて、滅多にしない昼寝を寝落ちという不本意なかたちですることになった。
「アルフェってば、託児所でもリーフちゃんにべったりだったみたいね」
「一緒に入れて良かったわ。明日からも宜しくね、アルフェちゃん」
目が覚めた時、アルフェがしっかりと僕に抱きついていたのが印象的だったらしく、迎えに来た母親たちがしきりにその話題を口にしている。
二人きりになった後のアルフェは、いつもよりも興奮気味に遊んでいて、普段よりも僕へのスキンシップが多かった。多分彼女なりに、環境の変化に戸惑っていたのだろうな。
「それにしても大きな子もたくさんいたのね。びっくりしちゃった」
「そうなの。これから小さい赤ちゃんたちも預かる予定だから、アルフェとリーフが来てくれて従姉も色々改善点を見つけたみたいよ」
なるほど。トントン拍子に話が進んだのが気になっていたが、どうやら僕とアルフェは実験台のようだ。
「しばらくは二人だけを別室で預かって、この年齢向けに工夫してみるって」
このままでは僕の身が保たないので、是非そうしてもらいたい。
「よかったわね、リーフ」
「あー……」
母に微笑みかけられて返事をしようとしたが、間の抜けた声が漏れた。
「リーフ?」
「リーフちゃん、どうしたの?」
どうも僕の様子がおかしいらしく、母親たちが揃って顔を覗き込んでくる。その顔も涙かなにかで滲んでぼやけて見えた。
「らいよー……」
大丈夫、ちょっと疲れただけだから。そう言おうと思ったが、舌がもつれて上手くいかなかった。熱が出る予兆なのか、あるいは既に熱が出ているのか身体の末端が冷えて酷く寒い。どういうわけか眠くて仕方がなく、そのことが酷く怖かった。
◇◇◇
深い闇に落ちるような眠りだった。僕の目を覚まさせたのは、両親が話す声だった。
「――そろそろ君も休んだらどうだい、ナタル」
「いいえ。私がリーフに無理をさせてしまったの。私が責任をもって看病しなきゃ」
いつの間にか夜になったらしい。まだ熱が上がっているのか、毛布にくるまれているのに身体の震えが止まらなかった。
――ああ、嫌だな、この感覚……。
大抵の不快なものは我慢できるが、この発熱の状況だけは本能的な危機を感じて嫌だった。熱が出るという感覚は、黒石病の初期症状を彷彿とさせ、グラスとしての僕の人生との因果を想像させるからだ。
女神が転生させたこのリーフとしての命が、こんなところで終わるなんて思いたくないものだが……。
「家のことを任せきりにしていた私の責任でもある。とにかく休みなさい」
「あなたは外で大切なお仕事をしてきたのよ、ルドラ。そんなふうに言わないで」
こうして父の声を聞くのも久しぶりだ。もしかして僕の不調を聞いて駆けつけてきてくれたのかな。だったらかなり申し訳ないのだが。
「……君には頭が上がらないな。では、こうしよう。君の言う通り先に休む。ただし、起きたら君と交代だ。いいね?」
「……ええ」
父の提案に母は渋々と言った感じで了承している。僕のことが心配でならないのだろうな、と素直に思った。
「……部下も話していたが、赤ん坊の発熱なんてしょっちゅうだよ。これまで熱も出さずに過ごしてくれたリーフに感謝こそすれ、自分を責める必要はないんだ」
「……でも、私、育児から少し離れたら錬金術の仕事を――。なんて自分のことを考えてしまって」
確かに僕を託児所に預けられれば、母は自分のために時間を使える。それはなにも悪くないし普通のことだ。そう伝えたいが、僕がいきなり喋り出したら気味悪がられるだろうな。
「それは、君のためでもあり、我々家族のためでもある。気に病むことはなにもないよ」
僕の考えていることと、父の考えが偶然にも一致する。やはり、父が居た方が母も心強いのだろう、相槌を打つ声に安堵の響きが混じっていた。
「……そもそも君の錬金術がなければ、この命はなかっただろうからね。君は命の恩人でもあるんだよ、ナタル」
「私たちもあなたに日々守られているんですから、おあいこですよ」
会話の端々に両親の馴れそめが散らばっている。軍人の父と錬金術師の母の出逢いに、少しだけ興味が湧き、耳をそばだてながら身体の向きを変えた。
「そうだといいな。この先も――」
寝返りを打つ僅かな衣擦れの音に気づいたのか、父が言葉を切る。そしてそのまま、僕のベッドへと大股で歩み寄ってきた。
「リーフ、目が覚めたか?」
久しぶりに見る父の顔だった。その目は今にも泣きそうに潤んでいる。
――これ以上、心配をかけてはいけないな。
そう思って僕は笑顔を作り、父に向けて手を伸ばした。
「……おかえり」
「ははは、リーフ! パパにお帰りが言えるのか!? 凄いぞ!」
だが、逆効果だったらしい。
「本当に、リーフ……。優しい子……」
父も母も僕の手を握り、溢れる涙を隠そうともせず泣いている。やっぱり大丈夫、と伝えた方がよかったのだろうか。熱に浮かされながら自分の判断について悩んでいると、額に母が手を当てた。
「まだ少し熱が高いわ。冷やしましょうね」
そう言って、母は前掛けで涙を拭くと、手際良く新しい氷嚢を用意して頭と首の後ろに当て、氷水に浸して絞った冷たい布を額に乗せてくれた。
「できるだけ眠って、ゆっくり休んでね」
頭が冷やされたことでかなりすっきりした。あれほど酷かった寒気も引き、熱が身体に回っているような感覚がある。だが、その熱もすぐに下がりそうな予感がして、希望が持てた。
「早く熱がさがりますように」
おまじないのように唱えながら、母が額の布が温くなる前に冷たく冷やしたものに取り替えてくれる。
僕は冷たい布と氷嚢の心地良さにウトウトと目を閉じた。
そのまま細切れの眠りの中に落ちた僕は、短い覚醒で両親の存在に安堵してまた眠るのを繰り返した。
目覚めている間、頭の布は交換され、常に冷たいままだった。
あるときは母が、あるときは父が交互に世話をしていたらしい。朝になって目を覚ますと、二人が自分の傍に寄り添うようにして眠っていた。
熱はすっかり下がっている。
こんなに大事にされることは、本性を現す前の養父でさえやらなかったことだ。
――養父……。
もうすっかり忘れていたと思ったが、前世の記憶はそっくりそのまま残されているらしい。
乾いたパンと水が食料として部屋の前に置かれて、床を這いながらそれを取りに行く。声をかけられることもなく、個室に何日も放置される――。僕がグラスだった頃に唯一受けた看病だ。
両親の看病はそれとは全く違う。
――この二人は、僕にかなりの愛情を注いでくれてる。
そのことが改めて有り難く、彼らに対する信頼を強いものにしていた。だが、同時に自分はそれにどうやって応えられるのだろうか。どうやったらこの恩に報いることができるのだろうかという不安めいた問いを僕は自らに与えることになった。
早く成長して、その術を見いだせると良いのだが。
1
お気に入りに追加
793
あなたにおすすめの小説
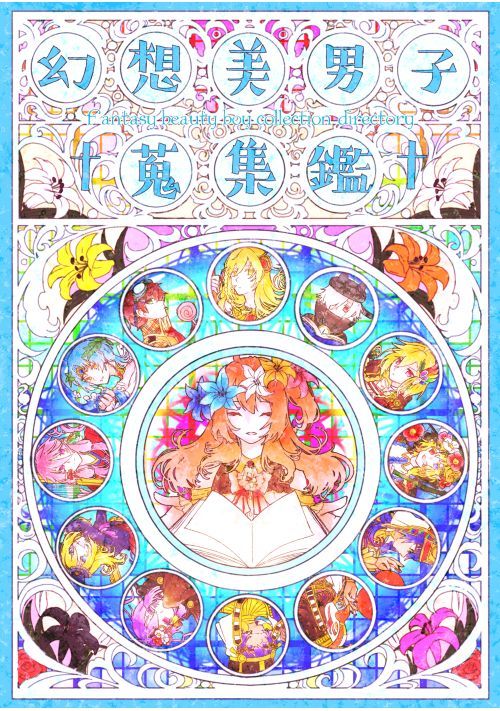
幻想美男子蒐集鑑~夢幻月華の書~
紗吽猫
ファンタジー
ーー さぁ、世界を繋ぐ旅を綴ろう ーー
自称美男子愛好家の主人公オルメカと共に旅する好青年のソロモン。旅の目的はオルメカコレクションー夢幻月下の書に美男子達との召喚契約をすること。美男子の噂を聞きつけてはどんな街でも、時には異世界だって旅して回っている。でもどうやらこの旅、ただの逆ハーレムな旅とはいかないようでー…?
美男子を見付けることのみに特化した心眼を持つ自称美男子愛好家は出逢う美男子達を取り巻く事件を解決し、無事に魔導書を完成させることは出来るのか…!?
時に出逢い、時に闘い、時に事件を解決し…
旅の中で出逢う様々な美男子と取り巻く仲間達との複数世界を旅する物語。
※この作品はエブリスタでも連載中です。

『ラノベ作家のおっさん…異世界に転生する』
来夢
ファンタジー
『あらすじ』
心臓病を患っている、主人公である鈴也(レイヤ)は、幼少の時から見た夢を脚色しながら物語にして、ライトノベルの作品として投稿しようと書き始めた。
そんなある日…鈴也は小説を書き始めたのが切っ掛けなのか、10年振りに夢の続きを見る。
すると、今まで見た夢の中の男の子と女の子は、青年の姿に成長していて、自分の書いている物語の主人公でもあるヴェルは、理由は分からないが呪いの攻撃を受けて横たわっていた。
ジュリエッタというヒロインの聖女は「ホーリーライト!デスペル!!」と、仲間の静止を聞かず、涙を流しながら呪いを解く魔法を掛け続けるが、ついには力尽きて死んでしまった。
「へっ?そんな馬鹿な!主人公が死んだら物語の続きはどうするんだ!」
そんな後味の悪い夢から覚め、風呂に入ると心臓発作で鈴也は死んでしまう。
その後、直ぐに世界が暗転。神様に会うようなセレモニーも無く、チートスキルを授かる事もなく、ただ日本にいた記憶を残したまま赤ん坊になって、自分の書いた小説の中の世界へと転生をする。
”自分の書いた小説に抗える事が出来るのか?いや、抗わないと周りの人達が不幸になる。書いた以上責任もあるし、物語が進めば転生をしてしまった自分も青年になると死んでしまう
そう思い、自分の書いた物語に抗う事を決意する。

けだものだもの~虎になった男の異世界酔夢譚~
ちょろぎ
ファンタジー
神の悪戯か悪魔の慈悲か――
アラフォー×1社畜のサラリーマン、何故か虎男として異世界に転移?する。
何の説明も助けもないまま、手探りで人里へ向かえば、言葉は通じず石を投げられ騎兵にまで追われる有様。
試行錯誤と幾ばくかの幸運の末になんとか人里に迎えられた虎男が、無駄に高い身体能力と、現代日本の無駄知識で、他人を巻き込んだり巻き込まれたりしながら、地盤を作って異世界で生きていく、日常描写多めのそんな物語。
第13章が終了しました。
申し訳ありませんが、第14話を区切りに長期(予定数か月)の休載に入ります。
再開の暁にはまたよろしくお願いいたします。
この作品は小説家になろうさんでも掲載しています。
同名のコミック、HP、曲がありますが、それらとは一切関係はありません。

『収納』は異世界最強です 正直すまんかったと思ってる
農民ヤズ―
ファンタジー
「ようこそおいでくださいました。勇者さま」
そんな言葉から始まった異世界召喚。
呼び出された他の勇者は複数の<スキル>を持っているはずなのに俺は収納スキル一つだけ!?
そんなふざけた事になったうえ俺たちを呼び出した国はなんだか色々とヤバそう!
このままじゃ俺は殺されてしまう。そうなる前にこの国から逃げ出さないといけない。
勇者なら全員が使える収納スキルのみしか使うことのできない勇者の出来損ないと呼ばれた男が収納スキルで無双して世界を旅する物語(予定
私のメンタルは金魚掬いのポイと同じ脆さなので感想を送っていただける際は語調が強くないと嬉しく思います。
ただそれでも初心者故、度々間違えることがあるとは思いますので感想にて教えていただけるとありがたいです。
他にも今後の進展や投稿済みの箇所でこうしたほうがいいと思われた方がいらっしゃったら感想にて待ってます。
なお、書籍化に伴い内容の齟齬がありますがご了承ください。

異世界王女に転生したけど、貧乏生活から脱出できるのか
片上尚
ファンタジー
海の事故で命を落とした山田陽子は、女神ロミア様に頼まれて魔法がある世界のとある国、ファルメディアの第三王女アリスティアに転生!
悠々自適の贅沢王女生活やイケメン王子との結婚、もしくは現代知識で無双チートを夢見て目覚めてみると、待っていたのは3食草粥生活でした…
アリスティアは現代知識を使って自国を豊かにできるのか?
痩せっぽっちの王女様奮闘記。

異世界転生したらたくさんスキルもらったけど今まで選ばれなかったものだった~魔王討伐は無理な気がする~
宝者来価
ファンタジー
俺は異世界転生者カドマツ。
転生理由は幼い少女を交通事故からかばったこと。
良いとこなしの日々を送っていたが女神様から異世界に転生すると説明された時にはアニメやゲームのような展開を期待したりもした。
例えばモンスターを倒して国を救いヒロインと結ばれるなど。
けれど与えられた【今まで選ばれなかったスキルが使える】 戦闘はおろか日常の役にも立つ気がしない余りものばかり。
同じ転生者でイケメン王子のレイニーに出迎えられ歓迎される。
彼は【スキル:水】を使う最強で理想的な異世界転生者に思えたのだが―――!?
※小説家になろう様にも掲載しています。

対人恐怖症は異世界でも下を向きがち
こう7
ファンタジー
円堂 康太(えんどう こうた)は、小学生時代のトラウマから対人恐怖症に陥っていた。学校にほとんど行かず、最大移動距離は200m先のコンビニ。
そんな彼は、とある事故をきっかけに神様と出会う。
そして、過保護な神様は異世界フィルロードで生きてもらうために多くの力を与える。
人と極力関わりたくない彼を、老若男女のフラグさん達がじわじわと近づいてくる。
容赦なく迫ってくるフラグさん。
康太は回避するのか、それとも受け入れて前へと進むのか。
なるべく間隔を空けず更新しようと思います!
よかったら、読んでください

辺境領主は大貴族に成り上がる! チート知識でのびのび領地経営します
潮ノ海月@書籍発売中
ファンタジー
旧題:転生貴族の領地経営~チート知識を活用して、辺境領主は成り上がる!
トールデント帝国と国境を接していたフレンハイム子爵領の領主バルトハイドは、突如、侵攻を開始した帝国軍から領地を守るためにルッセン砦で迎撃に向かうが、守り切れず戦死してしまう。
領主バルトハイドが戦争で死亡した事で、唯一の後継者であったアクスが跡目を継ぐことになってしまう。
アクスの前世は日本人であり、争いごとが極端に苦手であったが、領民を守るために立ち上がることを決意する。
だが、兵士の証言からしてラッセル砦を陥落させた帝国軍の数は10倍以上であることが明らかになってしまう
完全に手詰まりの中で、アクスは日本人として暮らしてきた知識を活用し、さらには領都から避難してきた獣人や亜人を仲間に引き入れ秘策を練る。
果たしてアクスは帝国軍に勝利できるのか!?
これは転生貴族アクスが領地経営に奮闘し、大貴族へ成りあがる物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















