17 / 19
第二章 私と618
5:到着 六月二十五日、午前八時四十分から、六月二十五日 昼 十二時半辺り 2
しおりを挟む
掃討作戦は、単純なものだった。
要は、ゾンビを一気に行動不能にすればいいわけである。
銃で撃つ? 火を点ける? 爆破する?
いやいや――我々は『全身を骨折』させることにしたのだ。
『群れ』が北上する国道は、広大な田畑地帯を通る。そこの両端に、バリケードを設置し、道路上に我々が『餌』として並ぶ。
ゾンビがバリケードに囲まれた国道に入ったら、前を塞ぎ、後方からタンデム式ロードローラー(車体の前後に一輪ずつローラーが着いているタイプ)を六台走らせ、押し潰すのである。(安全を考え、運転席の周りに鉄板を打ち付けた。今も、某町の倉庫に、定期メンテを受けながら待機している)
これで『動けるゾンビ』を極力減らし、『はぐれ』や『あぶれた奴』、『潰しそこない』は待機した警官隊が個別に拘束。その後、用意したハンマー等で、確実に仕留めていくという作戦である。
機動力が落ちたゾンビならば、処理は容易なのではないか、と考えたわけだ。
ちなみに、これが失敗したならば、ゴミ処理場まで誘導し、ゴミピット(焼却前にゴミを溜めておく場所)に閉じ込める作戦、バリケードで囲んだ駐車場に閉じ込める作戦、等を用意していた。(つまりは、ローラー作戦の失敗原因を探り、対策を立て直す為の時間稼ぎ案である)
午前十時過ぎ。我々はローラー作戦の現場に到着した。
気温は早くも35℃に達し、焼けたアスファルトに『逃げ水』が現れる。
風が無く、汗がダラダラと流れ出す。
誰も何も言わない。
十分、二十分、そして三十分が過ぎようとした時、我々の遥か前方に、大勢の人影が現れた。
うっと誰かが呻いた。
うっすらと臭いが漂ってきたから、だと思う。
腐った肉と人糞を混ぜたような臭い――と私は表現するが、読者諸君も嗅いだであろう、あの臭いが、段々と強烈になってくる。
Xが、目にくるなと呟き、Zが服に染み付きそうだ、とぼやいた。Yは双眼鏡でゾンビをずっと観察していた。
「やけに黒いな。日が照ってるからか?」
私の言葉に、Yが双眼鏡を下した。
「服が汚れているからな。あと――連中、まるで干物みたいだ」
Xと私が顔を見合わせた。
「そういや、ゾンビ予報にそう書いてあったような……」
Xの言葉に、Zが首を傾げた。
「つまり――どういうことだ? 水分が飛んでて、軽いって事か? このままやっても――大丈夫なのかな?」
私はYから双眼鏡を借りると、ゾンビに向けた。
ゆらゆらと揺れる空気の向こうを、連中は歩いていた。
だが、服は所々破れ、半裸に近いのに、目に入ってくる色は、人肌の色でも、映画でお馴染みの死人の青さや白さではなく、焦げ茶色だけだった。一番近いのは――ニシンの燻製だろうか?
顔も、手も足も、全てが萎びていた。口は大きく開き、全く動かない。目は開いてはいるようだが、動く気配はなく、やはり萎びて、茶色に近くなっている。
連中の殆どが、後に『熟成ゾンビ』と言われる状態にあったのである。
「動きが遅い。殆どすり足だ……」
私の言葉に、Xは双眼鏡を覗きこんだ。
「……おいおい、手も上げてないぞ。ゾンビお約束のポーズも無しだ」
Zが双眼鏡を受け取ると覗き込んだ。
「ふむ……こっちまで来るのに、随分と時間がかかりそうだな。飯でも食うか?」
私達は顔を見合わせた。
流石に飯は食わなかったが、一服はした。
ゾンビがバリケードに達したのは、なんと十五分後で、作戦が開始された(つまり、ゾンビの群れがバリケードでできた道に完全に入った)のは、更に三十分後、十二時十五分ぐらいだった。
今でも、あの時の事を思い出す。
ゾンビは声を上げた。
読者諸君の中にも、未だにトラウマになっているであろう、あの笛の音みたいな、ヒーッという声だ。
声帯が腐敗したうえで乾燥し、肺は機能していない。だから、体が動くか、風が吹くと、ごく稀に、喉が笛のような音を立てるらしい。
酷い臭いと、ゾンビの体が磨れあうたびに聞こえる、ガサガサという音で、辺りが埋め尽くされた。(後にYが、虫かごにいれすぎたバッタみたいだった、と言った)
バリケードの外から、警察官が、さすまたで押すと、ゾンビは簡単に倒れこんだ。
私達は、呆然と立っていた。
はっきり言えば――拍子抜けしたのだ。
結果を言えば、ロードローラー作戦は大成功だった。
大成功すぎた。
ばりばりとプラスチックを割った時みたいな音を立て、ゾンビはぐしゃぐしゃになっていった。茶色の体液を飛び散らせ、ヒーッという声を上げ、それでいて、腕も足も動かさず、碌な抵抗を見せず、ローラーの下に吸い込まれ、ぺらぺらでぐしゃぐしゃの汚い染みになっていったのだ。
約十五分後――六月二十五日 昼 十二時半辺り。
掃討作戦は終了した。
うだるような暑さと、耐え難い悪臭。
嘔吐する職員と警官達。
アスファルトを埋め尽くす、もはや大量の汚物としか言いようのない、ゾンビのなれの果て。
当初の予定では、ダンプ等で遺骸を焼却炉まで運ぶ予定であったが、両脇の畑の持ち主が、もうこの場所で作った物を喰う気がしない、と穴を掘って、焼く提案を持ちかけてきた。(後述するが、この場所は後に県が買い取って、記念碑を建てる事になる)
我々は積み込み用のブルドーザーと、人力をもって、道路からゾンビの残骸を引っぺがすと、畑に掘った巨大な穴に放り込み、ガソリンをかけて燃やしたのだった。
業火を見つめながら、全員が脱力をしていたように思う。
それでも、清掃車で道路を清掃すると、臭いも薄くなり、食事をとったり、談笑したりするものが出てきた。
火は、約五時間後、夜七時に鎮火した。
プレスされたせいか、はたまた、骨が何らかの腐食をしていたのか、穴の中には大量の灰があるのみであった。
「ようやく――地獄が一杯って台詞を肌で感じたよ」
全部が終わった後に、ぐったりとしたXが言った言葉である。
要は、ゾンビを一気に行動不能にすればいいわけである。
銃で撃つ? 火を点ける? 爆破する?
いやいや――我々は『全身を骨折』させることにしたのだ。
『群れ』が北上する国道は、広大な田畑地帯を通る。そこの両端に、バリケードを設置し、道路上に我々が『餌』として並ぶ。
ゾンビがバリケードに囲まれた国道に入ったら、前を塞ぎ、後方からタンデム式ロードローラー(車体の前後に一輪ずつローラーが着いているタイプ)を六台走らせ、押し潰すのである。(安全を考え、運転席の周りに鉄板を打ち付けた。今も、某町の倉庫に、定期メンテを受けながら待機している)
これで『動けるゾンビ』を極力減らし、『はぐれ』や『あぶれた奴』、『潰しそこない』は待機した警官隊が個別に拘束。その後、用意したハンマー等で、確実に仕留めていくという作戦である。
機動力が落ちたゾンビならば、処理は容易なのではないか、と考えたわけだ。
ちなみに、これが失敗したならば、ゴミ処理場まで誘導し、ゴミピット(焼却前にゴミを溜めておく場所)に閉じ込める作戦、バリケードで囲んだ駐車場に閉じ込める作戦、等を用意していた。(つまりは、ローラー作戦の失敗原因を探り、対策を立て直す為の時間稼ぎ案である)
午前十時過ぎ。我々はローラー作戦の現場に到着した。
気温は早くも35℃に達し、焼けたアスファルトに『逃げ水』が現れる。
風が無く、汗がダラダラと流れ出す。
誰も何も言わない。
十分、二十分、そして三十分が過ぎようとした時、我々の遥か前方に、大勢の人影が現れた。
うっと誰かが呻いた。
うっすらと臭いが漂ってきたから、だと思う。
腐った肉と人糞を混ぜたような臭い――と私は表現するが、読者諸君も嗅いだであろう、あの臭いが、段々と強烈になってくる。
Xが、目にくるなと呟き、Zが服に染み付きそうだ、とぼやいた。Yは双眼鏡でゾンビをずっと観察していた。
「やけに黒いな。日が照ってるからか?」
私の言葉に、Yが双眼鏡を下した。
「服が汚れているからな。あと――連中、まるで干物みたいだ」
Xと私が顔を見合わせた。
「そういや、ゾンビ予報にそう書いてあったような……」
Xの言葉に、Zが首を傾げた。
「つまり――どういうことだ? 水分が飛んでて、軽いって事か? このままやっても――大丈夫なのかな?」
私はYから双眼鏡を借りると、ゾンビに向けた。
ゆらゆらと揺れる空気の向こうを、連中は歩いていた。
だが、服は所々破れ、半裸に近いのに、目に入ってくる色は、人肌の色でも、映画でお馴染みの死人の青さや白さではなく、焦げ茶色だけだった。一番近いのは――ニシンの燻製だろうか?
顔も、手も足も、全てが萎びていた。口は大きく開き、全く動かない。目は開いてはいるようだが、動く気配はなく、やはり萎びて、茶色に近くなっている。
連中の殆どが、後に『熟成ゾンビ』と言われる状態にあったのである。
「動きが遅い。殆どすり足だ……」
私の言葉に、Xは双眼鏡を覗きこんだ。
「……おいおい、手も上げてないぞ。ゾンビお約束のポーズも無しだ」
Zが双眼鏡を受け取ると覗き込んだ。
「ふむ……こっちまで来るのに、随分と時間がかかりそうだな。飯でも食うか?」
私達は顔を見合わせた。
流石に飯は食わなかったが、一服はした。
ゾンビがバリケードに達したのは、なんと十五分後で、作戦が開始された(つまり、ゾンビの群れがバリケードでできた道に完全に入った)のは、更に三十分後、十二時十五分ぐらいだった。
今でも、あの時の事を思い出す。
ゾンビは声を上げた。
読者諸君の中にも、未だにトラウマになっているであろう、あの笛の音みたいな、ヒーッという声だ。
声帯が腐敗したうえで乾燥し、肺は機能していない。だから、体が動くか、風が吹くと、ごく稀に、喉が笛のような音を立てるらしい。
酷い臭いと、ゾンビの体が磨れあうたびに聞こえる、ガサガサという音で、辺りが埋め尽くされた。(後にYが、虫かごにいれすぎたバッタみたいだった、と言った)
バリケードの外から、警察官が、さすまたで押すと、ゾンビは簡単に倒れこんだ。
私達は、呆然と立っていた。
はっきり言えば――拍子抜けしたのだ。
結果を言えば、ロードローラー作戦は大成功だった。
大成功すぎた。
ばりばりとプラスチックを割った時みたいな音を立て、ゾンビはぐしゃぐしゃになっていった。茶色の体液を飛び散らせ、ヒーッという声を上げ、それでいて、腕も足も動かさず、碌な抵抗を見せず、ローラーの下に吸い込まれ、ぺらぺらでぐしゃぐしゃの汚い染みになっていったのだ。
約十五分後――六月二十五日 昼 十二時半辺り。
掃討作戦は終了した。
うだるような暑さと、耐え難い悪臭。
嘔吐する職員と警官達。
アスファルトを埋め尽くす、もはや大量の汚物としか言いようのない、ゾンビのなれの果て。
当初の予定では、ダンプ等で遺骸を焼却炉まで運ぶ予定であったが、両脇の畑の持ち主が、もうこの場所で作った物を喰う気がしない、と穴を掘って、焼く提案を持ちかけてきた。(後述するが、この場所は後に県が買い取って、記念碑を建てる事になる)
我々は積み込み用のブルドーザーと、人力をもって、道路からゾンビの残骸を引っぺがすと、畑に掘った巨大な穴に放り込み、ガソリンをかけて燃やしたのだった。
業火を見つめながら、全員が脱力をしていたように思う。
それでも、清掃車で道路を清掃すると、臭いも薄くなり、食事をとったり、談笑したりするものが出てきた。
火は、約五時間後、夜七時に鎮火した。
プレスされたせいか、はたまた、骨が何らかの腐食をしていたのか、穴の中には大量の灰があるのみであった。
「ようやく――地獄が一杯って台詞を肌で感じたよ」
全部が終わった後に、ぐったりとしたXが言った言葉である。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説





鹿翅島‐しかばねじま‐
寝る犬
ホラー
【アルファポリス第3回ホラー・ミステリー大賞奨励賞】
――金曜の朝、その島は日本ではなくなった。
いつもと変わらないはずの金曜日。
穏やかな夜明けを迎えたかに見えた彼らの街は、いたる所からあがる悲鳴に満たされた。
一瞬で、音も無く半径数キロメートルの小さな島『鹿翅島‐しかばねじま‐』へ広がった「何か」は、平和に暮らしていた街の人々を生ける屍に変えて行く。
隔離された環境で、あるものは戦い、あるものは逃げ惑う。
ゾンビアンソロジー。
※章ごとに独立した物語なので、どこからでも読めます。
※ホラーだけでなく、コメディやアクション、ヒューマンドラマなど様々なタイプの話が混在しています。
※各章の小見出しに、その章のタイプが表記されていますので、参考にしてください。
※由緒正しいジョージ・A・ロメロのゾンビです。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
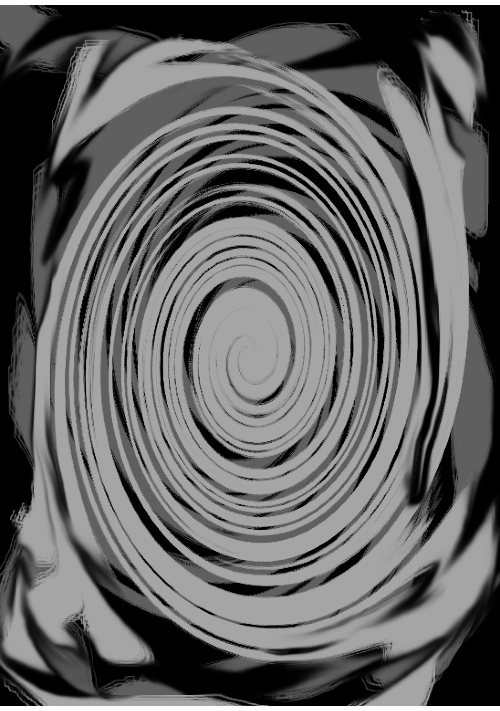

最終死発電車
真霜ナオ
ホラー
バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。
直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。
外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。
生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。
「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















