81 / 103
第1堡塁の戦い
第80話 戦闘糧食を
しおりを挟む
「本部から送られてきた作戦図と状況図の照合を急がせてくれ、それが済んだら、明日の戦闘予行をするから、各分隊長には時間を知らせてくれ、それ以外の者は、今のうちに休養を取らせてくれ、これは司令からの徹底事項だからな」
昭三は、眠さも疲れも感じることなく、今、自分の頭脳が猛烈な勢いで回転している事が理解出来ていた。
アドレナリン
自分の身体の芯から、アドレナリンが大量分泌されているのが、明白であった。
それは、快楽そのものであり、どんなに的確な指示を与え続けても、それは快楽に似た恍惚に変化してゆくのが解った。
空腹も感じない、自分はどこまでも行ける、そう思えるのであった。
そんな時、自分に話しかけてくる古参の軍人がいた。
「小隊長、少し食事を召し上がってください、最後まで持ちませんよ」
昭三の率いる第3小隊には、54連隊から小隊付軍曹の響鬼(ひびき)軍曹が付いていた。
偶然であるが、響鬼という珍しい名字が軍曹と重なると響(ひびき)鬼軍曹と読めるため、そのまま鬼軍曹と呼ばれていた。
実際にその指揮の補佐や訓練の厳しさは鬼軍曹と呼べる厳しいものがあり、名は体を表すの如く、この人物を理解しやすいネーミングと言えた。
そんな彼だからこそ、小隊長に言える一言もあった。
昭三は、彼が何を言っているのかが、理解出来ないでいた。
しかし、傍から見れば、彼のその的確過ぎる命令指示は、高校1年生のそれを遥かに超える異常なものであった。
「食べろ」と言ってきた古参の軍曹は、これと同じ状況を、過去に見たことがあった。
それは、国防大学校がまだ防衛大学校と呼ばれていた時代、任官間もない防大出の若手小隊長が、今回と同じように北富士第3堡塁に挑んだ時、それは起こっていたのである。
今の昭三と同じように、彼の目はギラギラと輝いて、ほとんど食事を手に付けないでいた。
しかし、そんな状況は長続きせず、恍惚と快楽に任せて勢いよく指揮していた新任小隊長は、最終日を前にして突然、電池の切れた玩具のように、動きが鈍くなり、自制が効かず動けなくなってしまったのである。
これは、優秀な新任小隊長によく起こる現象で、その頭脳故に、自身の作戦が「快楽」となってこだまし、自分のコンディションを掌握できなくなる現象なのだ。
古参の軍曹は、それをよく知っていた。
この昭三もまた、若いものの、そのような頭脳明晰タイプの小隊長であり、いくらスタミナがあっても、それは明日の後半までもたない事が、軍曹には理解出来ていた。
本来であれば、かなり年下の、それも高校生同等の昭三に対し、それでもプロの軍曹として、しっかりとした敬語を用いて小隊長として扱っていた。
それは、プロの軍人のプライドでもあった。
その敬語の裏には、それだけの補職に就いているのだから、それだけの働きをしろよ、という暗黙の了解があった。
もちろん昭三はそれを十分に理解していた。
「軍曹、ありがとうございます。でも、今はまったく空腹は感じませんし頭は冴えてます、大丈夫です」
「だいたい、若い小隊長はみんなそう言うんですよ、でもね小隊長、私の経験から食べない小隊長は勝てない小隊長なんですよ、ですから、無理にでも食べてください。」
昭三は、この古参の軍曹の言うことに従おうと思った。
なるほど、これが古参というものか、それは初めて触れる本物の軍人の気風に思えた、それ故に、このように諭される時こそ、自身は強くなっている最中なのだと感じるのである。
軍曹は、昭三にそんな話をすると、意外にも昭三は自身のコンディションを理解し、指揮を一旦中断し、食事に専念するのである。
食事と言っても、冷たく冷えた戦闘糧食であったが、アドレナリンが放出されている昭三にとって、それは特別なご馳走にすら思えた。
昭三は、それを一心不乱に勢いよく食べ続けるのであった。
それを見た、古参の軍曹は、思わず関心した。
なぜなら、過去に経験のある「動けなくなった小隊長」とは、他ならぬ敵の第1師団第2部長なのだから。
頭脳派として知られ、上条師団長の懐刀として活躍する彼ですら、新米小隊長時代には、そのようであったのだから、まだ16歳の昭三が、しっかりと自分のコンディションに気付いた事が、彼には頼もしく感じられた。
それでも強引に食事を口に押し込むと、昭三は再び作戦図の前に噛り付き、明日の戦いに向け、その頭脳を再起動させた。
明日は、夜明けとともに第2堡塁攻略戦が開始されるのだから。
昭三は、眠さも疲れも感じることなく、今、自分の頭脳が猛烈な勢いで回転している事が理解出来ていた。
アドレナリン
自分の身体の芯から、アドレナリンが大量分泌されているのが、明白であった。
それは、快楽そのものであり、どんなに的確な指示を与え続けても、それは快楽に似た恍惚に変化してゆくのが解った。
空腹も感じない、自分はどこまでも行ける、そう思えるのであった。
そんな時、自分に話しかけてくる古参の軍人がいた。
「小隊長、少し食事を召し上がってください、最後まで持ちませんよ」
昭三の率いる第3小隊には、54連隊から小隊付軍曹の響鬼(ひびき)軍曹が付いていた。
偶然であるが、響鬼という珍しい名字が軍曹と重なると響(ひびき)鬼軍曹と読めるため、そのまま鬼軍曹と呼ばれていた。
実際にその指揮の補佐や訓練の厳しさは鬼軍曹と呼べる厳しいものがあり、名は体を表すの如く、この人物を理解しやすいネーミングと言えた。
そんな彼だからこそ、小隊長に言える一言もあった。
昭三は、彼が何を言っているのかが、理解出来ないでいた。
しかし、傍から見れば、彼のその的確過ぎる命令指示は、高校1年生のそれを遥かに超える異常なものであった。
「食べろ」と言ってきた古参の軍曹は、これと同じ状況を、過去に見たことがあった。
それは、国防大学校がまだ防衛大学校と呼ばれていた時代、任官間もない防大出の若手小隊長が、今回と同じように北富士第3堡塁に挑んだ時、それは起こっていたのである。
今の昭三と同じように、彼の目はギラギラと輝いて、ほとんど食事を手に付けないでいた。
しかし、そんな状況は長続きせず、恍惚と快楽に任せて勢いよく指揮していた新任小隊長は、最終日を前にして突然、電池の切れた玩具のように、動きが鈍くなり、自制が効かず動けなくなってしまったのである。
これは、優秀な新任小隊長によく起こる現象で、その頭脳故に、自身の作戦が「快楽」となってこだまし、自分のコンディションを掌握できなくなる現象なのだ。
古参の軍曹は、それをよく知っていた。
この昭三もまた、若いものの、そのような頭脳明晰タイプの小隊長であり、いくらスタミナがあっても、それは明日の後半までもたない事が、軍曹には理解出来ていた。
本来であれば、かなり年下の、それも高校生同等の昭三に対し、それでもプロの軍曹として、しっかりとした敬語を用いて小隊長として扱っていた。
それは、プロの軍人のプライドでもあった。
その敬語の裏には、それだけの補職に就いているのだから、それだけの働きをしろよ、という暗黙の了解があった。
もちろん昭三はそれを十分に理解していた。
「軍曹、ありがとうございます。でも、今はまったく空腹は感じませんし頭は冴えてます、大丈夫です」
「だいたい、若い小隊長はみんなそう言うんですよ、でもね小隊長、私の経験から食べない小隊長は勝てない小隊長なんですよ、ですから、無理にでも食べてください。」
昭三は、この古参の軍曹の言うことに従おうと思った。
なるほど、これが古参というものか、それは初めて触れる本物の軍人の気風に思えた、それ故に、このように諭される時こそ、自身は強くなっている最中なのだと感じるのである。
軍曹は、昭三にそんな話をすると、意外にも昭三は自身のコンディションを理解し、指揮を一旦中断し、食事に専念するのである。
食事と言っても、冷たく冷えた戦闘糧食であったが、アドレナリンが放出されている昭三にとって、それは特別なご馳走にすら思えた。
昭三は、それを一心不乱に勢いよく食べ続けるのであった。
それを見た、古参の軍曹は、思わず関心した。
なぜなら、過去に経験のある「動けなくなった小隊長」とは、他ならぬ敵の第1師団第2部長なのだから。
頭脳派として知られ、上条師団長の懐刀として活躍する彼ですら、新米小隊長時代には、そのようであったのだから、まだ16歳の昭三が、しっかりと自分のコンディションに気付いた事が、彼には頼もしく感じられた。
それでも強引に食事を口に押し込むと、昭三は再び作戦図の前に噛り付き、明日の戦いに向け、その頭脳を再起動させた。
明日は、夜明けとともに第2堡塁攻略戦が開始されるのだから。
0
お気に入りに追加
9
あなたにおすすめの小説
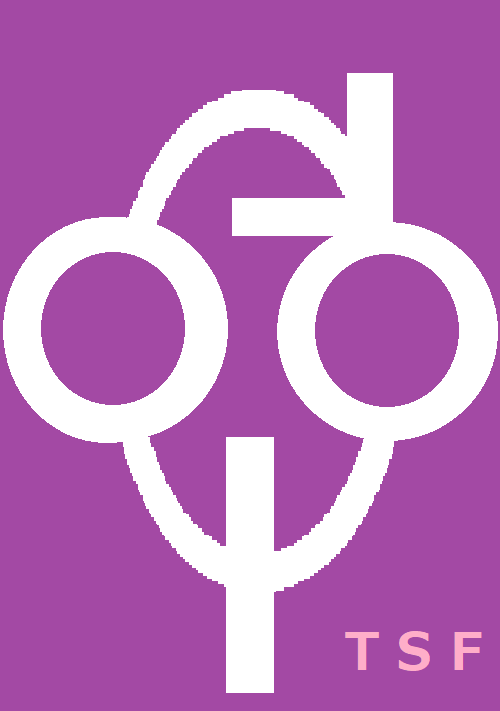

女子高生は卒業間近の先輩に告白する。全裸で。
矢木羽研
恋愛
図書委員の女子高生(小柄ちっぱい眼鏡)が、卒業間近の先輩男子に告白します。全裸で。
女の子が裸になるだけの話。それ以上の行為はありません。
取って付けたようなバレンタインネタあり。
カクヨムでも同内容で公開しています。

お兄ちゃんは今日からいもうと!
沼米 さくら
ライト文芸
大倉京介、十八歳、高卒。女子小学生始めました。
親の再婚で新しくできた妹。けれど、彼女のせいで僕は、体はそのまま、他者から「女子小学生」と認識されるようになってしまった。
トイレに行けないからおもらししちゃったり、おむつをさせられたり、友達を作ったり。
身の回りで少しずつ不可思議な出来事が巻き起こっていくなか、僕は少女に染まっていく。
果たして男に戻る日はやってくるのだろうか。
強制女児女装万歳。
毎週木曜と日曜更新です。


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。


忘却の艦隊
KeyBow
SF
新設された超弩級砲艦を旗艦とし新造艦と老朽艦の入れ替え任務に就いていたが、駐留基地に入るには数が多く、月の1つにて物資と人員の入れ替えを行っていた。
大型輸送艦は工作艦を兼ねた。
総勢250艦の航宙艦は退役艦が110艦、入れ替え用が同数。
残り30艦は増強に伴い新規配備される艦だった。
輸送任務の最先任士官は大佐。
新造砲艦の設計にも関わり、旗艦の引き渡しのついでに他の艦の指揮も執り行っていた。
本来艦隊の指揮は少将以上だが、輸送任務の為、設計に関わった大佐が任命された。
他に星系防衛の指揮官として少将と、退役間近の大将とその副官や副長が視察の為便乗していた。
公安に近い監査だった。
しかし、この2名とその側近はこの艦隊及び駐留艦隊の指揮系統から外れている。
そんな人員の載せ替えが半分ほど行われた時に中緊急警報が鳴り、ライナン星系第3惑星より緊急の救援要請が入る。
機転を利かせ砲艦で敵の大半を仕留めるも、苦し紛れに敵は主系列星を人口ブラックホールにしてしまった。
完全にブラックホールに成長し、その重力から逃れられないようになるまで数分しか猶予が無かった。
意図しない戦闘の影響から士気はだだ下がり。そのブラックホールから逃れる為、禁止されている重力ジャンプを敢行する。
恒星から近い距離では禁止されているし、システム的にも不可だった。
なんとか制限内に解除し、重力ジャンプを敢行した。
しかし、禁止されているその理由通りの状況に陥った。
艦隊ごとセットした座標からズレ、恒星から数光年離れた所にジャンプし【ワープのような架空の移動方法】、再び重力ジャンプ可能な所まで移動するのに33年程掛かる。
そんな中忘れ去られた艦隊が33年の月日の後、本星へと帰還を目指す。
果たして彼らは帰還できるのか?
帰還出来たとして彼らに待ち受ける運命は?

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















