20 / 103
出会うはずのない二人
第19話 少年少女
しおりを挟む
「そちらこそ大丈夫ですか? というか今、私の上を飛んでいきましたよね・・・。」
さっきまで抱えていた彼女の悩みが吹き飛ぶほどの衝撃であったが、その直後、更に彼女を困惑させる事態へと陥る。
「良かった、怪我はないようですね、本当に良かっ・・・。」
途中まで言い掛けたところで、彼は力尽きて倒れてしまった。
このときの佳奈は、もう色々な情報が唐突に入って来たことで、軽くパニックであった。
人も車も通る気配のないこの状況、とりあえずこの力尽きた兵士の介護に当たらねばならない、そう佳奈は思った。
陸軍工科学校の恒例行事、山地機動訓練。
本来であれば、この程度の山地であれば、一般的な行進訓練と分類されるところであるが、この学校の訓練では、山地機動中に、対抗部隊が配置され、さながら大人の鬼ごっこ状態で、山地を逃げ回らなければならない。
三枝昭三はこのとき、自身が持つ中途半端な運動能力を恨みながら、横須賀の山の中をひたすら逃げ回っていた。
中途半端というのは、体力の弱い者であれば直ぐに捕まりペナルティーとなり、体力優秀者であれば、完全に逃げ切り、そのまま帰来となるところだが、この中途半端な三枝昭三は、結局どちらにも付かぬまま、広大な横須賀の山林で完全に迷っていたのである。
横須賀の秋空は、その直上が最も濃紺であるが、このときの昭三は林の隙間から見える唯一の秋空を楽しむという気持ちにはなれないでいた。
「ああ、まったくなんて高校ライフなんだろう。中学の同級生達は、きっとクラスメイト(女子)達と楽しくやっているんだろうなあ。やっぱり選択を間違えたかなあ・・」
樹海ほどの深い山ではないため、おそらく付近の畑に助けを求めれば容易に保護してもらえただろう。
しかし、教官には緊急時をのぞき、くれぐれも民間人との接触は避けるよう言いつけられていたのである。
このことが、昭三を山林の深みへと引き込んでしまったのである。
そんな中、急峻な崖の下に目をやると、細いながらも一般道が通っているのが確認できた。
迂回して下まで行くこともできたが、このときの昭三は、早く帰らないと教官に何を言われるか、の方が重要な問題であった。
そして木から木へと腕を伸ばしながら、ゆっくりと崖に近い急な斜面を下へ下り始めたのである。
最初は順調であったが、横着な昭三は、斜面を一気に下れば早いだろうという程度の考えで、斜面を走り出した。
ところがこの林は、道路にたどり着く手前数メートルの高さで石垣に変わり、実際はロープでもないかぎり降りられない構造であった。
昭三がそれに気付いた時には既に遅く、ブレーキをかけたが、装備が重くて思うように止まらない。
そんな時、目の前の道路に、場違いな制服を着た女学生が立っていることに気付くのである。
昭三はとっさに石垣の先端を蹴り上げ、少女を飛び越えようとジャンプした。
この時もまた、教官に言われた民間人との接触は厳禁という言葉が脳裏を過ぎったのである。
確かに物理「接触」はしていないのだが。
それ以降の記憶は、少し混乱しているためか、消えている。
次ぎに目を覚ました、彼の目には美しいおさげ髪の少女の顔が映っていた。
「・・あのう、大丈夫ですか?」
どれくらいの時間が経過したのかは定かではない、彼女は、昭三の頭を自分の膝の上にのせたまま、硬いコンクリートの上で、昭三の意識が戻るまでずっと介抱してくれていたのである。
この時、昭三の目には、彼女が戦場に舞い降りた女神の如く映っていた。
彼女の膝枕越しに見える横須賀の秋空は、先ほどの不快な濃紺とは異なり、どこまでも続く美しい空であった。
それは、手前に見える美しくも儚げな表情を浮かべる佳奈を、一層引き立てていたように感じれる。
もうろうとした意識の中で、いっそこのまま、ずっとこうしていられたらいいのに、と都合の良いことを考えていたが、意識がはっきりするに連れて、忌まわしい現実の記憶も戻ってくるのである。
「あっ、今、今何時ですか?」
「午後2時になる頃ですよ」
彼女は3時間近くも、ずっとっこの状態でいてくれたのである。
しかし現実はもっと悲惨であった。
「・・・大変だ、4時間以上も行方不明になっている。あの、すいません、電話はお持ちですか?」
この時、ようやく佳奈は携帯電話という存在に気付いた。
もっと早く警察に通報するなり、救急車を呼ぶなりしていれば、それほどの大事にはならなかったはずである。
佳奈自身にとっても、傷付いた一人の兵士を介抱するという行為自体、失望感からの軽い逃避となっていた。
しかし、武装した生徒が、4時間も行方知れずという状況は、学校の行事全てを中止して、大規模な山岳救助へ移行している可能性すらあるのだ。
それはこの時代であっても、ニュースになる可能性すらある。
この時、佳奈の携帯電話の存在が、昭三を救う唯一のツールとなっていた。
軍では、僅かな電波発射が居場所を敵に特定されるため、携帯電話端末の所持が行動中は許されていなかったのである。
ところが、
「あれ、おかしいですね、電源が入りません」
佳奈が何度もメインスイッチを押してみるが、反応が無い。このメガネタイプの携帯電話は比較的丈夫に出来ているはずであったが、不運は続いてしまう。
「すいません、ボクは付近の民家にでも連絡を依頼します、あなたはお怪我はありませんか?」
そう言うと佳奈は少しにこやかに
「それ、二回目ですよ」
と上品に笑った。
この時、昭三は二回目という言葉が不思議であった。
初対面なのに、どうして二回目なんてと。
そう、この時の昭三は、着地以降の記憶が飛んでいたため、自分の身体がどのような状況であるか理解出来ていなかったのである。
ゆっくりと立ち上がろうとした次の瞬間、右足に激痛が走った。
「大丈夫ですか?痛みますか?」
これは予想以上にまずい状況であった。
着地の瞬間に、右足が骨折していたのである。
痛みに顔をゆがめる昭三を優しく寄り添う佳奈。
「ちょっと待っていてください、人を呼んできます。」
そう言うと、佳奈は走り出した。
そして一人になる昭三は、頭の中で情報の整理を始めた、が、どうしても彼女の存在が邪魔になり、整理がつかないでいた。
どうしても彼女の美しい顔と、秋空のコントラストが頭から離れず、そして心臓までもがドキドキとする。
まるで骨抜きのようであった。
さっきまで抱えていた彼女の悩みが吹き飛ぶほどの衝撃であったが、その直後、更に彼女を困惑させる事態へと陥る。
「良かった、怪我はないようですね、本当に良かっ・・・。」
途中まで言い掛けたところで、彼は力尽きて倒れてしまった。
このときの佳奈は、もう色々な情報が唐突に入って来たことで、軽くパニックであった。
人も車も通る気配のないこの状況、とりあえずこの力尽きた兵士の介護に当たらねばならない、そう佳奈は思った。
陸軍工科学校の恒例行事、山地機動訓練。
本来であれば、この程度の山地であれば、一般的な行進訓練と分類されるところであるが、この学校の訓練では、山地機動中に、対抗部隊が配置され、さながら大人の鬼ごっこ状態で、山地を逃げ回らなければならない。
三枝昭三はこのとき、自身が持つ中途半端な運動能力を恨みながら、横須賀の山の中をひたすら逃げ回っていた。
中途半端というのは、体力の弱い者であれば直ぐに捕まりペナルティーとなり、体力優秀者であれば、完全に逃げ切り、そのまま帰来となるところだが、この中途半端な三枝昭三は、結局どちらにも付かぬまま、広大な横須賀の山林で完全に迷っていたのである。
横須賀の秋空は、その直上が最も濃紺であるが、このときの昭三は林の隙間から見える唯一の秋空を楽しむという気持ちにはなれないでいた。
「ああ、まったくなんて高校ライフなんだろう。中学の同級生達は、きっとクラスメイト(女子)達と楽しくやっているんだろうなあ。やっぱり選択を間違えたかなあ・・」
樹海ほどの深い山ではないため、おそらく付近の畑に助けを求めれば容易に保護してもらえただろう。
しかし、教官には緊急時をのぞき、くれぐれも民間人との接触は避けるよう言いつけられていたのである。
このことが、昭三を山林の深みへと引き込んでしまったのである。
そんな中、急峻な崖の下に目をやると、細いながらも一般道が通っているのが確認できた。
迂回して下まで行くこともできたが、このときの昭三は、早く帰らないと教官に何を言われるか、の方が重要な問題であった。
そして木から木へと腕を伸ばしながら、ゆっくりと崖に近い急な斜面を下へ下り始めたのである。
最初は順調であったが、横着な昭三は、斜面を一気に下れば早いだろうという程度の考えで、斜面を走り出した。
ところがこの林は、道路にたどり着く手前数メートルの高さで石垣に変わり、実際はロープでもないかぎり降りられない構造であった。
昭三がそれに気付いた時には既に遅く、ブレーキをかけたが、装備が重くて思うように止まらない。
そんな時、目の前の道路に、場違いな制服を着た女学生が立っていることに気付くのである。
昭三はとっさに石垣の先端を蹴り上げ、少女を飛び越えようとジャンプした。
この時もまた、教官に言われた民間人との接触は厳禁という言葉が脳裏を過ぎったのである。
確かに物理「接触」はしていないのだが。
それ以降の記憶は、少し混乱しているためか、消えている。
次ぎに目を覚ました、彼の目には美しいおさげ髪の少女の顔が映っていた。
「・・あのう、大丈夫ですか?」
どれくらいの時間が経過したのかは定かではない、彼女は、昭三の頭を自分の膝の上にのせたまま、硬いコンクリートの上で、昭三の意識が戻るまでずっと介抱してくれていたのである。
この時、昭三の目には、彼女が戦場に舞い降りた女神の如く映っていた。
彼女の膝枕越しに見える横須賀の秋空は、先ほどの不快な濃紺とは異なり、どこまでも続く美しい空であった。
それは、手前に見える美しくも儚げな表情を浮かべる佳奈を、一層引き立てていたように感じれる。
もうろうとした意識の中で、いっそこのまま、ずっとこうしていられたらいいのに、と都合の良いことを考えていたが、意識がはっきりするに連れて、忌まわしい現実の記憶も戻ってくるのである。
「あっ、今、今何時ですか?」
「午後2時になる頃ですよ」
彼女は3時間近くも、ずっとっこの状態でいてくれたのである。
しかし現実はもっと悲惨であった。
「・・・大変だ、4時間以上も行方不明になっている。あの、すいません、電話はお持ちですか?」
この時、ようやく佳奈は携帯電話という存在に気付いた。
もっと早く警察に通報するなり、救急車を呼ぶなりしていれば、それほどの大事にはならなかったはずである。
佳奈自身にとっても、傷付いた一人の兵士を介抱するという行為自体、失望感からの軽い逃避となっていた。
しかし、武装した生徒が、4時間も行方知れずという状況は、学校の行事全てを中止して、大規模な山岳救助へ移行している可能性すらあるのだ。
それはこの時代であっても、ニュースになる可能性すらある。
この時、佳奈の携帯電話の存在が、昭三を救う唯一のツールとなっていた。
軍では、僅かな電波発射が居場所を敵に特定されるため、携帯電話端末の所持が行動中は許されていなかったのである。
ところが、
「あれ、おかしいですね、電源が入りません」
佳奈が何度もメインスイッチを押してみるが、反応が無い。このメガネタイプの携帯電話は比較的丈夫に出来ているはずであったが、不運は続いてしまう。
「すいません、ボクは付近の民家にでも連絡を依頼します、あなたはお怪我はありませんか?」
そう言うと佳奈は少しにこやかに
「それ、二回目ですよ」
と上品に笑った。
この時、昭三は二回目という言葉が不思議であった。
初対面なのに、どうして二回目なんてと。
そう、この時の昭三は、着地以降の記憶が飛んでいたため、自分の身体がどのような状況であるか理解出来ていなかったのである。
ゆっくりと立ち上がろうとした次の瞬間、右足に激痛が走った。
「大丈夫ですか?痛みますか?」
これは予想以上にまずい状況であった。
着地の瞬間に、右足が骨折していたのである。
痛みに顔をゆがめる昭三を優しく寄り添う佳奈。
「ちょっと待っていてください、人を呼んできます。」
そう言うと、佳奈は走り出した。
そして一人になる昭三は、頭の中で情報の整理を始めた、が、どうしても彼女の存在が邪魔になり、整理がつかないでいた。
どうしても彼女の美しい顔と、秋空のコントラストが頭から離れず、そして心臓までもがドキドキとする。
まるで骨抜きのようであった。
0
お気に入りに追加
9
あなたにおすすめの小説
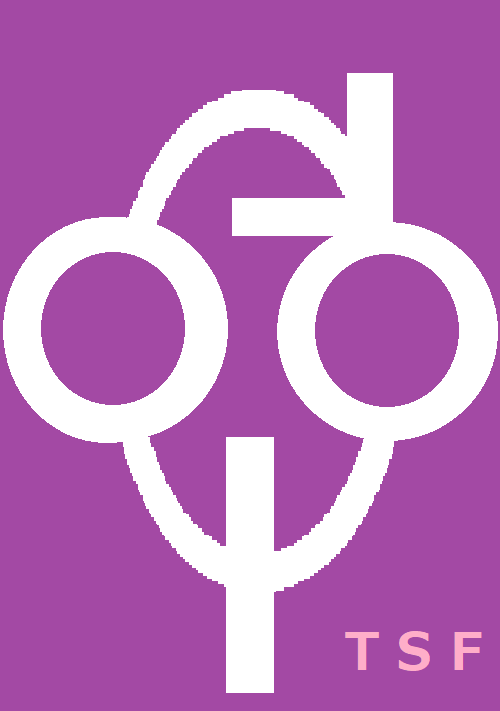

女子高生は卒業間近の先輩に告白する。全裸で。
矢木羽研
恋愛
図書委員の女子高生(小柄ちっぱい眼鏡)が、卒業間近の先輩男子に告白します。全裸で。
女の子が裸になるだけの話。それ以上の行為はありません。
取って付けたようなバレンタインネタあり。
カクヨムでも同内容で公開しています。

お兄ちゃんは今日からいもうと!
沼米 さくら
ライト文芸
大倉京介、十八歳、高卒。女子小学生始めました。
親の再婚で新しくできた妹。けれど、彼女のせいで僕は、体はそのまま、他者から「女子小学生」と認識されるようになってしまった。
トイレに行けないからおもらししちゃったり、おむつをさせられたり、友達を作ったり。
身の回りで少しずつ不可思議な出来事が巻き起こっていくなか、僕は少女に染まっていく。
果たして男に戻る日はやってくるのだろうか。
強制女児女装万歳。
毎週木曜と日曜更新です。


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。


忘却の艦隊
KeyBow
SF
新設された超弩級砲艦を旗艦とし新造艦と老朽艦の入れ替え任務に就いていたが、駐留基地に入るには数が多く、月の1つにて物資と人員の入れ替えを行っていた。
大型輸送艦は工作艦を兼ねた。
総勢250艦の航宙艦は退役艦が110艦、入れ替え用が同数。
残り30艦は増強に伴い新規配備される艦だった。
輸送任務の最先任士官は大佐。
新造砲艦の設計にも関わり、旗艦の引き渡しのついでに他の艦の指揮も執り行っていた。
本来艦隊の指揮は少将以上だが、輸送任務の為、設計に関わった大佐が任命された。
他に星系防衛の指揮官として少将と、退役間近の大将とその副官や副長が視察の為便乗していた。
公安に近い監査だった。
しかし、この2名とその側近はこの艦隊及び駐留艦隊の指揮系統から外れている。
そんな人員の載せ替えが半分ほど行われた時に中緊急警報が鳴り、ライナン星系第3惑星より緊急の救援要請が入る。
機転を利かせ砲艦で敵の大半を仕留めるも、苦し紛れに敵は主系列星を人口ブラックホールにしてしまった。
完全にブラックホールに成長し、その重力から逃れられないようになるまで数分しか猶予が無かった。
意図しない戦闘の影響から士気はだだ下がり。そのブラックホールから逃れる為、禁止されている重力ジャンプを敢行する。
恒星から近い距離では禁止されているし、システム的にも不可だった。
なんとか制限内に解除し、重力ジャンプを敢行した。
しかし、禁止されているその理由通りの状況に陥った。
艦隊ごとセットした座標からズレ、恒星から数光年離れた所にジャンプし【ワープのような架空の移動方法】、再び重力ジャンプ可能な所まで移動するのに33年程掛かる。
そんな中忘れ去られた艦隊が33年の月日の後、本星へと帰還を目指す。
果たして彼らは帰還できるのか?
帰還出来たとして彼らに待ち受ける運命は?

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















