1 / 1
CUERDA 弦
しおりを挟む ルークは里に戻ると、クロエをそのまま叔父の家に連れて行った。クロエがこのあとも里に残るのであれば、他の者にもそう伝えなければならない。とりあえず、一番身近な叔父一家に伝えておくべきだと考えた。ノックして扉を開けると、食卓を囲んでいた叔父一家は二人を見て、驚いた声をあげた。
「ルーク? その子は」
「クロエだ。森にいた」
ブルーノの問いにルークは簡単に答えた。それだけで回答としては十分だった。誰かを連れてくるとしたら、それは番ということだ。ルークはクロエを椅子におろしながら言った。
「叔父のブルーノと、その番のリーシャ。あと、娘のレナと息子のティム」
リーシャは呆れた様な声を出した。
「最近こちらに来ないと思ったら、どうして早く私たちに会わせてくれなかったの。それに服も……、これあなたのよね。私のをあげるからきちんとしたのを着せてあげなさいよ」
にっこりと微笑みながらクロエの顔を覗きこむ。
「よろしくね」
クロエは「よろしくお願いしま」と途中まで声を出しかけて、息を飲んだ。
目の前で微笑む一回り程年上だと思われる彼女の顔は、右半分は痘痕で覆われていて、腫れたまぶたが右目を隠していたからだ。
「ああ――あなたも『外』から来たのだものね。驚くわよね」
リーシャは顔の右側に手を当てると、視線を落とした。番の心に浮かんだ波を察知したブルーノは彼女の肩に手を回し、抱き寄せた。状況を把握していないルークは視線を泳がし、首を傾げる。
「ごめんなさい……」
口ごもるクロエに、リーシャは再び視線を上げて微笑んだ。
「いいのよ」
それからクロエの首元に顔を近づけると不思議そうな顔をした。
「――あら、『証』はまだなのね」
「『証』?」
「番の、証」
リーシャは自分の首元を見せた。そこには噛み跡のような赤い痣があった。
「――クロエは怪我がまだ治っていないから。そういうのは彼女の足が良くなってから、とりあえず、二人には紹介しておこうと思って」
ルークが間に入る。
「番って」
クロエは呟いた。
(妻のことって言ってたわよね。その証ってなんのこと)
状況が理解できなかったが、自分がその言葉を快く感じていることに気がついて、顔を両手で押さえた。顔が熱い気がする。クロエの反応にブルーノとリーシャは怪訝な顔をする。
一瞬沈黙が流れる。椅子に座ってじっと大人のやりとりを見ていた姪っ子が「ご飯食べようよ!」とスプーンで卓上の器を叩いたのでクロエは噴き出した。ルークも笑った。
「食事一緒にいい?」
「冷めちゃうものね。着替えはご飯を食べてからね」
リーシャは慌てて竈へ向かうと、湯気が立った鍋を運んできた。リーシャ、娘、クロエの前にはスープとふかした芋が並べられる。ブルーノは立ち上がると奥に行き、肉の塊を抱えてくると半分に裂き、ルークの前にどんと置いた。
「寝かしといたこの前の熊だ。まあ、とにかく祝いだな。酒も出すか」
ルークは苦笑した。
「そういうのは、きちんと今度でいいよ」
「そうか?」
ブルーノは、まだ小さい息子を膝に乗せると、肉を千切ってその小さい赤茶の狼の口元に運んだ。クロエはその子どもを見て目を瞬いた。
「かわいい。その子は赤毛なのね」
ルークとブルーノは銀色の毛並みだ。リーシャは顔を綻ばせると娘の赤毛の頭を撫でた。
「子どもたちは私似ね」
子狼は口元に運ばれる肉をがじがじとかじると、喉奥から「もっとー」と声を漏らした。口元には白い小さい牙が見える。姪の少女はクロエの隣に座ると興味深々といった風に聞いてきた。
「おねえさんは外から来たの?お母さんと一緒?」
「そうね。外から」
「外はどんなところ?」
「――大きな家に住んでいたわ」
「どのくらい?」
「このお部屋が100くらいはあるかしら」
「ひゃく」
少女は指を律義に10回折ると、目を広げた。
「すごーい」
クロエはくすりと笑った。誰と温かい食事を囲むのはいつぶりだろうか。
食事が終わると、クロエは奥の部屋に運ばれた。リーシャがルークを外に追い払うと、麻でできたドレスを持ったきた。袖と襟元に刺繍がされている。
「私のだけど、いいかしら」
「ありがとうございます」
ルークの上衣をワンピースのように着ていたので、きちんとしたものを着れるのは有難かった。ルークに見せると、彼は「いいんじゃないか」と頷いた。
「ここの人たちは、あんまり衣装を気にしないのよね」
リーシャはふふ、と笑った。
***
ルークはクロエを背負って家に戻った。その道すがら聞いてみる。
「ねえ、番の証って、」
「番になるとき、首に噛み跡を残すんだ。――ここにいるのは、俺たちとその番と、その子どもだけだ。子どもも皆将来のだれかの番で――だから、ここに住むなら、俺の番ってことにしないと――」
(『番ってことにしないと』ってのはおかしいよな)とルークは言いながら唸った。番ははじめから決まっている相手、する・しないではないはずだ。
「噛む」
クロエは思わず背中から、自分を背負う狼の口元を見た。牙が光る。
「――嫌なら、別にしなくても」
「嫌じゃないわ」
「え」
「――嫌じゃないわ」
目の前の灰色の毛に顔を押し付けた。
「ルーク? その子は」
「クロエだ。森にいた」
ブルーノの問いにルークは簡単に答えた。それだけで回答としては十分だった。誰かを連れてくるとしたら、それは番ということだ。ルークはクロエを椅子におろしながら言った。
「叔父のブルーノと、その番のリーシャ。あと、娘のレナと息子のティム」
リーシャは呆れた様な声を出した。
「最近こちらに来ないと思ったら、どうして早く私たちに会わせてくれなかったの。それに服も……、これあなたのよね。私のをあげるからきちんとしたのを着せてあげなさいよ」
にっこりと微笑みながらクロエの顔を覗きこむ。
「よろしくね」
クロエは「よろしくお願いしま」と途中まで声を出しかけて、息を飲んだ。
目の前で微笑む一回り程年上だと思われる彼女の顔は、右半分は痘痕で覆われていて、腫れたまぶたが右目を隠していたからだ。
「ああ――あなたも『外』から来たのだものね。驚くわよね」
リーシャは顔の右側に手を当てると、視線を落とした。番の心に浮かんだ波を察知したブルーノは彼女の肩に手を回し、抱き寄せた。状況を把握していないルークは視線を泳がし、首を傾げる。
「ごめんなさい……」
口ごもるクロエに、リーシャは再び視線を上げて微笑んだ。
「いいのよ」
それからクロエの首元に顔を近づけると不思議そうな顔をした。
「――あら、『証』はまだなのね」
「『証』?」
「番の、証」
リーシャは自分の首元を見せた。そこには噛み跡のような赤い痣があった。
「――クロエは怪我がまだ治っていないから。そういうのは彼女の足が良くなってから、とりあえず、二人には紹介しておこうと思って」
ルークが間に入る。
「番って」
クロエは呟いた。
(妻のことって言ってたわよね。その証ってなんのこと)
状況が理解できなかったが、自分がその言葉を快く感じていることに気がついて、顔を両手で押さえた。顔が熱い気がする。クロエの反応にブルーノとリーシャは怪訝な顔をする。
一瞬沈黙が流れる。椅子に座ってじっと大人のやりとりを見ていた姪っ子が「ご飯食べようよ!」とスプーンで卓上の器を叩いたのでクロエは噴き出した。ルークも笑った。
「食事一緒にいい?」
「冷めちゃうものね。着替えはご飯を食べてからね」
リーシャは慌てて竈へ向かうと、湯気が立った鍋を運んできた。リーシャ、娘、クロエの前にはスープとふかした芋が並べられる。ブルーノは立ち上がると奥に行き、肉の塊を抱えてくると半分に裂き、ルークの前にどんと置いた。
「寝かしといたこの前の熊だ。まあ、とにかく祝いだな。酒も出すか」
ルークは苦笑した。
「そういうのは、きちんと今度でいいよ」
「そうか?」
ブルーノは、まだ小さい息子を膝に乗せると、肉を千切ってその小さい赤茶の狼の口元に運んだ。クロエはその子どもを見て目を瞬いた。
「かわいい。その子は赤毛なのね」
ルークとブルーノは銀色の毛並みだ。リーシャは顔を綻ばせると娘の赤毛の頭を撫でた。
「子どもたちは私似ね」
子狼は口元に運ばれる肉をがじがじとかじると、喉奥から「もっとー」と声を漏らした。口元には白い小さい牙が見える。姪の少女はクロエの隣に座ると興味深々といった風に聞いてきた。
「おねえさんは外から来たの?お母さんと一緒?」
「そうね。外から」
「外はどんなところ?」
「――大きな家に住んでいたわ」
「どのくらい?」
「このお部屋が100くらいはあるかしら」
「ひゃく」
少女は指を律義に10回折ると、目を広げた。
「すごーい」
クロエはくすりと笑った。誰と温かい食事を囲むのはいつぶりだろうか。
食事が終わると、クロエは奥の部屋に運ばれた。リーシャがルークを外に追い払うと、麻でできたドレスを持ったきた。袖と襟元に刺繍がされている。
「私のだけど、いいかしら」
「ありがとうございます」
ルークの上衣をワンピースのように着ていたので、きちんとしたものを着れるのは有難かった。ルークに見せると、彼は「いいんじゃないか」と頷いた。
「ここの人たちは、あんまり衣装を気にしないのよね」
リーシャはふふ、と笑った。
***
ルークはクロエを背負って家に戻った。その道すがら聞いてみる。
「ねえ、番の証って、」
「番になるとき、首に噛み跡を残すんだ。――ここにいるのは、俺たちとその番と、その子どもだけだ。子どもも皆将来のだれかの番で――だから、ここに住むなら、俺の番ってことにしないと――」
(『番ってことにしないと』ってのはおかしいよな)とルークは言いながら唸った。番ははじめから決まっている相手、する・しないではないはずだ。
「噛む」
クロエは思わず背中から、自分を背負う狼の口元を見た。牙が光る。
「――嫌なら、別にしなくても」
「嫌じゃないわ」
「え」
「――嫌じゃないわ」
目の前の灰色の毛に顔を押し付けた。
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説



ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。


人生を共にしてほしい、そう言った最愛の人は不倫をしました。
松茸
恋愛
どうか僕と人生を共にしてほしい。
そう言われてのぼせ上った私は、侯爵令息の彼との結婚に踏み切る。
しかし結婚して一年、彼は私を愛さず、別の女性と不倫をした。
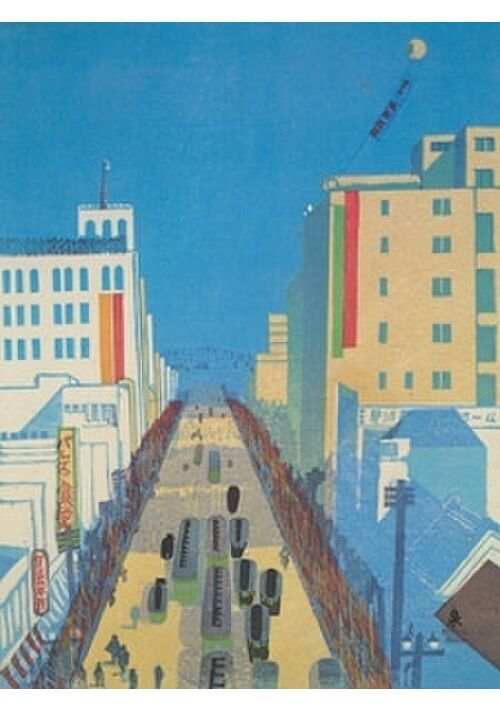
もんもんと汗
ふしきの
大衆娯楽
小町(こまちちょう)は、とても小さい町ですが、繊維工場があるため、昼夜問わず町には人がいます。女工さんもたくさん暮らしています。町には大通りが少なく、袋小路の道ばかりです。古くてエキセントリックな町ですが、駅もバスも通っています。

愛のゆくえ【完結】
春の小径
恋愛
私、あなたが好きでした
ですが、告白した私にあなたは言いました
「妹にしか思えない」
私は幼馴染みと婚約しました
それなのに、あなたはなぜ今になって私にプロポーズするのですか?
☆12時30分より1時間更新
(6月1日0時30分 完結)
こう言う話はサクッと完結してから読みたいですよね?
……違う?
とりあえず13日後ではなく13時間で完結させてみました。
他社でも公開

2度目の声優人生に突入いたします!
越路遼介
大衆娯楽
「おぬしのせいで妾は三流の悪者で終わってしまった!」と、かつて『魔法のお姫様☆ロゼアンナ』と云う魔女っ娘アニメで自分が演じた高飛車お嬢様キャサリンと死後不思議な空間で出会うアラフォー声優の村上真理子。当時は新人で役を演じきることが出来なかった。「今なら演じられる!」と言えば「なら見せてみろ」と、真理子は再び20歳からやり直し。中身は40歳。大逆転なるか。
※筆者の他作品にもある元消防士キャラ出てきます。あんまり物語に影響はないのですけどね。好きなんで、この設定。
全10話くらいの短い小説です。1話1話もそんなに長くはありません。よろしければご覧下さい。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















