151 / 210
五の段 顔 あやめのいる家(四)
しおりを挟む「おやかたさまを裏切らないでほしい。あのお方を、悲しませるな。」
「……途方もござりませぬ。」
あやめは乾いた咽喉を開いて、それだけをいう。
「そうか? ならばよいが……」
「お方さま。あやめは、いまはおやかたさまを……お慕いしておりまする。好きでたまらぬおやかたさまのおためにならぬ真似は、決していたしませぬ。」
「よくぞ申してくれた。」
「申し訳ございませぬ。お仕えする身の立場を忘れて、お方さまのお言葉に甘え、お慕いだの好きだのと分を過ぎた言葉を口走りました。されど、お許しください、嘘偽りのない、手前の気持ちでございます。」
「あやめ、今とて、わらわはうれしく思うた。あのお方は、さびしいひとだ。」
「……たしかに左様に存じます。」
「小さい時から他国で育った。津軽の浪岡御所。そこで何があったのかは、わらわにさえあまり教えて下さらぬ。だが、浪岡御所が今は滅んでしまったのは知っておるから、思い当たることはある。」
南北朝期の北畠顕家の流れを汲む奥州で最も高貴な家系であった浪岡北畠氏は、内紛の果てに急速に衰弱し、津軽統一を狙った大浦(津軽)氏に滅ぼされた。その居城であった浪岡城は正式に「御所」名乗りを許されてさえいたが、先年の落城後はごく一部を残すのみだという。新三郎は、天才丸と名乗った元服前から、その城に出仕していたのだ。
「浪岡では、色々なことがあったらしい。その後は。秋田か。こわいお方に侍に仕上げられたようじゃ。長じては後嗣ぎとして、名代として、いつも大舘で、たったひとりだった。大舘のどなたも頼られぬ。」
「おやかたさましか、お見えでないものが多いのでございましょう。」
政事はむろん、戦についてにせよ、蝦夷島のあるべき姿の考えにせよ、新三郎だけが抜きんでた考えを持つ。十四郎だけが、おそらく軍事でだけは拮抗できる存在なのだろう。
「そうよの。きっと、わらわたち女どもの中でしか、あのおさびしさは癒えぬのだろう。だがあやめ、そちだけは、あのお方しか考えられぬものを、ともに考えて差し上げられるようだ。どうか、おやかたさまから離れないでくれ。」
「はい。」
「すまぬな。」
「いえ、わたくしも、離れとうございませぬ。おやかたさまからも、お方さまからも、離れませぬ。……もしも、ひと時のお別れがあったとしても、必ず、お傍に戻って参ります。その時は、どうかお許しのうえ、また置いてやってくださいませ。」
「こちらからお伝えはせぬが、喜ばれるだろう。それを思うと、また、うれしい。あやめ、礼をいいます。」
「そんな。」
「そちの為にも、やはりよいことだと思う。」
「はい。」
「どこかに行っている間に、十四郎殿が蠣崎に戻ってこれるようにしたいのだな?」
「はい。左様にございます。願うばかりではなく、なんとか微力を尽くしたいと存じます。」
「あやめ、それでもおやかたさまと……どのような形になるのかは、わからぬが、一緒にいてくれような?」
「お方さま、もしそのようになれましたら、……なれましても、わたくしは、一体、……一体、どうすればいいのでしょう? そうなるように心より祈っておりますが、そのあとが、いくら考えても、見えませぬ。」
あやめは声が震えるのを感じた。もしもすべて今のあやめの願う通りにいったとしても、それからどうすればいいのか。本来なら、あやめの「図」の通りに進めば、迷うことなどなかったのだ。いま、新三郎に愛をおぼえてしまったあやめは、その結果にはとても耐えられない。だから新三郎の決断を祈っているが、では首尾よくそうなってから後、いったい自分はどうすればいいのか。
(いっそ堺に帰ってしまうか。十四郎さま、おやかたさま。お二人の前から消えてしまうのが一番よいのか。)
そう考えたとき、胸が文字通り締め付けられた。とても生きていられないと思った。では、どうする?
「見えぬな。つらいな。……だが、気に病むことはないのだ。唐高麗の、孔子様のお教えに厳しい方々からみれば、従兄妹でも婚姻するわらわらは、家の長幼の序を乱して平気な、禽獣のようだという。お家の都合で、死んだ兄弟の遺した妻を娶る例も少なくないが、一度は義理の姉や妹となった者を妻にするわけだから、これもけしからぬ所業かな。だが、天下六十余州ではそれで通るではないか。弟と兄とに心通じたとて、それは恥じることでも、後ろ指差されることでもない。堂々としておればよい。」
(そういうことばかりでも、ないのでございますが……)
「ありがとうございまする。お方さまのお心、身に染みてなりませぬ。ところがあやめは馬鹿でございますので、ついお尋ねしてしまいまする。御不快に存じましたら、どうかお叱りくださいませ。」
「遠慮はいらぬ。二人だけじゃ。」
「ああは、いってくださいましたが、お二人の室をおつとめするのは、とてもできませぬね?」
「同時に?……そち、それは、二夫にまみえずとはいうわな?」
「なぜ、女ばかりがそうなのでございましょう? おやかたさまは、……とは申しませぬが、世の殿様方はたいてい、ご正妻とご側室をお持ちです。それぞれにお好き、お情けをかけられる、で許される。ところが、女がそれをやれば、世の誹りを免れませぬ。しかしこれは、お方さま、理不尽ではございませぬか? もし万が一そんな真似をすれば、お方さまもあやめをお叱りでございましょうか?」
大真面目にいうあやめの顔を呆気にとられてみていた北の方は、しばらく難しい顔をつくったが、ついに噴き出した。
「あやめ、そちは、そちは、……」体を折って笑う。「それを、悩んでおるのか?」
「はい。あやめは世の指弾はすこしもおそれませぬが、お方さまに嫌われるのは厭にございますれば。あ、おやかたさまと、……あのお方が、お許しにならなければ、もとよりかなわぬことにて」
北の方はついに悲鳴のような声を立てて、突っ伏した。涙をこぼして、大笑いしている。
「あやめ、あやめ、そちの望みはそれか?……いや、嘘偽りなく申しておるのじゃろうが、……いまはそうしたいのも、やまやまじゃろうか、……まめざまに(まじめな様子で)そんなことを申して、……」
老女が時ならぬお方さまの笑い声をききつけて、様子をうかがいに戻ってきた。
「お方さま、堺殿がなにをいわれたので?」
「いや、仔細あらぬ。まだ、よい。まだ少し、ふたりで話したい。」
お方さまは笑い涙を浮かべて、老女を下がらせた。
「お方さま、お笑いとは慮外でございました。手前はお考えをまことにお尋ねしたく」
「あやめ、もうよい。わかった。」これ以上、笑わせないでくれ、とお方さまは手を振った。
「そちは、変わった女ごよのう。まことに、……手放したくないわ。」
「はあ。」
「あやめ、笑って……」お方さまはなにを思い出したのか、また笑いかけたが、「……す、すまなんだが、そちの気持ちは決して笑っておらんぞ。お二人ともに好きだというのだ。悩めば、辛い悩みぞ。」
「あやめは、お二人に心引き裂かれた、我が身の罪深さが苦しくて……」
「左様よな。であるから、教えてやろう。……悩むな。詮無いことじゃ。」
「……そうはおっしゃられますが。」
「いま悩んでも仕方あるまいし、もしそうなれば、うれしい悩みではないのか。十四郎殿が蝦夷地で死んでいれば、悩むことはなかったな?」
「あっ。」
(逆も、そうだ。もしおやかたさまが亡くなられれば、……)
「そちは、ここに召された頃よりもずっと、あかるい望みを抱けるようになったのだ。苦しいのも、悩むのも、それがゆえではないか。よかったではないか。」
「左様に考えまする。」
「そちが、うれしく悩むようになればよい。そうなったら、ふたりで考えよう。そちが側室をもちたいといっても、」お方さまはまた噴き出しそうになったが、堪えて、「わらわは、叱らぬよ。」
「ありがとうございまする。ご相談いたしてよろしいのでしょうか。」
「礼をいうのは早すぎるではないか!」
お方さまはまた笑い崩れかけたが、
「ただ、そちの評判が悪くなるのは心配じゃ。」
「堺は、なにやら町の方に悪名がたっているとかで。」
「噂であろう? 気にするな。ただ、わからんのう。そちをよく知らぬ者が増えたのかの? まあ、そちは今のようなことを、平気でいうのが、……」
お方さまは思いだして、また笑いがこみあげてきたらしい。
「のう、囲うのは、やはりおやかたさまのほうか?」
お方さまは自分でいって、夫のどんな姿を思い描いたのか、耐えきれずに腹をかかえた。あやめは、何がそれほどおかしいのか訝しく、ややしょげたようになる。
「……わたくしの申しましたのは、やはり淫婦姦婦のいいざまでございましょうか。」
北の方はまた弾けるように笑った。あやめ、むごいの、笑わせるなと申したのに、というが、あやめの表情に笑いを慌てて抑える。息を鎮め、
「どちらの方とどうなるかは知らぬが、やはりこっそりと、にはなりそうじゃな? 世間はともあれ、肝心のお二人には誤魔化せまいから、おわかりをいただくしかないが、さて、あの業の深いご兄弟が、それで譲られるかな?」
「左様でございますねえ。」
「あなた様方は、そうなさっているではないか、といっておやり。そうだ、わらわも加勢して、いうてやろう。」
「あ、御曹司さまはまだ、お浮気を一度だけのようで。」
お方さまは笑いをこらえるのに懸命だ。それをみて、あやめもついに笑い出した。
「……ああ、今日は笑うた、笑うた。あやめ、そちはやはり、面白いのう。」
「左様でございますか。」
「よい子じゃのう。」
「はあ。ありがとうございます。」
「あやめがいてくれれば、蠣崎のお家も、楽しくなりそうだ。……早く十四郎殿も帰り、左様な楽しいばかりの日がくるといいのう?」
お方さまの目に涙が光っている。あやめも目が潤んでならないのだが、それをまた見咎められないように、低頭した。
0
お気に入りに追加
8
あなたにおすすめの小説

夢の雫~保元・平治異聞~
橘 ゆず
歴史・時代
平安時代末期。
源氏の御曹司、源義朝の乳母子、鎌田正清のもとに13才で嫁ぐことになった佳穂(かほ)。
一回りも年上の夫の、結婚後次々とあらわになった女性関係にヤキモチをやいたり、源氏の家の絶えることのない親子、兄弟の争いに巻き込まれたり……。
悩みは尽きないものの大好きな夫の側で暮らす幸せな日々。
しかし、時代は動乱の時代。
「保元」「平治」──時代を大きく動かす二つの乱に佳穂の日常も否応なく巻き込まれていく。

幕府海軍戦艦大和
みらいつりびと
歴史・時代
IF歴史SF短編です。全3話。
ときに西暦1853年、江戸湾にぽんぽんぽんと蒸気機関を響かせて黒船が来航したが、徳川幕府はそんなものへっちゃらだった。征夷大将軍徳川家定は余裕綽々としていた。
「大和に迎撃させよ!」と命令した。
戦艦大和が横須賀基地から出撃し、46センチ三連装砲を黒船に向けた……。
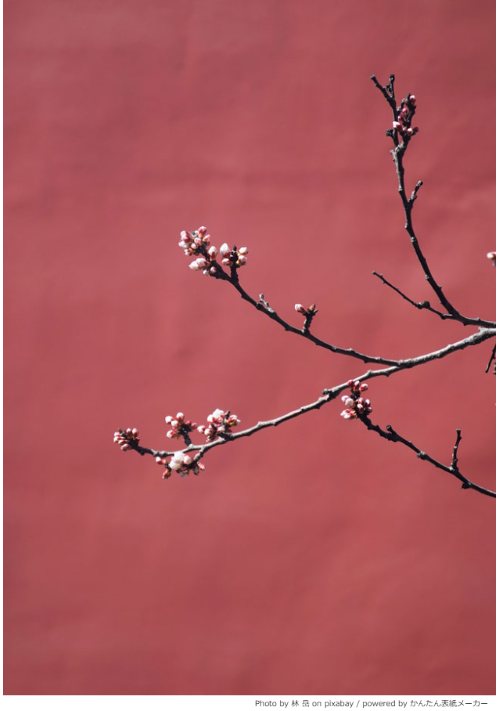
茜さす
横山美香
歴史・時代
【第一部】
願ったのは共に生きる未来。――ただそれだけだった。
戦乱の世が終わって数十年。大平の世の片隅の小藩で、本領と飛び地領との間の壮絶な跡目争いが繰り広げられていた。
生家が困窮し飛び地領に売られた隠密・樋口雅勝と、滅びゆく忍び里の娘・るいは惹かれ合い、共に生きたいと願うようになる。
しかし二人のささやかな願いもまた、お家をめぐる争いの中に飲み込まれて行く運命だった。
二十歳まで生きられない定めを負った隠密と、滅びゆく忍び里の娘のかなわなかった夢と恋の物語。
【第二部】
誰も幸せになれなかった藩主交代劇から三年。
清水忠雅は元許嫁・菊松尼との絆だけを支えに、友を死なせてしまった苦悩と悔恨の日々を生きていた。
そんな忠雅の前にある日、死んだはずの友とよく似た刺客があらわれる。
――この世の仕組みが間違っているのなら、仕組みそのものを変えてやる。
敵方として現れた男は、かつて同じ夢を見た友と同一人物なのか。
雅勝とるい、忠雅と菊乃の恋の行末は。そして長きに渡る藩の権力争いは終わるのか。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

妻がエロくて死にそうです
菅野鵜野
大衆娯楽
うだつの上がらないサラリーマンの士郎。だが、一つだけ自慢がある。
美しい妻、美佐子だ。同じ会社の上司にして、できる女で、日本人離れしたプロポーションを持つ。
こんな素敵な人が自分のようなフツーの男を選んだのには訳がある。
それは……
限度を知らない性欲モンスターを妻に持つ男の日常

藤散華
水城真以
歴史・時代
――藤と梅の下に埋められた、禁忌と、恋と、呪い。
時は平安――左大臣の一の姫・彰子は、父・道長の命令で今上帝の女御となる。顔も知らない夫となった人に焦がれる彰子だが、既に帝には、定子という最愛の妃がいた。
やがて年月は過ぎ、定子の夭折により、帝と彰子の距離は必然的に近づいたように見えたが、彰子は新たな中宮となって数年が経っても懐妊の兆しはなかった。焦燥に駆られた左大臣に、妖しの影が忍び寄る。
非凡な運命に絡め取られた少女の命運は。

生まれて旅して恋して死ぬ、それが殿様の仕事です
三矢由巳
歴史・時代
九州の小藩藩主山置隆礼(たかゆき)と江戸の正室祝(のり)姫、国の側室満津(みつ)の方の三人を中心とする人々の物語。舞台となるのは、元禄から安永までの八十年余り。災害、火事、飢饉、謀反等、様々な事件に翻弄されながら人々は生きる。
別サイトで「わたくしたちのお殿様」として掲載していた作品のR15改訂版。
表紙の三つ違い山形紋はフリー素材サイト発光大王堂の家紋素材です。

運命の麗しき皇妃たち・皇帝に愛された妃~薔薇のような美貌の皇妃 エーメとジョゼフーヌ~~【フランス皇帝ナポレオンとオスマン帝国の帝の妻】
のの(まゆたん)
歴史・時代
フランス革命前の事 占い師は二人の従妹同士の少女達を見て言った。
「二人とも皇妃になる」・一人はナポレオン・ボナパルト皇帝の皇妃ジョゼフィーヌ
・もう一人はオスマン帝国の皇帝、その妃として献上されたエーメ・デュ・ビュク・ド・リヴェリ
後のナクシディル皇妃 次期皇帝の母
※塩野先生のイタリア異聞、ネット等より
伝承、異説等含みます
※他サイトあります
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















