48 / 210
一の段 あやめも知らぬ 北へ(二)
しおりを挟む
蝦夷代官名代、蠣崎新三郎慶広が、供回り三名を連れて騎馬姿でやってきた。
「十四郎。大儀。皆、大儀である。」
「……ご名代様のお越しとは。」
十四郎はにわかに緊張した。見送りに来てくれた、とはさすがに思えぬ。
新三郎は剣技にすぐれている。まさか、この場で手ずから斬るつもりか。さらに、供回り三名。
(これは、数が合わぬな。)
十四郎のひそかな計算はたたない。
(森川がもしも加勢してくれても、斬りぬけるのはかなり面倒だ。……こんなところで、か。)
乱闘から脱出して西へ奔るとしても、納屋の人びとを巻き込みたくない。
と、森川が、刀の柄に手をかけるのがみえた。
(よせ。)
そのとき十四郎は、萩原、安部までもが、同じように利き腕に力をこめているのをみた。
(たまらぬな、六人、いや七人で滅多切りにするつもりか。)
と舌打ちした。
が、肝心の新三郎らが臨戦態勢に入っていない。むしろ、こちら―であろう―のぴりぴりとした緊張具合にあっけにとられたようになり、たじろいている。もし斬りつけてくれば十四郎を守る姿勢を三人が瞬時に見せたのに、驚いた様子だ。
三人が前に進み、十四郎が斬りつけられれば、即座に応じる構えになった。
(こやつらめ。)
十四郎は驚きつつもうれしくなったが、どうやら相手方も、ここで事を起こす気は最初からないらしい。
「十四郎。中途まで、送ってやる。」
供回りに下がらせ、新三郎は十四郎に馬に乗れ、と命じた。狭い道を、ふたりが馬頭をぴったりと並べて進む形になる。
新三郎は、この弟の得体のしれなさにあらためて触れ、ひそかに身震いする思いがした。
三人には、十四郎をどこかで斬り捨てる機会があれば、迷わずそうせよと命じておいた。
(どこかで、斬りあいが起きるだろう。それで片が付く。)
ただし、松前武士として、闇討ちは許さないといい添えた。万が一、卑怯な手を使って蠣崎家の者の首をとったことがわかれば、恩賞どころではないぞ、と固く肝に銘じさせたのだ。大舘の命でお命を頂戴する、と正々堂々宣言したうえで首をとれ、それ以外は許さぬ、といわれ、三人の侍は、困った顔になっていた。
部屋住みの「厄介者」ばかりで皆、恩賞には飢えているが、大した能も度胸もない。下手に手を出せば、なんといっても代官家の連枝として武技の訓練を積んだ十四郎が、まとめて斬って捨てることもありうる。
(だが、斬ってしまえば、十四郎のやつはもう二度と松前に戻れぬ。ひとりではポモールとやらの村にも、とても行けまい。それでよい。)
森川たちは捨て駒のようなものだ。運がよければ、一人二人でも松前に逃げ帰って、十四郎の非を鳴らすのが役目だ。その程度の連中で、使い捨てるつもりであった。
ところが、新三郎の思惑はすでに外れていた。
(そんな奴らを十四郎は、この短期間で手なずけ、大舘に逆らって剣を抜かんまでにしてしまうとは。)
(納屋の連中の手引きか? そうではあるまい。金だけで、ああいう真似はせぬ。できぬ。)
(何者なのだ、この弟は?)
「十四郎。おぬしをこの役にあてたとき、南条がかようにいうた。虎に翼をつけて野に放つ、の故事をお忘れかと。」
南条というのは、累代の重役の老臣である。十四郎ととくに近いわけでもなかったはずだが、なにかをこの異相の若者に感じていたらしい。
「兄上。縁起でもござらぬ。壬申の乱のお話ではござらぬか。拙者が大海人皇子様とは、幾重にも畏れ多いにもほどがありまする。……何度も誓って申しますが、拙者には、いや……」十四郎は唇を噛んだ。「お許しありたい。申し上げまする。与三郎兄上にも、大それたつもりは毛頭なかったのだ。兄上方にお考えの違いはござったろう。拙者の振る舞いに、勝手や軽率のそしりは免れぬやもしれぬ。だが、あのような誣告を取りあげられてのお裁きは、ご名代さまにあるまじきものでござった。」
「いまの言葉だけで首を刎ねてもよいのだぞ。」
「いかがなさいますか。」
「……愚か者め。いまは一対四ではないか。」
「さすがは兄上。」
「与三郎は、死なずともよかったのだ。あれが勝手に腹を切った。」
「何をおっしゃるか?」
「なんのために、与三郎は勝手に腹を切ったのか、考えてみよ。」
「……まさか。」
「そうだ、おぬしの身代わりのつもりであったろうな。二人生きていれば、腹を切らされるのはおぬしのほうだったろう。……大舘は、役に立つ方を残す。」
「わたしの、身代わり? 役に立つ方?」
(わからんのか。まあ、わからぬでよい。)
新三郎は何か考えたが、苦く笑って、言葉を継いだ。
「あれは、儂がおぬしを殺したいといつも思っているのを、知っていたのだ。」
「……!」
「十四郎。二度と松前の土を踏むな。北の地でもどこでも、いかようにも暮らし、いかようにも果てるがよい。誰となにをしようと、間違いさえなければ、いっこうに構わぬ。だが、もし戻ってくれば、許さぬ。必ず斬る。……ここまでが兄の慈悲じゃ。おやかたさまに何をいわれようと譲れぬ。」
「兄上。……兄上っ。お教えください。おれの何が悪かった? なにがお憎いのか? このような、とるにたらぬ部屋住みのおれが、兄上のお気に触っていたのは、いったい、何なのでございますか。」
「じぶんは何も悪くないとでもいうのか、お前はっ!」
新三郎は、今日はじめて大喝した。十四郎だけではなく、ついてきた三人も驚き、足を止める。
「いったい、お前という奴は、まだ……っ。」
「……?」
「そうか。……では、お前にはわからぬ。いうてもわからぬ。」
「なぜだっ?」
「それをなぜ、と訊くか。」
新三郎は、また少し考えた。そして、薄く笑った。
「おぬしには、翼など、……翼が、ないからだ。翼とは大志。大志なきものに虎の図体だけだ。だから、そんな奴には、なにをいうても、儂の言葉は通じぬのだ。」
「……。」
十四郎は、あやめの言葉を明瞭に思いだしていた。ふたりはおれに、おなじことを裏表でいっているのではないか。
「森川、萩原、安部。」
新三郎はふりかえって三人に呼びかけた。侍たちは電撃に打たれたようになる。
「おぬしらの忠義ぶりはみた。あっぱれである。十四郎によく仕えよ。いずこなりとも、ついていってやるがよい。」
馬頭を返し、新三郎は松前の町に戻っていく。
森川以外の二人は、途方に暮れた表情になっている。ご名代様の言葉の意味を測りかねているのである。
(気づかぬか。まあ、儂らも見限られたということだな。)
森川が目をやると、十四郎もなにやら複雑な顔つきだったので、やれやれと思う。
「御曹司。お進みあれ。」
「おう。」
森川が十四郎の馬の轡をとる形になる。後ろから、昂奮が去ってややしおたれた風の二人が急ぎ足でついてくる。
「儂ら四人は、どうやら一蓮托生と決まりましたな。」
と、これは同僚たちにも聞こえるようにいってやる。
「このうえは、儂らも、どこまでも御曹司のご下知に従うより道はなし。」
「なにをいう。」
十四郎は笑った。
「最初からそうだったのではないのか。」
「十四郎。大儀。皆、大儀である。」
「……ご名代様のお越しとは。」
十四郎はにわかに緊張した。見送りに来てくれた、とはさすがに思えぬ。
新三郎は剣技にすぐれている。まさか、この場で手ずから斬るつもりか。さらに、供回り三名。
(これは、数が合わぬな。)
十四郎のひそかな計算はたたない。
(森川がもしも加勢してくれても、斬りぬけるのはかなり面倒だ。……こんなところで、か。)
乱闘から脱出して西へ奔るとしても、納屋の人びとを巻き込みたくない。
と、森川が、刀の柄に手をかけるのがみえた。
(よせ。)
そのとき十四郎は、萩原、安部までもが、同じように利き腕に力をこめているのをみた。
(たまらぬな、六人、いや七人で滅多切りにするつもりか。)
と舌打ちした。
が、肝心の新三郎らが臨戦態勢に入っていない。むしろ、こちら―であろう―のぴりぴりとした緊張具合にあっけにとられたようになり、たじろいている。もし斬りつけてくれば十四郎を守る姿勢を三人が瞬時に見せたのに、驚いた様子だ。
三人が前に進み、十四郎が斬りつけられれば、即座に応じる構えになった。
(こやつらめ。)
十四郎は驚きつつもうれしくなったが、どうやら相手方も、ここで事を起こす気は最初からないらしい。
「十四郎。中途まで、送ってやる。」
供回りに下がらせ、新三郎は十四郎に馬に乗れ、と命じた。狭い道を、ふたりが馬頭をぴったりと並べて進む形になる。
新三郎は、この弟の得体のしれなさにあらためて触れ、ひそかに身震いする思いがした。
三人には、十四郎をどこかで斬り捨てる機会があれば、迷わずそうせよと命じておいた。
(どこかで、斬りあいが起きるだろう。それで片が付く。)
ただし、松前武士として、闇討ちは許さないといい添えた。万が一、卑怯な手を使って蠣崎家の者の首をとったことがわかれば、恩賞どころではないぞ、と固く肝に銘じさせたのだ。大舘の命でお命を頂戴する、と正々堂々宣言したうえで首をとれ、それ以外は許さぬ、といわれ、三人の侍は、困った顔になっていた。
部屋住みの「厄介者」ばかりで皆、恩賞には飢えているが、大した能も度胸もない。下手に手を出せば、なんといっても代官家の連枝として武技の訓練を積んだ十四郎が、まとめて斬って捨てることもありうる。
(だが、斬ってしまえば、十四郎のやつはもう二度と松前に戻れぬ。ひとりではポモールとやらの村にも、とても行けまい。それでよい。)
森川たちは捨て駒のようなものだ。運がよければ、一人二人でも松前に逃げ帰って、十四郎の非を鳴らすのが役目だ。その程度の連中で、使い捨てるつもりであった。
ところが、新三郎の思惑はすでに外れていた。
(そんな奴らを十四郎は、この短期間で手なずけ、大舘に逆らって剣を抜かんまでにしてしまうとは。)
(納屋の連中の手引きか? そうではあるまい。金だけで、ああいう真似はせぬ。できぬ。)
(何者なのだ、この弟は?)
「十四郎。おぬしをこの役にあてたとき、南条がかようにいうた。虎に翼をつけて野に放つ、の故事をお忘れかと。」
南条というのは、累代の重役の老臣である。十四郎ととくに近いわけでもなかったはずだが、なにかをこの異相の若者に感じていたらしい。
「兄上。縁起でもござらぬ。壬申の乱のお話ではござらぬか。拙者が大海人皇子様とは、幾重にも畏れ多いにもほどがありまする。……何度も誓って申しますが、拙者には、いや……」十四郎は唇を噛んだ。「お許しありたい。申し上げまする。与三郎兄上にも、大それたつもりは毛頭なかったのだ。兄上方にお考えの違いはござったろう。拙者の振る舞いに、勝手や軽率のそしりは免れぬやもしれぬ。だが、あのような誣告を取りあげられてのお裁きは、ご名代さまにあるまじきものでござった。」
「いまの言葉だけで首を刎ねてもよいのだぞ。」
「いかがなさいますか。」
「……愚か者め。いまは一対四ではないか。」
「さすがは兄上。」
「与三郎は、死なずともよかったのだ。あれが勝手に腹を切った。」
「何をおっしゃるか?」
「なんのために、与三郎は勝手に腹を切ったのか、考えてみよ。」
「……まさか。」
「そうだ、おぬしの身代わりのつもりであったろうな。二人生きていれば、腹を切らされるのはおぬしのほうだったろう。……大舘は、役に立つ方を残す。」
「わたしの、身代わり? 役に立つ方?」
(わからんのか。まあ、わからぬでよい。)
新三郎は何か考えたが、苦く笑って、言葉を継いだ。
「あれは、儂がおぬしを殺したいといつも思っているのを、知っていたのだ。」
「……!」
「十四郎。二度と松前の土を踏むな。北の地でもどこでも、いかようにも暮らし、いかようにも果てるがよい。誰となにをしようと、間違いさえなければ、いっこうに構わぬ。だが、もし戻ってくれば、許さぬ。必ず斬る。……ここまでが兄の慈悲じゃ。おやかたさまに何をいわれようと譲れぬ。」
「兄上。……兄上っ。お教えください。おれの何が悪かった? なにがお憎いのか? このような、とるにたらぬ部屋住みのおれが、兄上のお気に触っていたのは、いったい、何なのでございますか。」
「じぶんは何も悪くないとでもいうのか、お前はっ!」
新三郎は、今日はじめて大喝した。十四郎だけではなく、ついてきた三人も驚き、足を止める。
「いったい、お前という奴は、まだ……っ。」
「……?」
「そうか。……では、お前にはわからぬ。いうてもわからぬ。」
「なぜだっ?」
「それをなぜ、と訊くか。」
新三郎は、また少し考えた。そして、薄く笑った。
「おぬしには、翼など、……翼が、ないからだ。翼とは大志。大志なきものに虎の図体だけだ。だから、そんな奴には、なにをいうても、儂の言葉は通じぬのだ。」
「……。」
十四郎は、あやめの言葉を明瞭に思いだしていた。ふたりはおれに、おなじことを裏表でいっているのではないか。
「森川、萩原、安部。」
新三郎はふりかえって三人に呼びかけた。侍たちは電撃に打たれたようになる。
「おぬしらの忠義ぶりはみた。あっぱれである。十四郎によく仕えよ。いずこなりとも、ついていってやるがよい。」
馬頭を返し、新三郎は松前の町に戻っていく。
森川以外の二人は、途方に暮れた表情になっている。ご名代様の言葉の意味を測りかねているのである。
(気づかぬか。まあ、儂らも見限られたということだな。)
森川が目をやると、十四郎もなにやら複雑な顔つきだったので、やれやれと思う。
「御曹司。お進みあれ。」
「おう。」
森川が十四郎の馬の轡をとる形になる。後ろから、昂奮が去ってややしおたれた風の二人が急ぎ足でついてくる。
「儂ら四人は、どうやら一蓮托生と決まりましたな。」
と、これは同僚たちにも聞こえるようにいってやる。
「このうえは、儂らも、どこまでも御曹司のご下知に従うより道はなし。」
「なにをいう。」
十四郎は笑った。
「最初からそうだったのではないのか。」
0
お気に入りに追加
8
あなたにおすすめの小説

夢の雫~保元・平治異聞~
橘 ゆず
歴史・時代
平安時代末期。
源氏の御曹司、源義朝の乳母子、鎌田正清のもとに13才で嫁ぐことになった佳穂(かほ)。
一回りも年上の夫の、結婚後次々とあらわになった女性関係にヤキモチをやいたり、源氏の家の絶えることのない親子、兄弟の争いに巻き込まれたり……。
悩みは尽きないものの大好きな夫の側で暮らす幸せな日々。
しかし、時代は動乱の時代。
「保元」「平治」──時代を大きく動かす二つの乱に佳穂の日常も否応なく巻き込まれていく。

幕府海軍戦艦大和
みらいつりびと
歴史・時代
IF歴史SF短編です。全3話。
ときに西暦1853年、江戸湾にぽんぽんぽんと蒸気機関を響かせて黒船が来航したが、徳川幕府はそんなものへっちゃらだった。征夷大将軍徳川家定は余裕綽々としていた。
「大和に迎撃させよ!」と命令した。
戦艦大和が横須賀基地から出撃し、46センチ三連装砲を黒船に向けた……。
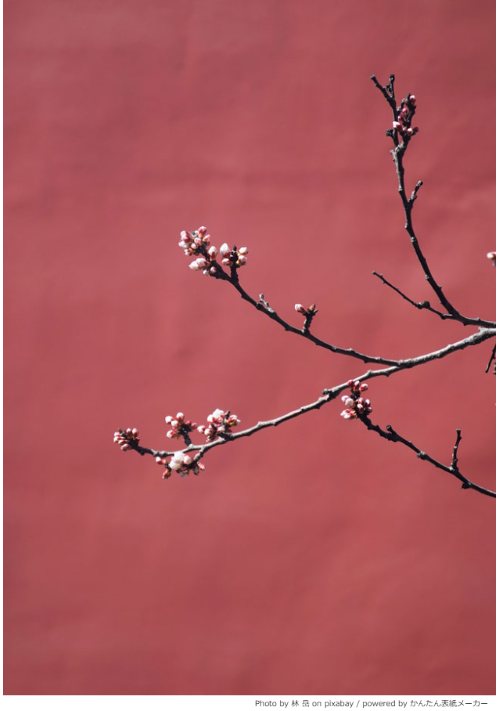
茜さす
横山美香
歴史・時代
【第一部】
願ったのは共に生きる未来。――ただそれだけだった。
戦乱の世が終わって数十年。大平の世の片隅の小藩で、本領と飛び地領との間の壮絶な跡目争いが繰り広げられていた。
生家が困窮し飛び地領に売られた隠密・樋口雅勝と、滅びゆく忍び里の娘・るいは惹かれ合い、共に生きたいと願うようになる。
しかし二人のささやかな願いもまた、お家をめぐる争いの中に飲み込まれて行く運命だった。
二十歳まで生きられない定めを負った隠密と、滅びゆく忍び里の娘のかなわなかった夢と恋の物語。
【第二部】
誰も幸せになれなかった藩主交代劇から三年。
清水忠雅は元許嫁・菊松尼との絆だけを支えに、友を死なせてしまった苦悩と悔恨の日々を生きていた。
そんな忠雅の前にある日、死んだはずの友とよく似た刺客があらわれる。
――この世の仕組みが間違っているのなら、仕組みそのものを変えてやる。
敵方として現れた男は、かつて同じ夢を見た友と同一人物なのか。
雅勝とるい、忠雅と菊乃の恋の行末は。そして長きに渡る藩の権力争いは終わるのか。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

妻がエロくて死にそうです
菅野鵜野
大衆娯楽
うだつの上がらないサラリーマンの士郎。だが、一つだけ自慢がある。
美しい妻、美佐子だ。同じ会社の上司にして、できる女で、日本人離れしたプロポーションを持つ。
こんな素敵な人が自分のようなフツーの男を選んだのには訳がある。
それは……
限度を知らない性欲モンスターを妻に持つ男の日常

藤散華
水城真以
歴史・時代
――藤と梅の下に埋められた、禁忌と、恋と、呪い。
時は平安――左大臣の一の姫・彰子は、父・道長の命令で今上帝の女御となる。顔も知らない夫となった人に焦がれる彰子だが、既に帝には、定子という最愛の妃がいた。
やがて年月は過ぎ、定子の夭折により、帝と彰子の距離は必然的に近づいたように見えたが、彰子は新たな中宮となって数年が経っても懐妊の兆しはなかった。焦燥に駆られた左大臣に、妖しの影が忍び寄る。
非凡な運命に絡め取られた少女の命運は。

生まれて旅して恋して死ぬ、それが殿様の仕事です
三矢由巳
歴史・時代
九州の小藩藩主山置隆礼(たかゆき)と江戸の正室祝(のり)姫、国の側室満津(みつ)の方の三人を中心とする人々の物語。舞台となるのは、元禄から安永までの八十年余り。災害、火事、飢饉、謀反等、様々な事件に翻弄されながら人々は生きる。
別サイトで「わたくしたちのお殿様」として掲載していた作品のR15改訂版。
表紙の三つ違い山形紋はフリー素材サイト発光大王堂の家紋素材です。

運命の麗しき皇妃たち・皇帝に愛された妃~薔薇のような美貌の皇妃 エーメとジョゼフーヌ~~【フランス皇帝ナポレオンとオスマン帝国の帝の妻】
のの(まゆたん)
歴史・時代
フランス革命前の事 占い師は二人の従妹同士の少女達を見て言った。
「二人とも皇妃になる」・一人はナポレオン・ボナパルト皇帝の皇妃ジョゼフィーヌ
・もう一人はオスマン帝国の皇帝、その妃として献上されたエーメ・デュ・ビュク・ド・リヴェリ
後のナクシディル皇妃 次期皇帝の母
※塩野先生のイタリア異聞、ネット等より
伝承、異説等含みます
※他サイトあります
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















