1 / 1
星と星
しおりを挟む
星と星
ブルーマウンテン(段々寝音)
頂点から落ちた日
1
私がアイドルとして目指すもの。それは、高み。
私は全てのアイドルを超える存在になる、なって見せる。だからこのライブで失敗することは絶対に許されない。
幕の向こう側には、たくさんの人達が待っている。
有名なファッションデザイナー、雑誌編集者、テレビ局の関係者、大手プロダクションの社長。
この機会を逃したら次のチャンスがいつになるか分からない。
「凛さん、そろそろ準備お願いします」
舞台そでに移動し、ファンたちの歓声を聞きながら、右手に持つマイクに力を入れる。
今までの努力を思い出す。つらいことしかほとんど経験してこなかったけれど、それは今日この舞台に立つための過程に過ぎない。
「証明、マイク、音響、準備出来ました」
「幕を開ける準備を! ファンを待たせないためにもすぐに始めるぞ」
「凛さん、幕を開けますよ」
「はい、よろしくお願いします」
今日、この時から私のアイドルとしての挑戦は始まる。この小さな舞台の開幕と同時に。
私は今輝いているのだろうか。ちゃんとアイドルが出来ているのだろうか。
私はふとそう思ってしまった。仕事も順調にこなしているし、アイドルとしての輝きが劣ってきている訳でもない。だからそんなことを考えることはないのに。
仕事終わりの車の中で、車窓から見える町の明かりを見つめながら、私は考えてしまう。暗闇に光り輝くいくつもの光源、その光は星のように、綺麗で美しい。
「凛、明日は朝から次のライブの打ち合わせが入っているから、寝坊しないように」
「大丈夫、遅れないようにする」
ライブという言葉を聞くと二年前のライブを思い出す。どうにかして有名になろうと必死になって練習した日々を思い出しながら、全ての力を出し切ったあの日。その結果、私は大手芸能プロダクションの社長の目に留まり、立派なアイドルとしてデビューすることになった。
あれから二年、今ではアイドルといえば斎条凛と言われるほど有名になり、トップアイドルの名をほしいままにしている。でも、それで満足してはいけない、ここで止まってはいけない。色々な人から持て囃され、羨ましがれ、騒がれる日々は別に嫌というわけではない。でも私が求めているものはこんなものではないのだ。私が目指しているものは、高み。ただそれだけだから。
「今日の仕事、お疲れ様」
一日の終わりがやってきた。今日もいつもと同じように夜景を見つめる。
「ねえ、凛。明日も厳しいスケジュールだけど、大丈夫かしら?」
「大丈夫、心配してくれてありがとう。でもなんで?」
私は車窓の外に輝くいくつもの星を見つめながら、マネージャーに問いかけた。
「最近の凛、なんだか少し無理をしているように見えてね。あなたのマネージャーになって、二年近く一緒にいるから。あなたの様子いつもと違うことぐらい、すぐに分かるわ」
「無理なんてしてないわ。だから心配しなくていいのよ」
心配するマネージャーに私は言った。
次の日の仕事は、来月行われるライブ会場の視察である。会場自体は結構前から決定していたのだが、私自ら会場に足を運ぶのは今日が始めてである。
大きなステージ、豪華な装飾、観客が入るスペース。野外に作られたステージは、大規模なライブというわけではないのに、やけに力が入っている。
「マネージャー、この会場やけに力が入っているわね」
「凛、何を言っているの。ここにいる人たちはみんな本気よ、誰一人力なんて抜いていないわ」
「そうね。だって私が出るライブなんですもの」
私は何を考えているのだろう、いつもそんなこと思わないのに。なんか、変。
「凛さん、音楽の準備が整いました。いつでもリハーサル出来るので、準備出来たら言ってください
「リハーサル? マネージャー、どういうことよ。今日は視察だけじゃないの?」
「そうなんだけど、これからのスケジュールを考えると、今一緒に行ったほうが、あなたにとっての負担も軽くなるんじゃないかと思って。あなたの練習着などもしっかり準備してあるわ」
「マネージャー、ありがとう」
私は、マネージャーの言うことに従った。確かにこれからのスケジュールは分刻みである。ライブに向けてのレッスンは当然のこと、雑誌のインタビューやラジオ、テレビなどに出演し、今回のライブを世間に宣伝しなければならない。そういうことを考えると、今ここで自分の体の調子や、ステージ上での演出、証明、音響の具合を確認するのもいいのではないか。と私は思ったからだ。私のスケジュールを確実に把握している彼女だからこそ思いついたことだろう。
「凛、ステージで踊る時は怪我に注意して。リハーサルをすることは、会場設営のスタッフの方たちに連絡はしているけれど、準備のために動いている人たちがいる。いつ何が起こるか分からないから、十分注意して」
「確認するけれど、私が踊っている時にステージには誰も上げないでよ。私の邪魔になるようなことは無いように」
「ええ、承知したわ」
私はステージの上に上り、深呼吸を一つ。
「初めて下さい」
スピーカーから流れ出す、シンセサイザーが特徴的なテクノ。ドラムマシンが奏でる単調な反復のビートにポップなメロディー。リズムに合わせたキレのあるダンス。
私の体は自然に動き出す。手を大きく動かし、足でステップを踏み。メロディーに合わせて歌う。五感を使って、私は音楽を奏でる。ただそれだけに集中して、必死に足掻く。
失敗はしない、たくさん練習したんだ、大丈夫、上手くいく。自分に自信をもって、次のステップを踏もう。そう自分に言い聞かせ足を動かした時、自分の体が前のめりになり、宙を浮いた。目の前には地面が見える。
「あっ」
そしてスイッチを切ったようにパチッと目の前が真っ暗になった。
凛――起きて、凛――
この声……マ、マネージャー……。
私は少しずつ、閉じていた目を開けた。白い天井がぼんやりと見える。でも私には見覚えのない部屋、誰かが私をここに運んできてくれたのだろうか。
「マネージャー……かな? 確か私、ステージの上から落ちたんだっけ」
横たわっていたソファーから起き上がる。
まだ少し体に痛みが走るが、歩けないほどではない。
「これなら、マネージャーのいる所まで行けるかも」
扉のほうまで行こうとした時、一人の女の子が部屋に入ってきた。そして、私を見るなり大声を上げて近づいてきた。
「体の方は大丈夫ですか! 痛い所とか、気になる所とか」
「特にないわ、でも少し痛みがあるかも。ねえ、聞きたいんだけど、ここどこかしら?」
「ここは私が所属する事務所の休憩室です」
「え? 今事務所って言った?」
「はい。私が所属している芸能プロダクション、大谷プロダクションです」
太谷プロダクション? そんな名前聞いたことない。
「そのような名前は聞いたことないのですが」
「ああ、小さな事務所なので知名度があまり無いのかもしれませんね、あ、私、星空ゆかりと言います! この事務所で新人アイドルをしています! よろしくお願いします!」
このゆかりという子はアイドルらしい。聞いたことのない名前なのは、彼女が新人アイドルだからだろうか。それにしても、元気な子である。
「わ、私、マネージャーさん呼んできますね。ちょっと待っててください!」
そう言ってゆかりは部屋の外に飛び出していった。
ゆかりがマネージャーを呼んでくるのにそんなに時間はかからなかった。彼女のマネージャー、本間さんは、ピシッとスーツを着こなしている二十歳半ばの男性。とても真面目そうに見える。
「怪我とかないですか」
「ええ、大丈夫です」
「いやぁ、ゆかりから話を聞いた時は驚きましたよ、公園で女の人が倒れてるなんて言うものですから。無事に目が覚めて本当に良かったですよ」
「ゆかりも驚きましたよ!」
ちょっと待って、それはどう考えてもおかしい。
私はさっきまでライブ会場にいたはず。でも二人は公園で私を見つけたと言っている。
「あ、あの、私さっきまでライブ会場にいたんです。今度行われるライブのリハーサルをしていて、その時にステージから落ちてしまって……それで目が覚めたらここに……」
「何を言ってるんですか、あなたが倒れてたのは公園ですよ。あそこにはライブ会場なんてありませんでしたし、そんなスペースもありません」
「うーん、それもそうだな。あと、君は歌手かな? ライブ会場でリハーサルを行うということは、私たちと同じ芸能関係に携わっているということにもなるけど……そうだ、名前を教えてくれないか」
その質問に私は驚いた。世間では「アイドルと言えば斎条凛!」という言葉が生まれるほど、私の人気は絶大で、私の顔を知らない人はいないはず。ましてや芸能関係の仕事をしているのに、私のことを知らないのは少し問題があるのではないだろうか。
そう思いながらも私は自分の名前を二人に言った。
「私はかの有名なアイドル、斎条凛です」
「斎条……凛? 聞いたことないな」
「ゆかりもです。アイドル関係の雑誌やニュースは欠かさずチェックしていますが、そのような名前は聞いたことがありません」
そんな馬鹿なことはないだろう。雑誌にも載ってないなんて。
「ゆかりさんその雑誌、見せてもらえないかしら」
「いいですよ、これです」
よく見かける芸能雑誌、でも見たことのない名前。中には男女問わず、様々な人物の写真が掲載されているが、私の知っている人物は一人もいない。ましてや、斎条凛という名前も載ってはいなかった。
「こんなこと、まるで私が存在してないみたいじゃない」
私は雑誌をもう一度雑誌を見直したが、私のことは何一つ書かれていない。
「嘘よ、こんなの嘘よ」
私はその場に座り込んでしまった。
「凛さん! 大丈夫ですか」
「大丈夫なわけないじゃない。今までに積み上げてきたものが一瞬で水の泡よ!」
私はゆかりにそう訴えた時、本間さんが口を開いた。
「凛さん、あなたがアイドルだということを証明する事は出来ますか? もしそれが出来るのであったら、私たちに見せてください。証明の仕方は何でも構いません」
「なんでも、ですか?」
「はい。あなたがアイドルだったのならば、証明の仕方はたくさんあるはずです。必要ならば、それに必要な準備もしましょう。あなたがそこまで主張してるのです。私たちにそれを証明してください」
「分かりました。私をオーデションに出してください。絶対に合格して見せます!」
私は立ち上がり、本間さんに強くそう言った。
ゼロからのスタート
2
私が事故に遭ってから五日ほど経った。あれから、インターネットなどで私の情報を調べようと試みたが何も出てこなかった。また私の所属しているプロダクションも調べたが出てこなかった。この世界には、私に関する情報が何一つ存在しないのだ。信じたくはないが、信じることしか私には出来なかった。
本間さんからオーディションを受ける準備が出来たと知らされたのは、そんな時だった。
「イメージキャラクターを決めるオーデションですか?」
「その通り。これは今度新しく発売されるお菓子のイメージキャラクターの募集だ。新人アイドル対象のものだから、君にとっては簡単かもしれない。それでもしっかりと、イメージキャラクターの座を手に入れるんだぞ!」
「分かりました、頑張ります」
「うむ。スケジュールの方はまた後日連絡するからな」
「はい、よろしくお願いします」
「それと、このオーデションにはゆかりも参加する。負けないようにね」
本間さんはそう言うと、休憩室から出て行った。
新人アイドル対象オーデション。まさかトップに輝いた私がこのようなものに出ることになるとは、五日前までは想像も出来なかったことだろう。でも、本間さんの前で自分から言い出したこと。自分がトップアイドルであること、ここで証明してみせる。
「凛さん、やっと見つけました」
息を切らしながら、ゆかりが部屋に入ってきた。
「どうしたんですか、そんなに急いで」
「それはオーデションまで時間がないから、凛さんと一緒に練習しようと思って!」
「私と一緒に練習ですか? でもなんで私なんかと」
「それは私が、凛さんと一緒に練習したいからですよ!」
そう言ったゆかりの顔は弾けるような笑顔で輝いていた。
「ゆかりさん、練習するって言ってませんでしたか?」
「うん、そうだよ」
「じゃあなんで、目の前に沢山のお菓子がおいてあるんですかね?」
ゆかりに練習しようと言われて、連れてこられた場所には、山のように詰まれたお菓子が置いてあった。
「ここに置いてあるお菓子は、今回オーデションを受けるお菓子会社のものです。ここのお菓子はおいしい物が多くて、年代問わず、多くの人たちに愛されている商品が多いんです。ここに準備したのは、ロングセラー商品のチョコレートと、先月販売されたバニラ味のお菓子です」
「今からこのお菓子を食べるのか? そんなの練習でもなんでもないんじゃあ……」
私がそう言うと、ゆかりは口をぎゅっと結んで頬を膨らませた。
「練習ですよ! 大事な練習! もしかしたら、どれだけおいしくお菓子を食べられるか、見たいなチェック項目があるかもしれないじゃないですか!」
「例えなかったとしても、凛さんは食べておいた方が良いと思います。食べたことないですよね?」
確かに、私はこのお菓子を食べたことはない。というか、このお菓子についても詳しく知っている訳でもない。
「おいしく食べられるかなんて項目があるかどうかは分からないけれど、味を知らない状態でオーデションを受けるのは、高校入試で入学希望校の情報をまったく調べずに面接入試を受けるのと同じくらい無謀だと思うんです。だから凛さん、一緒に食べましょう!」
そう言うと、お菓子の箱を一つ開け、チョコレートを一つ口に運んだ。
「うん、ほっぺがとろけちゃうほどの美味しさ! 止まらなくなっちゃう! 凛さんも食べてください」
「じゃあ、一個だけ、ん! 美味しい」
「ふふ、ではこっちも、いただきます!」
「やっぱり、ゆかりが食べたかっただけなんじゃ……」
笑顔で私にお菓子を差し出す彼女の表情は、とても楽しそうで、華やかだった。
次の日もゆかりは、私の所に来て一緒に練習しようと言ってきた。
「今日は一緒にジョギングをしましょう」
「ジョギングならいいけど、今やってるストレッチが終わったらね」
ゆかりは分かった、と言って、練習ルームから出ていった。
なぜ、ゆかりは私と一緒に練習したがるのだろうか。私にはそれが不思議でならなかった。
私が新人アイドルとして日々の練習を頑張っていた頃は、黙々と一人で練習をしていた。自分のペースで決められたメニューを次々とこなしていく。自分の目標に向かって、夢に向かって、己を磨きあげるのに精一杯だった。
苦しいことが殆どのこの世界。私はただ、自分の将来の為に頑張ってきた。それに、ゆかりと私はライバルなのだ。同じオーデションを受けると言うことは、どちらか一人しか受からないということ。
そんな状況でも、彼女は私と練習したいと言っているのだ。
私にはどうしてもそこが理解できなかった。
ストレッチをすませた私は急いで外に出た。
ジョギングはゆかりがいつも走っているコースを通るようだった。
住宅街の中を走り地区で一番大きい公園を折り返し地点として来た道を戻る。道も平坦で、距離もそんなに長くはない。
ゆかりは、私の少し先を走っている。毎日走っているからだろう、息切れはしていない。一定のリズム、スピードで進んでいく。そんな時、一人のお婆さんがゆかりに声をかけた。
「ゆかりちゃん、今日も走ってるのかい」
「はいっ、今度オーデションがあって、それに出るために走ってます!」
ゆかりはそのお婆さんの前で立ち止まると、笑顔で話し始めた。
「そうなのかい。私には良く分からないけれど、ゆかりちゃんは頑張り屋さんだからね。きっと上手くいくよ」
「本当ですか! ありがとうございます。私、絶対合格します」
おばあさんはその言葉を聞くと、挨拶をして私たちと反対側に歩いていった。
折り返し地点の公園まで行くのに、ゆかりは沢山の人と会話をしていた。さっきのおばあさん以外にも、子供や、買い物帰りのおばさん、それに野良猫まで。ゆかりは、誰に対しても笑顔で、優しく接していた。どうしてゆかりは、自分の練習中なのにも関わらず、他人に邪魔されてあんな笑顔をしていられるのだろうか。なんであんなに楽しそうなのだろうか。私にはとても考えられないことだった。
「凛さん、公園に着いたので少し休憩しましょう」
走り出してから約四十分。私とゆかりは無事、折り返し地点の公園に着くことが出来た。ゆかりが道中、色々な人達と会話していたため、着くのが少し遅れてしまった。
公園内のベンチに腰を下ろし、自動販売機で買ったスポーツ飲料水を口に含む。
「凛さん、大丈夫ですか?」
私の横に腰を下ろしたゆかりは、私の顔を覗き込んでそう言った。
私は、そんなに疲れてはいない。ただ、さっきのゆかりの笑顔について、私は少し考えていた。
「大丈夫。心配してくれてありがとう」
ゆかりはその言葉を聞くと、私に笑顔を向けた。
「うん。でも、言いたいことがあったら何でも私に言ってね」
そう言うと、彼女はベンチから立ち上がった。
「じゃあ、一つ聞いていいかしら」
ゆかりは、私の方を振り向いた。
「なんでゆかりは、いつも笑顔でいられるの?」
私の言葉を聞いたゆかりは、驚いた表情を見せた。
「凛さんは、何でそんなことを私に聞くのですか?」
「私は笑顔で練習したことがないから」
私はアイドルとして、高みを目指すため、今まで努力をしてきた。アイドル育成教室に小さい頃から通い、歌、踊り、劇、スポーツなどに汗を流した。教室には数十人の子供たちがいる。でもみんなライバルなのだ。共に戦う戦友ではない。誰もが一番になろうと、考え、行動し、何人ものライバルを蹴落としていく。そんな状況下でも数名で固まり仲良く活動している子経ちもいた、でもそんなに長くは続かなかった。仲良くなってもライバルなのは変わらない。そして、みんながみんなアイドルになれる保障はどこにもない。弱肉強食。この世界は醜く、重たい、シビアな世界なのだ。
「私があなたのような新人アイドルをやっていた時、塾みたいな教室で歌やダンスを習っていたの。ゆかりのように、アイドルとして輝きたいと夢見ている子供たちが沢山いた。でも、みんな笑顔だったのは、初めだけ。ここに来て私達が思い知らされたのは、仲間達と争い、蹴落とし合い、騙し合いの耐えない、恐ろしい世界だということ。そしてアイドルのシビアな世界には、友情も、楽しさも、何もかも存在しないということ。私がトップアイドルになれたのは、そんな厳しい世界で生き残っていくために、仲間を作らず、周りに目を向かず、自分のためだに日々練習を重ねていく。弱音を吐いたら、そこで試合終了。自分を助けてくれる仲間なんてここにはいない。苦しいことや悲しいことが多すぎて、辞めようと思ったけど、自分の夢のために努力した。だからトップに立てた。少なくとも、そういう辛い過去があったからこそ、今の私があると思ってる」
「凛さん」
「あなたがとても楽しそうに練習してたから、自分の過去と比べてしまっただけだから、そんなに気にしなくていいよ」
「アイドルって厳しい世界なんですね、私の思っていた以上に」
ゆかりは私の横で顔を下に向けた。もしかしたら、私の思っていたことを一方的に話してしまったために、ゆかりのアイドル活動を、今のゆかりを、いつの間にか否定していたのかもしれない。彼女に謝らなくては。
そう思って、ゆかりに話しかけようとした時、彼女はベンチから立ち上がり笑顔で私の方を向いた。
「そろそろ帰りましょう」
来た道と同じ道を走る。私はゆかりが落ち込んでいるのではないかと少し心配していたが、来た時と同じように多くの人達と会話をしながら走っていた。
事務所に帰り着替えを終えた時、ゆかりが私に声を掛けてきた。
「凛さん、ちょっと私と来てくれますか?」
ゆかりに連れられてきたのは事務室だった。
「なんで私をここに連れてきたの? もしかしてさっきのことで怒ってたりとか……?
「実はですね、凛さんに見てもらいたいものがありまして」
「え? 見てもらいたいもの?」
ゆかりは、事務所にある本棚から、大きく分厚い本のようなものを取り出した。
「これは?」
「私の、アイドルとしての活動をまとめた資料兼アルバムです。この中に、今まで培ってきた私の努力が全て詰まってます」
ゆかりが中を開くと、そこには彼女の思い出でいっぱいだった。
「これは、二年前に行われた町内会のお祭りをお手伝いした時の写真ですね。本番は子供たちと一緒に盆踊りしたり、屋台で射的したりしました。あ! これは、奉仕作業のボランティア活動の時の写真です! 懐かしいなぁ」
ゆかりは、昔の思い出を語りながらページをめくっていく。しかし、何枚かめくった時、そこに笑っているゆかりの姿はなかった。
他の写真よりも大きいその写真には、ゆかりの横に一人の女の子が写っている。二人の後ろには、「まゆちゃん、お誕生日おめでとう]と書かれた垂れ幕が吊るされていて、鮮やかな飾りが施されている。まゆちゃんとはゆかりの友達だろうか、それとも……。
「凛さんには、アイドルとしてお互いを高めあえる仲間がいましたか?」
「え?」
「私には、仲間がいました。この写真にはまゆと私しかいませんが、このほかにも五人いたんです。でもみんな辞めちゃいました。勉強とか家の都合とかでこの世界から引退していったんです。でも絶対にそれだけが原因じゃない。凛さん、どうしてだと思いますか?」
「そんなこと、急に聞かれても」
私がそう答えると、ゆかりはアルバムを閉じた。
「実は全然有名になれなくて、活動も写真にあったようなボランティアのようなことしかしたことないんです。本間さんは、汗水流しながら仕事を持ってきてくれるんですが、自分たちの実力不足で合格出来なくて。そんな状況で自分の夢を諦めていった仲間が私にはいたんです」
私はそれを聞いて腕を組む。
「それが、アイドルの世界、厳しい世界なのよ」
ゆかりは静かに顔を横に降り、言葉を続けた。
「でもある時、まゆが私に言ったんです。今はまだ有名になるような仕事が私たちの元に舞い降りて来なくとも、諦めなければチャンスは必ずやってくる。だから、ボランティアのような仕事ばかりでも、手を抜いたりしては絶対にいけない。それに私達が活動したことによって、町の人たちはとても喜んでくれる。笑顔になってくれる。これって、私達がステージ立って、沢山の人達を笑顔にさせるのと、同じことなんじゃないかって。だから、一緒に頑張ろう。一人でも多くの人を笑顔に出来るようにって」
「まゆっていう子はゆかりにとって、大切な存在だったんだな」
「はい、でも……まゆは家庭の事情でアイドルを辞めてしまいました。仕方ないことだけど、正直寂しかった。でも私はそのことをまゆには言いませんでした。私は彼女に絶対に有名になる、今まで自分の夢を諦めていった人達の分もまゆの分も含めて有名になる。だから私は諦めないって伝えました」
ゆかりはそう言って、アルバムを元あった場所に戻した。
私は、自分が見てきた世界がすべてだと、心の中で決めつけていたのかもしれない。ゆかりには彼女のアイドルとしてのやり方があり、誇りがあり、物語がある。それは私も同じ。めざすものは同じでも、進み方は沢山あるということを、私はゆかりに教えてもらったのかもしれない。
次の日もゆかりは私と一緒に練習しようと言ってきた。なぜそんなに、私と一緒に練習したいのかと聞くと、二人でやった方が自分では気付かないようなことに気付けたり、お互いで高め合うことが出来るなどの利点が多いからと彼女はそう言った。ゆかりからそんなしっかりした考えが出てくるとは当然思えない。おそらくまゆから言われたことだろう。
ゆかりは、一人でやるよりも二人でやった方が絶対に楽しいとも言っていた。この数日間、ゆかりとやった練習はとても楽しかったのも事実だ。ここは、彼女のやり方で、もう一度アイドルの高みをめざすのもいいかもしれない。
「ゆかり、これから一緒にがんばろうね」
「急にどうしたんですか凛さん。私はいつも頑張ってますよ?」
「そ、そうね、そうだったわ」
そして、オーデションの日がどんどんと迫ってくるのだ。
私とあなた
3
「凛ちゃんこっち向いて!」
「インタビューいいですか?」
カメラのフラッシュがとても眩しい。あちらこちらから、私の名前と質問が飛んでくる。そんなに大きくない会場に多くのマスコミが集まっている。こんな光景は久しぶりである。
今私がいるここでは、新しく発売されるお菓子の発表会行われている。そんなところになぜ私がいるのかというと、先日行われたイメージキャラクターのオーデションに合格したからである。
これのおかげで、本間さんにも私がアイドルだったということを証明することが出来た。
私という存在がないこの世界に来てから、一か月経った。この期間でここが私の知っている世界でないことは、十分に分かった。総理大臣が女性であることや、日本の首都が東京都ではなく、京都府であるなど、このような状況であると嫌でもここが違う世界であると思わなければならないのだ。元の世界に戻る方法は分からないが、それが分かるまではここで生きていかなくてはならない。
今回のオーディションに合格したことにより、私の知名度は一気に広がった。有名なお菓子会社のイメージキャラクターという条件が良かったこともあるが、今まで努力してきたことが今回の結果に結びついたに違いない。
イベントの終了後、本間さんの車の中で、私はふと、窓の外を見た。まだ明るい夕方の空にきらりと輝く一番星が見える。
「凛さんがこんなにメディアに注目されるとはね、さすがトップアイドル」
車を運転している本間さんが言った。
「今までの努力の結果ですよ。あと、もうトップアイドルではありません」
「え?」
「私はまだ、スタートラインから走りだしたばかりです、今までの栄光が通用しない世界でトップを目指すために」
「分かった。凛さんがこの世界でトップに立てるように、しっかりバックアップするから」
「はい、本間マネージャー」
「凛さん、私、心配なんです」
ゆかりが私にそう言ってきたのは、発表会が終わってから一週間が過ぎた時だった。
私のメディアへの露出が多くなり、事務所の名前が世に知られるようになったため、ゆかりにも仕事の依頼やオーデションへの誘いが多くなった。このことに関しては、ゆかりも本間さんも、とても喜んでいたが、いざ仕事に取り掛かってみると初めてやることが多すぎて、何をやったらいいのか分からなくなってしまいそうだ。そして今日も、分からないことについて私に質問をしにきたのだろう。
「実は、私にコマーシャルの仕事の依頼が来たんですが……」
コマーシャルか、それなら簡単そうだな。と私は思った。
「コマーシャルってそんなに難しくないよ。まあ演技を磨いてる人じゃなきゃ厳しいかもね」
「コマーシャルなんですが、その、歌の方で……」
「歌?」
ゆかりが言うには、コマーシャルで流れる曲を担当するらしい。アイドルらしい仕事がやっと舞い降りてきたのはいいが、歌を歌う仕事は初めてらしい。そこで、歌を歌う時のアドバイスを私に聞きに来たわけである。
「いちを、ボイスレッスンはしてきたのですが、いざ、このような仕事がやってくると、今までの練習だけで良かったのかどうか、不安になってしまって」
「不安……ね」
私も初めて人前で歌をうたった時は、自分の歌に自信が持てなくて不安だった。でも聞いてくれている人達が笑顔になったのを見たら、そんな悩みはどっかに消えていた。だからゆかりもそんなに心配することはないと思うんだけど。
「うん、じゃあ、歌の特訓しかないじゃない」
こういうことは、歌ってみなきゃ。ということで、私はゆかりにそう提案してみたのだ。するとゆかりは目をキラキラと輝かせながらはしゃぎ始めた。
「ということはカラオケですね! 行きましょう! 行きましょう!」
ゆかりが歌う曲は、この世界で名の知れているアイドルの曲が多かった。私がライブで歌っている曲は、テクノやダンスミュージックといった、クール系の楽曲なのに対し、ゆかりが歌うのはキュートでポップな可愛らしい楽曲が多い。また日ごろからボイスレッスンを行っているため、歌も下手なわけではない。
「ゆかりさん、自分にもっと自信を持ってもいいわ。音が外れている訳でもないし、歌の歌詞をよく理解して歌ってるから」
「本当ですか! でもまだ私には足りないものがあるんです」
ゆかりは自分の歌を完璧にしたいのかしら。
この時の私にはまだゆかりの悩んでいることがよく理解できていなかった。
数日後、私は本間さんに呼び出された。本間さんは、ゆかりが歌う曲の制作をするにあたり、私が歌う曲も一緒に作るかどうかを聞いてきた。
「どうかな、このタイミングに凛さんのソロ曲を作ろうと思うんだけれど」
「とてもうれしいお話、ありがとうございます。曲を作るにあたって、どのようなジャンルの曲になるのか、もうお決まりになられたのでしょうか」
本間さんは少し考えてから話し始めた。
「今回作曲をしてくれる人は、可愛らしい曲を多く作ってる。アイドルが歌うような、可愛らしい詩を書くのが得意なひとだからね。おそらく、凛さんの曲もそういう曲になるんじゃないかな」
自分の持ち歌とは違うジャンルの曲を歌う。今までこのようなジャンルの曲を聞いたことがあまり無かったが、新しいスタートを切った私には丁度良い機会である。
「分かりました。よろしくお願いします」
それから少したって完成したデモテープが送られてきた。
「二人にはこれからボイスレッスンや、レコーディング、CDの即売会など一緒に行動してもらうことになる。忙しいが、嬉しいことにイメージガールの件から二人とも仕事が入ってくるようになった。別々のスケジュールで行動していたが、俺がどうにか調節をしたからそこは気にしなくていい」
「ありがとうございます」
「頑張って、歌うたいます!」
ゆかりも今まで以上に力をいれているようだった。
「今日のレコーディングお疲れ様」
二日目のレコーディングが終わった時、私はゆかりにあることを聞いた。それは、以前カラオケに行った時のように緊張せず、しっかりと歌を歌えているかということだ。
「私が聞いた感じ、変に音程が外れているとか、そういう問題はないんだけれど、ゆかりがすごく悩んでいるみたいだったから心配で」
「歌のことはもう大丈夫。凛さんのおかげかも」
そういった、ゆかりの表情は少し曇っている。
「どうしたの、ゆかり」
私は気になったのでゆかりに聞いてみることにした。
「なにか、悩み事でもあるの? 話聞こうか?」
そういうと、ゆかりはしゃべりだした。
「実は私、凛さんがオーディションに合格してからの活躍を見てきて、凛さんの言っていたトップアイドルだったということが本当だったんだってことにやっと気づいたんです。あれからテレビ番組やラジオにゲストとして呼ばれた時も、初めてのメディア出演ということを感じさせないような堂々とした姿は、何度も出演していたんだなって私でも感じました。ダンスも、相当練習しなければ出来ないようなステップ、キレのある踊り。歌に限っては、透き通るような声で新人アイドルとは思えないようなすばらしさ」
「そんなに、私を褒めてもの何もでないわ。でそれがどうしたの?」
そう言うと、ゆかりは私の手を強く握って言った。
「そんな姿を見て、凛さんのようなアイドルになろうって私強く思ったんです! 凛さんみたいに、何をやっても完璧にこなせるようなアイドルになろうって。でも、そんなに簡単なことじゃないことは分かってるんです。どうすれば、凛さんに近づくことが出来るのか。それが私の今の悩み事です!」
「ちょっと!」
私はゆかりの手を払い、距離を取った。
「落ち着きなさい」
「ご、ごめんなさい」
少しもじもじしている彼女を見ると、私に伝えるのが恥ずかしかったのだろう。
しかし私はそれを聞いて少し複雑な気持ちになり、彼女が心配になってきた。
凛のようになりたい。この言葉はファンの子供たちに何度も言われたことがある。それはとてもうれしいことだが、正直私は誰かの憧れの存在になるような人間ではない。アイドルとして活動していくにあたって、自分の立ち位置だけが全てになり、いつしかファンの存在を忘れ、自己満足のためにアイドルとして頑張っていく存在になっていった。そんな私を目標にするなんて。
「ゆかり聞いて、誰かを目標に頑張っていくのはとてもいいことだと思う。でも、アイドルとしてトップになるためには、追いかける側の存在でいては駄目なの。目指しているところが同じなら、競い合っている存在を追い越して行かなくてはならない。それが私であろうと誰であろうと。それに私になるように努力しても成長することは出来ないわ。アイドルをするのはゆかり自身なんだから」
「そんな、でも、例えそうだとしても、私は凛さんを目標に頑張るんだから!」
そう言うと、ゆかりは事務所から出ていった。
彼女は本気で私になりたいのだ。
それから一週間近く私たちは行動を共にしていたが、あの時の話題にはお互い触れないでいた。ゆかりも、今までと同じように接してくれているが、まだ、私になろうと、努力しているらしかった。歌のうたい方や、踊りかたなどが、少し私に似ている。
ただ、それによって、彼女らしさというものが段々と無くなってきていることにも気が付いた。
完全にゆかりらしさが無くなっていた。
そのことに気付いていたのは私だけではなく、他の人たちもそうだった。
レコーディング最終日、音響スタッフの人があることをゆかりに言ったのだ。
「ゆかりちゃん、最初のころと歌い方変わったね」
「はい、少し大人っぽく歌うようにしてるんですが、駄目でしたか?」
「いや、別に問題があるわけじゃないんだけど、この曲のイメージだとその歌い方は合わないんじゃないかなと思ってね」
「そうですか……?」
「この曲は、元気いっぱいって感じの明るい曲だからね。レコーディング初めのころの方が、この曲のイメージに合う歌い方が出来てたと思うんだよね。ゆかりちゃんの歌だから歌い方とかは本人が決めていいんだけど、歌詞の意味を理解したり、曲のリズムに合わせて歌った方が、聞いてる人にゆかりちゃんの気持ちが伝わりやすいんじゃないかな」
「分かりました、少し考えてみます」
ゆかりは笑顔を保ってはいたが、彼女らしさがなくなったという言葉は、彼女を少し傷つけてしまったのかもしれない。
次の日ゆかりは事務所に顔を見せなかった。本間さんに話を聞くと、多忙なスケジュールにより熱を出したということだった。おそらく嘘だろう。でもゆかり自身、自分の気持ちや考える時間が必要である。私はそう解釈をしてアイドル活動に取り組んだ。
「おはようございます!」
次の日、彼女は元気よく事務所にやってきた。とても大きな声であいさつをしている。
「ゆかり、熱はもう大丈夫なの?」
「大丈夫。凛さん私、あなたに謝らなくちゃならないことがあって……」
「謝らなくちゃならないこと?」
「はい、この前相談したことで、凛さんのようなアイドルになりたいって言ったんですけど。凛さんが私に言ってくれた言葉の意味がようやく分かりました。凛さんを目指して頑張っても、結局は凛さんの真似でしかないんですよね。それによって自分の個性が失われてしまったら何も残らない。自分自身がアイドルになれないんですよね。それに、私を応援してくれるファンのみんなは、アイドルとしての私を応援してくれている。その声援に答えられるのは私だけなんですよね。誰かの真似をしている偽物の私じゃなくて、本当の私を」
彼女は理解がとても早い。もう少し長い時間を悩むと思ったが、想像以上の早さである。誰かに相談でもしたのだろうか。
ポジティブに物事が考えられるというのはとてもうらやましいことである。
「別にあなたが謝ることは無いわ。そのことに気付いてくれただけで、私は十分だから」
ゆかりはとてもいい笑顔をしている。ゆかりが自分の過ちに気付いたことによって、新しい彼女に生まれ変わることが出来たのだろう。新人アイドルとして、良い経験になったのではないだろうか。
それからのゆかりは彼女が持つ個性を発揮し人気が徐々に出始めている。この結果は、彼女自身が自分を変えることが出来たからこそ得られた事だと、私は強く思う。
輝くステージへ
4
私たち二人の曲が発売されたのは、私がこの世界に来てから三か月経った頃だった。この世界での生活にも慣れまた、アイドルとしても世間に名前が知れ渡り、元いた世界と同様の忙しさになってきた頃、私たち二人に大きな仕事が舞い込んできた。それは、この世界で人気の音楽番組のスペシャルライブへの参加依頼だった。
「私がこんなに有名な音楽番組に出れるなんて! しかも特番ということは、大きな舞台で歌うことが出来るんですね」
ゆかりはとてもうれしそうに本間さんに聞いた。
「そうだな、ここの番組はスペシャルの時は殆どスタジオを飛び出して、大きなライブ会場で行っている。今回も外の野外ステージでやることになるんじゃないかな」
「これは、落ち着いていられないかも! ちょっとジョギングしてきます!」
そう言ってゆかりは事務所から出て行ってしまった。
本間さんはそんなゆかりを見届けた後に私に向かって言った。
「君がこの事務所に来てから、三か月経つけど、その短い期間に色んなことがあった。まさか、ゆかりがテレビに出て、大勢の人の前で歌うことになるとは、私も彼女も想像していなかったと思う」
「私もこんなことになるなんて、三か月前は思っていませんでした。でも今はこの世界に来てとても良かったと思うんです。自分の存在がない世界で、アイドルとしてゼロからスタートする。今までと同じように一人で努力する方法もあった。けれど、誰かと一緒に努力する大切さや、ファンを笑顔にすることの大切さ、自分では気付くことの出来なかった未熟さをゆかりさんが私に思いださせてくれたんす。トップアイドルを目指す過程で忘れてしまっていた、新人アイドルの時の気持ちを改めて気付かせてくれたのです」
「じゃあ、この世界に来て結果的には良かったのかもしれないな」
本間さんはそう言うと、笑顔で笑っていた。
音楽番組の特番は再来週の週末に行われる。それまでに、ライブで披露する曲の最終確認をするため一度テレビ局に伺わなければならない。
本間さんとゆかり、私の三人でテレビ局に向かうと私たちは控室に案内された。
「ちょっと俺は番組スタッフと話をしてくるからここにいてくれ。あと、隣の楽屋に、トップアイドルの園田智恵理さんが来ているみたいだから、あいさつするのを忘れないようにね」
そう言って、本間さんは控室から出ていった。
「え! トップアイドルの園田智恵理さんがここに来ているの! 一度会ってみたかったんだ」
ゆかりはそういうと、自分の鞄の中から紙とペンを出しはじめた。
「それは置いていきなさい。その、園田智恵理さんって人はこの世界のトップアイドルっていうことでいいのかしら?」
「そうだよ、アイドルの中のアイドル! 歌も踊りも上手で、かわいくて、全てが完璧なアイドルです」
「私も会ってみたいわ。ゆかりさん、挨拶に行きましょうよ」
この世界のトップアイドル、とても興味がある。私はゆかりと一緒に挨拶に行くことにした。
「失礼します、私たち大谷プロダクションの星空ゆかりです」
「斎条凛です。音楽番組の特番に出演することが決まりました。よろしくお願いします」
「園田智恵理です。よろしくお願いします。あなたたち、最近有名になった新人アイドルですよね。会えてうれしいわ」
「私も、智恵理さんに会えてとてもうれしいです」
「ゆかりさんに凛さん、あなた達の活躍はテレビで見てますよ。二人とも、歌やダンスが上手ですよね。特に凛さんは新人アイドルとは思えないほどのオーラの持ち主よね」
「凛さんは、何をやっても完璧にこなしてしまう、凄い人ですからね」
「ゆかり、そろそろ、マネージャーさんが控室に帰ってくる頃よ。智恵理さんに迷惑掛けてしまうからそろそろ行きましょう」
「そうだね。すいません、失礼しました」
「お仕事一緒に頑張りましょうね。ゆかりさん、凛さん」
控室に戻ると、ゆかりはサインをもらい損ねたことにショックを受けていた、注意したはずなのだけれど。
彼女に会ってみて分かったことは智恵理さんが只者ではないことである。私を見ただけで、新人アイドルではないことを見破っていたのだから。もちろんこの世界でも、私が狙うのはアイドルとしての高み。トップアイドルになるためには、いずれ彼女を超えなくてはならない。
「相当厄介な相手が出てきたわね」
私はここに来て初めて危機感を覚えた。
それから一週間、私とゆかりはたくさんの練習を重ね、しっかりと準備をした。
そして特番当日を迎えた。
多くのアーティストに挨拶を終え、自分たちの楽屋に戻ってくる。
「わたし、もう疲れたよ」
「ゆかりさん、まだ番組始まってないのよ」
弱音を吐くゆかりに私はそう言い私は曲順の書かれた冊子を見てみる。私たちの出番の確認である。
「私たちの出番は……あった! 智恵理さんの次だって」
「なんか、アイドル対決みたいな演出で曲を披露するみたいだよ、ゆかり勝てる気がしないんですが」
「また弱音なんて吐いて、いい? アイドルとしてトップに立つためにはいつか智恵理さんを超えなくてはならないの。今はまだ駄目でも練習だと思って挑めばまたチャンスが巡ってくるわ」
私がそう言うとゆかりも、そうだね! と言って頑張ると宣言していた。
番組開始まであと一時間を切っていた。
「ゆかり! そろそろ支度して、出番が近づいてるわ」
順番的にはトップアイドルの智恵理さんの前のグループが歌っている頃である。衣装などの最終確認をしてステージの袖にスタンバイする。
「智恵理さんはもうステージにいるみたいだね」
暗いステージの中に薄っすらと女の人の影が見える。
「そろそろだね」
ゆかりがそういうと、 ゆかりがそういうと、司会者の合図と同時にステージがスポットライトで光り輝いた。
バラードを歌う智恵理さんはライトに照らされてとても綺麗だ。私とが歌う曲とは全然違う。ただ、歌に自分の気持ちをのせながら力いっぱい歌う姿は、とてもかっこよく見える。
「これが、この世界のトップアイドル。歌を聞いてくれる人達に伝えようとする気持ちは私と変わらないけれど、それ以外は全然違う。智恵理さんはとても楽しそうでとても良い表情をしていた」
智恵理さんの素晴らしい歌につい聞き入ってしまった。私たち二人は、番組スタッフの呼びかけで我に返った。
「そろそろですよ、準備よろしくお願いします」
「はい!」
私たちのライブはすぐに幕を開ける。
目の前に広がるのは大勢の人達。そして、私たちを照らすスポットライト。
トップアイドルだった頃のことがフラッシュバックされる。ポップでキュートな歌詞にファンへの感謝の気持ちを込めて歌うライブは新人アイドル時代以来である。
私がこの世界に来て、ゆかりに会って、自分の忘れていたアイドルとしてのあるべき姿を改めて認識することが出来た。これは私にとってとても大きな出来事であった。だからだろうか、トップアイドルステージに立っていた頃よりも歌うのが楽しく感じるのだ。今まで味わうことの出来なったこの気持ちに気付けたのはゆかりのおかげだろう。そして、智恵理さん。彼女の歌声は素晴らしかった。曲の歌詞に合わせた歌い方なのに、力強く、躍動感溢れる歌い方が出来る。これは私には出来ないことである。自分の上にはまだ上がいる。そのような存在がいることを認識出来たのは彼女がいたからである。
私たち二人の歌もそろそろ終わる。歌っている時の楽しさはこの時限り。つらい経験をしてきたからこそ味わえるもがあったのと同じように、楽しい経験をしたからこそ得られた新しい発見があることを知った。これからのアイドル生活、どんなことがあるかわからないけれど、トップアイドルを目指して頑張って行こう。今までとは違う、新しい自分で。
「凛さん」
ゆかりの掛け声で私たちは手をつなぐ。打ち合わせ通り、ここでジャンプをする合図だ。
「行きましょう! ゆかりさん」
「はい!」
曲の終わりと同時に二人でジャンプする。スポットライトの明かりで目の前が真っ白になる。
「ありがとう、ゆかり」
目を開けると、そこは保健室のような白い 目を開けると、そこは保健室のような白い部屋だった。窓からは日の光が差し込んでいる。
「ここは、病院?」
私は体を起き上がらせようとすると、聞き覚えのある声がドアの方から飛んできた。
「凛! 気付いたのね。良かったわ」
「マネージャー! ということは、帰ってきたんだ」
長年一緒にアイドル活動をしていたマネージャーの姿に私はほっとして 長年一緒にアイドル活動をしていたマネージャーの姿に私はほっとして泣き出してしまった。
「良かった、帰ってこれたよぉ、うう」
気分が落ち着いてから、 気分が落ち着いてから、どれくらい眠っていたのかを聞くと三日間ほど私は眠っていたらしい。そしてその間はライブの準備やステージ設営などの作業が全てストップしていることも聞いた。
「このまま、あなたが目覚めないんじゃないかと思って心配してたんだから」
そう言うマネージャーの目にも涙が光っていた。
「お帰りなさい、凛」
「ただいま、マネージャー」
「おい、証明の準備は出来てるか」
「出来てます、凛さんの準備は出来てますか」
「大丈夫です」
「よし、ライブを始めるぞ、ファンを待たせるんじゃない!」
暗いステージの上、見えるのは星空のように光る無数のサイリウム。一定のリズムで揺れる光は、毎晩車窓から眺めている夜空の星たちと同じくらい綺麗だ。私は今輝いているのだろうか。ちゃんとアイドルを出来ているのだろうかと悩んでいた時期もあるが、今回体験した不思議な出来事のおかげでそんな悩みはどこかに消えてしまった。ステージの上に立ち強く感じることは、とても楽しいということである。こう思えるようになったのは、多分ゆかりに出会えたからだろう。
シンセサイザーが鳴り響く。それと同時にスポットライトが私を照らす。会場のボルテージが上がる。
今私は会場の真ん中で、誰よりも強く輝いている。私はどの星にも負けないくらい、明るく輝いているのだ。
ブルーマウンテン(段々寝音)
頂点から落ちた日
1
私がアイドルとして目指すもの。それは、高み。
私は全てのアイドルを超える存在になる、なって見せる。だからこのライブで失敗することは絶対に許されない。
幕の向こう側には、たくさんの人達が待っている。
有名なファッションデザイナー、雑誌編集者、テレビ局の関係者、大手プロダクションの社長。
この機会を逃したら次のチャンスがいつになるか分からない。
「凛さん、そろそろ準備お願いします」
舞台そでに移動し、ファンたちの歓声を聞きながら、右手に持つマイクに力を入れる。
今までの努力を思い出す。つらいことしかほとんど経験してこなかったけれど、それは今日この舞台に立つための過程に過ぎない。
「証明、マイク、音響、準備出来ました」
「幕を開ける準備を! ファンを待たせないためにもすぐに始めるぞ」
「凛さん、幕を開けますよ」
「はい、よろしくお願いします」
今日、この時から私のアイドルとしての挑戦は始まる。この小さな舞台の開幕と同時に。
私は今輝いているのだろうか。ちゃんとアイドルが出来ているのだろうか。
私はふとそう思ってしまった。仕事も順調にこなしているし、アイドルとしての輝きが劣ってきている訳でもない。だからそんなことを考えることはないのに。
仕事終わりの車の中で、車窓から見える町の明かりを見つめながら、私は考えてしまう。暗闇に光り輝くいくつもの光源、その光は星のように、綺麗で美しい。
「凛、明日は朝から次のライブの打ち合わせが入っているから、寝坊しないように」
「大丈夫、遅れないようにする」
ライブという言葉を聞くと二年前のライブを思い出す。どうにかして有名になろうと必死になって練習した日々を思い出しながら、全ての力を出し切ったあの日。その結果、私は大手芸能プロダクションの社長の目に留まり、立派なアイドルとしてデビューすることになった。
あれから二年、今ではアイドルといえば斎条凛と言われるほど有名になり、トップアイドルの名をほしいままにしている。でも、それで満足してはいけない、ここで止まってはいけない。色々な人から持て囃され、羨ましがれ、騒がれる日々は別に嫌というわけではない。でも私が求めているものはこんなものではないのだ。私が目指しているものは、高み。ただそれだけだから。
「今日の仕事、お疲れ様」
一日の終わりがやってきた。今日もいつもと同じように夜景を見つめる。
「ねえ、凛。明日も厳しいスケジュールだけど、大丈夫かしら?」
「大丈夫、心配してくれてありがとう。でもなんで?」
私は車窓の外に輝くいくつもの星を見つめながら、マネージャーに問いかけた。
「最近の凛、なんだか少し無理をしているように見えてね。あなたのマネージャーになって、二年近く一緒にいるから。あなたの様子いつもと違うことぐらい、すぐに分かるわ」
「無理なんてしてないわ。だから心配しなくていいのよ」
心配するマネージャーに私は言った。
次の日の仕事は、来月行われるライブ会場の視察である。会場自体は結構前から決定していたのだが、私自ら会場に足を運ぶのは今日が始めてである。
大きなステージ、豪華な装飾、観客が入るスペース。野外に作られたステージは、大規模なライブというわけではないのに、やけに力が入っている。
「マネージャー、この会場やけに力が入っているわね」
「凛、何を言っているの。ここにいる人たちはみんな本気よ、誰一人力なんて抜いていないわ」
「そうね。だって私が出るライブなんですもの」
私は何を考えているのだろう、いつもそんなこと思わないのに。なんか、変。
「凛さん、音楽の準備が整いました。いつでもリハーサル出来るので、準備出来たら言ってください
「リハーサル? マネージャー、どういうことよ。今日は視察だけじゃないの?」
「そうなんだけど、これからのスケジュールを考えると、今一緒に行ったほうが、あなたにとっての負担も軽くなるんじゃないかと思って。あなたの練習着などもしっかり準備してあるわ」
「マネージャー、ありがとう」
私は、マネージャーの言うことに従った。確かにこれからのスケジュールは分刻みである。ライブに向けてのレッスンは当然のこと、雑誌のインタビューやラジオ、テレビなどに出演し、今回のライブを世間に宣伝しなければならない。そういうことを考えると、今ここで自分の体の調子や、ステージ上での演出、証明、音響の具合を確認するのもいいのではないか。と私は思ったからだ。私のスケジュールを確実に把握している彼女だからこそ思いついたことだろう。
「凛、ステージで踊る時は怪我に注意して。リハーサルをすることは、会場設営のスタッフの方たちに連絡はしているけれど、準備のために動いている人たちがいる。いつ何が起こるか分からないから、十分注意して」
「確認するけれど、私が踊っている時にステージには誰も上げないでよ。私の邪魔になるようなことは無いように」
「ええ、承知したわ」
私はステージの上に上り、深呼吸を一つ。
「初めて下さい」
スピーカーから流れ出す、シンセサイザーが特徴的なテクノ。ドラムマシンが奏でる単調な反復のビートにポップなメロディー。リズムに合わせたキレのあるダンス。
私の体は自然に動き出す。手を大きく動かし、足でステップを踏み。メロディーに合わせて歌う。五感を使って、私は音楽を奏でる。ただそれだけに集中して、必死に足掻く。
失敗はしない、たくさん練習したんだ、大丈夫、上手くいく。自分に自信をもって、次のステップを踏もう。そう自分に言い聞かせ足を動かした時、自分の体が前のめりになり、宙を浮いた。目の前には地面が見える。
「あっ」
そしてスイッチを切ったようにパチッと目の前が真っ暗になった。
凛――起きて、凛――
この声……マ、マネージャー……。
私は少しずつ、閉じていた目を開けた。白い天井がぼんやりと見える。でも私には見覚えのない部屋、誰かが私をここに運んできてくれたのだろうか。
「マネージャー……かな? 確か私、ステージの上から落ちたんだっけ」
横たわっていたソファーから起き上がる。
まだ少し体に痛みが走るが、歩けないほどではない。
「これなら、マネージャーのいる所まで行けるかも」
扉のほうまで行こうとした時、一人の女の子が部屋に入ってきた。そして、私を見るなり大声を上げて近づいてきた。
「体の方は大丈夫ですか! 痛い所とか、気になる所とか」
「特にないわ、でも少し痛みがあるかも。ねえ、聞きたいんだけど、ここどこかしら?」
「ここは私が所属する事務所の休憩室です」
「え? 今事務所って言った?」
「はい。私が所属している芸能プロダクション、大谷プロダクションです」
太谷プロダクション? そんな名前聞いたことない。
「そのような名前は聞いたことないのですが」
「ああ、小さな事務所なので知名度があまり無いのかもしれませんね、あ、私、星空ゆかりと言います! この事務所で新人アイドルをしています! よろしくお願いします!」
このゆかりという子はアイドルらしい。聞いたことのない名前なのは、彼女が新人アイドルだからだろうか。それにしても、元気な子である。
「わ、私、マネージャーさん呼んできますね。ちょっと待っててください!」
そう言ってゆかりは部屋の外に飛び出していった。
ゆかりがマネージャーを呼んでくるのにそんなに時間はかからなかった。彼女のマネージャー、本間さんは、ピシッとスーツを着こなしている二十歳半ばの男性。とても真面目そうに見える。
「怪我とかないですか」
「ええ、大丈夫です」
「いやぁ、ゆかりから話を聞いた時は驚きましたよ、公園で女の人が倒れてるなんて言うものですから。無事に目が覚めて本当に良かったですよ」
「ゆかりも驚きましたよ!」
ちょっと待って、それはどう考えてもおかしい。
私はさっきまでライブ会場にいたはず。でも二人は公園で私を見つけたと言っている。
「あ、あの、私さっきまでライブ会場にいたんです。今度行われるライブのリハーサルをしていて、その時にステージから落ちてしまって……それで目が覚めたらここに……」
「何を言ってるんですか、あなたが倒れてたのは公園ですよ。あそこにはライブ会場なんてありませんでしたし、そんなスペースもありません」
「うーん、それもそうだな。あと、君は歌手かな? ライブ会場でリハーサルを行うということは、私たちと同じ芸能関係に携わっているということにもなるけど……そうだ、名前を教えてくれないか」
その質問に私は驚いた。世間では「アイドルと言えば斎条凛!」という言葉が生まれるほど、私の人気は絶大で、私の顔を知らない人はいないはず。ましてや芸能関係の仕事をしているのに、私のことを知らないのは少し問題があるのではないだろうか。
そう思いながらも私は自分の名前を二人に言った。
「私はかの有名なアイドル、斎条凛です」
「斎条……凛? 聞いたことないな」
「ゆかりもです。アイドル関係の雑誌やニュースは欠かさずチェックしていますが、そのような名前は聞いたことがありません」
そんな馬鹿なことはないだろう。雑誌にも載ってないなんて。
「ゆかりさんその雑誌、見せてもらえないかしら」
「いいですよ、これです」
よく見かける芸能雑誌、でも見たことのない名前。中には男女問わず、様々な人物の写真が掲載されているが、私の知っている人物は一人もいない。ましてや、斎条凛という名前も載ってはいなかった。
「こんなこと、まるで私が存在してないみたいじゃない」
私は雑誌をもう一度雑誌を見直したが、私のことは何一つ書かれていない。
「嘘よ、こんなの嘘よ」
私はその場に座り込んでしまった。
「凛さん! 大丈夫ですか」
「大丈夫なわけないじゃない。今までに積み上げてきたものが一瞬で水の泡よ!」
私はゆかりにそう訴えた時、本間さんが口を開いた。
「凛さん、あなたがアイドルだということを証明する事は出来ますか? もしそれが出来るのであったら、私たちに見せてください。証明の仕方は何でも構いません」
「なんでも、ですか?」
「はい。あなたがアイドルだったのならば、証明の仕方はたくさんあるはずです。必要ならば、それに必要な準備もしましょう。あなたがそこまで主張してるのです。私たちにそれを証明してください」
「分かりました。私をオーデションに出してください。絶対に合格して見せます!」
私は立ち上がり、本間さんに強くそう言った。
ゼロからのスタート
2
私が事故に遭ってから五日ほど経った。あれから、インターネットなどで私の情報を調べようと試みたが何も出てこなかった。また私の所属しているプロダクションも調べたが出てこなかった。この世界には、私に関する情報が何一つ存在しないのだ。信じたくはないが、信じることしか私には出来なかった。
本間さんからオーディションを受ける準備が出来たと知らされたのは、そんな時だった。
「イメージキャラクターを決めるオーデションですか?」
「その通り。これは今度新しく発売されるお菓子のイメージキャラクターの募集だ。新人アイドル対象のものだから、君にとっては簡単かもしれない。それでもしっかりと、イメージキャラクターの座を手に入れるんだぞ!」
「分かりました、頑張ります」
「うむ。スケジュールの方はまた後日連絡するからな」
「はい、よろしくお願いします」
「それと、このオーデションにはゆかりも参加する。負けないようにね」
本間さんはそう言うと、休憩室から出て行った。
新人アイドル対象オーデション。まさかトップに輝いた私がこのようなものに出ることになるとは、五日前までは想像も出来なかったことだろう。でも、本間さんの前で自分から言い出したこと。自分がトップアイドルであること、ここで証明してみせる。
「凛さん、やっと見つけました」
息を切らしながら、ゆかりが部屋に入ってきた。
「どうしたんですか、そんなに急いで」
「それはオーデションまで時間がないから、凛さんと一緒に練習しようと思って!」
「私と一緒に練習ですか? でもなんで私なんかと」
「それは私が、凛さんと一緒に練習したいからですよ!」
そう言ったゆかりの顔は弾けるような笑顔で輝いていた。
「ゆかりさん、練習するって言ってませんでしたか?」
「うん、そうだよ」
「じゃあなんで、目の前に沢山のお菓子がおいてあるんですかね?」
ゆかりに練習しようと言われて、連れてこられた場所には、山のように詰まれたお菓子が置いてあった。
「ここに置いてあるお菓子は、今回オーデションを受けるお菓子会社のものです。ここのお菓子はおいしい物が多くて、年代問わず、多くの人たちに愛されている商品が多いんです。ここに準備したのは、ロングセラー商品のチョコレートと、先月販売されたバニラ味のお菓子です」
「今からこのお菓子を食べるのか? そんなの練習でもなんでもないんじゃあ……」
私がそう言うと、ゆかりは口をぎゅっと結んで頬を膨らませた。
「練習ですよ! 大事な練習! もしかしたら、どれだけおいしくお菓子を食べられるか、見たいなチェック項目があるかもしれないじゃないですか!」
「例えなかったとしても、凛さんは食べておいた方が良いと思います。食べたことないですよね?」
確かに、私はこのお菓子を食べたことはない。というか、このお菓子についても詳しく知っている訳でもない。
「おいしく食べられるかなんて項目があるかどうかは分からないけれど、味を知らない状態でオーデションを受けるのは、高校入試で入学希望校の情報をまったく調べずに面接入試を受けるのと同じくらい無謀だと思うんです。だから凛さん、一緒に食べましょう!」
そう言うと、お菓子の箱を一つ開け、チョコレートを一つ口に運んだ。
「うん、ほっぺがとろけちゃうほどの美味しさ! 止まらなくなっちゃう! 凛さんも食べてください」
「じゃあ、一個だけ、ん! 美味しい」
「ふふ、ではこっちも、いただきます!」
「やっぱり、ゆかりが食べたかっただけなんじゃ……」
笑顔で私にお菓子を差し出す彼女の表情は、とても楽しそうで、華やかだった。
次の日もゆかりは、私の所に来て一緒に練習しようと言ってきた。
「今日は一緒にジョギングをしましょう」
「ジョギングならいいけど、今やってるストレッチが終わったらね」
ゆかりは分かった、と言って、練習ルームから出ていった。
なぜ、ゆかりは私と一緒に練習したがるのだろうか。私にはそれが不思議でならなかった。
私が新人アイドルとして日々の練習を頑張っていた頃は、黙々と一人で練習をしていた。自分のペースで決められたメニューを次々とこなしていく。自分の目標に向かって、夢に向かって、己を磨きあげるのに精一杯だった。
苦しいことが殆どのこの世界。私はただ、自分の将来の為に頑張ってきた。それに、ゆかりと私はライバルなのだ。同じオーデションを受けると言うことは、どちらか一人しか受からないということ。
そんな状況でも、彼女は私と練習したいと言っているのだ。
私にはどうしてもそこが理解できなかった。
ストレッチをすませた私は急いで外に出た。
ジョギングはゆかりがいつも走っているコースを通るようだった。
住宅街の中を走り地区で一番大きい公園を折り返し地点として来た道を戻る。道も平坦で、距離もそんなに長くはない。
ゆかりは、私の少し先を走っている。毎日走っているからだろう、息切れはしていない。一定のリズム、スピードで進んでいく。そんな時、一人のお婆さんがゆかりに声をかけた。
「ゆかりちゃん、今日も走ってるのかい」
「はいっ、今度オーデションがあって、それに出るために走ってます!」
ゆかりはそのお婆さんの前で立ち止まると、笑顔で話し始めた。
「そうなのかい。私には良く分からないけれど、ゆかりちゃんは頑張り屋さんだからね。きっと上手くいくよ」
「本当ですか! ありがとうございます。私、絶対合格します」
おばあさんはその言葉を聞くと、挨拶をして私たちと反対側に歩いていった。
折り返し地点の公園まで行くのに、ゆかりは沢山の人と会話をしていた。さっきのおばあさん以外にも、子供や、買い物帰りのおばさん、それに野良猫まで。ゆかりは、誰に対しても笑顔で、優しく接していた。どうしてゆかりは、自分の練習中なのにも関わらず、他人に邪魔されてあんな笑顔をしていられるのだろうか。なんであんなに楽しそうなのだろうか。私にはとても考えられないことだった。
「凛さん、公園に着いたので少し休憩しましょう」
走り出してから約四十分。私とゆかりは無事、折り返し地点の公園に着くことが出来た。ゆかりが道中、色々な人達と会話していたため、着くのが少し遅れてしまった。
公園内のベンチに腰を下ろし、自動販売機で買ったスポーツ飲料水を口に含む。
「凛さん、大丈夫ですか?」
私の横に腰を下ろしたゆかりは、私の顔を覗き込んでそう言った。
私は、そんなに疲れてはいない。ただ、さっきのゆかりの笑顔について、私は少し考えていた。
「大丈夫。心配してくれてありがとう」
ゆかりはその言葉を聞くと、私に笑顔を向けた。
「うん。でも、言いたいことがあったら何でも私に言ってね」
そう言うと、彼女はベンチから立ち上がった。
「じゃあ、一つ聞いていいかしら」
ゆかりは、私の方を振り向いた。
「なんでゆかりは、いつも笑顔でいられるの?」
私の言葉を聞いたゆかりは、驚いた表情を見せた。
「凛さんは、何でそんなことを私に聞くのですか?」
「私は笑顔で練習したことがないから」
私はアイドルとして、高みを目指すため、今まで努力をしてきた。アイドル育成教室に小さい頃から通い、歌、踊り、劇、スポーツなどに汗を流した。教室には数十人の子供たちがいる。でもみんなライバルなのだ。共に戦う戦友ではない。誰もが一番になろうと、考え、行動し、何人ものライバルを蹴落としていく。そんな状況下でも数名で固まり仲良く活動している子経ちもいた、でもそんなに長くは続かなかった。仲良くなってもライバルなのは変わらない。そして、みんながみんなアイドルになれる保障はどこにもない。弱肉強食。この世界は醜く、重たい、シビアな世界なのだ。
「私があなたのような新人アイドルをやっていた時、塾みたいな教室で歌やダンスを習っていたの。ゆかりのように、アイドルとして輝きたいと夢見ている子供たちが沢山いた。でも、みんな笑顔だったのは、初めだけ。ここに来て私達が思い知らされたのは、仲間達と争い、蹴落とし合い、騙し合いの耐えない、恐ろしい世界だということ。そしてアイドルのシビアな世界には、友情も、楽しさも、何もかも存在しないということ。私がトップアイドルになれたのは、そんな厳しい世界で生き残っていくために、仲間を作らず、周りに目を向かず、自分のためだに日々練習を重ねていく。弱音を吐いたら、そこで試合終了。自分を助けてくれる仲間なんてここにはいない。苦しいことや悲しいことが多すぎて、辞めようと思ったけど、自分の夢のために努力した。だからトップに立てた。少なくとも、そういう辛い過去があったからこそ、今の私があると思ってる」
「凛さん」
「あなたがとても楽しそうに練習してたから、自分の過去と比べてしまっただけだから、そんなに気にしなくていいよ」
「アイドルって厳しい世界なんですね、私の思っていた以上に」
ゆかりは私の横で顔を下に向けた。もしかしたら、私の思っていたことを一方的に話してしまったために、ゆかりのアイドル活動を、今のゆかりを、いつの間にか否定していたのかもしれない。彼女に謝らなくては。
そう思って、ゆかりに話しかけようとした時、彼女はベンチから立ち上がり笑顔で私の方を向いた。
「そろそろ帰りましょう」
来た道と同じ道を走る。私はゆかりが落ち込んでいるのではないかと少し心配していたが、来た時と同じように多くの人達と会話をしながら走っていた。
事務所に帰り着替えを終えた時、ゆかりが私に声を掛けてきた。
「凛さん、ちょっと私と来てくれますか?」
ゆかりに連れられてきたのは事務室だった。
「なんで私をここに連れてきたの? もしかしてさっきのことで怒ってたりとか……?
「実はですね、凛さんに見てもらいたいものがありまして」
「え? 見てもらいたいもの?」
ゆかりは、事務所にある本棚から、大きく分厚い本のようなものを取り出した。
「これは?」
「私の、アイドルとしての活動をまとめた資料兼アルバムです。この中に、今まで培ってきた私の努力が全て詰まってます」
ゆかりが中を開くと、そこには彼女の思い出でいっぱいだった。
「これは、二年前に行われた町内会のお祭りをお手伝いした時の写真ですね。本番は子供たちと一緒に盆踊りしたり、屋台で射的したりしました。あ! これは、奉仕作業のボランティア活動の時の写真です! 懐かしいなぁ」
ゆかりは、昔の思い出を語りながらページをめくっていく。しかし、何枚かめくった時、そこに笑っているゆかりの姿はなかった。
他の写真よりも大きいその写真には、ゆかりの横に一人の女の子が写っている。二人の後ろには、「まゆちゃん、お誕生日おめでとう]と書かれた垂れ幕が吊るされていて、鮮やかな飾りが施されている。まゆちゃんとはゆかりの友達だろうか、それとも……。
「凛さんには、アイドルとしてお互いを高めあえる仲間がいましたか?」
「え?」
「私には、仲間がいました。この写真にはまゆと私しかいませんが、このほかにも五人いたんです。でもみんな辞めちゃいました。勉強とか家の都合とかでこの世界から引退していったんです。でも絶対にそれだけが原因じゃない。凛さん、どうしてだと思いますか?」
「そんなこと、急に聞かれても」
私がそう答えると、ゆかりはアルバムを閉じた。
「実は全然有名になれなくて、活動も写真にあったようなボランティアのようなことしかしたことないんです。本間さんは、汗水流しながら仕事を持ってきてくれるんですが、自分たちの実力不足で合格出来なくて。そんな状況で自分の夢を諦めていった仲間が私にはいたんです」
私はそれを聞いて腕を組む。
「それが、アイドルの世界、厳しい世界なのよ」
ゆかりは静かに顔を横に降り、言葉を続けた。
「でもある時、まゆが私に言ったんです。今はまだ有名になるような仕事が私たちの元に舞い降りて来なくとも、諦めなければチャンスは必ずやってくる。だから、ボランティアのような仕事ばかりでも、手を抜いたりしては絶対にいけない。それに私達が活動したことによって、町の人たちはとても喜んでくれる。笑顔になってくれる。これって、私達がステージ立って、沢山の人達を笑顔にさせるのと、同じことなんじゃないかって。だから、一緒に頑張ろう。一人でも多くの人を笑顔に出来るようにって」
「まゆっていう子はゆかりにとって、大切な存在だったんだな」
「はい、でも……まゆは家庭の事情でアイドルを辞めてしまいました。仕方ないことだけど、正直寂しかった。でも私はそのことをまゆには言いませんでした。私は彼女に絶対に有名になる、今まで自分の夢を諦めていった人達の分もまゆの分も含めて有名になる。だから私は諦めないって伝えました」
ゆかりはそう言って、アルバムを元あった場所に戻した。
私は、自分が見てきた世界がすべてだと、心の中で決めつけていたのかもしれない。ゆかりには彼女のアイドルとしてのやり方があり、誇りがあり、物語がある。それは私も同じ。めざすものは同じでも、進み方は沢山あるということを、私はゆかりに教えてもらったのかもしれない。
次の日もゆかりは私と一緒に練習しようと言ってきた。なぜそんなに、私と一緒に練習したいのかと聞くと、二人でやった方が自分では気付かないようなことに気付けたり、お互いで高め合うことが出来るなどの利点が多いからと彼女はそう言った。ゆかりからそんなしっかりした考えが出てくるとは当然思えない。おそらくまゆから言われたことだろう。
ゆかりは、一人でやるよりも二人でやった方が絶対に楽しいとも言っていた。この数日間、ゆかりとやった練習はとても楽しかったのも事実だ。ここは、彼女のやり方で、もう一度アイドルの高みをめざすのもいいかもしれない。
「ゆかり、これから一緒にがんばろうね」
「急にどうしたんですか凛さん。私はいつも頑張ってますよ?」
「そ、そうね、そうだったわ」
そして、オーデションの日がどんどんと迫ってくるのだ。
私とあなた
3
「凛ちゃんこっち向いて!」
「インタビューいいですか?」
カメラのフラッシュがとても眩しい。あちらこちらから、私の名前と質問が飛んでくる。そんなに大きくない会場に多くのマスコミが集まっている。こんな光景は久しぶりである。
今私がいるここでは、新しく発売されるお菓子の発表会行われている。そんなところになぜ私がいるのかというと、先日行われたイメージキャラクターのオーデションに合格したからである。
これのおかげで、本間さんにも私がアイドルだったということを証明することが出来た。
私という存在がないこの世界に来てから、一か月経った。この期間でここが私の知っている世界でないことは、十分に分かった。総理大臣が女性であることや、日本の首都が東京都ではなく、京都府であるなど、このような状況であると嫌でもここが違う世界であると思わなければならないのだ。元の世界に戻る方法は分からないが、それが分かるまではここで生きていかなくてはならない。
今回のオーディションに合格したことにより、私の知名度は一気に広がった。有名なお菓子会社のイメージキャラクターという条件が良かったこともあるが、今まで努力してきたことが今回の結果に結びついたに違いない。
イベントの終了後、本間さんの車の中で、私はふと、窓の外を見た。まだ明るい夕方の空にきらりと輝く一番星が見える。
「凛さんがこんなにメディアに注目されるとはね、さすがトップアイドル」
車を運転している本間さんが言った。
「今までの努力の結果ですよ。あと、もうトップアイドルではありません」
「え?」
「私はまだ、スタートラインから走りだしたばかりです、今までの栄光が通用しない世界でトップを目指すために」
「分かった。凛さんがこの世界でトップに立てるように、しっかりバックアップするから」
「はい、本間マネージャー」
「凛さん、私、心配なんです」
ゆかりが私にそう言ってきたのは、発表会が終わってから一週間が過ぎた時だった。
私のメディアへの露出が多くなり、事務所の名前が世に知られるようになったため、ゆかりにも仕事の依頼やオーデションへの誘いが多くなった。このことに関しては、ゆかりも本間さんも、とても喜んでいたが、いざ仕事に取り掛かってみると初めてやることが多すぎて、何をやったらいいのか分からなくなってしまいそうだ。そして今日も、分からないことについて私に質問をしにきたのだろう。
「実は、私にコマーシャルの仕事の依頼が来たんですが……」
コマーシャルか、それなら簡単そうだな。と私は思った。
「コマーシャルってそんなに難しくないよ。まあ演技を磨いてる人じゃなきゃ厳しいかもね」
「コマーシャルなんですが、その、歌の方で……」
「歌?」
ゆかりが言うには、コマーシャルで流れる曲を担当するらしい。アイドルらしい仕事がやっと舞い降りてきたのはいいが、歌を歌う仕事は初めてらしい。そこで、歌を歌う時のアドバイスを私に聞きに来たわけである。
「いちを、ボイスレッスンはしてきたのですが、いざ、このような仕事がやってくると、今までの練習だけで良かったのかどうか、不安になってしまって」
「不安……ね」
私も初めて人前で歌をうたった時は、自分の歌に自信が持てなくて不安だった。でも聞いてくれている人達が笑顔になったのを見たら、そんな悩みはどっかに消えていた。だからゆかりもそんなに心配することはないと思うんだけど。
「うん、じゃあ、歌の特訓しかないじゃない」
こういうことは、歌ってみなきゃ。ということで、私はゆかりにそう提案してみたのだ。するとゆかりは目をキラキラと輝かせながらはしゃぎ始めた。
「ということはカラオケですね! 行きましょう! 行きましょう!」
ゆかりが歌う曲は、この世界で名の知れているアイドルの曲が多かった。私がライブで歌っている曲は、テクノやダンスミュージックといった、クール系の楽曲なのに対し、ゆかりが歌うのはキュートでポップな可愛らしい楽曲が多い。また日ごろからボイスレッスンを行っているため、歌も下手なわけではない。
「ゆかりさん、自分にもっと自信を持ってもいいわ。音が外れている訳でもないし、歌の歌詞をよく理解して歌ってるから」
「本当ですか! でもまだ私には足りないものがあるんです」
ゆかりは自分の歌を完璧にしたいのかしら。
この時の私にはまだゆかりの悩んでいることがよく理解できていなかった。
数日後、私は本間さんに呼び出された。本間さんは、ゆかりが歌う曲の制作をするにあたり、私が歌う曲も一緒に作るかどうかを聞いてきた。
「どうかな、このタイミングに凛さんのソロ曲を作ろうと思うんだけれど」
「とてもうれしいお話、ありがとうございます。曲を作るにあたって、どのようなジャンルの曲になるのか、もうお決まりになられたのでしょうか」
本間さんは少し考えてから話し始めた。
「今回作曲をしてくれる人は、可愛らしい曲を多く作ってる。アイドルが歌うような、可愛らしい詩を書くのが得意なひとだからね。おそらく、凛さんの曲もそういう曲になるんじゃないかな」
自分の持ち歌とは違うジャンルの曲を歌う。今までこのようなジャンルの曲を聞いたことがあまり無かったが、新しいスタートを切った私には丁度良い機会である。
「分かりました。よろしくお願いします」
それから少したって完成したデモテープが送られてきた。
「二人にはこれからボイスレッスンや、レコーディング、CDの即売会など一緒に行動してもらうことになる。忙しいが、嬉しいことにイメージガールの件から二人とも仕事が入ってくるようになった。別々のスケジュールで行動していたが、俺がどうにか調節をしたからそこは気にしなくていい」
「ありがとうございます」
「頑張って、歌うたいます!」
ゆかりも今まで以上に力をいれているようだった。
「今日のレコーディングお疲れ様」
二日目のレコーディングが終わった時、私はゆかりにあることを聞いた。それは、以前カラオケに行った時のように緊張せず、しっかりと歌を歌えているかということだ。
「私が聞いた感じ、変に音程が外れているとか、そういう問題はないんだけれど、ゆかりがすごく悩んでいるみたいだったから心配で」
「歌のことはもう大丈夫。凛さんのおかげかも」
そういった、ゆかりの表情は少し曇っている。
「どうしたの、ゆかり」
私は気になったのでゆかりに聞いてみることにした。
「なにか、悩み事でもあるの? 話聞こうか?」
そういうと、ゆかりはしゃべりだした。
「実は私、凛さんがオーディションに合格してからの活躍を見てきて、凛さんの言っていたトップアイドルだったということが本当だったんだってことにやっと気づいたんです。あれからテレビ番組やラジオにゲストとして呼ばれた時も、初めてのメディア出演ということを感じさせないような堂々とした姿は、何度も出演していたんだなって私でも感じました。ダンスも、相当練習しなければ出来ないようなステップ、キレのある踊り。歌に限っては、透き通るような声で新人アイドルとは思えないようなすばらしさ」
「そんなに、私を褒めてもの何もでないわ。でそれがどうしたの?」
そう言うと、ゆかりは私の手を強く握って言った。
「そんな姿を見て、凛さんのようなアイドルになろうって私強く思ったんです! 凛さんみたいに、何をやっても完璧にこなせるようなアイドルになろうって。でも、そんなに簡単なことじゃないことは分かってるんです。どうすれば、凛さんに近づくことが出来るのか。それが私の今の悩み事です!」
「ちょっと!」
私はゆかりの手を払い、距離を取った。
「落ち着きなさい」
「ご、ごめんなさい」
少しもじもじしている彼女を見ると、私に伝えるのが恥ずかしかったのだろう。
しかし私はそれを聞いて少し複雑な気持ちになり、彼女が心配になってきた。
凛のようになりたい。この言葉はファンの子供たちに何度も言われたことがある。それはとてもうれしいことだが、正直私は誰かの憧れの存在になるような人間ではない。アイドルとして活動していくにあたって、自分の立ち位置だけが全てになり、いつしかファンの存在を忘れ、自己満足のためにアイドルとして頑張っていく存在になっていった。そんな私を目標にするなんて。
「ゆかり聞いて、誰かを目標に頑張っていくのはとてもいいことだと思う。でも、アイドルとしてトップになるためには、追いかける側の存在でいては駄目なの。目指しているところが同じなら、競い合っている存在を追い越して行かなくてはならない。それが私であろうと誰であろうと。それに私になるように努力しても成長することは出来ないわ。アイドルをするのはゆかり自身なんだから」
「そんな、でも、例えそうだとしても、私は凛さんを目標に頑張るんだから!」
そう言うと、ゆかりは事務所から出ていった。
彼女は本気で私になりたいのだ。
それから一週間近く私たちは行動を共にしていたが、あの時の話題にはお互い触れないでいた。ゆかりも、今までと同じように接してくれているが、まだ、私になろうと、努力しているらしかった。歌のうたい方や、踊りかたなどが、少し私に似ている。
ただ、それによって、彼女らしさというものが段々と無くなってきていることにも気が付いた。
完全にゆかりらしさが無くなっていた。
そのことに気付いていたのは私だけではなく、他の人たちもそうだった。
レコーディング最終日、音響スタッフの人があることをゆかりに言ったのだ。
「ゆかりちゃん、最初のころと歌い方変わったね」
「はい、少し大人っぽく歌うようにしてるんですが、駄目でしたか?」
「いや、別に問題があるわけじゃないんだけど、この曲のイメージだとその歌い方は合わないんじゃないかなと思ってね」
「そうですか……?」
「この曲は、元気いっぱいって感じの明るい曲だからね。レコーディング初めのころの方が、この曲のイメージに合う歌い方が出来てたと思うんだよね。ゆかりちゃんの歌だから歌い方とかは本人が決めていいんだけど、歌詞の意味を理解したり、曲のリズムに合わせて歌った方が、聞いてる人にゆかりちゃんの気持ちが伝わりやすいんじゃないかな」
「分かりました、少し考えてみます」
ゆかりは笑顔を保ってはいたが、彼女らしさがなくなったという言葉は、彼女を少し傷つけてしまったのかもしれない。
次の日ゆかりは事務所に顔を見せなかった。本間さんに話を聞くと、多忙なスケジュールにより熱を出したということだった。おそらく嘘だろう。でもゆかり自身、自分の気持ちや考える時間が必要である。私はそう解釈をしてアイドル活動に取り組んだ。
「おはようございます!」
次の日、彼女は元気よく事務所にやってきた。とても大きな声であいさつをしている。
「ゆかり、熱はもう大丈夫なの?」
「大丈夫。凛さん私、あなたに謝らなくちゃならないことがあって……」
「謝らなくちゃならないこと?」
「はい、この前相談したことで、凛さんのようなアイドルになりたいって言ったんですけど。凛さんが私に言ってくれた言葉の意味がようやく分かりました。凛さんを目指して頑張っても、結局は凛さんの真似でしかないんですよね。それによって自分の個性が失われてしまったら何も残らない。自分自身がアイドルになれないんですよね。それに、私を応援してくれるファンのみんなは、アイドルとしての私を応援してくれている。その声援に答えられるのは私だけなんですよね。誰かの真似をしている偽物の私じゃなくて、本当の私を」
彼女は理解がとても早い。もう少し長い時間を悩むと思ったが、想像以上の早さである。誰かに相談でもしたのだろうか。
ポジティブに物事が考えられるというのはとてもうらやましいことである。
「別にあなたが謝ることは無いわ。そのことに気付いてくれただけで、私は十分だから」
ゆかりはとてもいい笑顔をしている。ゆかりが自分の過ちに気付いたことによって、新しい彼女に生まれ変わることが出来たのだろう。新人アイドルとして、良い経験になったのではないだろうか。
それからのゆかりは彼女が持つ個性を発揮し人気が徐々に出始めている。この結果は、彼女自身が自分を変えることが出来たからこそ得られた事だと、私は強く思う。
輝くステージへ
4
私たち二人の曲が発売されたのは、私がこの世界に来てから三か月経った頃だった。この世界での生活にも慣れまた、アイドルとしても世間に名前が知れ渡り、元いた世界と同様の忙しさになってきた頃、私たち二人に大きな仕事が舞い込んできた。それは、この世界で人気の音楽番組のスペシャルライブへの参加依頼だった。
「私がこんなに有名な音楽番組に出れるなんて! しかも特番ということは、大きな舞台で歌うことが出来るんですね」
ゆかりはとてもうれしそうに本間さんに聞いた。
「そうだな、ここの番組はスペシャルの時は殆どスタジオを飛び出して、大きなライブ会場で行っている。今回も外の野外ステージでやることになるんじゃないかな」
「これは、落ち着いていられないかも! ちょっとジョギングしてきます!」
そう言ってゆかりは事務所から出て行ってしまった。
本間さんはそんなゆかりを見届けた後に私に向かって言った。
「君がこの事務所に来てから、三か月経つけど、その短い期間に色んなことがあった。まさか、ゆかりがテレビに出て、大勢の人の前で歌うことになるとは、私も彼女も想像していなかったと思う」
「私もこんなことになるなんて、三か月前は思っていませんでした。でも今はこの世界に来てとても良かったと思うんです。自分の存在がない世界で、アイドルとしてゼロからスタートする。今までと同じように一人で努力する方法もあった。けれど、誰かと一緒に努力する大切さや、ファンを笑顔にすることの大切さ、自分では気付くことの出来なかった未熟さをゆかりさんが私に思いださせてくれたんす。トップアイドルを目指す過程で忘れてしまっていた、新人アイドルの時の気持ちを改めて気付かせてくれたのです」
「じゃあ、この世界に来て結果的には良かったのかもしれないな」
本間さんはそう言うと、笑顔で笑っていた。
音楽番組の特番は再来週の週末に行われる。それまでに、ライブで披露する曲の最終確認をするため一度テレビ局に伺わなければならない。
本間さんとゆかり、私の三人でテレビ局に向かうと私たちは控室に案内された。
「ちょっと俺は番組スタッフと話をしてくるからここにいてくれ。あと、隣の楽屋に、トップアイドルの園田智恵理さんが来ているみたいだから、あいさつするのを忘れないようにね」
そう言って、本間さんは控室から出ていった。
「え! トップアイドルの園田智恵理さんがここに来ているの! 一度会ってみたかったんだ」
ゆかりはそういうと、自分の鞄の中から紙とペンを出しはじめた。
「それは置いていきなさい。その、園田智恵理さんって人はこの世界のトップアイドルっていうことでいいのかしら?」
「そうだよ、アイドルの中のアイドル! 歌も踊りも上手で、かわいくて、全てが完璧なアイドルです」
「私も会ってみたいわ。ゆかりさん、挨拶に行きましょうよ」
この世界のトップアイドル、とても興味がある。私はゆかりと一緒に挨拶に行くことにした。
「失礼します、私たち大谷プロダクションの星空ゆかりです」
「斎条凛です。音楽番組の特番に出演することが決まりました。よろしくお願いします」
「園田智恵理です。よろしくお願いします。あなたたち、最近有名になった新人アイドルですよね。会えてうれしいわ」
「私も、智恵理さんに会えてとてもうれしいです」
「ゆかりさんに凛さん、あなた達の活躍はテレビで見てますよ。二人とも、歌やダンスが上手ですよね。特に凛さんは新人アイドルとは思えないほどのオーラの持ち主よね」
「凛さんは、何をやっても完璧にこなしてしまう、凄い人ですからね」
「ゆかり、そろそろ、マネージャーさんが控室に帰ってくる頃よ。智恵理さんに迷惑掛けてしまうからそろそろ行きましょう」
「そうだね。すいません、失礼しました」
「お仕事一緒に頑張りましょうね。ゆかりさん、凛さん」
控室に戻ると、ゆかりはサインをもらい損ねたことにショックを受けていた、注意したはずなのだけれど。
彼女に会ってみて分かったことは智恵理さんが只者ではないことである。私を見ただけで、新人アイドルではないことを見破っていたのだから。もちろんこの世界でも、私が狙うのはアイドルとしての高み。トップアイドルになるためには、いずれ彼女を超えなくてはならない。
「相当厄介な相手が出てきたわね」
私はここに来て初めて危機感を覚えた。
それから一週間、私とゆかりはたくさんの練習を重ね、しっかりと準備をした。
そして特番当日を迎えた。
多くのアーティストに挨拶を終え、自分たちの楽屋に戻ってくる。
「わたし、もう疲れたよ」
「ゆかりさん、まだ番組始まってないのよ」
弱音を吐くゆかりに私はそう言い私は曲順の書かれた冊子を見てみる。私たちの出番の確認である。
「私たちの出番は……あった! 智恵理さんの次だって」
「なんか、アイドル対決みたいな演出で曲を披露するみたいだよ、ゆかり勝てる気がしないんですが」
「また弱音なんて吐いて、いい? アイドルとしてトップに立つためにはいつか智恵理さんを超えなくてはならないの。今はまだ駄目でも練習だと思って挑めばまたチャンスが巡ってくるわ」
私がそう言うとゆかりも、そうだね! と言って頑張ると宣言していた。
番組開始まであと一時間を切っていた。
「ゆかり! そろそろ支度して、出番が近づいてるわ」
順番的にはトップアイドルの智恵理さんの前のグループが歌っている頃である。衣装などの最終確認をしてステージの袖にスタンバイする。
「智恵理さんはもうステージにいるみたいだね」
暗いステージの中に薄っすらと女の人の影が見える。
「そろそろだね」
ゆかりがそういうと、 ゆかりがそういうと、司会者の合図と同時にステージがスポットライトで光り輝いた。
バラードを歌う智恵理さんはライトに照らされてとても綺麗だ。私とが歌う曲とは全然違う。ただ、歌に自分の気持ちをのせながら力いっぱい歌う姿は、とてもかっこよく見える。
「これが、この世界のトップアイドル。歌を聞いてくれる人達に伝えようとする気持ちは私と変わらないけれど、それ以外は全然違う。智恵理さんはとても楽しそうでとても良い表情をしていた」
智恵理さんの素晴らしい歌につい聞き入ってしまった。私たち二人は、番組スタッフの呼びかけで我に返った。
「そろそろですよ、準備よろしくお願いします」
「はい!」
私たちのライブはすぐに幕を開ける。
目の前に広がるのは大勢の人達。そして、私たちを照らすスポットライト。
トップアイドルだった頃のことがフラッシュバックされる。ポップでキュートな歌詞にファンへの感謝の気持ちを込めて歌うライブは新人アイドル時代以来である。
私がこの世界に来て、ゆかりに会って、自分の忘れていたアイドルとしてのあるべき姿を改めて認識することが出来た。これは私にとってとても大きな出来事であった。だからだろうか、トップアイドルステージに立っていた頃よりも歌うのが楽しく感じるのだ。今まで味わうことの出来なったこの気持ちに気付けたのはゆかりのおかげだろう。そして、智恵理さん。彼女の歌声は素晴らしかった。曲の歌詞に合わせた歌い方なのに、力強く、躍動感溢れる歌い方が出来る。これは私には出来ないことである。自分の上にはまだ上がいる。そのような存在がいることを認識出来たのは彼女がいたからである。
私たち二人の歌もそろそろ終わる。歌っている時の楽しさはこの時限り。つらい経験をしてきたからこそ味わえるもがあったのと同じように、楽しい経験をしたからこそ得られた新しい発見があることを知った。これからのアイドル生活、どんなことがあるかわからないけれど、トップアイドルを目指して頑張って行こう。今までとは違う、新しい自分で。
「凛さん」
ゆかりの掛け声で私たちは手をつなぐ。打ち合わせ通り、ここでジャンプをする合図だ。
「行きましょう! ゆかりさん」
「はい!」
曲の終わりと同時に二人でジャンプする。スポットライトの明かりで目の前が真っ白になる。
「ありがとう、ゆかり」
目を開けると、そこは保健室のような白い 目を開けると、そこは保健室のような白い部屋だった。窓からは日の光が差し込んでいる。
「ここは、病院?」
私は体を起き上がらせようとすると、聞き覚えのある声がドアの方から飛んできた。
「凛! 気付いたのね。良かったわ」
「マネージャー! ということは、帰ってきたんだ」
長年一緒にアイドル活動をしていたマネージャーの姿に私はほっとして 長年一緒にアイドル活動をしていたマネージャーの姿に私はほっとして泣き出してしまった。
「良かった、帰ってこれたよぉ、うう」
気分が落ち着いてから、 気分が落ち着いてから、どれくらい眠っていたのかを聞くと三日間ほど私は眠っていたらしい。そしてその間はライブの準備やステージ設営などの作業が全てストップしていることも聞いた。
「このまま、あなたが目覚めないんじゃないかと思って心配してたんだから」
そう言うマネージャーの目にも涙が光っていた。
「お帰りなさい、凛」
「ただいま、マネージャー」
「おい、証明の準備は出来てるか」
「出来てます、凛さんの準備は出来てますか」
「大丈夫です」
「よし、ライブを始めるぞ、ファンを待たせるんじゃない!」
暗いステージの上、見えるのは星空のように光る無数のサイリウム。一定のリズムで揺れる光は、毎晩車窓から眺めている夜空の星たちと同じくらい綺麗だ。私は今輝いているのだろうか。ちゃんとアイドルを出来ているのだろうかと悩んでいた時期もあるが、今回体験した不思議な出来事のおかげでそんな悩みはどこかに消えてしまった。ステージの上に立ち強く感じることは、とても楽しいということである。こう思えるようになったのは、多分ゆかりに出会えたからだろう。
シンセサイザーが鳴り響く。それと同時にスポットライトが私を照らす。会場のボルテージが上がる。
今私は会場の真ん中で、誰よりも強く輝いている。私はどの星にも負けないくらい、明るく輝いているのだ。
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

雨と一人
冬音-ふゆね-
SF
*あらすじ&作品説明*
1人が ただひたすらに
寂しさに 悲しさに
ついて悩む そして少年の悩みとは
悩んだその先に 何があるのか…
*注意*
〇1人と2人が出てきます!
〇一応SFです!
〇話はおもいです!
〇苦手な方は、読むのを、やめていいですよ!
〇1話完結です!

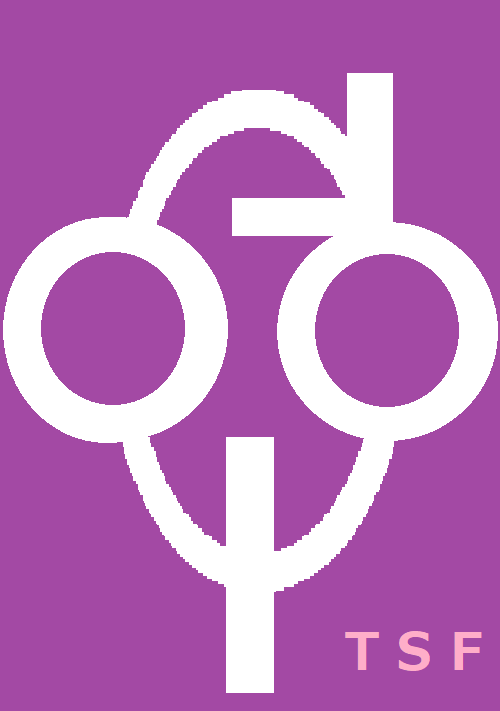

子供から目を離してはいけません
こうやさい
SF
ある日、目を覚ますと世界が滅んでいた。
帰省予定だったあたしはそのまま故郷に帰るために歩き出した。
町が瓦礫になる、人がいなくなるなどが苦手な方はお気をつけ下さい。
道中記ではありません。このオチが道中のいろいろが盛り上がった後にあったらたぶん腹立つ。
ああけど一度書いてみたいなぁ、道中記。
ただいま諸事情で出すべきか否か微妙なので棚上げしてたのとか自サイトの方に上げるべきかどうか悩んでたのとか大昔のとかを放出中です。見直しもあまり出来ないのでいつも以上に誤字脱字等も多いです。ご了承下さい。

母は姉ばかりを優先しますが肝心の姉が守ってくれて、母のコンプレックスの叔母さまが助けてくださるのですとっても幸せです。
下菊みこと
ファンタジー
産みの母に虐げられ、育ての母に愛されたお話。
親子って血の繋がりだけじゃないってお話です。
小説家になろう様でも投稿しています。

冷遇妻に家を売り払われていた男の裁判
七辻ゆゆ
ファンタジー
婚姻後すぐに妻を放置した男が二年ぶりに帰ると、家はなくなっていた。
「では開廷いたします」
家には10億の価値があったと主張し、妻に離縁と損害賠償を求める男。妻の口からは二年の事実が語られていく。

無能なので辞めさせていただきます!
サカキ カリイ
ファンタジー
ブラック商業ギルドにて、休みなく働き詰めだった自分。
マウントとる新人が入って来て、馬鹿にされだした。
えっ上司まで新人に同調してこちらに辞めろだって?
残業は無能の証拠、職務に時間が長くかかる分、
無駄に残業代払わせてるからお前を辞めさせたいって?
はいはいわかりました。
辞めますよ。
退職後、困ったんですかね?さあ、知りませんねえ。
自分無能なんで、なんにもわかりませんから。
カクヨム、なろうにも同内容のものを時差投稿しております。

悪役令嬢と言われ冤罪で追放されたけど、実力でざまぁしてしまった。
三谷朱花
恋愛
レナ・フルサールは元公爵令嬢。何もしていないはずなのに、気が付けば悪役令嬢と呼ばれ、公爵家を追放されるはめに。それまで高スペックと魔力の強さから王太子妃として望まれたはずなのに、スペックも低い魔力もほとんどないマリアンヌ・ゴッセ男爵令嬢が、王太子妃になることに。
何度も断罪を回避しようとしたのに!
では、こんな国など出ていきます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















