155 / 303
第29話ー4
しおりを挟む
ベルの友人ハナを除いた一同が部屋から出て行くと、フラヴィオは「アモーレ」とベルの栗色の髪を撫でた。
小さな顔は高熱で火照り、咳をした小さな身体は力無くぐったりとしている。
「フラヴィオ様……」
「大丈夫だアモーレ、余が必ず――」
「出て行ってください」
フラヴィオに衝撃が走った。
フラヴィオが何故だと問う前に、ベルが咳き込んで続けた。
「フラヴィオ様にうつすわけにはいきません」
「そうだな」とハナが続いた。
「フラビーだって一応人間だし、絶対うつらないとは言えないよな。やっぱりあたいが看てるからさ、フラビーも宴に戻ってなよ。国王が体調崩したらそれこそ大変だ」
フラヴィオが「大丈夫だ」と声高に言って、胸を張った。
「何故ならドルフが死ぬまで病気にならないのは当然のこと、余やフェーデだって物心付いたときから風邪を引いたことがないのだ。だから余の心配は一切いらぬ。安心して頼ってくれ、アモーレ。で、何をすれば良いのだ?」
「――って、何をすれば良いのか分からないんじゃないか」
とハナの顔が引き攣る。
「ベルが食べられるものでも持って来てよ。水はあたいがいつでも魔法で出せるから」
「おお、そうだな! 待っててくれ、アモーレ! 食事を持って来る!」
とフラヴィオが戸口へと駆けて行く。
ハナが「待った」と声高に呼び止めた。
「フラビーが料理するのか?」
「もちろんだ!」
と答えるなりフラヴィオが部屋を後にすると、顔を見合わせたベルとハナが苦笑した。
「フラビーって、一度でも料理したことあるのか?」
「無いかと……」
――1階にある厨房へと駆け下りて行ったフラヴィオは、まず料理長フィコたちに宴の料理を作り続けるよう命じた。
これからベルの食事を作ろうと思っていたフィコが「ええ?」と動揺する。
「んじゃあ、ベルの飯はどうするんでい」
「心配するな、余の第二の父上よ。余が完璧に作ってみせるのだ」
とフラヴィオが袖を捲っていくと、フィコが「待った待った」と狼狽した。
「陛下こそ宴に戻ってくれい。俺は陛下を生まれた頃から見てるが、料理をする姿は一度だって見たことがねぇ」
「アモーレの危機を目前に、余に出来ぬことなど無い!」
「いや、出来ねぇから。おとなしく出て行ってくだせぇ。お召し物に醤油なんて飛んだら、落ちなくて大変だって家政婦長に怒られますぜ?」
フラヴィオは「む?」と自身の衣類に目を落とすと、「分かった」と言って厨房の外へと出て行った。
諦めたのかと思いきや、廊下で衣類を脱ぎ捨てて全裸で戻って来る。
「これで良かろう?」
「何で思考がソッチの方に行くんでい」
とフィコがやれやれといった様子で、壁に掛けてあった白のフリル付きエプロン(女用)を取った。それを料理する気満々でいるフラヴィオの裸体に付けてやる。
厨房内が突っ込みたさそうな雰囲気で満たされたが、フラヴィオが「さ!」と厨房担当の使用人たちを催促させた。
「宴の料理をどんどん作るのだ、皆の者! 余は邪魔にならぬよう、厨房の端を借りてやるから気にしなくて良い」
気になったが、果てしなく気になったが、国王命令なので見て見ぬ振りをして使用人たちが従う。
フラヴィオは「よし」と気合の入れた声を出すと、冷蔵箱の方へと向かって行った。
中から霜降り牛肉を取り出したのを見て、フィコがすかさず突っ込む。
「風邪のときに何を作る気でい」
「元気になるのは肉なのだ。だからビーフステーキだ」
「陛下……」
「ビステッカは切って焼けば出来ることくらい、いくら何でも余だって知っているのだ」
「そうじゃねぇ。風邪のときに、普通そんな重たいもんは食えねぇんですぜ? ティーナ殿下が風邪引いたとき、俺はそんなもの作ってたかい?」
そういえばヴァレンティーナが風邪を引いたとき、食事には必ず細かく切った野菜を柔らかく煮込んだツッパ(パン入りスープ)を食べていた。
「そうか、ツッパだな。分かった」
と冷蔵箱の傍らにある野菜置き場から、とりあえず全種類の野菜をひとつずつ取って腕に抱えたフラヴィオ。
まな板の上に持って行って包丁を握り、いざ刻まん。
「待っていろ、アモーレ……!」
と「おりゃあぁぁぁあ!」とすべての野菜を一瞬で切ってみせたが、即刻フィコの突っ込みが入った。
「食い辛ぇってんだ」
具材が大き過ぎる。
カボチャは四等分、人参は三等分、大根は5cm幅、玉ねぎとカブは縦半分だった。
「10分くらい煮ればトロトロに――」
「なると思ってるんですかい?」
「ならないのか?」
フィコが呆れ顔になる。
「10分で柔らかくしたいなら、全部1cm角くらいには切らねぇと」
「分かった、1cm角だな。えーと…? まずは、こうして……――」
「ああもう、とれぇな! やっぱり俺が作りますぜ!」
と、包丁を取られそうになったフラヴィオが、「駄目だ!」とフィコを突き飛ばした。
「余が作るのだ! フィコは宴の料理に戻ってくれ!」
「ベルを何時間待たせる気ですかい! 陛下こそ宴に戻っててくだせぇ!」
「大丈夫だ、すぐに切るのだ! おりゃあぁぁ――イテッ!」
「ほらもう、怪我した! 早く医務室かハナちゃんたちんとこ行って、治療してきてくだせぇ!」
「血を隠し味に使おうと思っただけなのだ! もういいから、放っておいてくれ! ツッパくらいひとりで出来る、小童じゃあるまいし!」
「いや、34歳児にゃ出来ねぇって――」
「出ー来ーるーのーだっ!」
とフラヴィオが地団太を踏むと、フィコが溜め息交じりに「へいへい」と言った。
「んじゃあ、困ったら呼んでくだせぇ。俺ぁ、アッチの方にいるんでね」
「分かった。まぁ、困らぬから呼ぶこともないけどな」
再び「へいへい」と返したフィコ。
一歩踏み出すなり、「あ」とフラヴィオの声が聞こえて振り返る。
「早ぇ前言撤回で」
「違う、呼んでない。余は困ってない。しかし、ちょっと確認する。間違っていないと分かっているが、確認する」
もうすでに間違っているだろうと察しているフィコが、溜め息交じりに「はいよ?」と返すと、フラヴィオがまな板から手の届く場所にあるハーブ類を指差した。
「これがバジルだろう?」
「パセリでい」
「あれ?」と眉を寄せたフラヴィオが、今度は近くにある麻袋を指差した。
「この豆は分かるぞ。レオーネ国から買った苗を、パオラが見事に栽培してみせたやつだ――大豆だ!」
「昔っからうちの国で育ててるヒヨコ豆でい」
フラヴィオがまた「あれ?」と言って、今度はヒヨコ豆の隣の麻袋を指差す。
「おお、パオラの大豆は挽いて粉状に――キナコになっていたのか」
「それ小麦粉でい」
「え……!?」
と我ながら衝撃を受けたらしいフラヴィオが、ムキになった様子で辺りを見回し、調味料の入った容器を手に取った。
「こ、これは間違いないのだ。絶対間違いない。そう、これは……塩だ!」
「砂糖でい」
フィコの身体がわなわなと震えていった。
「もぉーーーっ、我慢ならねぇ! やっぱり陛下は出て行ってくだせぇ! 病気で弱ってる俺の可愛い一番弟子に、一体どんなゲテモノを食わせる気でい!」
「駄目だ、余が作るのだ! 余の愛の詰まった手料理を食べればアモーレはすぐ良くなるのだ! フィコは早く宴の料理に戻るのだ!」
「戻りたくても戻れねぇっ!」
とフラヴィオとフィコが包丁を奪い合っていると、「何してるんですか」とハモり声が聞こえた。
振り返るとそこに、裸グレンビューレ姿でいるフラヴィオを、さも不審そうに見るフェデリコとアドルフォが立っていた。
フェデリコの手には林檎が、アドルフォの手には器に盛られたヨーグルトが持たれている。
フラヴィオがむっとした。
「おまえたち、何だソレは?」
「何だって、兄上のことですから、どうせ昼過ぎまで掛かるんでしょう?」
「それじゃー、ベルが腹を空かせてしまうんでね」
とアドルフォがヨーグルトにハチミツを掛け、芸術の才に恵まれたフェデリコが林檎を手早く飾り切りにして皿に盛っていく。
フィコが「ほう」と感嘆した。
「食欲が無くても食べやすいヨーグルトを選ぶところといい、繊細な包丁捌きといい、お二方は陛下とは違いますなぁ」
フラヴィオの頬が膨れ上がった。
「余を馬鹿にするな! アモーレの危機を目前に、余に出来ないことなど無いのだ!」
フェデリコとアドルフォからは「はいはい」、フィコからは三度目の「へいへい」が聞こえると、尚のこと頬を膨らませたフラヴィオ。
一体、何人前を作る気なのか。
巨大な鍋を持って来て、厨房の隅に用意してある井戸水を満杯近くまで入れた。
これに用意してある具材を入れたらどう考えても溢れるのだが、それが分からないのか、どうでも良いのか知らないが、「よいしょ」と釜戸の上に鍋を乗せた。
そして「良いか?」と国王の威厳を漂わせながら、フェデリコとアドルフォ、フィコの3人の顔を見た。
「料理とは、手際の良さが大切なのだ! 具材を切っている時間に、他に何もしないというのは素人だ。よって玄人の余は、具材を切っているあいだに湯を沸かして味付けしておくことにする! まず、塩を大匙3!」
と言って、大きな手で3掴み分の塩を鍋に入れ、何の冗談かと3人に怒られ。
「何、大丈夫だ。あのな、どんなに塩を入れ過ぎたって、同じ分量の砂糖を入れれば中和されてゼロになるのだ」
という謎の理論の下、今度は3掴み分の砂糖を鍋に投入して、知能を心配される。
「大丈夫だ、焦るなおまえたち。料理とはエルベで決まるものなのだ!」
と、何十種類もあるエルベすべてを5本の指で摘まんで投入。
ほんの一つまみで充分なものや、とても希少で高価なものまであり、ついに堪忍袋の緒が切れたフィコの怒号が1階の廊下に響き渡っていく。
さらに湯が沸いてくると、厨房内に激臭が充満。
使用人たちがむせ返りながら廊下へ飛び出し、フェデリコとアドルフォはヨーグルトと林檎を持つと、呆れの長嘆息を吐いて4階へと向かって行った。
小さな顔は高熱で火照り、咳をした小さな身体は力無くぐったりとしている。
「フラヴィオ様……」
「大丈夫だアモーレ、余が必ず――」
「出て行ってください」
フラヴィオに衝撃が走った。
フラヴィオが何故だと問う前に、ベルが咳き込んで続けた。
「フラヴィオ様にうつすわけにはいきません」
「そうだな」とハナが続いた。
「フラビーだって一応人間だし、絶対うつらないとは言えないよな。やっぱりあたいが看てるからさ、フラビーも宴に戻ってなよ。国王が体調崩したらそれこそ大変だ」
フラヴィオが「大丈夫だ」と声高に言って、胸を張った。
「何故ならドルフが死ぬまで病気にならないのは当然のこと、余やフェーデだって物心付いたときから風邪を引いたことがないのだ。だから余の心配は一切いらぬ。安心して頼ってくれ、アモーレ。で、何をすれば良いのだ?」
「――って、何をすれば良いのか分からないんじゃないか」
とハナの顔が引き攣る。
「ベルが食べられるものでも持って来てよ。水はあたいがいつでも魔法で出せるから」
「おお、そうだな! 待っててくれ、アモーレ! 食事を持って来る!」
とフラヴィオが戸口へと駆けて行く。
ハナが「待った」と声高に呼び止めた。
「フラビーが料理するのか?」
「もちろんだ!」
と答えるなりフラヴィオが部屋を後にすると、顔を見合わせたベルとハナが苦笑した。
「フラビーって、一度でも料理したことあるのか?」
「無いかと……」
――1階にある厨房へと駆け下りて行ったフラヴィオは、まず料理長フィコたちに宴の料理を作り続けるよう命じた。
これからベルの食事を作ろうと思っていたフィコが「ええ?」と動揺する。
「んじゃあ、ベルの飯はどうするんでい」
「心配するな、余の第二の父上よ。余が完璧に作ってみせるのだ」
とフラヴィオが袖を捲っていくと、フィコが「待った待った」と狼狽した。
「陛下こそ宴に戻ってくれい。俺は陛下を生まれた頃から見てるが、料理をする姿は一度だって見たことがねぇ」
「アモーレの危機を目前に、余に出来ぬことなど無い!」
「いや、出来ねぇから。おとなしく出て行ってくだせぇ。お召し物に醤油なんて飛んだら、落ちなくて大変だって家政婦長に怒られますぜ?」
フラヴィオは「む?」と自身の衣類に目を落とすと、「分かった」と言って厨房の外へと出て行った。
諦めたのかと思いきや、廊下で衣類を脱ぎ捨てて全裸で戻って来る。
「これで良かろう?」
「何で思考がソッチの方に行くんでい」
とフィコがやれやれといった様子で、壁に掛けてあった白のフリル付きエプロン(女用)を取った。それを料理する気満々でいるフラヴィオの裸体に付けてやる。
厨房内が突っ込みたさそうな雰囲気で満たされたが、フラヴィオが「さ!」と厨房担当の使用人たちを催促させた。
「宴の料理をどんどん作るのだ、皆の者! 余は邪魔にならぬよう、厨房の端を借りてやるから気にしなくて良い」
気になったが、果てしなく気になったが、国王命令なので見て見ぬ振りをして使用人たちが従う。
フラヴィオは「よし」と気合の入れた声を出すと、冷蔵箱の方へと向かって行った。
中から霜降り牛肉を取り出したのを見て、フィコがすかさず突っ込む。
「風邪のときに何を作る気でい」
「元気になるのは肉なのだ。だからビーフステーキだ」
「陛下……」
「ビステッカは切って焼けば出来ることくらい、いくら何でも余だって知っているのだ」
「そうじゃねぇ。風邪のときに、普通そんな重たいもんは食えねぇんですぜ? ティーナ殿下が風邪引いたとき、俺はそんなもの作ってたかい?」
そういえばヴァレンティーナが風邪を引いたとき、食事には必ず細かく切った野菜を柔らかく煮込んだツッパ(パン入りスープ)を食べていた。
「そうか、ツッパだな。分かった」
と冷蔵箱の傍らにある野菜置き場から、とりあえず全種類の野菜をひとつずつ取って腕に抱えたフラヴィオ。
まな板の上に持って行って包丁を握り、いざ刻まん。
「待っていろ、アモーレ……!」
と「おりゃあぁぁぁあ!」とすべての野菜を一瞬で切ってみせたが、即刻フィコの突っ込みが入った。
「食い辛ぇってんだ」
具材が大き過ぎる。
カボチャは四等分、人参は三等分、大根は5cm幅、玉ねぎとカブは縦半分だった。
「10分くらい煮ればトロトロに――」
「なると思ってるんですかい?」
「ならないのか?」
フィコが呆れ顔になる。
「10分で柔らかくしたいなら、全部1cm角くらいには切らねぇと」
「分かった、1cm角だな。えーと…? まずは、こうして……――」
「ああもう、とれぇな! やっぱり俺が作りますぜ!」
と、包丁を取られそうになったフラヴィオが、「駄目だ!」とフィコを突き飛ばした。
「余が作るのだ! フィコは宴の料理に戻ってくれ!」
「ベルを何時間待たせる気ですかい! 陛下こそ宴に戻っててくだせぇ!」
「大丈夫だ、すぐに切るのだ! おりゃあぁぁ――イテッ!」
「ほらもう、怪我した! 早く医務室かハナちゃんたちんとこ行って、治療してきてくだせぇ!」
「血を隠し味に使おうと思っただけなのだ! もういいから、放っておいてくれ! ツッパくらいひとりで出来る、小童じゃあるまいし!」
「いや、34歳児にゃ出来ねぇって――」
「出ー来ーるーのーだっ!」
とフラヴィオが地団太を踏むと、フィコが溜め息交じりに「へいへい」と言った。
「んじゃあ、困ったら呼んでくだせぇ。俺ぁ、アッチの方にいるんでね」
「分かった。まぁ、困らぬから呼ぶこともないけどな」
再び「へいへい」と返したフィコ。
一歩踏み出すなり、「あ」とフラヴィオの声が聞こえて振り返る。
「早ぇ前言撤回で」
「違う、呼んでない。余は困ってない。しかし、ちょっと確認する。間違っていないと分かっているが、確認する」
もうすでに間違っているだろうと察しているフィコが、溜め息交じりに「はいよ?」と返すと、フラヴィオがまな板から手の届く場所にあるハーブ類を指差した。
「これがバジルだろう?」
「パセリでい」
「あれ?」と眉を寄せたフラヴィオが、今度は近くにある麻袋を指差した。
「この豆は分かるぞ。レオーネ国から買った苗を、パオラが見事に栽培してみせたやつだ――大豆だ!」
「昔っからうちの国で育ててるヒヨコ豆でい」
フラヴィオがまた「あれ?」と言って、今度はヒヨコ豆の隣の麻袋を指差す。
「おお、パオラの大豆は挽いて粉状に――キナコになっていたのか」
「それ小麦粉でい」
「え……!?」
と我ながら衝撃を受けたらしいフラヴィオが、ムキになった様子で辺りを見回し、調味料の入った容器を手に取った。
「こ、これは間違いないのだ。絶対間違いない。そう、これは……塩だ!」
「砂糖でい」
フィコの身体がわなわなと震えていった。
「もぉーーーっ、我慢ならねぇ! やっぱり陛下は出て行ってくだせぇ! 病気で弱ってる俺の可愛い一番弟子に、一体どんなゲテモノを食わせる気でい!」
「駄目だ、余が作るのだ! 余の愛の詰まった手料理を食べればアモーレはすぐ良くなるのだ! フィコは早く宴の料理に戻るのだ!」
「戻りたくても戻れねぇっ!」
とフラヴィオとフィコが包丁を奪い合っていると、「何してるんですか」とハモり声が聞こえた。
振り返るとそこに、裸グレンビューレ姿でいるフラヴィオを、さも不審そうに見るフェデリコとアドルフォが立っていた。
フェデリコの手には林檎が、アドルフォの手には器に盛られたヨーグルトが持たれている。
フラヴィオがむっとした。
「おまえたち、何だソレは?」
「何だって、兄上のことですから、どうせ昼過ぎまで掛かるんでしょう?」
「それじゃー、ベルが腹を空かせてしまうんでね」
とアドルフォがヨーグルトにハチミツを掛け、芸術の才に恵まれたフェデリコが林檎を手早く飾り切りにして皿に盛っていく。
フィコが「ほう」と感嘆した。
「食欲が無くても食べやすいヨーグルトを選ぶところといい、繊細な包丁捌きといい、お二方は陛下とは違いますなぁ」
フラヴィオの頬が膨れ上がった。
「余を馬鹿にするな! アモーレの危機を目前に、余に出来ないことなど無いのだ!」
フェデリコとアドルフォからは「はいはい」、フィコからは三度目の「へいへい」が聞こえると、尚のこと頬を膨らませたフラヴィオ。
一体、何人前を作る気なのか。
巨大な鍋を持って来て、厨房の隅に用意してある井戸水を満杯近くまで入れた。
これに用意してある具材を入れたらどう考えても溢れるのだが、それが分からないのか、どうでも良いのか知らないが、「よいしょ」と釜戸の上に鍋を乗せた。
そして「良いか?」と国王の威厳を漂わせながら、フェデリコとアドルフォ、フィコの3人の顔を見た。
「料理とは、手際の良さが大切なのだ! 具材を切っている時間に、他に何もしないというのは素人だ。よって玄人の余は、具材を切っているあいだに湯を沸かして味付けしておくことにする! まず、塩を大匙3!」
と言って、大きな手で3掴み分の塩を鍋に入れ、何の冗談かと3人に怒られ。
「何、大丈夫だ。あのな、どんなに塩を入れ過ぎたって、同じ分量の砂糖を入れれば中和されてゼロになるのだ」
という謎の理論の下、今度は3掴み分の砂糖を鍋に投入して、知能を心配される。
「大丈夫だ、焦るなおまえたち。料理とはエルベで決まるものなのだ!」
と、何十種類もあるエルベすべてを5本の指で摘まんで投入。
ほんの一つまみで充分なものや、とても希少で高価なものまであり、ついに堪忍袋の緒が切れたフィコの怒号が1階の廊下に響き渡っていく。
さらに湯が沸いてくると、厨房内に激臭が充満。
使用人たちがむせ返りながら廊下へ飛び出し、フェデリコとアドルフォはヨーグルトと林檎を持つと、呆れの長嘆息を吐いて4階へと向かって行った。
0
お気に入りに追加
91
あなたにおすすめの小説

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?
gacchi
恋愛
13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。
そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて
「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」
もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?
3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。
4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。
1章が書籍になりました。

公爵様、契約通り、跡継ぎを身籠りました!-もう契約は満了ですわよ・・・ね?ちょっと待って、どうして契約が終わらないんでしょうかぁぁ?!-
猫まんじゅう
恋愛
そう、没落寸前の実家を助けて頂く代わりに、跡継ぎを産む事を条件にした契約結婚だったのです。
無事跡継ぎを妊娠したフィリス。夫であるバルモント公爵との契約達成は出産までの約9か月となった。
筈だったのです······が?
◆◇◆
「この結婚は契約結婚だ。貴女の実家の財の工面はする。代わりに、貴女には私の跡継ぎを産んでもらおう」
拝啓、公爵様。財政に悩んでいた私の家を助ける代わりに、跡継ぎを産むという一時的な契約結婚でございましたよね・・・?ええ、跡継ぎは産みました。なぜ、まだ契約が完了しないんでしょうか?
「ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいませええ!この契約!あと・・・、一体あと、何人子供を産めば契約が満了になるのですッ!!?」
溺愛と、悪阻(ツワリ)ルートは二人がお互いに想いを通じ合わせても終わらない?
◆◇◆
安心保障のR15設定。
描写の直接的な表現はありませんが、”匂わせ”も気になる吐き悪阻体質の方はご注意ください。
ゆるゆる設定のコメディ要素あり。
つわりに付随する嘔吐表現などが多く含まれます。
※妊娠に関する内容を含みます。
【2023/07/15/9:00〜07/17/15:00, HOTランキング1位ありがとうございます!】
こちらは小説家になろうでも完結掲載しております(詳細はあとがきにて、)

余命宣告を受けたので私を顧みない家族と婚約者に執着するのをやめることにしました
結城芙由奈
恋愛
【余命半年―未練を残さず生きようと決めた。】
私には血の繋がらない父と母に妹、そして婚約者がいる。しかしあの人達は私の存在を無視し、空気の様に扱う。唯一の希望であるはずの婚約者も愛らしい妹と恋愛関係にあった。皆に気に入られる為に努力し続けたが、誰も私を気に掛けてはくれない。そんな時、突然下された余命宣告。全てを諦めた私は穏やかな死を迎える為に、家族と婚約者に執着するのをやめる事にした―。
2021年9月26日:小説部門、HOTランキング部門1位になりました。ありがとうございます
*「カクヨム」「小説家になろう」にも投稿しています
※2023年8月 書籍化

断る――――前にもそう言ったはずだ
鈴宮(すずみや)
恋愛
「寝室を分けませんか?」
結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。
周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。
けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。
他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。
(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)
そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。
ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。
そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?
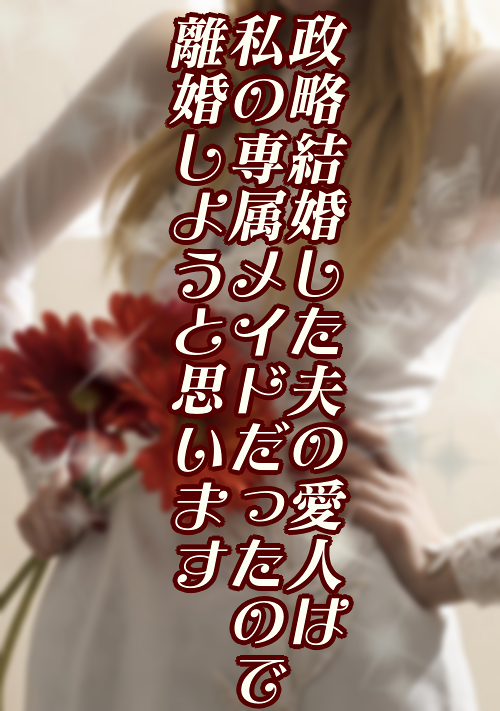
政略結婚した夫の愛人は私の専属メイドだったので離婚しようと思います
結城芙由奈
恋愛
浮気ですか?どうぞご自由にして下さい。私はここを去りますので
結婚式の前日、政略結婚相手は言った。「お前に永遠の愛は誓わない。何故ならそこに愛など存在しないのだから。」そして迎えた驚くべき結婚式と驚愕の事実。いいでしょう、それほど不本意な結婚ならば離婚してあげましょう。その代わり・・後で後悔しても知りませんよ?
※「カクヨム」「小説家になろう」にも掲載中

【完結】身を引いたつもりが逆効果でした
風見ゆうみ
恋愛
6年前に別れの言葉もなく、あたしの前から姿を消した彼と再会したのは、王子の婚約パレードの時だった。
一緒に遊んでいた頃には知らなかったけれど、彼は実は王子だったらしい。しかもあたしの親友と彼の弟も幼い頃に将来の約束をしていたようで・・・・・。
平民と王族ではつりあわない、そう思い、身を引こうとしたのだけど、なぜか逃してくれません!
というか、婚約者にされそうです!

【完結】公女が死んだ、その後のこと
杜野秋人
恋愛
【第17回恋愛小説大賞 奨励賞受賞しました!】
「お母様……」
冷たく薄暗く、不潔で不快な地下の罪人牢で、彼女は独り、亡き母に語りかける。その掌の中には、ひと粒の小さな白い錠剤。
古ぼけた簡易寝台に座り、彼女はそのままゆっくりと、覚悟を決めたように横たわる。
「言いつけを、守ります」
最期にそう呟いて、彼女は震える手で錠剤を口に含み、そのまま飲み下した。
こうして、第二王子ボアネルジェスの婚約者でありカストリア公爵家の次期女公爵でもある公女オフィーリアは、獄中にて自ら命を断った。
そして彼女の死後、その影響はマケダニア王国の王宮内外の至るところで噴出した。
「ええい、公務が回らん!オフィーリアは何をやっている!?」
「殿下は何を仰せか!すでに公女は儚くなられたでしょうが!」
「くっ……、な、ならば蘇生させ」
「あれから何日経つとお思いで!?お気は確かか!」
「何故だ!何故この私が裁かれねばならん!」
「そうよ!お父様も私も何も悪くないわ!悪いのは全部お義姉さまよ!」
「…………申し開きがあるのなら、今ここではなく取り調べと裁判の場で存分に申すがよいわ。⸺連れて行け」
「まっ、待て!話を」
「嫌ぁ〜!」
「今さら何しに戻ってきたかね先々代様。わしらはもう、公女さま以外にお仕えする気も従う気もないんじゃがな?」
「なっ……貴様!領主たる儂の言うことが聞けんと」
「領主だったのは亡くなった女公さまとその娘の公女さまじゃ。あの方らはあんたと違って、わしら領民を第一に考えて下さった。あんたと違ってな!」
「くっ……!」
「なっ、譲位せよだと!?」
「本国の決定にございます。これ以上の混迷は連邦友邦にまで悪影響を与えかねないと。⸺潔く観念なさいませ。さあ、ご署名を」
「おのれ、謀りおったか!」
「…………父上が悪いのですよ。あの時止めてさえいれば、彼女は死なずに済んだのに」
◆人が亡くなる描写、及びベッドシーンがあるのでR15で。生々しい表現は避けています。
◆公女が亡くなってからが本番。なので最初の方、恋愛要素はほぼありません。最後はちゃんとジャンル:恋愛です。
◆ドアマットヒロインを書こうとしたはずが。どうしてこうなった?
◆作中の演出として自死のシーンがありますが、決して推奨し助長するものではありません。早まっちゃう前に然るべき窓口に一言相談を。
◆作者の作品は特に断りなき場合、基本的に同一の世界観に基づいています。が、他作品とリンクする予定は特にありません。本作単品でお楽しみ頂けます。
◆この作品は小説家になろうでも公開します。
◆24/2/17、HOTランキング女性向け1位!?1位は初ですありがとうございます!

《勘違い》で婚約破棄された令嬢は失意のうちに自殺しました。
友坂 悠
ファンタジー
「婚約を考え直そう」
貴族院の卒業パーティーの会場で、婚約者フリードよりそう告げられたエルザ。
「それは、婚約を破棄されるとそういうことなのでしょうか?」
耳を疑いそう聞き返すも、
「君も、その方が良いのだろう?」
苦虫を噛み潰すように、そう吐き出すフリードに。
全てに絶望し、失意のうちに自死を選ぶエルザ。
絶景と評判の観光地でありながら、自殺の名所としても知られる断崖絶壁から飛び降りた彼女。
だったのですが。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















